| �p��f�[�^�x�[�X�@04_3 |
 �@ �@ |
| �R�D�����S�������̔��W |
| �A�D�����S���̑�鍑
|
| �` �`���M�X���n�� | �@���@�`���M�X���n�� |
| �����S������ | �����S�������烂���S���������@���݂ł������S�������i�����S���A�j�ŗV�q�����𑗂��Ă����A���^�C��n�̖����������S�������Ə̂��A���{�ł͖Âƕ\�L���Ă��邪�A���̂悤�ȁu�����S�������v�����������̂́A�P�R���I�́u�����S���鍑�v�����ȍ~�̂��Ƃł���B����ȑO�͖k�A�W�A�̑����Ŋ�������V�q�����̈ꕔ�����u�����S�����v�ƌ����Ă����ɉ߂��Ȃ������B���n��̗V�q���Ƃ��ẮA�Â��͂R�`�T���I�Ɋ��������N���i�g���R�n��������j���_�R����������B����ɖ֙Y�i�������j�Ƃ��ďo�Ă���B�ނ�͂U�`�X���I�ɂ͓˙E�E�C�O���̃g���R�n�����̎x�z���Ă������A�P�O���I�ɂ͓��n����_�O�i�Ɂj���L�͂ƂȂ����B�P�Q���I����܂ł͑����̕����ɂ킩��A�P���C�g����^�^�[�����Ȃǂ��L�͂ł��������A�P�R���I���߂ɁA���̒��̃����S�����Ƃ����������̒����猻�ꂽ�`���M�X���n�������������������S���鍑�i�����S�����E���X�j���������Ĉȗ��A���n��̗V�q����ǂ�ɓ��������g���R�n�����Ȃǂ��u�����S�������v�ƍl������悤�ɂȂ����B
�����S���鍑�̃����S�������@�`���M�X���n�����瑷�̃t�r���C���n���̎����ɂ����������S���鍑�͋}���ɗ̓y���g�債�A���A�W�A�E���V�A���璆���S�̂ɋy�ԑ�鍑���`������A�����S�����������̗̈�Ɋg�債�x�z�w���`�����Ă������B�������x�z���������S���͍��������Ƃ������A����������������邱�Ƃ͏��Ȃ��A���������Ƃ��Ďx�z�����B���ł������S���l�����`���Ƃ��A����l���F�ڐl�Ƃ��Ă��̎��ɒu����A�������͊��l�E��l�ɕ������Ă��̉��ɒu���ꂽ�B
�����S�������̏@���@�����S�������͒����V���[�}�j�Y���Ɏ~�܂��Ă������A�@���ɂ͊���ŁA����ɂ���ĕ�����l�X�g���E�X�h�L���X�g���A�C�X���[�����Ȃǂ̉e�������B���ɒ������x�z��������A�P�U���I�̃����S���������`�x�b�g������ی삵�����Ƃ����ڂł���B�����A�W�A�̃`���K�^�C���n�����A���A�W�A�̃C�����n�����A�샍�V�A�̃L�v�`���N���n�����ł͂��ꂼ���Z�����g���R�n�����Ɠ������i�݁A�܂��C�X���[���������B
���ŖS��̃����S�������@�P�R�U�W�N�A���̖ŖS��͖��ɂ���Ĉ�������A���̎x�z�̈�������S�����������Ɍ��肳�ꂽ�k���ƂȂ�B�����S�������̍��Ƃ����ł����킯�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ���B�P�T���I�����ɂ̓����S�������̈ꕔ���ł����I�C���g�����G�Z�����n�����L�͂ƂȂ�A�������������B���łP�U���I�����ɂ��^�^�[�������_�������n���������S���������Ăѓ��ꂵ�A�����A���^�����n���͂��т��і��̗̓y��N���A�k���Ƌ����ꂽ�B
�����ƃ����S���@�P�V���I�ɂ͐������S���ɃI�C���g���W�����K�������D���ƂȂ�A���̍N����̉����R�ƌ������R���������A�P�W���I�Ɋ�����̍U�����A�P�V�T�W�N�ɐ����̎x�z���ɓ���A�˕��̈�Ƃ��ė��ˉ@�̎x�z�����B�܂��W�����K���Ɉ�������ē������S���Ɉړ������n���n���͐����ɕ������A�O�����S������������S���ɂ��L�������B
�����S���̓Ɨ��Ɗv���@�P�X�P�P�N�ɐh��v���Ő������|���ƁA�k�����S���i������O�����S���j�`�x�b�g�����̊������匠�҂Ƃ��鍑�Ƃ̓Ɨ���錾�����B���̌ネ�V�A�̉e������悤�ɂȂ�A��P�����E����Ƀ��V�A�v���̉e�����������S���Љ��`�v�����N�����āA�P�X�Q�S�N�Ɂu�����S���l�����a���v�i���V�A�Ɏ����j��Q�Ԗڂ̎Љ��`���j�����������B�������샂���S���i�������S���j�͒����̂ɂƂǂ܂����B�����S���l�����a���́A�P�X�X�Q�N�ɎЉ��`��������A�u�����S�����v�Ɖ��̂����B���݃����S���l�Ƃ����̂́A�L���Ӗ��Ń����S�����b���l�X�Ƃ���A�����S�����A�����̓��Î�����A���V�A�ȂǂɂЂ낭���Z����B�����S����̓A���^�C�ꑰ�ɑ����A���{��Ƃ̋ߐe��������B
Epi.�@�����S���l�͎m�̊����@�P�X�X�Q�N�ɓ����������h�R�i�ō��ʏ����B�Q�O�O�U�N���ށj�ȗ��A�����S���l�͎m�����{�̑告�o�Ŋ���悤�ɂȂ�A���ɒ����Ɣ��Q���������ʼn��j�ɏ��i����قǁA�告�o��ʂ��ē��{�ƃ����S���̊W�͐[���Ȃ����B�����S���ɂ͌×��A�����S�����o�Ƃ������{�̑��o�Ɏ����i���Z�����邩��ł��낤���B�������A�����A���^�C��n�����ł���A������̖Ô��ȂǁA���{�l�Ƃ̋ߐe�������邱�Ƃ��傫���ł��낤�B���͂���S���l�͎m���O�l�͎m�ƌ����̂͂�߂��ق��������̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��A���̊J��҂ł��������h�R�͋A����̂Q�O�O�W�N�ɍ���c���ɓ��I���Ă���B |
| �����S������
| ���̓A���^�C�R������A���͑勻����i�V���A�������j�R���ɂ�����A�L��ȑ����ƍ����̍L����n�сB�����S���A�B���̒n�ɂ͌×��V�q���̏����������S�����B���̎�Ȃ��̂̏���������A���z���N�ځ��_�R���˙��E�C�O�����L���M�X���_�O�i�Ɂj�������S���A�ƂȂ낤�B�����Ƃ����̒n�������S�������ƌ����悤�ɂȂ�̂��A�`���M�X���n���ȗ��A�����S�������𒆐S�Ƃ��������S���鍑���ɉh���Ă���ȍ~�̂��Ƃł���B |
| �����S������
| �����S�������͎n�ߕ����������Ȃ��������A�`���M�X���n�����i�C�}�������]�����Ƃ��A�ߗ��Ƃ����b���̃E�C�O���l����A�E�C�O���������w�сA�����S�������𐧒肵���B�t�r���C���n���͂P�Q�U�X�N�Ɍ������p�Ƃ��ă`�x�b�g�n���p�X�p�����i�p�N�p�����j�𐧒肵�����A��ʂɂ͕��y���Ȃ������B�Q�O���I�ɓ���A�P�X�Q�P�N�Ƀ����S���l�����a���������i���E�łQ�Ԗڂ̎Љ��`���������j������A�\�A�̉e�������܂�P�X�S�Q�N�Ƀ����S���������p�~����A���V�A����L�����������g���邱�ƂƂȂ����B�������A�P�X�X�Q�N�ɍ����������S�����Ɖ��߁A�����S������������������B�����S�������͏c�����������B�@ |
| a�@�e���W��
| �`���M�X���n���̗c���B�����ł͓S�ؐ^�B |
| b�@�N�����^�C
| �����S���̕�������c�ő�W��̈Ӗ��B�N��i�n���j�̐��Ղ̑��A���i�E���X�j�̏d�v�������ٌ������B |
| c�@�n��
| �n�[���A�J���A�J�[���A�J�A���܂��̓n�K���A�J�K���Ƃ��\�L����B�����ł͊��̎������Ă�B�Â�����k���V�q���Љ�ł́A�N����Ӗ����錾�t�Ƃ��ėp�����Ă���A�N�ڂɎn�܂�A�_�R�Łu���v���g���A�˙A�E�C�O���ł��p�����ꂽ�B�����S���ł��J���A�n�����g��ꂽ�����̈Ӗ��ɂ��Ă͏�������B������ɂ���A�N��i�鍑�̏ꍇ�͍c��j�̈Ӗ��ƍl���Ă悢�B�����S���鍑�̃n���́A�O��̃n�������̃n�����w������̂ł͂Ȃ��A�`���M�X���n���̌������p�����̂̒�����A�ꑰ�̗L�͎҂̉�c�ł����N�����^�C�̍��c�őI�o���ꂽ�B���̓`���̓����S���鍑�̑����E���X�ł��p�����ꂽ�B
�n���̕\�L�ɂ����@�����̃J�^�J�i�\�L�𐳊m�ɂ���͓̂���B���{�̃J�^�J�i�ł͏\���ɕ\�L������Ȃ��ꍇ���������B���ƂɁu�n���v�ɂ��Ă͂��܂��܂ȕ\�L������Ă���B�����S������́u�J���v�ɋ߂������ł������炵���A�܂��B��l�̃����S���c��́u�J�A���v�i�J�K���A�J�n���͂��̌n���j�A���̑��̌N��E����́u�J���v�Ɠ�i�K�̎��ʂ����d�������B���������Ĉ�ʂɁu�n�[���v�ɓ��ꂷ��̂͗��j�����Ƃ��Č���Ă���B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@���@���Ƃ����@p.249�� |
| d�@�`���M�X���n�� | �`���M�X���n���i�c���e���W���j�͂P�P�U�Q�N�A�����S�������̃{���W�M�����̎G�X�K�C�i�C�F�X�Q�C�j�A�z�G�������Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�����S���̓`���ɋ���A���̐�c�́u�����T�v�ɁA�u�����Ď��v���ɐ��܂ꂽ�Ƃ����i�w������j�x�j�B�Ⴍ���ĕ��������A��Ɉ�Ă���B�^�^�[���A�P���C�g�Ȃǂ̃����S���n�̕��������X�ɐ������A�P�Q�O�S�N�ɂ��i�C�}���������ă����S�������ꂵ�A����̃E�C�O�����������B�P�Q�O�U�N�ɑS�����S���̌N��Ƃ��āA�N�����^�C�i��W��j���n���ɐ��Ղ���`���M�X���n���ƌĂ��B�����ł����g�v���Ə����B���ł����c�Ƃ����̍�����B��ː��Ƃ������͂ȌR���E�s���g�D�����グ�A�u���T�v�Ƃ�����@�߂𐧒肵�čL��ȍ��y���x�z�����B���̎q�Ƒ��̐���܂łɁA�����S���鍑�͓��͒�������A���͌��݂̃��V�A�A�C�����ɂ������鍑�����݂����B
�`���M�X���n���̐��������@
�E���푈�@�P�Q�P�P�N���瓌������ւ̉������J�n�A�P�Q�P�S�N�ɂ͂��̓s���s�i�����B���݂̖k���j���́B���_�\�Z�B���x�z�����B���͉��͂��z���ē�̊J���ɓ��ꂽ�i��P�����푈�j�B
�E���������@�P�Q�P�X�`�P�Q�Q�T�N�@�`���M�X���n���͐��ɓ]���A�g���L�X�^���ɓ���Ă����i�C�}�����i���ɂ̉��ʂ�D���Ă����j��łڂ����B���ɂɕ������Ă������E�C�O�������������S���x�z���ɓ���A�E�C�O���l�̓����S���鍑���x���銯���w�ƂȂ����B����ɐ��i�����`���M�X���n�����}�[�������[���A���i�t���ɓ������T�}���J���h�A�u�n���Ȃǂ�j�A���������A�W�A�̋����ł������z���Y���𐪕��A�C�����ɂ��N�U�����B�܂����̕����̈���̓J�t�J�X�R�����z���ē샍�V�A�ɐN�������B
�E���ĉ����@�`���M�X���n���͂P�Q�Q�V�N�Ƀ����S�������̓�Ɉʒu���鉩�͏㗬�I���h�X�n���������ɉ��������B�����͐��Ă������R�ւ̎Q���������Ƃɂ������B�����S���R�͑�R�œs�̋��c���͂B�������ח��O�Ƀ`���M�X���n���͂���ɓ���̘Z�ՎR�Ɉڂ�A�����Ŏ��i���L�Q�Ɓj�B
Epi.�@�`���M�X���n���̎��@1226�N�H����̐��Ăւ̍ďo���ŁA��s�J�Ăɔ���A���y�t�߂ɖ{�w��z�����B1227�N�āA���č������a����Ă����Ƃ��A�`���M�X���n���͊Ïl�ȘZ�ՎR���̐������Ŏ���ɗ��n���������������āA�W��18���A
���B���̎��͔閧�ɂ���A�▽�ɂ�萼�č����Ƃ��̈ꑰ�A����єJ�ď�̏Z���͂��Ƃ��Ƃ��E�C���ꂽ�B�`���M�X���n���̈�[�͑r��邵�ă����S���A�Ɉڂ��ꂽ���A������镺�͓r���ő��������҂��A���ׂĎE���Ȃ���i�B���̗��R���]���铽���邽�߂ƁA�n���̎���̐����Ɏd��������Ƃ������M���������ɂ������Ȃ��B�͂��߂đr�����\���ꂽ�͈̂�[���P�������͂̌��ɋ߂��{�c�ɓ���������ł���B��[�͏��@�܂̃e���g�ɏ������u����A�ꑰ����������҂��āA�I�m���E�P�������E�g���O�͂̌��u���n���R���̈��ɖ������ꂽ�B�т̖��E�����
���n�C���̐�˂����̒n�̎��𖽂����A�O���̎҂͋߂Â����Ƃ�������Ȃ������B�`���M�X���n���Ƃ��̌�p�҂̕�̏��݂͍��Ɏ���܂ŁA�����������Ă��Ȃ��B�����S���l�Ȃǂ̖k���V�q���͕��n���[�������K���������Ă����B���⑺�E�w������j�x�����V���@P.187-9�� |
| e�@�����S���鍑
| �����S�����������̗V�q�����ł����������S�����ɂ����ꂽ�`���M�X���n�����A�P�Q�O�U�N�Ɍ��݂�����鍑�B�`���M�X���n���̎��Ƀ����S���������璆���k���A�����A�W�A�A���g���L�X�^���ɂ���ԑ�鍑�����݂����B���̌`�Ԃ́A�`���M�X�̈ꑰ���x�z����V�q����s�s���A�_�����܂ލ��ƂƂ��Ă��E���X�����������A�A���̂ł������B��ɂ͂��̎x�z�̈�𒆍��S�y�A���A�W�A�A���V�A�ɂ��L���A����Ɏ��ӏ����������������A��n���̌��𒆐S�Ƃ���n�����i�E���X�j�ɕ�����čL��Ȓ鍑�̂��x�z�����B�n���̈ʂ́A�`���M�X���n���̌������Ђ����̂̒�����A�ꑰ�̗L�͎҉�c�ł����N�����^�C�ɂ���đI�o���ꂽ�B
�̓y�̊g���@��Q����I�S�^�C���n���͒���������łڂ��A�s���J���R�����ɒ�߁A�o�g�D�����[���b�p�����ɔh�������V�A�̒n�܂Ŏx�z���g�債���B��S��������P���n���̎��ɂ́A�`�x�b�g�A�_��𐧈��A�t���O�𐼃A�W�A�����ɔh�����ăA�b�o�[�X����łڂ����B�������ă��[���V�A�嗤�̓����ɉ��т�A���E�j��ő�̗̓y���������S���鍑�����������B
�E���X�̕����@��S�ヂ���P���n���̎�����n�C�h�D�̗����N����A����͏@���t�r���C���n���������������S���ƒ�����̓y�Ƃ������鍑�ƁA�C�����n�����A�L�v�`���N���n�����A�`���K�^�C���n�����A�I�S�^�C���n�����̂S�n�����i�E���X�j�Ƃɕ�����邱�ƂƂȂ����B�i���݂ł́A�I�S�^�C���n���͎��͖̂��������Ƃ��āA�R�n�����Ƃ�������L�͂ŁA�R��o�ŎЂ́w�ڐ����E�j�x���O�U�N�x�����ł���A�u�S�n�����v�Ɓu�I�S�^�C���n�����v�̊��q�����ł��Ă���j�B
���鍑�@�t�r���C���n���͂P�Q�U�S�N����s�i���݂̖k���j��s�Ƃ��A�V�P�N�ɍ��������ɉ��߂��B�P�Q�V�X�N����v��łڂ�������A���N�������������Ƃ��A���{�����i�����j�Ȃǎ��ӏ����ɂ������R��h�������B���̊ԁA�P�Q�U�U�N���瑱�����n�C�h�D�̗����P�R�O�T�N�ɒ�������A���̌�͊e�n�������@�Ƃ̌��ɕ������A�u�^�^�[���̕��a�v���������A�Q��ڂ̑�n�����@�̎��Ɍ��͑S�����ƂȂ����B�������A�����̃n�����͎���ɓƎ��������߁A�C�����n������L�v�`���N���n�����̓C�X���[���������B
���[���V�A�̓��������@�L��ȃ����S���鍑�́A��s�J���R�����𒆐S���w�`���x�i⋐ԁA�W�����`�j����������A�E�C�O���l�A�g���R�l�A�C�X���[�����k�Ȃǂ̏��Ɗ������L���W�J���ꂽ�B���[���b�p���\���R�̓W�J����Ă�������̌㔼�ɂ�����A�|�[�����h�E�h�C�c�ւ̃����S���̐N���͑傫�ȋ��ЂƂȂ������A���A�W�A���ʂł̓C�X���[�����͂ƑR��A�����S���鍑�Ƃ����ԓ������������B���̂悤�Ȓ�����A�P�R���I�̌㔼�ɂ̓��[�}���c�C���m�P���e�B�E�X�S���ɂ���J���s�j�A�t�����X�����C�X���ɂ�����u���b�N��̃����S���ւ̎g�߂�h���ƂȂ�A�܂��C�^���A�̏��l�}���R���|�[���͌��̑�s�ɕ����A�t�r���C���n���Ɏd����ȂǁA�������������ɂȂ����B
�����S���鍑�̖ŖS�@�P�S���I�ɂ́A���ł̓n���̒n�ʂ��߂�������������Ĉ��肹���A�܂��`�x�b�g�����ی�ɂ�������A����̗����ɂ��o�ς̍����Ȃǂ̂��߂ɎЉ�̕s���肪�����A�������̃����S���l�x�z�ɑ��锽�������܂����B�P�R�T�P�N�����@���k�Ƃ������ԏ@���̒c�̂̔�������n�܂����g�Ђ̗����g�債�A�P�R�U�W�N�ɓ싞����������������ƌ��͑�s��������A���͖ŖS�����B�܂��A�L�v�`���N���n�����ł̓��X�N����������������A�`���K�^�C���n�����ł̓e�B���[�����䓪����ȂǁA�����S���鍑�̃��[���V�A�x�z�͏I�����������B�������A�����A�W�A�̃e�B���[���鍑��C���h���x�z�������K���鍑�͂�������`���M�X���n���̌�p�҂������Ď��F���A�����S���鍑���p���������Ƃ����Ђ̋��菊�Ƃ��Ă���B |
| f�@��ː�
| �P�Q�O�U�N�A�`���M�X���n���������S���鍑�̌R�����s���g�D�Ƃ��ĕҐ��������́B����܂ł̌����I�ȕ��������ĕҐ��������̂ŁA�\�˂��P�O�W�߂ĕS�ˁA�S�˂��P�O�W�߂Đ�˂Ƃ��A���ꂼ��ɏ\�˒��A�S�˒��A��˒���u�����B��˒��ɂ͗L�͕����̑������C������A���ꂼ��S�ˁA�\�˂��璥�����A����������Ґ�����ƂƂ��ɁA�����̍s���ɂ������点���B�`���M�X���n���͎�����X�T�̐�˂����L���A�Z���q�������ɂ����ꂼ���˂Ɨ̒n��^�����B |
| ���@�E���X | �`���M�X���n�������݂������Ƃ́A�u�E���X�v�ƌ���ꂽ�B�����S����Łu���Ɓv��u�����W�c�v���Ӗ����A�g���R��̒n���s�s���Ӗ�����E���V�����炫�����t�ƍl�����Ă���B�����S���鍑�͓����́u�僂���S�����E���X�v�ƌ����Ă������A�₪�ė̓y���q�⑷�ɕ��^�����ƁA���ꂼ�ꂪ�u�E���X�v�Ƃ��ĕ������A�����S���鍑�̓E���X�̘A���̂Ƃ����`�ԂƂȂ����B
�`���M�X���n���̍����@�`���M�X���n���́A�O�l�̑��q�A�W���`�E�`���K�^�C�E�I�S�f�C�ɂ��ꂼ��S�̐�˂^���ĉ����̐����i�A���^�C�R�����ʁj�ɔz�u���ď��q�E���X�Ƃ��A�E���ɂ͎O�l�̎���̌n���ɂ��ꂼ��P�A�R�A�W�̐�˂�^���ĉ����̓����i��������ʁj�ɔz�u���ď���E���X�Ƃ����B���̓����ɂ͈ʒu�����ꑰ���Ƃ̒����ɁA�`���M�X���g�Ɩ��q�g�D���C�ɒ��������ˌQ���A��͂蓌���ɕ������Ă����B�`���M�X���g�̓P�V�N�Ƃ����߉q�R�c������S�����ɕ��u�����I���h�ƌĂ��V���Q����Ȃ�V�q�{�����点���B�܂�A�`���M�X�̐V�����́A�����Ƀ`���M�X�Ƃ��̓V���Q�i�I���h�j�Ƃ�������߉q�R�c�i�P�V�N�j��u���A���E�ɒ����̐�ˌQ����\������A���̊O���ɓ��l�ȍ\���������E�O���̈ꑰ�������z�u���ꂽ�B���ꂪ��̃����S�����E���X�̂��ׂĂ̌��^�ł���B
�����S���͖������ł͂������ł��邱���@�`���M�X���n���̍��Ƃ̖��́A�u�C�G�P�E�����S���E�E���X�v�A�܂�u�僂���S�����v�ł���B���̐V���ƂɎQ���������ׂĂ̍\���������́A���Ƃ��o�g�E����E�e�e������Ă��A�݂ȁh�����S���h�ƂȂ����B���̎������S���Ƃ́A�܂������̖��ł͂Ȃ��A�����܂ō��Ƃ̖��̂ɉ߂��Ȃ��B�ꖇ��́h�����W�c�h�Ƃ���̂͌���ł���B�僂���S�����Ƃ́A���푰�����̃n�C�u���b�g�W�c�ł���A�������̈ꑰ�E���X������鑽�d�\���̘A���̂Ƃ��ďo�������̂ł������B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@��@p.42-45�� |
| �@���T | �`���M�X���n�������肵���Ƃ����@�߁B��ʓI�ɂ͂P�Q�O�U�N�ɃN�����^�C�Ńn���̈ʂɂ����Ƃ��ɁA�`���M�X���n�����u�僄�T�v�𐧒肵�A���̌�⑫����Ȃ���A�����S���鍑�̖@���Ƃ��ꂽ�ƌ����Ă���B�������A�u�僄�T�v�̌����͎c���Ă��炸�A�`���M�X���n���̎��ɐ��肳�ꂽ���Ƃɂ͔ے�I�Ȍ���������B�����u���T�v�̐���́w������j�x��w�W�j�x�Ŏ��グ���Ă��邪�A���ۂɂ̓`���M�X�n���ȑO����̃����S���̊��K�@��A�`���M�X���n���̌��s�A�N�����^�C�ł̌��莖���̋L�^�Ȃǂ�����������A���̂��Ƃ́u�僄�T�v�ł������ƍl������悤�ɂȂ������̂ł��낤�B���c�D���[�K���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@���R�����E�哇�~�q��@p.91-95��
�����S���ɂ͐����@�͖����A�`���M�X���n������߂��u���T�v�i�܂��̓��T�N�̓g���R��B�����S����ł́u�W���T�v�܂��̓W���T�N�j�͌��`�œ`�K���ꂽ�A�����炭�����ɂ͌R���ł������B�E�C�O���l�Ȃǂ́u�g���v�Ƃ������K�@�̉e�����������炵���B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.194�� |
| �i�C�}��
| �����S�������̐��암���������Ă����V�q���ƁB�����S�����Ɠ��n���̃i�C�}�����Ƃ��������ł��������A�g���R�n�Ƃ̍�����������ł����炵���B�l�X�g���E�X�h�L���X�g��������Ă����B�P�Q�O�S�N�A�����S�������̓����ɋ����������S�������`���M�X���n���̍U�����A���̉��^�������n���͎E�����B�������ă����S�������̓�����}�����`���M�X���n���������S���鍑�̐����ƂȂ����B�^�������n���̎q���N�`�����N�́A�����A�W�A�̃g���L�X�^���ɓ���A�P�Q�P�P�N�J�����L�^�C�i���Ɂj�̉��ʂ�D�������A�P�Q�P�W�N�A�`���M�X���n���ɔh�����ꂽ�����S���R�ɔs��E���ꂽ���߁A�i�C�}�������͖ŖS�����B�Ȃ��A�i�C�}���������łт��A���L���Ƃ��Ďd�����̈�͂��Ǘ����Ă����E�C�O���l�̃^�^�g���K���߂炦���A�ނ����E�C�O�������������S���ɓ`�����A�`���M�X���n�����g��������w�сA�����S�������𐧒肵�A�����̐��x�����č��Ƃ炵���̐��𐮂����Ƃ����B |
| g�@�z���Y��
| �P�Q���I���ɐ��g���L�X�^���̃A���쉺����ɖu�����đ卑�ƂȂ������A�����S���ɂ���Ėłڂ��ꂽ�g���R�n�̃C�X���[�������B�z���Y���Ƃ����̂͒����A�W�A�̃A�����C�ɂ������A����̉�����n���������n���B�A���r�A��ł��t���[���Y���i��̌������̒n�Ƃ����Ӗ����}�[���A���[���A���i�t���Ƃ������j�B�W���I�ȍ~�C�X���[�������A�P�O�V�V�N�A�Z���W���[�N���̃g���R�l�}�����[�N�i�g���R�l�z��j�A�A�k�V�����e�M�������̒n�̑��ɔC������A�z���Y�����V���[���̂���B���̌�Z���W���[�N������Ɨ����A�z���Y���n���̃E���Q���`��{���ɁA�P�R���I�ɋ}���ɑ䓪�A�V��ڂ��A���[���A�b�f�B�[�������n���}�h�i�݈�1200�`1220�j�̎��ɍŐ����ƂȂ�A�P�Q�O�X�N���J�����L�^�C�i���Ɂj����T�}���J���h�A�u�n���Ȃǂ�D���A������S�[��������A�t�K�j�X�^����D�悵�A�C�����ɂ��i�o���Ē����A�W�A���琼�A�W�A�ɋy�ԋ��������݂����B���̂����40���̌R�������邱�Ƃ̏o���A�P�R���I�����̓����C�X���[�����E�̍ŋ����ł������B�������A�������듌���̃����S�������ł̓����S���`���M�X���n�����䓪���Ă����B�`���M�X���n���̓z���Y���Ƃ̌��Ղ��J�����ߑ�����h�������Ƃ���A�A���[���A�b�f�B�[�������n���}�h����������ۂ��A�������E�Q�����B����ɑ���Ƃ��āA�P�Q�P�X�N����`���M�X���n������z���Y���ɑ剓�����s���A���̍U���͂P�Q�Q�T�N�܂ł̂V�N�ԑ������B�z���Y���͓�������������Ĕs��A�}�[���A���[���A���i�t�����������B���̌�A���q�W�����[�����E�b�f�B�[���������Č�����ă`���M�X���n���ɒ�R�������A�P�Q�R�P�N�ɖŖS�����B�z���Y���n���͑唼���C�����n�����A�k�����`���K�^�C���n�������x�z���邱�ƂƂȂ����B����Ƀe�B���[���鍑�̎x�z������A�E�Y�x�N�l�̎O�n�����̂ЂƂA�q���@���n�������P�T�P�Q�N�ɐ�������B |
| h�@����
| �@���@��R�́@�R�߁@�C�D�k���̏����́@���� |
| �a�@�����i���[���b�p�j���� | �P�Q�R�T�N�A��Q��n�����I�S�^�C���n���͐����ւ̑剓��������A�o�g�D�i�`���M�X���n���̒��q�W���`�̎q�j���w�����Ƃ��ĉ����R��h�������B����̓`���M�X���n�������j�W���`�ɒ鍑�̐����ɗאڂ���n��̎x�z����^���Ă������A�W���`�������߁A���̎q�o�g�D�̔C���Ƃ��ꂽ���̂ł���B
�o�g�D�͐��i���Ă܂��P�Q�R�U�N�Ɍ��݂̃J�U�t�X�^���̑呐���n�тɓ���A���H���K�쒆���̃g���R�n���u���K�[���l�̍��Ƃ𐪕����A���̎��ӂ̍L��ȑ����Ŋ������Ă����g���R�n�V�q���ł���L�v�`���N�l���]���A�ނ���R�n�R�c�ɑg�ݓ��ꂽ�B����Ȍ�A�g���R�n�R�n�����̓����S���R�̏d�v�Ȑ�͂ƂȂ�B�P�Q�R�V�`�S�O�N�̊ԂɃL�G�t�𗪒D����Ȃǂ��ă��V�A�i�L�G�t�����j�𐧈��A����ɓ���ɕ�����A��ɉ�����o�g�D�̖{���̓n���K���[�ɐN�U�A�P�Q�S�P�N�n���K���[�����̃x�[���S���̌R�����j����s�u�_���y�X�g��j���B�k�Ɍ�����������̓|�[�����h�ɐN�U���A�������P�Q�S�P�N�A�V���W�A�̃��[�O�j�b�c�̋ߍx�����[���V���^�b�g�̐킢�Ń|�[�����h�ƃh�C�c�̘A���R��j�����B�P�Q�S�Q�N�A�����S���R�̓E�B�[���߂��ɔ��������A�}篓P�ނ����B�O�N�ɃI�S�^�C���n���������������ƁA���[���b�p�̐X�ђn�т̓����S���ɂƂ��ĉ��l���Ȃ��ƍl����ꂱ�ƁA�Ȃǂ����R�Ƃ��Ă������Ă���B
�����S���̐����̉e���@�����S���R�̐N���̓L���X�g�����E�ɑ傫�ȋ��ЂƂȂ�A���[�}�����̃t���l���A�b�e�B���剤�̐N�����v���o�������B������\���R�����̏I��肠���Ă���A���n�������ł����A�C�X���[�����͂ɉ�����Ă����L���X�g�����E�ł́A�����S���R�̓������v���X�^�[���W�����̓`���Ɍ��т��Ċ��҂��铮�������������A���̊��҂͗���ꂽ�B���[���b�p�ɂƂ��Ă̓����S���̐N�U�͌��ǁA��ߐ��̂��̂ɏI��������A�����S���R�̐N���ɂ��т��������̃��[���b�p�́A���[�}���c�Ɛ_�����[�}�鍑�c��i�t���[�h���q�Q���j���������Η����Ă����B�|�[�����h�̓h�C�c�l�������A�����W�J����Ă���A���ꍑ�Ƃ̌`���͒x��Ă����B�����S���̋��Ђɂ��炳�ꂽ�n���K���[���́A���c�ɑS�L���X�g�����E����̉�����v���������A���c�h����ɉ������Ȃ������B�P�Q�S�Q�N�ɂ��̊�@����������A���[�}���c�i�C���m�P���e�B�E�X�S���j�͎g���v���m���J���s�j��h�������B�܂��A�Ō�̏\���R��h�������t�����X�����C�X���̎��ɂ����u���b�N���J���R�����ɕ����Ă���B
Epi.�@�����S�������R�̏��N�����@�u�����S�������R�̎�͂́A���N�����ł������B�����S���������o�����鎞�́A�P�O��́A������O���̏��N�ł��邱�Ƃ����������B�ނ�͒��������̉ߒ��ŁA���܂��܂ȑ̌������A���n�̌P����ʂ��āA����ɂ����ꂽ��l�̐�m�ɂȂ��Ă������B�����S�������R�̊e�����̎w�����́A�����̌Ë��҂����Ă�ꂽ���A�������̂��͔̂N�Ⴍ�q���Ȏ҂������琬���Ă����̂ŁA�R���s�����v���ł������B�f���ŁA�w�����̌������Ƃ��悭�������B�����Ă��܂��Ȏq�������A�g�y�ȕ�����������ɂ�����݂₷�������B�s�N����V�N�������A���ꌇ�R�ɂ��悭�ς��A�Ђ�����퓬�̏�����簐i�����B�����������N���ɂƂ��āA�����̏o���͐l���ւ̗������ł��������B�E�E�E�E�ނ�͉�����ŁA���̂܂ܗ��������Ă��܂����Ƃ��A�����ł������B���̏ꍇ�A���₷�������l�ƂȂ������Ă̏��N����A����ɂ��̑��������A��͂�u�����S���v�ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ������B�͂邩�Ȃ郂���S���{�y�̍����ɂ́A�Z��o���A�ꑰ�e�ނ������B�A��ׂ��S�̂ӂ邳�Ƃ́A�݂ȃ����S�������ł������B�����āA�鍑�̊g��ɔ����ď����ɎU�����u�����S���v�������A�����Ȃ����ł�������ƌ��т��Ă�����̂́A�����ɕς�邱�ƂȂ������Ă���h�����S���E�E���X�h�ł������B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@p.78-79�� |
| a�@�I�S�^�C���n��
| �`���M�X���n���̑�R�q�B�I�S�f�C�Ƃ��\�L�B�P�Q�Q�X�N�N�����^�C�Ő�����������S���鍑�̑�Q����n���ƂȂ�i�_���͑��@�B�݈ʂP�Q�S�P�N�܂Łj�B�܂��A����������łڂ��i�P�Q�R�S�N�j�A�����S�������ɐV�s�J���R���������݁A�w�`���i�W�����`�j�̐����A�ˌ������Ȃǂ��s���A�����S���鍑�̊�b��z�����B�`���M�X���n���ɑ����A�_�O�l���뗥�^���������Ƃ��ďd�p�����B�P�Q�R�T�ȍ~�A�o�g�D�𐼕��ɔh�����A���V�A�𐧈����A�����[���b�p�ɐN���������B�P�Q�S�P�N�ɕa�����A��R��n���ʂ͒��q�O���N�Ɍp������邪�A�O���N���}��������A�`���M�X���n���̖��q�g�D���C�̎q�������P���A�N�[�f�^�[�ɂ���ăI�S�^�C�Ƃƃ`���K�^�C�Ƃ̐��͂���|���A��S��n���ƂȂ����B
Epi.�@�`���M�X���n���̎q�ǂ������̓����@�`���M�X���n���ɂ͂S�l�̑��q�������B���j�W���`�i�W���`�Ƃ��\�L�j�͋���������ł������͔��Q�ŗD�G�ł��������A���̓`���M�X���n���̎��q�ł͂Ȃ��A�Ƃ����\������A�n���ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�ƌ����Ă����B�P�Q�Q�V�N�ɒ����A�W�A�������Ɏ���ł����B���j���`���K�^�C�͋C�����������A�l�]���Ȃ������B�O�j���I�S�^�C�i�I�S�f�C�j�ł��邪�A���ƂȂ������Ɏ�蕿�̂Ȃ��l���Ǝv���Ă����B�S�j���g�D���C�͖����q�ŕ��ɍł����킢�����Ă���A�܂��D�G�Ȏ��͎҂Ǝv���Ă����B�����S���ɂ͓��Ɍ��܂��������@�͂Ȃ��A�Ɠ͎��͎�`�A�ƎY�͖��q���L���Ƃ����X�����������̂ŁA�g�D���C���I�o����邱�Ƃ��\�z����Ă������A���ʂ̓I�S�^�C�ɂȂ����B�����S���鍑�̐��j�ł̓N�����^�C�̑S���v�Ƃ����A�g�D���C���p������\��̉ƎY���I�S�^�C�ɏ������Ƃ����A�u�킵��������v�Ƃ���Ă��邪�A���ۂ̓`���K�^�C���g�D���C�ɑ��ʂ����Ȃ����߁A�I�S�^�C�𐄂������ʂ��낤�Ƃ����B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.27-58 �Ȃǂɂ�遄 |
| b�@��
�̖ŖS | ���^�������k�����x�z�������Ƃł������ɑ��������S���鍑�̍U���̓`���M�X���n���̂P�Q�P�P�N�Ɏn�܂�A�P���ƂQ���ɂ킽��푈�̌��ʁA�ŏI�I�ɂ��I�S�^�C���n���̔h�����������S���R�̍U���ɂ���āA�P�Q�R�S�N�����͖ŖS����B
��P�����푈�@�����S���R�̋��ւ̐N�U�́A�`���M�X���n���̎��̂P�Q�P�P�N�Ɏn�܂�B���̂Ƃ��̍U���Ŏ�s�̒��s�i�����A���݂̖k���j�̖k���̎��ł��鋏�f�ւ�j���A�Ȍ㖈�N�̂悤�Ƀ����S���R�̐N�U����B�P�Q�P�S�N�A���͎�s���ێ��ł��Ȃ��Ȃ�A��� ���i�J���j�ɑJ�s�i��S�̓�J�j���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������ă����S���鍑�͌��݂̖k���𒆐S�Ƃ��鉍�_�\�Z�B���x�z���Ɏ��߂��B ���i�J���j�ɑJ�s�i��S�̓�J�j���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������ă����S���鍑�͌��݂̖k���𒆐S�Ƃ��鉍�_�\�Z�B���x�z���Ɏ��߂��B
��Q�����푈�@�`���M�X���n���͂��̌㐪���̖ڕW�𐼂̃z���Y���Ɍ������̂ŁA�����S���̐N�U�͈ꎞ���܂������A��Q���I�S�^�C���n���i���@�j�ƂȂ��ē�i���ĊJ�����B�P�Q�R�O�N�Ƀ����S���R�͍����J�n�A���͂�n��J���ɔ������B�����S���R�Ƌ��R�̎��Y��������킢�͂P�Q�R�Q�N�A����A�J���̐���̎O���R�̐킢�������B�����R�͊�����B�i���������n�_�j������P�T���A����ɑ��čU�߂�g�D���C�̗����郂���S���R�͂S���A���邢�͂P���R��ł������B
�u�ǐ��̃����S���R�́A�Ȃ�Ɣn���~�肽�B�͍����@���āA�n�Ɖ䂪�g���B�����B���Ƃ��Ȃ����R�́A�U�߂ɍU�߂��B�������A�Q���Ɗ����ŁA�̗͂͂����܂��s�����B�����S���R�͔��U�ɓ]�����B�E�E�E���R��͂͑S�ł����B�v���̐H�ƕs���́A�u�l�����v�ɂ����̂������B�����S���̐N�U�����ꂽ�ؖk�̔_�����J���ɉ����A�H�ƕs������Љ�s���������Ă����̂ł���B�u�J������ł͉u�a���������A�X�O���ȏ�̊������o���ƋL�^����Ă���B�؍ނ̖R�����ؖk�ł͊����͍�������������A���ۂɎ��҂́Aꡂ��ɑ����ƌ����Ă���B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.61��
�P�Q�R�Q�N ���i�J���j�͊ח��A�������͋A���������B�ɓ��ꂽ���A���@�͂P�Q�R�S�N�Ɏ������A�������͖ŖS�����B�����암���x�z���Ă�����v�́A�����S���R�̓쉺�Ɍĉ����ċ��̗̓y�ɐN���������A�����S���Ɠ�v�̋���͐��������A���ŖS��͗��������E���̟̐��t�߂ŏՓ˂��J��Ԃ����ƂƂȂ����B ���i�J���j�͊ח��A�������͋A���������B�ɓ��ꂽ���A���@�͂P�Q�R�S�N�Ɏ������A�������͖ŖS�����B�����암���x�z���Ă�����v�́A�����S���R�̓쉺�Ɍĉ����ċ��̗̓y�ɐN���������A�����S���Ɠ�v�̋���͐��������A���ŖS��͗��������E���̟̐��t�߂ŏՓ˂��J��Ԃ����ƂƂȂ����B
Epi.�@���푈�̉p�Y�A�g�D���C�̕s���Ȏ��@�V��I�S�^�C�͂قƂ�ǎ��킷�邱�ƂȂ��A�p�Y�͎O���R�̐킢�������ɓ������g�D���C�i�`���M�X���n���̖��q�j�������B�Ƃ��낪�g�D���C�͌Z�I�S�^�C�ƈꏏ�ɖk�ɋA��r���}�������B�u�a���Z�I�S�f�C�̐g����ɂȂ�ƌ����āA��t�����݊����A�ӎ����������Ă݂܂������Ƃ����B��Ȕ��k�ł���B�v�����S���̐��j�ł���w�W�j�x�̓C�����n�����ō��ꂽ�B�C�����n�������������t���O�̓g�D���C�̎q�ł������̂ŁA�w�W�j�x�ł̓I�S�^�C�ƃg�D���C�̊ԂɊm�����������Ƃ͏��������Ȃ������̂ł��낤�B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.63�� |
| c�@�J���R����
| �P�Q�R�T�N�A�����S���鍑�̑�Q���I�S�^�C���n�������݂����s��B�J���E�R�����Ƃ́u�������I�v�̈Ӗ��B�`���M�X���n���̂���͒�܂����s���������A�V���ňړ����Ă����̂ŁA���ꂪ�����S���鍑�ŏ��̓s�ł���B�����S�������̒��̒n���̖L���ȑ����n�тɂ���ꂽ�s�ŁA�����𒆐S�ɁA�����S���鍑�̓��ɓ��H�Ԃ����݂���A�X���ɂ��w�`�i�W�����`�j���݂���ꂽ�B�J���R�����ɂ̓O���N�A�����P�܂ł̃n�����Z�݁A�����S���l�A�����l�A�C�X���[�����k�̑��A���[���b�p�l���Z��ł����Ƃ����B�܂����[���b�p�̃��[�}���c����h�����ꂽ�v���m���J���s�j�A�t�����X���̔h���������u���b�N�Ȃǂ◈�K���Ă���B�t�r���C���n������s�ɑJ�s���Ă���������������A�����S���鍑�ŖS��͍r�p���A���ł����B�P�W�W�X�N�ȗ��A��Ղ����@��������Ă���B�@ |
| �뗥�^�� | ���������B�����S���鍑���`���M�X���n���A�I�S�^�C���n���Ɏd���������B�_�O�l�ŁA�͂������Ɏd���Ă������A�P�Q�P�S�N�����S���̍U���ŋ��̒��s���ח������ہA�`���M�X���n���ɏ����o����d���邱�ƂƂȂ����B�`���M�X���n���̐��������ɓ��s�A���̋L�^�w���V�^�x�����B���ŃI�S�^�C���n���Ɏd���A����܂ő̌n�I�ȐŐ��̂Ȃ����������S���鍑�ɒ������̐Ő������A���̒��������ɑ傫�Ȗ������ʂ������B�I�S�^�C���n���̎���͕s���ł������炵���B |
| d�@�o�g�D
| �����S���鍑�̃`���M�X���n���̒��q�W���`�̎q�B�I�S�^�C���n���̂Ƃ��A�L�v�`���N��������A���V�A�A�����[���b�p�Ɏ���剓�����s�����B�`���M�X���n���͒��q�W���`�ɃC���e�B�V���͔Ȃ�{���Ƃ����E���X�i���Ɓj��^���A���̐��k�̍L��ȑ����ɗ̓y���g�傷��\��ł��������A�r���ŃW���`�������߁A���̂��c�������Ƃ��q�̃o�g�D���Ђ������ƂƂȂ����B���������ɁA�I�S�^�C���n���̎q�̃N�`������v�������s���Ă���A�����S���鍑�͓����ŕ��s���ė̓y�g��̑剓���R��h�����Ă����B
�o�g�D�̉����@�P�Q�R�T�N�ɏ������n�߁A�R�U�N�ɉ������J�n�A�E�����R�����z���āA�܂����H���K�쒆���̃g���R�n���u���K�[���l�̍��Ƃ𐪕������B���̎��ӂ̃L�v�`���N�����ŗV�q���������Ă����g���R�n�̃L�v�`���N�l���z�����A�P�T���̑�R��Ґ����A�P�Q�R�V�N���V�A���S���ɐN���A�����U���A���X�N���A�E���W�[�~�������X�Ɗח������A�P�Q�S�O�N�L�G�t�𐪕����L�G�t������łڂ����B����ɉ����R�����ɕ����A�o�g�D�̖{���̓n���K���[�ɐN�U�A�P�Q�S�P�N�n���K���[�����̃x�[���S���̌R�����j����s�u�_���y�X�g��j���B�k�Ɍ�������������|�[�����h�ɐN�U���A���N�A���[���V���^�b�g�̐킢�Ń|�[�����h�E�h�C�c�A���R��j�����B�P�Q�S�Q�N�A�o�g�D�R�̓E�B�[���߂��ɔ��������A�I�S�^�C���n���̎����̕�ɂ��A��n�[���I�o�̃N�����^�C�o�Ȃ̂��߉����𒆎~���A���Ɍ��������B�������A�J���R�����ɂ͖߂炸�A���H���K�����̃T���C���L�v�`���N���n�����i�W���`���E���X�j�̓s�Ƃ����B��R��O���N���n���ƑΗ��A���̈ÎE�ɂ���������Ƃ�������B��S�ヂ���P���n���̑I�o�ɂ͋��͂����B |
| e�@���[���V���^�b�g�̐킢 | �|�[�����h�ɐN�������o�g�D�̗����������S���鍑�R���A�P�Q�S�P�N�Ƀ|�[�����h�E�h�C�c�A���R�ƏՓ˂����ő�̌���B���[���V���^�b�g�̓|�[�����h�����̃��[�O�j�b�c�����ɂ���A���̐퓬�����[�O�j�b�c�̐킢�Ƃ������B�o���̌R���͂��ꂼ��R���ƌ�����B�����S���R�̓o�g�D�̕����o�C�_���ƃJ�_�A�����w���A�|�[�����h�E�h�C�c�A���R�̓V�����[�W�F���i�V���W�A�j���n�C�����b�q�i�w�����b�N�j�Q�����������B�����S���R�͌y���̋R���𒆐S�Ƃ����W�c��@�����A�d�����̋R�m�̈�R�ł���p���Ƃ�|�[�����h�ƃh�C�c�̘A���R��|�M���A�n�C�����b�q�Q�����펀���āA�����S���R�̑叟�ƂȂ����B�����S���R�͓���������G���̎������W�߂��̂��傫�ȑ܂X�܂ɂȂ����Ƃ����B
Epi. �@���[���V���^�b�g�̐킢�̋^���@�u���E�j��悭�m��ꂽ���̉����A���͖{���ɂ��������ǂ����A�肩�ł͂Ȃ��B�����㕶���ɂ͂܂������������A�P�T���I�̕����œˑR�ɑ傫������邩��ł���B���Ȃ��Ƃ��A�|�[�����h�������A�܂������͂��������Q�O�O����R�O�O���x�̓����͂����Ȃ������Ƃ�����h�C�c�R�m�c���A���́u���v�����ɁA�傫�����̊�G�ꂪ�ς��ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��B�q�Ϗ�́A���́u���v�����Ƃ��������Ƃ��Ă��A�����₩�Ȃ��̂ł��������Ƃ������Ă���B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.84�� |
| �b�@��E���A�W�A�̐���
| �����S���鍑�́A�����P���n���̖��߂Œ���t���O���A�P�Q�T�R�N���琼�A�W�A�������J�n�����B���łɃC�������ʂ́A�`���M�X���n���̉����ɂ���ă����S���̐��͉��ɓ����Ă���A�I�S�^�C����ɂ̓C�������{���u����A�z���[�T�[����J�X�s�C��݂�}���A�A�[���o�C�W��������J�t�J�X�n���A�A�i�g���A�ɂ������S���R���ԕ������������Ă����B����Ƀ����P���n���̓A�t�K�j�X�^������C���h���ʂւ̐i�o���\�z���Ă����悤�ł���B
�t���O�̉����̖ړI�@�����A�A����ȓ�̐��A�W�A�łŃ����S���鍑�ɕ��]���Ă��Ȃ������̂��A�k���C�����̎R�x�n�тɋ����Ă����V�[�A�h�C�X�}�C�[���h���ÎE���c�̐��͂ƁA�o�O�_�[�h�̃X���i�h���A�b�o�[�X���c�����͂ł������B���̐�̒n���C���ʂ܂Ői�o���邱�Ƃ�����l���Ă������ǂ����͂悭�킩��Ȃ��B�C�����n�����ŏ����ꂽ�����S���鍑�̐��j�w�W�j�x�ł́A�t���O�̓����P���n�����炱�̒n�ɃE���X�����݂��邱�Ƃ�F�߂��Ă����A�Əq�ׂĂ���B
�t���O�̏����Ɣs�k�@�܂��P�Q�T�U�N�ɂ͖k���C�������ÎE���c�𐧈��A����ɓ쉺���ăC���N�ɓ���A�P�Q�T�W�N���o�N�_�[�h���̂��A�A�b�o�[�X����łڂ����B�������ăC�����������烁�\�|�^�~�A�𐧈����A�G���鐨�͂̓G�W�v�g���}�����[�N���̐��͂̋y�ԃV���A�����ƂȂ����B�������A�P�Q�T�X�N�Ƀ����P���n�����}���������߁A�t���O�̓����S���A�҂��߂����Ėk���ɓP�ނ��A�V���A�v�����L�g�u�J�ɂ܂������B�L�g�u�J���\���R�Ƃ����͂��ĂP�Q�U�O�N�A�_�}�X�N�X���́A�B����ɃG�W�v�g���}�����[�N�������Ɍ����������A���N�A�C���W���[���[�g�̐킢�ŁA�N�g�D�Y���o�C�o���X�̗�����}�����[�N���R�ɔs���ނ����B�@���@�C�����n����
Epi.�@�����S�����\���R��������@�u�i�t�����X���j�����C�������A�W�A�ɓ�̃L���X�g���N��̑��݂����߂ĂP�Q�T�R�N�ɃJ���R�����ɔh�������t�����V�X�R��m���v���N�͖����C�����ʂ����ē�N��ɋA���������A���̒��ڂ̌��ʂł͂Ȃ��ɂ��ł��P�Q�U�O�N�����S�����\���R������킪�_�}�X�N�X��̂̌`���Ƃ��Ŏ����������Ƃ́A���C�㐢�̐헪���]������ꎑ���Ƃ����悤�B�����S�����̐����Ɉꗃ���ɂȂ����t���O�E�n���͂P�Q�T�W�N�o�O�_�[�h���ׂ�āA�܁����]�N�̓`�������A�b�o�[�X����ł�����A�k�V���A�ɐi�o���ăA���b�|���̂��A�����ŏ\���R�Ə��߂ĐڐI�����B�P�Q�U�O�N�R���̃_�}�X�N�X�U����ɂ́A�t���O�̕����Ōi���k�i�l�X�g���E�X�h�j�̃L�g�{�K�i�L�`�u�n�A�L�h�u�J�A�L�h�u�n�Ƃ��j�A�P���h�L���X�g���k�̃A�����j�A���փg�E���ꐢ�ƁA�A���`�I�L�A��{�w�����h�ܐ����������ď����������A�@�h�����Ⴄ���O�l�̃L���X�g���N�傪�����Ȃ�ׂĊM�������Ƃ����k�i�D�q�D�X�g���[���[�l�B���̂悤�ȋǒn�I�F�D�W���ǂ�قǂ̕K�R���������Čp�����邩�^��ł��������A���N�����S���R�͌��@�����P�E�n�����]��ɐڂ��ĕ����Ђ����̂ŁA�\���R�Ƃ̌𗬂��m�₵���B�v�������ω�w�\���R�x��g�V���@P.199�� |
| a�@�����P���n��
| �����S���鍑��S��n���B�_���͌��@�i�݈ʂP�Q�T�P�`�T�X�N�j�B�`���M�X���n���̖��q�g�D���C�̎q�B�I�S�^�C���n���̎��A�o�g�D�̐����ɉ����B��R��O���N���n�������Ƃ��A�o�g�D�̎x�����ăn���ɑ��ʂ��A�I�S�^�C���n���ƃ`���K�^�C���n���̎q���������Y�A�Ǖ��ɏ����A���͂��������B���t�r���C���`�x�b�g����_��n���A�x�g�i���ɐi�������ē�v�̓����}���A����ɒ��t���O�𐼃A�W�A�ɔh�����āA�C�����𐧈������A�o�N�_�[�h���ח��������B�Ō�Ɏ����v�����R���w�����ē쉺�������A�P�Q�T�X�N�A�l��ŕa�v�����B
Epi.�@�����P���n���̐l�����@�����P�́A���ʂ����Ƃ��S�S�B�u�ނ́A���J��������݂ɘb���A���[�N���b�h�w���͂��ߓ����̊w�p�E�����ɒʂ��Ă����B���ł͕��g�D���C�̎O���R�̌���ɂ��]�R���A���ł̓J�t�J�Y�ɂ������������B�����E�\�͂ɂ��ӂ�A���́E���сE���]�E���̂ǂ���Ƃ��Ă�����̂Ȃ��v�����X���̃v�����X�ł������B�l�ގj��ł��A�ނقǐ��܂�Ȃ���Ɋ��҂���A�鉤�ƂȂ�ׂ��h���Â����A�����������Ƀ��[���V�A�̓����ɂ܂�������n�̌��܂������^�����̎��͂��A�l�Ƃ��Ă����͎҂Ƃ��Ă��A�ǂ������Ă���l���͂قƂ�nj�������Ȃ��B�E�E�E�E�����P�́A�������ɗL�\�ł������B�ނ���A�l�̏�ɗ��ɂ́A���ׂĂɂ킽���Ĕތl���L�\�����邱�Ƃ��A�ނ̔ߌ��̉����ƂȂ����B�E�E�E�����P�́A������ׂ��ꐧ�N��ł��邱�Ƃ��A���ʂ̏��߂��猩�������B�ނ̑_���́A�`���M�X���E�Ȍ�̂��ꂽ����f����A���݂������鍑�̓��������邱�Ƃł������B�������A���܂�ɂ��ʒf�A�ɒ[�������B�鍑�̕s����v�f�́A�������đ������ꂽ�܂܁A�����҃����P�̂��ƂŐ��݉������B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.98-100�� |
| b�@�嗝��
| �@���@��R�́@�R�߁@�嗝 |
| c�@�t���O
| �����S���鍑�̃`���M�X���n���̖��q�g�D���C�̎q�ŁA�����P���n���̒�B�t���O�Ƃ��\�L�B�P�Q�T�R�N����A�����P���n���̖��߂����A�W�A�����ɏo���B�P�Q�T�U�N�ɖk���C�����̎R�x�n�тɐ��͂��Ă����V�[�A�h�C�X�}�C�[���h���ÎE���c�̖{�����U�����Ėłڂ����B���œ쉺���ă��\�|�^�~�A�ɓ���A�P�Q�T�W�N���o�N�_�[�h���ח������A�Ō�̃J���t�E���X�^�[�X�B�����E���A�A�b�o�[�X����łڂ����B���������N�A�����P���n���̎��ɂ��A���A�W�A�̃V���A�E�G�W�v�g�U���͕����̃L�g�u�J�ɔC���A�J���R�����A�҂��߂��������A�t�r���C�̑��ʂ̒m�点���A�P�Q�U�O�N�Ɏ���̓C�����̐������^�u���[�Y�����_���C�����n�����i�t���O���E���X�j���������A�C�����̓����ɂ����邱�ƂƂ����B�t���O�̕����̃L�g�u�J�̓V���A�U���𖽂���ꂽ���A�P�Q�U�O�N���}�����[�N�����o�C�o���X�Ƃ��A�C���W���[���[�g�̐킢�Ŕs��A�V���A����G�W�v�g�ւ̐i�o�͂ł��Ȃ������B�t���O�̓t�r���C���n�����x�������̂ŁA�t�r���C�ƑΗ����Ă����`���K�^�C���n�����ƑΗ����邱�ƂƂȂ�A����ɃC�����k���̔엀�ȃA�[���o�C�W�����n�����߂����ē��������S���鍑�̕����ł����L�v�`���N���n�����ƑΗ����邱�ƂƂȂ����B�P�Q�U�T�N�A�L�v�`���N���n�����Ƃ̐퓬�̂��Ȃ��ɋ}�������B |
| d�@�o�O�_�[�h
| �@���@��T�́@�Q�߁@�A�D�����C�X���[�����E�@�A�b�o�[�X���̖ŖS |
| �c�@�����S���鍑�̕���
| �����S���鍑�̓����ґ�n���̒n�ʂ́A�`���M�X���n���̌��������ꑰ�̗D�ꂽ�҂��A�N�����^�C�̑S����v�̐��Ղɂ���ďA�C���邱�ƂƂȂ��Ă����B���������̒n�ʂ��߂����āA�`���M�X���n���̂S�l�̑��q�i�W���`�A�`���K�^�C�A�I�S�^�C�A�g�D���C�j�̊Ԃł܂��������N����A��Q��ɂ��I�S�^�C���I�o���ꂽ���A���̌���������₦�Ȃ������B��R��̓I�S�^�C�̎q�O���N���p�����������Ɏ����i�ŎE�̋^��������j�A��S��ɂ̓g�D���C�̎q�����P���Ȃ����B���̂Ƃ��A�I�S�^�C�ƃ`���K�^�C�̈ꑰ�͒�������r������A���ꂼ��Ǝ��̃n�������`�������i�������蒅���Ȃ������j�B�܂��W���`�i�`���M�X���n���̎��q�ł͂Ȃ��Ƃ������킳���������j�ꑰ���������牓�������A�������L�v�`���N���n�������������B�����P���n���̒��t���O�͐��A�W�A�ɉ����A�����ő�T��ɌZ�̃t�r���C���n�����A�C����ƁA���̂܂��C�����n�����������ĂƂǂ܂����B�{���t�r���C���n���͋��_�𒆍��x�z�Ɉڂ��A���鍑���������B�������ă����S���鍑�͌��ƃn�����i�E���X�j�ɕ�����邱�ƂƂȂ�A����ɓƎ��������߁A�݂��ɑ����悤�ɂ��Ȃ�B�t�r���C���n���ɑ��ẮA�I�S�^�C�Ƃ̃n�C�h�D�̂悤�ɔ������鐨�͂������������A�t�r���C���n���̎���A�P�R�O�O�`�O�T�N���n�C�h�D�̗�����������Ă���̓����S���ƒ������x�z����{���ő�n���̌��ƁA�����A�W�A�̃`���K�^�C���n�����A���A�W�A�̃C�����n�����A�J�U�t�������烍�V�A�ɂ����ẴL�v�`���N���n�����Ƃ����R�n��������������������Ƃ����������������A�P�S���I�O���܂ł��^�^�[���̕��a�i�p�N�X�E�����S���J�j�Ƃ����郆�[���V�A�̈��肪�����炳�ꂽ�B
���݂̋^�킵���n�����@�����S���鍑���\������n�����́A�]���A�I�S�^�C���n�����A�`���K�^�C���n�����A�L�v�`���N���n�����A�C�����n��������ׂāu�S�n�����v�ƌ����Ă������A�ŋ߂̌����ł́A�I�S�^�C���n�����͂����ɖłтĎ��̂��Ȃ������Ƃ��āA�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�܂��A�n�����͌Œ�I�Ȃ̂��ł͂Ȃ��A���ۂ̃E���X�͏�ɕϓ������B��т��ăE���X�Ƃ��Ē蒅�����̂́A�匳�E���X�Ɛ��̃W���`���E���X�i�L�v�`���N���n�����j�A�t���O���E���X�i�C�����n�����j�����ł���B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@���@�u�k�Ќ���V���@p.67�� |
| a�@�C�����n����
| �����S�����t���O�����A�W�A�����ɂ���ăC�����𒆐S�Ƃ������A�W�A�Ɍ��������A�����S���鍑�̃n�����̈�B �s���^�u���[�Y�i�C���������j�B�Ȃ��A�C���Ƃ́A�g���R��Ől�ԏW�c�������͍����Ӗ�����̂ŃC�����n���Ƃ́u���O�̉��v�Ȃ����́u�����v�̈Ӗ��ƂȂ�B����͂��̍��̑��̂ł���A�������̓t���O�̌��Ă��E���X�Ȃ̂��t���O���E���X�Ƃ����B�A
�C�����n�����̐����N�@���̐����N�́A��ʂɂP�Q�T�W�N�Ƃ���邪�A����̓����S���R���o�O�_�[�h���̂��ăA�b�o�[�X����łڂ����N�ł���B���̒i�K�ł͖{���̃����P���n���͌��݂ł���̂Ńt���O���Ɨ�������邱�Ƃ͂Ȃ������B���̃����P���n�����}�����A�P�Q�U�O�N�Ƀt�r���C�ƃA���N�u�P���Ƃ��Ƀn���ʂɂ����m�点���A�t���O���J���R�����A�҂�������߂Đ��A�W�A�ɃE���X�i���Ɓj�����݂��邱�Ƃ����ӂ������Ƃ������Ďn�܂�Ƃ���̂��������B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.184��
�C�����n�����̋��S�@�t���O�̎��͂��̎q�A�o�K����Q��n���ƂȂ�A�P�Q�V�O�N�Ƀ`���K�^�C���n�����̃o���N���z���[�T�[���n���ɐU�������̂����ނ��āA�E���X�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�ł�����̂ɂ����B���̌�A���݂̃C�����𒆐S�ɁA�C���N�A�V���A���x�z���A�G�W�v�g��{���Ƃ����}�����[�N���ƑΗ������B�܂��k�����L�v�`���N���n�����Ƃ̓A�[���o�C�W�����̖L���ȕ�����R�[�J�T�X�n���̗̗L���߂����đΗ������B���̂悤�ȍ��ۏ�̂��ƂŁA�A���O�����n�������b�o�����\�E�}�Ƃ����l�X�g���E�X�h�L���X�g���k���A�r�U���c�鍑�A�t�����X�A�C�M���X�A���[�}���c�̂��Ƃɔh�����Ă���B���̌���C�����n�����̃n���͂��т��у��[�}���c��t�����X���Ɏg�߂𑗂��Ă���B
�C�X���[�����@�C�����n�����̓����S���l�̎x�z����n��ɁA��Ƃ����C�����l�����Z���A�C�����l�ɂƂ��Ă͈ٖ����x�z���邱�ƂƂȂ������A����ɃC���������i�݁A��V����K�U�����n���̎��A�P�Q�X�T�N�A�C�X���[�����i�X���i�h�j�ɉ��@�����B�K�U�����n���̓C�����l�ɑ����V�[�h���E�b�f�B�[����o�p���A�C��������i�߁A�C�������C�X���[���������J�Ԃ����邱�ƂƂȂ����B�K�U�����n��������̃��[�c�ł��郂���S���鍑�̐����̗��j�ƁA�C�����n���������͂ސ��E�̗��j���L�q�������̂��A���V�[�h���A�b�f�B�[�����Ҏ[�����w�W�j�x�ł���B
�C�����n�����̖ŖS�@�P�R�R�T�N�A��X��̃A�u�[���T�C�[�h���{����ōc�@�ɎE�Q�����Ƃ����������N���A�t���O�̌������r�₦���B�\���̗L�͏W�c�͂��ꂼ��p�������咣���đ����A�P�R�T�R�N�ɂ̓g���R�������S���n��C�����n�̒n���������e�n�Ɋ����R������悤�ɂȂ��Ď����㍑�ƂƂ��Ă̓����͎���ꂽ�B�P�T���I�ɂ��e�B���[���鍑�ɋz������邪�A�C�X���[�������������S���l�̈ꕔ�̓C����������A�t�K�j�X�^���̑����n�тŗV�q�����𑱂��A���݂��A�t�K�j�X�^���ł̓n�U���l�ƌ���ꏭ���h���`�����Ă���B |
| �^�u���[�Y | �C���������̗v�n�ŁA�ȉԂȂǂ̖L���Ȑ��Y�͂����n��̒��S�s�s�B�t���O�̓����S���ɖ߂炸�A���̒n��s�Ƃ��ăC�������x�z���A�C�����n���������Ă��B�P�T�O�P�N�A�T�t�@���B�[���������A�ŏ��Ƀ^�u���[�Y����s�Ƃ����B�T�t�@���B�[���͌�ɓs���C�X�t�@�n�[���Ɉڂ����B |
| b�@�L�v�`���N���n����
| �����S���鍑�̃n�����̈�B�`���M�X���n���̒��q�W���`�i�W���`�j�ɗ^����ꂽ�A���^�C�R���n�т̗̓y�i�W���`���E���X�j���n�܂�B�W���`�̎q���o�g�D�̃��V�A�E���������ɂ�����L�G�t������łڂ�����A�샍�V�A���璆���A�W�A�ɋy�ԍL��ȗ̓y���x�z���A�P�Q�S�R�N�{���K�쉺�����T���C��s�Ƃ��Đ����B�L�v�`���N�Ƃ̓����S���̐N���ȑO����J�X�s�C�k�݂���샍�V�A�A�J�U�t�X�^���̑����n�тŗV�q�����𑗂��Ă����g���R�n�̖������ŁA�����S���l������ɓ����������߂ɁA��ʂɂ��̍����L�v�`���N���n�����Ƃ����B���������Ƃ��\�L�B
�W���`���E���X�̐����@�o�g�D�̗����郂���S���R�̓I�S�^�C���n���̎����̒m�点���A�P�Q�S�Q�N�ɓ����[���b�p��������g�����B�������o�g�D�̓����S���ɖ߂炸�A���H���K�쉺���̑����n�тɍ��𐘂��ē����Ȃ������B�ނ͕��W���`��������p�����W���`���E���X�����̒n�Ɉێ����A���W�����铹��I�B�����ɃW���`�̒��j�I���_���[�߂�I���_���E���X�A�����̍L��ȃL�v�`���N�����Ƀo�g�D���g�̎��߂�o�g�D�E�E���X�A���̒��Ԃɂ̓W���`�̂��̑��̎q�ɗ^����Ƃ����L��ȃW���`���E���X�����肠�����B���V�A�ƃJ�t�J�Y�̖k���т͑��̂Ƃ����B
�L�v�`���N���n�����͑��́B�W���`���E���X���������@�u���̃W���`���E���X�̓����S�����ƂƂ͂������̂́A���̎��Ԃ̓g���R�n�̃L�v�`���N�����唼���߂Ă����B�W���`���E���X�̃����S���l�͌��t���e�e���}���Ƀg���R�����A����Ƀo�g�D�̒�x���P�̎�����C�X���[�������n�܂����B�W���`���E���X���u�L�v�`���N���n�����Ƒ��̂���̂́A��������������w�i�Ƃ��Ă���B�������A���Ƃ��Ɛl��E�������������W�c�����u�����S���v�̖{���ł������B�v�W���`���E���X�̐����ɂ���āA�엀�ȑ����n�т̖q�����E�Ƒ������X�ђn�т̗�ה_���Ƃ�����̐��E���������ꂽ�B�u�E�E�E�E���̑��d�\���̘A���̂̒��_�ɂ����̂��A���H���K�͔Ȃ��k�Ɂu�I���h�v���G�߈ړ�������o�g�D�Ƃ̓���ł������B���̋���ȓV�������V�A��Łu�]���^���E�I���_�v���Ȃ킿�u�����̃I���h�i�V���j�v�ƌ������B�����F�ɓ�������Ă�������ł���B�p��ŃS�[���f���E�z���h�A���{��Łu�����v�Ƃ����B���������Ƃ����ʏ̂́A����Ɉ��ށB�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.88-89��
�L�v�`���N���n�����̃��V�A�x�z�@�L��ȓ샍�V�A�̑������̓y�ł���A�x�z�҃����S���l�͏����ŁA�����̏Z���̓��V�A�l�A�g���R�n�V�q���̃L�v�`���N�l�ł������B���V�A�l�͂��̃����S���l�ɂ��x�z���u�^�^�[���̂��т��v�Ƃ��ĒQ�����B�������A���̎��Ԃ́A�m�u�S���h���A���N�T���h�����l�t�X�L�[���L�v�`���N���n�����ɐb�]���čv�[�����Ƃ��납��n�܂�A�L�v�`���N���n�����͔[�ł݂̂��`���Ƃ��ă��V�A����̎�����F�߂�Ԑړ����ł������B���ł������̓����S���l�̒��Ŋ��������������A��������X�N����������s����悤�ɂȂ�A�����S���l�ւ̔[�ŕ��S�ɔ��������_���̓��X�N�������ɂ���Ēe�����ꂽ�B
�}�����[�N���Ƃ̓����@�L�v�`���N���n�����́A������C�����n�����Ƃ́A�A�[���o�C�W�����ƃR�[�J�T�X�n���̗̗L���߂����đΗ������B���̂��߁A�C�����n�����Ɛ푈��Ԃ̑����Ă����G�W�v�g�E�V���A���x�z�����}�����[�N���Ƃ͗F�D�W�����сA����u�C�X���[�����L�v�`���N�A���v�����������B�w�i�ɂ́A�}�����[�N�����}�����[�N�̑����́A�W�F�m���@�̏��l�Ȃǂ̎�ŃG�W�v�g�ɔ����Ă����L�v�`���N�����̃g���R�l�V�q�������������̂ŁA�e�ߊ����������̂ł���B�܂��A�����̃r�U���c�鍑�i�P�Q�U�P�N�Ƀ��e���鍑����R���X�^���e�B�m�[�v����D�҂����j�Ƃ��C�����n�����Ƃ̑R��A�F�D�W��ۂ����B
�C�X���[�����Ɛ��S�@�P�S���I�O���̃E�Y�x�N���n���̎��ɑS�����ƂȂ�ƂƂ��Ɍ����ɃC�X���[�������A�s���{���K�㗬�̐V�T���C�Ɉڂ����B�������A�P�R�T�X�N�Ƀo�g�D�̌������r�₦�A�P�S���I�㔼���e�B���[���鍑�̐i�o�ɑ��g�N�^�~�V������R�������A���̌㍑�ƓI�����͎����A�P�T���I�ɂ̓��H���K������J�U�����n�����A�A�X�g���n�����n�����A���C�k�݂��N�������n�����A���V�x���A���V�r�����n�����Ȃǂ̏��n���������������B�����̏����͌N��ɂ̓����S���n��Ղ��Ă������A�����I�ɂ��^�^�[���l�Ȃǃg���R�n�����ł���A���̑����E�Y�x�N�l���J�U�t�l�����������B���V�A�͂P�Q�R�V�N�ȗ��A�L�v�`���N���n�����̎x�z���Ă������A�P�S�W�O�N�����X�N����������C���@���R�����Ɨ���B�����A������u�^�^�[���̂��т��v���I��点���B |
| �T���C | �P�Q�S�P�N�̃��[���V���^�b�g�̏����̗��N�A�I�S�^�C���n���̎����ɂ�蔽�]�����o�g�D�́A�����S�������ɖ߂炸�A�샍�V�A�̃��H���K�쉺���̃T���C��V���ȓs�Ƃ����L�v�`���N���n�����i�W���`���E���X�j�����������B�������A�T���C�͈��̓s��ł͂Ȃ��A���̎��Ԃ͈ړ����̓V���i�I���_�j�ŁA�G�߂��ƂɈ��͈͂��ړ������B�V���͍��ŁA���������ł������̂ŃL�v�`���N���n�����̂��Ƃ������ł����������A���V�A��ł́u�]���^�����I���_�i���̃e���g�j�Ə̂����B���̌�A�o�g�D�̒�̃x���P���n���̎��ɁA���H���K�㗬�̐V�T���C�Ɉڂ����̂ŁA����ȑO�����T���C�Ƃ������B�������u���̓o�g�D�̃T���C�ƃx���P�̃T���C�͓����ꏊ�ŁA�V�T���C�́i�E�Y�x�N���n���̎��j�P�R�R�O�N�܂Ō��݂���Ȃ������悤�ł���B�V�T���C�̈�Ղ̔��@�́A��������ǂ̂Ȃ��L��ȃ��g���|���X�ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�P�S���I���̃e�B���[���ɂ�闪�D�̂̂����̂Ă�ꂽ��Ղɂ́A���������̔ɉh�̏؋���������Ă����̂ł���B�v���c�D�S�[�h���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@���R�����E�哇�~�q��@p.151�� |
| c�@�`���K�^�C���n����
| �����S���鍑�̃n�����̈�B�`���M�X���n���̎��q�`���K�^�C���z���Y�����������Ō��т������C���여���A���}���N�𒆐S�Ƃ��������A�W�A�i���g���L�X�^���j�ɗ̒n��^����ꂽ�̂Ɏn�܂�B�`���K�^�C���E���X�Ƃ������B��S��n���̃����P���n���̎��A���̑��ʂɔ��������Ƃ���ꑰ�̑����͏��Y����āA���͎͂�܂�A�`���K�^�C�Ƃ����̌㕪�A�E���X�Ƃ��Ă̓��ꐫ�͖����Ȃ�B�t�r���C���n���̎��A�T�n�̃o���N���ꎞ������Ԃ������A�P�Q�V�O�N�ɃC�����n�����̃z���[�T�[���n����D�����Ƃ��Ĕs��A���̌�I�S�^�C�Əo�g�̃n�C�h�D�ɂ���ĈÎE����A�{���̒����A�W�A���}�[�������[���A���i�t���̓n�C�h�D�ɂ���Ďx�z����邱�ƂƂȂ����B�n�C�h�D�̗��̏I����A�P�R�O�U�N�Ƀ`���K�^�C�Ƃ̃h�D�A����s�̑�n���i���@�j����P�Ɛ����ƔF�߂��A������`���K�^�C���n�����i�`���K�^�C���E���X�j�̐����Ƃ��錩��������B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x���@�u�k�Ќ���V���@p.169��
�`���K�^�C���n�����̕����@�P�S���I���ɃC�X���[��������ƂƂ��ɓ��ɂ͓V�R���ʁA���ɂ̓}�[�������[���A���i�t���ɓƎ��������������A�����ɕ����B�P�R�S�U�`�U�R�N�ɂ̓g�D�O���N���e�����ɂ���Ĉꎞ�I�ɓ������ꂽ���A���̎���Ăѕ���B���`���K�^�C�͂ɂ́A�����S���n�̃o�����X�������e�B���[�����䓪����B���`���K�^�C�̓��O�[���X�^�������i�����S���̒n���Ӗ�����y���V�A��j�Ƃ�����悤�ɂȂ�A�������P�T���I�ȍ~�̓J�U�t�l��E�Y�x�N�l���䓪���Đ��ނ����B�@ |
| �A���}���N | �����A�W�A�̃`���K�^�C���n�����̓s�ł��������A���݂͐��S�����B���݂̒����̐V�d�E�C�O����������ɂ������B |
| d�@�I�S�^�C���n����
| ��Q��̃n���A�I�S�^�C���n���̏��̂����������A�W�A�ɑ��݂����Ƃ���Ă������A�ŋ߂̌����ł̓I�S�^�C�̎q�ő�R��n���̃O���N������Ɍ��͂���������S��n���������P���n���ɂ���ăI�S�^�C�Ƃ̐��͈͂�|���ꂽ�̂ŁA�I�S�^�C���n���������݂��Ȃ������Ƃ���Ă���B�@���@�����S���鍑
�u�i�����P���n���́j��ʂɑ����ƁA���Δh�����������l�������B�I�S�f�C�A�`���K�^�C���Ƃ̂����A�����̑��ʂɔ����A�N�����^�C�Ɂu�s�Q�v���������A���ʂ̏j�����}�P���悤�Ƃ����ƌ�����ʁX�́A���Y�Ȃ������߂Ƃ����B���̂������E���X�ɂ��Ă͏��̂��ו����A���Ƀp�~�[���Ȑ��ɂ��Ă͖��F�o�g�D�Ƌ�����������`���Ƃ����B�L�͏��������ł��V�V���Ƃ�����ʏl���́A���ĂȂ����܂����ł������B�E�E�E�I�S�f�C���́A�Ïl�𒆐S�Ƃ��铌���̃R�f���E�E���X�ƃG�~���|�R�{�N�𒆐S�Ƃ��鐼���̂��̑��̏��q�̂ƂɁA�͂�����ƕ����B�j��A�u�I�S�f�C�E�E���X�v�������͒ʏ́u�I�S�^�C���n�����v�Ȃǂƌ����ׂ����Ԃ́A���̌�͑��݂��Ȃ��B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.99-100��
���ȏ�����I�S�^�C���n�����������F�R��o�ŎЁw�ڐ����E�j�x�O�U�N�x�����ł��炱�̐���������A�����S���鍑�̌n�}����u�I�S�^�C���n�����v�͍폜����A�u�S�n�����v�Ƃ����p����g��Ȃ��Ȃ��Ă���B�������A���̋��ȏ��ł͈ˑR�Ƃ��ăI�S�^�C���n�����������S�n�����Ƃ��Ă�����̂������B |
| �G�~�[�� | �G�~���Ƃ��\�L�B�I�S�^�C���n�����̓s�ł������Ƃ���ŁA�n�C�h�D�̗��̋��_�ƂȂ����B���݁A�����̐V�d�E�C�O����������ɂ������B |
| e�@�t�r���C
| �`���M�X���n���̎q�g�D���C�̑�Q�q�B�N�r���C�Ƃ��\�L����B�����ł͍��K��B�Z�����P���n���̂��ƂŁA�`�x�b�g��_��i�嗝�j�ɉ����A��v�̔w���}���āA��v�����ɔ����Ă������A�P�Q�U�O�N�Ƀ����P���n���̋}����m��A�Ǝ��ɃN�����^�C�����s���A��T��n���ɑ��ʂ����B�����F�߂��A��������T��n���𖼏����������A���N�u�P���J���R��������ǂ��o���A�P�Q�U�S�N�Ɍ��͂��������B �P�Q�U�V�N�s����s�i���݂̖k���j�ɑJ�����B����ɂP�Q�V�P�N�ɂ͍����𒆍��������ɉ��߁A�{�i�I�Ȓ����x�z���Ӑ}�����B���㌳�c��Ƃ��Ă͕_�������c�Ƃ����B�����S���̒����x�z�������������c��Ƃ��ďd�v�ŁA����Ȍ�A�P�Q�X�S�N�܂��t�r���C���n���̓������s����B
�A���N�u�P�Ƃ̍R���@�P�Q�U�O�N�A�����P���n�������ʂƁA���̎q�ǂ������͂Q�O��Ńn���Ƃ��Ă͑��������̂ŁA�����P�̌Z�킽������I��邱�ƂƂȂ����B�L�͂Ȍ��̃t���O�͉����C�����ɂ����̂ŊԂɍ��킸�A�t�r���C�͓�v�������ł������������k���̊J���{�ɋ}����߂�A�Ǝ��ɃN�����^�C�����W���A��T��n���ɑI�o���ꂽ�B����ɑ��J���R�����ɂ�������̃A���N�u�P���A�N�����^�C�ő�T��n���ɐ������ꂽ�B�����ɓ����ɓ�l�̃n�������݂��镪���ԂƂȂ����B���҂̊ԂɁA�t�r���C�͒����{�y�ւ̐i�o���咣���A�A���N�u�P���J���R�����ɂƂǂ܂�]���ʂ�̗V�q�鍑�Ƃ��Ẵ����S���鍑�̈ێ����咣�����A�Ƃ����Η��ł������Ƃ����������邪�A�^�킵���B�܂��A���N�u�J�́w�W�j�x�Ȃǂł͑o���Ƃ���T��n���ƔF�߂��Ă���̂ŁA���̓�����u�A���N�u�P�̔����v�Ƃ����̂͌���Ă���B���A�W�A��]�풆�̃t���O�̓G�W�v�g�U��������߂ă����S���ɖ߂낤�Ƃ������A�r���̃^�u���[�Y�ŗ��܂�A���A�W�A�Ɂu�E���X�v�i�����S�����Ɓj�����݂��邱�Ƃɓ��ݐ����B�k���̃W���`���E���X�i�L�v�`���N���n�����j�̃x���P�i�o�g�D�̒�j���쉺���A�A�[���o�C�W�����Ȃǂ�D�����Ƃ��Ă��邱�Ƃɔ������̂ł���B���҂̓J���R�������߂����ĂS�N�ɂ킽���Č������킢�A�P�Q�U�S�N�ɃA���N�u�P�͓��~���ăt�r���C���������������B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.140-164��
���l�����̕Ґ��@�܂��t�r���C�͓�v�Ƃ̐퓬�Œ����{�y��]�킷�邤���ɁA�����S���l�̖{���ƕ���ŁA���l�E�_�O�i�L�^���j�l�E���^�Ȃǂ��琬�銿�l������Ґ����A�܂��v�����̌�ނɂ���Ċe�n�Ɏ����������l�R���𖡕��ɑg�ݓ���Ă������B�P�Q�U�Q�N�ɂ͎R���n���̌R�����������N���������A�������l��R�����j�V���i���Ă��j�Ȃǂ�������݁A���������B�j�V��̓t�r���C�ɏ]�������l�R���̑�\�I�l���ŁA�����S����ɂ����\�Ō��̒����x�z�ɑ傫�ȗ͂ƂȂ����B�������@��@p.145�A���@p.71-72�Ap.77�� |
| �@�A���N�u�P | �A���N���u�P�A�A���N�u�J�Ƃ��\�L����B�`���M�X���n���̑��̐���B�g�D���C�̑�S�q�ŁA�����P�A�t�r���C�A�t���O�̖���B�P�Q�U�O�N�A�Z�������P���n������v�������ɋ}�������Ƃ��A�Z�풆�ŗB���J���R�����Ɏc���Ă����̂ŁA�}����N�����^�C���J�Â��A��T��n���ɐ������ꂽ�B�������A������O�ɓ�v���������t�r���C���J���{�ŃN�����^�C���J���đ�T��n�����ʂ�錾���Ă����̂ŁA�Z��Ԃ̑����ƂȂ����B���҂͌��������������A�`���K�^�C�ƂȂǂ��t�r���C���ɕt���A�܂��L�͎҃t���O�����A�W�A�������ŁA�������L�v�`���N���n�����Ƃ̑Η����T���Ă����̂œ������A���͂ɏ���t�r���C�R�ɂ���ăJ���R������D���A�P�Q�U�S�N�ɓ��~�����B�w���j�x��w�W�j�x�Ȃǂ̃����S�����j�ł͐����ȃn���Ƃ��ĔF�߂��Ă���B |
| f�@�n�C�h�D�̗�
| �P�R�O�O�`�P�R�O�T�N�A���̑�n���ɑ��Ē����A�W�A�����_�Ƃ���ꑰ�̃n�C�h�D���N�����������B���[���V�A�ɂ����郂���S�����͂����傫�ȓ����ƂȂ������A�����������Ă��̎x�z�����肳�����B�n�C�h�D�͑�Q��n�����I�S�^�C���n���̑��B�J�C�h�D�A���邢�̓n�C�Y�Ƃ��\�L�B��S�������P���n���ȗ��A�I�S�^�C�Ƃ͕s���������̂ŁA�s�����������A�P�Q�U�X�N��������t�r���C���n���ɔ�����|���A�P�Q�W�O�N���ɂ͒����A�W�A���}�[�������[���A���i�t���ɓƗ��������������B�P�Q�X�S�N�t�r���C���n���̎�����A�P�R�O�O�N���痂�N�ɂ����āA��R�𗦂������S�������ɐN�U���A���̑�U��n���̃e�����i���@�j�Ɛ�����������s��Ă܂��Ȃ����������B���ꂪ�n�C�h�D�̗��ŁA�P�R�O�T�N�Ƀn�C�h�D�̎q�̃`���p���ƃh�������ɍ~�����ďI�������B�����A�W�A�̓`���K�^�C�Ƃ̎x�z���������ă`���K�^�C���n�����Ƃ��Ĉ��肵�A���̃L�v�`���N���n�����ƃC�����n�����ƂȂ�сA�����S�������ƒ����{�y���x�z���錳�鍑���@�卑�Ƃ����u�^�^�[���̕��a�v�����������B�@ |
 |
| �C.���̓��A�W�A�x�z
|
| �`�@�t�r���C�̓���
| �t�r���C�̓����P���n���̒�Ƃ��ă`�x�b�g�A�_��n�����嗝�����ɏ]�����A�����P���n���̎���A�P�Q�U�O�N�������S���鍑�̑�T��̃n���ƂȂ����B�݈ʂP�Q�U�O�`�P�Q�X�S�N�i���̍c��Ƃ��Ă͂P�Q�V�P����j�B���͏����܂ł��t�r���C�̍����Q�ƁB
���̌����@�t�r���C�͂P�Q�U�O�N�A�����k���̊J���{�ŃN�����^�C���J�Â��ăn���ɑ��ʂ��A�N���𒆍����ɒ������N�Ƃ����B�n�����̂�����A���N�u�P�̐��͂�|�����P�Q�U�S�N�ɁA�]���̎�s�J���R������������A����̖{���n�ł���J���{���u��s�v�Ɖ��߁A���Ă̋��̓s�ł������u���s�v�i���݂̖k���j�Ƃ��āA�Ƃ��Ɏ�s�Ƃ����B�܂��N�����������N�ɉ��߂��B�P�Q�U�V�N�Ɏ�s����s�i���݂̖k���j�ɑJ���A�����S�������ƒ����k���ɂ܂�����̈���x�z�����B�V�P�N�ɍ��������ɉ��߁A�����I�Ȋ������̗p���A�V�X�N�ɓ�v��łڂ��A�S������x�z����Ɏ������B�t�r���C���n���͍����̒��S�@�ւƂ�����������݂��A�R�������鐕���@�A�Ď@�̍ō��@�ւł����j��̎O�@�ւ��c��ɒ����������B�܂��n���s�����Ƃ��Ă͏B������p�����B�܂����ʂƂƂ��ɁA���ꎆ���Ƃ��������s���A�o�ς̔��W���͂������B
�t�r���C�̊O���ƌ��Ռ��̊g���@�t�r���C���n���̉ۑ�̓����S�������̔����i�n�C�h�D�̗��j�̒����ƁA��v�̐����ł������B�܂��A�P�Q�U�V�N�����v�̐����ɏ��o���A�P�Q�V�U�N�ɗՈ����́A��������v��łڂ����B����Ɉ���A�`�����p�A�r���}�ȂǓ���ɕ��ʂɐi�o���đ����������A���N�̍���������Ƃ����B�������A���{�����i�����j�ɂ͎��s�����B�@����Ƀt�r���C���n���͓���A�W�A���ʂ������R��h���������A���̊͑��h���͌��Ռ��̊g����߂������ʂ������A��V�i�C���瓌��A�W�A�A����ɓ�A�W�A�i�C���h�m�j�����ԊC�ニ�[�g�������S���鍑�ɂ���Č��т����邱�ƂƂȂ�A�C��f�Ղ�������������ƂƂ��ɁA�C�X���[�����̓���A�W�A�ւ̓`�d�Ȃǂ̉e���������炵���B
�t�r���C����̍��ې��@���̋{��ɂ́A���������ɃA���u�l�̃A�t�}�h������A�}���R���|�[�����o�p����A���ېF�̖L���Ȃ��̂ł������B�܂��`�x�b�g�����p�X�p�������A�`�x�b�g������ی삷��ƂƂ��Ɍ��p�����Ƃ����p�X�p���������点���B����Ȍ㌳���`�x�b�g�������@���c�ɑ���̔�p���o��邱�ƂƂȂ�B
�t�r���C���n���̔ӔN�̊�@�@�P�Q�W�V�N�A�������k����̒n�Ƃ��Ă��������S���̃`���M�X���n���ꑰ�̌���i�����ȂǁA�����O���Ƃ��t�r���C�ɑ��������N�������B�����A�W�A�̃I�S�^�C�Ƃ̃n�C�h�D���������铮�����������B���̂Ƃ����łɂV�R�ɂȂ��Ă����t�r���C�́A�q�ǂ������ɂ��旧����Ă���ő�̊�@�ł������B�������ނ͉ʊ��ɍs�������B�����ۂɏ���Ĕ����R���}�P���A�����Ƃ����Ԃɍ~���������B���̂Ƃ������t�r���C�̐e�q���́A�����A�W�A�������Ă����g���R�n�̃L�v�`���N�l�Ȃǂ̗ꖯ��m�A�܂��}�����[�N�ł������B�u���֗����}�����[�N�v�ƌ����邩������Ȃ��B�����R�̎c�}�͒��N�����ɓ��ꂽ���A�Ԃ��Ȃ����ƍ���̋������ʼn�ł�����ꂽ�B�������čő�̊�@���������t�r���C�͂P�Q�X�S�N�A�W�O�Œ��������B�����Ƃ��Ă͈ٗ�̒����������B�_���͒����������c�Ƃ��ꂽ�B��U���n���ɂ͑��̃e�����i���@�j����s�ł̃N�����^�C�őI�o���ꂽ�B |
| a�@��s
| ���̓s�Ō��݂��k���ɂ�����B�P�Q�U�V�N�t�r���C���n���͕��s�̈�ł������~�̎�s���s�̓��k�ɁA���������s������݂��A��s�勻�{�Ə̂����B���s�͂��������ƌ����A�퍑���ォ��̗v�n�ł���A���̓s�Ƃ��Ȃ����Ƃ���ł��邪�A�t�r���C�̌��݂����V�s�͂��̈ꕔ�͏d�Ȃ��Ă��邪���S�͖k���Ɉڂ��Ă���A�܂������V�����s�ƌ����Ă����B��s�̏�s�͓����A�u���͘Z�\���\���v�Ƃ���ꂽ���A�����ł͖�Q�W�D�U�����ł������Ƃ����B���̓암�����ɋ{�邪�����A�s�X�͓�k�̊X�H�ŋ�悳��A����͖V�ƌ���ꂽ�B�P�Q�U�U�N�ɑ�s���݂�錾���A���U�V�N�ɂ͑J�s�������A���������̂͂P�Q�X�R�N�ŁA�t�r���C�͂��̗��N�Ɏ�������B
��s�̓����@����Ɍ�����Ñ㒆���̗��z�̒��؎���s�Ƃ��Č��݂��ꂽ�B���̐v�͎��̎O���ɒʂ������l�����������B�s��Ȓ�s�ł��������A���̓n�������͂قƂ�Ǒ�s�̏���ɂ͓��炸�A�x�O�̖�c�n�ɑs��ȓV���̋{�a�ł������̂��D�B��s�́u�Z�ށv���߂̓s�ł͂Ȃ��A�����ɕK�v�Ȑl�ƕ������߂Ă����u��v�ł������B�ő�̓s�s�@�\�́A��s�������ɂ���Ȃ���A�Ȃ�Nj���ȓs�s���`�������Ă������Ƃł���B���������̍`�́A�ʌb����ʂ��ĒʏB�Ɏ���A�������甒�͂ɂ���ĊC�`�̒����i���݂̓V�Áj�ŊO�m�ɒʂ��Ă����B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.30-34��
���ۓs�s�Ƃ��Ă̑�s�@��s�ɂ͑����̕������@�A�`�x�b�g�����̎��@�A�����̓��ρA�L���X�g���̋���A�C�X���[�����̃��X�N����������ł����B���݂�������̌�����������B�܂���s�ɂ́A���E�e�n����g�߂⏤�l������Ă��āA���ۓs�s�Ƃ��Ĕɉh�����B���[���b�p�������Ă����}���R���|�[���́w���������^�x�ł́A��s���J�����o���N�i�n���̓s�̈Ӗ��j�ƌ����ďЉ��Ă���B�܂������e���R�����B�m�A�C�X���[�����k�Ń����b�R�l���C�������o�g�D�[�^�Ȃǂ���������K�₵�Ă���B����B�@���@�k�� |
| ��s | �����S���鍑���t�r���C���P�Q�U�O�N�ɑ�T��n���ɑ��ʂ������̋��_�͌��݂̓������S���̃h�������m�[���ɂ������J���{�ł������B�J���R�����ɂ͒�̃A���N�u�P����������T��n���Ƃ��đ��ʂ����B�P�Q�U�S�N�ɃA���N�u�P��|���ē���w���҂ƂȂ����t�r���C���n���́A�P�Q�U�S�N�ɐ����ɃJ���R��������J�s���A�J���{����s�Ƃ��A���̓s�ł��������s�i���Ă������A���݂��k���ɓ�����j�ƂƂ��Ɏ�s�Ƃ����B�܂�A��̓s��u���������Ƃ����̂ł���A�Ċ��͏�s�A�~���͂͒��s�Ŏ��������B�������͒����j�ł͂߂��炵���Ȃ��A���̒����Ɨ��z�A���̖k���Ɠ싞�Ȃǂ���������B�����S���鍑�̏ꍇ�́A�V�q�n���}�����s�ƁA�_�k�n���}���钆�s�Ƃ����Ӗ����������B���̑̐��͂P�Q�U�V�N�ɒ��s�����߂���s�����݂���Ă�����������B���̖ŖS�̎��A�j�ꂽ�B |
| b�@��
| �����S���鍑�̑�T����t�r���C���n�����P�Q�V�P�N�ɂ��̍������n�߂��A�����S�������ƒ����{�y�𒆐S�Ƃ������ƁB�����S���l���匳�E���X�Ə̂����B���̍c��������S���鍑�̏@�Ƃ̑��n���̈ʂ����˂��B�P�Q�V�X�N����v�̎c�����͂���|���Ă���́A�����S�y��x�z���A���ɂ�銿�����x�z�͂��ꂩ���X�O�N�ԑ������B���������猩��Έٖ����ł��郂���S���l���A�������ŗL�̓����`�����̗p���Ē������x�z����A�Ƃ����u���������v�ł������B��s�i���݂̖k���j��s�Ƃ��Ē����{�y�ƁA�����S�������A����A���B���܂݁A���ӂ̃`�x�b�g�A���N�A����Ȃǂ��Ƃ��Ďx�z�����B�@�@���@���̉����R�h��
���̓����@�\�@���̓����@�\�́A�������������E�����@�E��j��A�n���@�ւƂ��Ă̏B�����ȂNJ������̋@�\���̗p�������A���ۂ̎x�z�̓����S���l���ŏ�ʂɁA�����ŐF�ڐl�A���̉��Ɋ��l�i���̈▯�j�A�ʼn����ɓ�l�i��v�̈▯�j��u���Ƃ��������S���l�����`���Ƃ�ꂽ�B
�����ƐŐ��@�������{�̍����́A�]���̒��������̂悤�Ȕ_������̑d�łł͂Ȃ��A���̐ꔄ���Ə�����ɉېł���������ł������B���́u�����i����j�v�Ƃ�������������������A���ꂪ���{�̎����ƂȂ����B���ł́A���[���V�A����Ռ��̂̐����̂Ȃ��Ŏ��R�o�ς��f�����A�t�r���C���n���̎��ɂ���܂œs�s�E�`�p�E�֖��ʂ邲�Ƃɒ��W����Ă����ʉߐł�P�p���A���i�͍ŏI���p�n�ň�����ł��A����Ώ���Łi�ŗ��͂R�D�R���j�ƂȂ����B�������Ď�������債�A�₾���ł͕s�������i�P�U���I�̋�̑�ʗ����̑O�ł������j���ߎ����i�����j�����s���ꂽ�B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.191-194��
���̒n���s���@���͉ؖk�̋���łڂ�����A�ˌ��������s������ŁA�����S�������⏔���ɏ��̂z�A����Ɍ��ɍ~�������l�������͂ƕ����������B�P�Q�U�Q�N�A�t�r���C�͉ؖk�̊��l�R���̔�������肵����A�H�E�{�E�B�E���̂S���x���̍s���������A�e���x�����_���K�`��u���ĊĎ����钆���W���̐������肠�����B
������̒����Љ�ƕ����@���̎Љ�́A�w�`���i�W�����`�j���^�͂̐����ȂǂŌ�ʖԂ����B���A�O��̓�v�̏��H�Ƃ��p�����Čo�ς�����ł���A�����Ƃ������������ʂ����B�_���ł͋����̂Ȃ��Ɋ��l�̑�y�n���L�҂��������Ă����B�����ʂł̓����S�������̓Ǝ����͔���A�{��ł̓`�x�b�g�������ی삳��A�������ɂ̓p�X�p�������g��ꂽ�B�ȋ������f���ꂽ���ߎ⊿���w�͐��������A���O�ɂ͌��Ȃ�ʑ��I�ȕ��w�����s�����B���̎���̕����̑傫�ȓ����́A�����S���鍑�̐����Ƃ��������I������Đ���ɂȂ��������𗬂̌��ʁA�L���X�g����C�X���[���̕����������������Ƃł���B�@�@���@����̕���
���̋��S�@���鍑�̍c�遁��n���ʂ͕K����������ł͂Ȃ��A�n�C�h�D�̗�����p�����߂����ē������������B�P�R�O�T�N�ɗ��͕��肳��A�t�r���C���n���i���c�j�Ǝ��̑�n�������@�̎��������Ƃ����肵���B�܂��{��ł͎���ɋM���w���`������A���̚��ʂȐ����͍����̍���������A���̂��߂̏d�ł͎���Ɋ������̃����S���l�x�z�ɑ��锽�������߁A�Љ�s�������܂�Ȃ����@���k�Ȃǂ̐V���@�����c�����܂�A�g�Ђ̗��Ƃ��ĎЉ�s�����������ĂP�R�U�W�N�ɖŖS�A�����S���l�͒����{�y��������ă����S�������Ɉ����グ�A�k�������邱�ƂƂȂ�B�@���@���̖ŖS |
| c�@��v
�̖ŖS | �A���N�u�P�Ƃ̍R���Ɖؖk���l�R���̔����Ƃ��������S���鍑�̓��������߂��t�r���C���n���́A�P�Q�U�V�N�����K�͂���v�����ɒ��肵���B�t�r���C���n���͓�v���ł�����ȓG�ƍl���Ă����̂ŁA�U���ɓ������Ă͏]���̃����S���R�����S�̐�p�ł͂Ȃ��A�R���͏����ɗ��߁A���l�̕������������Ď�͂Ƃ����B����́u�ÁE���R�v�ƌ���ꂽ�B�܂��A�K�v�ȍ��������X�����n��l�X�g���E�X�h�M�҂̌o�ϊ����ɔP�o�������B�܂��A��p�Ƃ��Ă͒�������o�債�āA�����i���]�x���j�����z�U���Ɍ�����悤�ɁA���͂Ɋ�Ƃ����y�ۂ�z���ĕ�͂��ĐH�Ƃ̐s����̂�҂��A�ς����ꂸ�Ɏ�������o�����Ă���ƉΖC��Ί�ʼn��킵���B����Ńt�r���C���n���͋��Ƃ̐푈�̒�����C�R�̕K�v����F�����A�P���T��ǁA�V���l�̐��R��g�D�����B�U�N�ɋy�ԕ�͐�����z���ח������A���̌�͌��R�͗���ƒ��]�̐���𓌐i���A����̓s�s�����X�ƊJ��A�P�Q�V�U�N�ɓ�v�̓s�Ո��{�Ո��͖���R�ō~�����A���@�͍~������v�͖ŖS�����B��v�̖ŖS���P�Q�V�X�N�Ƃ���̂́A�����c�����c�}���L�B�p���̊R�R�őS�ł����N�ł���A�����I�ɂ͗Ո��J��œ�v�͖ł�ł���B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.88-102��
Epi.�@�����痈���V����ƘC�����̍~���@�t�r���C�͓�v�U���ŐV����������B����́A�C�����n�����ʼn��ǁE�J�����ꂽ���哊�@�ŁA�y���V�A��Łu�}���W���j�[�N�v�A����ł́u���C�v�Ƃ��ꂽ�B�t���O�̎q�̃A�o�K����t�r���C�ɁA�C�����l�Z�t�ƂƂ��ɉ���������Ă����B�P�Q�V�R�N�̊������ŏ��߂Ďg�p�B�J�^�p���g����͔��˂��ꂽ���e�͐���z���ĂV�O�O�`�W�O�O����сA��O�╺�ɂ����j���A���z�̎�����Ǝs�����Ȃ��|�����B���z�̎珫�C�����͑S�R�E�S�s���̏����������ɂ��ɊJ�邵���B���R�͖ǂ���A�N��l�E�����A���܂��ɘC�ȉ��Ƀt�r���C�����̐e�q�R�̖�����^�����B���������C�́A�����������В���A���s���Ă����v��������A�t�r���C�̐b���ƂȂ邱�Ƃ𐾂��A���̌�̓�v�U���ɑ傢�Ɋ����Ƃ����B�����悤�ɁA���R�ɐi��ō~�������v�̏��������������Ƃ����B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.92-98�� |
| �@�匳�E���X | �t�r���C�͂P�Q�V�P�N�i�����W�N�j�A�V�����������u�匳�v�Ɩ��Â����B�����ɂ́u�匳�C�G�P�E�����S���E�E���X�v���匳�僂���S�����A�����đ匳�E���X�Ƃ����B���Z���ȏ����ł͈�ʂɁA�u���v�Ƃ̂ݕ\�L����B���Ƃ��������́A�Ռo�́u�傢�Ȃ邩�ȁA�����v����̂����Ƃ����B�����Ƃ͓V�A�������͉F�����Ӗ����A�g���R�E�����S�����Ō����A�ނ炪���ׂĂ̌��Ƃ��ċ��ʂɐ��߂�u�e���O���v�ɂ�����A�u�匳�v���Ȃ킿�u�傢�Ȃ�݂Ȃ��Ɓv�Ƃ̓e���O���̑��̂ƂȂ�A�t�r���C�͎���̐V���Ƃ��u�傢�Ȃ�e���O���̍��v�Ɩ��������B�i���̑��@���˙��������Ƃ��V�����e���O���J�K���̏̍���ꂽ�B�j
�܂��A�t�r���C�͂��łɂP�Q�U�O�N�ɁA�����S���Ƃ��ď��߂Ă̔N�����߁A�u�����v�ƌ����A�A���N�u�P�Ƃ́u��ʌp���푈�v�ɏ������P�Q�U�S�N�ɂ́u�����v�ɉ�����������ɂP�Q�U�V�N�ɂ͐V��s�u��s�v�̌��݂ɒ���A����ō����E�N���E�s�������E���ƂƂȂ����B
���̑哝���̃v�����@�����S���鍑���������������匳�E���X�͂ǂ̂悤�ȃv�����ōs��ꂽ�̂ł��낤���B����́u�R���ƒʏ����^�C�A�b�v���������v�ł���A���̂R�̗v�f���g�ݍ��킳��Ă����B
�i�P�j�����S���x�z�̍����ł���u�����̌R�����v�B�����S���R�n�R�c�𒆐S�Ƃ��Ă��܂��܂Ȑl�킩�琬��R���̃V�X�e�����B
�i�Q�j���ƍs���@�\�ƍ�����Ղ̊m���B���̂��߂ɒ����̓`���ƕx�Ɛ��Y�́i���̌o�ϗ��j����ɓ���邱�ƁB
�i�R�j���[���V�A�S�y�ɂ킽�镨���V�X�e���B��J�A���̌��͂̂��ƂŁA�C�����n���X�������l�̌o�ϗ�����荞�ށB
�����āA������_�A���ӂ��Ă����������Ƃ�����B����̓N�r���C�������u�C��ւ̎���v�������Ă����炵�����Ƃł���B�N�r���C�́u���̒鍑�v�́A�u�C�̒鍑�v�Ƃ��Ă̑��ʂ����˔����A�u���ƊC�̋���鍑�v�����肠�����B���ƊC�̋N�_�Ƃ��ĐV���Ɍ��݂��ꂽ�̂���s�ł���B��s�͉^�͂ŊO�m�ƌ���Ă����B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.19-22,39-43�� |
| d�@�����i�����S���̎x�z�j | �����ɑ��ă����S���鍑�́A�P�Q�R�P�N����P�Q�T�S�N�܂ŁA�U��ɂ킽�艓���R�𑗂��Đ������悤�Ƃ����B����ł͕��l�̛����������s���J�邩��]�ؓ��Ɉڂ���R�𑱂����B�������A����ś����������|��A�a���h���䓪�A�P�Q�U�O�N�n���ʂɂ����t�r���C���n�������͂ł̐�������̂āA���퍑���Ƃ��ĕ������B����͓Ɨ��̖̑ʂ͈ێ����������̑����ƂȂ�A���N�̒��v�𑱂��邱�ƂƂȂ����B���̓��{�����i�����j�ɂ́A���̉����R�̕������o�������߁A�傫�ȕ��S�ƂȂ����B�܂��A�u�a�ɔ������R�����͂��P�Q�V�O�`�V�R�N�ɒ�����ϏB���Œ�R�𑱂����O�ʏ��̗����N�������B�܂��A���̎x�z���̍���ɂ����āA����ő呠�o�̊��s��A���������̔����A������̔��B�Ȃǂ̕����̐��������������Ƃ����ڂł���B
Epi.�@�[���A����@�����S���̍��퉓����������ɂ߂��B���ɂP�Q�T�S�N�̑�U��̉����ł́A�u�Õ��ɗ�����ꂵ�j��������Z���Z�甪�S�]�l�A�E�C���ꂵ�҂͌v����ɂ����ׂ��炸�B�o�鏊�̏B�S�݂ȊD���ƂȂ�B�v�܂��A�u���r�ȗ��A�[������������v�i�w����j�x�j�Ƃ���ꂽ�B�Ȃ��A���̂Ƃ�����̒��삪�]�ؓ��ɓ���A�����S���̍U���ɑς������Ƃ́A�]�ؓ������N�ɂƂ��đ�ȏꏊ�ł��邱�Ƃ�����B�@���@�P�W�V�T�N�@�]�ؓ����� |
| �O�ʏ��̗�
| ����ׂ��傤�̂��B�P�Q�V�O�`�V�R�N�A�����S���x�z���̍����ɂ�����A�R�����͂Ɩ��O�ɂ��A�������S���̒�R�^���B�ʏ��Ƃ͓��ʕ����Ƃ����Ӗ��ŁA�����̛����������x��̂��߂ɑg�D�������E�̓�ʏ��ƁA�����S���R�̕ߗ��ƂȂ�Ȃ���E�o���Ă������̂��W�߂ĕҐ������_�`�R�����킹�ĎO�ʏ��Ƃ�B�O�ʏ��͍���̕��b�����̌R���͂̊j�ƂȂ���̂ŁA�����S���Ƃ̐킢�ł��O�q�Ƃ��Đ�����B�P�Q�V�O�N�A���퉤���������S���Ƃ̍u�a�ɓ��ݐ�ƁA����ɕs���ȎO�ʏ��́A����C��̒����ɋ����ď��z���A���O�̎x�����Ē�R�𑱂����B�����S���͍��퐭�{�R�ƘA�����ĂP�N�ɂ킽��ҍU�ɂ��A�������ח����������A�O�ʏ��̎c�}�͂Ȃ�����̍ϏB���Ɉڂ��Ă���ɒ�R�����B�O�ʏ��͓��{�ɂ��~����v���������A���q���{�͎���𗝉��ł����A���͂��邱�Ƃ͂Ȃ������B�悤�₭�������ꂽ�̂͂P�Q�V�R�N�A�܂茳�̍ŏ��̓��{�N�U�i�����j�̑O�N�ł������B�����S���q�w���E���Z���̂��߂̒��N�E�؍��̗��j�x���}�Ѓ��C�u�����[�@p.106�� |
| ����ő呠�o
| �����炢�͂��������傤�B���N������������\���镶����Y�B�����S���̑�R���N�����͂��܂������N�A�������{�͕��͂ɂ�����悤�Ƃ��āA�呠�o�̒����ɒ���A�P�U�N�������č��@�R�W�N�i1251�j�Ɋ��������B�헐�̒��Ŕ���ȍ��́E�J�͂��X�������̂́A�x�z�ґw�ɂƂ��ċ~���̎��Ƃƍl����ꂽ����ł���B���펞��͕����͍����ł���A���ƒ���̖@�Ƃ��č����E�����S���ȉ��L�����ԂɐM����Ă����B���̌o�ł́A���̌㒷����ɕۑ�����A���܂��쒩�N�̊C�Ɏc���Ă��鐢�E�I���������ł���B���{�̎����E�퍑�̑喼�E���������N�Ɏg�҂𑗂�Ȃ�ǂ����̔Ŗł������呠�o�����Ƃ߂��B���ꂪ���݊e�n�Ɏc���Ă���B�����c�فw�����x�����V���@P.33-34�ɂ�遄�@���@����w�呠�o�x |
| ��������
| �P�R���I�̒��N��������������ɔ������ꂽ�B����ł͕����̕ی쐭��̈�Ƃ��đ呠�o�̊��s���s���A����p�����B�����B�͂��߂͖ؐ��������g��ꂽ���A�ϋv���Ɍ��E������A����̂���ςȘJ�͂��K�v�ł������B����������������̂Ƃ��ċ����������������ꂽ�B���N�����œ������������悤�ɂȂ����B�P�R���I�����̎x�z���̍����Ŕ��B�����B
�u���������̂��肩���́A�܂��ؘg������A���̒��ɒ����p�̍��������߁A����ɖ̊������������Ē��^������B�����ɂƂ������������������A�����܂����̂��Ђ������Č`���ƂƂ̂����B���̂悤�ȋ��������̐����́A���Ȃ��Ƃ��P�R���I���͎n�܂����悤�ŁA���[���b�p�̋��������������Q�O�O�N���旧���̂ł������B���������̔����́A�����A���{�Ȃǎ��ӏ����ɂ��傫�ȉe����^�����B���{�͎�������A���N�Ɏg���𑗂邽�сA�呠�o�⏑�����˂����Ă������A�P�U���I���̖L�b�G�g�̒��N�N���̂Ƃ��A�����̊����Ɩ{�A����Ɉ���̋Z�p�҂𗪒D���Ă�A���Ă���B�߂������Ƃ����A����ɂ��͂��߂āA���{�ł������̖{��������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂ł���B�v�����S���q�w���E���Z���̂��߂̒��N�E�؍��̗��j�x���}�Ѓ��C�u�����[�@p.116�� |
| �����
| �����炢�������B�����̑�\�I�ȍH�|�i�ł�����͂P�P���I���ɑv�����̉e���Ő������n�܂�A�P�R���I�����̎x�z���̍����Ŕ��B�����B���̐͒��N�̋�̐����ʂ������̂��Ƃ������A���̓Ɠ��Ȕ������͑��ɗ�����Ȃ��B����͍���̓��H���A�����̓y�A���킮����A�Ă������H�v���Đ��ݏo�������̂ł���B�O���̂��͖̂͗l���قƂ�ǖ������A����ɂȂ�ƏۛƂŕ�����`�������̂��嗬�ɂȂ�B�����S���q�w���E���Z���̂��߂̒��N�E�؍��̗��j�x���}�Ѓ��C�u�����[�@p.112�� |
| �a�@�����R�̔h��
�i���j | �������t�r���C���n���́A��v�𐪕����Ē����ꂷ��O��ɁA���ӏ��n��Ɏ��X�Ɖ����R�𑗂����B�����ł́A���łɒ��N�������Ă���A��x�ɂ킽�������{�����������i���i�E�O���̖��j�������Ȃ����B����ɑ��ẮA�x�g�i�������ň���i��z�������j�A�`�����p�[�i���j���U���A�r���}�i�p�K�����j�A�W�������ɂ������R�𑗂����B�����̉����͕K���������������킯�ł͂Ȃ��A���{�����A�x�g�i�������ƃW�����������̏ꍇ�͂���������s���Ă���B���{�����ł͑䕗�ŁA����A�W�A�����ł͕��y�a�ő傫�ȋ]�����o���Ă���B�������A�A�W�A�e�n�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ������Ƃ͊m���ł���B���{�͌��������ނ��邱�Ƃ͂ł������A���q���{�͂�����@�Ɏ�̉��Ɍ������A��k���̐헐���ɓ���A�`���̊������n�܂�B����A�W�A�ł́A�x�g�i���l�A�^�C�l�A�r���}�l�Ȃǂ̖����I���o���n�܂�A�x�g�i�������f��A�^�C�����Ȃǂ̕��������܂�A�^�C���X�R�[�^�C���E�W���������}�W���p�q�g���Ȃǂ̐V�������͂��o�ꂷ�邱�ƂƂȂ�B�܂��A���̊C��i�o�ɂ���āA���[���V�A���E�̊C�悪��Ɍ���A���Ռ����g�債���Ƃ������̂悤�Ȏw�E������B���̂悤������A�W�A�C��Ɠ�A�W�A�C������ԊC���ʂ̊������ɂ���āA�C�X���[����������A�W�A�n��ɋy��ł������Ƃ����������Ƃ͂ł��Ȃ��B
���Ռ��g����߂���������A�W�A�i�o�@�P�Q�W�V�N�A�t�r���C���n���͑ΊO������o�ρE�ʏ�����Ƃ������a�F�D�H���ɓ]�����A�X�������J�����߂Ƃ����C�����̂Q�S�����Ɏg�ߒc�𑗂���v�𑣂����B�P�Q�X�Q�N�̃W���������������̂悤�Ȓʏ��������߂��������̂ŁA�P���T��̂�������悹���匳�E���X�͑��͓�V�i�C�ƃW�����C�Ɍ��ꂽ�j��ő�̊͑��ł������B�������W�������Ƃ̌��͗��핔�����s�p�ӂɓ���ɉ���������߁u���s�v�����B�������A�����S���͑��̔h���ɂ���āA��V�i�C�|�W�����C�|�C���h�m�����ԊC�ニ�[�g�����܂�A�匳�E���X�ƃC�����n�����i�t���O���E���X�j�͊C�ニ�[�g�ł����ꂽ�B�}���R���|�[���̋A���͂��̊C�ニ�[�g�𗘗p�����B�������āA�P�R���I�̃��[���V�A���E�́A���͓��{���琼�̓u���e�����܂ōL���A���̗ւɂ���ď��߂ĂȂ��ꂽ���ƂɂȂ�B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.140-143�� |
| a�@���̓��{�����i�����j | �����t�r���C���n���ɂ��A�P�Q�V�S�N�̑�P���ƁA������v��łڂ��Ē����ꂵ������P�Q�W�P�N�̑�Q���ɂ킽����{�����ł��邪����������s�����B���{�ł́u�ÏP���v�܂��́A��1�u���i�̖��v�A��2�u�O���̖��v�Ƃ�������B�����̓��{�����q���{�̖k�����ɂ�鎷�������̎���ŁA�k�����@��̌�Ɛl������Č��R�����ނ������A���̑���ȕ��S�͖��{���S�̈���ƂȂ����B���ɂƂ��Ă͗̓y�̊g��Ɠ����ɁA����A�W�A���n��ւ̐i�o�Ɠ������C����Ռ��̊g����Ӑ}�������̂ŁA�āX�������Ă��ꂽ���A�t�r���C�����ɑ�������ł���n�C�h�D�̗��Ȃǂ��N����A�������Ȃ������B
��P���@�t�r���C���n���͍���Ƃ̊W�����肳������A�P�Q�U�U�N������{�ɑ��Ă��т��э����𑗂�C�D�����߂��B������v�𐪓����邽�߂ɂ͍���E���{�Ƃ͗F�D�W�ɂ��邱�Ƃ�v�������߂Ǝv����B�������A���{�̊��q���{�͌��̕�������ł���Ƃ��Ă��̗v�����B�t�r���C�͕��͂ɂ����{�����ɓ��ݐ�B�P�Q�V�S�i���i�P�P�j�N�P�O���A�����S���E����E���l�̍����Q���U��̕������X�O�O�z�̌R�D�ɕ��悳���A�Δn�E����N���A�����p�ɏ㗤�������A��Ɛl�Ȃǂ����m�̒�R������A�퓬����œP�ނ��A��P��̉����͎��s�����B����͏��蒲�דI�Ȃ��̂ł������B
��Q���@���̌���߂Č��͎g�߂�h�����������q���{�����̖k�����@�͂�����a��A�P�Q�W�P�i�O���S�j�N�̑�Q���ƂȂ����B���̂Ƃ��͂��łɓ�v�͖ŖS���Ă����̂ŁA���킩��̓��H�R�S���̑��ɁA���B����P�O���̍]��R���h�����ꂽ�B�U����{�A���H�R�������p�ɏ㗤�A���{���͐Ηۂ�z���Ėh�킵�A���M�Ŕ����ɏo���B��P�����퓬�����������A�\���J�ɂ���Č��R�����Q���A�P�ނ����B���R�P�O���A����R�V�炪��j�܂��͓M�����A�ߗ��Q�`�R�������Y���ꂽ�Ƃ����B�B
��Q���R�̍]��R�̎����@�P�O���Ƃ�����u�]��R�v�A�܂茳�ɍ~�������l�̕��m�́A�u�����ȈӖ��ł́A�ނ�͕��m�ł͂Ȃ������B�ǂ����ׂĂ��A�ނ炪������ׂ����������Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B�����̐l�X�́A��W�ɉ������m�������ł������B���Ɠ�v�̐��{�R�������l�X����A��]�������̂ł���B�]���A�܂܌�������悤�ȁA���������ł͂Ȃ������B�������A�����炭�ނ�́u�����v�ł͂Ȃ������B�E�E�E�E�ނ炪�g�т����̂́A�ǂ���畐��ł͂Ȃ��A�_���ł������炵���B�܂�A�P�O���̑啔���́A���A�̂��߂́u�ږ��v�ɋ߂������B�c�����o��������͑��́A������A�u�ږ��D�c�v�ł������Ƃ����邩������Ȃ��B�v��Ɂu�ږ��v���������g�����͑D�Ƌ����̊͑D�͕��ˉ��Ȃǂɑҋ@�����邤���A���ŕ��v���Ă��܂����B�u�C�O�ږ��v�͈�ʂɂ����āu�C�O�����v�ł������B�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x1996�@�u�k�Ќ���V���@���@p.129-135��
Epi.�@�_���͐��������@�����i�ÏP���j�͓�x�Ƃ���\���J�ɂ���Č��R����Q���̂��A���̓P�ނ̗��R�Ƃ���A�����͒���ȉ��̐_���ւ̋F�������ʂ��������ƌ��`����A��ɂ́u�_�����{�v�����u�_���v�ł���ƔF�������悤�ɂȂ����B�������A��P��̕��i�̖��Ŗ\���J�����������Ƃ͍������������B���a�R�R�N�A�C�ۊw�҂̍r��G�r���͋���̂P�O���Q�O���͐V��ł͂P�P���Q�U���ɂ�����A�䕗�V�[�Y���͋�������ł��邵�A�����̕����ł��\���J�̋L�^�͂Ȃ��Ƃ��Ēʐ���ے肵���B�\���J���������Ƃ����̂͏\���͂Ȃꂽ���s�̌��Ƃ̓`���ȂǂŋL����Ă���ɉ߂��Ȃ��B��Q��̍O���̖��̎��ɖ\���J���������͉̂[�V���P���A�V��łW���Q�R���̂��ƂŁA����͎����I�ɂ��m���ł���B�ǂ����u��x�Ƃ��_�����������v�Ƃ����̂͌���Ă���B�����̔s�ނ́A��͂茳�R�ƍ���R�̑Η��ȂǍU�����̖��ł������Ƃ��ׂ��ł���B���Ԗ�P�F�w�ÏP���x��@1974�@���w�ك��C�u�����[�@p.207,272��
Epi.�@���A���{�������~�B�������̂��Ƃ��B�@�P�Q�W�R�N�A�t�r���C�͓��{�āX�������v�悵�����A�]��̖��O�������������������A���̒����Ɏ�Ԏ��A���s���Ă����x�g�i�������ɗ͓_��J���悤�ɂȂ����B�t�r���C�͂Ȃ������{������������߂Ȃ��������������O�̔������������A�܂�����ł̃x�g�i����������R���Ă����B���̂悤�Ȓ��A�畔��������́A���{�ւ̏o�����čl���ׂ��ł���Ƃ̈ӌ��𐢑c�ɒ�o�����B
�u�d�d�������{�͊C�m�����A�d�y舉��A�i���ƌ���A��������x�g�i���̂��Ɓj�䂷�ׂ��ɔB�����̏o�t�A�O���������ӂ݁A���Ƃ����ɂ��킸���Ĕނ݂̊ɓ���Ƃ��A�`���͒n�L���k�O�Α�����B�ނ̕��l�W���ĉ䂪�t�����A����s���Ȃ�A�~������Ƃ�����A����\����n�����A�d�d��������{�͊C���ɕƍ݂��A�����Ƒ��ւ����Ɩ����Ȃ邨��v�i�w���j�x�j�Ɛ������̂ł���B���c������ɂ͔��ł����A�P�Q�W�U�N�̐����A�u���{�͖������đ��Ƃ����B���܌���͕ӂ�Ƃ��B�X�������{�������Č�������Ƃ��ׂ��B�v�Ƃ��ē��{�����𒆎~�����B���̒m�点���`���ƒ����̖��O�͂�낱�B�u�A�N���{�̖��A�S���͏H�ʂ��A���{�͏���B���t��낷�B�]���̌R���A�������̔@���B�v�i����j�Ɠ`������B�����c�فw�����x�����V���@P.161-162�� |
| b�@���̃x�g�i������ | �����S���鍑�͑O��R�x�ɂ킽��x�g�i���ɉ��������B�����t�r���C���n���̎������{��������x�g�i�������Ɏ�͂��ւ��A��K�͂ȉ������Q�s�������A��������k�x�g�i���̑�z���A���ɂ���Č��ނ���A���s�����B
��P���@�P�Q�T�V�N�@�����P���n���͓�v��w�ォ��U�����邽�߂Ƀt�r���C���_��ɔh�������B���̍��̈ꕔ�Ƃ��ă����S���R���_�삩��x�g�i���k���ɐN�������B�����S���R�̓n�m�C���̂������A���N�P�ނ����B
�t�r���C�͑��ʂ���ƃx�g�i���Ɏg�҂𑗂�A���̉������썑���ɕ����A�_���K�`�i�B�D�Ԑԁj��u���čs�����ē���̐����Ƃ����B�P�Q�V�X�N�A��v��łڂ��ƁA��C�����Ƃ̒ʏ��ɏ��o���A��B�ȂǂɎs���i��u���A�܂��g�߂��`�����p�[�i���j�A�W�����A�X�}�g���A�C���h�ɔh�������v�𑣂����B�W�P�N�A���̓`�����p�ɍs�Ȃ������ē�����������悤�Ƃ������A�`�����p������������ۂ������߁A�����R��h�������s���B�W�������U�߂������Ɋׂ����B
��Q���@�P�Q�W�S�N�@���̓`�����p���߂ɒ��ɂ��o����v���������A���͂�������ۂ����B���N�A�`�����p�����R�͖\���ɑ����呹�Q�������B�t�r���C�͗��H�`�����p���U�����邽�߁A���ɏo���A�n�m�C���̂����B���̏��R�G�n���i�E�}���j�̓x�g�i���R�ߗ����ʂɎE�Q�������A���R���s�ɗ�����ꂽ�x�g�i���R�̒�R�ł����A�P�ނ����B
��R���@�P�Q�W�V�N�@�t�r���C�͑O��̎��s�ɗ�̂��Ƃ��{��A���{�����̌v��𒆎~���āA��R��h�����ė���C�ォ��x�g�i���̒����U�������B�n�m�C�͊ח������m�@�͓��S�������A�x�g�i���R�͌��̗ƐH�A���D��_���Ă��̗A���H��f�������߁A���R�͎����������邱�Ƃ��ł������N�A�P�ނ����B�t�r���C�̓x�g�i��������������߂��A�P�Q�X�Q�N�ɃW�����ɉ����R�𑗂�����A���N�x�g�i���Đ����v�悵�����A�X�S�N�ɖv�������ߎ��{����Ȃ������B���ȏ�A���{���L�w�x�g�i���������j�x��g�V���@p.68-71��
Epi.�@�o�N�_����̊�v�@�u�P�Q�W�W�N�R���A���R�̃E�}�����R������D�c�̓o�N�_���]������B�}�����̂̓`�����E�N�H�b�N�E�g�A���i���s�j�̌R�������B�`�����E�N�H�b�N�E�g�A���̓o�N�_���]�ł̐퓬�����𐮂����̂��S�R�Ɍ������đi�����B�u�����G��S�ł����Ȃ���A�ӂ����т��̉��]�i�z�A�W�@���j�ɋA��Ȃ����Ƃ𐾂����v�i���]�ّ����]�̎x���A�^�C�r�����������ƃn�C�Y�I�����C�z�����Ȃ̋��𗬂��d�v�Ȑ�ŁA�ӂ����ю�s�ɂق��ǂ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��j�B�E�E�E�S���R���A���R�̊͑D���i�����Ă������A���������v����ă��F�g�i���̏��͒��R�����R�ɒ��B���R�̊͑D���o�Ă���̑҂��ă��G�g�i���͒��͂����Ɠ����o���A���R�ɒǐՂ����邩�������Ƃ����B����ƒ��������͂��߁A���̊͑D�͍Y�ɂ��������ē����Ȃ��Ȃ����B�����փ`�����R���˂�����ł����B����ɗE�C�����G�g�i�����͌����̊o��œG�Ɍ��������B���݂ő҂������Ă����`�����R������蕱��̖��A���Ɍ��R��j�����B�͑D�P�O�O�ǂ߁A�S�O�O�ǂ�ߊl�A���R���m�������������A�E�}�����R�Ƒ吨�̏��R�A�m���������ߗ��ƂȂ����B�v�����q��j�w���ꃔ�F�g�i���̗��j�x�����V���@p.87�� |
| c�@�p�K����
| �@���@��Q�́@�Q�߁@����A�W�A���E�̌`���@�p�K���� |
| �y�O�[��
| �r���}�i���~�����}�[�j�̃C�����f�B�쉺����������l�����������Ɓi�P�Q�W�V�N�`�P�T�R�X�N�j�B�����l�̓r���}�l���p�K�����Ɏx�z����Ă������A�p�K���������̍U���ŖŖS���A�r���}���������̐����ɕ��������ہA���̈�Ƃ��Ď��������B�s�̃y�O�[�i���݂̃p�S�[�j�͉��r���}�̗v�n�Ŗf�Ս`�Ƃ��Ă��h���A�|���g�K���l�����q�����B�P�T�R�P�N�Ƀr���}�l���g�D���O�[���Ƀy�O�[���̂���A�܂��Ȃ��ŖS�B |
| �^�C�l
| �^�C�ꑰ�̓V�i���`�x�b�g�ꑰ�ɑ�����B�^�C���b���l�X�Ƃ����L���Ӗ��ł̃^�C�l�i�V�����l�j�́A���݂̃^�C�����ł���ق��A����A�W�A�e�n��ɍL�����Ă��邪�A���Ƃ��Ƃ͒����̓쐼���ɂ����炵���B�P�P�`�P�Q���I�ɓ쉺���J�n���A����ɂP�R���I�ɂ������S���鍑�Ɉ�������A�C���h�V�i�����ɓ���A�`���I�v����������̕��암�ɈڏZ���Ă����B�����ɂ͂��łɃ����l���h�D���@�[�����@�e�B���������������A���̍��͓�����͂�L���Ă����N���[���l�̃J���{�W�A�Ɉ������ꐊ���Ă����B�^�C�l���͂��߂̓N���[���l�Ɏx�z����Ă������A�P�R���I���ɂ͂������̉���������A���̒��̈�`���I�v������㗬���X�R�[�^�C�����ł��L�͂ƂȂ����B�X�R�[�^�C���͂P�T���I�Ƀ`���I�v�����쉺���ɂ����������^�C�l���A���^�����ɕ������ꂽ�B�A���^�����͂P�V�U�V�N�Ƀr���}����N�U�����A���E���p���[���̌R���ɖłڂ���A�A���^�����j�ꂽ�B���̌�P�V�W�Q�N�Ƀ^�C�l�̍������^�i�R�[�V�����i�`���N�����j���������A���̉����������܂ő����Ă���B�^�C�l�̓^�C�S��̂ق��A���݂̃��I�X�A��J���{�W�A�A�~�����}�[�k���A�����쐼���ɂ����݂��Ă���B |
| d�@�X�R�[�^�C��
| �P�R���I�㔼�`�P�T���I�ɁA���݂̃^�C�ɋ������������B���Ƃ����^�C�l�i�V�����l�Ƃ������j�́A�����̎l��n����_��n���ɏZ��ł������A�����S���̓쉺�Ɉ�����āA�P�R���I�ɃC���h�V�i�����ɈڏZ���A��Z���Ɠ������Ȃ����Z�����Ƃ����B�͂��߃J���{�W�A�i�^�c�j���A���R�[�����ɏ]�����Ă������A�P�Q�T�V�N����ɃX�R�[�^�C��s�Ƃ��ăX�R�[�^�C�����N�������B��R������[�}�J���w�[�����̂P�Q�W�R�N�ɁA�J���{�W�A�̕��������ƂɓƎ����^�C�������������B�܂�������������ی삳��A�X�R�[�^�C���͂��ߊe�n�ɕ�����Ղ������B�P�R�T�O�N�ɓ�̃A���^�����A���^�������N����Ǝ���ɐ��ނ��A�P�T���I�ɂ͒n�������Ƃ��đ������邾���ƂȂ����B�@ |
| ���[�}�J���ց[���� | �^�C���X�R�[�^�C����R��ڂ̉��i���[���J���w���Ƃ��\�L�j�B�݈ʂP�Q�V�X�N���`�P�Q�X�X�N�B���͎x�z�̈���J���{�W�A��r���}�A�}���[�����ɂ܂ł̂��A�S�����������炵���B�܂��A�P�Q�W�R�N���^�C�����i�V���������j���l�Ă����A����̋Ɛт�蕶�Ƃ��Ďc���Ă���B���̔蕶�ɂ͂��̉��̑P�����q�ׂ��Ă���B�܂���������������Ƃ̗��O�Ƃ��ĕی삵���B�@ |
�^�C����
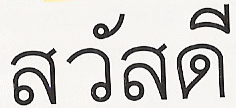 | �P�Q�W�R�N�Ƀ^�C���X�R�[�^�C���̑�R�㍑�����[�}�J���w�[�����̂Ƃ��A�N���[�������̑����̂��������^�C�l�̕����B�V���������Ƃ������B�P�Q�X�Q�N�ɂ���ꂽ���[�}�J���w�[�����̔蕶�ɍŌẪ^�C�������p�����Ă���B���͂��̗�i�T���b�f�B�[�A�������̂��Ƃj��������́w�}���E�A�W�A��������x�͏o���[�V�� p.36�� |
| �V���K�T���� | �W�������̉����ŁA�P�Q�Q�Q�N���N�f�B������|���Č����B�V���S�T���Ƃ��\�L�B�W�����������̃V���K�T���𒆐S�ɁA�q���h�D�[�����W�����A���̐��͂��V�����[���B�W���������̃p�����o���܂ł̂��A��������������B�N���^�i�K�����̎��A�������t�r���C���n���̎g�߂��P�Q�W�X�N�ɗ��q���āA������v�����Ă������A���͂��̎g�҂�߂炦�A�Ǖ����Ă��܂����B�P�Q�X�Q�N�Ƀt�r���C�͉����R���W�����ɔh���������A���̂Ƃ��͂��łɃV���K�T�����̓N�f�B�����̈�q�̔����ɂ���č������E�����Ƃ��������̒��ɂ������B�N���^�i�K�����̏������B�W�����̓}�W���p�q�g���ɓ���A���ʂ̉̂��߂Ɍ��R�̎x�����邱�Ƃɐ������A�}�W���p�q�g�������J�����B���n���\���w����A�W�A�j�x�݂������[�@p.51�@�Ȃǂɂ�遄 |
| e�@�}�W���p�q�g����
| �W�������ɋN�����������B�W�������ɂ��V���K�T����������A�P�Q�X�Q�N�����t�r���C���n���̐N�����邱�ƂƂȂ������A�������N���荑���N���^�i�K�������E���ꂽ�B���̏����̃��B�W�����͓������W�����������̃}�W���p�q�g���i�ꂢ�ʎ��Ƃ����Ӗ��j�ɓ���A���ʂ����邽�ߗ����������R�̋��͂����t����̂ɐ������A�����R����肵���B�������ă}�W���p�q�g�������������A���͍I�݂Ɍ��R���A�������ēƗ���������B���̌��������і��ɂ͒��v�𑱂��Ȃ���A���������B�}�W���p�q�g�������q���h�D�[�����ł��������P�U���I�ɃC�X���[��������}�^���������������W�������̐����ɐ�������Ǝ���ɗƂȂ�A�łڂ����B�V���K�T���ƃ}�W���p�q�g�͓���̉����̍��Ȃ̂ŁA�V���K�T�����}�W���p�q�g�����ƕ\�L���邱�Ƃ�����B |
�w�^�c���y�L�x
���@�c�̊g�� | ����낤�ӂǂ��B�P�Q�X�U�N�`�X�V�N�A�����A���R�[�����̃J���{�W�A�i�������^�c�j�ɔh�������g�߂ɓ��s�������B�ς��L�^���������B�P�R���I���̃J���{�W�A�̏�`����M�d�Ȏ����ł���B�A���R�[�����͓����A�W�������@���}���V���̑S�����i�P�Q�`�P�R���I�j���I���A�����̃X�R�[�^�C���A�����̃`�����p�[�ɉ�����A���ނ����������A����ł��A���R�[�����g���𒆐S�Ƃ��āu�x�M�^�c�v�ƌ�����悤�Ȕɉh���Ȃ��������Ă������Ƃ��L����Ă���B |
| �b�@���̑S���� | �@ |
| a�@�����S���l�����`
| ���������ł������ł́u�S���̒��̓����S���l�������ĔC�p����v�Ƃ����������������B�����S���l�ȊO�́A�F�ڐl�E���l�E��l�ɕ�����ꂽ���A��l�Ȃǎx�z�w�ƂȂ����̂̓����S���l�ł���A�����S���l�ŕs������ꍇ���F�ڐl�����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă����B�ؒ�����ؖk�́A���ċ��̎x�z����n��̏Z���̊������⏗�^���Ȃǂ����l�Ƃ����A�ؓ�̂��Ƃ̑v�̗̈�̊������Ȃǂ���l�ƌ���ꂽ�B���l�E��l�͍��������ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�x�z����鑤�Ƃ��đd�łS�����B���̂悤�ȑ̐��������S���l�����`�A���邢�̓����S���l����`�Ƃ����B |
| b�@�F�ڐl
| ������������B�����̂��Ƃł̐����̏o�g�҂������B�F�ڂƂ́u��ށv�̈Ӗ��i�Ⴊ���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��̂Œ��Ӂj�A�����̎푰���܂ށB�E�C�O���A�i�C�}���A�^���O�[�g�A�`�x�b�g�Ȃǐ��揔�n��̐l�X�ɉ����A�A���u�l�A�C�����l�A�C���h�l�A���_���l�A���V�A�l�A�g���R�l���܂ށB�}���R���|�[���Ȃǂ̃��[���b�p�l���u�t�����L�v�Ƃ����ĐF�ڐl�Ƃ��ėD�����ꂽ�B�F�ڐl�͌����ł̓����S���l�Ɏ����n�ʂɒu����A����������n���̑��߂ɓo�p����邱�Ƃ������A�x�z�ҊK�����\�������B |
| c�@���l
| ��ʓI�ɂ͂��������������������t�ł��邪�A�����S���l���������x�z�������������ł��錳�����ł́A�����S���l�A�F�ڐl�A���l�A��l�̖������g���I�ɋ�ʂ��ꂽ�ۂ́u���l�v�́A���Ă̋��̗̈�ɂ����l�X�ŁA�͈̉Ȗk�̊������A�_�O���A���^���A����l�A�݊C�l�Ȃǂ��Ӗ������B�����������ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��邱�ƁB�����̂��ƂŖ�l�ɓo�p����邱�Ƃ����������A���̐��͏��Ȃ��A�����͐��Y�ґw�Ƃ��ĐłS�����B�����S���l�����`�̉��ŁA�F�ڐl���D������Ă����̂ɔ�ׂāA���l�͓�l�Ƌ��ɗ}������Ă����B |
| d�@��l
| ����ŁA��v�ŖS�Ɍ��ɕғ����ꂽ�l�X�ŁA��v�̈▯�̊������������B�ł��Ō�Ɍ��ɕ����������߁A���ł͍ʼn��w�Ɉʒu�Â����A�㋉�̖�l�ɂȂ邱�Ƃ͂ł����A��Ƃ��ĐłS�����x�z�҂̗���ɒu���ꂽ�B�@ |
| �������i���j | �������́A�剺�ȁE�����ȂƂƂ����@���̗��ߐ��ȗ��̎O�Ȃ̈�Ƃ��āA�c��ُ̏��̋N���ɂ�����ŏd�v�����������B�����ł͖剺�ȂƏ����Ȃ͏�u���ꂸ�A�����Ȃ��ō��s���@�ւƂ���A�Z���������Ȃ̊NJ����ɓ���A���̎����I�����ł��鍶�E�告���ɑ��̖������ʂ����Ă����B�܂��A�n���̍s���E�R���E�������i��@�ւƂ��čs�����Ȃ������������A��ɒ����Ȃ��番�������B�Ȃ��A���̖��ɂȂ�ƁA�����Ȃ��p�~�����B�@ |
| �s�������i�s�ȁj | �������イ���債�傤�B�����̌����ɂ����āA�͂��ߒ����Ȃɒ������Ēn���̍s���E�R���E�������NJ��������A������v�����Ă���́A�����Ȃ��番�����āA�c��i��n���j�ɒ������Ēn���s���ɓ�����@�ւƂ��đS�y�ɐ݂����邱�ƂƂȂ����B�������s���Ƃ������B�͂��߂͗�k�A�ɗz�A�Ïl�A蟐��A�l��A�͓�A�]���A�L�A�]���A�_��̂P�O�n���ɐ݂���ꂽ�B�Ȃ��A����ȍ~�ɒn���s�������u�ȁv�Ƃ����悤�ɂȂ�̂́A�u�s�ȁv���痈�Ă���B |
| e�@�ȋ��̒��~
�i���j | �����S���l�����`���Ƃ�ꂽ���́A�������ȋ����s�Ȃ��������߁A�P�Q�V�U�N�̓�v�̖ŖS�ƂƂ��ɒ����̒����`���ł������ȋ��͂������f����邱�ƂƂȂ����B�ȋ����s���Ȃ��Ȃ������߁A�v�ȗ����m��v�i�n��w�o�g�Œm���l�Ƃ��Ċ����ƂȂ����l�X�j�͖v�������B�܂����ȗ��̊��w�ł�������w�������҂̒n�ʂ��������A���\���i���イ���ザ�������j�ƌ�����悤�ɂȂ����B
�Ȃ����͐m�@�̂Ƃ��A�P�R�P�R�N�ɏ��߂ĉȋ������{�A���̌�����͎��{���ꂽ���A���i�ҁi�i�m�j�ƂȂ���̂͂��������ł������B���S�ȉȋ��̕����͎��̖����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| ���\��
| ���イ���ザ�������B�ȋ������~���ꂽ����ŁA��҂̒n�ʂ��Ⴍ�Ȃ������Ƃ��������t�B��͎�҂̂��ƁA���i�����j�͌�H�̂��ƂŁA��҂͉������Ԗڂ̒Ⴂ�����N�ł���Ƃ����Ӗ��B�Ȃ��A�\�i�K�̃����N�Ƃ́u���|���|�m�|���|��|�H�|���|���|��|���v�Ƃ������̂ł��邪�A���i�㋉�E�j�Ɨ��i��ʊ����j�͉ȋ����ĊJ����Ă������S���l��F�ڐl�����������B�m���Ɠ��m�̒n�ʂ���r�I�������Ƃ����ڂ����B |
| �_���K�`
| �����S���鍑�A����ь����A�����n�Ǝx�z�n�ɂ��������E�B�B�D�ԐԂƕ\�L����B�����S���鍑�ł̓`���M�X���n���̎�����A�����n�̍s����ʂ��ē��銯�E�Ƃ��Ă�����Ă����B���ł͎�v�ȓs�s��A����A����Ȃǂ̐����n�Ƀ_���K�`��z�u���A�ˌ������A���ŋƖ��A�w�`�Ɩ��Ȃǂ̐�̍s�����s�킹���B�_���K�`�Ƃ��Ĕh�������̂́A�����S���l���F�ڐl�Ɍ����Ă����B |
| �c�@��ʁE�f�Ղ̔��B | �����S���鍑�̂��Ƃł̓��[���V�A�嗤�̓����ꌠ�͂̂��ƂŎ��������肵�A�܂��w�`���i�W�����`�j���^�͂Ȃǂ̌�ʖԂ����B�������ߓ������Ղ����H�A�C�H�Ƃ��Ɋ����ɂȂ�A�o�ς����W���Ď����Ƃ����������p����ꂽ�B�����f�Ղł͐F�ڐl�ƌ���ꂽ����o�g�̐l�X�����A�L�B�E��B��L�B�ɂ����X�������l�����q���ē���A�W�A��C���h�m���ʂƂ̓�C�f�Ղ������ɍs���Ă����B�t�r���C���n���̐ϋɓI�ȉ������A���̂悤�ȏ��ƌ��̊g������߂��Ƃ����ʂ�����B�܂������̍����̔_���ł́A�v��ȗ��̋����̂Ȃ��̊��l�̑�y�n���L�҂��������Ă���A�o�ϊ������x���Ă����B�@ |
a�@�w�`���i�W�����`�j

���́A�^�V�P���g�̃E�Y�x�L�X�^�����j�����قɂ������A�����S���鍑�̔v���ipayza�j | �I�S�^�C���n�����P�Q�Q�X�N�ɐ��x�����������S���鍑�i����ь��j�̌�ʒʐM�ԁB�����S������W�����`�i������⋐ԂƏ����j�Ƃ����̂́A�W�������u���v��u�w�v���Ӗ����A�`�͐ڔ���Łu�l�v�̈Ӗ��Ȃ̂ŁA�W�����`�Ƃ́u�w�Ɍg���l�v�̈Ӗ��ł��邪�A��ʂɉw�`���Ɩ�Ă���B⋐Ԃ�⋁i����j�͉w�Ɠ����Ӗ��ŁA��v���H�ɂP�O�����Ƃɂ������h�w�̂��ƁB�h�w�ɂ͂P�O�O�˂�⋌��i���j�������A�l�n������B�w�`�𗘗p����̂͌��p�̗��s�҂́A�ʍs��`�Ƃ����v�����g�s�����B�w�`���̓����S���ȑO�ɂ������Ŕ��B���Ă���A�܂��I���G���g�̃y���V�A�鍑�Ȃǂ̐��E�鍑�ɂ�����ꂽ�V�X�e���ł������B ���̃W�����`�́A�Q�O���I�ɃV�x���A�S�����J�ʂ���܂ŁA���[���V�A�ł̍ő��̏��`�B�V�X�e���ł������Ƃ���Ă���B
�����@�}���R���|�[���̓`����w�`���@����̉w�`�������������}���R���|�[���͎��̂悤�ɓ`���Ă���B
�u�������n���ɒʂ����v���H��ɂ́A�Q�T�`�R�O�}�C�����Ƃɏh�w���z�u����Ă���A�e�h�w�ɎO�S�`�l�S���̃E�}����������Ďg�b�̎��R�Ȏg�p��҂��Ă��邵�A�h���ݔ��ɂ��Ă���L�̂悤�Ȋق������āA�����ȏh�����ł���̂ł���B������������{�݂́A�J�[���̐��߂��s���Ă��邷�ׂẲ�����ʂ��Đ�������Ă���̂ł���B�E�E�E�E�ȏ�̂悤�Ȑ��x�ɂ���āA�J�[���̎g�b�����͍s�����������ɂ����Ă��h�ɂ�����E�}���p�ӂ���Ă��āA���X�̗��s�ɕs�ւ��Ȃ��B���̎��������͑S���A�×��̂����Ȃ�鉤�E�����Ȃ�l���ɂ���Ă��Ȃ������Ȃ������s�傳�̑傳��@���Ɏ����ł��P�������؋��ł���B�l���Ă������Ȃ����B�g�b�̗p�ɋ����邾���ł���\�����̔n�C�������h�w�Ɏ��{����Ă���A���̏�ɂȂ��ꖜ�ȏ�̊ق���L�̂悤�ɍ����Ȑݔ��𐮂��Đ݂����Ă���̂ł����B�S�����Q�ɒl���鎖���ł����āA���̕x�����͂ƂĂ��M��ł͐s�������Ȃ��Ƃ���ł���B�v���}���R���|�[���w���������^�x�P�@�������j��@���m���Ɂ@p.253�� |
�@�v��
�i��}�Q�Ɓj | �͂��ӁB�����S���鍑�̌�ʖԂł����w�`���i�W�����`�j�Ŏg�p���ꂽ�ʍs�B�v�q�Ƃ������B�@�u�p�C�U�Ƃ������Ђ̂����̂��̂��A��p�̌����ł���A������ł̓p�C�c�A�����S����ł̓Q���Q�Ƃ������B�p�C�U�͖ؐ��A��A���邢�͋����ŁA������������闷�s�҂̐g����d�v�x�ɂ���āA�����Ƀg����n���u�T�̏��肪����ꍇ���������B�����͊����̏ꍇ�ƃE�C�O���������g���Ă���ꍇ���������B���c�D�S�[�h���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@p.101�� |
| b�@���X�������l
| �@���@��T�́@�Q�߁@���X�������l |
| �����M
| �ق��ケ���B����ȍ~�A�v�E����ɂ������̃A���r�A�l���l�i�C�X���[�����k�ŏ��l�ł���̂����X�������l�Ƃ����j�����A�����Ŋ������Ă����B�����ł͔ނ����H�i�^�[�W�[�j�ƌ���ꂽ�B�����Ȑl�Ɋ����M�i�ق��ケ���j������B�ނ͓�v�̖�������B�Ŋ����A���r�A�l�i�܂��̓C�����l�Ƃ������j���l�ŁA�C�^�Ƃɏ]�����Ă����B�s���Ƃ�����E�ɂ��Đ�B�̖f�Ղ��������Ă������A���R���쉺���Ă���Ƃ���ɋ��͂��A���̕����E�L���n�������Ɋ���A����̓�C�f�Ղł��傫�ȗ��v���グ���B�����M�ȊO�ɂ��A���r�A�n���X�������l�̊����͎�s��s�̑��A�Y�B�A��B�A�Y�B�Ȃǂ̍`�s�Ŋ����ł������B�܂��A�t�}�b�h�Ƃ����A���r�A�l�͌��̍��������ɂȂ��Ă���B |
| c�@�Y�B
| �@���@��R�́@�R�߁@��v�@�Ո��i�Y�B�j |
| d�@��B
| �����̕����ȓ��암�ɂ���C�`�s�s�B���ォ��ɉh���n�܂�A�v�A���̎�������X�������l�����`���Ċ������Ă����B�v�i�k�v�j�ł��s���i���u����A��v�ł��L�B�ɑ����Ėf�Ղ̒��S�n�ƂȂ����B��v�̖��Ɍ��ɐQ�Ԃ��Č��т������������M�͐�B�Ŋ������Ă����A���u�n�̏��l�Ƃ��ėL���ł���B�P�R���I�ɂ��}���R���|�[���A�P�S���I�ɂ̓����b�R���C�������o�g�D�[�^�����K�������Ƃł��m���A���[���b�p�ł��U�C�g�D�[���Ƃ���ꂽ�B��B�͂��̌㐊�ނ��A���݂ł͖f�Ս`�Ƃ��Ă̋@�\�͎����Ă���B
Epi.�@�C�������o�b�g�D�[�^�̌�����B�@�C�������o�b�g�D�[�^�̓����b�R���܂�̑嗷�s�ƁB�P�R�S�T�N�ɐ�B�ɏ㗤���A���������s��K�₵�Ă���B���̎��̔ނ̌�����B�ɂ��āA���̗��s�L�w�O�嗤���V�L�x�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�u�܂��㗤�����̂̓U�C�g�D�[���i�h�ˏ�A���Ȃ킿��B�j�ł������B�E�E�E�s��Ȓ��ŁA�J���n�[�i�юсj��A�j�q���Y���邪�A�����͒��̖����Ƃ��ăU�C�g�D�[�j���ƌĂ�A�Y�B��n���o���N�i��s�j���̂��̂��D�G�ł���B�U�C�g�D�[���̍`�͐��E�ł������Ƃ��傫�Ȃ��̂̈�A���ȁA���E�ő�̂��̂ł��낤�B�킽�����͖�S�ǂ̑�^�W�����N�������B�����Ȃ̂Ɏ����Ă͐��������̂��ł͂Ȃ������B�傫�Șp���C���痤�n�ɓ���A��͂ƍ����Ă���B���̒��ł́A���̃V�i�̒��X�Ɠ������A�ǂ̎s������┨�������A���̐^���ɉƂ����ĂĂ��邱�ƁA�킪�̋��̃V�W���}�[�T�̒��Ɠ����ŁA���̂��߂ɃV�i�̓s�s�͍L�X�Ƃ��Ă���B�C�X�������k�͗��ꂽ�ʂ̒��ɏZ��ł���B�E�E�E�����̏��l�́A�ً��k�����̍��ɏZ��ł���̂ŁA���X����������Ƒ��т����u�C�X�����̍����痈���̂��v�ƌ��X�ɂ����āA�����̍��Y�̈ꕔ����̂��Ă����B�E�E�E�v���C�������n���h�D�[���w�O�嗤���V�L�x�O���M����@�p�앶�Ɂ@p.288�� |
| e�@�L�B
| �@���@��R�@�Q�߁@����̐��x�ƕ����@�L�B�@ |
| f�@��^��
�i���j | ���Ɠ�v�̑Η��̂��߂ɒ����S�y�̌o�ό��͕��f����Ă������A�����̐����ɂ���čĂѓ�������邱�ƂƂȂ����B�����ōĂыr���𗁂т��̂���^�͂ł������B�@�̑�^���́A�����E���z�Ɍ����āA�]��Ɖؖk�n�������x���^�Ō��Ԃ��̂ł������̂ŁA���͓s��s�ƍ]��n���ڌ��ԁA��k�c�f����^�͂̌��݂�V���ɊJ�n�����B�P�Q�V�U�`�P�Q�X�Q�N�̊Ԃɂ�������������A������悤�ȑ�^�͂ƂȂ����B������ŗL�����s��h�������Z�p�҂Ƃ��đ�s�ƒʏB�������ʌb���̐v�E���݂Ɍg������B�i����Ō��͓���̕������C��A���ʼnؖk�ɉ^�B����́A�~�G�ɂȂ�Ƒ�s�t�߂̉^�͂��������Ďg���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł������B�j |
| �ʌb��
| ���������B����Ɏ�s��s����ʏB�܂ŊJ�݂��ꂽ��^���̈ꕔ�B�P�Q�X�P�N�A�t�r���C���n���̖��߂ŁA�s��h�i�������̐���ł��m���銿�l�̋Z�p�ҁj���v���A���N���H�A�P�Q�X�R�N�Ɋ��������B�s��h�́A��s�̖k���̏�����������̐������琅�H���P�R���ɓ����A�����������̐ϐ��K�Ɉ������݁A���Ɍ������Ă����ɐ܂�A��̐��傩�狌�^�͂ɍ�������悤�ɂ����B���^�͂ɂ��P�S�̐����݂���ȂǁA�����ȑ��ʂƍH���ʼn^�͂������������B��Q���l�����A��X�P�����̑�H���ł������B���̉^�͂̊����ɂ���āA����܂ŒʏB�ʼnחg������Ă��������A�����̑D���́A��s�܂Œ��ʂł���悤�ɂȂ�A��s�̐ϐ��K�͑D�Ő��ʂ�������قǐ������o�������B�Ȃ��A�P�R���Ƃ́A���݂���a���̍����̑O�g�ł���B�����w���̑�s�@�}���R�E�|�[������̖k���x1984�@�����V���@p.64-65�� |
| �d�@�o�ς̔��W | �u�����S���鍑�̕����́A�L�^�C�鍑�i�Ɂj�ȗ��̗V�q�^�̐����ƒ�Z�^�̌o�ς̌����V�X�e���ł��������A�����S���̑吪���̌��ʂƂ��āA���[���V�A�嗤�̋��X�܂Ŏ����ƌ�ʂ̕ւ��悭�Ȃ�A���������̃V�X�e�����L�����y���āA���߂̏��n������Ԍo�ϊ���������܂łɂȂ������ɂȂ����B���̂̉ؖk�ł��łɐ������Ă����M�p����̌����Ǝ��{��`�o�ς̖G����A���̏�ɏ���ă����S�����E�S�̂ɍL����A���̊O���ɗאڂ��鐼���[���b�p�ɂ������e����^���邱�ƂɂȂ����B�n���C���E�ł́A�����S���鍑�̏o���Ɠ����̂P�R���I�ɁA���C�Ɠ��n���C�̖f�Ռ��������Ă������F�l�c�B�A�ɁA���[���b�p�ōŏ��̋�s���������Ă���B�v�����c�p�O�w���E�j�̒a���x1992
�����ܕ��ɔ� p.241���@ |
a�@����

���̌���
����͎����Q�S�N�i1287�N�j�ɔ��s���ꂽ2�т̐V�D�̓��ő�{�B�c28.3�����̑傫���������B�^�̕��Ɂu�U���҂͎��Y�ɏ����v�Ƃ���B
| �����̎����͖k�v�����q�Ɏn�܂�A��v����q�����s����A���Ō���ƌ�����悤�ɂȂ��Ĕ��W�������A�����S���鍑�͋���łڂ�����̂P�Q�R�U�N���A����̔��s���n�߂��B���̗̓y�������p���������̗̓��ɂ͓��R���Ȃ��������߁A���K�̌����ɕs���������߁A�ƌ����Ă���B�������K���s�����Ă����̂ŁA����s���A�ݕ��̑���Ƃ��Ă������A����ɗ����X���ƂȂ�A�o�ς����������Ă����̂ŁA�뗥�^�ނ̌���������A���┭�s�z�𐧌������B�����t�r���C���n���͂P�Q�U�O�N�ɑ��ʂ���Ɓu������v�i�����͌��̍ŏ��̔N���j�Ƃ�������ꎆ�������Ƃ��Ĕ��s���A���ׂĂ̎���A��l�ւ̕�Ȃǂ�����ōs�����ƂƂ����B�����̌���͉��u�n����ȂǁA�o�ς̔��W�ɑΉ����A�L�����ʂ����̂ŁA���K�̔��s���~�߁A����݂̗̂��ʂ�}�����B�������{��̚��ʐ����ɂ��o������債�A��������₪��������ĉ��l���������A���O�������ꂵ�߂�悤�ɂȂ��āA�����̖ŖS�𑁂߂��B
���E�ŏ��̕s�������̔��s�@�u���E�ŏ��̎����s�����̂������S���l�ł������B�����̃t�r���C���n�[���́A����ɂȂ����������f�Ղ̌��ς̕X�̂��߂ɁA�P�Q�V�T�N�A���E�ŏ��̕s�������s�����B���ꂪ�����̗B��̖@��ʉ݂ŁA�����̑��ɂ͋��݂���݂����݂��Ȃ������B���̃����S�������̐M�p�͍����A���ʂ͏����A���l�͈��肵�āA�C���t���[�V�����̒��x���債�����Ƃ͂Ȃ������B�����Ƃ��P�R�T�P�N�̍g�Ђ̗����N�����Ă���́A�����I�Ȉ����C���t���[�V�����ƂȂ�A�����̐M�p�͎��Ă����B�������璆����D���������́A�����ɕ���ĕs�������s�������A�����l�̖����̐M�p�̓����S���l�̌����ɉ����y���A���̎����͂܂��������ʂ����A�����̌o�ς͒������B�����̒����̌o�ς��D����悷��̂́A�P�U���I�̔��ɃX�y�C���l�������m�q�H�Ńt�B���s���ɓ������āA���L�V�R�Y�̋₪��ʂɒ����ɗ��ꂱ�݁A��n�������ςɎg����悤�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B�v�����c�p�O�w���E�j�̒a���x1992
�����ܕ��ɔ� p.241��
Epi.�@�}���R���|�[����������������̔��s�@�������[���b�p�ɂ͎����͂Ȃ���������A���Ŏ������g���Ă��邱�Ƃ��}���R���|�[�������������B�w���������^�x�ɂ��A���̎����̔��s�̗l�q���L�^����Ă���B����ɂ��ƌK�i�������̓R�E�]�j�̎�����ϋl�߂Ď�������A������������ْf���Ď��ʂɋ��z��������A�n���̎���悷�B�u��������Ă��̎������ł�������ƁA�J�[���͈�̎x����������ōς܂��A�����̑S�̈�E�S�����ɂ����ʍs�����߂�B���ʂ��m�Ȃ���Ύ��Y�ɂȂ�̂ŁA�����l�Ƃ��Ă��ꂪ��������ގ҂͂��Ȃ��B���ۂ̂Ƃ���A�ǂ̒n���ł��ǂ�Ȑl�ł��A���₵�����J�[���̐b������҂Ȃ炾��ł��A�������̎����ł̎x���������B�Ƃ����̂��A�ނ�͂ǂ��֍s�����Ƃ��̎����Ŗ����̎x�������ł���B�E�E�E�v���}���R���|�[���w���������^�x�P�@�������j��@���}�Г��m���Ɂ@p.244�`�� |
| b�@��y�n���L
| �@ |
| �e�@����̕���
| ����̕����̓����͎��̂悤�ȓ_�ɂ܂Ƃ߂���B
�i�P�j���������̔��W�@�v����ɉ萶�������������́A�����̗��s�╶�l��̕��y�Ȃǂɂ݂���悤�Ɍ���ő傢�ɔ��W�����B���ɓs�̑�s�̓s�s�����͓����𗬂̉e�����ĉ₩�������B
�i�Q�j�`�x�b�g�����̕ی��@�����͏@���ɑ��Ă͊��e�ŁA����ł��`�x�b�g�������M����A�����̑������s��ꂽ���A�����ŗL�������ł��S�^�������W���A�������F�߂��Ă����B�܂��]���A�X�^�[����i��������ɂ͕��������B
�i�R�j�����𗬂̐i�W�@���[�}���c�̎g�߂�A�x�l�`�A�̏��l�}���R�|�[���̗����A����ɃC�X���[�����k�̏��l��C�u�����o�b�g�D�[�^�̗����ȂǁA�����S���鍑�̃��[���V�A�x�z�̂��Ƃ������𗬂������������B |
| a�@���� | ���̕����̒��ł́A�v�̎�w�i��q�w�j�̂悤�ȁA�������̔��W�͂Ȃ������B�������A���Ȃ̗��s�̂悤�ȁA�V�������O�������萶�����̂����̎���ł���B�������w�j��̑�\�I�ȓ����Ƃ��āA����̕��́i�����w�j�A���̎��i�����j�ƕ���ŁA���̌������������Ă���B���ȂƂ́A�̕��E���ȁE���Z����̂ƂȂ�������|�p�ł���G���i�Y�ȁj�̑�{�̂��ƁB���̎���Ɉ�ʑ�O�̒�����n�܂�A�����\����B��̕��|�ƂȂ����B���ɑ�s�Ő���ɂȂ������̂��k���A�]��Ő���ɂȂ������̂�����Ƃ����B���̌コ��ɖ��A������ɔ��W���Ă����B��҂ƍ�i�Ƃ��Ă͊֊����́w�~���o�x�A�n�v���́w���{�H�x�A������́w�����L�x�A���m��́w��ˉJ�x�A�����́w���i�L�x�Ȃǂ��m���Ă���B����̒����ł͐��̖k���Ɏn�܂�Ƃ��������������ł��邪�A���Ȃ������ɉe����^���Ă���B |
| �w�����L�x | �������傤���B����̋Y�Ȃł��������̑�\�I��i�B������̍�B���N���ƛ�����̒j����l����l���Ƃ�����������ŁA�S���`�ʂɕx�݁A�܂�����̎Љ��m��j���ƂȂ��Ă���B |
| �w���i�L�x
| �т킫�B�����̒��ҋY�Ȃł��������̍�i�B�����i�����j�̍�B�`��I�ȓ�ȁi�]��Ő���ɂȂ������ȁj�̑�\�I�ȍ�i�B�㊿�̍���������ɂ��A����̒n��i�m��v�j�K����ᔻ�I�ɕ`���Ă���B |
| �����l��� | ���������l���̉�ƂƂ��Ċ����A�����]�A���ցA�� �i��������j�A�����̎l�l�B�����S���x�z���̌��̍]��n���̊������ł�����l�́A�ȋ��̎��i�������A�㋉�����ւ̓���������Ă����̂ŁA��l�̒m���l�w�͊G��̕���ō˔\��L�����B���l��͑v��ɋN����A���̌����l��Ƃ̎����ɁA�R����̉敗���m�����A���̖������@��i���j�ƌ�����悤�ɂȂ�B �i��������j�A�����̎l�l�B�����S���x�z���̌��̍]��n���̊������ł�����l�́A�ȋ��̎��i�������A�㋉�����ւ̓���������Ă����̂ŁA��l�̒m���l�w�͊G��̕���ō˔\��L�����B���l��͑v��ɋN����A���̌����l��Ƃ̎����ɁA�R����̉敗���m�����A���̖������@��i���j�ƌ�����悤�ɂȂ�B |
��� | ���傤�����ӁB�܂�����q�V�i���傤�������j�Ə̂��B���̕��l�B���ƊG��ɗD��A��v�̉@�̉�ɑ��ĕ��l��������A�����l����ւ̋��n���������B�܂����ł͉�㺔V�ȗ��̋M���I�Ȑ������p�������B�Ȃ��A������킩��悤�ɔނ͑v�̍c��ꑰ�ɑ����Ă������A�ٖ����̌����Ɏd���A�����ɂȂ����̂ŁA���ߑ��Ɣ���Ă���B�@ |
 |
| �E�D�����S������̃��[���V�A
|
| �`�@�����𗬂̊����� | �P�R�`�P�S���I�A���[���V�A�嗤�������S���鍑��������������́A�n���C���E�ł��\���R�^���̓W�J�̌㔼���ƁA���̌�̃C�^���A���l�𒆐S�Ƃ������Ƃ̕����̎���ł���A�܂��C���h�m�ł����X�������l�ɂ��C��f�Ղ��W�J����Ă����B�����S���鍑�̐����Ƃ���ɂ���Ă����炳�ꂽ�u�^�^�[���̕��a�v�́A���̂悤�ȍL�͈͂Ȑ��E���ƌ��̐�����w�i�ɂ��蓾���ƌ�����B���̂悤�Ȏ����ɁA�����̐l�I�A���I�Ȍ𗬁A����������Ε����I�A�o�ϓI�Ȍ𗬂������ƂȂ����B���̑�\�I�Ȑl���̓����Ƃ��Ă�������̂��A���[���b�p����A�W�A�ɂ���Ă����v���m���J���s�j�A���u���b�N�A�����e���R�����B�m��̃L���X�g���W�ҁA�������}���R���|�[����̏��l�A�t�ɃA�W�A���烈�[���b�p�ɕ��������b�o�����\�E�}�A�C�X���[�����k�Ƃ��ĎO�嗤�𗷍s�����C�������o�g�D�[�^��������邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��A�����L���X�g�����E�ɂ́A�������E�ɃL���X�g���̉������݂���Ƃ����v���X�^�[���W�����̓`��������A�\���R����ɃC�X���[�����͂̔w��̃L���X�g�����͂ƒ�g���邩�̐���T��Ƃ����������������B |
| �v���X�^�[���W�����̓`�� | �������[���b�p�̂P�Q���I�A�\���R���W�J���ꂽ����ɂ́A�������ꂽ�����̐��E�ɁA�L���X�g���k���Z��ł��āA���̎w���҂̃v���X�^�[���W�������A�\���R�������ăC�F���T�������C�X���[�����k����D�邽�߂ɂ���Ă���A�Ƃ����`�����L���M�����Ă����B�P�R���I�ɓˑR�A��������p�������������S���̐��������̋R�n�������A�v���X�^�[���W�����̌R���ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂������A�ނ�̓L���X�g���k�ł͂Ȃ��A���[���b�p�̒���j�A�l�X���E�C���ċA���Ă������B���[���b�p�l�̓����S���l���u�^���^���l�i�M���V�A��̒n�����Ӗ�����Tartarus���炫���Ƃ����j�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�����S���̐����҂��v���X�^�[���W�����ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ɂȂ������A���̌�����[�}���c�C���m�P���e�B�E�X�S����t�����X�����C�X���͌��̍c��Ƃ̒�g��͍����Ďg�҂�h�������B�܂��A��̑�q�C����̏����̃|���g�K�����G�����P�c���q���A�t���J���ݒT�����n�߂��̂��A�v���X�^�[���W�����̑��݂�T��ړI���������Ƃ����B
�`���̔w�i�@�A�W�A�ɃL���X�g���k�����݂���Ƃ����̂́A�����炭���Ĉْ[�Ƃ��Ēǂ����ꂽ�l�X�g���E�X�h�̂��Ƃł���A���̓_�ł͐��������A�v���X�^�[���W�����̑��݂͓`���ł���B���̂悤�ȓ`�������܂��w�i�Ƃ��āA�P�Q���I���J�����L�^�C�i���Ɂj�̑��݂��l������B�����k�����x�z���Ă����_�O�i�L�^�C���Ɂj���P�P�Q�T�N�ɋ��ɖłڂ��ꂽ�Ƃ��A���̉����̈ꕔ�����ɑ���A�P�P�R�R�N�ɒ����A�W�A�ɃJ�����L�^�C�i���Ɂj�����������B�J�����L�^�C�Ƃ́u�����L�^�C�v�̈Ӗ��ŁA�p��ł�Bblack
Cathay �Ƃ����A�������烈�[���b�p�̌���ɒ������Ӗ�����L���Z�C�Ƃ������t�����܂ꂽ�B�J�����L�^�C�����߂������A�W�A�i�����g���L�X�^���j�ɂ́A�C�X���[�����k�̑��ɁA�l�X�g���E�X�h�̃L���X�g���k�i�C�����n�����������j��]���A�X�^�[���k�A�����k�Ȃǂ����݂��Ă����B�P�P�S�Q�N�ɃJ�����L�^�C�̓C�����������Z���W���[�N���X���^���̃T���W�����Ƃ̊ԂŁA�T�}���J���h�x�O�̃J�g���[�������Ő킢�A���������߂��B���̃Z���W���[�N���̔s�k���`���Ƃ��Đ����ɓ`����ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����Ă���B���c�D���[�K���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@p.31�� |
| a�@�^�^�[���̕��a | �����S���鍑�����[���V�A�����̑唼���x�z�i�����{�y�̌���{�ƂƂ��āA�����A�W�A�̃`���K�^�C���n�����A���V�A�̃L�v�`���N���n�����A�C�����̃C�����n���������������S���n�̍��ƂƂ��Ă���ɏ]������̐����Ƃ����j���m�����A���ɂP�R�O�T�N���n�C�h�D�̗������肳��Č��̎x�z�����肵�����Ƃɂ���Ă����炳�ꂽ���a�����Ƃ������B���[�}�鍑�ɂ��n���C���E�ł́u�p�b�N�X�����}�[�i�v�i���[�}�̕��a�j�ɂȂ��炦�āAPAX TATARIKA �Ƃ����B�^�^�[���Ƃ����̂́A���Ƃ̓����S���n�̗V�q�����ł���^�^���l�i�����������j���w���Ă������A�P�R���I�Ƀ��V�A�E�����[���b�p�ɐN�U���������S���R�i�^�^���l���܂ރ����S���l��g���R�l�Ȃǂ��܂�ł����j�����[���b�p���Ń^�^�[���ƌ����悤�ɂȂ����B���́u�^�^�[���̕��a�v�̎����ɂ���āA���[���V�A�����������𗬂̊������������炳��A���l�T���X���q�C����A�Ђ��Ă͏@�����v�ɂȂ����Ă����B�@���@�^�^�[���̂��т� |
| �C���m�P���e�B�E�X�S��
| �P�R���I�̋��c���Ő��������[�}���c�̈�l�B�݈ʂP�Q�S�R�N�`�T�S�N�B���[�}�c���t���[�h���q�Q���i�V���^�E�t�F�����̍c��ŃV�`���A�̃p�����������_�ɃC�^���A�����i�߂悤�Ƃ��Ă����j�ƌ������Η����A�P�Q�S�T�N�̃���������c�Ńt���[�h���q�Q����j�債�A�c��p�ʂ����肵���B���̂��߁A�C�^���A�̓����o���f�B�A�s�s�����ȂNj��c���x���������c�h�i�Q���t�j�ƁA�c��ɂ�铝����x�������c��h�i�M�x�����j���������������ƂƂȂ����B���ǁA�t���[�h���q�Q���̎���A��C�^���A�̃V���^�E�t�F�������͂̓t�����X�̃A���W���[�Ƃɂ���Ēǂ��o����A���c�h�̗͓͂�C�^���A�ɋy�Ԃ悤�ɂȂ�B�܂������A�����S���R�̓����[���b�p�N�����L���X�g�����E�����|�Ɋׂ�A�P�Q�S�P�N�����[���V���^�b�g�̐킢�Ń|�[�����h�Ȃǂ̃L���X�g���R���s�ꂽ���Ƃ��āA�A�C�̔N�Ƀt�����`�F�X�R��C���m�v���m���J���s�j�������S���ɔh�����邱�Ƃɂ����B�J���s�j�̓J���R�����Ń����S���鍑�̃O���N���n���ɖʉ�A���c���ĕԏ����g���A�������B
Epi. �@�C���m�P���e�B�E�X�S���̖�]�@�u�C���m�P���e�B�E�X�S���́A��]������Ă����B��������ł́A���v�𐄐i�����B�O�����E�ɑ��ẮA�������ʂ̃l�X�g���E�X�h���͂��߂Ƃ��鏔���h��V�A���ʂ̐����������荞��ŁA�L���X�g����̑哝����߂������B�E�E�E�����S������ɂ́A���������L���Ӗ��ł́u��������v�ƁA����ɂ�鋳�c���͂̈�w�̊g��̎v�f����߂��Ă����̂ł���B�E�E�E�C���m�P���e�B�E�X�S���́A���������̏\���R����̏I�������鋐�l�ł������B�v�����R�����w�����S���鍑�̋��S�x��@�u�k�Ќ���V���@p.114�� |
| b �@�v���m���J���s�j
| �C�^���A�l���t�����`�F�X�R���C���m�ŁA�v���m���J���s�j�̃W���o���j�Ƃ����B�����S���R�������ɋ������P�N��̂P�Q�S�R�N�A���[�}���c�ɑI�o���ꂽ�C���m�P���e�B�E�X�S���́A�����S���鍑�ɂ��Ă̏��邽�߁A�g�߂�h�����邱�Ƃ����肵�A�v���m���J���s�j��h�������B�v���m���J���s�j�͂P�Q�S�U�N���J���R�����ɂ��ǂ蒅���A���肩�狓�s���ꂽ��R��n�����O���N���n���̑��ʎ��ɗ�Ȃ��A�O���N���n���̋��c�ւ̕ԏ������������ċA�������B����ɂ́u�������Ȃ鋳�c������A�����������̌��t�����Ȃ�A���ׂĂ̏����ƂƂ��ɓ��݂����痈����Ē��ɐb�]�𐾂��ׂ��E�E�E�E�_�̗͂ɂ��āA���̏���Ƃ�����A���̖v����Ƃ���܂ŁA���ׂĂ̓y�n��_�͒��Ɏ�����ꂽ��v�Ƃ������̂ł������B�ނ̎c�������́A�M�d�ȕ��Ƃ��ă��[���b�p�̐l�X�ɍL���m��ꂽ�B���c�D���[�K���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@p.199�@�y�ѓ����w�僂���S���Q�x�u���[���b�p�ɑ��郂���S���̏Ռ��v�@�m�g�j�@�p�쏑�X�� |
| c�@���u���b�N
| �P�Q�T�R�`�T�T�N�A�����S���ɕ������t�����V�X�R���C���m�i���u���N�̃M���[���j�B�t�����X�������C�X���̓C�X���[�����͂Ɍ����ď\���R��h������ɂ�����A���̔w��̃����S���鍑�Ƃ̒�g��}�낤�Ƃ����B���C�X���̓����S���c�邪�L���X�g���ɉ��@�����Ƃ����������ƂɁA�P�Q�S�X�N�����W�����[�̃A���h���[�Ƃ����鋳�t��h�������B�������A�A���h���[�������������͂��傤�ǃO���N���n�����������Č�p�����̍Œ��ŁA�ڌ������ې��̍c�@�I�O�����K�C�~�b�V���͍v���������Ă��Ȃ���Β�������Ƃ����ԓx�ł������B���̃��C�X���͂��̕��A�������g�̂P�Q�T�P�N�̏\���R�Ɏ��s���ăJ�C���ŕߗ��ƂȂ��Ă��܂��ȂǁA���ӂ̂����ɂ������̂ŁA�����S�����g�͂�����߂Ă����B�C���m���u���b�N�̐\���o�͎����I�Ȃ��̂ł����āA���C�X�����h���������̂ł͂Ȃ������B
���u���b�N�͐����Ȏg�߂̒n�ʂ�F�߂�ꂸ�A���̓`���҂Ƃ��Ă̗��ł������̂ŁA�v���m���J���s�j�ɔ�ׂč���ȗ��ł������B�ނ��J���R�����ɂ������đ�S��������P���n���ɖʉ���B�A����A���u���b�N���ڍׂȕ������C�X���ɒ�o�������A�v���m���J���s�j�̕��ƈ���ď��͖L�x�ł���A���m�������B���̗��s�L�ɂ��A���u���b�N�̓����P���n���̑O�ŁA�l�X�g���E�X�h�L���X�g���̋��m�Ə@���_�c�������Ƃ����B�������A�ꎄ�l�̋L�^�Ƃ��ꂽ���߂��A�قƂ�ǐ��ɒm���邱�Ƃ͂Ȃ������B���c�D���[�K���w�����S���鍑�̗��j�x1986�@�p��I���@p.202�@�y�ѓ����w�僂���S���Q�x�u���[���b�p�ɑ��郂���S���̏Ռ��v�@�m�g�j�@�p�쏑�X�� |
| d�@�}���R���|�[��
| �C�^���A�����F�l�e�B�A���܂�̏��l�B�P�Q�V�P�N�A�P�V�̎��A����f���ƈꏏ�ɓ����ւ̗��ɏo�����A���H���Ƃ�A�g���L�X�^���A�����ʂ��āA�P�Q�V�T�N�Ɍ��̓s��s�Ɏ������B���̐��c�t�r���C���n���Ɍ�������A�����ɎQ�������B�P�Q�X�Q�N�ɃC�����n�����ɉł������𑗂��Đ�B���o�q�A�C�H�}���b�J�C����ʂ��Ďg�����ʂ�������A�P�Q�X�T�N�Ƀ��F�l�e�B�A�ɋA�����B�}���R���|�[���̓��F�l�e�B�A�ɋA����A�f�Ղɏ]�����Ă������A�W�F�m���@�Ƃ̐푈���N����A���̎��ߗ��ƂȂ��ĕ߂炦���A�����ł��̌��������X�e�B�P���Ƃ����l���ɘb�������B���X�e�B�P�����L�q�����̂��w���������^�x�ł���B
Epi.�@�}���R���|�[���͖{���ɒ����֍s�����̂��@�}���R���|�[���͌��̓s�̑�s�ɕ����A�t�r���C�ɗp�����ėl�X�Ȃ��Ƃ��������A���̌����^���w���������^�x�ł���A���{�̊܂ރA�W�A�̏ڍׂȏ���߂ă��[���b�p�ɓ`����ꂽ���́A�ƈ�ʂɂ͐M�����Ă���B�������A�w���������^�x�̓}���R���|�[�����M�L�������̂ł͂Ȃ��A�������ł��d�˂�ɂ�}���R���|�[���ȊO�̓`�����������Ă������^��������B�܂��A���݂ł͊w�҂̈ꕔ�ɂ́A�������i���j�̎j���Ƀ}���R���|�[���̂��Ƃ���؏o�Ă��Ȃ����ƁA�P�V�N�������ɂ����͂��Ȃ̂ɁA�����̒����̕��ʂ̏K���A���Ƃ��u���v�̂��Ƃ�A�u�Z���v�̂��ƂȂǁA�܂��u�����̒���v�Ȃǂɂ��ӂ���Ă��Ȃ��Ƃ��������Ƃ𗝗R�ɁA�}���R���|�[�����͂����Ė{���ɒ����܂ōs�����̂��A�ƌ����^���悵�Ă���B�������ɂ������̋^��_�͂��邪�A�w���������^�x���P�R���I�̒����𒆐S�Ƃ���A�W�A�̏�`����M�d�Ȏ����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�͂Ȃ��B���t�����V�X���E�b�h�@����^�I�q��w�}���R�E�|�[���͖{���ɒ����֍s�����̂��H�x1995�@���v�Ё� |
| e�@�w���E�̋L�q�x�i�w���������^�x�j
| �}���R���|�[�����P�Q�V�P�N����P�Q�X�T�N�ɂ�����Q�T�N�Ԃ̓����ւ̑嗷�s���L�^���������B�A����W�F�m���@�̍����Ō��q�M�L����A���̎��㔭�\���ꂽ�B���̏ڍׂȋL�^�́A���[���b�p�ɏ��߂Ē����Ƃ��̎��ӂ̏����A�m�点�邱�ƂƂȂ����B���ɓ��{�̑��݂́A�W�p���O�Ƃ������ŏ��߂ă��[���b�p�ɓ`����ꂽ�B |
| ���b�o�����\�E�}
| ���b�o�����T�E�}�[�Ƃ��\�L����B�P�Q�W�V�N�A�C�����n�����̃A���O�������[���b�p�ɔh�������l�X�g���E�X�h�L���X�g���k�B�C�����n�����́A�C�X���[�����}�����[�N���ƑΗ����Ă����̂ŁA�L���X�g�����ƒ�g���邱�Ƃ��A�g�߂����[���b�p�e���ɔh�����邱�ƂƂȂ����B�g�߂ƂȂ������b�o�����\�E�}�͌��̑�s���܂���E�C�O���l�ŁA�l�X�g���E�X�h�̃L���X�g���k�ł������B�C�F���T��������Ɍ������r���A�C�����n�����̃n���̎g�߂ƂȂ��ă��[���b�p�Ɍ��������ƂƂȂ�A�R���X�^���e�B�m�[�v���A�i�|���A���[�}�A�W�F�m���@�A�K�X�R�[�j���A�p����K��A�ڍׂȋL�^���c�����B�ނ�������̂́A�r�U���c�c��A�t�����X���t�B���b�v�S���A�C�M���X���G�h���[�h�P���A���[�}���c�j�R���E�X�S���Ȃǂł������B���҂̓����͂Ȃ�Ȃ��������A�P�R���I�̓����̊W���z���ȏ�ɖ��ł��������Ƃ��������킹�邱�Ƃł���B�P�Q�X�S�N�ɑ�s�Ɏ����������e���R�����B�m�͂��̃��b�o�����\�E�}�̔h�����_�@�ƂȂ����Ƃ����B |
| f�@�����e���R�����B�m
| ��C�^���A�̃����e���R�����B�m�o�g�̃W���o���j�Ƃ����t�����V�X�R��C���m�B�����`�����u���C�����n�����ɓ���A�P�Q�W�X�N�A���b�o�����\�E�}���ă��[�}���c�j�R���E�X�S���ɖʉ�A���c���烂���S���c��ւ̎莆�������ē����Ɍ������A�C�����̃z�����Y����C�H�C���h�ɓn��A����ɂP�Q�X�S�N�A������s�ɓ��B�����B�Ȍ�A�L���X�g���̕z���ɂƂ߁A��s�̑���i���ɔC�����ꂽ�B����́A�����ɂ�����A�L���X�g�����g���b�N�̍ŏ��̖{�i�I�ȕz���̎n�܂�ł��������A�����l�̐M�҂͑����Ȃ������B�����e���R�����B�m�����̒n�ŖS���Ȃ�A�������|���ƁA���炭�L���X�g���z���͍s���Ȃ��Ȃ�A���͂P�U���I���C�G�Y�X���̃A�W�A�z����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �a�@���������̌� | �@ |
| a�@�s��h
| ���̃t�r���C���n���Ɏd�����Ȋw�ҁB��s�ɒʂ����^�����ʌb�����J�ʂ�����Ɛт��グ�A����ɓV����@�Œm����B�ނ́u�ȋV�v�u�V�v�u���\�v�Ȃǂ̓V�̊ϑ��@�����i���̎����͎c�O�Ȃ���c���Ă��Ȃ��j�A���z�̊p�x�𐳊m�Ɍv�����ĉĎ��E�~���̎������v�Z���A�P�N�̐��m�ȓ���������o���A��������ƂɂP�Q�W�O�N�Ɂu�������v�Ƃ����V������@��������B����Ɂu���R�v�Ƃ�����^�̋@�B���v���l�Ă����B�����w���̑�s�|�}���R���|�[������̖k���x���|���F��@�����V���@p.174�� |
| b�@������
| �����s��h���C�X���[�����Ɏh������āA�P�Q�W�O�N�ɍ������@�B�����ł͟u������ȗ��A�e���������肷�����A���i���ۂɂ����A���z���j�łP�N���R�U�T�D�Q�T���Ƃ��邳��Ă������A������ł͂P�N�͂R�U�T�D�Q�S�Q�T���ŁA�n���̌��]�����Ƃ̍��͂킸���ɂQ�U�b�ł������B���̐��m���͂��̖�R�O�O�N��̂P�T�W�Q�N�A���[�}���J�g���b�N����ŃO���S���E�X�P�R���̎��ɍl�Ă���A���ݒʗp���Ă����O���S���E�X���i���[���b�p�ł���܂ŗp�����Ă��������E�X���ɕς�萧�肳�ꂽ��@�j�ɓ������Ƃ������m�Ȃ��̂ł������B������͍���ɓ`�����A����̗�@�ɂ��e����^�����B����ɓ��{�ɂ��e����^���A�]�ˎ���̏a��t�C���P�U�W�T�N�ɍ�����u�勝���v��������Ɋ�Â��Ă���B
���̌�̒����̗�@�@�����ł́A���̖�������������ꕔ�C�����āA�P�R�U�W�N���哝�����̗p�����B�����ɂ����鐼�m��@�̎�e�́A�����̂P�U�Q�X�N�̃A�_�����V���[���Ə����[�ɂ��w������x�̍쐬����ł���A������������P�U�S�T�N�ɓK�p�����������Ƃ����B�O���S���E�X��i���z��j�ɐ�ւ��̂́A�h��v���̗��N�A���ؖ�����P�N�̂P�X�P�Q�N����ł���i���{�̑��z���ւ��͂P�W�V�R�N�j�B
�o���@������w�@�Q�O�O�V �@��Q��@��i�R�j�@�����ł͌Â�����A�V�̊ϑ��Ɋ�Â������Ă������A�x�z�҂̌��Ђ���������A���H�ȂǓV�����ۂ̗\���̐��m���������邽�߁A��@�����ς���Ă������B���`���̒����ɂ������@�̕ϑJ�ɂ��āA�S�s�i120���j�ȓ��Ő������Ȃ����B�@�i��j�@���@
(�R)���ł̓C�X���[����Ɏh�����ꂽ�s��h�������ȓV�̊ϑ����s���Ď�������쐬���A���̑哝��Ɏp���ꂽ�B�����ɂ͐鋳�t�A�_�����V���[���Ə����[�����m��@��������Đ�������쐬���A��������������ƂɎ�������{�s���A�h��v���Ō��s�̗�ɓ]�������B
|
| �~�j�A�`���[���i�ז���j
| �C�X���[�����Ō����鏑���̑}�G�Ȃǂɗp����ꂽ�ז��ő����I�ȊG���B�C�X���[�����ł��������q���������֎~����Ă����̂ŁA�ʎ��I�ȊG��⒤���͔��B�����A�A���r�A�����̏��̂�}�G�Ƃ��Ă̍ז���i�~�j�A�`���[���j�����B�����B�~�j�A�`���[���͂X���I����̃A�b�o�[�X���̋{��Ɏn�܂�A�C�����𒆐S�ɍ���Ă������A�P�R���I�ɃC�����𐪕������C�����n���������Ă������S���l���A�����G��̋Z�@���C�X���[�����E�ɓ`���A�Ǝ��̔��W������Ɏ������B���̌�A�~�j�A�`���[���́A�e�B���[�����ł��g���R���C�X���[�������Ƃ��ĊJ�Ԃ��A�S�������}���A��������K�����ł̓C���h�I�ȑ�ނ���������C���h���C�X���[�������Ƃ��Ĕ��W���A�{��ł����K���G���ɉe����^�����B |
| c �@�p�X�p����
| �����̋{��ŗp����ꂽ�����B�p�X�p�̓`�x�b�g�����̃T�L���h��T�����ŁA�����ł͔��v�b�Ə����A�p�N�p�Ƃ��\�L�B�t�r���C���n���Ɏd�����̍��t�ƂȂ��ĉe����^�����B�t�r���C���n���̓p�X�p�ɖ����āA�������̗l�X�Ȍ����\�L���邽�߂̕������쐬�������B���ꂪ�p�X�p�����ŁA�`�x�b�g���������ƂɂS�P�̂��ƂɂȂ镶�����߂����́B�p�X�p�����͖��O�ɂ͕��y�����A�{��̌��p�����Ɏg���A���̖ŖS��́A�`�x�b�g�����̈�͂ȂǂɎg���Ďc�����B |
| �p�X�p | �P�R���I���`�x�b�g�����w���ҁB�p�N�p�Ƃ��\�L����B�`�x�b�g�����̎�p�I�ȗv�f��r�����Ă��̏����ɓw�߂ăT�L���h���N�����A���̋���Ƃ��ă`�x�b�g�ŕ������O�Ɋ�Â��������s�����B���Ō����t�r���C�ɏ�����Ē����ɕ����A�����S���l�Ƀ`�x�b�g�������L�߂��B����Ƀt�r���C�̖��ɂ��`�x�b�g���������ƂɌ����Ŏg�p����镶����������B������p�X�p�����Ƃ����B |
 |
| �G�D�����S���鍑�̉��
|
| �`�@�����S���鍑�̉�� | �@ |
| a�@�e�B���[��
| �@����W�́@�R�߁@�e�B���[���鍑 |
| b�@���X�N�������
| �@����U�́@�Q�߁@���X�N������� |
| �a�@���̖ŖS | ���ł̓t�r���C���n���̎����i�P�Q�X�S�N�j�Ȍ�A���̑��̂U�㐬�@�i�e�����j���P�R�N����������}�����A�q���Ȃ������̂ł܂���ʌp���Ŗ�肪�N���A�V��ɂ͉��̃J�C�V�����i���@�j�����ʁA��������N�Ŏ����������ߌZ��̂W��A�����o�����_�i�m�@�j���p���A���͎q�̃V�f�B�o���i�p�@�j�ƂȂ����B�����̍c��ʂ̌p�����߂����čc���@�Ȃǂ̉���������Ύ��ԂG�ɂ��A�������₦�Ȃ������B�Ō�̍c�鏇�邪���ʂ���܂ł̂S�O�N�ԂɂX�l�̍c�邪��ւ��A���������͓����͐����s���𑝂��Ă������B���ɐm�@�E�p�@�̎���i�P�R�P�P�`�Q�R�N�j�͊������䓪���A�ȋ��̈ꎞ�I�����ȂǁA�������̓��������܂����A�`�x�b�g�������ߏ�ɕی삳�ꂽ�B�{��̚��ʐ����̂��߂����₪��������A�C���t���i�����㏸�j�������āA���O�����͋ꂵ���Ȃ��Ă����B
���̂悤�ȎЉ�s���̋��܂钆�A�P�R�T�P�N�����@���k�Ƃ����@���閧���Ђ��I�N���A���ꂪ�g�Ђ̗��Ƃ����S���I�Ȕ����ɂȂ������B�g�Ђ̗��̒����琶�܂ꂽ�錳���̐��͂́A�g�Ђ̗�����肵����A�P�R�U�W�N�싞�Ŗ����������A���N�A��R�ɂ���đ�s���U���A���̍c�鏇��i�g�S���e���[���j�͑�s��������k�サ������s�i�Ă̓s�j���ח����A���͖ŖS�����B�����S�������̖��R�͂���ɎR���A蟐����ʂ���������S���R����|���A�P�R�V�O�N�ɓ싞�ɊM�������B�����S�������Ɉ����������������S���l�́u�k���v���̂��đ������A���ɂƂ��Ă��Ȃǂ肪�������݂Ƃ��đ�������B |
| a �`�x�b�g����
| �@���@��R�́@�Q�߁@�`�x�b�g�����@ |
| b�@���� �i�̗����j | ���́A��v�𐧈��i�P�Q�V�U�N�j����ƁA�v�̔��s���Ă��������i��q�j�������i������j�Ɍ��������A�v�K�̗��ʂ��֎~�����{�ɉ�������B��v�̗̓y���ғ������ƁA���̌o�ϗ͂��p�����邽�߂́A����̑������s��ꂽ�B���̌�A�}���Ɏ����̗������i�̂ŁA���̉��l�͉������A�o�ς����������̂ŁA�P�Q�W�V�N�ɂ͐V�����̎�����s���A���i�̈����}�����B�������A���̌�������X���͎��܂炸�A�P�S���I�ɂ͂��̉��l�͖�R���̂P�ɉ��������B�����̍��A�������j�E���c���M�w�����S���Ƒ喾�鍑�x�u�k�Њw�p���ɔŁ@p.179�`182�� |
| c�@�g�Ђ̗�
| �@���@��W�́@�P�߁@�P�S���I�̓��A�W�A�@�g�Ђ̗� |
| d�@��
| �@���@��W�́@�P�߁@�P�S���I�̓��A�W�A�@�����̐��� |
 |

