| �p��f�[�^�x�[�X�@10_1 |
 �@ �@ |
| ��P�O�́@���[���b�p�匠���Ƒ̐��̓W�J |
| �P�D�d����`�ƌ[�ꐧ��` |
| �A�D�d����` |
| �P�D�P�V���I�̃��[���b�p |
| a�@�P�V���I�̊�@ |
�P�U���I�̃��[���b�p�́A�@�����v���n�܂鍬���̎���ł����������A����őO���I���ȗ��̑�q�C���オ�W�J���A�V�嗤����̋��E�₪��ʂɂ����炳��ď��H�Ƃ����W���A�o�Ϗ�̍D����w�i�ɐl�������������B���̂悤�ȃ��[���b�p�̔ɉh�́A�P�U�Q�O�N��ɋ}���Ɍ�ނ����B���̔w�i�ɂ́A�o�ϐ����̒���牺�~�A�V��s���ɂ�鋥��Ȃǂ�����A�l�������������B���̂悤�ȏ��u�P�V���I�̊�@�v�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B���[���b�p�e�������������O�\�N�푈�A�C�M���X���s���[���^���v���A�t�����X���t�����h�̗��A�X�y�C�����J�^���[�j���̔����A���V�A���X�e���J�����[�W���̔����A���[���b�p�S�y�Ɍ���ꂽ�u��������v�Ȃǂ́A���̊�@�̌���ƍl�����Ă���B |
| b�@�l���̒��
| �@ |
| c�@�O�\�N�푈
| �@���@��X�́@�S�߁@�I�D�P�V���I�̊�@�ƎO�\�N�푈�@�O�\�N�푈 |
| d�@�t�����h�̗�
| �@���@��X�́@�S�߁@�G�D�t�����X�̏@�������Ɛ�Ή����@�t�����h�̗� |
| e�@�s���[���^���v��
| �@���@�s���[���^���v�� |
| �X�e���J�����[�W���̔���
| �@���@��X�́@�S�߁@�J�D�����̐V���������@�X�e���J�����[�W�� |
| �J�^���[�j���̔��� | �J�^���[�j�����J�^���j�A�Ƃ��\�L����B�n���C�ɖʂ����t�����X�ƍ�����ڂ���n��ŁA���S�s�s���o���Z���i�B���݂̓X�y�C���̈ꕔ�����A���j�I�E�����I�ɓƎ��̕��݂������Ă���A�ŗL�̌���J�^���[�j��������B���Ƃ̓t�����N�����̕Ӌ������炨����A�s���l�[�R���̓�k�ɃJ�^���[�j���������`�����A�P�P�R�V�N�A�A���S���ƘA�������ƂȂ�B�P�T���I�ɃJ�X�e�B�[�����哱�̃X�y�C����������������Ƃ��̈ꕔ���\�����Ă������A�P�V���I�ɃJ�X�e�B�[�����̃X�y�C�����{���ɑ��I���o���X���O�\�N�푈�̌R��̊m�ۂ̂��߁A�J�^���[�j���Ȃǂɂ��ېłȂǂ̓��������߂�Ƃ���ɔ������A�P�U�S�O�N����T�Q�N�܂ŁA�J�^���[�j���̔_���������u���i���n�p�̑劙�������Đ�����̂Łu���n�l�푈�v�Ƃ����j�A�X�y�C�������h�������炵���B�����͒�������A�����ɉ�������t�����X�ɂ���ăs���l�[�Ȗk�̒n��D��ꂽ�B���c�V�k�w����J�^���[�j���̗��j�x�@2000�@�����V���@�Q�Ɓ�
���|���g�K���̓Ɨ��@���̔����Ɠ����ɁA�P�T�W�O�N�ȗ��A�X�y�C���ɕ�������Ă����|���g�K���ł��Ɨ��^�����N���A������̓u���K���T�Ƃ𒆐S�Ɍ��������|���g�K���l���A�P�U�S�O�N�ɓƗ��̉����������B�Ɨ��ĊJ��̃|���g�K���́A�C�M���X�Ƃ̒�g�����߂Ă����B |
| �������
�i�P�V���I�j | �u�P�V���I�̊�@�v�̌���ɁA�������̗��s����������B�������͂��Ƃ��ƃJ�g���b�N��������ɂ����āA�ْ[�������܂邽�߂������ٔ��Ƃ��čs���Ă������̂ł��������A�P�U���I�ɏ@�����v���n�܂�ƁA�V�����h�����ꂼ��G����@�h���Ƃ��č�������悤�ɂȂ�A����͂P�U�O�O�N�����Ő����ɁA�P�V���I�܂Ŏ������܂��B���l�T���X�̏I��鎞���܂ő������̂ł���A�܂��V���k��������ɖ��������s�����̂ł���B���ɃC�M���X�ł̓G���U�x�X�P����W�F�[���Y�Q���̎��A�u�������߁v�����т��яo����Ă���B�����̑��߂ɂ͓N�w�҃t�����V�X���x�[�R����Ȋw�҃E�B���A�����n�[�x�C�i���t�̏z�̔����ҁj�������ɂ�������炸�A�܂������̑��݂͐M�����A������Ă����킯�ł���B�Ō�̖����ٔ��́A�C���O�����h���P�V�P�V�N�A�X�R�b�g�����h���P�V�Q�Q�N�A�t�����X���P�V�S�T�N�A�h�C�c���P�V�V�T�N�A�X�y�C�����P�V�W�P�N�A�C�^���A���P�V�X�P�N�E�E�E�ł������B���X���P�Y�w�������x1970�@��g�V���@�ɂ�遄
Epi.�@�A�����J�ł̖������u�Z�[�����̖����v�����@�C�M���X�Ő������������́A���̐A���n�k�đ嗤�̃j���[�C���O�����h�ł��s��ꂽ�B�L���Ȏ������u�Z�[�����̖����v�����ł���B�P�U�X�Q�N�A�j���[�C���O�����h�̃Z�[�����Ƃ������̖q�t�̖������������̋^���őߕ߂��ꂽ�B�g���Ă������l�z�ꂩ�疧���Ƀu�[�h�D�[���̖��p��������ꂽ�Ƃ����̂��B���̖q�t�T���G�����p���X���������̐擪�ɗ����A�߂��̃{�X�g���Ȃǂň�Ăɖ�����肪�n�܂�A�e�^�҂͕ٖ��������ꂸ�ɗL�߂ƂȂ�A�Q�O�����i�E���ꂽ�B���������_�������ٔ��̕s������ᔻ����悤�ɂȂ�A���R�������ɋC�t�����B�ŏ��ɖ������Ƃ��ꂽ�̂͂����̃q�X�e���[���ɂ����Ȃ������̂��B�A�����J�ł͂��ꂪ�Ō�̖������ƂȂ����B���X���P�Y�w�������x1970�@��g�V��
p.185�� |
| �Q�D��Ή������Ƃ̌o�ϐ���@
|
| a�@�d����`
| �}�[�J���e���Y��(mercantilism)�B��ʓI�ɁA�P�U�`�P�W���I�̃��[���b�p����Ή������Ƃɂ݂���o�ϐ���т��̗��_�ŁA���Ƃ̕y�̌�����ݕ��̗ʂɂȂ�ƍl���A�ݕ��l�����o�ϐ���̎��Ƃ�����̂ŁA��Ή����̂��ƂŊ�����R���̋��^�A�{�쐶���̈ێ��Ȃǂ̍������K�v�ƂȂ����������A���Ƃ��d�����č��Ɠ����������A���邢�͓����I�ȏ��l��ی삷�邱�ƁB�}�j���t�@�N�`���A���Y�l���ɂ�鐶�Y�͂̌����O��Ƃ��A�܂���i�I�ȏ��H�Ƃ̔��B���݂���n��̍��Ƃ��A��i�n���A���n���o�ϓI�Ɏx�z����\�����B�܂��A�d����`�̌`�ԂƂ��āA����̊l������Ƃ����d����`�Ƃ����ŏ��̌`�Ԃ���A�A�o�傳���A����}���Ă��̍��z���f�Ս��z��`�Ɉڍs���A����ɍ����̎Y�Ƃ̕ی�琬�ɗ͂������Y�ƕی��`���Ƃ���B�܂��d����`�ɂ́A��Ή����i�K�̋{��i�����j�������I�ȑ古�l��ی삷��{��I�d����`�i�X�y�C����t�����X�̏d����`�j�ƁA�s���K���̐i�o�ɑΉ����Ď����̎Y�Ǝ��{�̕ی�琬�����Ɛ���Ƃ��鍑���I�d����`�i�C�M���X�̃E�H���|�[���̌o�ϐ���Ȃǁj�̈Ⴂ��������B�d����`�ɑ���ᔻ�͂P�W���I�̌㔼�A�t�����X���P�l�[���d�_��`��A�C�M���X�̃A�_�����X�~�X���w�������̕x�x�ɂ�鎩�R���C��`�̎咣�Ȃǂ�����Ă���B�P�X���I�̎��{��`�̑S�ʓW�J�̎����ɂȂ�ƁA�d����`�͎��R�ȋ����ɂ��o�ς̔��W��j�Q����Ƃ��Ĕے肳���悤�ɂȂ�A���R��`�f�ՂɈڍs����悤�ɂȂ�B |
| b�@������
| �r���[���N���V�[(bureaucracy)�B���������Љ�̋M�����̂��Ƃł̐��P�I�ȕ����Ɛb�c�ɑ��A���Ƃ̂��܂��܂ȋ@�\�̋Ɩ����e�l�̔\�͂őI�����ꂽ�������A�g�D�I�ɍs���V�X�e���B�����ł͌Ñ�E������ʂ��ĉȋ����ɂ�銯�������ێ����ꂽ���A���[���b�p�ł͎匠���Ƒ̐��i��Ή����j�̌`���ƂƂ��ɁA�v���������������̎�w���܂������Ƃ��Đ�Ή������x�����B�ߑ㍑�Ƃł͊��������}���ɔ��W���A�E�������̖��m���A���^�̌n�A�̗p�⏸���̐��x�A�����ɂ��Ɩ������Ȃǂ�����Ƃ��Ă���B���������������A���̑g�D���c��ɂȂ�ƁA�������x���鍑�ƍ������K�v�ƂȂ�A�Ő��E�R�����x�A����Ɋ����̈琬�̂��߂̋��琧�x�ȂǁA�ߑ㍑�Ƃ̂��܂��܂ȃV�X�e�����A�����Č`������Ă���B |
| c�@����R
| ���������Љ�i����ɌÑ㍑�Ƃ̉�̊��ł������ł��������j�ɂ�����R���͂̎�̂��b�����x�ł������B�b���͕K�v�ȂƂ��Ɍٗp�������̂ł����ď���R�ł͂Ȃ��������A�匠���Ƃ̌`���ƂƂ��ɗ̓y�R����W�J�������[���b�p�����́A����ɏ�Ɉ��̕��͂��ێ�����K�v�������A���̂��߂ɍ������璥�����邱�Ƃɂ���ĕ��͂�i�������j�V�X�e���������悤�ɂȂ����B���̂悤�ȏ���R�́u�����R�v�Ƃ�����Ή������Ƃ鏔���ǂ����̐푈�̎�͂ƂȂ�悤�ɂȂ����B����R�͐E�ƓI�R�l�ƁA�������璥������镺�m���琬��A�������ΖC�������͂����S�ƂȂ�B�����E�ƓI�R�l�ɂ͋��M���K�����Ȃ�ꍇ�����������i�h�C�c�ɂ����郆���J�[�K���Ȃǁj�B�Ȃ����S�Ȓ������ւ̈ڍs�́A�s���v����ɐi�s�����ƍl������B |
| �R�D���̏��`��
|
| a�@�d����`
| �d����`�̏����̌`�ԂƂ��Č����o�ϐ���ŁA����ݕ��̒~�ς��͂��邽�߁A�����̍z�R�̊J���ɓw�߂���A�C�O����̋���̊l���ɂƂ߁A�܂����̍��O���o��}���鐭��B�P�U���I�̃X�y�C���ɓT�^�I�Ɍ�����B |
| b�@�f�Ս��z��`
| �A�o��A����葽�����āi�o���j�A�f�Ս��z�ɂ���č��Ƃ̉ݕ������傳���悤�Ƃ���A�d����`�̔��W�����i�K�̌`�ԁB�A�o�������邽�߂ɂ͂��ꂼ������̂���A�o�Y�Ƃ�ی�琬����K�v���o�Ă��āA����ɎY�ƕی��`�Ɉڍs����B�܂��A���̗}���ɂ́A���Ő���i�ی�f�Ր���j���Ƃ���B�Y�Ɗv���O�̃C�M���X�̖ѐD���ƂȂǂɓT�^�I�Ɍ����A�t�����X�̐�Ή����̂��Ƃł��R���x�[���ɂ��d����`����͖f�Ս��z��`�ł������B�@ |
| c�@�Y�ƕی��`
| ���Ƃ������̎Y�Ǝ��{�̐������͂��邽�߁A���܂��܂ȕی��������o�ϐ���B��i�I�ȎY�Ɗv����W�J�������A�h�C�c����{�œT�^�I�Ɍ�����B�C�M���X�̃A�_�����X�~�X��J�[�h�Ɏn�܂鎩�R�f�Վ�`�ɑ��āA�h�C�c�̌o�ϊw�҃��X�g�i1789�`1846�j�́A�ی�Ő��̓����A���_�ی쐭��A�����S���Ԃ̐����ȂǎY�ƕی��`���咣�����B |
| �S�D�p���̏d����`
|
| a�@�R���x�[��
| �t�����X�E�u���{�������S���������C�P�S���̐�Ή������x�������������i�呠��b�j�B���V�����l�̑��q�ɂ����Ȃ��������}�U�����Ɏd���ē��p�������A���̎���A�P�U�U�Q�N�O�C�҃t�[�P������p�Ǝ��d�̍߂Ŏ��r������̍��������ƂȂ����B�R���x�[���͗A�o�����サ�č����Y�Ƃ�ی삷��A�T�^�I���d����`����𐄐i���A�u���{����Ή����̔ɉh�������炵���B��̓I�ɂ͏]���̖ѐD���E���D���E�O�~�E�S�u�����D�Ȃǂ̎Y�Ƃɉ����āA�K���X�E���[�X�E����Ȃǂ̎Y�Ƃ��N�����A�����H���ݗ������B����ł͘J���҂̓����ƃX�g���C�L�͋֎~���ꂽ�B�C���h�A�k�A�����J�A���āA�A�t���J�ȂǂɐA���n���l�������B�k�A�����J�ɂ̓~�V�V�b�s�여��ɍL������C�W�A�i�A���n���J�������i�~�V�V�b�s��͈ꎞ�R���x�[����Ƃ���ꂽ�j�B���Ăł̓A���e�B�[�������Ƀ^�o�R�A�ȁA���Ƃ����т͔̍|�����l�z��ɂ���čs�����B�܂��C���h�o�c�̂��߂����C���h������ݗ����ꂽ�B�R���x�[���͂��̂悤�ɓT�^�I�ȏd����`����𐄂��i�߂��̂ŁA���̌o�ϐ�����R���x�[����`�Ƃ������B |
| b�@���C���h����i�t�����X�j | �t�����X�����C���h����̓C�M���X�A�I�����_�ɑ����āA�P�U�O�S�N���A�����S���̒�����ɂ���Đݗ����ꂽ���A���ۂɃC���h�ւƂ̖f�Ղ͍s��ꂸ�A��Ђ͒�~��ԂƂȂ����B���ۂɊ������n�܂�̂́A�P�U�U�S�N�ɍ��������R���x�[�������C�P�S���̒�����čČ����Ă���ł���B�R���x�[�����d����`����𐄂��i�߁A���N�ɂ̓A�����J�嗤�Ƃ̌��Ղɂ��������C���h������ݗ������B�t�����X�̖{�i�I�ȃC���h�i�o�́A�P�U�U�V�N�A�t�����\�����J�������C���h���k���̃X���[�g�A�x���K���Ȃǂɏ��ق����݂��A�L�����R�i�ؖȁj�E�Ӟ��Ȃǂ�A�����Ă���ł���B���̌�A�|���f�B�V�F�����V�����f���i�S�������_�ɃI�����_�E�C�M���X�ƃC���h�f�Ղ����������B�������㔭�g�ł��������߁A�I�����_�E�C�M���X�̖W�Q���������A�����̏��Ǝ��{�̐������\���łȂ����㏬���債�����݂��Ȃ��������ߎ��{���W�܂炸�Ɍo�c���������A�P�V�X�U�N�ɉ��U�����B����c���w���C���h��Ёx�u�k�Ќ���V���@�Ȃǂɂ�遄
�@���@��X�́@�S�߁@���C���h����@�@�I�����_�����h����@�@�C�M���X�����h��� |
| c�@�����}�j���t�@�N�`���A
| �@ |
| d�@�s��
| �@ |
| e�@�A���n
| �@ |
 |
| �C�D�C�M���X�v��
|
| a�@�W�F���g��(���a)�@
| �@���@��U�́@�R�߁@�J�D�C�M���X�̏@�W�F���g�� |
| b�@�Ɨ����c�_���i���[�}���j
| �@���@��U�́@�R�߁@�G�D�����Љ�̐��ށ@���[�}�� |
| �`�@�W�F�[���Y�P��
| �X�`���A�[�g������̃C�M���X���i�݈ʂP�U�O�R�`�Q�T�N�j�B�X�R�b�g�����h���i�W�F�[���Y�U���j�̒n�ʂɂ��������A�����G���U�x�X��������p�҂Ȃ����������ہA��p�̃C�M���X���i�����ɂ̓C���O�����h���j�Ƃ��Č}����ꂽ�B���̕�̃X�R�b�g�����h�������A�����X�`���A�[�g�̑c�ꂪ�`���[�_�[���̃w�����V���̖��ł��������߁A�C�M���X���ʂ��p�����邱�ƂƂȂ����B����ɂ���āA�C���O�����h�ƃX�R�b�g�����h�͓��N�A���ƂȂ����B�W�F�[���Y�P���͎���w���R�Ȃ�N�卑�̐^�̖@�x�Ƃ���������ȂǁA���������_�������咣���A�R�����E���[�i�����Ƃ����ǂ��@�̎x�z�ɕ����ׂ��ł���Ƃ����v�z�j����������c��ƍŏ�����Η������B���̑��߂œN�w�҂Ƃ��Ė������t�����V�X���x�[�R���́A�c�����d�߂ō�������L�߂Ƃ���Ă���B�@������Ƃ��ẮA�C�M���X�������̗��ꂩ��J�g���b�N�A�v���e�X�^���g�i�C���O�����h�̃s���[���^���ƃX�R�b�g�����h�̒��V�h���v���X�r�e���A���j��������ے肵�A����I�ȉp����w�Ԓ���x���߂��B���̐����̉p��́A�ߑ�p��̐����ɑ傫�Ȍ_�@�ƂȂ����Ƃ���Ă���B�܂��A�W�F�[���Y�P���̎���ɁA�A�����J�嗤�̍ŏ��̍P��I�ȐA���n���@�[�W�j�A�����݁i�P�U�O�V�N�j����A�܂��ނ̍�������ɂ�锗�Q����s���[���^�����s���O�������t�@�[�U�[�Y���k�ĂɈڏZ�i�P�U�Q�O�N�j���āA�j���[�C���O�����h�̌��݂��n�܂����B
Epi.�@���A�����X�`���A�[�g�@�W�F�[���Y�P���̕�A���A�����X�`���A�[�g���g���ɕx���U�𑗂��������ł������B�X�R�b�g�����h���W�F�[���Y�T���̖��ł��������t�����X�{��ň�Ă��A�t�����\���Q���ƌ����A���̎���X�R�b�g�����h�ɖ߂艤�ʂ��p�������B�������s�s�Ղ��牤�ʂ�ǂ��A���q�̃W�F�[���Y������p�����B���A�����X�`���A�[�g�̓C�M���X�ɓ��ꂽ���A�J�g���b�N�h�̉A�d�ɉ��S�����Ƃ��ĕ߂炦���A�P�X�N�Ԋċւ��ꂽ��ŏ��Y���ꂽ�B |
| a�@�X�e���A�[�g��
| �C�M���X���e���[�_�[�����G���U�x�X�P���œr�₦����A�X�R�b�g�����h����}����ꂽ�X�e���A�[�g�Ɓi�P�R�V�P�N����X�R�b�g�����h���Ƃ��p���B���Ƃ��Ƃ̓X�R�b�g�����h���̍��������ł���X�e�����[�h�Ƃ����E������ł��B�j���W�F�[���Y�P������n�܂鉤���B�����`���[���Y�P�����s���[���^���v���ŏ��Y����Ă�������r�₦�邪�A���̎q�`���[���Y�Q���̎��ɉ������ÁA�W�F�[���Y�Q��������p���B���_�v���ł̓W�F�[���Y�Q���̖������A���Ƃ��̕v�̃I�����_���E�B���A���P�������������B�E�B���A���P���̎����Ƀ��A���̖����A�������ʂ��p�����A�P�V�O�V�N�C���O�����h�ƃX�R�b�g�����h����������B�A���������P�V�P�S�N�Ɍp�k�������������̂Ńh�C�c�̃n�m�[���@�[�I���W���[�W�P�����}�����A�n�m�[���@�[���ƂȂ�B |
| b�@�����_����
| �����̌��͂͐_����^����ꂽ�_���s�N�Ȃ��̂ł���A���R�͋�����Ȃ��Ƃ��鐭�����O�B�匠���Ƒ̐��̌`�����́A��������Ή������Ƃɂ����āA��������т���Ɉˑ�����M����E�҂ɂ���đ̐��ێ��̗��_�Ƃ��ēW�J���ꂽ�B�C�M���X�ł͍����W�F�[���Y�P�����g���w���R�Ȃ�N�卑�̐^�̖@�x���o�ł��Ă���A�܂��t�B���}�[�̓`���[���Y�P���Ɏd���A�����������Ől�ނ̑c�Ƃ����A�_���ɗR������ƕ������ł���Ƙ_�����B�t�����X�ł̓��O�m�[�푈�����W�������{�[�_���́w���Ƙ_�x�ō��������@�������匠�҂ł���ƈʒu�Â���u��Ή����v�𗝘_�Â����B�܂��u���͍��ƂȂ�v�ƒ[�I�Ɍ����\�������C�P�S���Ɏd�����{�V���G�͐_�w��̗��O�Ƃ��ĉ����_������������B�����Љ��匠���Ƃ̏o���̍ۂɂ͗L���ȃC�f�I���M�[�ł��������A�s���K�����䓪����Ǝ��R�ƕ�����}�����闝�O�Ƃ��Ĕے肳��A�P�W���I�㔼�ɂ��[�֎v�z�̒��ŁA�Љ�_��������b�N��\�[�ɂ���ď������A�ߑ�I�Ȍ��͂��x���闝�O�Ƃ����悤�ɂȂ�B |
| �t�B���}�[
| �P�V���I�O���̃C�M���X�̐����v�z�ƁB�`���[���Y�P���Ɏd���A���̒��w�ƕ������_�x(1680�N)�Ȃǂ������_������W�J���A�����������Ől�ނ̑c�Ƃ����A�_���ɗR������ƕ������ł���Ƙ_�����B���b�N�́w������_�x�́A�t�B���}�[�̉����_������ᔻ���Ă���B |
| c�@�c��
| �@���@��U�́@�R�߁@�C�M���X�c��x�̒蒅 |
| d�@������
| �@���@��X�́@�R�߁@�C�M���X������ |
| e�@�s���[���^��
| �@���@��X�́@�R�߁@�s���[���^�� |
| �a�@�`���[���Y�P��
| �C�M���X�E�X�e���A�[�g���̍����i�݈ʂP�U�Q�T�`�S�X�N�j�B���W�F�[���Y�P���̉����_�������p���A�܂��M����������̓��������߁A�s���[���^�������т����e�����A�W�F���g���̑����c��ƑΗ������B�X�y�C���E�t�����X�Ƃ̐푈�i�O�\�N�푈�j�̐��邽�߁A�V���ȉېł��s�����Ƃ������A�c��͂���ɔ����ĂP�U�Q�W�N�A�����̐������`���[���Y�P���ɒ�o�����B�ނ͗��N�c����J�Â������A����Ȍ�͂P�P�N�ɂ킽���ĊJ�Â��Ȃ������B�X�R�b�g�����h�̔�����������邽�߂̉ېł̕K�v�ɔ�����ƁA�P�U�S�O�N�Z���c������W�A�Ăыc��ƌ������Η��ƂȂ�A���}�h�Ƌc��h�̓������P�U�S�Q�N����u������B�P�X�S�T�N�ɂ��l�[�X�r�[�̐킢�ŁA�N�����E�F���̎w������c��R�ɔs��A�S�V�N�ɕ߂炦���A�P�U�S�X�N�P�������Y���ꂽ�B |
| a�@�����̐���
| �P�U�Q�W�N�A�C�M���X�c������ɑ��A�s���ȉېł�l�g��s���ɍS�����邱�ƂȂǂ̋֎~�𐿊肵�A���F�����������B�s���[���^���v���������炵�A�C�M���X�ߑ㍑�Ƃ̏d�v�Ȗ@�T�ƂȂ����BPetition of Right�@
�P�U�Q�W�N�A�`���[���Y�P�����X�y�C���E�t�����X�Ƃ̐푈�Ő�������������~�����߁A�l������@���ɂ��Ȃ��ŋ����I�ɋ��K���W�߂悤�Ƃ��A����ɂ���ɔ�����҂𗝗R���������ߕ߂���A�Ƃ����[�u�ɏo���B�傢�ɕs�����������c��A���ɉ��@�́A�P�U�Q�V�N�t�����X�̃��|���V�F���t�߂̃����Ń`���[���Y�P���R���s�ꂽ�̂��@�ɁA�����̐���ɔ��̌��c���������A��@�������A�������F�߂Ȃ����Ƃ����炩�Ȃ̂œP�A���炽�߂āA�G�h���[�h���R�[�N�̒�ĂŁA�������@���������Ƃ��l���~�ς����߂��i�ł���u����v�Ƃ����`�����Ƃ邱�Ƃɂ��A���@�ō̌����ꂽ�B�U���Q���ɍ����ɒ�o����A�V���ɍ����������ۂB�����ɂ́A�u�{����ɏ��W���ꂽ�m���̋M������я����ɂ��A�����É��ɕ��悳��A����ɑ��ĕÉ�������S�̂ɒ���������������v�S�P�P�́B�}�O�i�|�J���^�Ȃǂ̉ߋ��̖@���ł̍����̕s���ȉېł̋֎~�A�s���Ȑl�g�S���̋֎~�Ȃǂ��m�F���A�扤�W�F�[���X�P���̉߂���A���̂����ō��̋����A���ӓI�ȉېŁA�s�@�ȓ����A�R�@�ٔ��̗��p���ɔ������B�}�O�i�|�J���^�E�����͓̏T�ƂƂ��ɃC�M���X�̂R��@�T�Ƃ�����B�����ł̓C�M���X�����̌������P�R���I�ȗ��̗��j�I�����ł���R�����|���E�̐��_����ʂ���Ă���B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.73
�� �@ |
| ���u�����̐���v�̓��e
| �v�_�́A�u�c��̏��F�Ȃ��ɉېł��Ȃ����ƁE������@���ɂ�炸�ߕ߂��Ȃ������v�ȂǁB�@
�������@�����̐����@��P�O�́i�܂Ƃ߂̏́j�u���������āA����ɏ��W���ꂽ�m���̋M������я����́A�ނ�Ŏ����Ȃ�É��Ɏ��̂��Ƃ𐿊肵���Ă܂�B���Ȃ킿�A���㉽�l���A�����@�ɂ���ʓI���ӂȂ��ɂ́A�����Ȃ鑡�^�A�ݗ^�A��[���A�ŋ��A���̑�����̕��S���Ȃ��A�܂��͂���ɉ�����悤��������Ȃ����ƁB���l���A���̂��ƂɊւ��A�܂��͂�������ۂ������ƂɊւ��āA���فA�鐾�A�������͏o�������߂��邱�ƁA�S������邱�ƁA���̑����낢��ȕ��@�ŁA��ɂ��������A�S�̕��Â�D���邱�ƁA�͂Ȃ����ƁB���R�l�́A�O�L�̂悤�ȁi���R���������ɑ���߂����j���Ƃɂ���čS�ւ܂��͍S������Ȃ����ƁB�É��������������O�L�i��U�́j���C�R���m�𗧑ނ������܂��A�É��̐l������������ɂ���Ă킸��킳��邱�Ƃ̂��Ȃ����ƁB�R�@�ɂ��ٔ��i�𖽂���j�O�L�i��V�́j�̂悤�Ȏ����P��邱�ƁB���㓯�l�̐������������A�O�L�̂悤�Ɏ��s����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ĕ�������邱�Ƃ́|���ꂪ�����Ȃ�l�ɑ��Ăł���ɂ���|�Ȃ����ƁB�Ƃ����̂́A����������ɁA�É��̐b�����A���̖@������ѓ����ɔ����āA��Q��������ꂽ��A���ɂ����炵�߂�ꂽ�肵�Ȃ����߂ł���B���w�l���錾�W�x��g����P.60��
|
| c�@�X�R�b�g�����h�̓���
| �X�R�b�g�����h�ɂ͒��V�h�i�v���X���B�e���A���j�Ƃ����J�����@���h�̈�h�̃v���e�X�^���g�������A�C�M���X������̐M�����������`���[���Y�P���ɑ��������Ă����B���ɃX�R�b�g�����h����͎i�����x��F�߂��A��ʐM�҂̂Ȃ����璷�V��I��Ŏw���҂Ƃ��钷�V���x���Ƃ��Ă����B�P�U�R�V�N�A�`���[���Y�P���̓X�R�b�g�����h�̒��V�h����ɑ��A������̋F���������悤���������B����ɑ��ăX�R�b�g�����h�̒��V�h�͖�������сA�C�M���X������ƑΌ����ׂ����͂��W�ߎn�߂��B |
| ��d�@���V�h�i�v���X�r�e���A���j�@
| �@���@��X�́@�R�߁@�v���X�r�e���A�� |
| �b�@�C�M���X�v��
| �C�M���X�̃X�e���A�[�g���̐�Ή�����|���A�����N�吭�������������ϊv�B��ʂɁA�P�U�S�Q�N������s���[���^���v���ƁA�P�U�W�W�N�����_�v���Ƃ̂��āA�C�M���X�v���Ƃ����Ă���B
�`���[�_�[���������������ɂ�鋳��܂��͐M�̓����ɑ���A�X�R�b�g�����h�̃v���X�r�e���A���i���V�h�j�A�C���O�����h���s���[���^���i�����k�j���M�̎��R�����߂�킢���N���������ƂɎn�܂�A���}�h�Ƌc��h�̓���ƂȂ����B���������N�����E�F���̎w���̂��Ƃō����`���[���Y�P�������Y�����Ƃ������Ԃ܂œ˂��i�݁A���a�������������B���ꂪ�s���[���^���v���ł���B�N�����E�F���̓ƍ��́A���̃J�����@���h�I�Ȍ��i�Ȑ����������̎x����S�����A���̔���������ăN�����E�F��������������������B�������Ì�A�Ăщ��Ƌc��͑Η����A���Njc��͍�����Ǖ����A�I�����_���獑�����}���������͓T�����z���āA���������������������B���ꂪ���_�v���ł���B����ŁA�y�n�ϕ������߂�_���̉^���͒e������A�A�C�������h�E�X�R�b�g�����h�̓C���O�����h�̐A���n�I�x�z����悤�ɂȂ�ȂǁA�Ѝ����c�����B
�C�M���X�v���̔w�i�ɂ́A�}�j���t�@�N�`���A���Y�̔��W�ɔ����W�F���g���i�n��j�����[�}���i�Ɨ����c�_���j�̐���������A�����̋M���K���͖v���������A�s�s�̎s���w�̐����͂܂��\���ł͂Ȃ��A�����I�����̔p�~�Ȃǂ��O�ꂵ�Ă��Ȃ������̂ŁA�u�s���v���v�Ƃ��Ă͕s�\���Ȃ��̂ł���i�s���v���̍����Q�Ɓj���A���̂P�W���I�̃C�M���X�Y�Ɗv���̑O��Ƃ��Đ�Ή������|���ꂽ���Ƃ͏d�v�ł���B
�܂��A�C�M���X�v���ł́A�J�g���b�N�i�����j�E�C�M���X������E�s���[���^���i�����k�j�E�v���X�r�e���A���i���V�h�j�Ƃ����L���X�g�����@���e�h�̑Η����d�v�Ȏ��ł������B�����悻��F��������ƁA�����c��̒i�K�ł͍����i�W�F�[���Y�P���E�`���[���Y�P���j�͍�����A�c���͂͒��V�h�A�v���𐄐i�����N�����E�F����̓s���[���^���B�������Ê��ł͍����i�`���[���Y�Q���E�W�F�[���Y�Q���j�̓J�g���b�N�A���_�v���𐄐i�����c��͍�������S�A�Ɛ����ł���B |
| a�@�Z���c��
| �X�R�b�g�����h�Ƃ̍Đ�����ӂ����`���[���Y�P���́A���S�̃A�C�������h���㗝�E�F���g���[�X�i�X�g���t�H�[�h���j�̐i�������ċc����J�����ӂ����A�P�U�R�X�N12���A�c��W�������A�S�O�N�R�����I���A�S��13���c����J�Â����B�P�U�Q�X�N�A������������ċc������U���Ă���A�P�P�N�ڂł������B�c��ł͂܂������̗Վ��ېł̏��F���c��Ƃ��ꂽ���W�������s�����`���[���Y�P���̕��S�J���^�x���[��i�����[�h�̃J�g���b�N���̎p����s���ȉېŁA�����̖��c����Ȃǂ���A���|�I�Ȏx�������̂ŁA�`���[���Y�͂T���T�����U������B�������Ă킸���R�T�Ԃʼn��U������ꂽ�̂ŒZ���c��Ƃ����B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xp.89�� |
| b�@�����c��
| �P�U�S�O�N10�����I�����{�B�c���ɑI��邱�Ƃ̓G���U�x�X�̂���܂ł͖��_�ł�����͕��S�ƍl�����Ă����̂ŁA����܂ł͖������őI��邱�Ƃ������������A���̑I���ł͂��ĂȂ�����ƂȂ����B��@�͂P�O�O�����炸�̋M���Ǝ勳�ȏ�̑m�E�őI���Ƃ͖��W�B���@�͑I����Q�T�X�i�B�E�����s�E��w�j�Œ���S�X�R���B�S�P�N�܂łɒlj����ꂽ������v�T�S�V�̋c���̏o�g�K�w������W�F���g���R�R�R���A�@���ƂV�S���A���H�Ǝ҂T�T���A�����Q�V���A��b�Q�Q���ȂǁB�I�����͔N���S�O�V�����O�ȏ�̎��R�y�n���L�҂ƈ��̎s���ł�[�߂�s�s�̎��R���B�P�U�T�R�N�A�N�����E�F���ɂ���ĉ��U�����܂ŁA�P�R�N���������̂Œ����c��Ƃ���ꂽ�B�S�P�N�ɂ͂����Ɖ����𐧌����闧�@�𐬗������A�S�P�N�P�P���ɂ̓N�����E�F����̒�Ăō����ɑ�����R�c�����̑�����A�c����h�ƍ����̑Η��͌���I�ƂȂ�A�s���[���^���v���ɓ˓����邱�ƂƂȂ����B
�������c��ɂ�����A�����𐧌����闧�@
�@41�N�Q���@�O�N�c��@�F�����̏��W�������Ƃ����Ȃ��Ƃ��O�N�Ɉ��͋c����J�Â��邱�Ɓi���c����̍Č����ӂ����j
�@41�N�T���@���U���Ζ@�F�����̈���I�ȉ��U��j�~���邽�߁A�c��g�̌���ɂ��Ȃ���c������U�����Ȃ��Ƃ���
�@41�N�U���@�g���ŁA�|���h�Ŗ@�F�c��̓��Ӗ����ɗA�o���ł��ۂ����Ƃ͂ł��Ȃ�
�@41�N�V���@�������ٔ����E�����@���ٔ�����p�~ �Ȃǁ��l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�x p.92-95�� |
| ����R�c�� | �P�U�S�P�N�P�P���A�C�M���X�����c��Ō��c���ꂽ�����`���[���Y�Q���ɑ���R�c���B���|�`�i���j���Ƃ������B���ٌ̍����߂���c��͋c��h�Ɖ��}�h�ɕ��A�s���[���^���v���̓����ɓ˓������B�c�Ă̓W�������s���A�N�����E�F����ɂ���Č��Ă��쐬����A�����̎�d�҂Ƃ��ăJ�g���b�N���k�A�勳�Ƒ������m���A���s�����d�b���b�������A�ނ�̈����̓��e���A
�@1.�����ƍ����̊Ԃ̕s�M�Ƒ����̑���
�@2.�����ȏ@���̗}��
�@3.�J�g���b�N�E�A���~�j�E�X��`�ҁE�ْ[�҂̈琬
�@4.�c��ɂ�炴�鍑�������̊m��
�̂S�_�ɂ܂Ƃ߁A���łQ�O�S���ɂ킽���Ĉ����̋�̗�ƒ����c��̐��ʂ���Ă���B11���X������R�c���n�܂�A������ɑ�����A��@�����Ē��ڍ����ɑi���邱�Ƃ̉ۂ��߂����ĕ����A�^���P�T�X�[�A���P�S�W�[�̂P�P�[���ʼn����ꂽ�B���l�сw�C�M���X�s���v���j�xp.107-108�� |
| �C�M���X�̏@���e�h | �C�M���X�v���̗����ł́A�@���I�ȑΗ������ǂ̂悤�ł���������}���邱�Ƃ��K�v�ł���B�C�M���X�@�����v�̌��ʁA�C�M���X�������ɂ��@���������m���������A�Ȃ����@���Η��͑����Ă����B�܂��A�傫�ȑΗ����Ƃ��ăJ�g���b�N����ƐV���e�h�i�v���e�X�^���g�j�̑Η�������B����Ƀv���e�X�^���g�̒��ɂ�������i�A���O���J�����`���[�`�j�Ƃ���ȊO�����k�i�m���R���t�H�[�~�X�g�@Noncomformists �j�̈Ⴂ������B���k�͂���ɓƗ��h�i�����k�A�s���[���^���j�E���V�h�i�v���X�r�e���A���j�̓�h������A�Η����Ă����B�ȏ�̃C�M���X�̃L���X�g���S�h�̈Ⴂ�͂��悻�A���̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B
�i�P�j�J�g���b�N�F�C�M���X�@���v���ō�����������Ă�����A���A���P���̂悤�ɃJ�g���b�N���̂ĂȂ������������i�J�g���b�N�����j�B�G���U�x�X�P���ƃ`���[�_�[���̃W�F�[���Y�P���E�`���[���Y�P���͍�����̗�����Ƃ�A�J�g���b�N�E���k�̂���������e�������B�J�g���b�N�͍ʼnE���i�ێ�I�j�̐��͂ŁA�ێ�I�ȋM����古�l�ɑ����A�n��I�ɂ��A�C�������h�̓J�g���b�N�������B�܂��������Âō����ƂȂ����`���[���Y�Q���̓t�����X�Ƃ̊W���[���i���C14���Ƃ��h�[���@�[�̖����Ȃǁj�A���̒�̃W�F�[���Y�Q���ƂƂ��ɃC�M���X�ɃJ�g���b�N�������悤�Ƃ��A�c��ƑΗ������B�P�U�V�R�N�ɋc��Ő��������R���@�ɂ���ăJ�g���b�N�M�҂̓C�M���X�̌��E����Ǖ�����A�@���I���ʂ������A�悤�₭�P�W�Q�W�N�̐R���@�p�~�A���N�̃J�g���b�N���k����@�ŐM�̎��R������B
�i�Q�j������i�A���O���J���`���[�`�j�F�w�����W���Ɏn�܂�A�������ƂȂ��Ă���C�M���X�̍��ƓI�ȋ���g�D�B������͔��J�g���b�N�ŁA�傫��������ΐV���i�v���e�X�^���g�j�ɂ͂��邪�A�s���[���^���ƈႢ�A����ł��勳���x�i�J�g���b�N�ł̎i�����x�A�K�w�I�Ȑ��E�ґg�D�ɂ�����j��F�߁A�V�����J�g���b�N�I�Ȗʂ������c���Ă����B�C�M���X��ʍ����̑����h�͍�����̐M�ҁ������k�ƍl���Ă悢�B�W�F�[���Y�P���A�`���[���Y�P���͍�����̗���ɗ����A��Ή������������悤�Ƃ����B�s���[���^���v���Ŕ��k�̓Ɨ��h�N�����E�F�������͂��������̂ŁA������͈ꎞ�}����ꂽ���A�N�����E�F���̓ƍق��|��Ă���͍�����@���I�Ȏw�������������B�������Ê��̃`���[���Y�Q���E�W�F�[���Y�Q���̃J�g���b�N������ɂ������������A�P�U�V�R�N�ɋc����R���@�𐧒肵�A�J�g���b�N���k����є��k�̌��E�ɂ����Ƃ��֎~�����B����ɖ��_�v���ɂ���ăC�M���X�ł͍�����̏@���I�x�z���m������B
�i�R�j�s���[���^���i�����k�j���Ɨ��h�F���k�̈�ŁA�C���O�����h�ł̃J�����@���h�̗�������ސV���k�B������̎勳���x�ƒ��V�h�i�v���X���B�e���A���j�̒��V�̊Ǘ�����������ے肵�A����͓����̐M�҂̏W�܂�Ɨ��������̂ł���ׂ��ł���Ǝ咣�����̂��Ɨ��h�Ƃ������B�C���O�����h���W�F���g�������[�}���i�Ɨ����c�_���j�ɑ��������B�W�F�[���Y�P���̎���ɂ͍�����̗���ɗ���������e������A���̈ꕔ���s���O�������t�@�[�U�[�Y�Ƃ��ăA�����J�ڏZ�����B�s���[���^���v���ł̓N�����E�F���̎w������Ɨ��h�����͂����������A�������Ì�͐����Ă������B
�i�S�j�v���X���B�e���A���i���V�h�j�F���k�̈�ŁA�s���[���^���Ɠ������������J�����@���h�̗�������݁A�X�R�b�g�����h�Ŕ��W�����B�ނ�����V���x�i���E�҂ł���i���ł͂Ȃ��A�o���̖L���ȐM�҂�����̎w���҂Ƃ��鐧�x�j�ɂ�鋳��g�D�̉^�c���咣�����_���قȂ�B�X�R�b�g�����h�̒��V�h����W�F�[���Y�P����`���[���Y�P���ɂ�鍑����̋����ɔ������Ĕ������N�����A�C�M���X�v���̏o���_�ƂȂ����B�v�����i�s���钆�ŁA�C���O�����h�ł͒��V�h�͉����Ƃ̑Ë����͂��鉸���ȗ��������̎咣��W�J�������߁A�N�����E�F���̓Ɨ��h�ɂ���ċc���ꎞ�r�����ꂽ���A���̎���ɐ��͂�Ԃ��A�������Â���������B�������`���[���Y�Q���A�W�F�[���Y�Q�����J�g���b�N��������ƍĂђe������A�A�C�������h�ȂǂɈڏZ����҂����������B
�����̑��̔��k�@�C�M���X�̃v���e�X�^���g�͂��̌������𑱂��A�o�v�e�B�X�g�A�N�G�[�J�[�A���\�f�B�X�g�A���j�e���A���Ȃǂ̋��h���������܂�Ă���B |
| �c�@�s���[���^���v��
| �P�U�S�Q�N����S�X�N�Ɏ���A�C�M���X�̃X�e���A�[�g����Ή�����|�����v���������B�v���̎�̂ƂȂ����c��h���W�F���g����[�}�����s���[���^�������������̂ŁA�s���[���^���v���i�����k�v���j�Ƃ����B���̊v���ɂ���č����`���[���Y�P���͏��Y����A���a�������������B�������A�w�����N�����E�F�����g���ƍِ������s���悤�ɂȂ��Ė��S������A���̎���͉������ÂƂȂ�B���̖��_�v���ƂƂ��ɁA�C�M���X�v���ƈꕔ���\������B |
| a�@�c��h
| �����`���[���Y�P���̐�Ή����A��������ɔ������A�s���[���^���v���̒��S�ƂȂ������́B�ʖ����~���}�Ƃ����B�V�����͂ł����W�F���g���𒆊j�Ƃ��A�i���I�ȋM���ƃ��[�}���i�Ɨ����c�_���j�A��H�Ǝ҂��x�����͂ł������B�܂��M�̏�ł��s���[���^�������������B�܂��n��I�ɂ͏��H�Ƃ̔��B���������h���𒆐S�ɃC���O�����h�̓��암�ɂ���ՂƂ��Ă����B�������A�s���[���^���ł����N�����E�F���𒆐S�Ƃ��ċ��a���̎�������������}�i�I�ȓƗ��h���䓪����ƁA�c��h���̉����h�͉����ȗ����N�吭���u�����钷�V�h������A����ɂ��̗��҂͑Η�����悤�ɂȂ����B |
| b�@���}�h
| �@���@���}�h |
| c�@�Ɨ��h
| �J�����@���h�̗���������s���[���^������Ȃ�A���V�h�̂悤�ȁA���V�ɂ�鋳��̓����ɔ����A�e����̓Ɨ��d����l���������Ă����B�Ɨ��h���x�������̂͒����x���W�F���g���ƃ��[�}���i���R�_���j�A����ɓs�s�̏��H�Ǝ҂����ł������B�c����ł͏����h�ł��������A���̔h���N�����E�F�����V�^�R��g�D���A�R���͂������Ă����B |
| d�@���V�h
| �s���[���^���Ɠ����A�J�����@���h�̗���������v���X�r�e���A���̂��ƂŁA�C�M���X�v���̎����ɂ͋c��h�̒������V��`�i���V���x�j�ɂ�鋳��̓���i�܂荑����̋����ɂ͔�����j�Ɖ����ȗ����������咣���鑽���h�ƂȂ����B�����h���̑古�l��M���w�A��w�̃W�F���g���ɂ͒��V�h���x��������̂������A�����ɑ��Ă͂���ȏ�̒Nj��ɂ͔����A�v������������������Ɍ����Ă����B�c��ł͑����h�ł��������A�P�U�S�W�N�ɂ��N�����E�F���ɂ���Ē����c���Ǖ�����Ă��܂��B���̌�A����ɐ��͂�Ԃ��A���}�h�Ƃ̑Ë���}�������������������������B |
| b�@���}�h
| ���E�ҁE�����I�古�l�E�M���E��n��Ȃǂ̍�����M�k�����S�ƂȂ������͂ŁA�����`���[���Y�P�����x�����A�c��ƑΗ������B�R�m�}�Ƃ�����ꂽ�B�n��I�ɂ͖k�����ɑ����A���������[�N�����_�Ƃ��A�����h�������_�Ƃ����c��h���D���ł������B �������A�c��h�ɃN�����E�F��������A�S�R����Ґ����ČR���I�ɗD�ʂɗ��ƁA���}�h�͎���ɗɂȂ����B |
| ���[�N
| �C���O�����h�k���̓s�s�B�V���I�ɃJ���^�x���[�ƕ���ő�i������������A�@���s�s�ƂĔ��W���邪�A�s���[���^���v���̎���ɂ́A���}�h�̋��_�ƂȂ�B |
�d�@�I�����@���N�����E�F��
 | �C�M���X���s���[���^���v���i�P�U�S�Q�`�S�X�N�j�̎w���ҁB������p�~���A���a�����������Č썑���ƂȂ�A�ƍٓI�Ȍ��͂��������B�N�����E�F���͎���u���͐��܂�Ȃ���̃W�F���g���}���ł���v�Ƃ����Ă���悤�ɁA�T�����W�F���g���Ƃ��Đ��܂�A�M�S���s���[���^���ł������B�P�U�S�O�N�P���u���b�W�s����c���ɑI�o����A�P�U�S�Q�N�ɓ������u������Ɓu�S�R���v��Ґ����c��h�̌R���͂̒��S�ƂȂ�A�P�U�S�S�N�̃}�[�X�g�������[�A�̐킢�ŏ��������߂��B�����ĂP�U�S�T�N���l�[�Y�r�[�̐킢�Ō���I�ȏ������������A�`���[���Y�P���͋c��R�ɂЂ��n���ꂽ�B�P�U�S�X�N�A�N�����E�F���͍����`���[���Y�P�������Y�A�C�M���X�ɍŏ��ŗB��̋��a���������������B�@���N�����E�F���̐��� |
a�@�S�R��
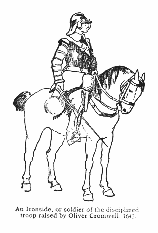 | �s���[���^���v���̎��A�c��h���N�����E�F�����g�D�����R�������B�A�C�A���T�C�h (Ironsides)�Ƃ����B�}�[�X�g�������[�A�̐킢�Ȃǂ̋c��R�̏����ɑ傫�ȍv���������B���̓S�R�������f���ɂ����V�^�R������ꂽ�B
�u�P�U�S�Q�N12���A�D���ł����������R�ɑR���邽�߁A�c��R�͏B�̖����R�̃��[�J���Y����Ŕj���Ē����A���R�Ɠ����A���R��Ґ������B�N�����E�F���͂��̓����A���̒������R�_���𒆊j�Ƃ���R���̈琬�ɒ��肵���B����͕����Ɛb�c�𒆊j�Ƃ��������R�Ƃ��A�_���̎��q�g�D���قƂ���]���̋c��R�Ƃ��܂��������I�Ɉ�����v���R�ł���A�s���[���^�j�Y���Ƃ������_�I�Ȏx���ƓS�̋K���������s�ł������B�P�U�S�R�N�T�������J���V���[�̃O�����V�����t�߂̐퓬�ŁA�Q�{�̕��͂��������R����Ԃ�A�ŏ��̐�ʂ��������B�v���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.132�� |
| ��b�@�V�^�R
| �C�M���X�̃s���[���^���v���ŁA�P�X�S�T�N�ɕҐ����ꂽ�c��R�̒��������B�V�͔͌R�A�j���[�|���f���R�iNew Model Army�j�Ƃ������B�N�����E�F�����S�R����͂Ƃ��āA�G�Z�b�N�X�R�Ɠ����A���R�A�E�H���[�R�̈ꕔ���W�߁A�t�F�A�t�@�b�N�X�i�ߊ��Ƃ��A�U�O�O�l�̋R�������P�P�C�P�O�O�O�l�̗��R�������P�C�P�Q�O�O�l�̕��������P�Q�C�v�Q�Q�O�O�O�l�ŕҐ��B���̌o����e�B�Ɋ��蓖�Ă钼�ڐłŎx�����B���̌R���́A�s���[���^�j�Y���_�I�Ȏx���Ƃ��A�`���I�ȎЉ�K�w�����āA�v���I�E�R���I�ϓ_����Ґ�����A�C����n�Ԉ������M���ƕ���ŕ������ƂȂ����B���N�U�����l�[�X�r�[�̐킢�ō����R��j��A�v���̏����������炵���B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.145�@�Ȃǂɂ�遄 |
| ��c�@�l�[�X�r�[�̐킢
| �P�U�S�T�N�U���̃s���[���^���v���ł̋c��h�̏����B�����R�͂V�T�O�O�ɑ��A�c��R�͂P�S�O�O�O�̕��͂ł��������A�N�����E�F���̕Ґ������V�^�R���y�̂��鍑���R�̃��p�[�g�͑����������čU���������A�펀�P�O�O�O�A�ߗ��T�O�O�O�Ƃ����s�k���i���A�����R�͉�ŁB ���̌�P�N�ԁA�e�n�ō����R�̎c�������̑|�����s���A�S�U�N�t�܂łɂ͍����R�̋��_�̓쐼���E�F�[���Y�n�����c��R�̎�ɗ������B�`���[���Y�P���͋c��̘a���h�ƌ����������ɘa���h�ɂ͗͂��Ȃ��A�S���ɂ͕ϑ����ăI�b�N�X�t�H�[�h�̍����R�w�n��E�����X�R�b�g�����h�ɐg�𓊂����B�X�R�b�g�����h�ƃC���O�����h�̋��c���������A�S�V�N�Q���A�����͂悤�₭�c��R�ɉ������B����ł������́u�ӋC�g�X�v�ł������B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.147�@�Ȃǂɂ�遄�@ |
| �e�@���a�� | �@ |
| a�@�`���[���Y�P���̏��Y
| �C�M���X���s���[���^���v�����i�s����Ȃ��A�P�U�S�X�N�P���S�����@�݂̂̌��c�ō����`���[���Y�P�����Y�̂��߂̍ō��ٔ������ݒu����A20������ٔ����J�n���ꂽ�B�ٔ��ψ��͂P�R�T�����C�����ꂽ�����ۂ���҂������A���ۂɂ͂U�O�����炢�ō\���B27�������ɑ��鎀�Y�̔��������쐬����A�T�V���̈ψ����������|�ނ�͌�Ɂu�����E���v�Ƃ�ꂽ�|�A30���z���C�g�z�[���Ŏ��Y�����s���ꂽ�B�������ɂ͍������u�c��Ƃ���ɑ�\����鍑���ɔ��t���s���Ȑ킢�����������v�߂�Nj����A�u�ꐧ�N��A���t�ҁA�E�l�҂ł���A���Ƃɑ�����G�v�ł���Ƃ��Ă���B�������A�����͂ނ���u�}���ҁv�Ƃ��Ď]�����A���̈⒘�Ƃ��Ĕ���o���ꂽ�����͐��{�̋֎~�ɂɂ�������炸�A�T�O�ł��z���锄��s���������B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.191���@ |
| b�@���a��
�̐��� | �C�M���X���s���[���^���v���ɂ���āA�P�U�S�X�N�Q���U���ƂV���̉��@���c�ŌN�吧�Ə�@��p�~���邱�Ƃ�����B�R��17���A�N�吧�p�~�̏�߂������B �u�����Ƃ����E�́A�d�d�s�K�v�ł��蕉�S�̑������̂ł���A�����̎��R�ƈ��S�ƌ����̗��v�ɗL�Q�ł����āA�����̌��͂Ɠ����͑�Ă��̏ꍇ�b����}�����A���������A�ꑮ�����߂�̂ɗ��p���ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B
�u�C���O�����h����т���ɕ������邷�ׂĂ̗̓y�A�n��̍����́A�����ɋ��a���A���R���ƂƂȂ�d�d�A����A���a���A���R���ƂƂ��āA���̍��̍ō��̌��Ђł���c��ɂ����鍑���̑�\�ƁA�����̕����̂��߂ɋc��̂��ƂɔC�������s���҂���ъ��E�҂ɂ���āA�������@�Ȃ��ɁA���������ł��낤�B�v ����ɂ���ăC�M���X�͈�@���̋��a���ƂȂ����B ���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.193�� |
| ��c�@�R�����E�F���X
| Commonwealth�@�{���́u�����̕����v�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A�C�M���X�̃s���[���^���v���Ő����������a�����Ƃ��P�U�S�X�N�Q������P�S�U�O�N�̉������Â܂ŃR�����E�F���X�ƌ���ꂽ�B�Ȃ��A��ɃC�M���X�A�M���w���ăR�����E�F���X�Ƃ����ꍇ������B |
| �f�@�N�����E�F���̐���
| ���͂��������N�����E�F���͂������ɓƍٓI�ƂȂ�A���Y���ƎQ�����̕�����v�����������h��A�y�n�ϕ���v�������f�B�K�[�Y�̉^����e������ƂƂ��ɁA�����̉��}�h�E�J�g���b�N���͂������������܂����B�܂��c��̉����h�ł������V�h���P�U�S�W�N�ɂ͒Ǖ����āA�Ɨ��h�݂̂œƐ肵���i����Ȍ�̒����c����A�����v�c��Ƃ����B�����v�Ƃ͎c���̈Ӗ��j�B�܂����v���^����}��������ŁA�A�C�������h�i�P�U�S�X�N�j���X�R�b�g�����h�i�P�U�T�O�N�j�𐪕������B�P�U�T�P�N�ɂ͖f�Տ��̗v���������q�C�@�𐧒�A�I�����_�Ƃ̑Η���[�߁A���N�����p���푈���n�܂����B�P�U�T�R�N�ɂ������c�������U�����A�썑���ɏA�C�����B�N�����E�F���́A�C�M���X��Ή����̂��ƂŊl�����ꂽ�C�O�̓y�ɑ��Ă����a���x�����g���悤�Ƃ��A�͑��𑗂����B�����Ɂu��������v�Ə̂��āA���C���h������k�đ嗤�̃X�y�C���B���n�ɑ��čU���������A�W���}�C�J���A�g���j�_�[�g���g�o�S�Ȃǂ𐪕����A����ɂ���ăC�M���X�̐��C���h�������`�����ꂽ�B�@���@�N�����E�F���̓ƍ� |
| a�@�����h
| �C�M���X�̃s���[���^���v�����ɓo�ꂵ���}�h�̈�ŁA�����F���[�Y Levellers �A�����h�Ƃ������B�Ɨ��h�̋}�i�I�Ȑl�тƂ����������}�h�ŁA�W�����������o�[�����w�����A���_�����H�ƎҁA�����l�����������B�ނ�͂P�U�S�V�N�A�u�l�������v�ɂ��̗v�����܂Ƃ߂Ă���B
�@�P�D�C�M���X�̐l���͑I���̂��߂ɂ͏Z���̐��ɉ����Ă������������ɕ��z�����B
�@�Q�D���c��͂P�U�S�W�N�X�������ɉ��U�����B
�@�R�D�l���͓�N�Ɉ�x�c��������I������B
�@�S�D�c��̌��͂́A�����I������I�����̌����ɑ��Ă̂ݗ����̂ł���B
���̂悤�ɐl���̌������ő���ɔF�߂邱�Ƃ�v���������̂ł���A�Ɨ��h�Ƃ̑Η��_�m�ɂ����B�����h�͂͂��߂̓N�����E�F���ɋ��͂������A�N�����E�F���̓ƍ������܂�A���̐��ێ�I�ɂȂ�ɏ]���A�Η���[�߁A�P�U�S�X�N�ɒe������A���ł����B�@���@�j�q���ʑI�� |
| ���f�B�K�[�Y | �f�B�K�[�Y Diggers �Ƃ́u���@��l�v�̈Ӗ��ŁA�^�������h�Ƃ������B�u���ׂĂ̐l�͐��܂�Ȃ���ɂ��č��Y�ɕn�x�̍��͂Ȃ��A�����ɐ_�̔푢�������錠��������v�Ǝ咣���A���L���Y�̔ے�A�y�n�̋ϕ����咣���A�����h���x�O�̍r��n���J���̂ł��̖�������B�s���[���^���v���Ő����h�̂���ɍ����Ɉʒu����}�h�ŁA�P�U�S�X�N�ɃE�B���X�^�����[�ɂ���Č������ꂽ�B���w�_���̎x�����ċ}�i�I�Ȋ�����W�J���A�N�����E�F���ƍ������ɂ���Ēe�����ꂽ�B�@ |
| b�@�A�C�������h����
| �s���[���^���v���ɂ���Č��͂��������N�����E�F���́A�J�g���b�N���k���������}�h�̋��_�ƂȂ��Ă���Ƃ����A�C�������h�𐪕������B�P�U�S�X�N�U��15���c��̓N�����E�F�����A�C�������h���ɔC���B�A�C�������h�ł͍����R�̃I�[�����h�J�g���b�N�R�Ɠ����A���c��̊�����W�J���Ă����B�N�����E�F���͂W��13���u���X�g�����o�q�A15���_�u�����ɏ㗤�A�A�P�Q�O�O�O���̐V���̕����Ɛ�C�̂T�O�O�O���̕��������������A�X���h���[�G�_�A10���E�F�b�N�X�t�H�[�h�Ȃǂ��U���A���̊ԃ~���|�}�E���g�̋s�E�A���@�̏Ă������A�w���q�̏�����{�[�g�߂�Ȃǎc�s�s�ׂ��s�����B�N�����E�F���͂�����u�_�݂̂��т��v�Ƌc��ɕ��Ă���B�T�O�N�T��26���u�N�����E�F���̍��݁v���c���A���B
���l�сw�C�M���X�s���v���j�xP.199-201���@���@�A�C�������h����i19���I�j |
| c�@�X�R�b�g�����h����
| �P�U�T�O�N�U��27���A�`���[���Y�P���̎q�̃`���[���Y���X�R�b�g�����h�̃A�o�f�B�[���ɏ㗤�A���v���̍��d�ƃX�R�b�g�����h�̔��C���O�����h������т����B�c��͂U��26���X�R�b�g�����h�i�������c�A�N�����E�F���i�ߊ��ɔC�������B�P�U�O�O�O�̕��͂͂������ɍs�����J�n�A�V��22���Ƀg�E�B�[�h����킽���ăX�R�b�g�����h�ɐN���A�����x���h�ƒ��V�h�̓����Η��̂���X�R�b�g�����h�R���X���R���_���o�[�̐킢�Ő펀3000�A�ߗ��P���Ƃ������Q��^���đ叟�B�`���[���Y�͒��V�h�̔s�k�����ĂT�P�N�P���P���p�[�X�ߍx�̃X�R�[���őՊ��������s�B�������A�X���R���N�����E�F���R�̓E�[�X�^�[�ō����R��j��A�`���[���Y�͎���ň����߂�������A�t�����X�ɖS���B�`���[���Y�̓N�����E�F������ɃC�M���X�ɖ߂�A�������Â����`���[���Y�Q���ƂȂ�B���l�ёO�f�� P.201-204�� |
| d�@�d����`
| �@���@�d����` |
| e�@�q�C�@
| �q�C��߂Ƃ������B�L�`�ɂ͂P�S���I�ȗ��̃C�M���X�̓`���I�f�Ր���ł��邪�A���`�ɂ̓s���[���^���v�����̂P�U�T�P�N���N�����E�F���̎���߂�ꂽ�q�C�@�������B���̌�A�P�U�U�O�N�̑�Q���q�C�@�i�C�㌛�́j�A�U�R�N�ɂ͖f�Ց��i��߁i�s��@�j�����肳�ꂽ�B �A�W�A�E�A�t���J�E�A�����J����̗A���͂��ׂăC�M���X�D�ɂ�邱�ƁA���[���b�p����̗A���̓C�M���X�D�����̐��Y���A���邢�͍ŏ��̐Ϗo���̑D�ɂ�邱�ƁA���߂����̂ŁA��������ƂȂ��Ă����I�����_�̒��p�f�ՂɑŌ���^���悤�Ƃ������̂ł���B�N�����E�F���̐��{�̐���ł͂Ȃ��A�����@���g�A���C���h�A�C�[�X�g�����h�Ȃǂ̖f�Տ��l�̗v�]�Ő����������́B�C�M���X�͍q�C�@�Ɋ�Â��ăI�����_�D�ɑ���Ռ��{�������s�g���悤�Ƃ������߁A���N���������I�����_�Ƃ̊Ԃ��p���푈���n�܂�A�R���ɂ킽��W�J����A�C�M���X�͂��̐푈�ɏ������邱�Ƃɂ���Đ��E�̊C��f�Ղ̔e�����������B���̌���A�C�M���X�d����`�̍������Ȃ��@���Ƃ��Ă��̊C�O�i�o���x�������A�P�X���I�ɂ����R�f�Վ�`���䓪���A�P�W�S�X�N�ɔp�~�����B |
| f�@�I�����_
| �@ |
| �g�@�C�M���X���I�����_�i�p���j�푈 | �C�M���X���N�����E�F���̎�����n�܂�A�C�M���X�ƃI�����_�i�l�[�f�������g�A�M���a���j�̑O��R��ɂ킽��푈�B�C�M���X���I�����_�Ɨ��푈���������A���ɂP�T�W�W�N�ɂ̓X�y�C���̖��G�͑���j��ȂǁA���ʂ���I�����_�̓Ɨ��������������B�������A�����I�ȓƗ���B�������P�V���I�����N�ȍ~�́A�I�����_�̓��[���b�p�̒��p�f�Ղɐi�o���ė��v���グ�A�܂��V�嗤�E����A�W�A�ɐi�o���āA�C�M���X�ƑΗ�����悤�ɂȂ����B�P�U�Q�R�N���A���{�C�i���������̈�ł���B���̂悤�Ȓ��œ��ɃC�M���X�̖f�Տ��̖�����A�I�����_���͂�}����悤�v�]���o����A���ꂪ���������̂��P�U�T�P�N�̃N�����E�F���̎��ɏo���ꂽ�q�C�@�ł������B����ɂ���ė����̑Η��͐퓬�ɓ]�����p���푈�ƂȂ����B�p���푈�͎����̂R���ɕ�������B
��P���F�P�U�T�Q�`�T�S�N�@�C�M���X���q�C�@�ɂ��ƂÂ��A�I�����_�D�ɑ��ėՌ��{�������咣�����Ƃ��납��n�܂�B�C�M���X�͍q�C�@��F�߂����A�������i�E�F�X�g�~���X�^�[���j�B
��Q���F�P�U�U�T�`�U�V�N�@�������Ì�C�M���X�͍q�C�@���X�V����Ƌ��ɁA�U�S�N�ɂ͐V�嗤�̃j���[�l�[�f�������g��N���A���̒��S�j���[�A���X�e���_�����j���[���[�N�Ɖ��̂����B�P�U�U�T�N�ɑ�Q���p���푈��������A�I�����_�C�R�͈ꎞ�e���Y��������̂ڂ胍���h���`�����ėD�ʂł��������A�t�����X�̋��Ђ��������I�����_���u�a���}���A�P�U�U�V�N�C�M���X����ăX���i�����������Ƀj���[�l�[�f�������g���m�ہi�u���_���j���ďI�������B
��R���F�P�U�V�Q�`�V�S�N�@�`���[���Y�Q�����t�����X�̃��C�P�S���̃I�����_�N���Ɍĉ����ăI�����_�Ɛ�����B�c��̎x���Ȃ��푈�̂��ߍ�����ƂȂ�A�u�a�����B
�����͂��̌�Đڋ߂��A�P�U�W�W�N�����_�v���ł̓I�����_���E�B�������C�M���X�����Ɍ}�����邱�ƂƂȂ�B�Ȃ��A��������قƂ�NJC��ł̐푈�ɏI�n���A���ʓI�ɃC�M���X�C�R����������A���̂P�W�`�P�X���I�̃C�M���X�鍑���o�������邱�ƂɂȂ����B |
| a�@�j���[���[�N
| ���̒n�́A�P�U�O�X�N�ɁA�I�����_���{�̖������w�����[�E�n�h�\�����T�����A���̌�I�����_�l���l�����т��іK��ăC���f�B�A���ƗF�D�W�����сA�I�����_���C���h��Ђ��C���f�B�A������}���n�b�^�������������i�i�Q�S�h�������Ƃ����j�̕i���ƌ������āA���̓�[����A���n�j���[�A���X�e���_�������݂����B�k�̎��ɒ���߂��炵���u�E�H�[���E�X�g���[�g�v�̒n���̋N����ł���B�P�U�U�O�N�����́A������R�O�O�A�l����P�R�O�O�B�n�h�\������ӂɍL�������I�����_�l�A���n�̒��S�ɂȂ��Ă����B���̌�A�t�B�������h�l�A�h�C�c�l�A�X�E�F�[�f���l���n�����A�j���[�C���O�����h����s���[���^�����ڏZ���Ă����B
��Q���p���푈�i�P�U�U�T�`�U�V�N�j�̒��O�A�P�U�U�S�N�ɃC�M���X�̍����`���[���Y�Q���̒탈�[�N��̖��߂Ŕh�����ꂽ�t���Q�[�g�͂S�ǂ������ƁA�R������ԑ��̖��߂����āA���̐l�тƂ͂����ɍ~�����Ă��܂����B�������ē��N�A�j���[�A���X�e���_���̒��͂S�O�N���炸�̖����I����āA�C�M���X�̂ƂȂ�A�j���[���[�N�Ɖ��������B�Ȍ�A�j���[���[�N�̓C�M���X�̖k�Ăɂ�����P�R�A���n�̈�Ȃ�B�͂��߂̓��[�N����̎�Ƃ���̎�A���n�ł��������A��ɂ��̓���j���[�W���[�W�[�ɕ������A���̐A���n�ƂȂ�B�Ɨ����̂P�R�B�̈�B |
| a�@���{��`�o�ς̐��� | ���Y��i�����L���鎑�{�Ƃ��A�J���҂��ٗp���ď��i�Y��������Nj�����o�ϑ̐��B��ʂɎ��{��`�́A�P�U�`�P�V���I�̃��[���b�p��Ή����̎���ɉƓ�����H�Ƃ���H�ꐧ��H�Ɓi�}�j���t�@�N�`���A�j�̒i�K�ɁA���{�̌`���ƘJ���͂̏o���Ƃ������n�I�~�ς��o�ď�������A�P�W���I�㔼����P�X���I�����܂ł��Y�Ɗv���ŎY�Ǝ��{�̐����������Ċ��������A�Ɛ�������Ă���B�������A�ŋ߂ł����{��`�I�Ȑ��E�o���̌`�����A�P�T�`�P�U���I�̂������q�C����ɋ��߂錩�����o����Ă���B ���@���{��`�Љ� |
| b�@�s���v��
| �s���v���Ƃ́A�����[���b�p�ɂ����ĕ����Љ�̖����Ɍ��ꂽ��Ή�����|���s���Љ���o���������ϊv�������B�P�V���I�̃C�M���X�v���A�P�W���I���̃A�����J�Ɨ��v���ƃt�����X�v�������̓T�^�ł���B
�s���v���̊T�O�F�u�s���v�Ƃ́A�u�M���v��u�̎�v�A�u�����I�古�l�v�A�u��n��v�Ȃǂɑ���K���T�O�ł���A�����ɂ͎�H�ƍH���A���n��ȂǂƂ��Ď��{��~���A�Y�Ɗv�����o�Ď��{�ƂƂȂ����K���ł���A�L�Y�K���u�u���W�����W�[�v�i���̒P���`���u���W�����j�Ƃ�������B�]���Ĉ�ʂɂ��s���v���́u�u���W�����v���v�̖���Ƃ��ėp������B�������A���{�ł́u�s���v�T�O�ɍ��������邽�߁A�}���N�X��`�Ō����u���W�����v���̖��Ƃ��āu�s���v���v�����Ă�ꂽ���A�����̂͂��̂܂܂́u�s���v���v�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A����͓��{�ꂾ�Ƃ����w�E������B�i���R�h��w���E�j�̒m�W�W�x�V����
p.111�j
���낢��Ȏs���v���F�u�s���v���v�́u�s���Љ�v���o���������Ƃ������A���ۂɂ͂��̒ʂ�ł������̂��A�����J�Ɨ��v�����炢�̂��̂ŁA���̐��Ƃ�����C�M���X�v���͂P�V���I�ɋN�����ăC�M���X�����N�吧�𐬗����������A�M����n��i�W�F���g���j�ɑւ��s���i�u���W�����j�̐����͂܂��s�\���ł���A�ނ炪���͂�����͎̂Y�Ɗv�����o����̂P�X���I�O���̎��R��`�I���v���W�J���ꂽ�����ł���B�܂��A�P�W���I���t�����X�v���ł��������ɉ����͓|����A�����I�����͔p�~����A�l���錾���o���ꂽ���A��C�Ɏs���Љ���������̂ł͂Ȃ��A�i�|���I���̒鐭�A���É����A���������Ȃǂ��o�āA�P�W�S�W�N�̓v����ɂقځu�s���Љ�v����������Ƃ������G�ȉے����Ƃ��Ă��邱�Ƃɏ\�����ӂ��Ă������B�܂��A�P�X�P�V�N�̃��V�A�v���́A���̒��̓v���i�O���v���j�͎s���v���I�ȈӋ`�t�����ł��邪�A���̔N�̂����ɋN�������\���v���i�\�ꌎ�v���j�ł͈�C�ɎЉ��`�v���ɓ˂�������ł��܂����B
�A�W�A�̎s���v���F�Ȃ��A�u�s���v���v�����[���b�p�ȊO�̐��E�œ��Ă͂߂悤�Ƃ���ƁA�Y���������Ă���B���Ƃ��Γ��{�̖����ېV�́u�s���v���v�Ƃ�����̂��ǂ����A�u��Ύ�`�v�̐����ƌ����̂��������̂ł͂Ȃ����A�Ȃǂ̌Â�����c�_�����邪�A�P���ɔ�r���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����ł��u�h��v���v�͈�ʂɎs���v���Ƃ͑�����ꂸ�A�P�X�Q�S�`�Q�V�N�̍����v�����s���v���ɋ߂��B����ɂ��Ă��A�ё͕s�\�����ƌ��Ă���A���́u�V�����`�_�v�ł͂P�X�S�X�N�̒��ؐl�����a���̌�������̓��ʂ̉ۑ肪�����Ǝ��̎s���v���ł���Ƒ����Ă���B�A�W�A�ɂ�����v���́A�����Ɨ��̗v�f���[���Ȃ��Ă���B |
| c�@�s���Љ�
| ���Y�͂̔��W��w�i�Ƃ��A���R�Ɛl���̂��F�߂�ꂽ�l�����������Љ�B�l�Ԃ������I�ȎЉ�W�⑼���I�ȏ@���Ɏx�z����Ă��������Љ�ɑ��āA���������s���𒆊j�Ƃ����Љ�ߑ�Љ�ł�����B�u�s���v�T�O�͓��ɂP�V�`�P�X���I�̃��[���b�p�Ō`�����ꂽ���̂ł���A���̎O�̑��ʂ�����ƍl������B
�@�P�D���O�I�ɂ͌[�֎v�z�A���Ƀ��b�N��\�[�Ȃǂ��Љ�_����Ɋ�Â���{�I�l���̎�́B
�@�Q�D�o�ϓI�ɂ��Y�Ɗv����ʂ��Č`�����ꂽ���{��`�Љ���\�����鎑�{�ƊK���B
�@�R�D�����I�ɂ͋c����Ȃǂ�ʂ��ĎQ�������l���������`������������́B
�s�����u���W�����W�[�F�u�s���v�́u�M���v��u�̎�v�Ƒ����̊K���A�܂�������y�n�̏��L�҂ł͂Ȃ��A���Ƃ⏬�y�n���L�ɂ���Ď����ł�����Y�������A�Y�Ƃ̔��W�ɔ����Ď��{��~�����L�Y�K���ł���u�u���W�����W�[�vbourgeoisie�i���̒P���`���u���W���� bourgeois�j�Ƃ����T�O�����Ă͂܂�B�}���N�X��`�̗��j�ςł͂��̂悤�ɊK���Ƃ��āu�u���W�����W�[�v���Ƃ炦�Ă���A���̖��Ƃ��āu�s���v�Ă͂߂Ă���B���̗����Ō����A���̂悤�ȁu�s���v����Ή�����M���A�������l�̌��͂�|�����̂��u�s���v���v�i���u���W�����v���j�ł���A�ނ炪�c��x�Ȃǂ�ʂ��č��ƌ��͂��������Љ�u�s���Љ�v�ł���Ƃ�����B���̎s�����u���W�����W�[���o�ꂵ�A�������Ă����̂́A���Y�͂̔��W�A�܂�_�ƎЉ��Y�Ɗv�����o�čH�ƎЉ�ɂȂ�A���{��`�o�ς��������Ă������ƂƏd�Ȃ��Ă���B
���܂��܂ȁu�s���v�T�O�F�u�s�����u���W�����W�[�v�ɂ��L���Ȏ��{�Ƒw����A�����l�A������ҁA���������Ȃǂ̏��s���K���i�v�`�u���W�����ȂǂƂ����j���܂܂��B����ɑ��āA���Y���قƂ�ǎ������A�J���͂����i�Ƃ��Đ����Ă��������Ȃ��K����J���ҊK�����v�����^���A�Ƃ����B����̓}���N�X��`�̏������{��`���͂ŗp����ꂽ�p��ł���A���݂ł͂��̂悤�ȊK���I�ȐF�����͎��Ԃɍ���Ȃ��Ȃ��Ă���A���܂�p�����Ȃ��B
�������A�u�s���v��u�s���Љ�v�̊T�O�͕����L���A�܂����ʓI�ł���A�p�������ʂňӖ����قȂ��Ă���B������́u�s���v�T�O�́A���݂ł���ʂɁu�s���^���v�Ƃ��u�s����فv�Ȃǂ̂悤�Ɏg���Ă�����̂ŁA�p���civil
�̖��ɓ�����B����́u���ƌ��́v��u�s���v�ɑ���A���̒n��Z���̏W���������ꍇ�ł���B�{���͓s�s�̏Z���Ƃ��������Ӗ��ł������s���T�O�ł��邪�A���̂悤�ȈӖ������ł͌���ł͔_���̏Z�����u�s���v�ƌ�����Bcivil
�Ƃ�����͂��Ƃ͐��E�҂ɑ��鑭�l���Ӗ����A�����Ƃ����Ӗ�������B����ɁAcivilian �Ƃ����Ε����A�����i�����A�R�l�ɑ��āj�ƂȂ�B���̂悤�ɁA���L���p��ł��邪�A���E�j���w�ԏ�ł͊K���Ƃ��Ắu�s���v�A�܂�u���W�����W�[�������̂��Ƃ��ėp���邱�Ƃ������B |
 |
| �E�D�C�M���X�c����̊m��
|
| �`�@�N�����E�F���̓ƍ�
| �s���[���^���v���������ɓ������N�����E�F���͂P�U�T�R�N�썑���ƂȂ��Ă���A�T�W�N�̎��܂œƍَ҂Ƃ��ăC�M���X�ɌN�Ղ����B���ɂ������h�̔��̐��^���A�E�ɂ͉��}�h�̔��v���A�d�A�Ƃ������E��������̍U���ɑ��A�N�����E�F���͌��͂̈ێ��̂��߂��R���ƍّ̐������������B�S�����P�O�̌R��ɂ킯�A�e�R��ɌR��������u���A�R���ƍs���̌�����^�����B���̌R�������ɂ͗��R���������Ă�ꂽ�̂ŁA���̑̐����u�������v�Ƃ����B���̌R�������̉��A�s���[���^�������������ɋ��v����A�����q���A���n�Ȃǂ̌�y�͋֎~���ꂽ�B
�c��i���@�݂̂̈�@�ł������j�̓N�����E�F���ɍ����̏̍���^���悤�Ƃ������A�������ɂ���͋��ۂ����B�������A�a���ƌĂ�A��p�҂��w�����邱�Ƃ��ł��A���@��݂��ăN�����E�F�����c����C���ł���悤�ɂ����B�܂��Ɏ����I�ȍ����ƂȂ����Ƃ����邪�A�C���t���G���U�ɂ�����P�U�T�W�N�X���R���Ɏ���ł��܂��B���̎q���`���[�h���썑���ɏA�C�������c����������A���`���[�h�͐l�]����������Ɏ��s���킸���W�����Ŏ��C���Ă��܂����B���̌�A�c��͉������Âɓ����B�@���@�N�����E�F���̐���
Epi.�@�N�����E�F���̎��@�N�����E�F���̈�̂̓E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɓA�d�Ɉ��u���ꂽ�B�Ƃ��낪�������ÂƂȂ�A�N�����E�F���������Ƃ��Ĕ����ƁA���̊��͂�����A��̂̓o���o���ɐؒf����A��͓S�̖_�̐�ɓ˂��h����āA���̌�Q�S�N�Ԃ������h���ł��炵���̂ɂ��ꂽ�B�Ƃ��낪�P�U�W�T�N�A�嗒�������h�����P���A�N�����E�F���̎�͖_�̐悩�痎���Ă��܂����B��q�̈�l�����̎������Ɏ����A��A����̉��˂̂Ȃ��ɂ������A���ɂ������̔閧�𖾂����Ď��B�ǂ̂悤�Ȍo�܂����炩�ł͂Ȃ����A�P�V�P�O�N���A���̎���ɏo����A������������̂��������ɂ��ċ����҂����Ƃ����B���̌�����l���̎���o�āA�P�W�P�S�N�E�B���L���\���Ƃ����l����������āA�ƕ�Ƃ��ĕۑ��A�P�X�U�O�N�ɃE�B���L���\���Ƃ̓��傪�N�����E�F���̏o�g�Z�ł���V�h�j�[�E�T�Z�b�N�X��w�ɑ��邱�ƂƂ��A���݂ł͓��Z�\���ɖ�������Ă���Ƃ����B�����̘b�́A�W�����E�t�H�[�}���w�Ƃт�������ȃC�M���X�j�x�����ܕ��� p.124 �ɂ��L�ڂ�����B�� |
| a�@�썑��
| �P�U�T�R�N12��16���m����c�œ����͓T�������B�C�M���X�j��B��̐������@�ƂȂ�B�����͓T�͑S��42���A��P�͂ŋ��a���̍ō��̗��@�����v���e�N�^�[�Ƌc��ɂ���ƋK��A�s�����̓v���e�N�^�[�ƍ�����c�������A�v���e�N�^�[�͊����C�ƌ��A�R�����A�O���������B���̑��A�I���͋c��ɔ��R���Ȃ��������̂œ��Y�܂��͕s���Y���Q�O�O�|���h�ȏ㎝���́A�c��͂R�N�ɂP��J�ÁA�c��̉������@���̓v���e�N�^�[�̏��F���Ȃ��Ă��@���Ƃ��Đ�������A�ȂǁB
�����A�N�����E�F���̓v���e�N�^�[�ɏA�C�B���a���͏I������B�����̌R����E���̂Ă��N�����E�F���ɑ��A���m�▯�O�͎��]�̐F���B���Ȃ������B���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���xP.277-8�� |
| b�@�R���I�ƍّ̐�
| �@ |
| �a�@��������
| �P�U�U�O�N�A�C�M���X�Ń`���[���Y�Q���������ƂȂ��ăX�e���A�[�g���̉����������������ƁB����ɂ���ăs���[���^���v���Ő����������a���͖�P�O�N�ŏI���������B�N�����E�F���̎���A���̌��i�ȌR���ƍِ����ɕs�����点�������́A�c����̉����Ȓ��V�h���x������悤�ɂȂ����B���V�h�Ɖ��}�h�̑Ë������������c��́A�c��̌����̑��d�������ɖ����邱�Ƃ������Ƀ`���[���Y�P���̎q���ŃI�����_�ɖS�����Ă����`���[���Y�Q���̍������A�ɓ��ӂ��A�������Â����������B
�u�P�U�U�O�N�A���풆�̍s���ɂ��Ă̑�́A�y�n�w���̊m�F�A�M�̎��R�̕ۏA�̂R�_��A����ȊO�̂��ׂĂ��c��̌���ɂ��A�Ƃ���������ۂ��`���[���Y�Q���́A�I�����_����A���A�T��25���Ƀh�[���@�ɏ㗤�����B���O�͔M���I�Ȋ��Ăō������}�����B �������Ì�A�N�����E�F����̕�͂�����A�R�O���̊v����d�҂͎��Y�ƂȂ�A�����_���������������B�v
���l�ѐ��v�w�C�M���X�s���v���j�xP.310-312�� |
| a�@�`���[���Y�Q��
| �C�M���X�E�X�e���A�[�g���̍����i�݈ʂP�U�U�O�`�W�T�N�j�B�`���[���Y�P���̎q�B�s���[���^���v���ŕ������Y�����ƁA�X�R�b�g�����h�ɂ̂���ĂP�U�T�P�N�X�R�b�g�����h����錾�B�������N�����E�F�����X�R�b�g�����h�����R�ɔs��āA�t�����X�ɖS���B�N�����E�F������̂P�U�U�O�N�A�����h���ɖ߂�A�u�u���_�̐錾�v���Đ�Ή����̕�����ے肵���̂ŋc��͔ނ��`���[���Y�Q���Ƃ��đ��ʂ��邱�Ƃ����F���A���������ƂȂ����B�P�U�U�T�N����͑�Q���p���푈���N�����B�P�U�V�O�N�ɂ̓t�����X�̃��C�P�S���Ɓu�h�[���@�[�̖����v�����сA�J�g���b�N�M�҂Ƃ��Ă��̕������A�c��Ƃ̑Η���[�߂�B�c��̓`���[���Y�Q���̃J�g���b�N������ɔ������āA�P�U�V�R�N���R���@�𐧒�A�܂��V�X�N�ɂ��l�g�ی�@�𐧒肵�Ďs���̌����̕ی��}�����B�`���[���Y�ɂ͌p�k���Ȃ��A�������J�g���b�N�̒�W�F�[���Y�̉��ʌp����F�߂邩�ǂ����ŋc����ɑΗ��������A���ꂪ���_�v���̗v���ƂȂ�B |
| ���u���_�̐錾 | �P�U�U�O�N�A�t�����X�S������߂����X�e���A�[�g�Ƃ̃`���[���Y�����������̂ŁA�V�����y�n���L�҂̏��L���̕ۏ�A�v���W�҂̑�́A�M�̎��R�A�R�����^�̎x�����̕ۏȂǁA�܂��Ή����������Ȃ����Ƃ�������́B�c��͂��̏��������ă`���[���Y�̃C�M���X�������ʂ�F�߁A���������ƂȂ����B���������ʌ���`���[���Y�Q���́A�u���_�̐錾�ɔ����ăJ�g���b�N�̕������͂���ȂǁA�c��ɑΗ����Đ�Ή����̕��������B |
| ���h�[���@�[�̖��� | �P�U�V�O�N�A�C�M���X���`���[���Y�Q���ƃt�����X�����C�P�S���Ƃ̊ԂŌ��ꂽ����B�J�g���b�N�M�҂ł������`���[���Y�������Ƀt�����X�̉����悤�Ƃ��Ē��������B�������c��̒m��Ƃ���ƂȂ�A�����ɑ��锽���������邱�ƂƂȂ����B |
| b�@�R���@
| �������Ê��̂P�U�V�R�N�A�C�M���X�c����肵���@���ŁA������M�҈ȊO�̎҂͊��E�ɏA���Ȃ��Ƃ��āA�J�g���b�N���͂̔r�����˂�������́B�R�����iTest Act�j�Ƃ������B�C�M���X�c����`���[���Y�Q�����J�g���b�N���͂̕������˂���ĂV�Q�N�ɐM���R�錾���o�����̂ɑ��A���̃J�g���b�N�����j�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�����錾��P���Ă���ɐR���@�𐧒肵���B���ׂĊ��E�ɂ��҂́A������̋V���ɏ]���Đ��`�������A��������̐��������A���̐����̐錾�ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��߂����̂ŁA����ɂ���ăJ�g���b�N�M�҂ƂƂ��ɍ����k�ȊO�̃v���e�X�^���g�i���k�Ƃ����j�����̑ΏۂƂ��ꂽ�B���������̖ړI�̓J�g���b�N���k��r������ړI�ł������B�V�W�N�ɂ͗��@�̋c���ɑ��Ă������悤�ȐR�����ۂ����Ƃ���߂�ꂽ�B����ɂ���č����Ɏd���鐔�S�l�̃J�J�g���b�N�M�����Ǖ�����A�����k�̐����x�z���m�������B ���_�v����̂P�U�W�X�N�Ɋ��e�@�����肳��A���k�̔r���͓P�p���ꂽ���A�J�g���b�N�ɑ���r���͑����A�悤�₭���R��`�̋��܂�Ƌ��ɂP�W�Q�W�N�ɐR���@�͔p�~����A�J�g���b�N���k��@�����肳���B |
| �@���k
| �m���R���t�H�[�~�X�g�iNoncomfomists�j�Ƃ����A�C�M���X�ɂ�����A�����k�i������A���O���J�����`���[�`�̐M�ҁj�ȊO�̃v���e�X�^���g�i�V���j�M�҂̂��ƁB�J�g���b�N�M�҂͊܂܂�Ȃ��B�P�U�V�R�N���R���@�ł̓J�g���b�N���k�Ɠ��������k�����E����Ǖ����ꂽ���A���_�v���̗��N�P�U�W�X�N�̊��e�@�ɂ���ĎO�ʈ�̂�ے肷��ꕔ�i���j�e���A���j���������v���e�X�^���g�̐M�̎��R�͔F�߂���B �@���@�C�M���X�̏@���e�h |
| c�@�l�g�ی�@
| �P�U�V�X�N�A�C�M���X�c����肵���@���ŁA�l���͗��R�Ȃ��ɑߕߍS�ւ���邱�Ƃ͖����A�ߕߍS�ւ̏ꍇ�͐l�g�ی�ߏ�ɂ��Ȃ���Ȃ炢�ƒ�߂����́B���̖@�߂ɔ������ٔ����͌����ɏ�������Ƃ��ꂽ�B�������Ê����`���[���Y�Q�����A��Ή����������悤�Ƃ������Ƃɑ���A�c��̒�R�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�B�}�O�i���J���^�Ȃǒ����ȗ��A��߂��Ă����l���ی�̗��@���������������̂ŁA���݂ł��C�M���X�̏d�v�Ȗ@���Ƃ��Đ����Ă���B |
| �b�@���}�̐���
| �`���[���Y�Q���ɂ͒��q�������A���@��̉��ʑ����l�̉����W�F�[���Y�̓J�g���b�N���k�ł������B�W�F�[���X�̉��ʌp����F�߂Ȃ���h�͐V���k�̏��q�����}�X���𑊑��҂Ƃ��邽�߁A1679�N�A���ʌp���r�˖@�Ă��o�����B����ɑ��č��@�I�ȑ����҃W�F�[���Y�̑�������F�߁A���̎���A�V���k�ł��郁�A������уA�������ʌp���҂Ƃ��悤�Ƃ����B�O�҂̓V���t�c�x������̂Ƃ��閯���h�Œn���}�A���肩����z�B�b�O�i�X�R�b�g�����h�̖d���l�̈Ӗ��j�Ƃ��A��҂��_���r�[����̂���R�m�h�ŋ{��}�A���肩����g�[���i�A�C�������h�̖��@�҂̈Ӗ��j�ƌĂꂽ�B���}�̓W�F�[���Y�Q���̉��ʌp���ł͌��������������A���_�v���ł͋������ăI�����_���E�C�����Ƃ��̍ȃ��A���̏��ق��͂���A�E�B���A���R�������ł͗��}����t�����o���A�����t�̌`�����������A�P�U�X�S�N����̓z�C�b�O�ɑg�t�����A���}�����ւ̓����J�����B�@ |
| a�@�g�[���}
| �`���[���Y�Q���̌�p�Ƃ��č��@�I�ȑ����҂Ƃ��ăJ�g���b�N���k�̉����W�F�[���Y�̑��ʂ�F�߂���h�̂��ƁB�_���r�[����̂Ƃ���A���M���K���������A�{�����ՂƂ��Ă����B�Η�����l�тƂ�����u�A�C�������h�̖��@�ҁv�̈Ӗ��̃g�[���iTory �g�[���[�Ƃ��\�L�j�ƌ���ꂽ�B�A�C�������h�ɂ̓J�g���b�N���k�����������̂ŁA�J�g���b�N�̃W�F�[���Y���x��������h�����̂悤�Ɍ����A�{���͕̏̂ł��������A����Ɏ�����g�[���Ə̂���悤�ɂȂ����B�����A������A���R�m�K���Ȃǂ̕ێ�h���\���鐨���ł��������A�t�����X�v�����ɏ��s�b�g�Ȃǂ̐l�ނ�����A�z�B�b�O�̉��v�ɑ���ێ琨�͂Ƃ��Đ��}�����i�݁A�P�W�R�O�N����ێ�}�ւƓ]�g���A�Q�O���I�O���܂ł͎��R�}�Ƃ́A�Q�O���I�㔼���猻�݂܂ł͘J���}�Ƃ̓�吭�}���̈���̐����S�����}�Ƃ��đ����Ă���B |
| b�@�z�C�b�O�}
| �J�g���b�N���k�ł����W�F�[���Y�̉��ʌp����F�߂��A�V���k�̏��q�����}�X���𑊑��҂Ƃ��邱�Ƃ��咣���P�U�V�O�N�ɉ��ʌp���r�˖@�āi���̖@�Ă͋c��Ŕی����ꂽ�j�Ɏ^�������l�тƂŁA�V���t�c�x���[����̂Ƃ��Ēn���̃W�F���g���[�𒆐S�Ƃ����������������d������X�����������B�G����l�тƂ���A�u�X�R�b�g�����h�̖d���l�v�Ƃ����Ӗ��̃z�B�b�O�iWhig �E�B�b�O�Ƃ��\�L�j�ƌ���ꂽ�B�X�R�b�g�����h�͔��C���O�����h��������A�����ɂ����R�I�ł������̂ŁA�������̈�h�ɑ���̏̂Ƃ��Ďg��ꂽ���A�₪�Ĕނ玩����z�C�b�O�Ə̂���悤�ɂȂ����B��������k�Ɠs�s�̏��H�Ǝ҂̗��Q���\����悤�ɂȂ�A�P�W���I���E�H���|�[�����t���o���������B�Y�Ɗv����́A�I���@�����ȂǂŎ��R��`�̗�����Ƃ�A�P�W�Q�O�N�`�R�O�N��̈�A�����R��`�I���v�𐄐i���A�P�W�R�Q�N�ɂ̓z�C�b�O�}�̃N���C���t����P��I���@���������������B�P�W�R�O�N���납�����R�}���̂���悤�ɂȂ�A�u���W�������R��`���}�Ƃ��āA�Q�O���I�O���܂ł͕ێ�}�Ɠ�吭�}������`������B |
| �c�@���_�v��
| �P�U�W�W�N�A�W�F�[���Y�Q���ɒj�q���Y�܂��ƁA�V���k�ł��閅�̃��A���ւ̉��ʌp�����]�܂�Ȃ��Ȃ����B�C�M���X�c��̃g�[���A�z�B�b�O�̗��}�͂Ƃ��Ƀ��A���̕v�̃I�����_���E�B���������ق����B�E�B�����͐V���k����Ȃ�R�����g�[�x�C�ɏ㗤���������A�W�F�[���Y�Q���̓t�����X�̃��C�P�S���̎x����f��Ɨ͂őR���悤�Ƃ����B�����������R�͕��čR�킷�邱�Ƃ��ł����A�e�n�ɔ������̖I�N���n�܂�A�����h���s���������r���ɗ����オ�����B���ɂP�Q���A�W�F�[���Y�͍Ȏq�ƂƂ��Ƀt�����X�ɖS�������B���W�X�N�A�c��́u�����̐錾�v���o���A�E�B�����ƃ��A������������F�����E�B���A���R�������A���Q���Ƃ��đ��ʂ����B����ɋc��́u�����͓̏T�v�𐧒�A�����N�吧�����������B������u���_�v���v�iGlorious Revolution�j�Ƃ����Ă���B
�u���_�v�̈Ӗ��ɂ��āA�C�M���X�j�̑��l�҂Ƃ���ꂽ�g�����F���A���́A���̂悤�ɐ������Ă���B���̖��_�Ƃ́A���炩�̕��M�Ƃ��A�p�Y�I�s�ׂƂ��A�ꍑ������ۂƂȂ�ΈË��ȍ�����Ǖ��ł��邱�Ƃ��������Ƃ��Ƃ��������ɑ�����̂ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A�C���O�����h�l���C�Ⴂ���݂��}�h�Ԃ̔��ڂ̒��ŘQ��Ă��܂������R�̉��͂��邽�߂ɁA�O���̌R����K�v�Ƃ������Ƃ́u�s���_�v�Ȃ��Ƃł���B�w�C�M���X�v���̐^�́u���_�v�́A���ꂪ�����ł��������ƁA��������s�E���l�����D���Ȃ��������ƁA�����ĂȂ����A�l�X�Ɠ}�h���������v�����A�������͂��������ꂽ�@����A������̈ӌ��̑���ɂ��āA���ӂɂ������ɓ��B�������Ƃ��������ɂ���������̂ł���B�x���g�����F���A���w�C�M���X�j�xp.199�� |
| a�@�W�F�[���Y�Q��
| ���_�v���ʼn��ʂ��������X�`�����[�g���C�M���X���i�݈ʂP�U�W�T�`�W�W�j�B�t�����X�l���Ƃ��A�t�����X�ŗ{�炳�ꂽ�M��ȃJ�g���b�N���k�ŁA���`���[���Y�P���ȏ�̔����I�Ȑ�����Ƃ����B�����}�X���̔����i�W�F�[���Y�Q���̑��ʂɔ����A���ʌp�����咣�����`���[���Y�Q���̏��q�����}�X���̔����j�������ɏ���R��ݒu���A�J�g���b�N���k�̕������C�p���i�R���@��������p�~�j�����A�W�V�N�ɂ͐M���R�錾���A�J�g���b�N���k�̐��E�A�C���������B���N�A�M���R�錾�����q�ɂQ�x�ǂނ��Ƃ������A�������J���^�x���[��i����V����ߕ߂���ȂǁA�����̎x�����������B�P�U�W�W�N�A�c����ق����I�����W���E�B�����Ƃ��̍ȃ��A���i�W�F�[���Y�Q���̖��Ńv���e�X�^���g�j���㗤�A������l�̖��A�����c��ɑ������̂ŃW�F�[���Y�Q���͌Ǘ����A�P�Q���Q�R���C�M���X�𗣂�ăt�����X�ɖS���i���_�v���j�A���C�P�S���̒��Ă��ꂽ�T�����W�F���}���̉B��Ƃɐg�����B |
| b�@���A��
| �@���@���A���Q�� |
| c�@�E�B����
| �@���@�E�B���A���R�� |
| d�@�����̐錾
| Declaration of Rights�@���_�v���̍ہA�P�U�W�X�N�Q���A�C�M���X�i�C���O�����h�j�̍������c��i���c��j���A�E�B�����ƃ��A���ɒ�o�����錾�B��l����������F�����E�B���A���R���ƃ��A���Q���Ƃ����C�M���X�̋��������҂Ƃ��đ��ʂ����B�u�����̐錾�v�͂P�R���ڂɂ킽��扤���W�F�[���Y�Q���̐�����ᔻ���A�����̌����Ǝ��R���m�F�������́B�u�����͓̏T�v�Ƃقړ�����e�ŋc��Ő��肳��A�����̖��Ō��z���ꂽ�@�����u�����͓̏T�v�B |
| e�@�E�B���A���R��
| �l�[�f�������g�A�M���a���̃I�����_���̈ʁi������̃I�����_���ʁj�𐢏P����I���j�G�Ɓi�I�����W���j�̃E�B�����R���B�Ȃ��C�M���X�̃X�e���A�[�g���W�F�[���Y�Q���̖����A���B�C�M���X�c��̗v���ɂ��A�C�M���X�����Ƃ��ă��A���ƂƂ��ɂP�U�W�W�N�ɂP���S��̕��𗦂��ăC�M���X�ɏ㗤�B�E�B���A���R���ƂȂ�i�݈ʂP�U�W�X�`�P�V�O�Q�N�j�B���ꂪ���_�v���Ƃ����B�I�����_�͂��Ă͊C�O�f�Ղ��߂����ďՓ˂��A�p���푈����������ł��������A���̎����ɂ̓J�g���b�N���t�����X�����C�P�S���̗̓y�I��S�ɋ�������Ă���A�C�M���X�Ƃ̒�g�ɈӖ��������������Ƃ��ł����B�����ł͋c��Ƌ������ė����N�吭�𐄂��i�߁A�O���ł̓t�@���c�푈����іk�Ăɂ�����t�����X�Ƃ̐A���n�푈�ł���E�B���A�����푈�i�P�U�W�X�`�X�V�N�j���J�n�A�t�����X�Ƃ̑�Q���S�N�푈�Ƃ����钷���R���ɓ˓������B�E�B���A���R���́A���C�P�S���Ɍ㉟�����ꂽ�W�F�[���Y�Q�����A�C�������h�ɏ㗤����Ƃ�����}���������Č��ށi�P�U�X�O�N�{�C����̐킢�j���A����ɂX�Q�N�ɂ̓m���}���f�B���Ńt�����X�C�R��j��A���C�����m�ۂ����B���C�P�S���͂��ɃE�B���A���R�����C�M���X���Ƃ��ď��F�����B�P�V�O�P�N�X�y�C���p���푈���N����ƁA�C�M���X�̓I�����_�A�I�[�X�g���A�ƎO�����������сA�t�����X�E���C�P�S���ƑR�����B���P�V�O�Q�N�A�E�B���A���R���͏�n���ɔn���|��A�]����܂����̂������Ŗv�����B���A���Q���Ƃ̊ԂɎq���͂Ȃ��A���ʂ̓��A���̖��̃A���Ɍp�����ꂽ�B |
| f�@���A���Q��
| �C�M���X�����W�F�[���Y�Q���̖��ł��邪�A�v���e�X�^���g�̋�����A�I�����_���E�B�����ƌ��������i�P�U�V�V�N�j�B���_�v���ɂ���āA���W�F�[���Y�Q�����t�����X�ɖS��������A�v�E�B�����ƂƂ��ɃC�M���X�ɓn��A�v�̓E�B���A���R���A�ޏ��̓��A���Q���Ƃ��ċ��������ɂ��������i�݈ʂP�U�W�X�`�X�S�N�j�B |
| g�@�����͓̏T
| Bill of Rights�@�P�X�W�X�N�P�Q������B���m�ɂ́u�b���̌����y�ю��R��錾���A���ʌp�����߂�@���v�B�W�F�[���Y�Q���S����̑P�㏈�u�Ƃ��č������c������W�A�����������̐錾���N������A�E�B���A���R���ƃ��A���Q������������F���邱�Ƃ������ɋ��������Ƃ��đ��ʂ�F�߂��B����ɂ���ɖ@�I���͂�^���邽�߁A�u�����͓̏T�v�Ƃ��Đ��肵���B ���@���E���Ō��E�R�����̋c��ɂ��邱�Ƃ�ۏ�A������C�Ƃ��錠�����c��ɂ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�����N�吧�̊�b�𐘂����B�����͐��{�̎��s���E��b�̔C�ƌ���ێ������B���̖@���́A�}�O�i���J���^�ƕ��сA�C�M���X���@���\�����Ă���B
�u�����͓̏T�v�iBill of Rights�j�̎�ȋK��
�@�P�D�����́A�����ɂ��A����̏��F�Ȃ��ɖ@�����~�A�܂��͖@���̎��s���~�����邱�Ƃ͕s�@�ł���B
�@�Q�D�c��̓��ӂȂ����āA�匠�̖��ɂ����ĉ��̎g�̂��߂ɋ������邱�Ƃ͕s�@�ł���B
�@�R�D���ɐ��肷�邱�Ƃ͐l���̌����ł���B
�@�S�D�c��̓��ӂȂ��ɏ���R����A�ێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�T�D�c���̑I���͎��R�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@�U�D�c����̌��_�̎��R�́A�c��O�Œe�N����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�ȉ��� ����g���Ɂw�l���錾�W�xp.82�� |
| h�@�������� | �@ |
| i�@�C�M���X�v��
| �@���@�C�M���X�v�� |
| �d�@���}����
| �@ |
| a�@���t | �����̓��t���x�F���t�Ƃ�������́A�P�S�O�Q�N�ɖ��̉i�y��̐ݒu�����A�c��̕⍲���ł������t��w�m�̖�������͂��܂�B���̐����ł��c�鐭�����x����@�ւƂ��ē��t���݂����A����ɏd�v�ȋ@�ւƂȂ����B�����ł�贐���̎����R�@�����݂����ē��t�͎������������B���̌�A�ߑ���{�⒆�ؖ����ł̓C�M���X���̐������x����������邪�A���̍ہA�p��� Cabinet �̖��Ƃ��ĕ������A���݂܂ŗp�����Ă���B
�C�M���X�̓��t���x�F�p��� Cabinet �Ƃ����͖̂����̈Ӗ��ŁA�s���[���^���v����������������i�P�V���I�����j�ɍ����̐�����⍲���钷����c�𖧎��ŊJ�������ƂɗR������B���_�v����ɐ��}�������m������ƁA���t�͋c��̎x�����s���ƂȂ�̂ŁA�c��̑����}������I��ē��t��g�D���A�c��ɑ��ĐӔC���ӔC���t�����n�܂�B���̍ŏ����W���[�W�P���̂Ƃ����E�H���|�[�����t�ŁA�iPrime Minister ���t���̑��l�҂̈Ӗ��j�Ƃ����̍������ނɎn�܂�B���̌���t���x�𒆐S�Ƃ����C�M���X�̐������x�͋ߑ㍑�Ƃ̃��f���Ƃ��đ��̍��ɂ��̗p����Ă����B |
| b�@�A������
| �C�M���X�E�X�e���A�[�g���̍Ō�̏����i�݈ʂP�V�O�Q�`�P�S�N�j�B���̃W�F�[���Y�Q���ƈႢ�A�o�̃��A���ƂƂ��Ƀv���e�X�^���g�̋�����A���_�v���ł��o���A�����x�������B���A���Ƃ��̕v�E�B���A���R���Ɏq���Ȃ������̂ŁA���ʂ��p���B���̏����̎��ɁA�C�M���X�̓��[���b�p�ł��X�y�C���p���푈�Ɩk�ĐA���n�ł��A�������푈�ŁA�t�����X�ɑ��鏟�����߁A�C�M���X�v���̍������������Ĕ��W���p���������B�܂��P�V�O�V�N�ɂ́A�C���O�����h�����ƃX�R�b�g�����h��������������u���e���������������A�����Ƃ��ɃC�M���X���ƂȂ����B
Epi.�@�s�K�ȃA�������Ɖ��ʌp�����@�E�B���A���R���ƃ��A���̊Ԃɂ͎q�������Ȃ������B�����A���ʌp���Ŗ�肪�N���邱�Ƃ����O�����E�B���A���R���́A�P�V�O�P�N�ɉ��ʌp���߂z���A�u����̉��ʂ̓X�e���A�[�g���Ƃ̌��������v���e�X�^���g�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƌ��߂��B����ɂ���ăE�B���A���R���̎��́A���A���̖��̃A�������ʂ����B�A���̓f���}�[�N���̎��j�Q�I���N�ƌ������A�P�W�l���̎q�������܂ꂽ���A�s�K�ɂ��Ă��̂��ׂĂ����Y���A�q���̂����Ɏ���ł��܂��A�u�q�������X�Ǝ������߂��݂ŃA���͎��ɂ��ڂ�A�R�V�ʼn��ʂɂ����Ƃ����얞�䂦�ɕ��s���܂܂Ȃ炸�A�����Ēɕ��ɔY�܂����Ƃ����S�邽�邠�肳�܂������B�v�E�B���A���R���̌��O�����Ƃ���A���ʌp�������ƂȂ��Ă��܂������A���ʌp���߂����܂��@�\���A�傫�ȍ������Ȃ��A�W�F�[���Y�P���̑��̃]�t�B�A�̎q�ł���n�m�[���@�[�I���W���[�W���p�����邱�ƂƂȂ����B�����я͕v�w�C�M���X��������x1996�@�u�k�Ќ���V���@p.118�� |
| c�@��u���e������(�O���[�g�u���e���j
| �X�e���A�[�g���A�������̂P�V�O�V�N�A�z�C�b�O�}�̎哱���鐭��Ƃ��āu�����@�v�������A�C���O�����h�ƃX�R�b�g�����h���A����܂ł̓�̉��������ʂ̈�l�̉������������̐�����A���ʂ̋c��Ɛ��{��������l�̍��������������A�������Ƃ����A���ٖ��ȊW�����B�X�R�b�g�����h�́A���V�h�����`��Ǝ��̖@���A�ٔ����x�Ȃǂ�ۂ������A�����I�A�o�ϓI�ɂ̓C���O�����h�ɕ�������邱�ƂƂȂ����B���@�P�W�O�P�N�@�A�C�������h�����Ɓu�O���[�g���u���e������уA�C�������h�A�������v���� |
| �e�@�ӔC���t��
| ���t�͋c��̑������߂�}�h�̑�\���\�����A�����ɑ��Ăł͂Ȃ��c��ɑ��ĐӔC���A�Ƃ��������̌����������B���̐��x�ł͓��t�͋c��ŏ��F���ꂽ���@�ɂ���čs����S������Ƃ������͕������͂����邱�ƂɂȂ�B�C�M���X�̃n�m�[���@�[���W���[�W�P���̎����E�H���|�[�����t����n�܂�Ƃ���Ă���B |
| a�@�W���[�W�P��
| �C�M���X�E�n�m�[���@�[������̍����i�݈ʂP�V�P�S�`�Q�V�N�j�B�h�C�c�̃n�m�[���@�[�I���ł��������A�X�e���A�[�g���̃A���������p�k��������������A�C�M���X�����Ƃ��Č}������B��̃]�t�B�A���W�F�[���Y�P���̑��ŃX�e���A�[�g�Ƃ̌��������Ă��Ă���A�v���e�X�^���g�ł���������ł������B���ʂ����Ƃ��ɂ��łɂT�S�A�������قƂ�ljp�ꂪ�b�����A�܂��n�m�[���@�[�I���̒n�ʂ����˂��̂ł����h�C�c�ɋA��A�������قƂ�nj��Ȃ��������߁A�E�H���|�[���̐ӔC���t�������W����B���ʗ��N�̂P�V�P�T�N�ɂ́A�X�e���A�[�g�Ƃ̃W�F�[���Y�Q���̒j�q�n�������ʂɌ��Ă悤�ƌ�����h�̃W���R�o�C�g�̗����N���������������ꂽ�B�W���R�o�C�g�Ƃ́A�W�F�[���Y�̃��e�����W�F�C�R�u�X�ɗR������B |
| b�@�n�m�[���@�[��
| �P�V�O�P�N���肳�ꂽ���ʌp���@�Ɋ�Â��āA�X�e���A�[�g���A�������̖v��A�P�V�P�S�N�Ƀh�C�c�̃n�m�[���@�[�I���W���[�W���C�M���X���W���[�W�P���Ƃ��đ��ʂ����B�W���[�W�P���̓C�M���X���ʂƃn�m�[���@�[�I���̒n�ʂ����˂��B�W���[�W�P���̓C�M���X�������قƂ�NJ֗^���Ȃ������̂ŁA���̊ԁA�C�M���X�̐��}�������ӔC���t�����m������B�n�m�[���@�[���͂��̌�A�W���[�W�Q���A�W���[�W�R���i�P�V�U�O�`�P�W�Q�O�A�A�����J�̓Ɨ��A�t�����X�v���A�Y�Ɗv���̎���j�A�W���[�W�S���Ƒ����A�P�X���I�㔼�����B�N�g���A��������i�P�W�R�V�`�P�X�O�P�j�ɁA��p�鍑�̔ɉh�����}����B�Ȃ��A���B�N�g���A��������A�n�m�[���@�[��̒n�ʂ͏����̑������F�߂��Ȃ������̂ŃC�M���X�����P�ƂƂȂ����B���B�N�g���A�����ƃA���o�[�g���̊Ԃɐ��܂ꂽ�G�h���[�h�V���̑��ʂ����P�X�O�P�N���牤�������T�b�N�X���S�o�[�O���S�[�^���ɑ���A����ɑ�P�����E��킪�u������ƃh�C�c�n�̉����������炢�A�P�X�P�V�N���E�B���U�[���Ɖ��̂����B |
| �E�B���U�[��
| �C�M���X���n�m�[���@�[�����P�X�O�P�N����̃T�b�N�X���S�o�[�O���S�[�^�����o�āA�P�X�P�V�N�ɂ��̉������ɉ��̂������́B�O�̉��������h�C�c�̉ƌn���p��������̂ł������̂ŁA��ꎟ���E��킪�n�܂����Ƃ��ɉ��{�̏��ݒn�ɂ��Ȃ��̖��̂ɕύX���ꂽ�B�W���[�W�T���i��P�������j�A�G�h���[�h�W���i�P�X�R�U�N�A���l���ʼn��ʂ���������j�A�W���[�W�U���i��Q�������j�Ƒ����A���݂̃G���U�x�X�����i�P�X�T�Q�`�j�Ɏ���B |
| c�@�E�H���|�[�����t
| �E�H���|�[���̓C�M���X�E�n�m�[���@�[���W���[�W�P���̎��̐����ƁB�P���u���b�W��w�𑲋ƌ�A�z�C�b�O�ɑ����鐭���ƂƂ��ċc��Ŋ���A�P�V�Q�O�N�́u��C�A�������v�̍��������E���ē��p�������A�P�V�Q�P�N������呠���߁A���t�̃����o�[�ƂȂ����B�����W���[�W�P���͂��܂�p����b�����A�������E�H���|�[���ɔC�����̂ŁA�ނ́u�t���̑��l�ҁv�Ƃ����Ӗ��́A�v���C���E�~�j�X�^�[�ƌĂ��悤�ɂȂ�A���ꂪ���t������b�i�j���Ӗ�����悤�ɂȂ�i���x�Ƃ��Ă͂P�X�O�V�N����j�B�E�H���|�[���͑ΊO�푈���ł��邾���}���č����̈����}��A�d����`����i��Ƃ��ĕی�Ő���B���ޗ��̗A���ł͒Ⴍ���A���Ȃǂ̚��ʕi�ɑ��Ă͍����ݒ肵���B�j���Ƃ��ăC�M���X�Y�Ƃ�ی삵�A��p�鍑�ւ̔��W�����������B�ΊO�푈�ł͂P�V�S�O�N���I�[�X�g���A�p���푈�ɍۂ��ăI�[�X�g���A���x���i���ڌR���͑���Ȃ������j�A�X�y�C�����W�F���L���Y�̎��푈�ƁA�t�����X���W���[�W���푈�������B�P�V�S�Q�N�A�c��i���@�j���Ŕ��Δh���������߂�ƁA�E�H���|�[���͉����@�̎x�����������ɂ�������炸�������C�����B���ꂪ�A�c��ő������߂�}�h�̓}���t��g�D����Ƃ����ӔC���t���̐�Ⴊ�J����邱�ƂɂȂ����B�������āA���t�͍����ɑւ���č����̑S�ʂ��������A�����̑�\�ł���c��ɑ��ĐӔC�����Ƃ����ӔC���t�������������Ƃ����B
Epi.�@�o�u���o�ς̌��_�A��C�A�������@�X�y�C���p���푈���N�������Ƃ��A�C�M���X���{�͐��邽�߂Ɍ��s�����������߁A���̗����̎x�����ɋꂵ��ł����B�����Łu��C��Ёv�Ƃ����f�Չ�Ђ�ݗ����A��Ă̓���C�ݒn�тƂ̖f�Փ�����^���A���̊����Ō�����邱�Ƃ��v�悵���B��C��Ђ͐l�тƂ̓��@�S���h�����A�P�V�Q�O�N�P���̔������̊����P�O�O�|���h�����N�łP�O�T�O�|���h�܂Œl�オ�肵���B����Ɏh������āA���Ԃɂ����X�Ɠ��@�ړI�̉�Ђ����ꂽ���A�����͎��̂̂Ȃ��A�A���i�o�u���j��Ђł������B�U�����s�[�N�Ɋ����͉�����͂��߁A�P�Q���ɂ͂P�Q�T�|���h�ɖ\�������B�܂�A�o�u�����͂����Ă��܂��A�s�[�N���ɍ��l�Ŕ�������ʂ̓����҂͑呹���A�j�Y������̂����o�����B���̓^�����u��C�A�������v�Ƃ����A���{�̂P�X�W�U�`�X�P�N�̊����ƒn���̍������o�u���o�ςƌ����Ă���̂͂��̖A���A�܂�o�u�����炫�Ă���B�E�H���|�[���͓�C��Аݗ��ɂ͔����A���̔j�]�����炩�ɂȂ��Ă���Č��������A�z��f�Ղƕߌ~���ƂƂ����Ђɏk�����čČ��ɐ��������B���N�ƂȂ����ނ͂��̑̌������A�����Y�ƂƊC�^�̕ی�ɂ�����A�����I�d����`������Ƃ��ăC�M���X�o�ς����Ē������B |
| ��e�@�����͌N�Ղ���ǂ���������
| �@ |
| f�@�Q����
| �@ |
 |
| �G�D���C�P�S���̎���
|
| �`�@���C�P�S��
| �@����X�́@�S�߁@�G�D�t�����X�̏@�������Ɛ�Ή����@���C�P�S�� |
| a�@�u���͍��ƂȂ�v
| �@ |
| b�@���z��
| �@ |
| c�@�����_����
| �@���@�����_���� |
| �{�V���G
| ���[�̎i���ŁA���C�P�S���Ɏd���A�����_�����𗝘_�Â����B�u���ʂƂ͐l�g�̈ʂł͂Ȃ��A�_���̂��̂̈ʂł���B����䂦�ɉ��҂͒n��ɂ�����_�̑㗝�l�Ƃ��čs��������̂ł���B�v |
| d ���F���T�C���{�a
| ���C�P�S�����P�U�U�P�N���琔�\�N�������đ��c�����{�a�B�p���̓쐼�ɂ���B���Ƃ̓��C�P�R������̍ۂ̏h���̂��߂ɍ���������ȏ�ł������Ƃ�����A���C�P�S�������C�E�g�������B�{�a�̒��S�́u���̊ԁv��A�뉀���L���B�L��Ȓ뉀�̓����m�[�g���̐v�A�{�a�{�ق̓������H�[�A���̊Ԃ̓��u�����ƃ}���T�[�����肪�����B�Ȃ��A�u���{�����̋{��́A�p���̃T�����W�F���}���A�t�H���e�[�k�u���[�ɂ����������A�P�U�W�Q�N����t�����X�v���̖u������P�V�W�X�N�܂ł́A���F���T�C���{�a�ɋ{�삪�u���ꂽ�B�@�� |
| e�@�R���x�[��
| �@���@�R���x�[�� |
| �a �N���푈�̓W�J
| �@ |
| a�@��l�[�f�������g�p���푈
| �@ |
| b�@�I�����_�푈
| �@ |
| c�@�t�@���c�푈
| �@ |
| �b�@�i���g�̒��߂̔p�~
| �P�U�W�T�N�A���C�P�S�����i���g�̒�����p�~�����B���O�m�[�����̏�Ȃ��c���ɔ��Q���A���O�S������֎~���A����ɂ����ă~�T�ɖ�����o�Ȃ����A�j�O���z��̔@���ɉƑ��𗣎U�����A�j�̓K���C�D�ɑ���A���q���ɂ͕ڑł��Ƌs�҂������Ĕޏ���̊������@�����������܂��悤�Ƃ����B���̌��ʁA��\���̐l�X����ɃC���O�����h�A�I�����_���邢�̓v���V�A�ɖS�������B���̑唼�͍����ȐE�l�⏤�l�ł������̂Ńt�����X�̏��H�Ƃ��v�������B�܂��A�C�M���X�ł̋��c��`�ւ̑����傳���A�W�F�[���Y�Q���̃J�g���b�N����ɑ���c��̌x�������߂��B |
| a�@���O�m�[
| �@���@��X�́@�R�߁@���O�m�[ |
| �c�@�X�y�C���p���푈
| �P�V�O�P�`�P�S�N�́A�t�����X�C�M���X�E�I�[�X�g���A�E�I�����_�Ȃǂ̐푈�B�X�y�C���E�n�v�X�u���N���̃J�����X�Q���ɉ��ʌp���҂���������������A�t�����X�����C�P�S�������A���W���[���t�B���b�v���X�y�C�����t�F���y�T���Ƃ��Ď�����̎x�z������B����ɔ������C�M���X�i�E�B���A���R���j�E�I�[�X�g���A�E�I�����_���������A�푈�ƂȂ����B���[���b�p�ł̓C�^���A�E�l�[�f�������g�E�h�C�c�E�k�C�^���A�����ƂȂ�A����ɃA�����J�A���n�ł��C�M���X�E�t�����X�Ԃ��A�������푈���W�J���ꂽ�B�t�����X�R�͊e�n�Ŕs��A�A���n�ł��������B���̊ԁA�P�V�O�S�N�C�M���X���W�u�����^����́B�P�V�P�Q�N����I�����_�̃��g���q�g�Řa����k�A�P�V�P�R�N���g���q�g����A�P�S�N�̃��V���^�b�g���i�t�����X�ƃI�[�X�g���A�̍u�a�B�I�[�X�g���A�̃X�y�C���̃l�[�f�������g�̗̗L���F�߂�ꂽ�B�j�ŏI��B�t�B���b�v�̉��ʌp���͔F�߂��A�t�F���y�T���ƂȂ����i�X�y�C���E�u���{�����̎n�܂�j���A�t�����X�ƃX�y�C���̍����͉i�v�ɋ֎~����A�t�����X�͓����ɓW�J���ꂽ�C�M���X�Ƃ��A�������푈�ł��s��A�k�A�����J�嗤�̊C�O�̓y�i���݂̃J�i�_�̈ꕔ�j���C�M���X�ɒD��ꂽ�B�\�ʓI�ȏ����҂̓I�[�X�g���A�̃n�v�X�u���N�Ƃł��������A�����I�ɍł��傫�ȗ��v���̂̓C�M���X�ł���A���̐A���n�鍑�̊�Ղ�z�����ƌ�����B |
| a�@�t�F���y�T��
| �@ |
| b�@�C�M���X
| �@ |
| c�@�A�������푈 | �X�y�C���p���푈�ɕ��s���čs��ꂽ�C�M���X�ƃt�����X�̃A�����J�A���n�ɉ�����퓬�i�P�V�O�Q�`�P�R�N�j�B�X�y�C���A���n�̌p�������_�ƂȂ�B���C���h�ł̎��\�ߑD�̐퓬�A�j���[�C���O�����h�ł̃t�����X�E�C���f�B�A���A���R�̃C�M���X�R�U���Ȃǂ��������B�P�V�P�R�N�����g���q�g����ŃC�M���X�̓n�h�\���p�n���A�A�J�f�B�A�i�m���@�|�X�R�V�A�j�A�j���[�t�@�E���h�����h���l�������ق��A�X�y�C���̎��A�t���J���l�z��ꔄ���ł���A�V�G���g���l�������B |
| d ���g���q�g���
| �P�V�P�R�N�A�X�y�C���p���푈�Ȃ�т��A�������푈�̍u�a���Ƃ��Đ����B
�@�P�D�t�����X�ƃX�y�C�����������Ȃ����������Ƀt�F���y�T���̃X�y�C�����ʌp�������F
�@�Q�D�C�M���X�̓X�y�C�������W�u�����^���A�~�m���J�����l���A�t�����X����A�J�f�B�A�i�m���@���X�R�V�A�j�A�j���[�t�A���h�����h���l��
�@�R�D�I�����_�̓X�y�C���̃l�[�f�������g�̐��s���l��
�@�S�D�v���C�Z���͉�����F�߂���
�@�T�D�T���H�C�A�̓V�`���A�������l���i��ɃT���f�[�j�����ƌ����A�T���f�[�j�������ƂȂ�j
�i�t�����X�ƃI�[�X�g���A�͕ʂ����V���^�b�g���������j
���̏��ɂ���āA�C�M���X�͊C�O�̓y���g�債�A�C�M���X�鍑�ɉh�̑�P����z�����ƌ�����B
�������A�̓y�l���ɂ��܂��ė��j�I�Ӗ����傫�������̂́A�C�M���X���t�����X����A�A�t���J�̍��l�z���V�嗤�̃X�y�C���̂ɉ^���A�V�G���g�i�z�ꋟ���_��j�����n����A�����N�܁Z�Z�g���̑D��ǂ��A�f�Ղ̂��߃X�y�C���̃A�����J�ɔh�����鋖����������Ƃł������B���̌��ʁA�X�y�C���̃A�����J�嗤�A���n�x�z�͏I���������邱�ƂƂȂ����B
���g���q�g���̕t�я���F���g���q�g����ꂽ���N���ꂽ�t�я��ɂ���āA�C�M���X���A�V�G���g�i�z�ꋟ���_��j�����F����A�ނ����O�Z�N�Ԃɂ킽��A���N��Z�Z�Z�����̍��l�z����X�y�C���̃A�����J�A���n�ɗA�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����́A�������P�V�P�P�N�ɐݗ����ꂽ��C��ЂɈϑ������B����ɂ��ƁA��Ђ͐��A�t���J�ɔh�D���A���n�̉����A�t���J��Ђ̑㗝�l�����������̑D�ɓz����������邱�Ƃ���߂��Ă����B���̏��ɂ���āA�C�M���X�́A������K���r�A�삩��R���S�܂ł̐��A�t���J�C�݂̎x�z�����m�ۂ����̂ł���B�����c�`�Y�w���D�̊C�J���u�xp.157�� |
| �@���V���^�b�g���
| �X�y�C���p���푈��̂P�V�P�S�N�Ƀt�����X�����i�u���{�����j�Ɛ_�����[�}�鍑�i�n�v�X�u���N�Ɓj�̊ԂŒ������ꂽ�u�a���B���g���q�g����Ƃ͕ʂŁA�C�M���X��������Ă��Ȃ��̂ŁA�C�O�̓y�ł͂Ȃ��A���[���b�p�ł̗̓y�ύX�̎�茈�߁B�t�����X�ƃX�y�C���������I�ɔs�ꂽ�̂ŁA���C�P�S���́A����܂ŃX�y�C�����n�v�X�u���N�Ɨ̂ł�������l�[�f�������g�i����x���M�[�����j�E�~���m�E���F�l�c�B�A�E�T���f�[�j�����I�[�X�g���A���n�v�X�u���N�Ƃɏ��邱�ƂƂ����B�@�@ |
| e�@ ���C�P�T��
| �t�����X�E�u���{�����̍����i�݈ʂP�V�P�T�`�V�S�N�A���C�P�S���̑��ŁA���̎��̉��j�B�킸���T�ō����ƂȂ����̂ŁA�͂��߂̓I�����A�����t�B���b�v���ې��Ƃ��Đ���������A�P�V�Q�R�N����e�����J�n�B���������ł͔�r�I�����ł��������A�ΊO�I�ɂ̓C�M���X�Ƃ̐A���n�푈�Ŕs��A�܂����[���b�p�ł��I�[�X�g���A�p���푈�i�P�V�S�O�`�S�W�N�j�A���N�푈�i�P�V�T�U�`�U�R�N�j�ɉ���������A�v���C�Z���̑䓪�������ȂǁA����ȋǖʂ��}���Ă����B���̃��C�P�U���͔ނ̑��ɓ�����B���C�P�T�����N�Ղ����P�W���I�̃t�����X�ɂ́A���H���e�[���A���\�[�A�f�B�h���Ȃǂ��[�֎v�z���o�ꂵ�A�܂��v�z�ʂ���s���v�����������ꂽ����ł������B
Epi.�@�u�����x�z���鎞��v�|���p�h�D�[���v�l�@���C�P�T���̋{��ōł����͂��������̂́A���̈����|���p�h�D�[���v�l�ł������B�ޏ��͕����̏o�g�ł����������̔��e�ƍ˒m�Ń��C�P�T���̐S�����݁A�P�V�S�T�N�ȗ��{�����������͎҂Ƃ��ČN�Ղ����B�����ɊS�̂Ȃ����C�P�T���́A�|���p�h�D�[���v�l�̐����ɂւ̊֗^�������A�l���Ȃǂ��ޏ��ɔC�����Ƃ����B�t�����X�̊O����j���P�W�O���W�J�������u�O���v���v�ɂ�����Ă����B�ޏ��͌[�֎v�z�Ƃ̕ی�҂ł�����A�d�_��`�Œm����P�l�[�͔ޏ��̎厡��ł������B�܂��f�B�h���̕S�ȑS���̏o�ł���������������B����̐�[���s�������������킯�ŁA����u�����x�z���鎞��v�ƌ������Ƃ����B���������̂P�N�ō����P�O�O���t�������g���Ƃ��������O��̘Q��́A�u���{�����̍��������������A�t�����X�v���̗v���̂ЂƂƂȂ����B |
 |
| �I�D�v���C�Z���ƃI�[�X�g���A
|
| �P�D�v���C�Z��
|
| �`�@�v���C�Z������
| �@���@��X�́@�S�߁@�v���C�Z������ |
| a�@�X�y�C���p���푈
| �@���@�X�y�C���p���푈 |
| b�@�t���[�h���b�q�����B���w�����P��
| �v���C�Z���E�z�[�G���c�H���������̍����i�݈ʂP�V�P�R�`�S�O�N�j�B�v���C�Z�������̋��͂ȌR�������A�����������A�d����`������Ƃ�A�T�^�I�Ȑ�Ή�����W�J�����B���̑傫�ȓ����́A�u���S�̂ɂɂ���v�Ƃ���ꂽ�R����`����ł������B
Epi.�@���l�R��D���ȁu�������v�@�t���[�h���q���E�B���w�����P���́A���̗��\�ȐU�镑���A���{�̂Ȃ�����u�������v�Ƃ��������ꂽ�B�ނ̌R���̒��j�ƂȂ�߉q���͔w�̍������m�����낦�u���l�R�v�Ə̂��A����ڂ��������߂������ČP�������Ƃ����B�̂̑傫���A�����Ȏ�҂�����ƁA�x����������ɘA��Ă��āi���ɂ͖\�͂Łj�߉q���ɂ��Ă��܂����Ƃ����B���̂悤�Ȗ\�͂ŏW�߂��R���Ȃ̂ŁA�K�����\�͓I�ɂȂ�A�E���ɂ́u��ԕڑł��v�̔����^����ꂽ�B |
| c�@ ��Ή���
| �@����X�́@�S�߁@��Ή��� |
| �a�@�I�[�X�g���A�p���푈
| �P�V�S�O�`�S�W�N�܂ł́A�I�[�X�g���A�ƃv���C�Z���̑Η������Ƃ��āA�C�M���X���O�҂��A�o�C�G�������E�t�����X�E�X�y�C������҂��x�������A��Ή������ƊԂ̗̓y���߂���푈�B�P�V�P�R�N�A�I�[�X�g���A�̐_�����[�}�c��J�[���U���́A�n�v�X�u���N�Ƃ̒�ʌp���̌����Ƃ����v���O�}�e�B�b�V�F���U���N�c�B�I���i�d�v�ȍ����Ɋւ���N��̒�߂��u�����ُ��v�j���߂��B����ɂ̓n�v�X�u���N�Ƃ̗̓y�̕s���ƁA�j�q�̂��Ȃ��J�[���U���̎��̍c����}���A���e���W�A�Ɍp�������邱�Ƃ��߂Ă����B���[���b�p�����͂��̌�������������͔F�߂����A�J�[���U�����v����ƁA�܂��v���C�Z�����t���[�h���b�q�Q�����ًc���͂��݁A�����Ńn�v�X�u���N�Ƃ̎�̉����˂炤�t�����X�A�X�y�C��������ɓ������A�o�C�G�����������ʂ̌p�������咣���ĂP�V�S�O�N�ɐ푈���d�|�����B�t���[�h���q�Q���̓I�[�X�g���A�̂��V�����W�F���i�@�ƁE�z�Y�Ƃ�����j�̗̗L���˂���ĐN�������̂��V�����W�G���푈�Ƃ������B�I�[�X�g���A�̃}���A���e���W�A�͌Ǘ����ċ�킵�����A�A���n�Ńt�����X�E�X�y�C���Ɛ���Ă����C�M���X���A�I�[�X�g���A���ɂ����i�o�ϓI�����ɂƂǂ܂�R���̔h���͂Ȃ������j�̂Ő���Ԃ��A�P�V�S�W�N�A�A�[�w���a���ōu�a�������A�I�[�X�g���A�̓V�����W�F�����v���C�Z���ɒD��ꂽ�����̑��̗̓y�͊m�ۂ��A��ʌp�������F�����ďI������B���Q�ɔR�����}���A���e���W�A�́A�t�����X�Ƃ̒�g���͂���A�P�V�T�U�N���O���v���ɐ������A���̎��N�푈�ւƓW�J����B�I�[�X�g���A�p���푈�ƕ��s���āA�C�M���X�́A�X�y�C���Ɛ��C���h�������W�F���L���Y�̎��푈�A�t�����X�Ƃ͖k�đ嗤�ł��W���[�W���푈�ƃC���h�ł��J�[�i�e�B�b�N�푈��W�J���A�킢��L���ɐi�߂Ă����B |
| a�@�t���[�h���q�Q��
| �v���C�Z���E�z�[�G���c�H�������Ƃ̍����i�݈ʂP�V�S�O�`�W�U�N�j�B�T�^�I���[�ꐧ�N���Ƃ��ăv���C�Z���̑S�����������炵�u�t���[�h���q�剤�v�ƌ���ꂽ�B�ΊO����ł̓I�[�X�g���A���}���A���e���W�A�̑��ʂɈًc���������I�[�X�g���A�p���푈�i�P�V�S�O�`�S�W�N�j���������A�V�����W�F����D���A���̕��Q��ł������N�푈�i�P�V�T�U�`�U�Q�N�j�ł͍��ۓI�ɌǗ����Ȃ��炻�̗̓y���ێ������B���̌��ʁA�v���C�Z���̓��[���b�p�ŋ��̍��ƂƂȂ�A�h�C�c����̎哱�������邱�ƂƂȂ�B��������ł͌R���Ɗ������̐����A�d����`�o�ϐ���A������u�x�������v�𐄐i�����B�ނ̓t�����X�̌[�֎v�z�ƃ��H���e�[���Ƃ��e��������A�[�ꐧ��`���̗p���āu�N��͍��Ƒ��̖l�i�����ׁj�v�ƌ��������A���̖{���̓v���C�Z���̃����J�[�K������ՂƂ����������̏�ɐ��Ȍ��͂��s�g�����ꐧ�N��ł���B�x�������̍x�O�|�c�_���̗��{�ɁA���R�R���̑�\�I���z�ł����T���X�[�V�{�a�����������B
Epi.�@���ɔ��R�����t���[�h���q�Q���@�����t���[�h���q���E�B���w�����P���͖\�͓I�ȍ����ł��������A���̎q�t���[�h���q�͓N�w���D�݁A�t���[�g�����t���鉸�₩�ȐN�������B�Ⴂ���A���̖\�͂Ɍ��C�������A�t�����X�ɓ���悤�Ƃ������߂炦���A���s�����F�l���ڂ̑O�ŏ��Y�����Ƃ����V���b�L���O�Ȏ������������B���̎�����A���ς����̂��A�����ւ̓�����݁A�P�V�S�O�N�ɑ��ʂ����B�푈�ɖ����������A�w��ƌ|�p�ɗ�݁A���́u�������v�ɑ��A�u�N�l���v�ƌ���ꂽ�B�t���[�g�ł͍�Ȃ�����قǘr���グ���B�܂��w��ł̓��H���e�[���Ɏ���莆�������ċ����𐿂��A�_���w���}�L�A���F���_�x�������Č��悵���B���H���e�[���͂��̏����A�N��̏������ŗǂ̏��Ƃ��Đ�^�������A���̒��Ńt���[�h���q���}�L�A���F���̌��d�p����ے肵�A�N��͐l���ɑ�����̖l�ɂ����Ȃ��A�Ƙ_�����B�P�V�T�O�N�ɂ͎���̋{��̂���|�c�_���̍x�O�̖��J�{�i�T�����X�[�V�[�j�Ƀ��H���e�[���������Ă���B���̐e���͐e���ł��������A���H���e�[���͎���ɒ�q�Ƃ��Ă̌������ƍ����Ƃ��Ă̑��傳���g��������t���[�h���q�Ɍ��C�������悤�ɂȂ�A��l�͍��ׂȂ��Ƃ��炯�ʂ�����Ă��܂��A���H���e�[���̓p���ɋA��B |
| b�@�}���A���e���W�A
| �@���@�Q�D�I�[�X�g���A�@�}���A���e���W�A |
| c�@�V�����W�G��
| ���݂̃|�[�����h�̃I�[�f���쒆�E�㗬�n��B�P�S���I�ȗ��{�w�~�A�����̂ƂȂ�A�P�T�Q�U�N�Ƀn�v�X�u���N�Ƃ̏��̂ƂȂ����B�S�E�ΒY�̎Y�n�ł���A�P�W���I�����A�@�ƁE�z�Ƃ�������ŁA�h�C�c�ł͗B��̍H�Ƃ����B���Ă���n��ł���A�l�����P�O�O���ɒB���Ă����B�v���C�Z�����t���[�h���q�Q���́A���Ȃ̕n��ȍ��y�ɁA���̒n�������邱�Ƃ�M�]���A�킸���Ȍ����ł��̕��������B�I�[�X�g���A�p���푈�̌��ʂP�V�S�O�N�Ƀv���C�Z���ɐ�̂���A�A�[�w���̘a���ŃI�[�X�g���A�͊�����F�߂��B���̌�A�I�[�X�g���A�̃}���A���e���W�A�̓V�����W�F���D�҂�ڂ����A�Ăуv���C�Z���Ƃ����N�푈�ƂȂ������A�Ăєs��A�V�����W�F���̓v���C�Z���̂Ƃ��ď��F���ꂽ�B���̌�A�v���C�Z���������甭�W�����h�C�c�鍑�̂Ƃ�A�h�C�c�l�̈ڏZ���������B�P�X�P�X�N�A��P�����E���Ńh�C�c�鍑���s��ĉ�̂����̂ŁA���F���T�C�����ɂ���ăV�����W�F���̓|�[�����h�A�`�F�R�ɕ�������邪�A��Q�����Ńh�C�c���ĕ����A����ɑS�V�����W�F�����|�[�����h���ƂȂ�A�h�C�c�n�Z���͓P�ނ��Č��݂ɂ������Ă���B���S�s�s�u���X���E�i�|�[�����h�������c���t�j�B�߂��Ƀ����S���R�ƃ|�[�����h�R����������[���V���^�b�g�i���[�O�j�b�c�j������B |
| d�@�o�C�G������
| �h�C�c����̂ЂƂo�C�G�����I���i�o�C�G�����̓o���@���A�Ƃ������A�h�C�c�암�̃~�����w���𒆐S�Ƃ����n���j�B�Ȃ��n�v�X�u���N�Ƃ̏o�g�i�}���A���e���W�A�̂��Ƃ��j�ł������̂ŁA�n�v�X�u���N�Ƃ̑��������咣�����B |
| e�@�t�����X
| �@ |
| f�@�C�M���X
| �@ |
| �A�[�w���̘a��
| �P�V�S�W�N�A�I�[�X�g���A�p���푈�̍u�a���B�t�����X�E�X�y�C���ƃI�[�X�g���A�Ȃǂ̊Ԃłނ��ꂽ�B�I�[�X�g���A�R���t�����X�R�ɔs�ꂽ�����߁A�I�[�X�g���A�̓}���A���e���W�A�̒�ʌp�������O���ɔF�߂���������ɁA�v���C�Z������̂��Ă����V�����W�F�������������B |
| g�@�O���v��
| �@���@�O���v�� |
| �b�@���N�푈
| �P�V�T�U�`�U�R�N�̃v���C�Z���ƃI�[�X�g���A�̑Η������ɁA�v���C�Z���̓C�M���X�ƁA�I�[�X�g���A�̓t�����X�A���V�A�ƌ��сA�S���[���b�p�ɍL�������푈�B�C�M���X�ƃt�����X�̐A���n�ɂ�����푈�ƌ��т��A���E�I�ȍL��������푈�ƂȂ����B���ʂ̓v���C�Z���ƃC�M���X�̏����ƂȂ�A���[���b�p�ł̃v���C�Z���ƒn�ʂ����コ���A�C�M���X�̐A���n�鍑�Ƃ��Ă̔ɉh�������炳�ꂽ�B�����ɂ��̐푈�͐�Ή����e���̍������������A�C�M���X����̃A�����J�A���n�̓Ɨ��A����уt�����X�v���Ƃ����s���v���������������Ƃŏd�v�ł���B
�o�܁F�I�[�X�g���A�p���푈�Ŕs��̓y���������I�[�X�g���A���}���A���e���W�A�́A��_�ȊO�𐭍�̕ύX�Ńt�����X�ƒ�g���邱�Ƃɐ����i�O���v���j���A�v���C�Z�����Ǘ������炽�B����ɑ��ăv���C�Z�����t���[�h���q�Q�����A�`���̋t�]���˂���ăI�[�X�g���A�̂ɐN�����A�푈���J�n���ꂽ�B�v���C�Z���R�̓v���n�A���X�o�n�A���C�e���Ȃǂ̐퓬�ŏ����������A�t�����X�R�̖{�i����ɂ���ĂT�X�N�̃N�l���X�h���t�̐킢�ɔs��A�ꎞ�x���������̂���A��@�Ɋׂ����B���������V�A�łP�V�U�Q�N�ɏ���G���U���F�[�^�i�s���[�g�����̖��j���}�����A�t���[�h���q�Q���𐒔q���Ă����s���[�g���R��������ƂȂ������߂ɒP�ƍu�a�ɉ����A���s���čs��ꂽ�p���A���n�푈���t�����`�E�C���f�B�A���푈�A�v���b�V�[�̐킢�Ńt�����X���s�ꂽ���Ȃǂ���A�v���C�Z���͐푈��ς��������B�P�V�U�R�N���t�x���g�D�X�x���N�̘a�c�ŃV�����W�F���̗̗L���I�[�X�g���A�ɔF�߂������B
�e���F���́A�v���C�Z���̍��ۓI�n�ʂ����サ�A�C�M���X�̐��E�A���n�鍑�������������A�k�ĐA���n�ւ̉ېł������������ߔ����������Ȃ�A�A�����J�Ɨ��푈���n�܂�B�I�[�X�g���A�̓��[�[�t�Q���̌[�ꐧ��`�ɂ����v�Ɍ������A�t�����X�͍��ɂ̋������[���ɂȂ�A���Ƀt�����X�v�����u������B���N�푈�͂����̂P�W���I�㔼�̌����̈������ƂȂ����푈�ł������B
���v���C�Z���̏����̗v���@�v���C�Z���̓I�[�X�g���A�E�t�����X�E���V�A����ɃX�E�F�[�f�����ɓG�ɉĐ�����B�C�M���X�̓v���C�Z�����ɂ��������͂͑��炸���������ɂƂǂ܂����B�܂��ɐl���I�ɂ͂R�O�P�̐킢�ŁA�����̏펯���炵�ď��Ă�킯�̂Ȃ��킢�ł���i�����̐��̓v���C�Z���Q�O���A�A���R�S�O�����炢�B�j�����t���[�h���b�q�剤�͏����Ȃ������B��v�Ȑ퓬�͂P�U���āA���̔����͕������̂ł���B�������A�ŏI�I�ȕ��a���ɂ����ăV�����[�W�F���ƃO���[�c�邱�Ƃ��ł����B�t���[�h���b�q�剤�ƃv���C�Z���R���R�O�P�̐푈�����Ƃ��������R�͎��ł���B
�@1.��������ɐ��ɂ�����ō��i�ߊ��ł���A�����J�[�K�������Z�c�Ƃ��Ē蒅���Ă����B
�@2.�����푈�̃L�[�|�C���g�Ƃ��ēG�̕⋋�H��f�헪�����{�����B���̂��߂ɍs�R���x�𑬂߂�H�v�������B
�@3.���i�ȌR���ƓO�ꂵ�������̓`���B
�@4.�剤�́u�H�v�̍ˁv�B��C��e�̐��\�����߂�H�v������s�����B
���n������w�h�C�c�Q�d�{���x�����V���@p.23-24�� |
| a�@�C�M���X
| �@ |
| b�@�t�����X
| �@ |
| c�@���V�A
| �@ |
| �t�x���g�D�X�x���N���
| �P�V�U�R�N�A���N�푈�̍u�a���Ƃ��āA�v���C�Z���ƃI�[�X�g���A�̊ԂŒ������ꂽ�u�a���B�t�x���g�D�X�x���N�̓��C�v�c�B�q�̋ߍx�B���e�͎��̓�_�B
�E�V�����W�F���̓v���C�Z���̂ł邱�Ƃ��I�[�X�g���A�͍ď��F����B
�E�v���C�Z�����t���[�h���q�Q���́A�I�[�X�g���A�̃��[�[�t�i�}���A���e���W�A�̑��q�B�����̓I�[�X�g���A����j�������_�����[�}�鍑�c��ɑI�o�����Ƃ��͂���ɋ��͂��邱�Ƃ�B�@ |
| �c�@�[�ꐧ��`
| �P�W���I�㔼�̃��[���b�p�̐�Ή������Ƃ̌N��Ɍ���ꂽ�������_�B���Ƀv���C�Z�����t���[�h���q�Q���A�I�[�X�g���A�����[�[�t�Q���̐������T�^�I�Ȍ[�ꐧ��`�ł���A���V�A���G�J�`�F���[�i�Q��������ɋ߂��ƌ�����B�����̌N����[�ꐧ�N���Ƃ����B�P�W���I�̃t�����X�ɋN�������[�֎v�z�́A���R�@��Љ�_����Ɋ�Â��A�l���╽���̎v�z�ݏo�������A�[�ꐧ�N��͂����̎v�z���A�u�����_�����v�ɂ����N��̓����ɗ��p���A�N��̓���I�x�z�̗��O�Ɏ����ꂽ�B����ɂ��A�N������Ƃ̈�@�ւƂ��č����ɕ�d������̂ł��邪�A���̍��������ɂ���Đ�f���邱�Ƃ��ł��A���@�A�i�@�A�s���̎O�����������Ƃ��Ă��A�����͂����܂ŌN��̌��͂�₤���̂ɂ����Ȃ��Ƃ��ꂽ�B�܂��A�����̎��R�ƕ�������������Ă��炸�A�ނ�̂��܂��܂Ȍ������F�߂���Ƃ��Ă��A�����܂ŌN�傩��̉����Ƃ��ė^�����Ă�����̂Ƃ��ꂽ�B�܂��o�ϊ��������Ƃ��Ǘ����Ă��̕ی쓝���̂��Ƃɍ����Y�Ƃ��ی삳���d����`���Ƃ�ꂽ�B |
| a�@�t���[�h���q�剤
| �@���@�t���[�h���q�Q�� |
| b�@�u�N��͍��Ƒ��̖l�v | �v���C�Z�������t���[�h���q�Q���̌��t�ŁA�[�ꐧ��`�̗��O��[�I�ɒ[�I�Ɍ����\���Ă���B |
| c�@���H���e�[��
| �@���@���H���e�[�� |
| d�@�[�ꐧ�N��
| �[�ꐧ��`�����Ɠ������O�Ƃ����N�傽���ŁA�P�W���I�㔼�̃v���C�Z�����t���[�h���q�Q���A�I�[�X�g���A�����[�[�t�Q���A���V�A���G�J�`�F���[�i�Q���Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B�ނ�̓C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̐�i�n��ɑR���邱�Ƃ��ӎ����A���Ƃ̔��W���Y�Ƃ�f�Ղ̐U���A�R���͂̋����Ȃǂɂ���Đ}�낤�Ƃ����B����ɕK�v�ȋZ�p��������A���Ƌ@�\�̈��́u�ォ��̉��v�v�ɂ���ċߑ㉻��}�邽�ߌ[�֎v�z�Ɋw�сA�����̉����_�����ɑ��铝�����O�Ƃ��悤�Ƃ����̂ł������B |
| e�@�s���w
| �@ |
| f�@�N��
| �@ |
| g�@�����J�[
| �@���@�����J�[�@ |
| h�@�_�z
| �@ |
| �Q�D�I�[�X�g���A
|
| a�@�I�[�X�g���A | �@���@�I�[�X�g���A |
| b�@�v���O�}�e�B�b�V�F���U���N�e�B�I�� | �P�V�P�R�N�A�_�����[�}�c��J�[���U������߂���ʌp���Ɋւ��钺�߁B�n�v�X�u���N�Ɨ̂̕s���ƁA���q�̑��������߂����̂ŁA����}���A���e���W�A�̒�ʌp���̍����ƂȂ�A����Ɉًc���������v���C�Z���ȂǂƂ̊Ԃ��I�[�X�g���A�p���푈���N����B
�v���O�}�e�B�b�V�F���U���N�`�I���Ƃ́u�����Ɋւ��钺�߁i�c��̖��߁j�v�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A��ʓI�ɂ͂��̎��ɏo���ꂽ�A�c��ʌp���@���w���Ă���B���e�̓n�v�X�u���N�Ƃ̉Ɨ̂̕s���i�����ł��Ȃ����Ɓj�Ə����̑�������F�߂����́B�{���̓n�v�X�u���N�Ƃ̉ƌP�ł��������̂�_�����[�}�鍑�̍����Ƃ��č��ۓI�ȏ��F�悤�Ƃ����̂��˂炢�ł���B���̗��R�́A�J�[���U���̒��j���ᎀ�ɂ��A���̔N���q���}���A���e���W�A�����܂ꂽ�̂ŁA�������̎q���c����p�����邱�ƒ鍑���O�ɔF�߂����邱�Ƃɂ������B�I�[�X�g���A�x�z���ɂ������{�w�~�A�A�N���A�`�A�A�n���K���[�Ȃǂ̋c��́A���̎�����F�߂邱�Ƃ������ɏ��F�����B�������₪�ĂP�V�S�O�N�ɃJ�[���U������������ƁA���̋K��ɏ]���ă}���A���e���W�A����ʂ��p������ƁA���ꂼ�ꏳ�F��P�A�v���C�Z���̃t���[�h���q�Q���Ȃǂ��ًc��\�����āA�I�[�X�g���A�p���푈�ƂȂ����B |
| �`�@�}���A���e���W�A | �I�[�X�g���A���n�v�X�u���N���̏���i�݈ʂP�V�S�O�`�W�O�N�j�B���J�[���U���̒�߂���ʌp���@�i�v���O�}�e�B�b�V�F���U���N�c�B�I���j�ɂ���ăn�v�X�u���N�Ƃ̉Ɠ𑊑������B���̑����Ɉًc���͂��v���C�Z�����t���[�h���q�Q����o�C�G�������̊��ɂ���āA�P�V�S�O�N�A�I�[�X�g���A�p���푈���u���A�v���C�Z���R�ɃV�����W�F�����̂��ꂽ�B�t�����X���v���C�Z�����x�����A�B��t�����X�ƑΗ����Ă����C�M���X���I�[�X�g���A���x���������A�o�ϓI�����ɂƂǂ܂�A�R���̔h���͂Ȃ������B���n�ɗ������}���A���e���W�A�͓����ݎq�i��̃��[�[�t�Q���j������ăn���K���[�ɓ���A�����r���ɐg����Ńn���K���[�M�������ɒ�R���Ăт������B���̌㍢��ȓ�����蔲�����}���A���e���W�A�́A�V�����W�F���͎��������̂́A�I�[�X�g���A�c��̒n�ʂ�v�̃g�X�J�i����t�����c���p������i�t�����c�P���j���Ƃ����F�����āA�P�V�S�W�N���A�[�w���̘a���Ő푈���I��点���B�s���A�I�[�X�g���A�̌R���A�����@�\�̉��v�ɏ��o���A�O���ł̓t�����X�̃u���{���Ƃƌ����O���v�����������ăv���C�Z�����Ǘ������邱�Ƃɐ������A�Ăуv���C�Z���̃t���[�h���q�Q���Ƃ����N�푈�i�P�V�T�U�`�U�R�N�j�������B�������V�����W�F���D��͎��s���A�P�V�U�T�N�ȍ~�͑��q�����[�[�t�Q���Ƃ̋��������ƂȂ肻�̐����������A�I�[�X�g���A�鍑�𑶑��������B�t�����X�̃��C�P�U���̉��܂ƂȂ����}�����A���g���l�b�g�̓}���A���e���W�A�̖��ł���B
Epi.�@�}���A���e���W�A�̎̂Đg�̑i���@�I�[�X�g���A�p���푈�ł̓t�����X�̌R������Ń}���A���e���W�A�͐�̐▽�̋��n�ɗ������ꂽ�B�ޏ����Ō�ɖ]�݂�������̂̓n���K���[�̋M���ł������B�n���K���[�M���̓I�[�X�g���A�̎x�z����E����D�@�ƍl���A���I�[�X�g���A�I�N����Ă�̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����Ă������A�ޏ��͂����ċt�̍s�����Ƃ����B�S�P�N�X���A�ޏ��͌��݂̃u���`�X�����@�ŊJ��̃n���K���[�c��ɁA�����ݎq�j���[�[�t�i���̍c��j���������Č��I�ɓo�ꂵ�A�ւ荂���n���K���[�M���ɗ܂Ȃ���x����i�����B����Ɋ��������c������u��炪�����A�����A�c���Ɍ��Ɩ����v�̋��т��N����A�U���̏o�����̑��̎x�������t�����̂ł���B�ޏ����n���K���[���@�̏���A�M���̖Ɛœ����A�s���I�����̕ۏȂǂ�����B���w�h�i�E�E���[���b�p�j�x�V�Ő��E�e���j�@�R��o�ŎЁ� |
| a�@�I�[�X�g���A�p���푈
| �@���@�I�[�X�g���A�p���푈 |
| b�@�u�O���v���v
| �I�[�X�g���A�p���푈��ɁA�}���A���e���W�A�̃I�[�X�g���A�E�n�v�X�u���N�Ƃ��A����܂ł̊O����j����ς����āA�t�����X�̃u���{�����Ɠ����������ƁB����ɂ���āA�P�W���I�㔼�̃��[���b�p���ې����̑Η����́A�C�M���XVS�t�����X�A�v���C�Z��VS�I�[�X�g���A�Ƃ�����d�Η��ɏW��A�C�M���X�ƃv���C�Z���A�t�����X�ƃI�[�X�g���A����������Ƃ����\�}�ɂȂ����B���̊O���v���𐄐i�����̂́A�}���A���e���W�A�̐M�C�̌����J�E�j�b�c���Ƃ����l���ŁA�ނ̓I�[�X�g���A�p���푈��ɒ��t�����X��g�Ƃ��ĕ��C���A���C�P�T���̋{��Łu�����̏����v�ƌ����Ă������̈����|���p�h�D�[���v�l�����A�I�[�X�g���A�Ƃ̓����ɓ��ݐ点���B�t�����X�̓C�^���A�푈�ȗ��̃n�v�X�u���N�ƂƂ̑Η�����A���̎�̉���}�邽�߂Ƀv���C�Z���ƌ���ł������A�v���C�Z��������ȏ㋭�͂ɂȂ邱�Ƃ����ꂽ�̂ł��낤�B�܂��I�[�X�g���A�͂���܂ŃC�M���X�ƌ���ł������A�C�M���X�̓t�����X�Ƃ̐A���n�푈���d�����A�o�ϓI�����݂̂ŌR���𑗂邱�Ƃ͂Ȃ������̂ŕs�M�������߂Ă����B���̂悤�Ȏ����w�i�ɁA���I�ȃ��[���b�p���ې����̓]�����͂���ꂽ�̂������B�O���v���ɂ���đ嗤���ŌǗ������v���C�Z�����t���[�h���q�Q���́A�`���t�]���˂���čĂуI�[�X�g���A�ƊJ�킷��B���ꂪ���N�푈�ł���B |
| d�@���N�푈
| �@���@���N�푈 |
| �a�@���[�[�t�Q��
| �P�V�U�T�N����A���}���A���e���W�A�Ƌ����������s�����I�[�X�g���A�E�_�����[�}�c��i�݈ʂP�V�U�T�`�X�O�N�j�B��l�͂͂��߂͂��܂������Ă������A���[�[�t�Q��������Ɍ[�֎v�z�̉e�����A���v�H�������߂Ă����ƁA�[�֎�`���������}���A���e���W�A�Ƃ̈ӌ��̈Ⴂ���ڗ����n�߂��B���[�[�t�Q�����[�ꐧ��`���Ƃ�A�t���[�h���q�Q���ɕ�����ォ��̋ߑ㉻����𐄂��i�߁A�M�̎��R�A�_�z���̔p�~�ƂƂ��Ɏi�@���x�A�x�@���x�ȂǂŒ����W������}�����B�������A���̉��I�Ő��}�ȉ��v�́A�I�[�X�g���A�x�z���̃n���K���[��x�[�����A�x���M�[�ȂǂŔ��������܂�A�������Ȃ����B�I�[�X�g���A�͑��������Ƃł���A�܂����y���o���o���ł��邱�Ƃ��Ȃɂ������̓���x�z������Ȃ��̂ɂ��Ă����B |
| a�@�n�v�X�u���N | �@ |
| ��b�@������������
| �@ |
| c�@�`�F�b�N�l | �@���@��U�́@�Q�߁@�`�F�b�N�l |
| d�@�}�W���[���l
| �@���@��U�́@�P�߁@�}�W���[���l |
 |
| �J�D�o���g�C�̔e��
|
| ���V�A�鍑�̔��W�@�@���@���V�A���� |
| �`�@�s���[�g���P��
| ���V�A�����}�m�t���̔ɉh���o���������c��i�݈ʂP�U�W�Q�`�P�V�Q�T�N�j�B�s���[�g������ƌ�����B�X�U�N����P�Ɠ������s���A�X�V�`�X�W�N�A�c��ł���Ȃ��烈�[���b�p�e���̎��@������s���B���̗��s�Ŏh�����ĐϋɓI�������������𐄐i�A�����̋Z�p�҂𑽐����ق��A�Y�Ƃ̋ߑ㉻���s�����B����ł��I�X�}���鍑�����A�]�t���l���A�k���ł̓o���g�C�̔e�����߂����ăX�E�F�[�f���Ƃ��k���푈��킢�A�ꎞ�͔s�k���i������������@�ɌR���𐮂��A�|���^���@�̐킢�ɏ������ăo���g�C�̔e�҂ƂȂ����B�o���g�C���݂ɖʂ��ĐV�s���y�e���X�u���N�����݂����B�܂������ł̓V�x���A�i�o�𐄂��i�߁A���̍N����Ƃ̊Ԃ��l���`���X�N�������������B�܂��x�[�����O��h�����ăJ���`���b�J�A�A���X�J���ʂ�T���������B�R���ł͓��ɊC�R�̈琬�ɓw�߁A�y�e���u���N�̋߂��̃N�����V���^�b�g�v�ǂ����_�Ƀo���`�b�N�͑���n�݂����B
Epi.�@�s���[�g���̃��[���b�p��K�@�P�U�X�V�N�A���V�A�̐����[���b�p�����ւ̑�g�ߒc���Ґ����ꂽ�B�s���[�g���́u�s���[�g�����~�n�C���t�v�Ƃ����ϖ��ŁA�ꐏ���Ƃ��ĉ�������B�܂��v���C�Z���̃P�[�j�q�X�x���N�ŖC�p���K�����B�I�����_�ɂ͂���ƃs���[�g���͒P�ƍs�����Ƃ�A���D���ň�E�H�Ƃ��ē����n���}�[���ӂ���đ��D�Z�p���K�������B�S�����ɂ킽��I�����_�؍݂ő��D���ɓ��Q�����ق��A�����فA�a�@�A�ٔ��������w���A���C�f����w�ł͉�U�w�̍u�`�����B�X�ɑ��D�w���w�Ԃ��߃C�M���X�ɓn��A�E�B���A���R���Ɋ��}����A���D���ŋZ�t���K���Ƃ��ē����A�C�e�H��Ȃǂ����w�����B���̃s���[�g���̃v���C�Z���A�I�����_�A�C�M���X��K�́A���V�A�̐���������̌_�@�ƂȂ�A�܂��k���푈�����������͂ƂȂ����B�����^�|�ҁw���E�̗��j�x�W�@1961�@�������_�Ё@�Ȃǂɂ�遄 |
| a�@���}�m�t��
| �@���@��X�́@�S�߁@���}�m�t�� |
| b�@����������
|  �P�V���I�͂��߁i�P�U�P�R�N�j�ɐ����������V�A�E���}�m�t���́A�X�E�F�[�f�������A�|�[�����h�����Ɉ�������A�����[���b�p�ł͎㏬���͂ɂ����Ȃ������B�����ɂ͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�z������ՂƂ����L�͋M�������݂��A�Y�Ƃ����n�ł���A�ߑ�I�ȌR���̑n�݂��}����Ă����B�����Ń��}�m�t���̃c�@�[���́A�����[���b�p�����ɏK�������Ƃ̑n�o���߂����A���x�E�Y�Ƃ̐�������i�߂��B���ɋ}���ɐi�߂��̂��s���[�g���P���i���j�ł������B�s���[�g���P���̎���ɁA�Y�ƁE�R���E�Ő��E�������Ȃǂœ��Ƀv���C�Z������{�Ƃ������v���s��ꂽ�B�������A�Љ�̍����ɂ���_�z���ɂ͊�{�I�ɂ͎�������A�u�ォ��̉��v�v�ɂƂǂ܂�A�u���V�A�̌�i���v���ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B �P�V���I�͂��߁i�P�U�P�R�N�j�ɐ����������V�A�E���}�m�t���́A�X�E�F�[�f�������A�|�[�����h�����Ɉ�������A�����[���b�p�ł͎㏬���͂ɂ����Ȃ������B�����ɂ͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�z������ՂƂ����L�͋M�������݂��A�Y�Ƃ����n�ł���A�ߑ�I�ȌR���̑n�݂��}����Ă����B�����Ń��}�m�t���̃c�@�[���́A�����[���b�p�����ɏK�������Ƃ̑n�o���߂����A���x�E�Y�Ƃ̐�������i�߂��B���ɋ}���ɐi�߂��̂��s���[�g���P���i���j�ł������B�s���[�g���P���̎���ɁA�Y�ƁE�R���E�Ő��E�������Ȃǂœ��Ƀv���C�Z������{�Ƃ������v���s��ꂽ�B�������A�Љ�̍����ɂ���_�z���ɂ͊�{�I�ɂ͎�������A�u�ォ��̉��v�v�ɂƂǂ܂�A�u���V�A�̌�i���v���ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
Epi.�@�s���[�g���A�M���̕E����@�s���[�g���͊O�V����A������ƁA���̕������������ɉ��߂��B�����Ĉ��A�ɂ����M����߂܂��ẮA���ɍT�������тƂɗr�їp�̃n�T�~���������A�����Ђ����������Ă��܂����B���V�A�̋M���͐̂��炠���Ђ���~����̂��K���ł��������A�s���[�g���́u�V�������V�A�v�ɂ͂�����Ȃ��ƁA�M�������̂����Ђ�����Ă��܂����̂ł���B�E�̊G�͓����̃s���[�g���̖��߂ŋM���̕E��邱�тƂ�`�������́B |
| c�@�l���`���X�N���
| �@���@��W�́@�Q�߁@�l���`���X�N��� |
| d�@�N����
| �@���@��W�́@�Q�߁@�N���� |
| ��e�@�x�[�����O
| �s���[�g��������x�[�����O�ɃV�x���A���n�̒T���𖽂����̂́A�Ȋw�҃��C�v�j�b�c�Ƃ̖�����������ł������B���C�v�j�b�c�͂P�V�P�R�N�A�s�������g�Ńs���[�g���P���Ɛ��������ɂ��A�A�W�A�嗤�ƃA�����J�嗤���Ȃ����Ă���̂��ǂ����̋^��������ł���͍̂c��������Ă��Ȃ��A�Ɛi�����Ă��B���̖��v���o�����s���[�g�����́A���̂R�T�ԑO�ɃV�x���A���n�T���𖽂��鏐���������B�����ɑI�ꂽ�x�[�����O�̓f���}�[�N���܂�ŊC���ƂȂ�C���h�q�C�ȂǂŖ��������A�c��ɂ���ă��V�A�C�R�ɍ̗p����Ă����B�P�V�Q�T�N�Q���y�e���u���O���o���A�R�N�ȏ�̓����������ăj�W�l�E�J���`���b�J�ɒ����A�����ŒT���D���K�u���[�������������A�P�V�Q�W�N�W���P�T���ɖk��67�x18���ɒB���D����ɓ]�����B�x�[�����O�͂���ŊC���̑��݂͖��炩�ɂȂ����ƍl�������A�A�����J�嗤���m�F���邱�ƂȂ��A�H�ɒ����A�P�V�R�O�N�R���P���Ƀy�e���u���O�ɋA�҂����B�P�V�S�P�N�A�ĂуJ���`���b�J�T�����s�����x�[�����O�̈�����A�����J�嗤�̈ꕔ�ɓ��B�������A�x�[�����O�͋߂��̖��l���Ŏ��B���������N�w�V�x���A�ɜ߂��ꂽ�l�X�x��g�V��P.31-52�� |
| �@�A���X�J
| �P�V�S�P�N�A���V�A���x�[�����O���x�[�����O�C����n���ē��B���A���V�A�̂ƂȂ����B�@���@�A�����J�ɂ���A���X�J���� |
| f�@�I�X�}���鍑�i���V�A�̐N�o�j | �P�V���I���`�P�W���I���߂̃s���[�g�����ȗ��A���V�A�̓o���J����������э��C���ʂւ̐N�o�����݁A�I�X�}���鍑�̗̓y��N�Ƃ��n�߂��B���̓����͂P�X���I�ȍ~����Ɍ������Ȃ郍�V�A���쉺�����̎n�܂�ł���A�������������ɂȂ����Ă����B
���V�A�ƃI�X�}���鍑�i�g���R�j�̐푈�́A�L���Ӗ��̃��V�A���g���R�푈�ƌ����邪�A����͂P�W�`�P�X���I�ɐ����ɂ킽���ēW�J����Ă���B�P�U�X�U�N���s���[�g��������A�]�t���̂��ċN�������푈�i�P�V�U�X�N�ɏI���j�A�����łP�V�U�W�N���G�J�`�F���[�i�Q�����d�|���A�P�V�V�S�N���L���`���N���J�C�i���W������ŗ��C���̍q�s���Ȃǂ��l�������푈�ɂ���đ���������߂��B���̌�P�X���I�ɓ���A�N���~�A�푈�i�P�W�T�R�`�T�U�j�ł̓��V�A�͔s�k���A����ɘI�y�푈�i�����Ӗ��̃��V�A���g���R�푈�A�P�W�V�V�`�V�W�N�j�ŃI�X�}���鍑��j�������A���[���b�p�e���̉���������A�x��������c�Ō�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�B |
| g�@�k���푈
| �P�V�O�O�N�`�P�V�Q�P�N�A�����̐V�������V�A�̃s���[�g����邪�A���[���b�p�̑卑�X�E�F�[�f�����x�z����o���g�C���ʂɐi�o����ċN�������푈�B���V�A�͋��̖��A�o���g�C�i�o���ʂ����A�P�W���I�̑卑���̑����ƂȂ����B
�P�V���I�̃X�E�F�[�f���͎O�\�N�푈�ɉ�����A�E�F�X�g�t�@���A���Ŗk�h�C�c�Ȃǂɂ��̓y�āA�o���g�C�S����x�z���郈�[���b�p�L���̑卑�ƂȂ��Ă����B���V�A���s���[�g���P���̓o���g�C�ւ̏o�������߂ăX�E�F�[�f���̎x�z����o���g�C��тɌR��i�߂����A�P�V�O�O�N�̃i�����@�̐킢�œ����P�W�̐N�����J�[���P�Q���ɗ�����ꂽ�X�E�F�[�f���R�ɑ�s����B�s���[�g���P���͉�ł����R���̍Č��Ɏ�肩����A���V�A�ōŏ��ɒ������x�������A�P�V���̏���R��Ґ������B�����C���@�̏����W�߂đ�C�𒒑����A�R�������������B���̏�łX�N��ɍĂуX�E�F�[�f���ɒ���A�P�V�O�X�N���|���^���@�̐킢�ő叟�����B�s���[�g���͌R�X�ƌC���e�e�Ɏ˔����ꂽ���A�ꖽ�����Ƃ߁A����̃J�[���P�Q���͏d�����A�g���R�ɂ̂��ꂽ�B���̃|���^���@�̐킢�́A�����X�E�F�[�f���̖v���A�V�������V�A�̑䓪�������炵�A�u���[���b�p�̓]�@�v�ƂȂ����A�ƌ����Ă���B�|���^���@�̏����ɂ���ă��[���b�p�ւ̓����J�������V�A�́A�o���g�C�ɖʂ����y�e���u���N�����݂��A�V�s�Ƃ����B�P�V�Q�P�N�A�j�X�^�b�g�̘a���ōu�a�����B |
| �j�X�^�b�g�̘a��
| �P�V�Q�P�N�ɒ������ꂽ�A���V�A�ƃX�E�F�[�f�����k���푈�̍u�a���B�j�X�^�b�g�͍u�a��c�̊J�Â��ꂽ�t�B�������h�̒n���B���V�A�̓��K���܂݃����H�j�A�A�G�X�g�j�A�A�C���O���A�A�J�����A�̈ꕔ�Ȃǃo���g�C���݂̒n����l���B�X�E�F�[�f���̓��V�A�ɐ苒����Ă����t�B�������h���������A�������̎x�����̋`�������B�����͏��Ƃ̎��R������A���V�A�͔O��̃o���g�C�i�o���ʂ����A�X�E�F�[�f���͂��̔e�����������B���V�A�̔��W�ɂƂ��ďd�v�ȓ]�@�ƂȂ���ł������B |
| h�@�J�[���P�Q��
| �X�E�F�[�f���͂P�V���I��ʂ��A�J�[���P�O���A�J�[���P�P���ƗL�\�ȌN�傪�����A�h�G�f���}�[�N�Ƃ̐푈��L���ɐi�߂ė̓y���g��A���݂̃X�J���W�i�r�A�����̑啔���ƁA�t�B�������h�A�G�X�g�j�A�A���g���B�A��̗L���A�u�o���g�鍑�v�ƌ���ꂽ�B�J�[���P�Q�������ʂ��p���i�݈ʂP�U�X�V�`�P�V�P�W�N�j�������A�V���͂킸���P�T�A���̋@�ɏ悶�ă��V�A���s���[�g���P�����o���g�C�i�o��������݂P�V�O�O�N�A�k���푈���u�������B�����̃i�����@�̐킢�ł͏����������A�Ԑ��𗧂Ē��������V�A�R�Ƃ̂P�V�O�X�N���|���^���@�̐킢�ɔs��A�X�E�F�[�f���͔s�ނ��A�o���g�鍑�͕����B
Epi.�@�u�헐�̍����v�X�E�F�[�f�����J�[���P�Q���@�J�[���P�Q���́A���ʓI�ɃX�E�F�[�f����j�łɒǂ���������A�ǖقŐ��i���������A�e����̉����u���ꂼ�킪���y�v�ƌ����A���̐��U��ʂ��Đ�w�����w�����M�O�̐l�ł������B�P�W�̍����Ƃ��ăi�����@�Ń��V�A�̑�R���}�������A�킸���P���̕��͂Ń��V�A�R�R���T��ӂ����B��j�ł͏����̌R����R��j���������Ȃ���Ƃ����B�J�[���̌R�͈�C�Ƀ��V�A�R��nj��������A�s���[�g���͌�ލ���Ƃ�i��̃i�|���I���푈�Ɠ����j�A�J�[�������X�N�������������ɉI�����ߌ���I�ȏ����ɂ͎���Ȃ������B�P�V�O�X�N�A�|���^���@�̐킢�ł́A�O��̔s�k�ɂ��肽�s���[�g���̃��V�A�R�͉ΖC���S�̑����ɐ�ւ��A�J�[�����g�����ɕ����������ߔs�k�����B�J�[���͓���ɓ���A�I�X�}���鍑�̃X���^���̕o�q�ƂȂ����B�I�X�}���鍑�̓��V�A�̓쉺��j�~���邽�߃X�E�F�[�f���ƌ��ڂ��Ƃ����̂ł���B�T�N�ԃg���R�ɑ؍݂����J�[���́A�g���R�R�����ꎞ�s���[�g���R�̕�͂������A�s���[�g���͑�����g���R�ɑ��肻�̊�@��E�����B�ӂ��������J�[���͂P�V�P�S�N�~�A�]�҈�l����ċR�n�Ń��[���b�p���c�f�A�P�S���Ԃ������ăX�E�F�[�f���ɋA�����B�ċN�������ăm���E�F�[���f���}�[�N����D�����Ƃ����J�[���͂P�V�P�W�N�A�틵���@���ɓ�����ł�������펀�����B�������猂���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������������������̂ŁA�P�X�U�O�N��Ɉ�̂��@��o���Ē��������Ƃ���A�O���킸���Q�O�����猂���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ����������Ƃ����B���݃X�g�b�N�z�����̃I�y�������̌����ɂ���J�[���P�Q���̓����͉E����������V�A�̋���w���Ă���B�����c���v�w����k���̗��j�x1993�@�����V���@p.61�`�� |
| i�@�o���g�C
| �@ |
| j�@�y�e���u���N
| �������̂̓T���N�g���y�e���u���N�B�u���Ȃ�y�e������肽�������v�̈Ӗ��B���V�A�E���}�m�t�����s���[�g���P�����A���G�X�E�F�[�f���Ƃ��k���푈�ɍۂ��A�o���g�C�ɐi�o���āA�����[���b�p�ւ̑����Ƃ��邽�߂ɂP�V�O�R�N���猚�݂��J�n���A�P�V�P�Q�N�Ƀ��X�N������J�s���ă��V�A�́u���[���b�p�ւ̑��v�ƂȂ����B����Ȍ�A���V�A�v����������P�X�P�W�N�Ɏ�s�����X�N���Ɉڂ����܂ŁA���V�A�鍑�̓s�Ƃ��Ĕɉh�����B�s�̒��S�ɂ͋{��̒u���ꂽ�u�~�{�v�i�G���~�^�[�W���B�G�J�`�F���[�i�Q�������W�������[���b�p�G����������邽�߂Ɍ��݂������{�B�G���~�^�[�W���Ƃ̓t�����X��Łu�B��Ɓv�̈Ӗ��j�ȂǗ��j�I�������������B���̓���ɉĂ̗��{�c�@�[���X�R�G�E�Z���[���������B�܂��y�e���u���N�̖ʂ����N�����V���^�b�g�p���̓��ɁA�v�ǂ�݂��A���ꂪ��̃o���`�b�N�͑��̊�n�ƂȂ����B
���̓s�s�́A������ɂ���ĉ��x���s�s����ύX���Ă���B�P�X�P�S�N�A��P�����E��킪�N����ƁA�E�E�E�u���N�Ƃ����h�C�c���̖��O�����炢�A�y�g���O���[�h�Ɖ��̂��ꂽ�B���V�A�v���ł͂��̒��S�n�ƂȂ����̂ŁA�P�X�Q�S�N�A���[�j���̎���A���̖��O�����������j���O���[�h�ƂȂ����B�\�A�̕����A�P�X�X�P�N�ɂ��Ƃ��T���N�g���y�e���u���N�i�ʏ̃y�e���u���N�j�ɖ߂��ꂽ�B |
| �a�@�G�J�`�F���[�i�Q��
| ���V�A�E���}�m�t���̏���i�݈ʂP�V�U�Q�`�X�U�N�j�B�h�C�c���܂�ŁA�s���[�g���R���̍c�@�ƂȂ�A�߉q�A���̃N�[�f�^�ɂ���ď���ƂȂ����B���������[���b�p�̓A�����J�̓Ɨ��푈�i�P�V�W�O�N�A����������������ăA�����J���������j�A�t�����X�v���A�C�M���X�̎Y�Ɗv�����W�J���������ŁA���[���b�p�̓��̒[�Ɉʒu���郍�V�A�ł��ߑ㉻���}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł������B�������A�v���̖u���͔����˂Ȃ炸�A�G�J�`�F���[�i�͂����ς�ォ��̉��v�A�܂�[�ꐧ�N��Ƃ��Ẳ��v��i�߂邱�ƂƂȂ����B�܂��e�g���̑�\�����W���ĐV�@�T�Ҏ[�ψ����ݗ����āu�P�߁v���A���Ƌ@�\�̐����ɓw�߂��B�܂��A���V�A�|�g���R�푈�A�|�[�����h�����ɂ���ė̓y�̊g����}�����B�P�V�V�R�N�ɂ̓t�����X����[�֎v�z���f�B�h�������������A���̔N�ɁA�v�K�`���t�̑�_���������u�����Ă���B�����������Ă���̓G�J�`�F���[�i�Q���̐���͂���ɔ����I�ɂȂ�B�܂����{�l�Y�����单�������v�𑗊҂��邽�߂P�V�X�Q�N�����N�X�}���������ɔh���A�]�˖��{�ɊJ���𔗂����B
Epi�D�@�N�[�f�^�ŕv��Ǖ����čc��ƂȂ����G�J�`�F���[�i�@�G�J�`�F���[�i�Q���ɂ͏ڍׂȁw��ژ^�x������B�\�A��̌�̏����J�ł��̑S�������炩�ɂȂ������A�����ɂ͕v�s���[�g���R���Ƃ̕s�K�Ȍ���������A����c��ƂȂ����o�܂ȂǁA�ڂ���������Ă���B�ޏ��Ƃ̒������������s���[�g���R���́A���Ⴍ�����ŕa��A��@�I�ȍ�����Ԃ��������郍�V�A�̍c��Ƃ��Ă͂��̓����\�͂ɂ��^���������Ă����B�P�V�U�Q�N�A���J�̐ȏ�Ńs���[�g���R������u�o�J�v�Ă�肳�ꂽ�G�J�`�F���[�i�̓N�[�f�^�����ӂ��A���s���[�g���h�̋M���Ƌ߉q�����ƌ���ōc�鑦�ʂ�錾�A�s���[�g���ɑވʂ𔗂����B���a�ȃs���[�g���͋����������ӂ��A�ވʂ����B���n�ɂ܂����胍�V�A�̋߉q�A���̐����ɐg���R�̐擪�ɗ������G�J�`�F���[�i�Q���́A�u�h�C�c���v�Ƃ����n���f�B�ɂ�������炸�A�����̎x�����A�܂��c��Ƃ��Ă����ƍ����̍Č��ɓw�߁A�u���v�ƌ�����悤�ɂȂ����B�ވʂ����s���[�g���͐�����ɖS���Ȃ������A�G�J�`�F���[�i�̖d�E�̉\���₦�Ȃ������B�����엝�q�w����̃��V�A�x1994�@��g�V���ɂ��B�� |
| a �v�K�`���t�̔_������
| �P�V�V�R�N�A�G�J�`�F���[�i�Q���������̃��V�A�ŋN��������_�������B�_�z���̋����A�d�łȂǂ̃��}�m�t����Ή����ɑ���_�������ł������B���̎w���҃v�K�`���t�́A�����Ă���u�s���[�g���R���v�i�G�J�`�F���[�i�Q���ɂ���Ĕp����A����Ɏ��S�����Ƃ���Ă���j�ł���Ǝ��̂��A�G�J�`�F���[�i�Q�����ʙӒD�҂Ƃ��Ĕ����B�ނ̓h���E�R�T�b�N�ł������̂ŁA�Ăт����ɉ����Ċe�n�̃R�T�b�N���I�N�A����ɒ鍑���̃��V�A�l�ȊO�̖�����H��J���҂܂Ŏx�����L���A�唽���ƂȂ����B�P�V�V�S�N�A�I�����u���N�Ő��{�R�̓v�K�`���t�R�ɑŌ���^���A�v�K�`���t�͕߂炦���A�V�T�N���Y���ꂽ�B
�Ȃ��A���̃v�K�`���t�̔������ނƂ����������A�v�[�V�L���́w��т̖��x�i1836�j�ł���B |
| b�@�_�z��
| �@���@��X�́@�S�߁@�_�z���i���V�A�j |
| c�@�N���~�A����
| ���C�ɓ˂��o�������ŁA�P�W���I��ʂ��A���V�A�ƃI�X�}���鍑�̑��D�̑ΏۂƂȂ����B�P�T���I�ɃL�v�`���N���n�����̕������N�������n�������������A���̌㓯���C�X���[�������̃I�X�}���鍑�̕ی쉺�ɓ������B�������A�G�J�`�F���[�i�Q���̎��Ƀ��V�A�̓I�X�}���鍑�Ɛ킢�A�P�V�V�S�N���L���`���N���J�C�i���W������ŃN�������n�����̕ی쌠���l�������B�P�V�W�R�N�ɂ̓N�������n�����̓��V�A�ɂ���Ėłڂ���A�N���~�A�����̓��V�A�̂ƂȂ����B����ɂP�W�T�R�N���N���~�A�푈���u���A���̒n�̃��V�A�̃Z���@�X�g�|���v�ǂ̍U�h������Ƃ��ă��V�A�ƃg���R�A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ̏����Ƃ̊Ԃ̌���ƂȂ����B���݂̓E�N���C�i���a���ɑ�����B�����^��k���J�Â��ꂽ�ۗ{�n�Ƃ��ėL���ȃ����^�̓N���~�A�����̐�[�ɂ���B |
| �@�N�������n����
| �@ |
| d�@���N�X�}��
| ���{�̕Y�����ł����单�������v��ی삵�A�y�e���u���N�܂œ������Ă��̋A���ɐs�͂����L���������N�X�}���̎��j�ŊC�R�̌R�l�B�P�V�X�Q�N�A�G�J�`�F���[�i�Q���̖����单�������v����č����ɍs���A�]�˖��{�Ɍ��Ղ�\�����ꂽ�B���O�Ŗ��{��\�ƌ��������A���̘V��������M�́A�����𗝗R�Ɍ������ہA����ł���Ό��͉\�ł���ƉA���N�X�}���͖ړI��B���邱�Ƃ��ł����A�������B�]�˖��{�ɑ��鉢�ď����ɂ��J���v���̍ŏ��̂��̂ł������B���̌ネ�V�A�́A���̎��̖Ɋ�Â��A�P�W�O�S�N�g�߃��U�m�t��ɔh���A�J����v�����������{�͂�������ށA�̂��߃��V�A�͑��������A�𑣂��P������Ƃ����������N�������B |
| �单�������v
| �ɐ��o�g�̓��{�l�����ŁA���ɂ����đ����m��Y�����A�瓇�ɕY���A���V�A�l�ɋ~������ĂP�V�X�P�N�Ƀy�e���u���N�ɘA�s����A���}�m�t�����G�J�`�F���[�i�Q���ɉy�������B�G�J�`�F���[�i�Q���́A���{�ɋ����������A���N�A���N�X�}���ɖ����đ单�������v�𑗂�͂��A���킹�č]�˖��{�ɊJ����v�������B
Epi.�@�G�J�`�F���[�i�Q���ɉy���������{�l�@�]�ˎ���̓��{�l�ő����m��Y�����A�A�����[�V�����ɕY�����ă��V�A�l�ɋ~������A�y�e���X�u���N�܂ōs���Ď��̃��V�A�c��G�J�`�F���[�i�Q���ɉy���������{�l������B�ɐ��i�O�d���j�o�g�̑D���单�������v�ł���B�ނ�͂P�V�W�Q�N�P�Q���A�ɐ����q�`����]�˂Ɍ����Ă̕������^�Ԑ_���ۂőD�o�������A���B���ŗ��ɑ����A�Y�������̂ł���B�A���`�g�J���ɕY��������A���V�A�l�ɔ����ăV�x���A�����f���A�X�N��̂P�V�X�P�N�Ƀy�e���u���N�ɂ��ǂ���B���q�`���o���Ƃ��̏�g���͑S���łP�V�l�ƔL���P�C�ł��������A�r���a�Ŏ���A�C�X�N�[�c�N�Ń��V�A�ɋA�������肵�āA�y�e���u���N�ɒ������̂͑D���̑单�������v�ƑD���g�̓�l�����ɂȂ��Ă����B��l���y�e���u���N�ɘA��Ă����̂̓L���������N�X�}���ŁA���̓�l����{�ɋA�����Ƃō������̓��{�ƌ��Ղ̋@�����邱�Ƃ��G�J�`�F���[�i�ɐi�����悤�Ƃ��ē�l��A��Ă����̂ł���B�����v�Ɛe�����ڌ������G�J�`�F���[�i�i���̎��U�Q�j�A�A�d�ɔނ������A�A����F�߂��B�����v�����̓A�_�������N�X�}���i�L�����̎q���j�Ɠ������ē��{�ɖ߂邱�ƂɂȂ����B���ꂪ���N�X�}���̓��{���q�̗��R�ł���B���N�X�}���Ƃ�������ɓ��{�ɖ߂��������v�ƈ�g�͂P�V�X�R�N�ɍ]�˂ɓ���A���R����ƐĂɉy���A���̑̌�������B���̕��o���A�L�^�����̂��j�����́w�k�ʕ����x�ł���B��l�͍]�˂ɉ��~��^����ꂽ���A���I�̌��Ղ̊J�n�ɂ͖𗧂��Ƃ��ł��Ȃ������B���R���P�v�w�单�������v�x�|�鐭���V�A�Y���̕���|�@2004�@��g�V����
���Ȃ����̑单�������v����l���ɂ����������A�����w�I���V�A������杁x��g�����w�单�������v�x�ł���B�@ |
| e�@�|�[�����h����
| �@���@�|�[�����h���� |
 |
| �L�D�|�[�����h����
|
| a�@�|�[�����h
| �@���@��U�́@�Q�߁@�E�D�X���u�l�Ǝ��ӏ������̎����@�|�[�����h |
| b�@���Q�E�H��
| �@���@��U�́@�Q�߁@�E�D�X���u�l�Ǝ��ӏ������̎����@���Q�E�H�� |
| c�@�I������
| �|�[�����h�����i�|�[�����h�����g�A�j�A�A���������p���������̂ŁA���݂̃|�[�����h�������̃��g�A�j�A��x�����[�V�A�E�N���C�i�̈ꕔ���܂ލL��ȗ̓y�������Ă����j�ł́A�P�T�V�Q�N�����Q�E�H���̉��ʌp���҂������f�₵�Ă���A�̎�K���i�M���j�⏬�M���Ȃǂ̎x�z�w�i�V�����t�^�Ƃ����j���\������c��ō�����I������Ƃ����I���������s��ꂽ�B�I���͗L�͋M���̑����A�O���̉�����������ƂɂȂ�A�|�[�����h���ƖŖS�̈���ƂȂ����B�V�����t�^�ɂ���č\�������c��͈��̐g�����c��ł���A���̋c��ō������I�o�����̐����V�����t�^���吧�Ƃ����ꍇ������B���̓n�v�X�u���N�ƂƑR����K�v����A�t�����X�̃��@���A�Ƃ�X�F�[�f���̉��Ƃ���o�g�҂��I�o���ꂽ�B�I����������̂P�V�`�P�W���I�́A�卑�ł������|�[�����h���}���ɐ��ނ��������ł���A�P�W���I���ɂ̓|�[�����h�����ɂ�鍑�Ə��ł��}���邱�ƂƂȂ�B
�|�[�����h�́u��^���v�F�P�U�S�W�N�A�|�[�����h�����ɑ�����E�N���C�i�ŃR�T�b�N���������N�������B�ނ�͂��āA�����S���̐N���ȂǂƐ���������̋R�n�R�c�̎q���ł��������A���V�A�l�Ɠ������M���V�A������̐M�������Ă����̂ŁA�J�g���b�N�̑����|�[�����h�A���̎x�z�ɂ͔����������Ă����B�����ŃR�T�b�N�̓E�N���C�i�̎��������߂Ĕ������N�����A���V�A�̎x���������B�P�U�T�S�N�A���V�A�����R�𑗂�ƁA���N�X�E�F�[�f�����k������N���A�|�[�����h�́u��^���v�Ƃ�����A�X�E�F�[�f���R�ƃ��V�A�R�̐N�����āA�ŖS�̊�@�ɗ������ꂽ�B�P�U�U�O�N�ɍu�a�ƂȂ������A�|�[�����h�̍��y�̍r�p���i�݁A�����̃V�����t�^���v���A�����̋M���̎x�z�����ԂƂȂ����B���́u��^���v���|�[�����h���ނ̂��������ƂȂ����B
�P�V���I�㔼�ɂ́A�I�X�}���鍑�̃E�B�[����͂̍ہA�|�[�����h�������R���i�v���Ԃ�Ƀ|�[�����h�l�ʼn��ɑI�o���ꂽ�j�͂R���̌R���𗦂��ăE�B�[�����~�o���A�L���X�g�����E�̏^���A���̎���̃J�������B�b�c���ł̓I�X�}���鍑����E�݃E�N���C�i��D���B |
| �V�����t�^
| �|�[�����h��Łu�M���v�̈Ӗ��B�قڐl���̂P�O�����߂�x�z�ҊK���B�P�T�V�Q�N�ȍ~�̑I�������ł́A�V�����t�^�������I���̑I�����ȂǁA�����̌����������A�c���́u���R���ی��v�̓�����F�߂��Ă����B���R���ی��Ƃ͋c������l�ł����ی�������ƌ��c�ł��Ȃ��Ƃ������̂ŁA�������Ō��肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ����B�|�[�����h�̋c��x�̓��[���b�p�̒��ł��Â��`���������A���̂悤�ȓ���ȃ��[���̂��߁A����Ɍ`�[�����A���Ƃ̕��������ꂴ��Ȃ��Ȃ����Ƃ�����B |
| d�@�|�[�����h����
| �P�W���I���A�|�[�����h���אڂ��郍�V�A�A�v���C�Z���A�I�[�X�g���A�ɂ���ĕ�������A���Ƃ����ł��������ƁB
�|�[�����h�����̐����F�|�[�����h�����ł��I�������������Ă������A�P�V�O�O�N�Ɏn�܂����k���푈�̓��V�A�ƃX�E�F�[�f�����傽��Η����ł��������A�|�[�����h�����V�A�ƌ���Ő�����B�J�퓖���A���V�A���s�k����ƃX�E�F�[�f���R���|�[�����h�ɐN���A�e���V�A�̃|�[�����h�����͒Ǖ�����A�e�X�E�F�[�f���̍��������ʂ����B����Ȍ�A�����ł̓V�����t�^���c��Ŏ��R���ی����s�g�������͑����ɏI�n���A�܂������̑I�o���߂����Ă͎��ӂ̃��V�A�A�v���C�Z���A�I�[�X�g���A�A�t�����X�Ȃǂ̗L�͍��̉�����i�|�[�����h�p���푈�ƌ�����j�A���Ƃ̓���̈ێ�������ɍ���ƂȂ��Ă������B���̂悤�Ƀ|�[�����h�������{���̂������Ҕ\�͂������Ă����A���ӂ̐�Ή������������������̉a�H�Ƃ���Ă��܂����B
�����̌o���F�|�[�����h�����X�^�k�X���t���͋c��ł̎��R���ی��̐�����R���A�����̉��v�Ȃǂ�}�������A�G�J�`�F���[�i�Q���̓v���C�Z�����t���[�h���q�Q���ƂƂ��Ƀ|�[�����h�ɉ�������B���̌����̓|�[�����h�ɂ����ăJ�g���b�N���k�ȊO�̃M���V�A�����k�ƃv���e�X�^���g�ɂ������I������F�߂�Ƃ������̂ł������B
��̉������|�[�����h�ɑ��A�܂��A���V�A���G�J�`�F���[�i�Q�������̑S�y�̕ی�̂���_�����B��������ꂽ�v���C�Z���̃t���[�h���q�Q�����A�I�[�X�g���A�����[�[�t�Q���i�����̓}���A���e���W�A�j���������A�P�V�V�Q�N�ɑ�P���̕������|�[�����h�ɔF�߂������B��P���̓|�[�����h�����ɐ[���Ȋ�@�����ĂыN�����A�����ɂ����v���s���A���@�����肳�ꂽ�B�������A���V�A�̃G�J�`�F���[�i�Q���́A�t�����X�v�����i�s���Đ����������Z�E����Ă���ԂɎc��̃|�[�����h�̗̗L��_���A�v���C�Z���̃t���[�h���q���E�B���w�����Q���ƂƂ��ɁA�P�V�X�R�N�ɑ�Q�����|�[�����h�ɔ���A���F�������B��P��Ε��哯���ɉ�����Ă����v���C�Z���ƃI�[�X�g���A�̂����A�I�[�X�g���A�̓t�����X�v���R�ɔs�ꂽ���߁A�|�[�����h�ɂ͊֗^�ł��Ȃ������B���̑�Q���ɑ��āA���N�A�|�[�����h���R�V���[�V�R�͔_����g�D���ĖI�N���A���V�A�R�Ɛ�������s��A�P�V�X�T�N�ɑ�R�����A���V�A�A�v���C�Z���A�I�[�X�g���A�̂R���ɂ���čs���āA�|�[�����h�͍��ƂƂ��Ă͒n�}�ォ����ł���B |
| �`�@��P��
| �P�V�V�Q�N�A�܂����V�A�i�G�J�`�F���[�i�Q���j�ƃv���C�Z���i�t���[�h���q�Q���j�Ƃ̊Ԃŏ��������A�I�[�X�g���A�i���[�[�t�Q���j������ɉ�������B�O������̓y�����𔗂�ꂽ�|�[�����h�c��́A��̔��͂��������A���N�̓y���������F�����B�v���C�Z���́u���̃v���C�Z���v�i�P�S�U�U�N�h�C�c�R�m�c���|�[�����h�ɏ������y�n�j��̗L�i���S�s�s�O�_�j�X�N�͏����j�A���V�A�̓����H�j�A�ƃx�����[�V�̈ꕔ���A�I�[�X�g���A�̓K���c�B�A�n���̈ꕔ�����ꂼ��l�������B����ɂ���ă|�[�����h�͗̓y�̂R�O���ƁA�l���̂R�T�����������B |
| a�@�v���C�Z���i�t���[�h���q�Q���j
| �@���@�t���[�h���q�Q�� |
| b�@�I�[�X�g���A�i���[�[�t�Q���j
| �@���@���[�[�t�Q�� |
| c�@���V�A�i�G�J�`�F���[�i�Q���j
| �@���@�G�J�`�F���[�i�Q�� |
| �a�@��Q��
| ��P��|�[�����h�����̌�A�|�[�����h�����ł͊�@�������߁A�������v���s���A���Ƃ̓Ɨ����ێ����悤�ƌ����w�͂��Ȃ��ꂽ�B�P�V�X�P�N�ɂ́u�T���R�����@�v�����肳��A�V�����t�^�ɂ�鍑���I���Ǝ��R���ی��͔p�~����A�����N�吧�E�O�������E�`�����𐧂Ȃǂ���߂�ꂽ�B���̌��@�́A�A�����J���@�Ɏ������������̋ߑ�I���@�ł������B�܂��A�|�[�����h�̐g�����c��̈����ł������u���R���ی��v��ے肵�āA�������ŋc���ł���Ƃ����B�܂����ʂ��s����ȑI����������߁A�U�N�Z���Ƃ̐��P�Ƃ��ꂽ�B����ɓy�n�������ʃV�����t�^�͋c�Ȃ������A����ɓs�s��\����������B�������A���̌��@�͂P�N���������Ȃ������B���V�A�̃G�J�`�F���[�i�Q���́A�V���@���t�����X�v���̈��e���ł��邩��r������Ƃ��ČR���𑗂�A�|�[�����h�R��j�����B����ɑR�����v���C�Z������������N�U���|�[�����h�R��j�����B�������ĂP�V�X�R�N�A���V�A�R�̊Ď����̋c��́A���V�A�ƃv���C�Z���ւ̗̓y���������F�����B�|�[�����h�̓��V�A�Ƀx�����[�V�����ƃE�N���C�i�̑啔�����A�v���C�Z���Ƀ|�[�[���ƃ_���c�B�q�i�O�_�j�X�N�j���������B���̑�Q���Ń|�[�����h�͎����㍑�Ƌ@�\���������B���Ə��ł̊�@�ɑ��āA���P�V�X�S�N�A�R�V���[�V�R�炪�I�N�������A���҂����t�����X�̋~���������������ꂽ�B |
| a�@�t�����X�v��
| �@ |
| b�@�R�V���[�V�R
| �R�V�`���[�V�R����茴���ɋ߂��\�L�B���V�A�A�v���C�Z���A�I�[�X�g���A�ɂ�镪���ɒ�R�����|�[�����h�̉p�Y�B�����V�����ƃp���̎m���w�Z�𑲋Ƃ����R�l�ŁA�A�����J�ɓn��A�Ɨ��푈�ɎQ���B�P�V�W�S�N�ɋA�����āA�P�V�X�Q�N����Q��|�[�����h�����Ń��V�A�R�Ɛ키�B�~���ɔ����ď������A�P�V�X�S�N�ɔ_����g�D���ė����オ�����B������R�V���[�V�R�I�N�Ƃ����B���V�A�R�Ƃ̏���ɏ��������R�V���[�V�R�͔_���̎��R��錾�A����ɏ������d�ˁA��Q���O�̃|�[�����h���قډ��A�����V�����ɗՎ����{�����Ă��B�������A�t�����X�̎x��������ꂸ�A�����ł��V�����t�^�w���_�z����ւ̕s�����狦�͂��Ȃ��悤�ɂȂ�A�U���Ƀv���C�Z���R�ɃN���N�t��D���A�W���ɂ̓��V�A�R�Ƀ��B���m��D���A�P�O���̐퓬�ł݂͂�������������ĕߗ��ƂȂ��Ă��܂��A�P�P���ɂ̓����V���������V�A�R�ɐ�̂���A�I�N�͒������ꂽ�B���P�V�X�T�N�ɎO���ɂ����R�����s���A�|�[�����h�͊��S�ɏ��ł���B�R�V���[�V�R�͂P�V�X�U�N�Ɏߕ�����Ă���p���ɈڏZ�A�|�[�����h�̍ċ����߂����Ȃ���ʂ������Ƃ��ł����v�����i�P�W�P�V�N�j�B |
| �b�@��R��
| �P�V�X�T�N�A�R�V���[�V�R�I�N���������ꂽ��A�v���C�Z���E�I�[�X�g���A�E���V�A�Ń|�[�����h�������m�F���A�|�[�����h�͊��S�ɖŖS�����B���̌�A�i�|���I���ɂ�郏���V����������̌����A�i�|���I���v����̓��V�A�̎����x�z�̉��ɂ����ꂽ�|�[�����h���������̎�����o�āA�|�[�����h���Ɨ�������̂́A�P�Q�R�N��̑�P�����E����̂P�X�P�W�N�̂��Ƃł���B |
| a�@�|�[�����h�ŖS
| �@���@�����V����������@�@�|�[�����h���������@�@�|�[�����h�Ɨ� |
 |

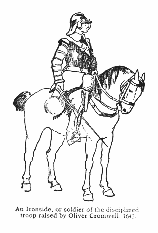
 �P�V���I�͂��߁i�P�U�P�R�N�j�ɐ����������V�A�E���}�m�t���́A�X�E�F�[�f�������A�|�[�����h�����Ɉ�������A�����[���b�p�ł͎㏬���͂ɂ����Ȃ������B�����ɂ͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�z������ՂƂ����L�͋M�������݂��A�Y�Ƃ����n�ł���A�ߑ�I�ȌR���̑n�݂��}����Ă����B�����Ń��}�m�t���̃c�@�[���́A�����[���b�p�����ɏK�������Ƃ̑n�o���߂����A���x�E�Y�Ƃ̐�������i�߂��B���ɋ}���ɐi�߂��̂��s���[�g���P���i���j�ł������B�s���[�g���P���̎���ɁA�Y�ƁE�R���E�Ő��E�������Ȃǂœ��Ƀv���C�Z������{�Ƃ������v���s��ꂽ�B�������A�Љ�̍����ɂ���_�z���ɂ͊�{�I�ɂ͎�������A�u�ォ��̉��v�v�ɂƂǂ܂�A�u���V�A�̌�i���v���ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�P�V���I�͂��߁i�P�U�P�R�N�j�ɐ����������V�A�E���}�m�t���́A�X�E�F�[�f�������A�|�[�����h�����Ɉ�������A�����[���b�p�ł͎㏬���͂ɂ����Ȃ������B�����ɂ͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�z������ՂƂ����L�͋M�������݂��A�Y�Ƃ����n�ł���A�ߑ�I�ȌR���̑n�݂��}����Ă����B�����Ń��}�m�t���̃c�@�[���́A�����[���b�p�����ɏK�������Ƃ̑n�o���߂����A���x�E�Y�Ƃ̐�������i�߂��B���ɋ}���ɐi�߂��̂��s���[�g���P���i���j�ł������B�s���[�g���P���̎���ɁA�Y�ƁE�R���E�Ő��E�������Ȃǂœ��Ƀv���C�Z������{�Ƃ������v���s��ꂽ�B�������A�Љ�̍����ɂ���_�z���ɂ͊�{�I�ɂ͎�������A�u�ォ��̉��v�v�ɂƂǂ܂�A�u���V�A�̌�i���v���ʂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B