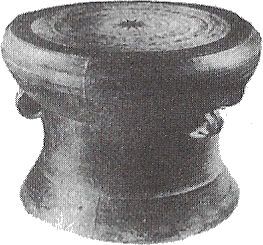| 用語データベース 02_2 |
  |
| 2.東南アジアの諸文明 |
| ア.東南アジアの風土と人びと
|
| a 大陸部
| または半島部とも言う。東南アジアのインドシナ半島の地域。紅河、メコン、チャオプラヤ、イラワディなどの大河の流域の平野部は豊かな米作地帯である。この地域の民族は、オーストロアジア語族(南アジア語族)といわれる、ベトナム人、モン人、クメール人(カンボジア人)がまず活動しており、中部ベトナムにはオーストロネシア語族のチャム人がいた。ついでシナ=チベット語族に属し、はじめ北方の山岳部にいたタイ語族のタイ人、ラオス人が7,8世紀に南下して定着した。またイラワディ川中流には同語族の中のビルマ人がモン人と抗争しながら定着した。
中国文明の影響:紀元前5世紀頃から北部ベトナム地方には中国文明の影響が及び、青銅器文明であるドンソン文化が形成され、秦・漢時代からは中国王朝の直接支配を受け、唐時代頃まで続いた。
港市国家の形成:1世紀頃から海岸地方には河川を利用して内陸の物品を集め、海洋を利用してインドや中国などと交易をする港市国家が発達した。1世紀末にベトナム南部に現れた扶南がその例である。同時に扶南にはインド文明の影響が見られ、インド化の第一段階が始まった。中部ベトナムに現れたチャンパーも港市国家として栄えた。
インド化の進展:紀元後3世紀頃からインドの影響を強く受け、「インド化」が進んだ。宗教面では4世紀のインドのグプタ朝で栄えたヒンドゥー文化が伝わり、7世紀に成立したクメール人のカンボジアではヒンドゥー教が信仰された。一方、現在のビルマのピュー人やビルマからタイの北方にいたモン人は上座部仏教を信仰した。
仏教の普及:大陸部ではヒンドゥー文化と仏教信仰が重層的に重なり合って独自の文明を形成していく。12世紀に建造されたカンボジアのアンコール=ワットもはじめはヒンドゥー寺院として造られたが後に仏教寺院とされた。次第に仏教(上座仏教)が優勢となり、特にビルマ、タイでは王権の保護を受けて栄えた。特にビルマのパガン朝は多くの造寺造仏を行ったことで知られる。
植民地化:18世紀以降、タイをのぞいてイギリスとフランスに分割された。ビルマはイギリスの植民地支配を受け、ベトナム・ラオス・カンボジアのインドシナ三国はフランスの植民地となった。その中間にあったタイ(シャム)のみが独立を維持することができたが、領土は大幅に削減されることとなった。
現在の諸国:現在の国家ではベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー(ビルマ)にあたるが、以下に登場する東南アジアの歴史上の国々は必ずしも現在の国と領域が一致しない点に注意することと。カンボジアのクメール王国は一時はインドシナほぼ全域を支配し、ビルマのコンバウン朝も一時期はタイを支配した。タイのラタナコーシン朝も現在のタイよりも広大な領土を支配していた。また、ベトナムは、18世紀までは北部ベトナム(紅河流域)、中部ベトナム、南部ベトナム(メコンデルタ地帯)は別個な国家であったことに留意すること。 |
| インドシナ | 東南アジアの大陸部(または半島部)をインドシナというのは、インドと中国の中間に位置するところからヨーロッパ人が名付けたもの。現在、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマーの5カ国がある。マレー半島は諸島部にはいる。中国文明とインド文明の双方の影響を受け、多くの民族が歴史を形成してきた。 → 大陸部 |
| 紅河 | ベトナムではホン川。中国の雲南地方からベトナム北部の平野を流れ、トンキン湾に注ぐ。流域は豊かな水田地帯で人口が多く、中心都市はハノイ。河港の都市がハイフォン。ベトナム戦争でアメリカ軍の激しい空爆を受けた。 |
| メコン川 | チベット高原の奥地の源流から発し、中国の雲南地方からインドシナ半島に入り、上流はミャンマーとラオスの国境となり、さらにほぼラオスとタイの国境を流れ、下流ではカンボジアを環流し、ベトナムに入り、河口に広大なメコンデルタを作っている。インドシナ半島最大の河川。ラオスのビエンチャン、カンボジアのプノンペン、ベトナムのホー=チ=ミン(旧サイゴン)はいずれもメコン川流域にある。 |
| チャオプラヤ川 | 流域全域がタイに属する大河。日本ではメナム河ということもあるが、メナムとはタイ語で川を意味し、固有の河川名としてはチャオプラヤ川が正しい。支流のピン川(上流にチェンマイがある)とメイン川(この流域にスコータイがある)が合流する地点から河口までをチャオプラヤ川といい、下流にアユタヤ、河口にバンコクがある。河川交通路としても南北を結ぶ動脈の役割があり、この川沿いにタイの歴史が展開された。 |
| イラワディ川 | ミャンマー(ビルマ)を北から南に貫流する大河。エヤワディ川とかイラワジ川とも表記する。上流にマンダレー、中流に古都パガン、河口近くにヤンゴンがある。 |
| b モンスーン
| 季節風。季節によって風向きが異なる風で、夏は海洋から大陸へ、冬は大陸側から海洋に向けて吹く。南アジア(インド周辺)では、夏は南西風、冬は北東風が卓越する。日本を含む東アジアでは、夏は南東風、冬は北西風が卓越する。東南アジアの大陸部は熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分で言えばAm)に属する。
モンスーンのもたらす降雨は稲作などの農耕に欠かせず、また季節によって一定方向をとるので遠洋航海に利用され、人類の文明形成に大きな影響を与えている。 → 季節風貿易
東南アジアのモンスーン:「インド洋では、4月になると、南西のモンスーンが吹き始め、インド大陸の東岸に沿って、船をベンガル湾からビルマ方面へと送り込む。ここに達すると、船は、ヒマラヤ方面から吹く偏西風に乗って、マラッカ海峡へと針路をとる。5月には、この南西風はさらに発達して、海峡を越え、南シナ海からインドシナに達する。南西モンスーンは、7月には時速30ノットの最盛期に達する。それ以後減衰期に入り、10月には、逆に、東北風が南シナ海から下ってくる。この東北モンスーンのもっとも厳しい12月から翌年の2月にかけては、マラヤ半島東岸の航路が、実質的には閉鎖状態となる。」<鶴見良行『マラッカ物語』1981 時事通信社 p.34> |
| c 諸島部
| 群島部、島嶼部ともいう。マレー半島とスマトラ島、ボルネオ島(カリマンタン島)、ジャワ島、スラウェシ島、モルッカ諸島など現在のインドネシアの島々、及びフィリピン諸島からなる。マレー半島はインドシナ半島と地続きだが、気候的にも、文化的にも諸島部に入れるので注意すること。人種的にはマレー=ポリネシア語族(オーストロネシア語族ともいう)が多く、現在はマレーシア、シンガポール、インドネシア、ブルネイ、東ティモールの諸国を形成している。
港市国家の発達:早くからインド洋の商業圏と中国の商業圏の中間に位置して交易が盛んであったので港市国家が発達した。マレー半島とスマトラ島の間のマラッカ海峡を抑えて7世紀に起こったシュリーヴィジャヤ王国、ジャワ島に8世紀に起こったシャイレーンドラ朝などがそれにあたり、インドや中国とも交易を行い栄えていた。
仏教文化とヒンドゥー文化:東南アジアの半島部と同じように、この地域もはじめは仏教とヒンドゥー教が伝わった。シュリーヴィジャヤ王国には唐僧義浄がインドに行く途中たちより、大乗仏教が盛んだったことを伝えている。また8世紀にはジャワ島のシャイレーンドラ朝でボロブドゥール寺院が建設された。
イスラーム化:13世紀以降、次第にイスラーム化が進み、15世紀のマラッカ王国が最初に栄えたイスラーム教国である。ジャワ島にはヒンドゥー強国マジャパヒト王朝があったが、後にイスラム化し、マタラム王国などのイスラーム王朝が香料貿易で栄えた。スマトラ東北西部にはアチェ王国が同じく香料貿易で栄えた。フィリピン南部のミンダナオ島もイスラム化した。
ヨーロッパ諸国の侵出:1511年のポルトガルのマラッカ占領以来、ヨーロッパ人の進出が始まり、ついでオランダ、イギリスが進出してきた。フィリピンにはスペインが進出した。オランダがポルトガルの勢力を駆逐した後、イギリスとの競争が厳しくなり、それは1623年のアンボイナ事件の結果、オランダの勝利となり、イギリスはインド・ビルマ・マレー半島に後退し、東南アジア諸島はオランダ領東インドとなった。
英蘭米による分割:その後、ナポレオン戦争の時、オランダがフランスに占領されたのを期にイギリスが一時ジャワ島なども占領したが、ナポレオン没落後の1824年のイギリス=オランダ協定でマレー半島はイギリス領、スマトラ島・ジャワ島などはオランダ領とすることで合意した。これによって諸島部はマレー半島とボルネオ島の北部がイギリス、その他の島々がオランダにが支分割支配されることとなり、第2次世界大戦後に独立する際に、前者がマレーシア、後者がインドネシアとして独立することとなった。またフィリピンはマゼラン以来スペインの支配下にあったが、米西戦争の結果、アメリカの植民地となった。
現在の諸国:第2次世界大戦後、旧オランダ領東インドはインドネシアとして独立。マレー半島とボルネオ島北部にはマレーシア連邦が成立、その後シンガポールがそこから分離した。またフィリピンはアメリカから独立した。さらにブルネイがマレーシアから分離し、東ティモールはインドネシアから分離独立した。 |
| マレー半島 | マラヤ半島とも言う、インドシナ半島から東南に延びた半島。現在は北はタイとビルマが領有し、南部はマレーシアの一部となっている。その南端にシンガポール島がある。またマラッカ海峡を隔ててスマトラ島が平行している。マレー半島の住民(マレー人)は本来、マレー=ポリネシア語族系で諸島部の現在のインドネシアの人々と同系統であったので、文化圏としては諸島部にはいることに注意すること。シュリーヴィジャヤやマラッカ王国はマレー半島とスマトラ島を勢力範囲とする港市国家であったが、マレー半島には1511年のポルトガルによるマラッカ占領から植民地化が始まり、ついで1641年にオランダ領となり、19世紀にはイギリスの植民地となった。
また、本来のマレー半島は、海岸部はマングローブ林が広がる泥地であり、内陸は山地が多く、河川流域にの狭い平地もほとんど沼沢地であったので農耕には向かなかった。近代のスズ鉱山の開発、ゴム園やパーム椰子などプランテーションの設置にともなってマレー半島の地形と景観は大きく変化した。平行して中国人(華僑)とインド人の流入も多くなり、現在は多民族地域となっている。
マレー半島は、インド洋(その一部のベンガル湾)と南シナ海(その一部のシャム湾)を隔てているが、古代のこの地の東西交易は、マラッカ海峡の通行が季節風で制約されたから、河川を利用して内陸に入り、船を陸揚げして半島をこえるコースがとられていた。半島部の最も狭い地峡がクラ地峡である。 |
| スマトラ島 | インドネシアでボルネオ島に次いで大きく、世界で6番目に大きな島。面積約47万3506平方kmである。メルカトル図法の世界地図では日本の方が広く感じるが、実際にはスマトラ島の方が1.3倍であることに注意しなければならない。北西から南東に長く横たわり、ほぼ中央を赤道が横切る。マラッカ海峡を挟んでマレー半島があり、スマトラ島の東には大スンダ列島といわれるジャワ島が連なる。西側海岸沿いに山脈が連なり、東側に平地が広がるが、多くは密林や沼地であり、生産性は低かった。原住民はマレー半島と同じくマレー人で、7世紀には南西部のパレンバンを中心にしたシュリーヴィジャヤ王国が港市国家として栄え、仏教が信仰されて唐僧義浄がインドに往来する途次に滞在したことが有名。その後、ジャワ島に起こったシャイレーンドラ朝などの支配を受け、13世紀頃からはイスラーム化が始まり、15世紀には島の一部はマレー半島のイスラーム教国マラッカ王国の支配を受けた。その後、西北部のアチェー王国や、中部のミナンカバウなどイスラームの地方政権が生まれた。16世紀のポルトガルを初めとするヨーロッパ諸国の進出が始まると、スマトラ島には初めオランダが進出、ついでイギリスも進出し、1824年のイギリス=オランダ協定でスマトラ島はオランダ、マレー半島はイギリスの植民地とされた。その後、オランダ領東インドの一部として植民地支配が続いたが、イスラーム教徒を主力としたオランダに対する抵抗(アチェ戦争)も続いた。現在はインドネシア共和国に属し、ゴム・石油・天然ガスの産地として重要になっている。 → 現代のインドネシア |
| ボルネオ島 | 東南アジアにある島で、世界第3位の面積を持つ巨大な陸地で、面積約57万平方km(日本は全土で37万平方km)。現在はマレーシア、ブルネイ、インドネシアの三国に領有されている。マレーシア領は島の北西側で、北のサバ州と南のサラワク州に分かれる。サラワク州の北に小さなブルネイ王国がある。中央山脈の南側がインドネシア領でカリマンタンという。海岸部にはいくつかの港市が発達しているが、内陸は山岳部には密林、平野部には湿地が広がっており、オランウータンなど野生動物の宝庫であった。しかし最近や石油など地下資源の開発で熱帯雨林が急速に減少している。
民族的には原住民のダヤク人と海洋民であるマレー系の諸民族、さらに中国系の華人が混在している。北部のマレー系住民は、フィリピンのスルー諸島やミンダナオと関係が深く、イスラーム教徒である。また現在のブルネイ王国もイスラーム教を奉じた原住民がサルタンを称したもの。
ボルネオの周辺の海洋民であるイスラーム教徒は海賊として恐れられており、また内陸のアニミズムにとどまる原自民の中には首狩りの習慣があったりして恐れられ、東南アジアでもヨーロッパ勢力の進出が最も遅れたところであった。19世紀にはイギリス人のジェームズ=ブルックと言う人物が北部ボルネオの北部のサラワクをブルネイ王から買い取って、自らサラワク王を名乗り、後にイギリス領に編入された。南部はオランダが進出し、その植民地とされた。そのような植民地の歴史が前提となったため、イギリス領サラワクとサバはマレーシアに組み込まれ、オランダ領カリマンタンはインドネシア領となった。 → 現代のインドネシア
Epi. ボルネオの白人ラジャ 北部ボルネオのサラワクに王国を築いたイギリス人がいる。彼はジェームズ=ブルックといい、インドで判事をしていたイギリス人の子として生まれ、本国で教育を受けたが悪童ぶりが祟って放校となったためインドに戻り、第1次ビルマ戦争に従軍して負傷した。36歳で父の遺産を引継ぎ、一旗揚げようとボルネオにやってきた。そこでブルネイ王のために海賊鎮圧で功績を挙げ、1842年、ラジャ(太守)としてサラワクを治めることになった。事実上の白人王国の誕生である。彼と彼の後をついだ甥のリチャードが二代にわたってサラワク王として君臨することとなる。このサラワク白人王国は、ブルネイ王国から土地を次々と買い増し、領土を広げていった。それが現在のマレーシア領サラワク州のもとである。二代目のリチャードは、イギリス流の植民地支配を押しつけるのではなく、首狩り族として知られるイバン族などを兵士に採用して周辺の海賊を鎮定するなど、独自の王国を建設した。<くわしくは、鶴見良行『マングローブの沼地で』1983
朝日新聞社 p.297 白人ラジャ を参照> |
| モルッカ諸島 | → 第9章 1節 モルッカ諸島 |
| d 香辛料
| 東南アジアの香料生産の中心地は、スラウェシ島とニューギニア島にはさまれた海域に点在するモルッカ諸島で、一般にこの島々を香料諸島といっている。モルッカ諸島では他の地域では生育しない、丁字(クローブ)に代表される豊かな香料の産地で、17世紀にはポルトガル、スペイン、オランダ、イギリスが激しくその利権を巡って争うことになる。 |
| 南シナ海交易圏 | 南シナ海は北を中国南部(海南島など)、台湾、東をベトナム、西をフィリピン、南をボルネオ島、マレー半島に囲まれた海域。古来、中国と東南アジア諸地域を結ぶ交易圏が成立していた。特に1世紀以降は季節風(モンスーン)を利用した海上貿易が盛んになり、沿岸各地に港市国家が成立した。さらにマラッカ海峡を通してベンガル湾からインド洋交易圏とつながり、北は台湾海峡を抜けて東シナ海・東アジア交易圏の琉球、朝鮮、日本ともつながる。なお、現在南シナ海ではほぼ中央に点在する南沙諸島の帰属をめぐって、中国・ベトナム・フィリピン・マレーシアなど沿岸諸国の間で対立がある。 |
| イ.インド・中国文明の受容と東南アジア世界の形成
|
| ドンソン文化
| 東南アジアの北部ベトナムを中心に、中国の青銅器文化の影響を受けて成立した文化。ドンソンは北部ベトナムのタインホワ州のにある遺跡。成立時期は前5世紀頃とされる。最大の特徴は、銅鼓という青銅器で、中国の昆明地方から北部ベトナムにかけて出土している。なお、北部ベトナムにはまもなく中国から鉄器が伝わり、青銅器と併用されるようになる。また、東南アジアの金属器文化としては他に、中南部ベトナムのサーフィン文化、東部タイのバンチェン文化がある。 |
銅鼓
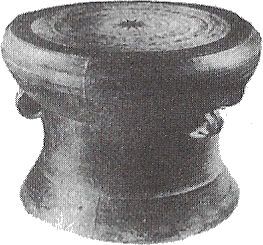 | 北部ベトナムを中心にした紀元前5世紀頃のドンソン文化に特徴的な青銅器。中国昆明地方から始まり北部ベトナムに広がり、さらに東南アジア全域に広がった。大きなものは直径1m、高さ80cmほどの鼓型の青銅器である。表面に太陽をかたどったと思われる模様が描かれ、側面には船を漕ぐ人々が図案化されている。
銅鼓の役割 「銅鼓自体を綿密に観察することによって、銅鼓の機能もおのずからはっきりしてくる。まず第一にそれはあの世とこの世、それに両者をつなぐ舟という世界の構造を具体的に示した、世界軸、あるいは宇宙軸であって、当然のこととして稲作の導入によって生まれた首長の権威を高めるものであったに違いない。その金色燦然たる輝きと、それを叩いた時に発する深い音はそれ自体が「畏れ多い」雰囲気をかもしだしたはずである。第二にそうした機能の延長として、葬儀などの儀礼の際に祭具として使用されたと思われる。そういう意味で、わが国の銅鐸と似たような役割を果たしたものと思われる。<生田滋『世界の歴史13』東南アジアの伝統と発展(中央公論新社)1998 p.60>
出題 2009年 センターテスト世界史B 第3問 問4 (正誤判定) ア 左の写真の遺物は、「ドンソン文化を代表する器物である。」 → 正解 ○ |
| サーフィン文化
| 中国南部・北部ベトナムのドンソン文化と同じ時期(紀元前5世紀ごろ)、ベトナムの中南部の海岸沿いには、青銅器を使用し、農耕に従事しながら、独自の漁撈文化を持つ遺跡が見つかっており、この文化はサーフィン(またはサフィン)文化と呼ばれている。同系統の漁猟文化はフィリピンにも見られる。なお、東南アジアの金属器時代の遺跡として、東部タイのバンチェン文化が知られている。バンチェン文化の青銅器はかなりふるい様式を示しているという。 |
| 中国の北部ベトナム支配 | 中国を統一した秦の始皇帝は、前214年に遠征軍を派遣し、現在の広東省、広西チュウアン族自治区、北部ベトナムの一帯を征服し、南海郡・桂林郡・象郡の三郡を置いた。北部ベトナムにあたるのは象郡であり、これによって中国王朝の郡県制支配をうけることとなった。しかし、秦が滅亡すると、南海郡の知事であった人物が独立して南越を建てた。次いで漢の武帝は、前118年にやはり遠征軍を送って南越を滅ぼし、その地に7郡をおいた。そのうち北部ベトナムに置かれたのは、交趾(こうし)、九真、日南(じつなん)の三郡である。後漢の北部ベトナム支配を継続したが、それに対してベトナム人民衆を率いた土豪の娘の徴姉妹の反乱が起こった。後漢は将軍馬援を派遣して反乱を鎮圧し、直接支配を強化し抑圧を続けたので、その後もたびたび反中国の農民反乱が起こった。魏晋南北朝時代の南朝政権による支配の後、中国の統一を回復した唐によって支配された。唐はハノイに安南都護府を置いて、羈縻政策による統治を行った。唐が衰退すると、中国南部にあった南詔が一時安南都護府を占領するなどの混乱が始まった。10世紀にはいるとベトナム人土豪が独立の動きを召せ、939年から呉権、丁部領、黎桓という王を称するものが三人現れたが、いずれも短命に終わり、安定したベトナム人政権が登場するのは、1009年の李公蘊が建国した李朝(リ朝)からである。その後、北部ベトナムには陳朝、胡朝、黎朝(後黎朝)が続くが、元、明、清の中国統一王朝はいずれも北部ベトナムへの直接支配をねらい、もしくは宗主国としての権利を主張し干渉を続けた。 |
| インド化
| 東南アジアへのインド文化の伝来は、二段階にわけて考えられる。まず、前1世紀の末に、南インドに成立したサータヴァーハナ朝(アーンドラ朝)のインド人が西方のローマとの交易に必要な金や香料などの品々を求めて東南アジアの半島部の海岸や諸島部の港にやってくるようになったのが第一段階であり、商人とともにバラモンが渡来してヒンドゥー教やサンスクリットなどのインド文化を伝えた。この時期に起こったインドシナ南部に起こった扶南はインドから渡来したバラモンと現地の主張の娘が結婚して王となったという建国神話を持っていることが、「インド化」の一端を示している。
東南アジアの「インド化」が顕著になるのは、3世紀に始まり、4世紀にインドでグプタ朝が成立して豊かな都市を背景としたインド古典文化の全盛期となった時期に進んだ。4世紀から5世紀にかけて、バラモンの渡来によってヒンドゥー文化が東南アジア全域に広がり、半島部では北部ベトナムを除いて中国文化の影響は薄くなり、特に「インド化」が進んだ。<石澤良昭・生田滋『東南アジアの伝統と発展』中央公論社世界の歴史13 などによる>
一般的に、「インド化」の指針としては、・インド的な枠組みでの王権の成立、・ヒンドゥー教と仏教の信仰、・インド的な神話と法律、・サンスクリット語の使用、があげられている。
補足 インド文字の伝播 現在の東南アジア諸国で使用されている文字の中で、カンボジア(クメール文字)、ビルマ文字、タイ文字はいずれも古代インド・アショーカ王時代のブラーフミー文字をもとに作られたもので、「インド化」の結果といえる。ジャワ島にもかつてインド文字系のジャワ文字があったが現在は使われていない。なお、ベトナムとインドネシアの文字はラテン文字(ローマ字)表記が正式となっており、マレーシアやシンガポールは英語なのでアルファベットが普通に使われている。<東京外国語大学AA言語文化研究所編『図説・アジア文字入門』河出書房新社> |
| a 扶南
| ふなん、とよむ。扶南と漢字で書くのは中国の歴史書に現れた表記で、クメール語のプノーム(山の意味)と関係があるらしい。東南アジア最古の王朝と考えられる、紀元1世紀末にメコン川下流の現在のカンボジアからベトナム南部にかけて成立した王朝。この王朝の民族は、クメール人(オーストラロアジア系民族、現在のカンボジア人)か、マレー人(マレー=ポリネシア系)か、いずれかであるがはっきりしない。扶南王国はカウンディンヤというインド人バラモンの王子が、南方より海路やってきて、その地の人民を服従させ、柳葉という名の女首長と結婚した、という伝承がある。その後、4〜5世紀にヒンドゥー教・シヴァ神信仰・サンスクリットなどを取り入れ、「インド化」が進んだ。彼らは海上貿易でも活躍し、中国にも使節を派遣し、その貿易港オケオ(タイランド湾に面する港で、1940年代に遺跡が発掘された)などが繁栄した。扶南はメコン川を利用して内陸の物資を集積し、それを南シナ海交易圏でインドや中国との交易を行って利益を上げるという港市国家であった。7世紀中頃までに、メコン川上流に起こったクメール人の国真臘(カンボジア王国)に征服された。
Epi. 扶南→プノンペン 「扶南」の位置はどの辺だったか。漢字が使われているので、中国に近い現在のベトナム北部あたりと勘違いしやすいが、メコン川下流のほぼ現在のカンボジアにあたる。実際には東南アジア全体にその支配領域を及ぼしていたらしい。この扶南は、クメール語の山を意味するプノムの古語プナムからきた言葉で、その地方の王が「クルング=プナム」すなわち「山の王」と言われていたのを中国人が扶南と書き写したものとされている。メコンデルタの平野部では小高い山が神聖な場所とされていたらしく、カンボジアの首都のプノンペンも「ペンの丘」という意味で、古い塔のあるペンの丘の南に出来た街である。扶南→プナム→プノンペン、と連想すれば、これがカンボジアの古代国家だったことが思い出せる。<石井米雄『世界の歴史14』インドシナ文明の世界 講談社 1977> |
| 港市国家 | 海岸や河川に面した港市を持ち、内陸の物資を集積し、海上を通じての他の諸地域との交易ルートをおさえることによって形成された国家。近代の主権国家のような領土はなく、複数の港市の連合体を構成している。
紀元前後から、特に南インドから東南アジアにおいて、インド人の商業活動が活発になったことによって形成された。港市は、商品の集積、積み替え、風待ち、水や食料の補給などの機能を持ち海上交易ルートの要地に生まれていった。それらの港市の中で国家に成長したのが、インドのサータヴァーハナ朝や、シャム湾に面した扶南、インドシナ半島東岸のチャンパーである。さらに7世紀ごろからマレー半島、スマトラ島、ジャワ島などの半島部に港市国家としてシュリーヴィジャヤ王国、マラッカ王国、アチェ王国、シャイレンドラ朝などが起こった。タイのアユタヤ朝なども港市国家である。 |
| オケオ遺跡 | 現在のベトナム南部、メコンデルタ地帯でタイランド湾に面した港市の遺跡。古代の扶南の港として栄えた港市で、インドと中国を結ぶ中継地としてインド商人が定住していたらしい。遺跡からはインド製の仏像やヒンドゥー教の神像、後漢時代の鏡、ローマ帝国の五賢帝時代の金貨などが出土している。この遺跡は1940年にフランス人考古学者マルレが発掘した。 |
| b チャンパー
| 扶南に遅れて2世紀頃にインドシナ半島東部、現在のベトナム中部から南部にかけてチャム人(オーストロネシア語族)が活動するようになった。始めこの地方は漢の武帝の日南郡に支配されていたが、192年頃の後漢時代に独立して林邑と言われた。このころから東西を結ぶ海上交通の要地にあったため港市国家として発展し、3世紀には「インド化」が進んだ。その後、7世紀の唐代には環王国、9世紀以降は占城国という名で中国史上に現れる。彼らは自らは「チャンパー王国」と称していた。都は10世紀末から中部ベトナムのヴィジャヤ。12世紀には西方のカンボジア王国(真臘)のアンコール朝と争い、13世紀には元の侵入を受けた。チャム人は北方から起こったベトナム人(中国文化の影響を強く受けていた)に次第に圧迫され、15世紀に大越国(北部ベトナム)の黎朝に征服され、衰退した。 |
| チャム人 | インドネシア人などと同じく、オーストロネシア語族で、ベトナム人(オーストロアジア語族)とは系統が違う。はじめ漢の日南郡の支配を受けていたが、2世紀頃から中部ベトナムを中心に交易に従事し、国家を形成した。いわゆる港市国家の一つと考えられる。この国は中国の史料には林邑として現れるが、次第にインド化したため、チャム人たちはサンスクリット語であるチャンパーと自称するようになった。現在ではベトナムの山岳地帯に住む少数民族となっている。ベトナム中部から南部で見られる「カラン」という石塔は、チャム人が残したものである。チャム人は現在はベトナムの少数民族として存在している。 |
| 林邑 | 中部ベトナムに存在したチャム人の国チャンパーの中国名。その後、7世紀の唐代には環王国、9世紀以降は占城国という名で中国史上に現れる。 |
| 占城 | チャンパーの中国名で、9世紀頃から史料に現れる。この地を原産とする占城稲(チャンパー米)が、10世紀末の宋代に中国に導入され、江南地方の二期作を可能にして、生産力が急速に増したこともよく知られている。 |
| c カンボジア
| 扶南がメコン下流の海岸部で活躍したのに対し、クメール人でメコン川の中流域の山岳部で活動していた農耕民が、6世紀以降有力となり、7世紀に扶南を滅ぼし、カンボジア王国(クメール王国ともいう)を建設した。中国ではこの王国を「真臘」と言っている。この真臘も「インド化」した文明を持ち、ヒンドゥー教とシヴァ神信仰を受け入れた。8世紀中頃、北の陸真臘と南の水真臘に分裂したが、9世紀以降はアンコール朝のもとで全盛期を迎えた。アンコール朝の12世紀に、壮大な寺院建築であるアンコール=ワットが建設されと、都城であるアンコール=トムが建設され、東南アジア文明の代表的な文化遺産となっている。カンボジアはその後、西に起こったタイ人に圧迫されて衰退する。近代にはいるとヨーロッパ勢力の進出を受け、1863年にフランスの保護国となる。1949年独立するが、ベトナム戦争に巻き込まれ、その後1970年から1991年まで激しいカンボジア内戦が展開された。1993年からカンボジア王国となりシアヌークが国王に復帰。現在の国旗にはアンコール=ワットの図柄を取り入れている。 → カンボジア(独立) カンボジア王国(現在) |
| 真臘
→ロウ→拡大 | 中国の文献で、現在のカンボジアのこと。真臘の語源についてはわかっていない。唐以降の中国各王朝と交渉を持ったカンボジア王国(クメール王国)を真臘といい、8世紀頃に陸真臘と水真臘に分裂、ついでアンコール朝が起こるがアンコール朝も真臘といわれた。13世紀末にカンボジアを訪れた元の周達観が著した書物も『真臘風土記』という。 |
| クメール人 | 現在のカンボジアの大部分をしめる人々で、オーストロアジア語族に属する。カンボジアの周辺、メコンデルタ地帯やタイのコーラート高原地方にも広がっている。7世紀に扶南に代わって登場したカンボジア王国(真臘)が彼らが建設した最初の国家とされる。12世紀にはアンコール朝のもとで全盛期を迎えた。初めはヒンドゥー文化を受容したが、アンコール朝全盛期のジャヤヴァルマン7世は大乗仏教を信仰した。 |
クメール文字
 | カンボジア王国の公用語であるクメール語を書き表すための文字。東南アジア大陸部ではビルマ文字の起源となったモン文字と並んで古い文字である。最も古い例として7世紀の碑文が残っている。ビルマ語と同じくインドのブラーフミー文字を手本としており、ヒンドゥー教の受容と共に「インド化」の一例といえる。左はそのその例で、チョムリアプスオ、というあいさつの言葉。<『図解・アジア文字入門』河出書房新社 p.33>
後にカンボジアを領有したフランスは、ベトナムと同じようにラテン文字を押しつけようとしたが、カンボジア人はクメール文字の使用をやめず、現在に至っている。 |
| アンコール
| カンボジア王国(真臘)の都の置かれたところ。トンレサップ湖の北岸にあたり、アンコール朝の代々の都であった。アンコールとは、「都市」を意味するサンスクリット語「ナガラ」がクメール語化したもの。9世紀以降、アンコール朝の諸王はこの地を中心にインドシナ半島を広範囲に支配し、道路網を築いた。都の周辺にはバライという貯水施設を多数建設し、水路をめぐらしていた。その中心部には都城であるアンコール=トムがあり、その南にもとはヒンドゥー教の寺院として造られ、後に仏教寺院となったアンコール=ワットの巨大な石造建築群が残っている。アンコール朝は14世紀にタイのアユタヤ朝に押されて首都をプノンペンに移したため、アンコールは荒廃し、現在はジャングルの中に埋もれている状態である。またカンボジア内戦期にはポルポト派によって文化財の破壊が行われ、荒廃が進んだため、国際的な復興の援助が始まっている。 |
| アンコール朝
| カンボジア王国(真臘)全盛期の王朝。真臘は8世紀に分裂していたが、802年にアンコール朝のジャヤヴァルマン2世が立って統一された。その後、アンコール帝国とも言われて繁栄が続いた。12世紀のスールヤヴァルマン2世の時、領土を拡大し、使節を宋に派遣し、アンコール=ワットに建造した。1177年にはチャンパーによってアンコールを占領されたが、ジャヤヴァルマン7世が1181年に奪回、首都アンコール=トムを復興させた。ジャヤヴァルマン7世は仏教徒であったのでこの時期には仏教美術が発達した。しかし、13世紀になると西方のシャム人(暹羅)が反乱を起こし、スコータイ朝として自立し、アンコール朝は衰退に向かう。13世紀末には元の使節が来ているが、随行した周達観が記録した『真臘風土記』には、この時期「富貴真臘」と言われてなおも繁栄していたことが伝えられている。14世紀にはタイ人のアユタヤ朝が勃興し、その侵攻を受けるようになり、1432年にアンコールを放棄してプノンペンに首都を遷した。 |
| スールヤヴァルマン2世 | 12世紀前半、カンボジアのアンコール朝の王。東は1145年にチャンパー(現在の中部ベトナム)の首都ヴィジャヤを陥れ、西はビルマの国教までの広い範囲を支配した。また30年の年月をかけてアンコール=ワットを造営した。アンコール=ワットは当初はヒンドゥー教寺院として造られ、東南アジアのヒンドゥー文化の最高傑作とされる。 |
d アンコール=ワット

| 12世紀に建設されたカンボジアのアンコール朝時代の文化遺産である大寺院建築群。アンコールとは「都市」、ワットが寺を意味するので「首都の寺」となる。スールヤヴァルマン2世がヒンドゥー教の寺院として建設した。中央と四隅に塔を持ち、周囲の回廊の壁面には『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』の物語が細かにレリーフされており、見る人を圧倒する。12世紀末のジャヤヴァルマン7世は仏教を厚く信仰するようになり、アンコール=ワットも仏教寺院として用いられるようになった。アンコール=ワットは東南アジアの文明を代表する遺跡であり、現在のカンボジア王国の国旗にも用いられている。現在はカンボジア内戦で荒廃し、ユネスコを中心とした保存運動が展開されている。上智大学の学長石沢良昭氏はアンコール=ワットの研究者で、その保存運動に取り組んでいる。
Epi. アンコール=ワットの日本人の落書き アンコール=ワットには、鎖国以前に訪れた日本人の落書きが一四カ所ほど残っている。その一人の「肥州の住人藤原朝臣森本右近大夫一房」は、父儀大夫の菩提を弔い、老母の後生を祈るため、はるばる数千里の海上を渡り、寛永九(1632)年正月にこの寺院に到来し、仏像四体を奉納した、と墨書している。森本右近大夫は肥前松浦家の家臣で、父儀大夫は加藤清正の家臣で朝鮮の役で武勇を馳せた人物であった。当時は徳川家康の朱印船貿易が盛んに行われ、カンボジアにもたくさんの日本町がつくられていた。日本人はこの地を「祇園精舎」と思い込んでいたようで水戸の彰考館には「祇園精舎の図」としてアンコール=ワットの図面が残されている。森本右近大夫の子孫は岡山に現存し、彼の墓も京都で見つかったが、位牌には森本左大夫となっていう。彼が落書を残した1632年には日本人の海外渡航禁止令が出されており、彼も帰国後は名前を変えなければならなかったらしい。<石澤良昭『アンコール・ワット 大伽藍と文明の謎』 1996 講談社現代新書 p.193>
出題 2009年 センターテスト世界史B 第3問 問4 (正誤判定) イ 左の写真(別写真)の遺物は、「大乗仏教寺院として建造されたものである。」 → 正解 × (解説)アンコール=ワットはヒンドゥー教の寺院として建設され、後に仏教寺院となった。 |
| アンコール=トム
| 9世紀末から建造が始まり、12世紀末に完成したカンボジア王国のアンコール朝の王都。1181年、チャンパーの支配からアンコールを奪回したジャヤヴァルマン7世が完成させた。「大きな都」の意味で、5つの城門を持つ1辺約3kmの城壁と環濠に囲まれ、中央にバイヨン寺院が建造されたほか、多数の寺院が築かれている宗教的な都城である。20キロほど北方には、アンドレ=マルローの小説『王道』の舞台となったことで有名なパンテアイ=スレイ寺院があり、また南に隣接して東南アジアのヒンドゥー文化遺産として最も有名なアンコール=ワットがある。これらの多くの石造建造物は、カンボジア内戦で大きな被害を受け、また盗難などの被害が深刻になっている。
Epi. 略奪が繰り返されているアンコール遺跡 クメール人はすぐれた石彫技術を持ち、その遺産はアンコール=ワットとアンコール=トムおよびその周辺にたくさん残っている。しかしさらに多くの文化財がカンボジア国外に持ち出されてきた。まず14世紀にアンコール朝を滅ぼしたアユタヤ朝によって持ち出されたものは今もタイ国内にみられ、さらに18世紀にアユタヤ朝がビルマのコンバウン朝に滅ぼされたため、ビルマにも多数のクメール美術の遺品が持ち去れている。フランスがカンボジアを植民地化すると、クメール美術のすばらしさが注目され、多数の女神像や仏像、彫刻が海外に持ち出された。最も有名なのが、後にフランスの文化相になる作家アンドレ=マルローがパンテアイ=スレイ寺院の女神像(カンボジアのモナ=リザといわれた)を持ち出そうとして逮捕された事件であろう。彼は自ら『王道』という作品でその顛末を描いている。第2次大戦後の1970〜80年代のカンボジア内戦が文化財の散逸に拍車をかけた。ポルポト派は遺跡の石像を切り出して密輸出し資金を稼いだ疑いをもたれている。そして戦乱のやんだ現在でも、アンコール周辺の遺跡は盗掘の被害が続いている。いわゆる骨董ブームがそれらの遺品に高値を呼んでいるのである。<三留理男『悲しきアンコール』2004 集英社新書> |
| ジャヤヴァルマン7世 | カンボジアのアンコール朝全盛期の王。1177年にチャンパーによって占領されたアンコールを1181年に奪回し、王位に即いた。さらに1190年にチャンパーを征服し、アンコール朝の版図をほぼインドシナ半島全域に広げた。篤く仏教を信仰し、都城のアンコール=トムを仏教都市として完成させ、多くの仏教寺院を建造した。一方でヒンドゥー教に対しては冷淡で、ヒンドゥー寺院であったアンコール=ワットも仏教寺院として使われるようになった。ジャヤヴァルマン7世は、国内に道路網を整備し、その道沿いに102の病院(施療院)をはじめ、多くの石造寺院を建造し、その版図はインドシナ半島全体に及んだ。しかし王の死後、アンコール朝の衰退が始まった。
Epi. 『癩王のテラス』 ジャヤヴァルマン7世は多くの病院を建造したことでも知られるが、伝説に拠れば、彼自身が癩病(ハンセン氏病)を病み、若くして死んだという。アンコール=ワットを訪れた三島由紀夫は、この「若き癩王の美しい彫像」をみて着想を得、戯曲『癩王のテラス』を発表した。しかし、ジャヤヴァルマン7世がハンセン氏病であったという確証はない。「タ・プローム碑文によれば、王は国内に102の施療院(アーロギャーシャーラ、「病人の家」の意味)を建て、王みずから病人の世話に関わり、年に三回薬や薬草を供与していたという。<石澤良昭『アンコール・王たちの物語』2005.7 NHKブックス> |
| ピュー
| ビルマ(ミャンマーは現在の国名。地域名としてはビルマを使う)に最初に現れた民族。8世紀頃、イラワディ川中流で栄えた民族で、シナ=チベット系の民族。中国の史料では「驃」という字があてらている。やはりインドの影響を受け、仏教が広がっていた。9世紀に中国南部に起こった南詔に圧迫されて衰え、史料から姿を消した。なお、イラワディ川下流から海岸部にはオーストロネシア語族のモン人が仏教文化を生み出していた。 |
| ビルマ人 | ビルマ人はもとチベットから中国甘粛省のあたりに居住し、南詔に属していたらしいが、8、9世紀ごろから南下し、イラワディ川流域の平地に定住するようになった。先住民である中流のピュー人や、下流のモン人を征服しながら、文字や上座部仏教を彼らから受け入れ、潅漑農業を学んで勢力を強め、11世紀までにビルマ最初の統一国家パガン王国をつくった。16世紀のトゥングー朝、18世紀からのコンバウン朝もビルマ人主体の国である。現在のビルマにおける多数民族でもあるが、ビルマにはモン人やシャン人、カチン人、カレン人などさまざまな少数民族が存在している。 |
| e パガン朝
| 11世紀中頃、ビルマ人が作った最初の統一王朝。1044年、パガンに都を置いたアノーヤター王が、モン人を征服し、パガン朝をひらいた最初の王とされる。先住民であるモン人はスリランカ(セイロン)の高度な上座部仏教の文化の影響を受けていたので、パガン朝はそれを取り入れ、首都パガンに多くのパゴダ(仏塔)を建造した。第3代のチャンシッター王(在位1084〜1112年)の頃が最盛期でモン人との融和も図られ、仏教文化が開花した。その後も多くの仏塔・寺院を建設したので、建寺王朝と言われている。しかし仏塔・寺院の建造に力を入れすぎて13世紀後半には国力は衰亡し、雲南地方を併合した元のフビライ=ハンの大軍が1287年に首都パガンを攻撃し、パガン朝は滅亡した。
Epi. 建寺王朝、仏寺成って国滅ぶ パガン朝の寺院建築は、マルコ=ポーロの『東方見聞録』にも、「太陽の光に触れては燦然と輝き、はるか彼方からでもその光輝を望見できる」美しい大塔のことを伝えている。王たちは仏教に深く帰依し、自ら僧院生活を送り、寺院建築に打ち込んだ。最後の国王ナラティハパテ王も6年かかってパゴダをつくったが民衆から「仏寺成って国滅ぶ」といわれた王であった。<石澤良昭/生田滋『東南アジアの伝統と発展』1998
中央公論社 p.200-202> |
| 上座部仏教(ビルマ) | ビルマ人はモン人を征服する過程で、モン人から上座部仏教を受け入れたが、初めは大乗仏教およびヒンドゥー教も同時に信仰され、それらの要素が入り交じっていた。12世紀中頃にスリランカから上座部仏教のマハー・ヴィハーラ派(大寺派)が伝えられた。この派はスリランカ王パラークラマ1世が改革したもので、パーリ語による仏典研究、僧院の修行規定などを重視し、パガン朝の王が帰依することとなり、主流となった。こうして大寺派の上座部仏教がビルマに定着し、13世紀にはタイ、カンボジア、ラオスに広がり、東南アジアの民衆の篤い信仰を受けるようになった。<石澤良昭/生田滋『東南アジアの伝統と発展』1998
中央公論社 p.200-202> |
| 仏塔・寺院(ビルマ) | 11世紀中頃から13世紀までのパガン朝では上座部仏教が篤く信仰され、盛んに仏塔・寺院が建造され、建寺王朝といわれた。その建築様式はインドの影響を受けているが、次第にビルマ独自の様式を強めていった。仏塔(ストゥーパ)はインドに起源を持つがビルマで段状の基壇を持つ巨大なものがつくられるようになった。ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダがその代表的なものである。寺院建築も大型化し、全盛期の12世紀初頭のアーナンダ寺院(パガン)などが有名。いずれにせよパガン周辺にはいたるところに仏塔・寺院を見ることができる。 |
| 建寺王朝
| 12〜13世紀のビルマのパガン朝は、上座部仏教を篤く保護し、首都パガンを中心に多くの仏塔・寺院を建設したので建寺王朝といわれる。しかし、代々の王が建寺に熱中するあまり、次第に国力を消耗し、衰退の一因ともなった。 |
ビルマ文字
 | ビルマ(現ミャンマー)で使用されている文字で、インドのブラーフミー文字(ヒンディー語を書き表す文字)の系統にある文字(漢字系統とは全く違う)。9世紀中頃中国南西部からイラワディ川流域の平野に進出したビルマ人、東南アジア大陸部で進んだ文化を持っていたモン人の使用していた文字を借りて作った。丸い字形が特徴だが、これはヤシの葉(貝葉)に書くためであったらしい。左はビルマ文字の例(ミンガラーバー、あいさつのことば)<『図解アジア文字入門』河出書房新社 絵も> |
| モン人 | モン人は、ベトナム人やクメール人と同じく、オーストロアジア語系に属し、現在のタイのチャオプラヤ川流域やビルマのイラワディ川下流域に居住していた。河川交通を利用した交易で栄え、タイでは6〜7世紀にドゥヴァーラヴァティ王国を作った。また9世紀にビルマのイラワディ川河口部のペグーを中心にベンガル湾を隔てたインドとの交易を行う港市国家を作った。モン人はインドの影響受け、仏教を早くから信仰していた。ビルマのモン人は13世紀末にパガン朝の滅亡に乗じて自立し、ペグー朝を建てるが、1531年に再びビルマ人のトゥングー朝に併合される。その後もビルマ人との対立が続き、トゥングー朝の弱体化の要因となる。1752年からはコンバウン朝の支配を受ける。現在はタイからビルマにかけての海岸地方に少数民族として続いている。 |
| f ドヴァーラヴァティー王国
| 7世紀頃、現在のタイに現れた最初の国家。タイからビルマにかけて活動したモン人の建てた国と言われ、チャオプラヤ川下流のアユタヤを中心に遺跡が発掘されている。チャオプラヤ川を利用して内陸部と南シナ海交易圏を結ぶ交易活動を行った港市国家であった。インド文化の影響を受け、仏教が保護され、仏像などが発掘されている。また、この時代の仏教寺院建築として残っているのが、プラパトム寺院である。7世紀には中国の文献に現れ、玄奘は「堕羅鉢底国」、義浄は「杜和鉢底国」として伝えている。9世紀頃には衰え、10世紀頃に滅亡した。
Epi. 日本にやってきたドヴァーラヴァティ人 奈良時代の文献『日本書紀』によると斉明天皇の時の西暦657年に、「覩貨邏国の男二人、女四人、筑紫に漂い泊まれり」という記事がある。これがドヴァーラヴァティ人であろうと言われている。おそらく中国への使節か交易に赴いたドヴァーラヴァティ人が嵐に流され、日本に漂着したのであろう。 |
| ベトナム人 | 現在のベトナムは多民族国家であるので、ベトナム国民という意味ではいくつかの民族を含む。多数民族はキン族(ベト族ともいう)で、彼らはモン人やクメール人と同じ、オーストラロアジア語系に属する。彼らの本拠は北部の紅河流域(トンキン地方)で、次第に中部のチャム人や、メコン流域のクメール人などを征服して、現在のベトナムが形成された。彼らは中国と接しており、長くその支配を受けたために、漢字・儒教などの中国文化の影響下にあった。 |
| g 大越国
| ベトナムの北部では漢の武帝の征討を受けて南越が滅亡して以来、中国支配が続き、唐代には安南都護府が置かれたが、唐末五代十国の混乱期を経て、ようやく独立の機運が出てきた。966年、丁部領が独立を達成、大瞿越(ダイクヮックヴィェト)を建国した(丁朝)。丁朝と次の黎朝(前黎朝)は短命に終わったが、李公蘊が1009年に建てた李朝(リー朝)は、1054年以降国号を大越国とし、ベトナム最初の長期権力となり、1225年まで続く。その間、李朝では中国の諸制度を取り入れ、儒教・仏教・道教が保護された。1225年から陳朝(チャン朝)に交替し、その時代1258年に元のフビライ軍の侵攻を受けて粘り強く抵抗したが、最終的には服属(安南国と言われる)した。また南方のチャンパーとも戦い、民族意識が高まって字喃(チュノム)が考案された。1400年には胡朝(ホー)に代わったが、1406年、明の永楽帝の征服を受け、ベトナムは再び中国の支配を受けるようになり、1428年に黎利が明からの独立を勝ち取り、黎朝を起こすまで明の支配が続く。 |
| h 李朝
| 1009年に李太祖(李公蘊)がひらいた大越国の王朝(中国からは安南国といわれる)。北部ベトナムのホン河下流のデルタ地帯の治水事業を行い、都ハノイ(昇竜)を中心に国力を充実させた。李朝では、中央官庁を中国風に整備し、1075年には科挙を導入し官僚制を整備した。また儒教・仏教・道教をともに保護した。1075年には宋の神宗が王安石の進言をいれ、大越国遠征を行ったが、李朝はそれを撃退し、以後は宋と対等な外交を展開している。1225年、女帝昭皇を最後に滅亡した。 |
| i 陳朝
| 1225年から1400年の北部ベトナムの大越国の王朝。中国からは安南国と言われる。13世紀にはモンゴルの三度にわたる侵攻と戦い、独自のベトナム文化を創り上げた。まず1258年、モンゴルのモンケ=ハンの時、フビライの侵攻を受け服属したが、その後もたびたび反旗をひるがえした。ついでチャンパーへの出兵の協力を拒否し、1289年フビライ=ハンのとき再び服属した。その後、南部ベトナムのチャンパーと戦いその領土を広げた。そのような民族意識が高まり、ベトナム独自の文字である字喃(チュノム)を考案した。またベトナムの歴史書である『大越史記』(漢文で記されている)が編纂された。14世紀には豪族が台頭して衰退し、王が宰相に暗殺されてしまった。実権を握った宰相は胡氏を名乗り、1400年に胡朝を開いたが、この内紛に乗じた明の永楽帝が1406年に大軍を派遣し、翌年胡朝は滅び、陳朝が一時復活する。間もなく明はベトナムを直轄支配するが、反明の戦いに決起した黎利が独立を回復し1428年に黎朝を成立させる。 |
j 字喃(チュノム)
   
| 13世紀に、ベトナムの陳朝の時代、漢字をもとにしてつくられたベトナム独自の文字。字喃の音がチュー=ノム。中国の文明の影響の強かったベトナムで、民族意識が強まってきたことを示す。ベトナム語を表記するために作られた文字で、このころベトナム語で唱われた詩をチュノムで書き記す国語詩が流行した。陳朝の次の胡朝もチュノムの使用を奨励した。左は字喃(チュノム)の例<『今昔文字鏡』CD−ROM 紀伊國屋書店 より>
補足 現在のベトナム語の文字 ベトナム独自の文字としてつくられたのがチュノムであるが、現在は使われていない。チュノムは習得が難しく、一般には広がらなかった。ベトナムにやってきたイエズス会宣教師たちは慣れ親しんだラテン文字でベトナム語を書き表そうとした。1651年にはフランス人宣教師ローズがラテン文字によるベトナム語表記の基準を作った。19世紀後半にフランス領になってからラテン文字表記が広まり、新聞や小説もラテン文字で表現されるようになった。1945年独立したとき、ホー=チ=ミン大統領は識字率向上のためラテン文字の使用を推進することを宣言、公式文字となった。現在は複雑なベトナム語の母音を表記するための補助記号を導入したベトナム正書法(チュー・クォック・ングー、「国語の字」の意味)が制定されている。<『図説・アジア文字入門』河出書房新社
p.102> |
| マラッカ海峡 | → 7章 マラッカ海峡 |
| マレー人 | 現在のマレーシアやスマトラ島、ボルネオ島などに広がるマレーポリネシア語族(オーストロネシア語系とも言う)に属するマレー語を話す人々。シュリーヴィジャヤ王国やマラッカ王国などの港市国家を発展させた。また東南アジアでイスラーム化したことも特徴である。 |
| k シュリーヴィジャヤ王国
| スリウィジャヤとも表記する、スマトラ島東南部からマレー半島にかけて7世紀頃から繁栄したマレー人の王国。扶南に代わって東南アジアの貿易の中心として繁栄した港市国家であった。都はスマトラ島のパレンバン。マラッカ海峡を挟んだマレー半島とスマトラ島、さらに最盛期の7世紀にはジャワ島やタイなどにも勢力が及んだが、自国領には主たる産物はなく、中継貿易を行っていた。中国の史料には、室利仏逝または三仏斉などという名で出て来ており、定期的に中国に使節を送り、交易を行っていた。672年に唐の僧侶義浄がインドに行く前にシュリーヴィジャヤに4年間滞在したことが知られ、彼の『南海寄帰内法伝』によると、この「室利仏逝国」には千人もの僧侶がいる大乗仏教の盛んな国であったという。この間、ジャワ島に起こった同じ仏教国のシャイレンドラ朝とは関係が深く、連合したもあったらしいが文献が少なくよくわかっていない。その後、1025年には南インドのタミル人国家チョーラ朝の侵攻を受けて次第に衰退し、14世紀にジャワ島にマジャパヒト王国が起こると消滅した。シュリーヴィジャヤの支配権は15世紀のマラッカ王国に継承される。 |
| l 義浄
| → 3章 2節 イ.唐代の制度と文化 義浄 |
| m シャイレーンドラ朝
| 8〜9世紀にインドネシアのジャワ島中部を中心に存在した王国。大乗仏教を保護し、仏教寺院であるボロブドゥールを建造した。海上貿易に従事する港市国家として栄え、一時はベトナム、カンボジアにも進出し、隣接するスマトラ島のシュリーヴィジャヤとも連合したことがあったらしい。 |
| ジャワ島
| ジャワ島は現在のインドネシアの中心となる島で、大きさは日本の本州の半分強。面積ではインドネシア全体の7%にすぎないが、人口では60%を超える約1億人が集中している。ジャワ原人の化石が見つかったトリニールもジャワ島にある。現在も人口密集地帯である。ジャワ島はおよそ三分の一ずつ、西部・中部・東部に分けられ、それぞれ違った歩みをしているので注意しなければならない。住民も西部はスンダ人、中部・東部をジャワ人として区別する(民族系統はいずれもマレー人)。
仏教文化とヒンドゥー文化 5世紀頃からインド商人の渡来によってインドのグプタ文化が伝えられ、仏教・ヒンドゥー教の双方が伝えられ、またスマトラ島・マレー半島のシュリーヴィジャヤ王国とも関係があった。8世紀の中部ジャワにシャイレーンドラと古マタラムという二つの国生まれた。シャイレーンドラは大乗仏教が信仰され、仏教寺院としてボロブドゥール寺院が建設され、古マタラム王国ではヒンドゥー教が信仰されて、プランバナンというヒンドゥー寺院が建設された。その後、ジャワ島には11世紀にはクディリ朝、13世紀にはシンガサリ王国が興亡した。
元の艦隊の来航 1292年、元のフビライ=ハンが大艦隊を派遣して来たときはシンガサリ王国は抵抗し、元と結んだマジャパヒト王国が権力を握るという王朝交替が起こったが、マジャパヒト王国は巧みな交渉で元軍を撤退させ、独立は維持した。
イスラーム化 マジャパヒト王国はヒンドゥー教を奉じていたが、16世紀から西部にバンテン王国、東部にマタラム王国というイスラーム勢力が生まれ、イスラーム化が進んだ。
オランダの植民地支配 17世紀末にはオランダの進出が始まり、オランダ東インド会社の植民地経営の拠点として建設されたバタヴィアをを中心にオランダ領東ンドとして植民地支配を受ける。1825年〜30年にはディポネゴロを中心とした反オランダ蜂起であるジャワ戦争が起こったが、それを鎮圧した後、オランダの総督ファン=デン=ボスは強制栽培制度によるコーヒー、サトウキビ、藍の生産を強制した。
インドネシアの独立 20世紀に入り、インドネシア独立運動が始まり、第2次世界大戦後に独立、インドネシアの首都ジャカルタとして、政治経済の中心地となっている。 |
| n ボロブドゥール
| インドネシアのジャワ島中部にある8世紀のシャイレーンドラ朝時代の大乗仏教遺跡。大乗仏教を保護したシャイレーンドラ朝の王によって建設された山岳寺院で、カンボジアのアンコール=ワットと並ぶ、東南アジアの貴重な文化遺産である。大石塔(ストゥーパ)を中心に、インドのグプタ朝の影響が見られる。ボロブドゥール遺跡は東南アジアの仏教建築の最高傑作とされ、世界遺産にも登録されているが、その建造の経緯などは文献が無くよくわかっていない。10世紀にはジャワ中部のムラピ火山が大噴火を起こし、人々が住めない状況となったため、ボロブドゥールの存在も忘れられてしまい、19世紀にイギリスのラッフルズによって再発見され、その後はオランダ人によって修復が進められた。最近ではユネスコの手で修復工事が行われ、その構造や建築技法が判ってきた。 |
| 古マタラム王国
| 8世紀にジャワ島中部にあったヒンドゥー教国。マタラムはジャワ島中部の古地名で、現在のジョクジャカルタの周辺を言う。この地に16世紀に出現したイスラーム教国であるマタラム王国と区別して古マタラム王国という。古マタラム王国の時に造営されたと考えられるヒンドゥー教の寺院がプランバナンに現存している。同じ時期にジャワ中部にシャイレーンドラ朝が造営した仏教寺院のボロブドゥール寺院とともに世界遺産に登録されている。しかし、この両者の関係はまだよくわかっていない。 |
| クディリ朝
| ジャワ島東部に11世紀の初めに生まれた王朝。初代の王エルランガ王(1037年〜1049年)を讃える碑文が残っており、それによるとヴィシュヌ神の化身とされ、バラモンによって推されて王になったという。このころから仏教に代わりヒンドゥー教が優勢となり、『マハーバーラタ』もジャワ語に翻訳され、ジャワ独特の影絵芝居ワヤンの題材とされるようになる。ジャワ島には次の13世紀にはシンガサリ朝が元の侵入を撃退したことで知られ、13世紀末にはマジャパヒト王国が登場する。マジャパヒト王国を最後に、次のマタラム王国からはジャワはイスラーム化することとなる。 |
| ワヤン=クリ
| ワヤンはジャワの伝統演劇の総称で、本来は「影」の意味。特にその中の影絵芝居をワヤン=クリ(あるいはワヤン=クリット)という。影絵芝居の他に絵巻の絵解き(ワヤン=ベベル)、木偶人形芝居(ワヤン=ゴレ)、板人形芝居(ワヤン=クリティ)、俳優が演じる芝居(ワヤン=オラン)がある。10世紀頃、ジャワの宮廷でインドの古代叙事詩『ラーマーヤナ』『マハーバーラタ』が翻訳され、その物語を題材として芝居が演じられるようになり、14〜15世紀頃、イスラーム神秘主義の布教者たちが影絵芝居(ワヤン=クリ)を考案して盛んになった。19世紀にはさまざまな人形が作られ、また伴奏音楽のガムラン楽器も発達して、高度な演劇形態となり、世界に知られるようになった。 |
 |