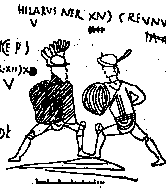| 用語データベース 01_3 |
  |
| 3.ローマ世界 |
| ア.ローマ共和政 |
| 古代イタリア人 | イタリア半島にひろがり、古代文明を築いたインド=ヨーロッパ語族に属する民族。古代イタリア人がイタリア半島に南下してきた時期には前16世紀ごろから前10世紀ごろまでの幅で諸説ある。イタリア人以前に旧石器文化から新石器文化、さらに青銅器文化も存在していたが、イタリア人はこの地に鉄器文明をもたらしたものと考えられている。彼らは半島に広がり、先住民族と混合しながらイタリア人となっていった。半島各地に都市を造っていくつかの系統に分かれ、その一つで最も有力になったのが、ローマを建国したラテン人。ギリシア人が南イタリアに住んでいたイタリ人と接してからこの半島全体をイタリアと呼ぶようになった。その後も古代のエトルリア人や、4世紀ごろからのゲルマン人、10世紀からのノルマン人など、外来の諸民族との混合が進み、「イタリア」という民族国家が形成されるのは、ずっと遅く、19世紀の近代イタリアの成立からである。 |
| a ラテン人
| インド=ヨーロッパ語族に属するイタリア人の一系統。イタリア人はギリシア人の南下と同じころの前16世紀にイタリア半島に南下したと思われるが、その中のラテン人は前11世紀ごろにイタリア半島の中部に入ったようである。ラテン人が定住したのがラティウム地方で、ローマなどの都市が建設された。彼らの言語であるラテン語は、ローマ文明を支える言語となる。 |
| b ローマ
(建国神話) | ローマの建国神話は国民的詩人ヴェルギリウスの『アエネイス』の叙事詩に物語られている。それ以後の伝承では、アエネイスの子孫がアルバ・ロンガの王となる。200年の後、兄ヌミトルの王位を狙った弟アムリウスは、兄の孫のうち男は皆殺し、女子のレア・シルヴィアをウェスタ神の巫女にしてしまった。レアは川辺で居眠りするうち、軍神マルスの子を身籠もる。彼女は双子の男の子を産んだがアムリウスは怒って双子を籠に入れてテヴェル川に流してしまった。だが双子を入れた籠はイチジクの木に引っかかって川岸に流れ着いた。そこに一匹の雌狼がやってきて双子に乳を与えた。その後双子は王の羊飼いに発見されて育てられ、ロムルスとレムスと名づけられる。やがて成長した二人はアムリウスを討ち、祖父のヌミトルを復位させる。そして自分たちが拾われた場所に新しい都を建てようと、それぞれ丘を選び、どちらが新都の支配者になるか鳥占いで決することにした。翌朝、ロムルスの選んだ丘には12羽、レムスの丘には6羽が飛来したので、ロムルスが選ばれたことになった。ロムルスは二頭の牛に引かせた犂で都の聖域を定めた。しかし不満なレムスはそれを飛び越えてしまう。怒ったロムルスはレムスを殺し、聖域を侵す者は殺すと宣言、絶大な支配者となり、その都はロムルスにちなんでローマといわれるようになった。この出来事は前753年4月21日のこととされ、今でもローマの住民のまつりの日となっている。またローマ人は、キリスト紀元が行われるようになるまでは、この年を紀元元年として年代を数えていた。そして現代でもローマの町の象徴は、狼のお乳を飲む双子の像である。<モンタネッリ『ローマの歴史』中公文庫、本村凌二『ギリシアとローマ』1997
世界の歴史2 中央公論新社 などによる> |
| ティベル川
| ティベレ川とも表記。ローマ市中を流れる川で、建国神話ではロムルス兄弟がこの川に流され、流れ着いたところで牝狼に育てられたという。ロムルスがその地に建設した都市が、その名にちなんでローマと言われるようになったという。ティベル川の船運はローマの重要な交通手段とされ、河口のオスティアはローマの外港として栄えた。 |
| A 王政
| 伝説で前753年にローマを建国したというロムルスから、全部で7代の王政が続いた。王位は世襲ではなく、有力者の中から選出された。そのうちの五代目からはエトルリア人の王であるされている。王たちは都市の建設と防衛に努めてきたが、前509年にローマ市民は王を追放し共和政としたと伝えられている。
Epi. ローマの建国とサビニ人の女たち 伝説では、前753年にローマを建国したロムルスは、ローマに女性が少なかったので、近隣のサビニ人の女性を奪ってきた。そのためため両者は戦いとなったが、略奪された女たちが「どちらが勝っても私たちは不幸になる、サビニ人が勝てば夫を失い、ローマ人が勝てば兄弟を亡くすことになる」、と訴えたので戦いはやみ、その時の約束でローマ人とサビニ人が交互に王位に就くこととなったという。そこでロムルスの死後の2代目の王はサビニ人のヌマが選ばれたという。 |
| a エトルリア人
| エトルリア人は系統は不明であるが、前7世紀の末に北イタリアに入り、前6世紀にはほぼイタリア全土を支配していた。ギリシア文化の影響を受け、鉄器を使用し、ギリシアとも交易を行い繁栄していた。その遺跡からは、独自のエトルリア文化といわれる金属器や壺、壁画などが見つかっている。ラテン人のローマも、この時期にはエトルリア人の王に支配されていた。その言語は、インド=ヨーロッパ語族に属しておらず、文字はギリシア文字を使用しているが、まだ完全に読解されていない。
エトルリア人は前6世紀には地中海貿易にも進出し、ギリシア人やフェニキア人とも競争していた。イタリア半島の西側の海をティレニア海というのはエトルリアからきているという。 |
| B 貴族共和政の成立 | 都市国家ローマでエトルリア人の王を追放し共和政を樹立したのは紀元前509年とされており、前6世紀末には王政に代わって貴族共和政に移行したと思われる。ローマ市民は貴族・騎士・平民・無産市民(プロレタリー)などの階級があったが、当初権力を握ったのは少数の貴族であり、貴族共和政といわれる。最高議決機関として市民の直接参加の原則のもとで「民会」が開催されたが、実権は貴族のみが参加する元老院が握り、また執行機関である執政官や非常時に置かれる独裁官も貴族から選ばれるなど、寡頭(少数者による)共和政であった。ローマがイタリア半島統一を進める過程で、平民が重装歩兵として発言力を強め、次第に貴族と平民の身分闘争が行われるようになり、前3世紀には平民による共和政が成立する。 |
| a 貴族(パトリキ) | 土地と奴隷などの豊かな財産をもち、都市の上層部を形成する市民で、元老院議員や執政官(コンスル)の地位を独占し、エトルリア人の王を追放してからは貴族共和政を行った。騎士(エクイテス)は厳密には貴族とは別で、貴族よりは一段下だが、豊かな商工業者として騎士となり、発言権を持つようになって貴族と並んで元老院議員になれるようになった階層。貴族と騎士が支配階層を形成した。貴族は大土地を世襲し、奴隷を所有するほか、有力者として平民(自由民、プレブス)を保護した。貴族の保護を受け服従する人をクリエンテスという。 |
| b 平民(プレブス) | 中小農民や商工業者としてローマの一般市民層を構成。はじめは参政権は認められなかったが、ローマが半島統一を続ける過程で、重装歩兵としてその武力の中心となり、次第に発言権を増し、政権を独占する貴族と身分闘争を展開し、さまざまな機関の創設、立法などを通じて貴族と対等な権利を獲得していく。初めは貴族との通婚も認められていなかったが、前445年のカヌレイウス法によって認められるようになった。さらに参政権を得てからは、平民会・護民官などを足場に共和政の中核となっていく。 → 中小農民の没落 |
| c 重装歩兵
(ローマ) | ギリシアの重装歩兵と同じく、兜・鎧・楯を装備し槍を武器とする歩兵。都市国家ローマの平民(農民や商工業者)で、それらの武器を自弁(自分で調達)することのできるものが市民としての権利を得た。前5世紀の中頃、ローマが他の都市国家と抗争したり、北方からのガリア人の侵入と戦ったりするなかで形成されてきたものと思われる。ローマ共和政は中小農民が重装歩兵となる「市民軍の原理」によって軍事力を強め、イタリア半島統一から地中海制圧に向かっていくが、戦争が長期化する中で中小農民が没落し、彼らが重装歩兵となって市民軍を編制することが出来なくなり、前2世紀末にはマリウスの兵制改革で市民軍から職業軍人制に転換することになる。 |
| d 執政官(コンスル )
| 古代ローマで、国制と軍事の最高権力を握る機関(命令権者)がコンスルで執政官または統領と訳す。民会の一つである兵員会で選出されるが、貴族に独占され、任期は1年で、必ず二人が選出され、互いに拒否権を持つなど、権力の個人への集中をさける工夫がされていた。伝承によると前509年に王に代わってローマにおける最高権力をもつものとしてコンスルがおかれた。「人気1年制」や「複数任命制」は権力の集中を防止する工夫として後に定められ、さらに護民官が設置されてコンスルを牽制した。前367年には二名の統領(これを大統領という場合もある)の他に1名(後に8名に増員)の法務官(小統領という場合もある)が置かれた。
執政官に選ばれるためには、その前に財務官と法務官を経験することが必要で、経験を積んだ有能な人物が選ばれるようになっていた。また、その政治は元老院の助言を受けて行われた。前367年のリキニウス=セクスティウス法で、コンスルの一人は平民から選ばれることになった。後の帝政期になると有名無実化した。
Epi. ファッショの起源 なお、この執政官のシンボルとされたのが「ファッショ」という、小枝を束ねたもので、権力は人民に由来し、それが執政官に委託されていることを示すものであった。20世紀のイタリアの独裁者ムッソリーニはそれを持ち出し権力のシンボルとしたところから、ファシズム(全体主義)という言葉が生まれる。 |
| e 元老院
| 古代ローマの共和政から帝政まで一貫して国家の最重要機関となったもので、ローマ市民(成年男子)が参加する民会に対し、貴族(パトリキ)のみから議員が選ばれる。初めはローマ共和政の中心となった執政官や独裁官の諮問機関であった。ローマの公共広場(フォルム)に建物があった。定員は当初300人で、議員は30歳以上、いったん選出されると終身議員であった。後には平民(プレブス)でも富裕なものは議員になるようになる。帝政時代になっても皇帝の諮問機関として重きをなす。
ラテン語でセナトゥス senatus といい、英語のsenate(上院)、senator(上院議員)はこれに由来し、現代のアメリカでも上院は senete という。また、共和政ローマ時代の記念碑に必ず刻印された「SPQR」は、Senatus
Populusque Romanus (元老院とローマ市民)の頭文字で、共和政の理念を示している。 |
| 民会 (ローマ) | 古代ローマの都市共和国時代の最高議決機関。リヴィウス(前1世紀末の歴史家)によれば王政時代に市民総会として設けられたのが、市民権を持つ成年男性のみが参加する「兵員会(ケントゥリア会議)」であった。「兵員会」は武装した市民の集会であり、外国人・奴隷・兵役と課税を負担できない極貧層は参加できなかった。市民は財産に応じた騎兵、重装歩兵、軽装歩兵などの兵役義務の違いにより、それぞれ「百人組」(ケントゥリア)を編成、騎兵は18、重装歩兵は80、それ以下は少数の百人組に、無産市民は1組に押し込まれた。全部で193の百人組があり、「兵員会」はこの百人組を投票単位とし、市民はまず百人組に直線参加して投票し、組ごとの票が決まり、193の組の中で多数決で決まる。騎兵と重装歩兵の組で合計98の過半数になり、この二つの階層の意向が通るので、下層市民には事実上参政権はなかった。兵員会は最高国政担当者である執政官(コンスル)以下の官職を選出し、和戦の決定などを行うが、国政の実権は「元老院」が握り、立法権も持っていた。元老院は貴族に独占されていた。
後に平民だけが構成員となる「平民会(トリブス会議)」が生まれるが、それは別な機関なので注意する。 → ギリシアの民会 |
| C 貴族と平民の身分闘争
| 前5世紀から3世紀初めにかけて、都市国家ローマで展開された、貴族(パトリキ)と平民(プレブス)の身分をめぐる闘争。貴族(パトリキ)と平民(プレブス)の身分的な違いははじめの頃は明確ではなかったが、紀元前5世紀初めまでにいわゆる「パトリキの封鎖」がおこなわれ、貴族と平民の結婚ができなくなり、貴族が政治と祭事を独占する体制ができあがった。それに対して平民は団結し、前494年の聖山事件をおこした。貴族も対外戦争を進める上で、平民に譲歩する必要があり、平民会の議長として護民官を設けることを認めた。それ以後、次第に平民の権利を認めるようにになり、前451年に最初の成文法である十二表法が制定され、前445年のカヌレイウス法によって両者の通婚も認められるようになった。前367年にはリキニウス=セクスティウス法の制定をへて、前287年のホルテンシウス法の制定で決着をみ、両者の関係は対等となる。この間は、同時に都市国家ローマが膨張し、イタリア半島を統一する過程(半島統一戦争)であった。 |
| 聖山事件 | 前494年、ローマの貴族と平民の身分闘争の発端となった事件。ローマの戦争にかり出されて土地を失い、債務に苦しむ平民が、借金の棒引き・土地の再分配・平民の代表の政治への参加を要求し、ローマの東北約5キロ離れた聖山にたてこもった。当時北方からの異民族の侵入に悩んでいたローマ元老院が折れて、平民の要求を呑み、借金は棒引き、債務奴隷は解放、さらに毎年平民から二人の護民官を選出することを認めた。これを聖山事件といい、身分闘争での平民の勝利の第一歩であったとされている。聖山闘争とも言う。 |
| a 平民会
| ローマの「民会」の一つとして、前5世紀前半に設置された。平民のみで構成され、護民官が議長を務めた。はじめはその決議は平民にしか及ばず、国法になるには元老院の承認が必要であったが、後に前367年のホルテンシウス法で、元老院の承認が泣くとも平民会の決議が国法とされることになる。これによってローマ市民(国民)の総会である平民会が市民全体を拘束する立法機関となった。平民会には定員はなく、その都度集まれる市民で決議できたので、ローマ領が広がり海外に出る市民が多くなると、ローマ市に住む市民が(貧民が多かったが)決定権を持つに至った。
ローマ市民の数:「ローマ市民」(つまり公民権をもつ者、の意味で奴隷や外国人は除く)の総数はどのぐらいであったか。そのうち何割がローマ市に在住していたのであろうか。前70年ごろのローマ公民の数は当時の国勢調査でよれば成年男子(17歳以上)だけで91万、海外で従軍中などを入れれば実際には115万ぐらいと想定されている。ローマ市全体の住民は全体で50万、奴隷・解放奴隷などがその4分の3ほどで、解放奴隷を除いた生粋のローマ公民は成年男子が4万、女子どもを含めて13万ほどだったという。<吉村忠典『古代ローマ帝国』1997
岩波新書 p.95 によるイギリスのブラントという学者の推定> |
| b 護民官
| 前494年の平民が起こした聖山事件の結果、設けられたという(伝承上)。護民官(トリブヌス)は平民会で選出され、その議長となり、元老院・執政官の決定に対して拒否権を持った。始め定員2名であったが、前449年に10名に増員、平民の権利の日常的な保護に当たった。その身体は神聖不可侵とされ、高い権威を持ち、ローマの実質的統治にあたった。著名な護民官としては、前4世紀のリキニウス・セクスティウス法を制定した二人、前2世紀のグラックス兄弟などがある。次第に形骸化し、帝政期には皇帝が兼任する名誉職的な名称に変質した。 |
| c 十二表法
| それまでローマの法律は神官に独占され、神官は貴族が独占していたため、平民は法律を知ることが出来なかった。聖山事件ののちも闘争を続けていた平民は、元老院に法律の公開を要求、元老院もその要求を容れて、議員3名をギリシアに派遣して立法者ソロンの業績を調査させ、帰国後十名からなる立法委員会が前451年に「十二表法」を編纂した。これが「ローマ法」の基本となるものである。<モンタネッリ『ローマの歴史』中公文庫p.64>
十二枚の板(材質は不明)に書かれたので十二表法という。内容は旧来の慣習法を明文化したものであるが、それまで神官(貴族階級から選ばれる)が独占していた訴訟日程や手続きの決定に市民が関与し、市民の手による裁判が行われるようになった。つまりこれによって、「神のお告げ」としての裁判ではなく、法によって裁く裁判が始まったと言え、貴族と平民の身分闘争の中での、平民の権利を守る市民法が成立し、法の前においては貴族と平民は対等となったたということができる。ただし、貴族と平民の通婚は禁止されていたので、後にその点がカヌレイウス法で是正される。市民法は主に民法の分野で発達し、さらに帝政時代にはローマ市民以外に適用される万民法に変質していく。 |
| カヌレイウス法 | ローマでは貴族と平民の通婚は禁止されていたが、貴族と平民の身分闘争が進行する中で、前445年、カヌレイウス法が制定され、貴族と平民の通婚が認められることとなった。これによって、平民の中の有力なものは、貴族と婚姻関係を結び、政界にも進出するようになった。
出題 2003年度早大社会科学部 |
| 戸口監察官(ケンソル)
| 古代ローマの貴族共和制時代の前443年に始まるとされる官職で、本来は市民の財産を調査する任務であったが、次第に権限が大きくなり、元老院議員の適格性の審査、風紀取り締まり、国家財政の監察なども任務とするようになった。定員は2名で、任期は18ヶ月。 |
| d リキニウス・セクステウス法 | 前367年、護民官であったリキニウスとセクスティウスの二人が元老院を通過させ制定された法律。三つの法からなる。(一般に1と2の二項が取り上げられる。)
(1)コンスルの一人を平民(プレブス)から出すこと。
(2)公有地の占有面積を一人最大500ユゲラ(約125ヘクタール)に制限した。
(3)負債の返却に関する法律。
これによって平民の地位は実質的に貴族と同じく成り、これによって平民の身分闘争は大きく前進した。また公有地の占有制限により、平民の没落防止がはかられた。(3)も平民の社会的地位の安定をめざしたもの。 |
| D 共和政の完成
| 前5世紀始めに平民会の設置、護民官の設置にはじまった、平民の政治的権力獲得の歩みは、中頃の十二表法制定で法の前での平等を実現させ、前4世紀中頃のリキニウス=セクスティウス法制定でコンスルの一人を平民から選出することが決まり、前3世紀前半のホルテンシウス法で平民会の決議が国法となることによって完成した。「ローマ共和政」は、都市国家ローマの市民によって運営されることになったが、そのローマがイタリア半島を統一し、さらに地中海世界にその支配を拡大していくに伴って共和政の形態は維持されたが、「ローマ帝政」へと移行していく。
ギリシアの民主政との相違点:ギリシアの民主政と比較すると、成年男子のみの市民権を持つ市民による民主制という点、奴隷制を基盤としている点は共通するが、相違も多い。まず、ローマの民会(兵員会)の構成員は平等ではなく、また平民会は存在し国家の最高機関となったが、門閥的な元老院は依然として力を持ち、独裁官などの権力手中が法的に認められていたことなど、民主政は不徹底であった。また市民権がローマ市民以外にも拡大されたことなどが特徴である。
基盤であった奴隷制も、ギリシアは家内奴隷が主であったが、ローマでは戦争捕虜の奴隷化が進み、大規模な奴隷制労働による大土地所有制が発達した。ギリシアは都市国家が統合されることはついになかったが、都市国家から出発したローマは最終的には世界帝国となり、民主政、共和政は形骸化して専制君主政に変質した。→ ギリシアのポリス民主政 |
| a ホルテンシウス法
| 前287年、独裁官であったホルテンシウスが制定。平民会の決議は元老院の承認が無くとも、ローマの国法とされることとなった。これによって前5世紀から続いた貴族と平民の身分闘争は一応終結し、平民が貴族と台頭の権利を獲得し、ローマ共和政は完成の時期を迎えたと言える。 |
| b 独裁官(ディクタトル)
| 前5世紀後半に始まる、ローマ共和政下で非常時に国家大権を与えられた機関。元老院が、2名の執政官の中から選び、任期は6ヶ月以内で、再任されないと決められていた。非常時とは、主に北方からのガリア人などの異民族の侵入の危機の場合であった。後にスラとカエサルも独裁官となるが、そのころはだいぶ性格が変わっており、カエサルは終身の独裁官となり、帝政の前段階となる。 |
| c 市民法 | ローマ市民権を持つ市民に適用される法律のこと。ローマで成文法が生まれたのは前451年の十二表法に始まり、市民生活に必要な民法の規定を中心に、共和制時代から帝政時代までのさまざまな政治に関する規定も制定された。当初は都市国家としてのローマ市民にのみ適用されていたが、その領土が拡大するにつれて、ローマ市民権は拡大され、紀元後212年のカラカラ帝の時のアントニヌス勅令で帝国領内のすべての自由民に拡大されたため、法律もすべての人間に適応するという意味で万民法といわれるようになった。これらの法律をローマ法と総称する。 |
 |
| イ.地中海征服とその影響 |
| A 半島統一戦争
| 都市国家として出発したローマは、前4世紀か日頃から前3世紀後半にかけて、イタリア半島全域に支配を及ぼし、その過程で平民による共和政を完成させた。半島統一戦争は、ラティウム都市制圧→サムニウム戦争→ギリシア人植民市制圧の三段階で展開された。
ローマはまず近隣のラティウム地方の同系のラテン人諸都市を前338年までに制圧した。次いでイタリア半島の中部(カンパニア)から東南部にかけて牧畜を主体に生活していたサムニウム人と第1次、第2次のサムニウム戦争を展開して、前3世紀の初めまでには制圧した。さらにイタリアの南端には古くからのギリシア人植民市がマグナ=グラエキアと言われて栄えていたが、ローマはその制圧にものりだし、その中心のタレントゥムが援軍を依頼したギリシアのエペイロス王ピュロスの軍を破り、前272年にタレントゥムを制圧し、イタリア半島の統一を完成させた。
ローマは征服したイタリア半島の諸都市と個別に条約を結んで、植民市、自治市、同盟市という区別をも受け、それらの都市が互いに同盟できないように、「分割統治」という方法で支配した。前3世紀中期からはローマの勢力は海外に向かうこととなり、まずカルタゴと衝突、ポエニ戦争となる。
半島統一戦争の背景:このローマのイタリア半島統一戦争が行われた前4世紀末から前3世紀前半は、平民層が重装歩兵としてこの統一戦争の主体として活動したため、その発言力が強まり、身分闘争を展開して貴族との対等な権利を獲得し、市民による共和政を実現した過程と一致していた。 |
| サムニウム戦争
| サムニウム人とはイタリア人の一派で、ラテン人より南の半島中部(カンパニア)から東南部のアペニン山脈で牧畜を主に生活して多人々で勇猛な戦士を擁していた。ローマは前4世紀後半からサムニウム人への攻勢を強めた。
第1次サムニウム戦争 前343~341年 サムニウム人の都市カプアが山地の同じサムニウム人から攻撃され、ローマに支援を要求。このサムニウム人の内紛に乗じてローマはカンパニアに進出。カプアはかえってローマの支配を恐れ、反旗をひるがえす。それにローマとラテン連盟を結んでいたラテン人都市も同調。ローマはラテン連盟を解消して、周辺の都市と全面戦争となるが、それに打ち勝つ。ローマは征服した都市にたいし「分割統治」で臨む。
第2次サムニウム戦争 前327~290年 ローマは残る南イタリアの併合を進める。ギリシア人の植民都市であったナポリを占領、さらに山岳部のサムニウム人に迫る。苦戦の末、前305年それを破り、ローマの勢力がアドリア海に達する。前290年までにサムニウム、エトルリア、ルカーニ、ウンブリなどの諸種族すべて降服。 |
| タレントゥム(ローマ時代) | タレントゥムはギリシア人がイタリア半島南部に建設した植民都市で、前272年にローマに服属した。建設したのはスパルタ人で(前8世紀)、南イタリアのギリシア人植民地域(マグナ・グラエキア)の中心であった。中部イタリアに起こったラテン人のローマの勢力が南下し、タレントゥムは本国ギリシアのエペイロス王国ピュロス王の援軍を求めたが、結局ローマ軍に敗れ、前272年にはローマに服属した(ピュロス戦争)。これによって、ローマのイタリア半島統一戦争が終わった。第2回ポエニ戦争では一時、カルタゴ側についたが、再びローマに制圧された。その後は、ローマの地中海進出の重要な港として栄えたが、9世紀以降はたびたびイスラーム教との侵攻を受けた。現在のタラント市。 |
| ピュロス
| ピュロスは、アレクサンドロス帝国が解体した後のギリシアで、マケドニアの西のアドリア海一帯を支配したエペイロス王国(エピロスとも表記)の王。野心家でギリシアの統一、さらにイタリア遠征を考えていた。
ピュロス戦争 前280~275年 イタリア半島南端のギリシア人植民都市タレントゥム(タラント)が本国のエペイロス王ピュロスに援軍を依頼、ピュロスはイタリア半島に進出し、何度かローマ軍を破ったが、決定的な勝利を得ることが出来ず、結局撤退した。結局前272年にはタレントゥムがローマに降伏、前270年までに、南イタリアのギリシア系植民市(マグナ・グラエキア)はすべてローマに服属し、ローマの半島統一は終わった。ついでローマの勢力はシチリア島に伸び、カルタゴと対立することとなる。
Epi. ピュロスの勝利 ピュロス戦争の時、タレントゥムはギリシアのマケドニアにあったエペイロス王国の王ピュロスに援軍を要請した。ピュロスは象部隊を含む大軍を派遣してローマ軍を破ったが、テレントゥム救出にはならなかった。このことから、「大きな犠牲を払っても引き合わない勝利」のことを”ピュロスの勝利”という。 |
| b アッビア街道
| 監察官(ケンソル)のアッピアウス=クラウディウスが前312年(第2次サムニウム戦争の時期)に建設したといわれる。後にプリンディシとタレントゥムまで延長され、ローマの南イタリア支配の幹線道路とされた。幅8メートルの舗装道路で、馬の引く戦車を走らせるための軍用道路である。アッピア街道は一部が現存し使用されており、このような道路がローマ支配地域にはりめぐらされ、「すべての道はローマに通ず」といわれた。
Epi. 盲目の監察官アッピアウス 監察官とは、前443年に設置された重要官職の一つで、戸口調査(5年ごとに行われた国勢調査)にもとづいて市民の納税額と兵役期間を定める任務。また公職者の不正やプライバシーの監視もその権限にふくまれていたので大きな権威があった。アッピアウス=クラウディウスは「盲目の監察官」として知られ、前312年にはローマに上水道を建設、さらに同年、ローマからカプアまでラティウム地方の沼沢地帯を一直線に切り開いて街道を開いた。「アッピア街道」はその名に由来する。 |
| c 「分割統治」
| ローマが半島統一戦争で服属させたイタリア半島内の都市に対し一律に支配するのではなく、与えられた自治権、市民権の程度によって、植民市・自治市・同盟市の三種類の形態に分けて支配した。それは共通の利害をもたせないための工夫であり、「分割して統治せよ」というい考えに基づいていた。服属都市はそれぞれローマとの個別の条約のみ締結して政治関係を持ち、都市間相互間の関係は一切許されなかった。 |
| 植民市 | ローマ人が入植して建設した都市で、ローマと同等の市民権が与えられた都市、または征服された都市でもそれと同等の権利をあえられた都市。コロニアという。例えば、現在のドイツの都市ケルンは、ローマの植民市(コロニア)アグリッピネンシスがその起源で、コロニアであったところから、後にケルンという地名となった。 |
| 自治市 | ローマに征服された都市で、上層市民には市民権が与えられ、一定の自治は認められた都市。自治は認められたが、軍事面や裁判ではローマに権限を握られていた。また認められた市民権は、婚姻、財産などの民法上にとどまり、ローマ市の役人への立候補や選挙という参政権は認められなかった。 |
| 同盟市 | ローマに征服された都市で、完全にローマに従属し、市民権も自治権も認められなかった都市。共和政末期の前91~87年に起こった同盟市戦争は、同盟市がローマ市民権を要求して反乱を起こしたもの。この反乱はスラによって鎮圧され、それらの都市の市民権は与えられたが、逆にローマの一部とされ、ローマがイタリア半島(ポー川以南)を一律に支配することとなった。 |
| d ローマ市民権
| はじめは都市国家としてのローマに居住し、義務を果たすもののみが市民とされ、ローマの発展は彼等ローマ市民が支えていた。ギリシアのアテネ市民権は市民権法の定めにより、アテネ居住者以外に拡大されることはなかったが、ローマはその支配圏を拡大さえるにとない、市民権も拡大した。まずイタリア半島統一戦争の過程で服属した都市の上層市民にはローマ市民権を与え懐柔する必要が出てきた。ローマはギリシアと異なり市民権拡大には寛容で、上層市民には市民権を与えた。ローマ居住以外のローマ市民も形の上ではローマの35の区(トリブス)に属するものとされた。しかし直接民主政の原則であるから、ローマまで行かなければ意見を反映させる機会はなかった。また支配下に入れた都市でも同盟市の市民には市民権を与えなかった。紀元前1世紀にローマの領土が全地中海に及ぶと、その統治は都市国家の形態をとることができなくなり、服属した都市の住民も市民権を要求するようになった。 → ローマ市民圏の拡大 |
| B ポエニ戦争
| 紀元前3世紀中頃から前2世紀の前半まで、3回にわたって起こったローマとカルタゴの西地中海の覇権を巡る戦争。敗れたカルタゴは滅亡し、勝利したローマが地中海支配を確立させ、世界帝国に成長する端緒となった。
カルタゴは現在のチュニジアにあったフェニキア人の植民市が発展した商業国家。ローマがカルタゴ人のことをポエニと呼んでいた。この戦争は、前3世紀中頃までにイタリア半島の統一戦争を終えたローマが、カルタゴから西地中海の海上支配権を奪うことを目的とした征服戦争で、直接的にはシチリア島でカルタゴと対立していたシラクサがローマの援軍を要請したことから起こった。
経過:前264年からの第1回ポエニ戦争ではシチリアが主な戦場となり、ローマが勝利し、シチリアを占領し最初の属州とした。さらにサルデーニャ、コルシカを奪われたカルタゴは対抗してイベリア半島に進出。前218年からの第2回ポエニ戦争はカルタゴのハンニバルがイタリア半島のローマ本土に侵入し脅かし、カンネーの戦いでは大勝した。しかしローマは将軍スキピオの指揮によって逆襲し、カルタゴの近郊ザマの戦いでハンニバル軍を破り、カルタゴは再び敗北した。その後、カルタゴの殲滅を狙ったローマは、マケドニア戦争でギリシアを制圧した後、前149年からの第3次ポエニ戦争で、前146年にカルタゴを滅ぼし、ポエニ戦争は終結した。
意義と影響:この勝利によってローマは西地中海の覇権を獲得し、海外領土を所有する大国となったが、戦争の長期化、海外領土(属州)からの奴隷と安価な穀物の流入は市民階級を没落させ、都市国家としての共和政の維持は困難となり、帝政に移行する契機となった。<参照 長谷川博隆『ハンニバル』1975
講談社学術文庫、松谷健二『カルタゴ興亡史』1991 中公文庫 など>
Epi. 2131年ぶりの和平条約 「1985年、チュニジアは「建国2800年展」を開催し、その前年にイタリアとのあいだにカルタゴ遺跡保存に関する協力協定を結んだが、それを機会に同年2月5日、ローマ史とカルタゴ市は2131年ぶりで平和条約を締結した。チュニス郊外、かつてのカルタゴの迎賓館跡で両市長が議定書に調印したという。」<松谷健二『カルタゴ興亡史』1991
中公文庫 p.249> |
| a カルタゴ
| フェニキア人の都市の一つティルスが、アフリカ北岸の現在のチュニスの地に建設した植民市。東地中海の海上貿易で活躍し、商業帝国を建設、ローマの拡張期に対立し、前3世紀中頃から100年以上のポエニ戦争を戦った後に敗れ、消滅した。
成立と繁栄:伝承によれば、前814年、フェニキア人の都市国家ティルスの王の妹エリッサが建設したとされているが、確証はない。「新しい都市」を意味する「カルト・アダシュト」をローマ風に読むと「カルタゴ」となる。フェニキア人は本国がペルシア帝国の支配下にはいるとその保護を受けて地中海交易で活動を広げた。しかし、同じように地中海に進出してきたギリシア人との間で交易圏をめぐって争うようになった。ペルシア戦争でペルシアとギリシアが戦うと、カルタゴはペルシア帝国側につき、前480年のサラミスの海戦と同じ時に、シチリアのギリシア植民市シラクサを攻撃したが敗れている(ヒメラの戦い)。ペルシア戦争後はアテネ海軍が強大となり、カルタゴは西地中海を勢力圏とすることとなった。前4世紀にシドン、ティルスがアレクサンドロスに征服された時、多数のフェニキア人が移住し、それ以後地中海の中央に位置することから交易の拠点となり、商業国家として繁栄していった。すでに紙幣を発行し、その紙幣は西地中海の国際通貨となっていた。このころ、カルタゴの商船はジブラルタルを超えてブリテン島まで進出し、錫(スズ)などを得ている。カルタゴはシチリア島、サルデーニャ島、コルシカ島などを勢力下におさめ、ギリシア人植民都市であるマッサリア(現マルセイユ)などと対立するようになった。またイベリア半島にはカルタヘナ(新しいカルタゴを意味するカルタゴ=ノヴァが語源)、アルメリア、バレンシア、バルセロナなどを築いた。シチリア島では西半分を支配し、東側のギリシア人植民市シラクサとの対立が激しくなった。そのシラクサがローマの援軍を要請したので、ローマはシチリア進出の好機と捉えてカルタゴと直接対決することとなった。
ポエニ戦争:そのために起こったポエニ戦争は、第1次でローマに敗れてシチリア島を失い、さらに第2次では将軍ハンニバルが活躍してイタリア半島まで攻め込んだが、スキピオの率いるローマ軍に反撃されて敗れ、海外領土を失った。さらに第3次でカルタゴはことごとく破壊され、前146年に滅亡した。市民はすべてがローマ軍によって殺されるか奴隷にされるかいずれかであったという。カルタゴの地はローマの属州「アフリカ」とされた。カルタゴの旧都は一時カエサルが復興したが、紀元後5世紀にはゲルマン人のヴァンダル族がこの地に国を建て、さらにイスラームによって破壊される。現在チュニジアの首都チュニスの郊外でカルタゴの遺跡が確認されている。
カルタゴの敗因:ポエニ戦争でのカルタゴはハンニバルに代表されるようにローマとよく戦い、その地中海支配に抵抗した。しかし最終的に敗れ、ローマの大国化を許した。カルタゴの敗因は古来、さまざまな説が行われているが、一般に定着していることは、カルタゴはもともと交易に依存する海洋帝国はで領土拡大の意欲がなかったこと。そのため海軍には市民が参加し強大だったが、陸軍は市民は参加せず、リビア人などの傭兵に依存し、また指揮に当たる軍人もローマのように文民が元老院から派遣されるのではなく、職業軍人であったので私利私欲に動くことが多かったこと。またハンニバルは優れた戦術家であったが、イタリア半島に攻め込みながら半島内に反ローマ勢力を形成してそれらと結んでローマを包囲するという戦略がなかったこと(あっても失敗したこと)、などが挙げられている。 |
| 第1次ポエニ戦争 | 前264~241 カルタゴ側の勢力下にあったシチリア島西部をローマが攻撃。海軍力でローマが勝利した。その結果、シチリア島を最初の属州として獲得した(属州シチリア)。
その後、カルタゴはイベリア半島に進出、ローマの支援を受けるギリシア系都市マッサリアの勢力と衝突。前226年ローマのと間でエブロ条約を結び、エブロ川をマッサリアとの勢力圏として合意した。 |
| シチリア(属州) | シチリア島は、第1次ポエニ戦争の結果としてローマ最初の属州となった島。その後もローマの重要な属州として穀物供給地とされた。はじめ島の東部に建設されたシラクサなどのギリシャ人植民市を中心に大きな勢力を持っていたが島の西部にカルタゴが進出してその支配を受けるようになり、ローマとカルタゴの対立からポエニ戦争が勃発した。ローマの勝利の結果、西部はローマの支配下に入った。前227年からはローマは総督を置いて統治し、ローマの海外に持った最初の属州となった。ただシチリア東部はローマの盟友シラクサの統治が認められていた。前218年に起こった第2次ポエニ戦争ではシラクサはローマから離反して、カルタゴとともにローマに敗れ、全島がローマ市支配下に入った。その後シラクサはローマの属州として総督の統治を受け、奴隷反乱の舞台となったがそれも鎮圧され、特にローマ市民の食糧としての穀物を供給しつづけた。ローマ元老院の議員カトー(大カトー)はシチリアを「ローマの穀倉、ローマ平民の乳母」と呼んでいる。
Epi. シチリアの悪総督 前1世紀前半、属州シチリアの総督として悪名が高かったのがウェレスである。前70年にウェレス弾劾裁判が行われ、有名なキケロがその検察官として長文の弾劾演説を残している。それによるとウェレスは総督という地位をフルに利用して、徴税請負人からリベートを巻き上げ、抵抗する者を投獄し、美術品をあさり、夜な夜な美女を侍らせて宴会をしていたという。元老院によって解任された後、キケロの告発によって有罪が決定的になったウェレスはひそかにマルセイユに亡命した。<くわしくは、吉村忠典『古代ローマ帝国』1998 岩波新書を見よ> |
| b 属州
| 第1回ポエニ戦争で獲得したシチリアが最初の属州。ついでコルシカ島とサルデニア島を合わせて第2の属州とした。属州はプロヴィンキアという。現在の南フランスをプロヴァンスというのは、ここがかつてローマの属州だったからである。 → 属州の拡大
属州には総督(知事ともいう)がおかれ、元老院から有力者が任命されてその統治に当たり、「十分の一税」という租税を徴収した。その下で実際に徴税にあたった徴税請負人は総督に請け負った税額よりも多くの税を徴収し、その差額を着服するという方法で私腹を肥やし、大きな富を獲得するようになり、ローマの有力者の利権の対象となっていった。
また属州からは奴隷と大量の安価な穀物がローマ本土にもたらされた。ローマの奴隷制と共和政を支えることとなった。それだけに属州統治はローマにとって重要な課題となり、またその拡大がローマの社会と政治のあり方を大きく変えることになる。 |
| カルタヘナ | イベリア半島(現在のスペイン)の地中海に面した都市で、古代カルタゴが建設した植民市、カルタゴ=ノヴァ(新しいカルタゴの意味)が起源。カルタゴのハンニバルはこの地を拠点にイベリア半島の経営にあたり、第2次ポエニ戦争ではこの地からイタリア遠征に出発した。 |
| 第2次ポエニ戦争 | 前218~201年。ハンニバル戦争とも言う。カルタゴ領のカルタへナを拠点としていたハンニバルは、イベリア半島の支配を拡大し、ローマと再び衝突することとなった。ハンニバルは果敢にアルプスを越えてローマ本国を突き、前216年にはカンネーの戦いでローマ軍を破る。しかし、ローマ側も前212年、親カルタゴに転じたシラクサを攻撃して陥落させ(この時アルキメデスが戦死した)、さらにハンニバルの本拠のイベリアを脅かし、また将軍スキピオ(大スキピオ)が北アフリカに上陸したため、ハンニバルはローマを直接攻撃することが出来ずに本国に戻る。前202年、両軍はカルタゴの郊外で衝突、ザマの戦いでローマ軍の勝利となった。ローマではハンニバル戦争ともいわれて大きな危機であったが、カルタゴ軍は陸軍は市民兵ではなく傭兵を中心としていたこと、海軍は市民が参加したが、第1次ポエニ戦争で制海権を失ったことなどが大きな敗因となり敗れた。
Epi. 日和見将軍ファビウス カンネーの決戦前までローマ軍を指揮していたのは将軍ファビウスであったが、彼はハンニバル軍と直接対決する愚を避け、持久戦で敵の崩壊を待つことを主張、元老院の主戦派に「日和見」と批判され、将軍を解任された。民衆も彼を弱将とあざけった。しかしカンネーの敗戦はファビウスの見通しが正しかったことを示した。なお、1884年にイギリスのウェッブ夫妻などが設立した漸進的社会主義運動をめざしたフェビアン協会の名は、このファビウスに由来する。 |
| カンネーの戦い
| 前216年、第2回ポエニ戦争の時のハンニバルの指揮するカルタゴ軍とローマ軍がイタリア半島東南部のカンネー(カンナエ)で決戦し、ハンニバル軍が大勝した古代史上最大の戦い。
カルタゴ軍の主力は1万の騎兵と2万のケルト人、その他スペイン人の重装歩兵5千、リビア人やフェニキア人の重装歩兵7千。対するローマ軍は8万の大軍で圧倒的に有利だった。カンネー(カンナエ)はローマから4百キロ近く離れた南イタリア東海岸の原野。カルタゴの将軍ハンニバルはテーベのエパミノンダスやアレクサンドロス大王のアルベラの戦いの斜線陣を採用、ローマ軍主力を盆地に誘い込み、両側から騎兵で挟撃する方法でローマ軍を包囲することに成功、大勝した。ローマ軍の死者は5万、それに対してハンニバル軍の戦死者は5千人。一度に5万以上の死者を出した戦闘は、第1次世界大戦まで無かったという。<長谷川博隆『ハンニバル』1973 講談社学術文庫版 p.104-109 などによる>
Epi. 殲滅戦の典型、カンネーの戦い カンネーの戦いでのハンニバルの勝利は、野戦での完璧な包囲戦に成功したことであった。この勝利は幾世紀も殲滅戦の典型としてナポレオンやクラウゼヴィッツ(19世紀プロイセンの軍人、『戦争論』で近代的戦争論を展開した)などの戦術家の手本とされた。またドイツのシュリーフェンは第1次世界大戦前にカンネーの戦いの研究に没頭し、対フランス包囲戦を構想したという。 |
| c ハンニバル
| 古代カルタゴの将軍。第2回ポエニ戦争で戦象を率いてアルプスを越えてイタリア半島を転戦し、カンネーの戦いでローマ軍を破って脅威を与えた後、カルタゴ近郊のザマの戦いでローマのスキピオに敗れた。
父のハミルカルもカルタゴの将軍で、第1回ポエニ戦争でローマ軍と戦い、その後カルタゴで傭兵の反乱を鎮圧して名を挙げた。その子ハンニバルは父の築いたカルタゴの植民地のスペインで育ち、父の死後、26歳でカルタゴ軍を率いる将軍となった。前218年第2回ポエニ戦争が起きるとスペインのカルタゴ=ノヴァ(カルタヘナ)を出発し、ロー戦象30、歩兵5万、騎兵9千を連れてピレネー山脈を越え、さらに冬のアルプスを超えてローマ領内に攻め込んだ(アルプス越えのルートには諸説あって明らかではないが、ローマの歴史家ポリビオスによれば15日かかかったという)。その後イタリア半島を転戦、ローマの将軍ファビウスの持久戦法に悩まされたが、ヴァビウスが元老院で罷免された後の前216年、ローマ軍が決戦を挑んでくると、カンネーの戦いで巧みな戦法を駆使して大勝した。ハンニバルはローマの同盟市が反乱を起こすことを期待したが、その動きはなく、また長期の遠征でカルタゴ軍も疲弊し、ローマ軍スキピオが本国を攻撃した知らせに急遽カルタゴに戻り、前202年のザマの戦いで敗れた。ハンニバルはその後もカルタゴの将軍の地位にとどまったが、親ローマ派が台頭したため脱走し、小アジアのアンティオキアに亡命。なおも各地で反ローマ連合を働きかけたがはたさず、ローマの追跡を受け、前183年自殺した。
Epi. ハンニバルの戦象部隊 ハンニバルは象部隊を率いてアルプスを越えたことで有名であるが、その戦象については次のような説明がある。「ハンニバル軍の戦象の主体としてのアフリカ象は、森の小型の象であり、灌木地帯のアフリカ象ではない。肩までの高さは、2.4m(インド象は3m。灌木地帯のアフリカ象は3.3m)。ただし前218年から217年にかけて生き残った象シュルスは、カトーによれば、第2次ポエニ戦争中、最も勇敢に戦ったインドの戦象だったという。ところで、この小型のアフリカ象は-よく画に見られるように-上に象カゴをつけるには小さすぎ、一人の象使いがこれに乗って投げ槍を使ったものであろう。」<長谷川博隆『ハンニバル』1973
講談社学術文庫 p.60> |
| ザマの戦い
| 第2回ポエニ戦争でカルタゴのハンニバル軍をローマ軍が破った戦い。前202年、ローマの将軍スキピオはカルタゴの虚を突き、その本国に上陸。急を聞いたハンニバルが本国に戻り、カルタゴ近郊のザマで相対した。ここではスキピオがカルタゴ軍を挟撃することに成功し、ハンニバルは敗戦を認めて、カルタゴは降服した。カルタゴは海外領土すべてを失い、賠償金などの支払いを約束、ハンニバルはしばらく将軍にとどまったが、結局カルタゴを離れる。 |
| スキピオ
| 共和政ローマ時代の軍人で閥族派の政治家。第2回ポエニ戦争のザマの戦いでハンニバル率いるカルタゴ軍を破り名声を高め、大スキピオ、大アフリカヌス、ともいわれる。始め父に従ってイベリア半島でカルタゴ軍と戦う。父の戦死後、カルタゴ側の拠点カルタゴ=ノヴァ(カルタヘナ)攻略に成功、前206年までにイベリア半島を平定した。その成功で自信を深め、ハンニバル軍がイタリア半島南部に居座っている間に、カルタゴを直接攻撃する案を立て、消極的な元老院を尻目に民衆の支持を受けて遠征軍を率いてカルタゴに上陸した。ハンニバル軍が急遽アフリカに渡り、カルタゴに迫るとその近郊ザマで迎え撃ち、前202年のザマの戦いとなった。戦いに勝利したスキピオはローマの英雄となり、次いで小アジアに遠征し、シリア軍を破った。スキピオの名声が高まるとその独裁化を恐れたカトー(大カトー)はスキピオを横領などの罪で元老院で告発。スキピオは政敵カトーとの争いに敗れ失意の内に引退し、前184年に没した。その孫が小スキピオで、第3回ポエニ戦争でカルタゴを破壊した人物。 |
| 第3次ポエニ戦争 | 前149~前146年 ローマによるカルタゴ壊滅戦。大スキピオの孫の小スキピオが活躍。4年にわたる抵抗の後、ローマはカルタゴを徹底的に破壊した。生き残った5万人のカルタゴ人は奴隷として売られたという。カルタゴの都城は跡形もなくなり、現在チュニスの郊外に遺跡をとどめているだけである。この地は属州アフリカとして、ローマの支配を受けることとなる。後に政体循環史観で知られる『歴史』を書いたギリシア人歴史家ポリビオスも小スキピオに従って従軍した。 |
| C 地中海世界の制圧
| ローマは前264年から始まるポエニ戦争で、前146年にカルタゴを滅亡させてまず西地中海を制圧し、次いで前215年からのマケドニア戦争で、前168年にマケドニアを滅ぼし、さらにギリシアを制圧して東地中海に及んだ。こうして前2世紀の中頃にはローマは地中海ほぼ全域を支配することとなった。それが完成するのが、前31年のアクティウムの海戦でオクタヴィアヌスがプトレマイオス朝エジプト海軍を撃破したときである。これによって地中海は完全にローマの「内海」となり、ローマ人は地中海を「われらの海」と言うようになった。
しかしこの間、地中海には反ローマの海賊勢力が存在しスパルタクスの反乱などとも呼応していた。それらの海賊もポンペイウスによって平定され、抵抗が終わった。 |
| a マケドニア戦争 | ローマは前215年~205の第1回、前200~196の第2回、前171~167の第3回の前後3回にわたる「マケドニア戦争」で、アンティゴノス朝のマケドニアを滅ぼした。ローマはさらに南のギリシアに侵入、コリントなどのポリスを破壊し、マケドニアとギリシアを合わせて属州とした。
前168年、ピドナの戦いでマケドニアが敗れた時、千人のギリシア人知識人が人質としてローマに連れてこられ、ギリシア文化がローマにもたらされることになった。後に『歴史』を著すギリシア人ポリビオスもその一人である。 |
| b 属州の拡大
| ローマの海外領土である属州は、前3世紀の第1次ポエニ戦争の時に獲得したシチリアが最初で、その後、サルデーニャ・コルシカを加え、前2世紀に入りヒスパニア(スペイン)、マケドニア、アフリカ、アジア、ガリア、前1世紀にシリア、キリキア、イリリクム、パンノニア周辺、トラキア、エジプト、ブリタニア(大ブリテン島)と拡大した。
拡大された属州からは、奴隷と穀物が大量にローマ国内にもたらされた。いずれも戦勝によって獲得した海外領土であり、大量の捕虜は奴隷としてローマ本国に送られ、また属州からは穀物が租税として招集され、ローマ本国の市民の食糧とされていた。しかし、紀元後2世紀までには属州の拡大は終わりを告げ、奴隷の供給が無くなったため、奴隷に依存したローマ社会も大きく変動することとなる。 |
| c 徴税請負人
| 古代ローマにおいて、属州の徴税や公共事業を国にかわって請け負う人。旧来の貴族ではなく、新興貴族にあたる騎士(エクイテス)といわれる有力者が任命され、プブリカヌスといわれた。徴税請負人になると、実際の額より多くの税額を徴収して、差額を着服することができ、私腹を肥やし、富豪に成長するものが多かった。また属州民にとっては大きな負担となった。
徴税請負人の具体例:属州シチリアの総督ウェレスのもとで、徴税請負人アプロニウスがどのような利益を得たか、次のような礼がある。前71年に総督ウェレスからレンティーニというポリスの小麦の「十分の1税」を21万6000モティエ(量の単位。1モディエは8.754リットル)で請け負い、レンティーニ人とは54万モディエを支払わせる契約を結んだ。この差額の32万4000モディエが「儲け分」である。その他、54万モディエの6%、すなわち3万2400モディエをそれに付加させ、さらにリベートとして3万モディエの小麦に相当する金額を受け取った。つまり38万6400モディエを手にしたわけである。ローマ人が1年に必要とする小麦の量がせいぜい40モディエであったから、この利益は莫大だった。現地の生産者がそれに従っていたのは、アプロニウスが「お前たちは脱税しようというのか」という恫喝があったからだ。<吉村忠典『古代ローマ帝国』1997
岩波新書 p.103> |
| d 騎士
(エクイテス) | 共和政ローマで前3世紀末ごろからあらわれた富裕市民層を貴族と区別して騎士(エクイテス)といった。
もとは豊かな市民で騎兵として戦争に参加できる人々を騎士(エクイテス)と言っていたが、第2回ポエニ戦争頃から属州の徴税請負人などになって富裕となった市民が特に騎士といわれるようになった。元老院に基盤を持つ貴族と異なり、いわば新興貴族に属し、徴税請負人など様々な請負事業で富を蓄え、貴族身分には禁じられていた高利貸しや海外取引などでさらに力を付け、政治的には改革派である平民派を支援した。 |
| D ローマ社会の変質 | |
| a 戦争の長期化
| ポエニ戦争は前3世紀中頃から、前2世紀始めまで断続的に続き、ローマ市民は重装歩兵として長期間従軍した。また特に第2回ポエニ戦争ではハンニバル軍との戦闘がイタリア半島で行われ、国土が荒廃した。 |
| c 中小農民の没落
| 中小農民とは、言い換えれば「平民」の大部分であり、ローマの共和政を支えた市民でもあった。また重装歩兵としてローマのイタリア半島統一戦争を支えてきた階層であった。前3世紀終わりごろから続いたポエニ戦争は前2世紀の中頃まで続き、さらにマケドニア戦争など海外領土を獲得する戦争が長期化する中で、彼ら中小農民は耕地を離れ戦場に居続けたため、耕地は荒廃した。ローマが獲得した海外領土(属州)からは奴隷と穀物が大量に流れ込むようになった。奴隷の流入は有力者の大土地所有(ラティフンディア)経営を拡大させ、中小農民の農園はそれらに併合されていった。また、属州からの安価な穀物の流入は、農作物の価格を下げ、中小農民の利益を少なくすることとなった。それらの理由によって中小農民の自営農場は経営が困難となり、彼らの多くは土地を手放して都市に流れ込み、無産市民(プロレタリア)となっていった。このような中産農民の没落は、市民が重装歩兵となって国防にあたるという都市国家の原則が維持できなくなり、ローマの国防は有力者の私兵か、傭兵にゆだねられるようになる。そしてなによりも中小農民の没落は平等で自由な市民に支えられた共和政を動揺させることになる。前2世紀のグラックス兄弟の改革は、中小農民の没落を防止することを目指したが、保守派・元老院の反対で実施されず、その流れはさらに続くこととなった。 |
| 遊民 | 遊民とは都市で生活しながら生産手段、財産を持たず、公共の保護を受けるか、有力者の庇護を受けているひとびと。
→ 無産市民(プロレタリア) |
| d 大土地所有(ラティフンディア)
| ローマの大土地所有はラティフンディウム(複数形がラティフンディア)という。ポエニ戦争を契機として中小農民が没落し、農地が富裕な貴族や騎士階級に集中した。属州の拡大に伴い、ローマに住む有力者が属州で大土地を経営することも多くなった。ラティフンディウムでは奴隷を労働力とし、ブドウ・オリーブなどの果樹栽培が行われていた。 |
| e 奴隷(ローマ) | 古代ローマもギリシアと同じく奴隷制社会であったが、ギリシアが家内奴隷が主であったのに対して、ローマは奴隷制による大土地所有制が発達した。また奴隷の数も膨大で、その供給源は対外戦争による捕虜であった。奴隷は人権は認められず商品として売買され、奴隷主に服従した。奴隷の中にもその身分から解放されて解放奴隷となるものもあったが、市民権を持つのは困難であった。また奴隷の中には、武術に優れた者を剣闘士奴隷(剣奴)とする特別な場合もあった。彼ら奴隷は厳しい搾取のもとにあったので、前2世紀ごろからしばしば奴隷反乱を起こした。シチリアの奴隷反乱に続いて起こった前1世紀の剣奴スパルタクスの反乱がその最大のものであった。
ローマ奴隷制は帝政時代も継続するが、ローマ領が最大となり対外戦争が行われなくなると次第にその供給が減少し、またあい次ぐ奴隷反乱によって、奴隷の待遇も少しずつ向上し、コロヌス制に移行していく。 → ギリシアの奴隷制度
奴隷の売買:「奴隷は急流のように流れ込んだ。前177年、一挙に四万のサルデーニャ人が奴隷としてローマに連れてこられ、その十年後、エペイロス人五万が同じ運命に陥る。ローマ軍団は今やギリシアを超え、あるいはアジア、あるいはドナウ河流域、はてはロシアとの境界にまで進入しつつあったが、奴隷商人はその軍旗のあとをついて歩いた。いくらでも奴隷を確保できたから、デロス島の国際奴隷市場で一万人の奴隷が一度に売買されるくらいは日常茶飯事となり、値段も一人当たり五〇〇円程度まで下がった。」<モンタネッリ『ローマの歴史』中公文庫P.161> |
| 無産市民(プロレタリア)
| 土地などの財産を持たない貧困層。古代ローマでは都市国家から地中海全域に領域を拡大する戦争が続き、その結果ら大土地所有制と奴隷制が広がって貧富の格差が拡大し、市民層の中に土地を無くして没落する人々が現れれてきた。図式化すれば、前2世紀前半から均質な市民階級が富裕な新貴族(騎士)と無産市民への階層分化した、とまとめることが出来る。ローマではそのような無産市民をプロレタリアと言った。もともと、民会の中で、騎士や重装歩兵などの武装を出来ない最下層の市民を、子ども(プローレス)しか持たない人々、という意味でプロレタリーと言っていたことによる。つまり「子どもしか財産のない人」という意味であった(子どもさえいない人は何と言われたのか?それはわからない)。彼らは無産者であっても「市民」であったので、投票権などの諸権利は認められていたので、政府も彼らの「パンを見せ物」という要求には答えざるを得なかった。しかしローマが共和政から帝政に移行していくと、彼らの一部は有力者の私兵となったり、大農園の小作人などになっていった。
この言葉は近代になってはなばなしく復活する。つまり資本主義社会になって生み出された、囲い込みなどによって土地を無くし、労働力を売るしか無くなった賃金労働者をプロレタリアートと言うようになったのである。資本家階級を「ブルジョア」、労働者階級を「プロレタリアート」と言い、階級闘争が説明する用語とされ、中国ではプロレタリア文化大革命で使われた。 → ギリシアの無産市民 |
| f 「パンと見せ物」
| 中産市民が没落して無産市民(プロレタリア)となっても、市民であるので平民会の選挙権はもっていた。彼らは国や有力者に「パンと見世物」の提供を求め、それらを提供してくれる政権や人物を支持した。パンとは穀物つまり小麦のことで、穀物の特別価格での販売とか、無料配布が国や有力者の手で行われていた。見世物はサーカスともいわれるが現在のサーカスのことではなく、競技場での戦車競争とか、円形闘技場での剣闘士試合、ライオンと剣奴の試合などのことで、これらも国や有力者が主催して無料で市民に提供されていた。経済的、社会的な不満を持つ貧民層は、そのはけ口として「パンと見世物」をローマ当局に要求したのであろう。 |
| E 共和政の動揺 | 中小農民の没落によってもたらされた市民層の中の貧富の格差拡大は、共和政を大きく動揺させることになった。一つは執政官や独裁官、護民官などの執行機関とその基盤である議決機関の平民会と諮問機関の元老院というローマ共和政のシステムがくずれ、政治の実権は一部の有力者にゆだねられ、彼らが閥族派・平民派に別れて争うようになったこと。一つは大土地所有の進行は奴隷制に依存していたので、その拡大は奴隷に対する収奪を激しくすることとなり、それに反発した奴隷反乱が起き始めたことであった。前2世紀後半には共和政の動揺は覆い隠すことが出来なくなり、前1世紀の「内乱の1世紀」という混乱期を経て、共和政はくずれ帝政ローマに移行することとなる。 |
| a 閥族派
| オプティマテスという。古くからの名門の出で元老院の議員を世襲してきたような閥族を中心とした保守派。元老院を中心とした寡頭政治体制の維持をはかった。スラ、ポンペイウスらがその代表的人物であるが、それを支えるのは没落してその私兵となったような人々であり、彼らの社会的不満は平民派と違いはなく、両派は階層的な対立よりは、同じ支配層の中の私的な権力争いのグループという面が強い。その主張は従来の元老院の権益を保持しようとしたので、保守派ということが出来る。 |
| b 平民派
| ポプラテス(民衆派)という。平民会を基盤に力を持ち、元老院とは対立する政治的立場の有力者たち、血統にとらわれず実力で地位を獲得した騎士(エクイテス)といわれる新貴族に多い。その代表はマリウスで、カエサルもこれに入る。平民派というが彼らは平民だったわけではなく、その支持基盤が没落して彼らの私兵となった貧困層であり閥族派との違いはない。その主張は元老院の既得権に反対することが多かったので、改革派と見られた。 |
| シチリア島の奴隷反乱 | 共和政ローマ時代の末期、前2世紀の終わりに属州シチリアで起こった奴隷反乱。前135~前132年のものと、前104~100年までとの2回起こっている。反乱はいずれも鎮圧されたが、前2世紀のローマ共和政の動揺を示し、また後の前1世紀に起こる大規模なの奴隷反乱であるスパルタクスの反乱の先駆となった。
前135年の奴隷反乱 シチリア島東部シラクサの西の山中のエンナの奴隷エウヌス(シリア人であったらしい)は、口から炎を吐くという妖術を行い、予言者であると称して自ら王に就くことが約束されていると語り、周辺の奴隷をさそって反乱を起こした。エンナの町を占領した奴隷反乱はエウヌスを王としてあがめた。島の西南部でも奴隷反乱が始まり、全島を支配した。ローマ当局はようやく前133年にコンスル自ら鎮圧にあたり、ようやく奴隷軍を制圧した。
前104年の奴隷反乱 前103年に剣闘士奴隷の試合が公的な見世物のひとつとなったが、その翌年の前104年に、シチリア島でサルウィウス、アテニオンが指導する大奴隷蜂起がおこり、この奴隷軍は、五年間にわたって頑強にローマ軍に抗戦した。その反乱は、「指導者アテニオンが戦死したのちも、なお、粘り強くつづけられた。これに手をやいたローマの将軍は、最後に残った奴隷部隊千人の指揮者サテュルスにたいして、無抵抗に降服すれば処罰することなく解放すると約束した。こうして、ローマの将軍は奴隷たちをだまして捕え、ローマに剣闘士奴隷として送りこんだ。そして、彼らは猛獣と闘うことを強制された。しかし、彼らはこれを拒否した。奴隷たちは、ローマ市民の見世物になるよりは死を選んだのである。つまり、彼らは猛獣と闘う前に、フォルムの祭壇の前で、衆人環視のなかで相互に殺しあい、サテュルスは最後の一人を殺してから、自らの手で自らを殺し、英雄的な「もっとも輝かしい」壮絶な最期をとげたのであった。」<土井正興『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 p.14> |
 |
| ウ.内乱の1世紀 |
| A グラックス兄弟の改革
| 前2世紀の後半、大土地所有制の進行をとどめて中小農民の没落を防ぎ、ローマ共和政の維持をはかろうとした護民官グラックス兄弟による土地改革。保守派の元老院の反対でグラックス兄弟は殺されたり、自殺に追いやられ、結局実現されずローマ共和政の崩壊は一気に進み、内乱の1世紀を経て帝政に移行する。
グラックス兄弟は名門スキピオ家につながる貴族の出であるが、改革派であった。兄のティベリウス=グラックスは前133年、護民官に選ばれ、次のような土地制度の改革案を提示した。
1)公有地125ヘクタール以上の占有を禁止する。ただし子供二人以上の場合は250ヘクタールとする。
(これは前367年のリキニウス=セクスティウス法を復活させたもの)
2)制限以上の土地を占有している場合は、返還させる(没収する)。
3)土地配分委員を設け、返還された土地は貧しい市民に抽選で配分する。その地は転売は禁止で課税を受ける。
民会はその提案を可決したが、元老院を中心とした保守派が激しく反発し、もう一人の護民官に反対させる。グラックスは民会にその護民官の解任を提案、それも可決される。反対派は実力を行使しグラックスを撲殺してしまう。
ついで前123年に護民官に選ばれた弟ガイウス=グラックスも改革を進めようとしたが、元老院派に襲われて自殺に追い込まれ、グラックス兄弟による改革は頓挫した。
Epi. 棍棒で殴り殺された兄、自殺した弟 元老院の妨害が続き、グラックスは翌132年年、護民官に再立候補を決意した。護民官の再任は国法に反するので、選挙に敗れれば裁判で死刑になることを覚悟し、喪服で議場にはいる。投票の最中に反対派の元老院議員の一団が棍棒をもって議場に現れ、グラックスの護衛たちは元老院議員の威信を恐れて道をあけて護衛の役を放棄、グラックスは脳天に棍棒の一撃を受けて倒れ、死体はテーヴェレ川に投ぜられた。弟のガイウス=グラックスは前123年に護民官に選出される。兄の定めた土地法の実施に努め、徐々に改革の実績を上げたが、保守派の元老院と、彼を支持する民会の対立はますます激しくなった。彼は護民官再々任選挙で敗れ引退する。グラックス兄弟の改革を実施しない元老院に対し怒った民会のグラックス派が元老院の最右派を斬殺、両派の対立はついに武装党争となり、グラックスは調停に努めたが失敗、元老院派に追われる中、自殺した(前121)。グラックス派支持者250名が死刑、3000名が逮捕され、グラックス派は壊滅した。しかしその土地改革はしばらくの間は継続され、効果も上げた。<以上、モンタネッリ『ローマの歴史』中公文庫 p.159~ などによる> |
| a 大土地所有者の土地を没収
| |
| B 内乱の1世紀
| 前121年グラックス兄弟の改革が失敗に終わると、共和政の再建は困難となり、政局は元老院、平民会入り乱れての閥族派と平民派の有力者同士の政争の時期となった。それから前27年のアウグストゥスの即位による帝政ローマの成立までのほぼ紀元前1世紀にあたる100年間を、内乱の1世紀という。両派の内乱の他、都市の反乱、奴隷の反乱そして辺境の反乱が相次いだ。 |
| a マリウス
| 農民出身の軍人で、ユグルタ戦争(前111~105、北アフリカのヌミディアの王ユグルタが起こした叛乱)で武勲をたて護民官に当選。さらに異例の5年連続の執政官となった。当時北方のガリア人(キンブリ族、チュートネス族)の侵攻が始まり、大きな脅威となっていたが、マリウスは軍制改革を実施、有産市民からの徴兵制をやめ、無産市民から給与の支給、掠奪の許可、土地の配分を条件に志願兵を募るという職業軍人制に転換することとした。これによって軍を立て直したが、ローマ共和政を支えた市民軍の原則(徴兵制)は終わり、職業軍人あるいは傭兵に依存する国家に変質した。
ガリア人との戦争でも大勝したマリウスは、奪った戦利品と領土を贈与され、大富豪となった。彼自身は政治には無関心であったが、平民派は彼の名声を利用しようとした。一時引退するが、前91年同盟市戦争が起こるとふたたび呼び出されて軍の指揮を取り、反乱軍を厳しく弾圧。その戦争で副官だったスラと対立、前88年には敗れてアフリカに逃れる。スラが小アジアに向い、ローマで平民派のクーデターが起こるとローマに戻り、閥族派を処刑、権力を奪回した。前86年、その死後権力は子の小マリウスが継承するが、ローマに戻ったスラ軍に敗れる。 |
| b スラ
| 貧乏貴族の家に生まれ、若い頃は無頼生活を送ったという。ユグルタ戦争・同盟市戦争でマリウスの副官となり勲功をたてる。その後、マリウスと対立、閥族派(保守派)の中心人物と目されるようになり、前88年全権を委任されて小アジアのミトリダテス戦争鎮圧に向かう。スラのいなくなったローマでは平民派がクーデターを起こし、マリウスもアフリカから戻り内乱状態となる。マリウスが前86年に死ぬと、小アジアから戻ったスラが勢力を盛り返し、前82年にはローマ最初の無期限の独裁官(ディクタトル)となり、敵対者をリストにある人物は誰が殺してもいいという「処罰者リスト」に載せ、前81年までに平民派を一掃、グラックス兄弟の改革以前の貴族政に戻した。 |
| ユグルタ戦争
| 前111~前105年の、ローマと北アフリカのヌミディア王ユグルタとの戦争。ヌミディアとは、北アフリカのカルタゴの西にあった国。その王のユグルタがローマに反抗した戦争。ローマは将軍マリウスを派遣して鎮圧した。カエサル時代の歴史家サルスティウスが『ユグルタ戦争』を書き残している。 |
| 職業軍人制
| ローマ共和政が変質し、グラックス兄弟の改革が実施されなかったこともあって中小農民の没落が明確となり、前2世紀末には中小農民を重装歩兵とするいわゆる「市民軍の原則」は成り立たなくなっていた。一方、ローマの周辺ではユグルタ戦争、同盟市戦争、ミトリダテス戦争が相次ぎ、また北方のゲルマン民族の侵攻も始まっていたので、国防体制の再建に迫られていた。そこでマリウスは、コンスルとなると画期的な兵制改革に乗り出し、無産市民を志願兵として採用し、職業軍人として育成することに変更した。全ての兵士には長槍と剣を与え、新しい部隊の編制を目指した。しかし、現実には兵士は有力者の私兵となり、マリウス以下、スラやポンペイウス、カエサルなどの強大な軍事勢力が抗争することとなる。 |
| c 同盟市戦争 | 前91年、ローマに征服されたが市民権を認められていなかったイタリア半島内の都市が同盟を結び、ローマに対してローマ市民権を求めて反乱を起こした。それが同盟市の反乱(同盟市戦争 ~88年)。ローマは将軍マリウスの軍を派遣し、元老院は反乱に参加しないことを条件に市民権を認めるなど、懐柔策を採り、さらに将軍スラが前88年までに反乱を鎮圧した。しかしその結果、イタリア半島にすむ自由民はすべて市民権を持つこととなり、ローマの民会は事実上機能を果たせなくなる。 |
| ミトリダテスの反乱
| 前88年から前63年まで、前後3回にわたる、ローマと小アジアのポントス王ミトリダテスの戦争。ミトリダテス戦争ともいう。ミトリダテスはローマの東地中海支配に反発して挙兵、一旦はローマ将軍スラとも和睦した。その後再び反乱、最後は将軍ポンペイウスによって征討された。 |
| C スパルタクスの反乱
| 前73~71年に起こった、ローマ史上最大の奴隷反乱。ローマ共和政は奴隷制を基盤としていたが、大土地所有の進展は奴隷に対する搾取を強め、すでに前2世紀には2度にわたってシチリアの奴隷反乱が起きていた。前1世紀の「内乱の1世紀」といわれる混乱期に起こったのがスパルタクスの反乱。最終的にはポンペイウスやクラッススの率いるローマ軍に鎮圧されたが、ローマの社会と政治に大きな衝撃を与えた。
反乱の経緯:カプアの剣闘士学校では、剣闘士奴隷(剣奴)が、観衆の娯楽のために死ぬ訓練を受けていた。ある日二百人が脱走を企て、七十八人が成功、付近を掠奪し、スパルタカスというトラキア出身の仲間を首領に選ぶ。雄弁で才能豊かなスパルタクスは、イタリア全土の奴隷階級にアッピールを発し、七万を組織、自由と報復に餓える反乱軍団を作り上げ、武器の製造と用法を教え、元老院派遣の鎮圧軍を再三にわたって敗走させる。スパルタクスは勝利に酔わず、アルプスを超えて解散帰郷の方針を立てる。しかし仲間を一本化できずイタリアにとどまる。一時はローマに迫ったが、クラッススがローマ軍全体を指揮して迫ると激突を避け、南進してシチリアに向かい、そこからアフリカへ逃れようとする。クラッススは急追して本隊にせまり、さらにスペインから急行したポンペイウスが叛乱軍の不意をついて急襲。スパルタクスは自ら敵陣に突入して死に、叛乱軍も壊滅した。生き残った叛乱軍七千は捕らえられ、アッピア街道に磔柱が立ち並んだ。<モンタネッリ『ローマの歴史』中公文庫p.192>
※なお、スパルタクスの反乱については、土井正興氏『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 が多くのことを教えてくれる。 |
剣奴(剣闘士奴隷)
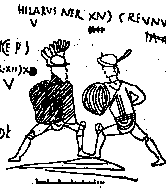
| 古代ローマで、市民への見世物として互いに戦闘することを強制された奴隷を剣奴、あるいは剣闘士奴隷という。いわゆるグラディエイターである。多くは戦争捕虜の中から選抜されて養成所で育成され、各地の闘技場で互いに戦わされたり、猛獣と戦わされるなどした。そのような剣奴の境遇の中から起ち上がったのが、前73年のスパルタクスの反乱であった。彼は前73年に剣奴養成所を脱走して反乱を組織し、ローマを大いに脅かした。その反乱が鎮圧され、和制時代から帝政に移行してからも剣闘士奴隷は続き、紀元80年、ティトウス帝の時にローマの円形競技場(コロッセウム)が完成すると、そこでは大々的な剣闘士同士の殺し合いや猛獣との戦いが、皇帝がローマ市民に与える娯楽として興行された。5世紀の初め、キリスト教信仰が広がり、404年に剣闘士試合は中止されることとなった。左の図は、剣闘士試合を描いたポンペイの落書の一部。<土井正興『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 p.12>
剣闘士奴隷の公認 「……剣闘士の決闘は、エトルリア人の習慣が、ローマをはじめイタリア各地に伝わったものであった。事実、エトルリア人の骨壺や墓には、しばしば闘っている剣闘士が描かれている。それは、エトルリア人が、死者の霊をとむらうために、戦争捕虜を墓の前で闘わせるという習慣を持っていたからである。ローマ人自身が、はじめて公然と剣闘士の試合をおこなったのは、前二六四年のことであった。ブルトゥス・ペラの息子が、父親の葬式にあたって、その霊の名誉のために、三組の剣闘士を市場で闘わせたのである。たしかに、それは身内だけの前で演ぜられたものであり、素朴で質素で、むしろ父の死をとむらうという宗教的側面が強いものであった。その剣闘士の試合が、前一〇五年には、二人の執政官によって公的な見世物のひとつとして、民衆に提供することを承認されたのである。つまり、剣闘士の試合は国家によって、民衆に提供される見世物のひとつとして公認されたのであった。しかし、このことは、剣闘士試合の興行権を国家が独占したことを意味するものではなかった。国家が開催する剣闘士の試合とならんで、個人が剣闘士の試合を民衆に提供することも法的に保障されていたのである。……」<土井正興『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 p.17>
剣闘士試合の中止 ローマ市民は、こうした競技を無上の楽しみにしていた。「だから、404年に剣闘士試合を中止させるきっかけをつくった白衣の修道僧テレマクスが、闘技場におり立って、この残酷な競技を中止するよう要求したとき、観衆は怒って彼に石を投げつけ、ひるまずに要求をつづけたテレマクスを、ついに打ち殺してしまったのは、観衆にとってみれば、きわめて当然のことだったのである。この血なまぐさい残酷な競技は、これほどローマ市民によって愛好されていたのである。」<土井正興『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 p.13> |
| a 奴隷反乱
| ローマが海外領土(属州)を獲得すると、被征服民を大量に奴隷として本国に連れ帰り、貴族や有力者の家内奴隷として、またラティフンディウムでの労働奴隷として、一部は剣闘士奴隷として売買した。この大量の奴隷が古代ローマの繁栄を支えていたが、権利はまったく認められず、早くから反乱を起こすことがあった。奴隷の反乱はローマ社会の根底をゆるがすことなので、政府は徹底して弾圧にあたった。その頂点にあるのが前1世紀のスパルタクスの反乱であるが、それ以外にも、前2世紀には2回にわたりシチリア島の奴隷反乱が起こっている。古代ローマの奴隷反乱はいずれも鎮圧されるが、2世紀以降となると奴隷の供給も止まり、奴隷の中には解放されるものも現れ、その待遇を向上させ、コロヌスと言われるようになっていく。 |
| D 第1回三頭政治
| 前60年、カエサル・ポンペイウス・クラッススの有力三者が、争いを止め、協力態勢をとった政治同盟のこと。元老院の合議制というローマ共和政の原則の前に、完全な独裁権を実現できず、有力者が私的な盟約を結び、元老院に対抗しようとしたもの。カエサルは将軍、ポンペイウスは軍人で政治家、クラッススは富豪として、それぞれ人気があったが、まだ互いの名声に依存しなければならなかった。また、カエサルはガリア、ポンペイウスはスペイン、クラッススはシリアというそれぞれの勢力圏を持っていた。前53年のクラッススの戦死をきっかけに、カエサル・ポンペイウス間に亀裂が入り、前49年解体する。 |
| a ポンペイウス | 前1世紀、ローマ共和政末期の代表的な閥族派の軍人、政治家。カエサル、クラッススと共に第1回三頭政治の一角を占め、後にカエサルとの争いに敗れエジプトで殺害された。
スラの腹心で女婿として頭角を現し、スパルタクスの反乱を鎮圧するのにクラッススとともに功績を挙げ、元老院からさらに東方遠征の指揮権を認められ、小アジアのミトリダテス戦争を平定。また地中海の海賊を平定して名声を上げる。カエサルが台頭すると、元老院の意に反してそれと妥協、クラッススとともに第1回三頭政治を実現する。その中でスペインでの支配権を認められた。クラッススの戦死後、次第に元老院保守派と結んでカエサルと対立するようになり、その排除をもくろむ。しかしガリアから戻ったカエサルを恐れてローマを逃れ、最後はエジプトで殺される。 |
| b クラッスス | 共和政末期のローマで、カエサル、ポンペイウスと共に第1回三頭政治を行った政治家。東方遠征の途次、パルティアとの戦いで敗れて戦死した。
父はスラの副官でマリウス派と戦い自決した。その遺児のクラッススに対しスラは消防団の組織を与えた。クラッススは火事が起こると現場にかけつけ、消化の前に持ち主に権利を売り渡すことを約束させてから消火に当たったという。そのようにして財産を蓄え、将軍となってスパルタクスの反乱の鎮圧にポンペイウスとともに功績を挙げる。カエサルに資金を提供してその協力者となり、ポンペイウスとともに第1回三頭政治を行う。彼の勢力圏はアジアのシリアであったので、東方遠征を試み、パルティアとの戦争で戦死する(前53)。 |
| c カエサル | 前1世紀の共和政ローマの軍人、政治家。ポンペイウス、クラッススとの第1回三頭政治の後、権力を集中させ、終身独裁官となる。最後は皇帝となることを狙ったが、共和派によって暗殺される。
名門であるが貧乏貴族の家に生まれた。生年には前100年と102年の2説ある。禿げ上がった大きな頭と張り出たえら、口をへの字に曲げ下唇が突き出ていて、けして美男ではなかったが女性には人気があり、部下は「禿の女たらし」と呼んだという。マリウスの甥にあたり、また平民派キンナの娘コルネリアを妻としていたので平民派と見られた。一時はスラから離婚を命じられ、それを拒否してローマを追放された。スラ引退後、属州スペインの総督として財力を蓄え、前60年、ポンペイウス、クラッススの支持を得て執政官となった(第1回三頭政治)。さらに彼は軍事力の基盤を固めるため、前58年からガリア遠征を実行。それを平定することに成功した。一方、クラッススは東方遠征に向かったがパルティアとの戦いで戦死してしまった(前53年)。ローマに残ったポンペイウスは元老院と結び、独裁権を得ようと画策する。それを知ったカエサルは、前49年1月10日属州とローマ本土の境界線であるルビコン川を超え(「賽子は投げられた!」)、ローマに入り、ポンペイウスを倒して独裁権力を握った。敗れたポンペイウスは東方に向かい、最後はエジプトに逃れたがそこでプトレマイオス朝の王に裏切られて殺された(前48年)。ポンペイウスを追ってエジプトに入ったカエサルはプトレマイオス朝の王を廃してその姉のクレオパトラを女王とし、二人は夫婦ともなった。ローマからの帰還要求に応え、途中小アジアを平定(「来た、見た、勝った。」)してからローマに帰った。さらにアフリカを拠点としていた保守派のカトー、スペインのポンペイウスの残党などを破り、権力を集中させた。前46年には独裁官、前44年には終身独裁官に就任、3月15日、元老院会議場でカエサル独裁の反対派の暗殺団(その一人がブルートゥス)の手によって暗殺された。
カエサルは文人としても才能があり、『ガリア戦記』『内乱記』を今に伝えている。また政治家としては、暦法を統一して、「ユリウス暦」を定めたことも重要である。
Epi. 7月の名前(July) カエサルの名はユリウス。英語での綴りは、Julius Caesar で、ジュリアス=シーザー。7月をJulyというのは、カエサルがこの月の生まれだったので、それにちなんで名つけられた。なお、Caesar という名から、後に皇帝を意味するドイツ語のカイザーや、ロシア語のツァーリという言葉が派生した。 |
| ガリア遠征
| 前58年~51年まで、ローマのカエサルによる軍事遠征。ガリアとはほぼ現在のフランスにあたり、ケルト系のガリア人が居住し、ローマの影響を受け、それに服属していたが、ライン川東方のゲルマン諸部族が次第にガリアに侵攻し、ローマに反抗するようになっていた。ローマで三頭政治の一角に位置したカエサルは、その軍事的な征服によって、政治的な優位を勝ち取る好機と考え、自ら軍隊を率いて遠征を行った。数回にわたる遠征の結果、カエサルはガリアのほぼ全域をローマの領土に編入し、その名声を一段と高めた。また彼はその詳細な記録を『ガリア戦記』として残しており、文学的な価値とともに、当時のガリアにおけるゲルマン民族の社会を知る上での貴重な資料となっている。 |
| E カエサルの独裁
| カエサルは三頭政治の崩壊の後、エジプトに遠征してポンペイウスを破り、さらに小アジア、アフリカ、イベリア半島に遠征をつづけて反対勢力をすべてつぶし、圧倒的な軍事力を背景に前46年ローマに戻り、10年間の独裁官(ディクタートル)に就任した。その後も元老院を有名無実化して、インペラトル(軍の最高司令官)として事実上の独裁政治を行った。その内政の主なのもには次のようなものがある。
・海外に植民市を建設し、約8万人の遊民(無産市民)を入植させる。
・穀物配分を32万人から15万人に削減する。
・結社を禁止する。また牧場の労働者のうち3分の一は自由人であること。(奴隷反乱の防止)
・混乱していた暦を改訂して、太陽暦(ユリウス暦)を制定した。
・ローマの都市計画の立案(実現せず)。
・市民権の拡大。ガリア=キサルピナに一括してローマ市民権を与える。
・属州民に市民権を与えてローマの正規軍に採用する。
Epi. シーザー(カエサル)の野望と最後:「外面のはなやかさにひきかえ孤独だったシーザーは次第に君主政に惹かれていった。前44年の春・・・共和主義者の蛇蝎視した王(レクス)という称号が彼の心を占領した。「終身の独裁官」の称号を帯びた彼は、昔の王のように紫衣をまとい、金色の玉座についた。・・・残るは王の名と王冠だけである。2月15日のルペルカリアという昔からの祭に、民意打診の奇妙な演出が行われた。年中行事のうちとけた気分でフォルムに集まった民衆を前に、コンスルのアントニウスがうやうやしく王冠を捧げた。ところが予期された民衆の拍手は起こらなかった。カエサルはとっさの気転で王冠を辞してその場をつくろった。それから一ヶ月後・・・シーザーはイタリア内では独裁官、外では王となるという妥協案を出すつもりでいた。彼の着席するのを待って一人の嘆願者が進み出た。願いを容れられないで彼はシーザーの衣を捉えた。それを合図に、短剣をかざした人々がシーザーに襲いかかった。傷にひるまず身をかわして抵抗した彼も、ブルーツスを認めたときは顔を上衣でおおい、力尽きてポンペイウスの立像の下に倒れた。」<秀村欣二『ギリシアとローマ』1961
世界の歴史2 中央公論社 p.317-318> |
| a インペラトル
| 本来は「命令権」を持つ者の意味。兵士が軍司令官に対し「無限の権をもつもの」という意味の称号として使われていた。前45年、敵対勢力を全て打ち負かしたカエサルがローマに凱旋したとき、元老院がこの称号を贈り、カエサルも終生それを用いた。強いて訳語を充てれば、「最高司令官」とか「凱旋将軍」となるが、後に初代皇帝となったオクタヴィアヌス(アウグストゥス)もこの称を用いたので、「皇帝」を意味するようになった。英語の emperor の語源である。 → ローマ皇帝 |
| b ブルートゥス | 前44年3月15日、元老院の会議場で仲間のカッシウスらとともにカエサルを襲撃し殺害した。彼は共和政の熱心な支持者であった。初めはカエサルを支持していたが、カエサルの独裁が強まると、共和政に反するものと考え、カエサル殺害を実行した。しかしブルートゥスは元老院の支持を得られず、カッシウスとともにローマを逃れマケドニアに入り、前42年フィリッピの戦いでオクタヴィアヌス=アントニウス連合軍に敗れ、自刃する。
Epi. ブルータスおまえもか! ブルートゥス(ブルータス)は実はカエサルが愛人との間にもうけた実子だという。彼はその義兄カッシウスからカエサルの独裁政治に対する批判(カエサルは王になりたがっている)を吹き込まれ、また実の父であることをうすうす知っており、憎んでもいたので暗殺団に加わったものと思われる。暗殺団の中にブルータスの姿を見て、カエサルが「ブルータス、おまえもか!」と言ったのは、実の子だったからであろう。 |
| F 第2回三頭政治
| カエサル・ポンペイウス・クラッススの第1回三頭政治についで、ローマ共和政末期に出現した、有力三者の妥協による政治同盟。前43年、カエサルの部将アントニウスと、カエサルの養子オクタヴィアヌスが、カエサルの部将レピドゥスを仲介役として妥協が成立、アントニウスはエジプト・ギリシア・西アジアを、レピドゥスはアフリカを、オクタヴィアヌスはヨーロッパをそれぞれ支配することとなった。 |
| a アントニウス
| カエサルのもっとも信頼の深い部将であった。暗殺直後にカエサルの遺言をあずかり、その後継者は自分であると確信をもったが、実はカエサルが指名した後継者は、オクタヴィアヌスだった。もくろみが外れたアントニウスはオクタヴィアヌスと争ったが、元老院の支持がオクタヴィアヌスにあるのを見て妥協し、同じ部将のレピドゥスを仲介にして第2回三頭政治を成立させた。第1回と同じく、元老院を抑えるための妥協であった。それによってエジプトの支配権を得たアントニウスはエジプトに向かうがそこでプトレマイオス朝女王のクレオパトラの魅力に取りつかれ、その進言によってオクタヴィアヌスとの決戦に踏み切る。しかし、前31年アクティウムの海戦に敗れ、翌年アレキサンドリアで自殺。 |
| b レピドゥス
| カエサルの部将。前43年、アントニウス、オクタヴィアヌスとともに第2回三頭政治を始める。前36年失脚。 |
| c オクタヴィアヌス | ローマ帝国初代の皇帝アウグストゥスとなった人物。カエサルの養子でその後継者となり、アントニヌスなどとの第2回三頭政治の後、アントニヌスと覇を争い、アクティウムの海戦で勝利して権力を確立し、帝政に移行させた。
祖母がカエサルの妹。カエサルには(4度も妻を取りかえたが)男子に恵まれなかったので、このオクタヴィアヌスを養子にした。彼は病弱でいつでも腹巻、襟巻、毛の帽子を離さず、薬を持ち歩いていたという。しかし意志力と決断力は優れており、カエサルはそこを見込んで後継者に指名したらしい。カエサルが暗殺された時はわずか17歳であったが、ただちにローマに駆けつけ、アントニウスに面会した。アントニウスは「坊や」といって取り合おうとしなかった。アントニウスがカエサルと同じ独裁者になることを恐れたキケロなどの元老院議員はオクタヴィアヌスを支持、両者はモデナで戦い、オクタヴィアヌスが勝利した。アントニウスは同じカエサルの部将レピドゥスの仲介でオクタヴィアヌスと講和し、前43年第2回三頭政治を成立させた。オクタヴィアヌスは腹心のアグリッパを用い、支配体制の強化につとめた。前31年、エジプトのクレオパトラと結んだアントニウス軍をアクティウムの海戦で破り、ついで翌年アレクサンドリアを攻略してアントニウスとクレオパトラを自殺に追い込み、プトレマイオス朝を滅ぼした。権力を掌握したオクタヴィアヌスは、五十万の軍を二十万に削減、三十万を帰郷させて土地を買わせ農業に就かせた。また国家に対する私人の負債を帳消しにし、公共事業を興し、官僚組織を整備し、財政を再建させた。彼は連続十三回、執政官に当選、元老院を完全に抑えることができた。そのような情勢を背景に、前27年、アウグストゥスの称号を与えられ、事実上の最初のローマ皇帝となり、「ローマ帝国」を創始した。 → 皇帝としてのオクタヴィアヌスは、アウグストゥスの項を参照。
Epi. 譲り合いの精神で生まれた?ローマ帝政 「前27年、(オクタヴィアヌスは)突然全権力を元老院に返還、共和政復帰を宣言、引退して一私人にもどると言った。まだ三十五歳、耳なれぬ「第一人者(プリンケプス)」という称号しか受けていない。元老院はそれにこたえて自分達自身も総辞職し、全権力をあらためてオクタヴィアヌスに委譲し、国の全権を握って頂きたいと懇請、アウグストゥスすなわち「尊敬すべき人」という称号を奉る。オクタヴィアヌスはいやいやながらという顔つきでこの懇請を容れた。両側で念入りに演出したこの芝居は、今や保守共和派の反抗が終結したことを天下に宣明した。誇り高い元老院も、混乱よりは独裁を選んだ。」<モンタネッリ『ローマの歴史』p.242> |
| d クレオパトラ | 前1世紀中ごろ、プトレマイオス朝エジプトの女王で、クレオパトラ7世という。プトレマイオス朝はヘレニズム国家であるから、クレオパトラはエジプト人ではなく、マケドニア系の人。ローマの圧力に苦しんでいたエジプトを、ローマの有力者の争いを利用して存続をはかった。まずポンペイウスを追ってエジプトに来たカエサルを誘惑(クレオパトラは寝台のシーツの間に身を隠し、寝台ごとカエサルのもとに運ばせたという)、夫婦となり、一子カエサリオンを産んだ(カエサリオンは後にオクタヴィアヌスに殺される)。次にはオクタヴィアヌスと対立したアントニウスと結んだが、前31年アクティウムの海戦に敗れ、首都アレクサンドリアに戻り、追ってきたオクタヴィアヌスを誘惑しようとしたが、すでに41歳、彼はその手に乗らず、もはやこれまでと観念したクレオパトラはわが胸を毒蛇にかませて自殺した(前30年)。その死体はオクタヴィアヌスによって、アントニウスと並んで埋葬された。カエサルやアントニウスを惑わしたその美しさは、中国の唐の楊貴妃と並び称されている。アクティウムの海戦でエジプトが敗れた前31年は、前331年のアレクサンドリアが建設されてからちょうど300年目にあたっていた。これによって、プトレマイオス朝エジプトは滅亡し、ローマの地中海支配は完成した。 |
| e アクティウムの海戦
| 前31年、オクタヴィアヌスのローマ海軍と、アントニウスとプトレマイオス朝エジプトのクレオパトラの連合軍が、ギリシア西北の地中海上で対戦した海戦。オクタヴィアヌス軍は数では劣ったが、アグリッパの指揮によって大勝、アントニウス軍はアレクサンドリアに敗走する。これによってプトレマイオス朝は滅亡し、ローマの東地中海制海権が獲得し、地中海を「われらの海」とする画期となった。 |
| G 帝政ローマの成立
| 一般に前27年、オクタヴィアヌスが元老院より「アウグストゥス」の称号を与えられたときから、帝政ローマ、または「ローマ帝国」という。ただし、「帝国」を皇帝の治める国ではなく、広大な異民族を含む範囲を支配する世界帝国という意味で用いれば、共和政ローマの段階の前2世紀中頃のポエニ戦争の勝利によって「ローマ帝国」が成立したと言うことも出来る。また帝政ローマの皇帝は元老院をはじめとする共和政のシステムを存続させていた段階の元首政の時期と、3世紀中頃以降の皇帝が専制権力を握った専制君主政の時期とに分けられる。 → ローマ帝国 |
| ローマ帝国 | 古代ローマの歴史の中で、共和政ローマと区別し、前27年の初代皇帝アウグストゥスの即位から、実質的には395年の東西分裂まで、形式的には1453年のビザンツ帝国滅亡まで存続したのが「ローマ帝国」、あるいは「帝政ローマ」である。
ローマ帝国は全地中海世界を支配し、北は現在のイングランドと大陸ではライン川からドナウ川を結ぶ線、南はエジプトなどアフリカ北岸、東はメソポタミア、西はイベリア半島に属州を置いた世界帝国であった。この広大な領域をローマ皇帝が統治する専制国家であったが、当初の政治は元首政(プリンキパトゥス)という皇帝も市民の第一人者として権威を持ち、形の上では元老院も機能している共和政の伝統を強く残した体制であった。その全盛期は1世紀末から2世紀の五賢帝の時代であり、地中海世界に「ローマの平和」(パックス=ロマーナ)を実現した。しかし3世紀の軍人皇帝時代をへて帝政の性質も大きく変化し、3世紀末のディオクレティアヌス帝の時から専制君主制(ドミナトゥス)という、共和政の伝統を無視し、皇帝は神として君臨する体制となり、同時に帝国の四分統治が導入された。4世紀のコンスタンティヌス帝は帝国を再建したが、新たな精神的な柱としてキリスト教を公認し、また都をローマからコンスタンティノープルに移した。帝国を支えていた奴隷制を基盤としたラティフンディウム(大土地所有制)と多くの属州が3世紀頃から崩れて生きたことが帝政の変質と衰退の原因であった。さらに外的な要因として東方でのササン朝との抗争、北辺からのゲルマン人の侵入があり、4世紀末には東西に分裂し、西ローマ帝国は476年に滅亡する。東ローマ帝国は、もはやローマから離れたところを都とし、実質的にギリシア化してビザンツ帝国と言われるようになるが、理念的にはローマ帝国そのものであった。18世紀のイギリスの歴史家ギボンの大著『ローマ帝国衰亡史』も五賢帝時代からビザンツ帝国の滅亡までを対象としている。またヨーロッパ世界においてはローマ帝国およびローマ皇帝は全ヨーロッパを統治する権能を持つ厳かな名称とされ、フランク王国のカール大帝、東フランクのオットー大帝のように「ローマ皇帝」の冠を戴き「ローマ帝国」を復活させるところに全ヨーロッパに及ぶ支配権の根拠を求めている。そして中世ヨーロッパの「神聖ローマ帝国」にもその理念は復活してくる。
ローマ帝国が地中海世界で繁栄した1~2世紀は、東アジア世界においては漢帝国(後漢)の時代であった。このユーラシア大陸の東西に時を同じくして出現した世界帝国は、直接交渉を持つことはなかったが、おりから活発となった陸上でのシルクロードと、インド洋の季節風を利用した海の道を通じて、間接的ながら交易が始まった。7世紀以降のイスラーム世界と唐の交易ほど密ではなかったが、ローマと漢の登場は、世界の文明史の展開でも重要な契機であった。
ローマ帝国の「帝国」の意味:一般に「ローマ帝国」は、アウグストゥスが皇帝となった前27年以降をさし、それ以前の「共和政」と区別しているが、「帝国」という用語は必ずしも「皇帝の治める国」を意味するものではない。現代では「帝国主義」諸国のこと、あるいは「アメリカ帝国」とか、ソ連社会主義「帝国」などのような使い方もある。「帝国」を意味する英語の
empire はラテン語のインペリウムからきた言葉で、皇帝の治める国という意味ではなく、ローマ共和政の時代からローマによって支配されている「くにぐに」から成る一つの世界をあらわすものとして使われてきた。従って共和政の時代でも地中海支配を成立させた前2世紀の中頃から「ローマ帝国」という場合もある。
ラテン語のインペリウムとは、「命令」という意味であり、さらに「ローマの命令が行われる地域」の意味となった。共和政時代にすでにローマの命令が他の国々に及ぼされ「ローマ帝国」と意識されていた。ただし、そのローマと服属国の関係を、近代の「主権国家」の観念でとらえると時代錯誤となる。古代においては「主権」の概念がないため、例えばシチリアの諸国は属州となったが、「主権を接収された国」という意味の属国ではない。「主権を保全する国」という意味の独立国でもない。「自由」なローマ国民が「自由」な国々を「友邦」として「支配」するのがこの時代の「ローマ帝国」であった。これを「古典的ローマ帝国」と呼ぶ。<以上の説明は、吉村忠典『古代ローマ帝国』1997
岩波新書 p.2-4、および p.140-146 を参照> |
 |
| エ.ローマ帝国 |
| A 元首政
| → 元首政(プリンキパトゥス) |
| a プリンケプス | プリンケプスとは「市民の中の第一人者」と言う意味で、具体的には元老院の議員リストの初めに名前が記されること。日本では「元首」と訳す。実質的には「皇帝」または「君主」であるが、オクタヴィアヌスは義父のカエサルの失敗を繰り返さないために、共和政の伝統を尊重する姿勢をとったので、この称号を用いた。プリンケプス(元首)による政治という意味で、ローマ帝国前半の政治形態を元首政(プリンキパトゥス)という。
オクタヴィアヌスの権力掌握時期:オクタヴィアヌスが権力を核とした経緯は次のようになり、そのいつの時期をもって権力掌握とするかについては説が分かれている。一般的には前27年のアウグストゥスの称号を得た時を帝政の始まりとしている。
前30年 エジプトのプトレマイオス朝とアントニウスを破り、ローマに凱旋。その前後から「インペラトル」(凱旋将軍、最高司令官の意味)と言われる。
前29年 元老院から「プリンケプス」(市民の中の第一人者)の称号を贈られる。
前27年 内乱時の非常大権を元老院に返し、共和政再興への意志表示を行う。それを讃えて元老院は「アウグストゥス」(尊厳のある者)の称号を贈る。
同 年 元老院と民会の決議により、イスパニア・ガリア・シリア・エジプトの軍隊命令権を10年間付与される。
同時に属州総督(プロコンスル)命令権を元老院と分けて行使することを認められる。
〃 護民官職権を付与される。
前19年 コンスル命令権を付与される。
前12年 最高司祭長(大神祇官)となる。
前2年 「祖国の父」の名誉称号を贈られる。
オクタヴィアヌスの実質的権力は前30年に「内乱の1世紀」を終わらせ地中海世界の安定をもたらしたときに成立した。さらに共和政との駆け引きの中で、「元首政」という妥協点を見出し、「アウグストゥス」として実質的な皇帝となった前27年が権力を確立させた時期と言うことが出来る。 |
| b アウグストゥス
| 本来は「尊厳者」を意味するラテン語の称号。前27年にローマ元老院がオクタヴィアヌスにこの称号を贈り、以後は彼自身をアウグストゥスと呼ぶ。またこれ以後の皇帝の称号ともなるので、ここからローマ帝政が始まるとされる。初代皇帝としてのアウグストゥスは、「ローマ帝国」の体制を作り上げた。
アウグストゥスの業績:彼は各地に「業績録」の碑文を残している。自画自賛の部分を差し引いて次のようなことが彼の実績および失政とされる。
・内政では身分制の確立に努めた。元老院身分(セナトーレス)は100万セルテルティウスの財産を持ち、生まれながらローマ市民で、財務官職に就いたことのあるもの。幅の広い緋色の縁取りの上衣(トガ)、赤皮の靴を着用することが出来る。騎士身分(エクイテス)は40万セルテルティウス以上の財産をもつ生まれながらのローマ市民であること。金の指輪、狭い緋色の縁取りの上衣を着ける。この層がアウグスティヌスの政治を支える官僚層となった。それ以外の市民は平民(プレブス)とされたが、この身分は固定ではなく能力によって変動した。
・また、帝国の首都にふさわしい都市としてローマの整備に努めた。「私はローマを煉瓦の町として引き継ぎ、大理石の都として残すのだ」と自慢している。その他、警察力の強化、結社の禁止など治安の維持をはかり、内政につとめた。何よりもローマ市民からは平和を実現したことがアウグストゥスを皇帝として指示した最大の理由であった。
・対外的には属州を拡大させ、穀物供給を増やした。特にエジプトの属州化は大きかった。また獲得した属州の辺境にケルン(植民地を意味するコロニアが地名の起源)、マインツ、トリアー、アウクスブルク(アウグストゥスの名による)などの植民都市を建設した。しかし、ゲルマン人との戦いではゲルマニアとの国境をエルベ川まで拡大しようとしたが、紀元後9年のトイトブルクの森の戦いで大敗を喫し、失敗している。
Epi. 8月(August)の名前 アウグストゥスは、カエサルが定めた暦が無視され混乱していたので、以前の暦法に戻した。この時の暦法の調整で8月を自分の称号にちなみ「アウグストゥスの月」と名付けた。彼は9月生だったが、執政官に就いたのが8月だったことなどから、と弁明した。これが August という月の名の起源である。<スエトニウス『ローマ皇帝伝』上 岩波文庫による> |
| c 元首政(プリンキパートゥス) | 前27年、オクタヴィアヌスはアウグストゥスの称号を与えられたが、彼自身は自らを「市民の中の第一人者」の意味でプリンケプスと呼ばれることを望んだ。それは、アウグストゥス(皇帝)の地位は、あくまで市民の中から選ばれ、市民を統治するものであるという共和政の理念を維持するためであった。実態は皇帝はすべての権力を集中させていたとしても、形の上では元老院や平民会、執政官や護民官も継続されている体制であった。そのような共和政を基盤とした帝政のあり方を、「プリンキパートゥス(元首政)」という。これは帝政後期の3世紀末のディオクレティアヌス帝の時から「ドミナートゥス(専制君主政)」に変わる。 |
| ローマ皇帝
| ローマ皇帝の称号:初代皇帝アウグストゥスの最終的な(崩御の時の)正式な肩書きは、「インペラトル(最高司令官)・カエサル・神の子・アウグストゥス・大神祇官・コンスル十三回・最高司令官の歓呼二十回・護民官職権行使三十七年目・国父」という恐ろしく長いものであった。元首(プリンケプス)は称号ではなく、地位を意味する。肩書きが長すぎるので、元首つまり皇帝に呼びかけるときは最初のインペラトルか、次のカエサルを用いられるようになる。「皇帝」を意味する英語のエンペラーはインペラトルに、ドイツ語のカイザーはカエサルに由来する。<本村凌二他『ギリシアとローマ』1997 世界の歴史5 中央公論新社 p.325 などによる>
ローマ皇帝の継承:初代皇帝アウグストゥスの子供は娘のユリア(ユリアはスキャンダルの多い女性であったため、父帝によって幽閉される。)一人でその子も若死にしたので、妻の連れ子でユリアの夫であったクラウディウス家ティベリウス(ユリアの乱行に怒りロードス島に隠棲していた)をその後継者に指名した。彼は2代目の皇帝となった時、すでに60歳を超えていた。その後、ローマ皇帝の地位は、第5代ネロ帝までこのユリウス=クラウディウス朝(カエサル-アウグストゥスがユリウス家、ティベリウス以下がクラウディウス家)に世襲された。ネロ帝が自殺したあとは、何代か近衛部隊に推された者が皇帝となったがいずれも長続きせず、69年のウェスパシアヌス帝からフラウィウス家の皇帝が三代世襲する(フラウィウス朝)。次のネルヴァ帝からの五賢帝は、血縁のないものを養子にし、次の皇帝に指名する形態が続いた。このように、皇帝位は元老院の推薦のもとで、世襲か、養子で継承するというものであった。共和政でもない、東洋的専制君主制もとれない、というローマ帝国の事情がそのような皇帝位継承形態となったのであろう。
ローマ皇帝と軍隊:五賢帝の最後のマルクス=アウレリウス=アントニヌスは長子のコンモドゥスを皇帝に指名した。コンモドゥスは暴政を行ったので反乱が起き、その混乱の中で、近衛部隊を買収した人物が皇帝になるなどの混乱が続き、193年にセプティミウス=セヴェルスが皇帝となって混乱を治めた。彼はアフリカ出身の軍人で、ドナウ川上流のパンノニア知事を務めていた人物であった。彼の次の皇帝には、子のカラカラとゲタ兄弟が共同統治をおこない、セヴェルス朝と言われ、軍人皇帝時代の始まりまで続いた。235年以降の軍人皇帝時代は軍人が皇帝を擁立し、次々と交替するすることとなった。もともとインペラトルとは「命令権」を持つ者の意味で最高司令官であった。軍の最高司令官(日本で言えば戦前の天皇が大元帥として統帥権を持っていたようなもの)である皇帝は軍が服従するにたる人物かどうかが重視されていたのであろう。 |
| d ”ローマの平和” Pax Romana
| 前27年のアウグストゥスの即位から、後180年の五賢帝時代の終わりまでの200年間、地中海世界に大きな戦争がなかく、ローマの支配権のもと平和が実現された。地中海世界は、前5世紀のペルシア戦争とペロポネソス戦争、前4世紀のアレクサンドロスの戦争、イタリア半島統一戦争、前3世紀のポエニ戦争、前2世紀のマケドニア戦争、前1世紀の「内乱の1世紀」とその終わりのアクティウムの海戦まで、常に戦争が絶えなかったが、ローマの派遣によって地中海は「ローマの内海」と化したことをいう。パックス=ロマーナはラテン語で「ローマの平和」の意味。これをもじって、パックス=ブリタニカ(19世紀の大英帝国)、パックス=アメリカーナ(現代)などどいう。 |
| e ネロ
| ネロ帝はユリウス=クラウディウス朝の5代目皇帝。はじめは師のストア哲学者セネカの補佐もあって善政を強いたが、次第に狂気を発し、セネカも失脚する。64年7月、ローマの新しい都市計画を思いつき、自らローマ市街に火をつけたと言われる。その放火犯人をキリスト教徒であるとして大迫害を行った。さらに陰謀の疑いがあるとしてセネカを捕らえ死に至らしめた。一時期はギリシアに渡り演劇や音楽に熱中するなど、完全に皇帝としての人望を無くし、元老院も廃位を決定、ネロは追いつめられて68年、自殺した。 |
| ポンペイ | |
| B 五賢帝時代
| 96年のネルヴァ帝から、トラヤヌス帝、ハドリアヌス帝、アントニウス=ピウス帝、マルクス=アウレリアス=アントニヌス帝の退位する180年までの約100年間を五賢帝時代という。それまで相次いだ皇帝位をめぐる血腥い事件もなく、政局は安定し、またローマ帝国の領土が最大となるなど、その最盛期を迎えた。この帝位は、ハドリアヌスをのぞき、有能な人物が前帝の養子となる形で継承された。
18世紀イギリスの歴史家ギボンは『ローマ帝国衰亡史』の中で次のように述べている。
ギボンの五賢帝論 「仮にもし世界史にあって、もっとも人類が幸福であり、また繁栄した時期とはいつか、という選定を求められるならば、おそらくなんの躊躇もなく、ドミティアヌス帝の死からコンモドゥス帝の即位までに至るこの一時期を挙げるのではなかろうか。広大なローマ帝国の全領土が、徳と知恵とによって導かれた絶対権力の下で統治されていた。軍隊はすベて四代にわたる皇帝の、強固ではあるが平和的な手によって統制され、これら皇帝たちの人物および権威に対して、国民もまたおのずからなる敬仰の念を献げていた。その文民統治はネルヴァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、そして両アントニヌスとつづく歴代皇帝によって慎重に守られた。彼らとしても自由の世相に喜びを感じ、みずから責任ある法の施行者であることを任としていたのだ。もし当時のローマ人にして、理性的自由を楽しむ心があったならば、おそらくこれら皇帝こそは、かつての共和制時代をふたたび蘇らせたという栄誉に値いしたはずである。」<エドワード・ギボン(中野好夫訳)『ローマ帝国衰亡史』1 ちくま学芸文庫 p.156> |
| ネルヴァ | 前帝ドミティアヌスが暗殺され、継嗣がなかったので、元老院は議員の中からネルヴァを指名した。すでに70歳を越していた。彼は元老院にはかりながら政治を行い、後継者も元老院にはかってトラヤヌスを選んだ。これ以後、養子を後継とした皇帝の交代が行われる。ネルヴァは五賢帝の最初とされるが、政治面に特筆すべきことはなく、このトラヤヌスを後継に指名したことが功績とされる。 |
| a トラヤヌス
| 属州のスペインで生まれ、軍人として育ち、皇帝に指名された時はガリアの戦線にいた。内政では元老院の意を尊重し、もっぱら外征にあたり、まずダキア(現在のルーマニア)を征服、60歳を超えてからインドを目指して東方遠征に出発、パルチアの都クテシフォンを占領し、メソポタミア・シリア・ペルシア・アルメニアを奪った。しかし老齢のためローマにもどる途中、117年、セリーノで64歳の生涯を終えた。トラヤヌス帝の時ローマ帝国の領土が最大となった。またローマの公共広場(フォーラム)の「トラヤヌスの円柱」の他、多くの建造物を造った。 |
| ハドリアヌス | トラヤヌスと同じ、スペイン生まれ。トラヤヌス急死の後、元老院から後継者に指名される。皇帝になるとまず東方のパルチアとの戦争を中止して兵を引き揚げ、ペルシア・アルメニアはパルチアに返還した。これで建国以来続いた外征はいったん終わることとなった。彼自身は旺盛に帝国各地を巡回し、ブリタニアでは北方のケルト人に対して「ハドリアヌスの長城」と言われる防壁を築いた。それはイギリスに現存するローマ帝国時代の遺跡である。 |
| アントニウス=ピウス | 23年の治世の間、何事も問題は起こらなかったと言われる。元老院は彼を「最良の君主(オプティムス・プリンケプス)」と呼び、死後ピウスの称号を贈った。 |
| b マルクス=アウレリウス=アントニヌス
| スペイン生まれのストア派哲学者として知られていたが、161年40歳の時皇帝を継承する(~180年まで)。哲学者が皇帝になったと言うので「哲人皇帝」といわれた。自らも『自省録』という著作がある(ギリシア語で書かれている)。五賢帝の最後の皇帝であるが、この頃から、北のゲルマン人、東のパルチアの侵攻が激しくなり、その対応に追われるようになった。また東方からペストがローマ領内に伝染し、被害が大きくなった。対ゲルマン人戦争でウィンドボナ(ウィーン)に出征、その地で亡くなった。後継者として実子のコンモドゥスを指名し、五賢帝の養子に継承させる形態が終わりを告げた。次のコンモドゥス帝からはローマ帝国は衰退に向かう。なお、この時代東西交渉が盛んで、彼は中国にまで使者を派遣したらしく、後漢書に「大秦王安敦」とあるのは彼のことであろうとされている。また彼の侍医として知られるのが著名な医師ガレノスである。
Epi. マルクス=アウレリウス=アントニヌスの唯一の失政 マルクス=アウレリウス=アントニヌスは五賢帝の一人として、人民に寛容と慈愛を示し、善政を施した。ただ一つの失政は、それまでの優秀な人物を養子にしてその人物が次の皇帝となると言う慣行をやめ、実子のコンモドゥスを後継者としたことであった。コンモドゥスは、マキアヴェッリの『君主論』によると、「獣のように残忍な心の持ち主だった。だから人民に対して強欲ぶりをいかんなく発揮しようとした。軍隊を手なずけ、彼らに放埒のかぎりを許した。ほかにも、皇帝の尊厳などわきまえず、しばしば格闘場におりて、剣闘士あいてに戦い、およそ皇帝の品性にそぐわない数々の下劣な行為に走った。」こうして憎しみにあい、見くびられて、陰謀にあって殺された。<マキアヴェッリ『君主論』1515 池田廉訳 中公クラシックス
p.150> |
| 自省録
| |
| c ロンドン(ロンディニウム) | ローマ帝国の属州ブリタニアの統治のため建設されたのがロンディニゥム。タキトゥスの『ゲルマニア』に、商業の中心地として出てくる。現在のロンドンの中心部シティ一帯がそれにあたるらしく、地下からローマ時代の城壁のあとが見つかっているという。 → 中世のロンドン
Epi. ローマ時代のロンドン ロンドンという地名の由来には、ケルト語の「リン(湖)」と「ダン(砦)」からできた、という説がある。ローマ人が沼地を埋め立てて建設した砦がその始まり。ロンディニウムを中心に道路がしかれ、ローマのブリテン支配の拠点とされた。62年にブリテン人の反乱(ブーディカという女性に率いられた)があって町は灰燼に帰し、今でもその時の瓦礫や骸骨が地下から見つかることがある。その後本格的な都市建設が始まり、壮大なバジリカやフォーラム(広場)、公共浴場、円形劇場などが建造された。またロンドン港からはローマに向けて穀物や海産物が積み出された。190年には市街の周囲に高さ6mの壁が建造された。しかし、410年にはローマ人は撤退し、一時衰え、601年にローマ教皇がイギリス人のキリスト教化の拠点として大司教を派遣し、このころからロンドンバラ、あるいはロンドンと言われるようになった。(しかし大司教はロンドンではなく、カンタベリーに居を構えた。)<ジョン・フォーマン『とびきり不埒なロンドン史』1999 筑摩書房より> |
| d パリ(ルテチア) | ガリアの一都市ルテチアから発展したのがパリ。パリの名は、このあたりに住んでいたパリシ族(カエサルの『ガリア戦記』に出てくる)によるらしい。 |
| e ウィーン (ウィンドボナ) | ローマ時代の国境であったドナウ川中流に、ローマが建設した砦の一つがウィンドボナ。それが現在のオーストリアの首都、ウィーンのもとになった。五賢帝の最後のマルクス=アウレリウス=アントニヌスは遠征先のこの地で死んだ。
なお、ヨーロッパでその他のローマ時代に起源のある主な都市は、ケルン(コロニア=アグリピネンシス)、ボン、バルセロナ、トリエルなどなど。現在も各地からのローマ時代の都市遺跡が見つかっている。 → ウィーン |
| C 市民権拡大
| ローマ市民権は本来、都市国家ローマ在住の市民のみに付与されていた。ギリシアの都市国家アテネの市民権法では両親ともアテネ人であることを終始その市民の条件としていたが、ローマはその支配圏を拡大するにつれ、市民権も拡大していった。服属した都市の中でも植民市の市民、自治市の上層市民、海外の属州の上層市民にも認めらるようになった。しかし、半島内の同盟市や、属州には市民権は認められなかった。ところが、次第に同盟市や属州の自由民の中に市民権を求める声が強まり、前1世紀の同盟市戦争を契機にイタリア半島の全自由民に市民権が認められた。さらに3世紀初めのカラカラ帝の時、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(アントニヌス勅令)。これによって全自由民は(ラテン人でなくとも)市民権が与えられることとなり、ローマは法的にも都市国家ではなく、世界帝国となったといえる。 |
| a カラカラ帝
| 212年、カラカラ帝は帝国領内の全自由民にローマ市民権を与えた。一般的には、属州の含めての全自由民に市民権を拡大したことは、ローマが単なる都市国家が膨張した国家ではなく、ここで正式に「世界帝国」となった、という意義が認められている。しかし、カラカラ帝の市民権拡大の意図は、ただ相続税収入を増やすために過ぎなかったとも言われている。それまで市民権のない者は相続税を払わないでよかったからである。(カラカラの本名はマルクス=アウレリウス=アントニヌス。そこでこの命令をアントニヌス勅令ともいう。五賢帝と同じ名前だがもちろん別人。)カラカラ帝はまた、ローマの大浴場を建設したことで有名。
Epi. カラカラ帝の弟殺し カラカラ帝の弟はゲタといった。カラカラは父から弟のゲタと二人で帝位をわけて受け継いだが、独占欲が強く、弟を殺し帝位を独り占めにした。彼は、毎朝起き抜けに熊と格闘して筋骨を鍛え……たという。<モンタネッリ『ローマの歴史』p.342> カラカラという名は、彼はガリアのリヨン生まれで、いつも着用していたガリア風の長い上着に由来する。彼の治世には犯罪と狂気の連続で、約2万人がその犠牲になったという。彼自身は、第2のアレクサンドロス大王を自負してシリアに進出、パルティアと戦ったが、その最中、217年メソポタミアのカラエで部下に暗殺された。 |
| b 万民法
| 万民法という概念は、ローマ市民権を持つものを対象とした市民法(十二表法に始まる)に対し、市民以外のものも含む、普遍的な法という意味で、ローマで用いられていた。ローマの征服が進み、その支配下にローマ人以外の多くの人々が含まれるようになると、市民法だけでは処理しきれなくなってきた。そこで、212年にカラカラ帝がアントニヌス勅令を発布し、ローマ帝国の領内の全自由人に市民権を認めることとした。それ以後は、ローマ法は万民法として機能するようになる。ローマ帝国が衰退すると万民法の理念も衰え、法による社会秩序の維持に代わってキリスト教の宗教倫理が社会を律する時代である中世となり、次いでルネサンス期には「自然法」の理念がグロティウスなどによって確立されていく。 |
| アントニヌス勅令 | 212年、ローマのカラカラ帝が出した勅令で、帝国内のすべての自由民にローマ市民権を与え、ローマ法をすべての人に適用する万民法としたもの。ローマ市民権の拡大がはかったものであるが、同時に相続税の増収を図るという狙いもあった。この勅令をアントニヌス勅令というのは、カラカラ帝のカラカラはあだ名で、その本名がマルクス=アウレリウス=アントニヌス(五賢帝の最後の皇帝と同名)であったからである。 |
| 東西貿易 | ユーラシア大陸の西と東の文明圏間を結ぶ貿易関係。いわゆる4大文明間にも、例えば彩文土器の広がりに見られるような交易関係が在ったことが知られているが、大規模に展開されるようになったのは、西側の地中海世界にローマ帝国が、東側に漢帝国が成立した紀元1世紀ごろから。陸上でのシルクロード(絹の道)や草原の道などのルートがあり、海上でも地中海、紅海、アラビア海、インド洋を舞台とした南アジア貿易圏が成立していた(海の道)。南アジア海上貿易ではまずギリシア人商人が活動したがその様子は『エリュトゥラー海案内記』という1世紀ごろの記録が知られている。後に7世紀ごろからはイスラーム教徒のムスリム商人や、東方からの中国商人の活躍が始まる。イスラーム教徒のイブン=ハルドゥーンや、明の鄭和などが東西貿易ルート上で活躍した。 |
| 季節風貿易 | ローマ帝国の東方には当時、西アジアにパルティア王国、北インドにクシャーナ朝、中央インドにサータヴァハナ朝、南インドにチョーラ朝やパーンディヤ朝、東南アジアには扶南、中国には後漢があり、それらの国々を結ぶ交易が行われていた。特にインド洋では1世紀頃に季節風を利用した遠距離航海が行われるようになりインド産の品々がローマにもたらされ、ローマの金貨がインドにもたらされた。 → 季節風貿易(インド)
Epi. ヒッパロスの風 インド洋の季節風は、紀元前後にギリシア人のヒッパロスが発見したとされ、「ヒッパロスの風」と言われている。インド洋の季節風は1月前後は北東の風が強いが、夏は南西の風がインドに向けて吹く。この夏の季節風を利用すれば2週間ほどで容易にアラビア半島からインドに渡ることができた。ローマ帝国領からはぶどう酒やオリーブ油、珊瑚、ガラス器などが運ばれ、インドからは胡椒などの香辛料、真珠、象牙、綿布、中国産の絹、アフガニスタンのトルコ石やラピスラズリなどが輸入された。そのほとんどはローマ側の輸入超過で、金貨や銀貨がインドに流出していた。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 p.227-228
など> |
| 後漢 | → 第2章 3節 中国の古代文明 後漢の成立 |
 |
| オ.西ローマ帝国の滅亡 |
| A 軍人皇帝時代
| ローマ帝国の3世紀の中頃の約50年間、ローマ皇帝の地位が軍人出身者によって占められ、頻繁に交替した時代を言う。この時期を経てローマ帝国は前半の元首政の時期と、後半の専制君主制の時期に分けられる。
235年、皇帝セウェルス・アレクサンデルがライン川付近のゲルマン人討伐作戦中、その兵士によって暗殺されてから、285年にディオクレティアヌス帝が専制君主政をしくまでの50年間、ローマ皇帝位は軍隊によって動かされ、18人も入れ替わった。260年にササン朝軍と戦って捕虜となったヴァレリアヌスや、272年にシリアのパルミラを征服したアウレリアヌスらが典型的な軍人皇帝であった。彼らのうち、暗殺された者が16名という不安定な時期であり、ササン朝ペルシアとの抗争と共に北方のゲルマン民族の動きも活発となり、ローマ帝国の軍事力もゲルマン人傭兵に依存する度合いが強くなり、ローマにとって「3世紀の危機」と言われている。それを乗り切ったのがディオクレティアヌス帝であったが、それ以降は共和政の性格は全くなくなり、専制国家として存続することとなる。 |
| a ゲルマン人
との戦い | ローマとゲルマン人の戦いは、前1世紀のカエサルがガリア遠征の際、ライン川を越えてゲルマン人と戦っており、またアウグストゥスはローマのすべての権力を一点に集中させたたが、ゲルマン民族との戦いでは手痛い敗北を喫している。紀元後9年、彼は将軍ウァールスに3軍団をつけて、ライン川を越えさせ、アルミニウスという首長が率いるゲルマンの一派を攻撃させた。ところがトイトブルクの森の戦いで、ローマ軍は大敗を喫してしまう。
その後もローマにとってゲルマン人は強敵であり、長くライン川とドナウ川を結ぶ線を国境として対峙していた。軍人皇帝時代の251年にはデキウス帝がドナウ川を越えたゴート族と戦い戦死している。ゲルマン人の中にはローマ領内に移住するものもあり、ちょうどローマ市民だけで軍隊を維持できなくなっていたローマは、ゲルマン人からの防衛をゲルマン人傭兵に依存するようになった。その状況を破ったのが375年の西ゴートに始まるゲルマン人のローマ領内への民族大移動であった。 |
| b ササン朝ペルシア
との戦い | ササン朝ペルシアは226年にパルティアを倒してイラン高原に建国された、イラン人の国家。西アジアに広大な領土を持ち、イラン文化の全盛期をもたらす。ローマ帝国は東方でパルティア、さらにこのササン朝ペルシアと国境を接していたので、たびたび交戦した。軍人皇帝時代の260年には皇帝ヴァレリアヌスが、アルメニアに進出してきたササン朝ペルシアのシャープール1世と戦い、エデッサの戦いで大敗して捕虜となり、現地で捕虜となった。それ以後も、ササン朝はローマ帝国(さらにビザンツ帝国)にとっても最大の脅威となる。
ササン朝とビザンツの抗争の影響:このササン朝とビザンツ帝国の長期にわたる抗争が、東地中海-レヴァント地方-シリア-メソポタミアを結ぶ東西貿易を衰退させ、その戦乱を避けた商人たちがアラビア半島南部のヒジャスを通るようになり、それがメッカやメディアの繁栄をもたらし、そこから世界史の新たな主役となるイスラーム教とその国家が台頭することとなる。ササン朝は651年、イスラームによって滅ぼされ、ビザンツ帝国はその領土を大幅に減少させることとなる。 |
| ヴァレリアヌス
| 軍人皇帝時代のローマ皇帝(在位253~260年)。ローマの名門出で元老院議員であるが軍人として軍隊によって皇帝に推戴された。260年、西アジアでローマ領に侵入してきたササン朝ペルシアのシャープール1世に対する遠征軍を起こし、エデッサの戦いで敗れて捕虜となった。ローマ皇帝のみでありながら捕虜となったのは彼が最初である。また捕虜となった後の境遇は判っていない。ヴァレリアヌスの敗北以来、東からのササン朝と西北からのゲルマン人の侵攻が激しくなり、国内でも軍隊の反乱が相次ぎ、いわゆる三十僭帝といわれる混乱期に入った。 |
| パルミラ
| パルミュラともいう。シリア砂漠のほぼ中央に位置するオアシス都市で、ペルシア湾方面からダマスクスと地中海東岸の海岸都市を結ぶ中間の要衝として栄えた。ヘレニズム時代から繁栄した都市であったが、1世紀からはローマに服属した。3世紀にササン朝が進出するとそれに抵抗し、女王ゼノビアはシリアからエジプト、小アジアにかけての勢力を築く。272年、ローマ帝国のアウレリアヌス帝(軍人皇帝の一人)が遠征軍を派遣し、パルミュラを制圧した。女王のゼノビアは、才色兼備の女王でありローマ軍とよく戦ったが、敗れて捕虜となりローマに連行された。アウレリアヌス帝によって破壊されたパルミラは、現在は砂漠の中の遺跡として残っている。
Epi. 女傑ゼノビア 18世紀イギリスの史家ギボンの『ローマ帝国衰亡史』第11章では、このパルミラと女王ゼノビアについて述べている。「・・・おそらくゼノビアこそは、アジアの風土風習が女の性(さが)として与える隷従怠惰の悪癖をみごとに打破してのけた、ほとんど唯一の女傑だったのではなかろうか。・・・その美貌はクレオパトラにもおさおさ劣らず、貞節と勇気でははるかに上だった。最大の女傑というばかりでなく、最高の美女としてもその名は高い。肌は浅黒く、・・・歯並みは真珠のように白かったという。漆黒のおおきな瞳は、ただならぬ光を帯びて輝き・・・声は力強く、しかも実に音楽的だった。」という最大限の賞賛を与えている。<ギボン『ローマ帝国衰亡史』2 p.39 ちくま学芸文庫> なお、ゼノビアとパルミラの遺跡については、牟田口義郎『物語中東の歴史』中公新書p.45~ にも詳しく述べられている。 |
| B ローマ社会の変化
| |
| a 内乱と異民族の侵入
| |
| b 都市への重税
| |
| c 解放奴隷
| |
| d コロナトゥス
| 従来の奴隷労働による大土地所有(ラティフンディウム)に変わって、ローマ共和政末期から帝政期にかけて出現してきた、有力者が土地を小作人に貸し付け、地代を取る形態の土地経営方式。小作人のことをコロヌスという。ローマ領の拡大が終わり、奴隷の供給が途絶え、奴隷の地位も向上して解放奴隷の一部はコロヌスとなり、さらに没落した中産農民もコロヌスになっていったものと思われる。 |
| e コロヌス
| ローマ帝政期のコロナトゥスのもとでの小作人のこと。奴隷と違い、家族を営み、人格的自由は認められたが、土地所有者に対し重い負担(地代ははじめは金納で、しだいに現物納に変わった)を課せられていた。さらに、コンスタンティヌス大帝の時、身分制度の強化の一環として、コロヌスの移動は禁止され、土地に縛り付けられ移動の自由はなくなった。ヨーロッパ中世の農奴の前身と思われる。 |
| C ディオクレティアヌス帝
| 3世紀末のローマ皇帝(在位284~305年)。軍人皇帝時代の混乱を収拾し、皇帝の政治体制をそれまでの元首政(プリンキパトゥス)から専制君主制(ドミナートゥス)に切り替え、「四帝分治制」によって帝国を再建した皇帝。また、キリスト教に対する最後の大迫害を行った皇帝としても重用である。
彼は属州ダルマティア(イタリア半島のアドリア海を隔てた対岸。現在のクロアティア)の解放奴隷の子と言われる。軍人としてとして頭角を現し、執政官、親衛隊指揮官となり、284年を収拾して皇帝となる。腐敗したローマを離れ、都を小アジアのニコメディアに移し、帝国を二分割、それぞれに正副皇帝をおく「四帝分治制」を始める。また東洋的な専制君主制を導入、皇帝崇拝を強要して、それを拒否したキリスト教徒に対する最後の大弾圧を行う。その経済統制、物価統制、身分統制(コロナトゥス制)などは一定の効果を持ち、ローマ帝国後期の体制を作り上げ、その滅亡を遅くしたといわれる。ディオクレティアヌスは皇帝位は世襲とせず、20年の統治期間の公約どおり、305年東西同時に副帝に譲位し、55歳で引退した。
Epi. 奴隷出身のローマ皇帝 ギボンの『ローマ帝国衰亡史』の一節。「ディオクレティアヌス帝の治世は、歴代先任帝の誰よりも見事だったのにひきかえ、当人自身の出自は、これまた誰よりも卑賤草の生まれだった。才幹と武力という強力な資格が、しばしば貴族という観念的諸特権の壁を打破してきたことは事実だが、さりとてなお自由民と奴隷階層との間には、依然として明確な一線が画されていた。ディオクレティアヌス帝の両親というのは、元老院議員アヌリアス家に仕えた奴隷だったし、また彼自身の名前からしてが、母の旧故郷だったダルマティア属州のある小村、その名前から取られた文字通り無名の姓にしかすぎなかった。だが、父の代になってやっと自由権をえ、まもなく同様条件の人間がよく就く書記職にありついたらしい。が、その息子(ディオクレティアヌス)というのは、ひどく青雲の志に燃えた青年で、好運の託宣でも受けたものか、それとも己の才幹を自覚したものかとにかくそれに動かされて、軍務に将来の夢を賭けることになった。・・・・」<ギボン・中野好夫訳『ローマ帝国衰亡史』2 ちくま学芸文庫 p.113> |
| a 四帝分治制(テトラルキア)
| ディオクレティアヌスは正帝(アウグストゥス)としてニコメディアを都に東部を担当、マキシミアヌスを同格の正帝としてミラノを都に西部を治め、それぞれに副帝(カエサル)をおいた。東の副帝は現ユーゴのスリエムスカに、西の副帝は現ドイツのトリアーに本営をおいた。ローマは政治的軍事的機能を失った。 |
| d 専制君主政(ドミナートゥス)
| ディオクレティアヌス帝は、宮廷に煩雑な儀礼を導入し、ユピテル大神の化身であると自称し、豪華な金糸で飾られた帝衣をまとい、皇帝をドミヌス(陛下)と呼ばせた。元老院はほとんど形骸化し、ローマの共和政の伝統は途絶えて、ローマ皇帝は東洋的な専制君主となった。このような帝政のありかたを帝政前半のプリンキパートゥス(元首政)に対して、ドミナートゥス(専制君主政)という。 |
| c 皇帝崇拝
| |
| d キリスト教徒
| |
| D コンスタンティヌス帝
| 4世紀初頭のローマ帝国皇帝で、専制君主制を確立し、また四分割統治から単一帝政に戻して帝国を再建し、新都コンスタンティノープルを建設した。またキリスト教を公認するという大転換を図ったローマ帝国後期の最も重要な皇帝。
在位は306~337。西の副帝であったコンスタンティウス=クロルスの子。人質のようなかたちで東の正帝の都ニコメディアで幼年時代を過ごす。東西の正帝、副帝の後継をめぐって争いが生じ、コンスタンティヌスも西帝位を主張して312年マクセンティウスと戦い、ローマに入った(そのときにローマにコンスタンティヌス帝の凱旋門が建てられた)。翌313年、東正帝リキニウスとミラノに会見して、ミラノ勅令を出し、宗教の自由を認めキリスト教を公認した。これによって帝国によるキリスト教迫害は終わり、教会には経済的援助も与えられた。さらに324年には東正帝リキニウスと対立してその軍を破り、統一ローマを再興した。翌325年にはニケーア公会議を主催してキリスト教の教義の一本化を図り、アタナシウス派を正統、アリウス派を異端とした。330年には「第二のローマ」を旧ビザンティウムの地に建設、新しい都とした(コンスタンティノープル)。また、租税州の安定を図って、コロヌスの移動を禁止して身分を固定化し、地中海交易を活発にするために基軸通貨としてソリドゥス金貨を鋳造発行した。
歴代皇帝で最も長い30年(副帝時代を含む)の在位期間であったが、帝政前期(元首政)とはまったく違った国家となっていた。政治形態では共和政の伝統は形だけとなって専制君主政(ドミナートゥス)が確立し、キリスト教が新たな国家理念とされるようになり、何よりも「ローマ帝国」といいながら、その中心は東方のコンスタンティノープルに遷った。
Epi. この印によりて汝は勝つ コンスタンティヌス帝がマクセンティウムと戦った時、天に燃える十字架の影と、「この印によりて汝は勝つ」という4語が空中に浮かぶのを見て、十字架を押し立てて戦ったところ、勝利を得た。このことがコンスタンティヌス帝がキリスト教の信仰に入るきっかけとなったという。この伝説に対して、ギボンは『ローマ帝国衰亡史』の中で詳しく論じている。彼は最初のキリスト教皇帝とされるが、彼自身が洗礼を受けたのは死の直前であり、ミラノ勅令の頃は明確な信仰を持つにはいたっていなかった。事実、その凱旋門には、信仰の力とは記されてはおらず、むしろ太陽神が描かれている。ギボンも言う通り、後の教会史をまとめたエウセビオスらが述べたのであり、それまで罪人の死刑に使われていた十字架が皇帝の勝利を導いたと当時考えらるというのは無理がある。<ギボン、中野好夫訳『ローマ帝国衰亡史』3 p.225~ など> |
| a キリスト教を公認 | 313年、コンスタンティヌス帝が、ミラノ勅令でキリスト教を公認した。厳密に言うと、このときはコンスタンティヌスは西の正帝で、東の正帝リキニウスとミラノで会見し、両者共同で公布したもの。勅令の主旨は、いわは「宗教寛容令」であり、いかなる宗教の信仰も認めるもので、キリスト教もその一つとつとして認められた。それによって1世紀のネロ帝以来続いたキリスト教に対する迫害が終わりを告げ、信仰を隠す必要が無くなりったので、帝国領内各地の教会がそれぞれ表だった活動を開始した。しかし、そのころすでにイエス時代から約300年経っており、その教義に関して、また儀式のあり方などでも、さまざまな分派が現れており、キリスト教内部の対立も同時に表面化した。そのため、コンスタンティヌス帝は自らの手で教義の統一を図る必要が出てきた。 |
| b コロヌス
| → コロヌス |
| d ソリドゥス金貨
| ローマ帝国のコンスタンティヌス帝が制定した金貨。帝国領の地中海域全域で流通させ、商業の活発化をもたらした。そのため、ソリドゥス金貨は、ローマ時代の地中海交易の繁栄の象徴であった。西ローマ帝国滅亡後のゲルマン諸国家もソリドゥス金貨の鋳造を続けたが、イスラーム勢力に地中海商業を抑えられたため、次第に流通しなくなり、ソリドゥスはラテン語の金貨の単位の名称として残ったが、中世では金貨は鋳造されず、銀貨の時代となる。東ローマ帝国でもソリドゥス金貨は継承されたが、ノミスマという呼称が使われるようになる。なお、現在もドルを$と表記するのはラテン語の金貨を意味するソリドゥスの頭文字Sからきている。 → 中世ヨーロッパの貨幣経済 |
| d ビザンティウム
| →第1章 2節 ビザンティオン |
| e コンスタンティノープル
| ギリシア人が建設した植民市ビザンティオン(ビザンティウム)の地に、前330年、コンスタンティヌス帝が「第二のローマ」(または新ローマ)として遷都した。帝の名前を冠してコンスタンティノープル(ラテン語ではコンスタンティノポリス)と言われるようになる。その地は黒海とマルマラ海(さらにエーゲ海を経て地中海につながる)をむすぶボスフォラス海峡に面し、帝国の西半分の中心にふさわしい交通の要所であった。その後、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の都として続き、ビザンツ文化の中心地、東西交易の中心地として繁栄した。その後イスラームのオスマン帝国がバルカン半島に侵入、オスマン軍のコンスタンティノープル包囲戦の結果、1453年にに征服されてからはイスタンブルと改称されて、現在に至る。 |
| f ゲルマン民族の大移動
| → 第6章 第1節 ゲルマン民族 参照 |
| E 東西分裂
| |
| a テオドシウス帝
| 東の正帝としてゴート人の侵入などに対応、西の正帝が殺されるとその支配権も収め、394年全ローマ帝国を再統一した。しかし395年、その死にあたり、息子のホノリウス(16歳)を西ローマ皇帝に、同アルカディウス(18歳)に東ローマ皇帝に指名し、ローマの東西分裂が確定した。テオドシウス自身はローマには一度も行ったことがなく、あくまで中心は東のコンスタンティノープルにあった。またテオドシウスは392年、異教徒禁止令を出し、アタナシウス派のキリスト教を国教とした。
Epi. テオドシウスの懺悔 テオドシウス帝は390年、ギリシアのテサロニケで暴動を起こした住民7000人を殺害した。ミラノ司教アンブロシウスは、皇帝がその罪を懺悔しなければ聖餐式(キリスト教の重要な儀式)を許さないと申し渡す。やむなくテオドシウスはアンブロシウスに従ってミラノの教会で懺悔し、その後その影響を強く受けるようになった。その結果が、キリスト教国教化につながる。なおアンブロシウスは、教父アウグスティヌスの師としても有名。<J.M.ロバーツ『世界の歴史3 古代ローマとキリスト教』1976
創元社 p.187> |
| b 東口ーマ帝国
| テオドシウス帝の長子アルカディウスから始まる。都はコンスタンティノープル。ゲルマン民族の侵攻を受けたが彼らはさらに西方に移動したため、東ローマは領土を維持することが出来た。コンスタンティノープルの旧名ビザンティオンから、ビザンツ帝国と言われるようになる。6世紀にはユスティニアヌス大帝の時代となり国力を高めて西地中海方面に進出、ゲルマン諸国を次々と破ってかつてのローマ帝国の支配領域を回復する。東方のパルティア、ササン朝ペルシアとの抗争は長期化し、7世紀にはアラビアに起こったイスラームの攻勢により、次第に領土を縮小させていくが、ギリシア正教会の宗教的な支配のもと、独自のビザンツ文化を維持し、1453年まで、1000年以上存続する。 |
| c 西ローマ帝国
| 幼帝ホノリウスが継承し、都はローマだが、すぐにミラノに移る。補佐するスティリコ将軍は忠誠心と賢明さで有名でヴァンダル族出身のゲルマン人であった。403年、ゲルマン人の攻撃を受けやすいミラノを捨て、首都を沼地に囲まれた一寒村であったラヴェンナに移す。彼はまず東ゴートの侵入、次の西ゴートのアラリックの侵攻から西ローマを守ったが、讒言によりラヴェンナで処刑される。410年再びアラリックが侵攻、ローマは掠奪にまかされるが、皇帝はラヴェンナにこもり抵抗できず。さらに属州アフリカをヴァンダルに奪われ、451,2年には北方からのフン族アッティラ大王の侵入を受ける。その後領土をゲルマン諸部族に奪われて縮小する中、皇帝位も不安定となり、軍の実力者が自分の子ロムスル=アウグストゥスをたてた。そのような状況の中でゲルマン人傭兵隊長のオドアケルが叛乱を起こし、476年皇帝を追放し、西ローマ帝国は滅亡した。オドアケルは廃位した皇帝を年金を与えてナポリに幽閉、東ローマ帝国皇帝ゼノンに帝国の旗章を返送し、自分は東ローマ皇帝の代官としてイタリア統治にあたると宣言した。
Epi. ラヴェンナの女帝 ガラ=プラキディア 410年の西ゴートのローマ侵攻からアッティラ大王のローマ侵攻までのあいだの40年間、西ローマ帝国は比較的安定していた。その間、西ローマ帝国の実権を握っていたのは、ガラ=プラキディアという女性だった。彼女は、テオドシウス帝の娘であったが、410年ローマが西ゴートの手に落ちたとき、その捕虜となった。そこで西ゴート王アラリックの子のアタウルフと愛し合い、蛮族の王子とローマ皇帝の娘の結婚ということとなった。しかし、アタウルフは他の王子にねたまれて暗殺されてしまう。ガラ=プラキディアはその後、何度かの結婚を経て、425年西ローマ皇帝となり、ラヴェンナで政治を執ることとなる。実質的な最後の西ローマ皇帝である。しかし頼るもののない彼女は、ローマに移り、教皇レオ11世を頼り、450年、波乱の生涯を閉じる。彼女の墓は現在、ラヴェンナのサン=ヴィターレ聖堂の近くにあり、美しいモザイクで飾られている。和辻哲郎もここを訪れ「外観がいかにもみすぼらしい煉瓦建てで、・・・中にはいって見てあっと驚いた」と行っている。<和辻哲郎『イタリア古寺巡礼』岩波文庫。ガラ=プラキディアの話は、藤沢道郎『物語イタリアの歴史』中公新書による> |
| F 西ローマ帝国の滅亡
| 395年の東西分裂後も、西ローマ帝国は存続したが、5世紀にはいるとゲルマン民族、さらにアジア系のフン族の侵入を受け、ローマはたびたびその掠奪の対象となった。帝国の防衛もゲルマン人傭兵部隊に依存しなければならず、皇帝は傭兵部隊の意向でたびたび廃位された。5世紀のゲルマン民族・フン族の侵入はつぎのとおりである。
406年 東ゴート族の侵入
410年 西ゴート族のアラリックのローマ掠奪
430年 ヴァンダル族のガイセリック、アフリカに入りピッポでローマ軍を破る。
451年 フン族のアッティラ大王のガリア侵入
452年 アッティラ大王、ローマに侵入。ローマ教皇レオ1世による説得で撤退。
455年 ヴァンダル族のガイセリック、ローマ掠奪
474年 ヴァンダル族のガイセリック、アフリカ・シチリアその他の地中海諸島を領有。
475年 西ゴート族のスペイン領有、ブルグンド族などのガリア分割。
476年 西ローマ帝国、オドアケルによって滅ぼされる。 |
| a オドアケル
| 第6章 1節 ゲルマン民族の大移動 オドアケル 参照 |
| ローマ市 | 西ローマ帝国滅亡後の、都市としてのローマの歴史を概観すると次のようになる。帝政末期にアラリック(西ゴート族)やガイセリック(ヴァンダル族)の掠奪を受け荒廃し、かつてのローマ帝国の都であった時代の繁栄は終わりを告げたが、中世にはいると文化と宗教の上で、ヨーロッパの中心としての役割をもった。特にローマ教皇庁の所在地として西ヨーロッパのキリスト教世界の中心地としての地位は重要でり、叙任権闘争を経て教皇権が最も盛んとなった12~13世紀には最も繁栄した。しかし、教皇権の衰退期には教皇のアヴィニヨン捕囚もあってローマは衰え、ルネサンス期に一時復興したが、フランスと神聖ローマ帝国の間でイタリア戦争が起こると、カール5世は1527年にローマを破壊、それ以降は世界史の表舞台からはしばらく姿を消す。そしてナポレオン時代のフランスによる支配を経て、イタリア統一運動(リソルジメント)の結果、1860年にイタリア王国が成立したが、ローマは依然としてローマ教皇領として残り、統一国家には編入されなかった。イタリア王国がローマを併合し、その首都とするのは1871年を待たなければならない。 → 近代のローマ |
 |
| カ.キリスト教の成立 |
| A ユダヤ教の変質
| 紀元前後のユダヤ教は、次の三つの党派に分かれて争っていた。
1)パリサイ派 神の恵みに答えて日常生活で律法(トーラー)を遵守することを強調する。
2)サドカイ派 従来のイェルサレム神殿を中心とした儀礼の遵守を主張する保守派。
3)エッセネ派 神殿儀礼の形式化を厳しく非難、律法の遵守も日常生活だけでなく、一種の共同体を形成して禁欲的に実践することを主張。(その一派の「クムラン教団」の修道院遺跡が死海のほとりで発掘され、「死海文書」という沢山の文献が発掘された。)<この項、および以下の項は佐藤研『聖書時代史』新約編に負うところが多い。> |
| a パレスチナ(ローマ時代) | パレスチナのユダヤ人は、前63年ポンペイウスに征服され、ローマの支配を受けることとなった。その後、前40年にヘロデがローマのオクタヴィアヌス(後のアウグストゥス)から王として認められて統治を行い、イェルサレム神殿を再建した。ヘロデ王は聖書に拠れば、イエスが生まれたとき、「ユダヤの王となる子が生まれた」と聞き、ベツレヘムの2歳以下の男子を皆殺しにしたという(イエスの両親のヨセフとマリアは天使のお告げによって難を逃れた)。前4年のヘロデ王の死後、内紛がおき、ローマが直接介入することとなり、紀元6年にはローマの属州として支配されることになった。ローマ総督としてこの地を支配したのがポンティオ=ピラトで、彼がイエスを処刑した。 |
| ヘロデ王 | |
| b ユダヤ人 | 第1章 第1節 古代オリエント世界 ウ.東地中海の諸民族 ユダヤ人 参照 |
| 死海文書 | |
| B イエス | イエスはアウグストゥス時代のローマが支配するパレスチナで、ユダヤ教の律法主義を否定して、神の愛を説き、多くのユダヤ人に受けいえられたが、反ローマの嫌疑で処刑された。その復活をシンする人々によって教団が成立し、やがてローマ帝国領内に広まり、民族を越えた世界宗教としてキリスト教に発展した。
「キリスト」とはのちに与えられた「救世主」を意味するギリシア語から来た言葉。ユダヤ人として生まれてた実在の人物であるが、イエスの生まれた年を紀元元年とするのは6世紀のローマの修道僧ディオニュシウス・エクシグウスという人が計算したことで、正しくない。聖書の記事からは紀元前4年以前と推定されている。なお、聖書のマタイ伝第2章にイエスが生まれた時、輝く星を頼りに東方の博士たちがユダヤにやって来たという記事があるが、コンピューターで計算すると紀元前6年に木星と金星がほぼ一つに接し、大きな光を放ったとことがわかるという。これがマタイ伝の東方の博士たちが見た輝く星であったはわからない。ガリラヤ地方のナザレの大工ヨセフと妻マリアの子として生まれた(ベツレヘムというのは根拠はない)。28年、ガリラヤ地方にヨハネという人物があらわれ、荒野で人々に呼ばわり、終末の審判が近づいた、悔い改めて洗礼(バプテスマ)を受けよ、と説き始めた。これは旧来のユダヤ教の神殿の祭司による「罪の許し」を否定することなので、ガリラヤの領主ヘロデ=アンティパス(ヘロデ大王の子)は捕らえて処刑してしまった。そのヨハネから洗礼を受けたのが若いイエスだった。イエスは、「神の国は近づいた、悔い改めよ」と伝道を開始し、ガリラヤ地方の貧民や病に苦しむ人々の中に入っていき、あちこちで病を治すなどの奇蹟を起こしたとされる。そして「十二使徒」をはじめとする信者が急激いに増えてきた。30年春過越祭(ユダヤ人の出エジプトを記念する大祭)に都イェルサレムに信者を率いて上京した。下層の民衆は救世主(メシア)の到来と受け取ったが、ユダヤ教の指導者や保守派は、神殿体制という秩序を破壊する危険な動きとして領主ヘロデ=アンティパス、ローマの代官ポンティオ=ピラトに訴えた。当局はイエスの動きに反ローマの民衆蜂起につながる恐れを感じ、ローマ軍の手を借り、ゲッセマネの丘で「最後の晩餐」を終えたイエスを捕らえ、都の外れのゴルゴタの丘で盗賊二人と十字架にかけて処刑した。弟子たちはなすすべもなく逃げ隠れたが、イエスの死後間もなく、イエスを見たという弟子たちが現れ、彼らはイエスの「復活」をイエスを裏切ったことへの赦しととらえ、そこに原始的なイエスの信者の団体(原始教会)が生まれた。彼らはさらにイエスは再び昇天し神のもとで最後の審判を下すであろうことを信ずるようになった。
イエスの教えから「キリスト教の成立」にいたるには、使徒のペテロなどによるローマでの布教、またパウロがイエスの死を人間の現在を贖うものと位置づけ、人種・民族を越えた救世主であると説いて世界宗教となってからである。 |
| a 神の国
| |
| b 福音
| |
| c パリサイ派
| ユダヤ教との保守派で、神の恵みに答えて日常生活で律法(トーラー)を遵守することを強調する。 |
| ピラト(ポンティウス=ピラトゥス) | |
| d 十字架
| |
| e 「復活」
| |
| f 救世主(メシア)
| |
| g キリスト
| |
| C イエスの教えの広がり
| |
| a 神の絶対的な愛
| |
| b アガペー
| |
| c 隣人愛
| |
|
| |
 |
| キ.迫害から国教化へ |
| A キリスト教の成立
| イエスが十字架に架けられた後、3日後に復活したことを信じ、キリスト(救世主を意味する)とあがめる宗教。その直後から少数の信者団体である原始キリスト教団が生まれた。はじめはユダヤ教の一分派としかとらえられなかったが、ペテロやパウロが小アジアのユダヤ人らに広め、さらにローマに赴き伝道することによってローマ領内に広まった。特にパウロが、イエスを救世主としてその愛によって人が原罪から救済されると説いてから、単なるユダヤ人のための信仰ではなく、あらゆる人々の信仰を受ける「世界宗教」としてのキリスト教に変質した。皇帝崇拝を拒否したキリスト教徒はローマ帝国では弾圧されたが、その間にも信仰はローマ領内に広がった。また地中海世界に五本山を拠点に教会も造られていった。
また3世紀ごろまでには『新約聖書』がまとめられ、教義も調えられ、312年のミラノ勅令でローマ帝国はキリスト教を公認した。イエス死後数百年を経てその教えの理解にも違いが生じていたが、国教化するに及んで教義の統一がはかられ、アタナシウス派の三位一体説が正統の教理と定められた。ローマ教会は西ローマ帝国の滅亡後、保護者を失って危機に陥り東方教会の下風におかれるが、教父アウグスティヌスは『神の国』を著して世俗の国家を超越した教会という理念を打ちたて、その後はゲルマン民族、特にフランク王国との結びつきを強め、800年の「カールの戴冠」によってゲルマン民族の封建社会とローマ=カトリック教会の結びついた西ヨーロッパ中世世界を成立させた。こうして西ヨーロッパではローマ=カトリック教会が絶大な精神上も世俗的にも力を持つようになる。一方東方のビザンツ教会はビザンツ帝国と一体となって繁栄し、ギリシア正教会をなっていく。その両者は8世紀の聖像崇拝問題以来対立を深め、1054年に分離する。 → 教会の東西分離 |
| a 使徒
| イエスの主要な弟子で十二使徒という。十二使徒は、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、ヤコブ、タダイ、シモン、ユダ(『新約聖書』マタイ伝第十章)。名前には聖書でも違いがある。なお、最後のユダ(イスカリオテのユダ)はイエスを裏切ったので後に十二使徒から外され、替わりにマッテヤが入る。また、キリスト教伝道で重要な役割を果たしたパウロは、イエスの死後に回心したので十二使徒には入らないが、広く「使徒」に加えられている。なお、12という数は、神の民であるユダヤ人は12の部族からなるとされていたので、それを反映していると言われている。 |
| b ペテロ
| ガリラヤ湖畔の漁師だったがイエスの最初の信者の一人となり、十二使徒の代表格。しかし、イエス逮捕の時はその場から逃げ、信者であることを否認した。そのことに悩んでいる時、イエスが復活したのを目の当たりにして、イエスは自分を赦してくれたと信じる。またそのとき、イエスから「私の羊を飼いなさい」と言われ、イェルサレムの教団建設の先頭に立つ。さらに小アジアのユダヤ人に教えを広め、ローマにおもむき、ネロ帝の迫害に遭遇し、逆さ十字架にかけられて殉教した。彼の遺骸の埋められたところに後にコンスタンティヌス帝が建てた教会が聖ペテロ教会であり、それを含む一角がキリスト教(ローマ=カトリック教会)の中心であるヴァティカンとなる。ペテロが初代ローマ教皇に擬せられているわけである。なお、ペテロは英語読みではピーター Peter。ペテル、ピョートル、皆同じ。
Epi. クォ・ヴァディス ペテロはローマで迫害にあったとき、一旦はローマから逃れようとした。その途中、キリストと出会い、「主よ、いずこへ行き給う」(クォ・ヴァディス)と尋ねたところ、キリストは「十字架にかかるためにローマに行く」と答えたので、ペテロはおのれを恥じ、意を決してローマに戻り、殉教したという。この話をもとに、ポーランドの作家シェンキェヴィチが書いた有名な歴史小説が、『クォ・ヴァディス』(1896)である。この作品でシェンキェヴィチは、当時ロシアに支配されていた祖国ポーランドの自由と独立への希望を、キリスト教徒の迫害に耐え抜く姿に託して描いたのだった。 |
| c パウロ
| パウロはユダヤ人で、ユダヤ教のパリサイ派に属し、イエスに敵対していたが、あるとき突然「なぜ私を迫害するのか」というイエスの声を聞いて、回心し信者となったと伝えられる。彼はギリシア語を話すことが出来、ローマ市民権ももっていたので、小アジアの非ユダヤ人(異邦人)の間に初めてイエスの教えを伝えることができた。パウロによって非ユダヤ人にイエスの教えが広がるに伴い、イエスは単なる救済者にとどまらず、神そのものである、という思想も生まれてくる。そこから、この宗派はユダヤ教と決定的に違う「キリスト教」となり、民族の枠を越えた「世界宗教」へ脱皮していく。パウロはローマに行き、ネロ帝の迫害で殉教したとされる。なお、パウロは英語読みではポール Paul。 |
| d 異邦人
| |
| e 世界宗教
| |
| B ローマ帝国による弾圧
| ローマ帝国領内に広がったキリスト教に対し、ローマ帝国は他の宗教と同じように寛容であり、はじめはそれ自体を禁止することはなかった。しかし、キリスト教徒がローマ法を守らない(ローマの神々への供え物を拒否するなど)場合は罰せられた。また庶民の間にも、キリスト教徒は「人肉食をしている」などの誤解(聖餐式というキリストの血と肉を象徴するブドウ酒とパンを信者が食べる儀式ご誤解された)されたり、奴隷も同じ信者として同席して会合していることを社会秩序を乱すことと恐れられたりするようになり、危険な宗教とみられるようになった。ローマ帝国を通じ、迫害が続いたわけではなく、何度かの迫害の時期と、容認される時期があった。大きな迫害として知られているのが、1世紀のネロ帝の時と、4世紀のディオクレティアヌス帝の時である。帝政後期には、皇帝崇拝が強要されるようになり、キリストのみを信仰するキリスト教徒はそれを拒否し、激しい迫害を受け、殉教するものも多くなった。このような迫害にもかかわらず、キリスト教徒はローマ領内の下層民を中心に、カタコンベに隠れて信仰を守り、ますます広がっていった。 |
| a ネロ帝
の迫害 | 64年、ネロ帝はローマ大火の原因をキリスト教徒の放火であると断定した。それまでキリスト教についてはほとんど知られていなかったがこれで人々にその存在が知られるようになった。ネロは捕らえたキリスト教徒を簡単な裁判で死刑に決め、猛獣の餌食にしたり、十字架にかけたり、松明代わりに燃やしたりしたという。またこのとき、キリスト教の最高指導者として捕らえられたペテロも、逆さまに十字架にかけられ殉教した。パウロもこのときローマで殉教したとされる。 |
| b 殉教
| |
| c 力タコンべ
| ローマ時代の地下墓所をカタコンベ(カタコーム)という。ローマのものが最大で、幅約0.8m、高さ約2m、総延長560キロにも及ぶ。他に、ナポリ、シラクサ、マルタ、アレクサンドリアなどでも遺跡が見つかっている。キリスト教が非合法とされたローマ帝政時代には、信者はここで祈りを捧げるなどして信仰を守った。その壁面には彼らの信仰を示す壁画が残されており、美術的価値も高い。 |
| 教会
| 教会はキリスト教徒が団体とその信仰の場をしめすことばで、新約聖書ではギリシア語の「エクレシア」の語があてられている。エクレシアはギリシアでは市民の「会議」または「集合」(その反対がディアスポラ=離散)を意味する言葉であった。キリスト教が発展する過程で、「教会」はキリスト教団そのものをさすようになった。5世紀初めの教父アウグスティヌスは、この世に「神の国」を出現させるものとして教会を位置づけ、教会の恩寵を説き、それ以降の中世ヨーロッパではローマ教皇を中心とした聖職者の組織である「教会」が世俗の国家に超越する存在とされた。ローマ=カトリック教会は教皇-大司教-司教-司祭という聖職者の組織(ヒエラルキー)を持ち、教会会議(公会議、宗教会議とも言う)が最も重要な組織的決定を行い、教会法によって運営された。また中世では教会は寄進、開墾、購入によって教会領を所有する領主ともなった。16世紀の宗教改革の時代になると、ローマ=カトリック教会の権威を否定する人々は新たにプロテスタント教会をつくったが、そこでは聖職者の存在は否定された。また教会そのものの存在を否定する無教会派のキリスト教も登場した。 |
| d ディオクレティアヌス帝
の迫害 | 303年、ディオクレティアヌズ帝は最後で最大のキリスト教迫害を行った。自らをユピテル神になぞらえ、神としての皇帝崇拝と、伝統的なローマの神々への祭儀への参加をキリスト教徒に強要した。またキリスト教の書物は焼却され、教会の財産は没収された。次の東西正帝のうち、特に東の正帝ガレリウスは迫害を続け、エジプトや小アジアで多数の教徒が殉教した。西の正帝コンスタンディヌスは迫害を中止する。 |
| e 「新約聖書」
| ユダヤ人とヤハウェ神の救いの約束を記した書が『旧約聖書』であるのに対し、イエス=キリストによる救いの約束を記したのが『新約聖書』とされている。イエス自身が書いたわけではなく、イエスの行いや言ったことを、その弟子たちが伝え、伝道されるうちにまとめられていった。はじめは布教の対象となった小アジアやギリシアで用いられていたヘレニズム世界の共通語(コイネー)であるギリシア語で書かれていた。2~3世紀にかけて、各巻ごとに書かれ、グノーシス派という異端との対立の必要から正しい聖典の制定に迫られ、397年カルタゴ公会議で現在の27巻の聖書が公認された。また4世紀末には、ヒエロニムスによって聖書のラテン語訳(ラテン語訳聖書をウルガータという)がなされた。
マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの四福音書でイエスの行動と説教を伝え、次にペテロ、パウロなどの活動を伝える「使徒行伝」があり、パウロの手紙といわれる13の書簡が続く。最後に最後の「ヨハネの黙示録」ではローマ帝国の迫害下にある信者に対し、忍耐と希望を呼びかけ、終末での神の審判への期待を記している。New Testament
聖書はその後、旧約・新約ともラテン語に訳され、ローマ・カトリック教会では聖職者がその知識を独占して、ラテン語もギリシア語も読めない中世の農民、庶民は聖書を読むことはできず、彼らの信仰の拠り所は聖書ではなく教会の聖職者の説教であった。カトリック教会の説教は次第に本来の聖書から離れることとなると、それに対する批判がおこり、13世紀のイギリスのウィクリフは初めて聖書を英語に訳したが異端として弾圧された。そして16世紀の宗教改革が起こり、ルターがドイツ語に翻訳し、またそれが活版印刷によって普及してはじめて一般庶民が読めるようになった。 |
| C キリスト教の公認
| ローマ帝国は、皇帝崇拝を拒否する異教であるとして、厳しくキリスト教を弾圧した。しかし、キリスト教は社会の下層民にひろがり、さらにローマの市民・上層民にも信者が現れるようになった。4世紀に登場したコンスタンティヌス帝は、軍人皇帝時代の混乱を克服して、帝国の統一を回復しようとしたとき、キリスト教を認めることに踏み切り、313年にミラノ勅令を出し公認した。さらに325年にニケーア公会議で教義の統一を図りった。キリスト教はその後、教義をめぐっての争いが続き、さらにユリアヌス帝のときは再び弾圧されることになったが、392年にテオドシウス帝によってローマ帝国の国教とされ、国家宗教となった。 |
| a ミラノ勅令
| 313年にローマ帝国のコンスタンティヌス帝が、キリスト教を公認した勅令。これによってキリスト教に対する弾圧は終わった。312年、西の正帝の地位をめぐってマクセンティウスと戦っていたコンスタンティヌスは、(伝承によれば)夢のお告げに従って十字架をかかげて戦って勝利してから、キリスト教を認めるようになった。翌年313年、西の正帝として、東の正帝リキニウスとミラノ(当時はメディオラヌム)で会見し、いずれの宗派の信仰も認めることで合意し、両帝の名で勅令として公布された。特にキリスト教をあげていたわけではないが、これによってそれまでの非合法な宗教ではなく、国家公認のもとで信仰が出来るようになった。ところが東の正帝リキニウスはやがてキリスト教弾圧にもどったので、帝国の西半分でしか認められないこととなった。そこでコンスタンティヌスはリキニウスと対決し、323年クリソポリスの戦いでそれを破り、後にリキニウスを処刑した。これによって帝国は統一され、キリスト教は全ローマで公認されるとともに、帝国が保護する宗教と位置づけられるようになった。 |
| D キリスト教の国教化 | 392年、ローマ帝国末期の皇帝テオドシウス帝はキリスト教以外の異教の祭礼と供犠を法的に禁止した。この勅令によって、キリスト教はローマの唯一の宗教、つまり国教とされたのである。それまでの伝統的なローマの神々や、ミトラ教の太陽神信仰などは禁止されることとなった。そして393年にゼウスを主神とするオリンポス十二神の祭礼が行なわれると、神殿の財産を没収して異教禁圧への断固とした姿勢を示した。これに伴いギリシアの古代オリンピア競技会も終わりを告げた。 |
| a ニケーア公会議 | 325年にローマ帝国の皇帝コンスタンティヌス帝が主催して小アジアのニケーアで開催されたキリスト教の宗教会議。イエスの神性を否定するアリウス派を異端と断定し、アタナシウス派を正統と認定した。その前年の324年、コンスタンティヌス帝は自らキリスト教徒であることを宣言、翌325年ニケーア(ニカイア。小アジアのニコメディアの近く。)に約300人の司教を集め、コンスタンティヌス帝自ら黄金の椅子に座り議長を努めた。公会議とは、宗教会議、司教会議ともいい、キリスト教教会の全体意志を決定する重要会議で、これから何度か開催される。会議は当時キリスト教内部に起こったアリウス派の考えを認めるかどうかがテーマであった。コンスタンティヌス帝としてはキリスト教を公認した以上、その教義は一本化していなければならず、司教間の対立は皇帝として仲裁しなければならないと考えていた。会議はアリウス派に反対するアタナシウス派との間で2ヶ月間にわたる議論が展開され、その結果、中間派も含めてアタナシウス派が大勢を占め(300人の司教のうち反対は5人だった)、三位一体説をとるアタナシウス派が正統、アリウス派は異端とされ、ローマ領からの追放が決定された。
Epi. コンスタンティヌス帝の宗教政策の評価 ニケーア公会議でアタナシウス派が正統とされたが、それが確定するまではなお曲折が続いた。会議の後、コンスタンティヌス帝がアリウス派に対して寛容に転じ、両派の抗争は再燃したのだ。アタナシウスの項でも触れるように、彼はその後、帝と厳しく対立するようになる。実は定見がなかったコンスタンティヌス帝の宗教政策に対し、ギボンはこう評価している。「帝の教会政策はどうみても軽率、そして薄弱という非難を免れえぬものと思う。だが、神学論議の戦略について当然不慣れな君主が、異端派の謙虚で尤もらしい教説など聞かされれば、どうせ彼等の感情を完全に理解できるはずはないし、欺かれる可能性は十分ありうるのだ。が、ともかくも帝は一方ではアリウスを庇護し、アタナシウスを迫害しながら、しかも他方では依然といしてニカエア公会議をもってキリスト教信仰の防砦、そしてまた帝治下の大いなる誇りと自負していたのだった。」<ギボン『ローマ帝国衰亡史』3 ちくま学芸文庫
p.328> |
| b アタナシウス派
| アレクサンドリアの司教アタナシウスは、「哲学的、論理的であろうとなかろうと、キリストは本当の神性を持ち、まさに神自身と全く同質である」と主張した。論理的ではないけれども、これはキリスト教の伝統的なキリスト観であり、多くの素朴なキリスト教徒たちは、自分たちの救いを神なるキリストに託していたのであった。ニケーア公会議で正統とされ、さらに神とイエスを一体と見るこの考えに、聖霊にも神性を認める考えが結びついて、後に三位一体説が出来上がる。
Epi. その後のアタナシウス 実はニケーア公会議のとき、アタナシウスはわずか30歳ぐらいで、特に重要な人物ではなかった。会議の後にアレクサンドリアで司教となった。ところがローマはその後、アリウス派が勢いを盛り返し、皇帝も妥協に傾いた。それを知ったアタナシウスは、正統信条の擁護のため敢然と「世界を敵として」戦闘を開始した。以来七十七歳の生涯に五度も追放をうけ、帝国の東西に流浪した。エジプトの荒野の庵や、アレクサンドリアの民家に潜伏し、抵抗を続け、ニケーア公会議の決議をよりどころに、次第に同志を増やし、国家の教会に対する干渉に反対した。ようやくその死後の381年に召集された第一コンスタンティノープル公会議でアタナシウスの三位一体説が正統信条として確定した。後にカトリック教会の信条は「アタナシウス信条」と言われるようになった。<高橋秀ほか『ギリシア・ローマの盛衰』1993 講談社学術文庫 p.337 および ギボン『ローマ帝国衰亡史』3の第21章 ちくま学芸文庫p.334~ に詳しい> |
| c 三位一体説
| ニケーア公会議で、アタナシウスの、子なる神としてのイエスの神性を認める説を正統とすることで落着したが、ついで聖霊をどう考えるかという新しい間題が加わった。キリストが地上を去った後、罪や死や律法から人類を救い、信者に信仰と心の平和を写えるのは、聖霊という形で信者の心に宿るキリストであると考えられた。しかし、聖霊に神性を認めれば、論埋的には多神教となってしまう。会議後もアリウス派の勢いが盛り返し、一時アタナシウスの説は逆境に経ち、対立が続いた。ようやくテオドシウス帝によって381年に召集された第一コンスタンティノープル公会議で、聖霊の神性は認められ、神は父と子と聖霊なる三つの位格(ペルソナ)を持つ、すなわち、父なる神と子なるイエスと聖霊とは各々完全に神である、が、三つの神があるのではなく、存在するのは一つの実体(スブスタンティア)、一つの神である、とされた。これが三位一体説であり、教会(その後分離するローマ教会も東方教会も)の現在に至る基本的な正統の教理とされる。次いで三位一体説を否定しキリストの人性を認めるネストリウス派との間で論争が生じたが、431年のエフェソス公会議でそれを異端と断じ、さらにその流れをくむ単性説に対しては451年のカルケドン公会議で異端として退け、三位一体説が正統の教理として確定した。
三位一体説のパラドックス 「ニケーアの公会議で問題とされたのは、父なる神に対するイェスの人性、神性をめぐる議論であった。これは、子なる神としてのイェスの神性を認めることでいちおう落着したが、聖霊をどう考えるかという新しい間題が加わってまたまた困難な事態が起こってきた。神から遣わされて自らも神であるキリストが地上を去った後、罪や死や律法から人類を救い、信者に信仰と心の平和を写えるのは、聖霊という形で信者の心に宿るキリストであると考えられた。だからはしめからパウロなどは、聖霊はキリストと有機的に結ばれていると考えていたのである。それでは聖霊も神性を待つといえるのだろうか。そういえるとすれば、キリスト教は論埋的には多神教となってしまう。マケドニア学派の神学者たちが、キリストの神性は認めながら聖霊の神性を否定したのは、一神教であることを守ろうとする精一杯の論理的抵抗であったと考えることができる。この紛糾を最終的に解決したのが、テオドシウス帝(在位379~395)によって381年に召集された第一コンスタンティノープル公会議であった。この会議によって、聖霊の神性は認められ、神は自らを同時に、父と子と聖霊なる三つの位格(ペルソナ)の中に示す一つの神と宣言された。すなわち、父と子と聖霊は各々完全に神である。が、三つの神があるのではなく、存在寸るのは一つの実体(スブスタンティア)、一つの神であることが決定されたのである。x=3xという方程式は、x=0の場合を除き成立しない。けれども、xの性格が神秘性であり、信仰によって理解されるために、信者の心には素直に受け人れられ、豊かな恵みを約束するものとして定着したのである。これが三位一体論のパラドックスである。」<半田元夫『キリスト教史Ⅰ』山川出版社 1977 p.199> |
| d アリウス派
| アリウスもアレクサンドリア教会の長老であった。彼は、神の本性はいかなる分割もありえないものであるから、キリストは神から放射されたもの、したがって神に従属するものでなければならない。キリストの本性は、神聖ではあっても、神性ではありえない、その本性は神の本性とは異質のものである、と主張した。つまり、平たく言うと、イエスはやっぱり人だった、ということ。前325年のニケーア公会議で異端とされたためローマ領から追放され、主として北方のゲルマン民族に布教されていく。そのわかりやすい教義は、ゲルマン人の土俗的な信仰と合体して独特なキリスト教となっていく。 |
| e 正統
| キリスト教がローマ帝国で公認されてから、教義の統一が必要とされ、ニケーア公会議に始まる公会議で異端を排除しながら形成されてきた、キリスト教の正しく公認された教理であるアタナシウス派の三位一体説を言う。オーソドクス(orthdox)。公認されない教義は異端とされたが、正統が正統であり続けるには、常に異端を創り出さなければならなかったという傾向がある。 |
| f 異端
| キリスト教において、公認された教である正統に対し、間違えた教義、有害な教義とされ、否定されてた教義を奉じる教派。ニケーア公会議で異端(heresy)とされたアリウス派の他にも、グノーシス派、ドナートゥス派、ネストリウス派、単性説、中世ヨーロッパでのワルド派(アルビジョア派)、など多数ある。異端とされると布教は認められず、弾圧された。主としてイエスは神であるか、人であるか、あるいはその両方であるのか、という論争で、イエスの人性を主張するものが異端とされることが多かった。 |
| g 神と神の子キリストと聖霊
| |
| h ユリアヌス帝
| 373年のコンスタンティヌス大帝の死後、帝位をめぐる争いがまた激しくなり一族の殺し合いが展開されたが、大帝の甥の子であったユリアヌスは生き残り、唯一血を引くものとして副帝となった。ゲルマン人、ペルシアとの戦闘で軍の支持を受け、361年皇帝となる。ユリアヌス帝は、コンスタンティヌス帝の統治を否定するため、そのキリスト教公認も改め、自らローマの神々への信仰に復帰し、キリスト教否認に転じた。キリスト教を否認したことで有名で後に「背教者」と言われる。わずか2年の在位期間でササン朝ペルシアとの戦闘で傷を負い、32歳で死去した。 |
| E 教義の確立
| |
| 教父
| 古代キリスト教教会で、正統的な教理(神学)を説き、人々を教化する清貧な生活を送る宗教上の指導者。コンスタンティヌス帝時代のエウセビオスはその一人であり、古代最大の教父が西ローマ末期のアウグスティヌスとされる。 |
| a アウグスティヌス
| 古代キリスト教世界の代表的な教父。アウグスティヌスは西ローマ帝国の属州、北アフリカのヌミディアの出身でカルタゴで学んだ。父は異教徒、母は熱心なキリスト教徒であったが、青年時代の彼は、一時若い奴隷の女性と結婚したり、マニ教の教義に惹かれたりして信仰に悩む。そのあたりの自伝が『告白録』である。384年、ミラノに行きアンブロシウスの説教を聞き、また新プラトン主義の哲学に触れて思索を深め、キリスト教に回心した。アフリカにもどり、ピッポの司教として、マニ教などの異教やキリスト教の異端との論争を通じて、次第にカトリック教会としてのキリスト教理論をうち立てる。430年、ヴァンダル族がカルタゴに侵入、ピッポを包囲する中で病死した。彼の思想は、ローマ帝国の国教となったキリスト教を、国家に奉仕する宗教としてではなく、この世に「神の国」を出現させるものとして教会を位置づけ、教会の恩寵を説き、その典礼を定めたもので、世俗の国家に超越する「教会」(ローマ教皇を中心とした聖職者の組織)という中世ヨーロッパのもっとも根幹となる思想の原型を造ったと言える。主著は『神の国』『告白録』など多数。 |
| 『神の国』 | |
| b エフェソス公会議
| 431年、東ローマ帝国皇帝テオドシウス2世が開催した公会議。エフェソスは小アジアのエーゲ海岸。議題はネストリウス派のイエス人性説を認めるかどうかであったが、それは異端として退けられ、正統である三位一体説が強化されて終わった。 |
| c ネストリウス派
| コンスタンティノープルの総大司教のネストリウスは、マリアを「神の母」と呼ばず「キリストの母」と呼ぶことによって、キリストの人性を明確に示そうとした。彼は人性と神性は区別されるべきであり、キリストの人性は受肉によって神性と融合し、単一の神性を有した、と主張した(単性説と言われる)。これに対するアレクサンドリアの司教キュリロスは、キリストは人性と神性の両性をそなえていると反論し、激しい議論が続いた。431年のエフェソス公会議ではネストリウスの主張は退けられ、異端とされた。その後、ネストリウス派のキリスト教は、東方に広がり、イランを中心に独自の発展を遂げ、ササン朝ペルシアを通じ中国に伝わり景教と言われた。唐の都長安には景教の寺院が建てられ、大秦景教流行中国碑も建てられた。宋代以降は中国の景教は衰えたが、ネストリウス派は中央アジアを中心に存続し、現在もイラクや南インドにわずかだが残存している。 |
| d 景教
| → 第3章 2節 唐代の制度と文化 景教 |
| e カルケドン公会議 | 451年、東ローマ皇帝マルキアヌスが主催した公会議。カルケドンはコンスタンティノープルの対岸のアジア側にある。この公会議では単性説が問題とされ、三位一体説をとるローマ教皇レオ1世の要求によって、単性説は異端とされた。これによって、ローマ教会の三位一体説が、キリスト教の唯一の正統な教理として確定した。 |
| f 単性説 | キリストの人性は、この世において神性と融合し(または人性は仮性で、神性のみを認めると説明する)、単一の神性をそなえた存在となったと考えるキリスト教の一教理で、キリストを人性と神性の両性を持った存在とする両性説(その発展したものが三位一体説)と対立した。ネストリウス派の考えに始まり、根強い支持があったが、451年のカルケドン公会議で異端とされた。その後、エジプトのコプト教会や、エチオピア(アクスム王国)、シリア(ヤコブ派)、アルメニアなどにひろがり、現在でも残存している。 |
| コプト教会 | コプト教会はエジプトのキリスト教徒のこと。コプトとはエジプト人を指すギリシア語(アイギュプトス)のアラビア語なまりである。紀元2世紀ごろからローマ支配下のエジプトで広がったキリスト単性説を信仰する人々である。東ローマ帝国の時代になり、451年のカルケドン公会議が開催され、単性説は異端であると退けられたが、エジプトでは信仰が守られた。またエチオピアに成立したアクスム王国でもコプト教会が受容された。641年、エジプトがイスラーム勢力に征服されると、多くはイスラームに改宗したが、現在のエジプトの人口の10%程度がコプト派キリスト教徒として存続し、カイロにはその総本山がある。近代ではイギリスの植民地支配に協力することが多かったので、イスラーム過激派との間で衝突事件も起きている。
Epi. 豚インフルエンザとコプト教徒 2009年5月、新型インフルエンザが世界的に猛威を振るい、豚から人への感染が騒がれたとき、エジプト政府は国内で飼育されている豚約35万頭の豚の全頭処分に着手した。ところが、それに対して、養豚業を手がけてきたキリスト教系コプト教徒が強く反発し、カイロなどで抗議行動が激しくなった。豚を「不浄な動物」とみなす多数派のイスラーム教徒との宗教上の軋轢が高まったという。カイロのある地区では約3万5千人のコプト教徒が、ごみ処理と養豚で生計を立てており、6万頭の豚が飼育されているが、5月3日にはこの地区でも機動隊に守られた保健当局が豚を処分しようとして騒ぎとなった。まだ患者が出ていないのに、政府が予防措置として豚の処分を開始したのは、世論の後押しがあるからで、イスラーム教徒の多数派は「イスラーム国家のエジプトで豚を飼うべきでない」と政府を支持しているという。<朝日新聞 2009.5.10 朝刊> |
 |
| ク.ローマの生活と文化 |
| 1.ローマ文化 | ギリシア文化を継承したヘレニズム文化に続く、紀元前1世紀のローマの地中海制覇から紀元後5世紀の西ローマ帝国滅亡ごろまでのローマを中心とした文化。共和政の都市国家ローマに始まり、強いギリシア文化の影響の下で成立したので、自由な市民による人間性あふれる文化であり、「古典古代」としてルネサンス以後のヨーロッパの憧憬の対象であった。彫刻や建築などの美術ではギリシア美術を模倣することが多かった(かえってそのため、ギリシア彫刻はほとんど現存しないがローマ時代の模造品を通じてその姿が伝えられている)。また哲学・思想の面ではギリシアを越えることはなかったと言われるが、ラテン語による文芸・歴史書、ローマ法にまとめられた法律の発展、実用的な文化などは、ギリシア文化を凌駕するものがあった。しかし、ローマ文化は紀元後4世紀にキリスト教を受容したことによって、大きく転換する。ローマは古代ローマ帝国の都としては衰退し、後にローマ教皇の居所として復興する。ギリシア文化とともにローマ文化が脚光を浴びるのは、長い中世キリスト教時代を経た、14世紀以降のルネサンスにおいてであった。 |
| a ギリシア文化の影響
| ローマの詩人ホラティウスには「征服されたギリシアが野蛮な征服者をとりこにした」という有名な言葉がある。この言葉のように、ローマはギリシアを征服し、属州として支配したが、文化においてはギリシアを模倣する面が多く、独創性はないとされる。たしかに芸術学問の分野ではギリシアを越えることはできなかったが、しかしローマ文化は「ローマ法」や土木建築技術にみられるような実用性ではローマを上回っているとも言える。彫刻などは実際のギリシア時代のもはほとんど現存せず、ローマ時代に模写されたものが残っているケースが多い。 |
| b 実用的な文化
| |
| c 古典古代
| → 古典古代 |
| 2.実用的文化 | |
| 建築・土木 | ローマの実用的な文化の一つに、建築と土木が優れていたことが挙げられる。建築にはローマのコロッセウムやパンテオン、凱旋門などがあり、土木にはアッピア街道などの道路と、フランスのガールなどに残る水道橋が挙げられる。これらの建築と土木を支えた技術は、コンクリートとアーチの二つだと言われている。コンクリートはイタリアの火山性の土と石灰を混ぜてセメントをつくり、それに石や煉瓦のクズを加えて水で練り、表層に煉瓦を張りつめ、さらに一番表に大理石の薄板を貼り付けて装飾にするという技法。アーチは重力を分散させて大きな開口部をつくる技術で、巨大建造物にはよく用いられている。 |
| フォルム | |
| カラカラ浴場 | |
| 凱旋門 | |
| コロッセウム | コロッセウム(円形競技場)跡はローマのものが有名であるが、同じようなものが全ローマ世界のうちに全部で二五〇もあったことがわかっている。ここで剣闘士奴隷の競技、キリスト教徒の処刑などが「見世物」として興行された。もっとも有名なローマのコロッセウムは、75年にウェスパシアヌス帝がネロの宮廷の跡地に建造を命じ、その子のティトウス帝のとき、79年に完成した。高さ48.5m、長径188m、短径156m、4万から4万5千の観客席があり、さらに5千人分の立ち見席が最上階にあった。観客席はアリーナに一番近い大理石の座席が元老院議員、その上が騎士階級席、その上が商人や職人などの上級市民席、最上階が一般席であった(今でも座席に「学校の先生のため」とか「来賓のため」などと記されているのを見ることができる)。アリーナは板張りの上に砂を敷きつめ、その下に猛獣小屋が作られていて、巧みな構造でアリーナに出るようになっていた。コロッセウムの出し物は、剣闘士(グラディエーター)同士の試合や、キリスト教徒や罪人を猛獣に襲わせる見せ物であった。<S&D.ペリング『復元透かし図・世界の遺跡』1994 三省堂 p.70~>
※なお、コロッセウムは4層からなるが、その第1層の柱はギリシア建築のドーリア式、第2層はイオニア式、第3層がコリント式でつくられている。
Epi. コロッセウムでの剣闘士試合 「この巨大な建築物は、古来、ローマの象徴とされており、「コロッセウムが立つ限り、ローマも立つであろう。コロッセウムが倒れるとき、ローマも倒れるであろう。ローマが倒れるとき、世界も倒れるであろう。」とうたわれてきた。その観客席に五万の観衆をのんだ、この闘技場で、いったいなにがおこなわれていたのであろうか。紀元80年、コロッセウムの落成式がおこなわれたとき、時のローマ皇帝ティトウスは百日間にわたって各種の競技をおこなった。剣闘士奴隷どうしのちなまぐさい競技もあったし、たった一日のあいだに人間と猛獣の格闘のなかで、あらゆる種類の5千頭もの猛獣が殺されるということもあった。この闘技場を水でみたして人工の湖をつくり、三千人もの剣闘士を動員する模擬海戦もおこなわれた。ローマ帝国の各地からやってきた大観衆を前にして、このような人間と猛獣の数知れない死によって血ぬられたコロッセウムは、その後、404年の剣闘士試合の中止、523年の猛獣演技の廃止にいたるまで、毎年のように残酷な死のゲームを、熱狂した観客に提供し続ける場となったのであった。」<土井正興『スパルタクスの蜂起』1973(新版は1988)青木書店 p.13-14> |
| パンテオン | |
| アッピア街道 | アッピア街道 |
| ガール橋 | フランスに残るローマ時代の全長270mの3層のアーチ式水道・道路。 |
| b ローマ法
| 十二表法にはじまる古代ローマの法体系。初めはローマ市民権を持つもののみに適用される市民法であった。共和制時代、帝政時代を通じて整備され、2世紀には法学者ガイウスなどが現れて体系化された。(もっとも、帝政時代は五賢帝の全盛期にはほとんど立法されることがなく、軍人皇帝以降の衰退期に多くなると言う指摘もある。)3世紀には市民権が全ローマ帝国内の自由民に拡大されたため、ローマ法は万民法ととらえられるようになった。東ローマ皇帝ユスティニアヌス大帝は歴代の皇帝の立法を集大成して『ローマ法大全』を編纂させた。ローマ法は中世でもゲルマン諸国、神聖ローマ帝国に受け継がれ、その後のヨーロッパ各国の法律の手本とされ、現在でも法律の原典として尊重されている。 |
| c 万民法
| → 万民法 |
| d 『ローマ法大全』
| → 第6章 2節 ビザンツ帝国 ユスティニアヌス帝 『ローマ法大全』の編纂 |
| e ユリウス暦
| 古代ローマでは前7世紀から太陰暦をもとに、1ヶ月を29日、1年を12ヶ月、1年が355日の暦を使っていたが、地球の公転周期(365.242……日)とのずれが生じてきたため、前400年ごろから隔年に22~25日の閏月を入れて調整するようになった。その運用は神官にまかされていたが、前1世紀ごろには実際の季節と暦との間に約2ヶ月のずれが生じた。そこでカエサルは、前46年、エジプトのアレキサンドリアで行われていた太陽暦を採用し、365日と1/4を1回帰年とし4年ごとに閏年をおく、いわゆる「ユリウス暦」を制定した。実際の季節とほぼ一致するこの方式はローマ世界で広く用いられ、1582年の「グレゴリウス暦」の制定まで用いられた。 → 元の授時暦 |
| グレゴリウス暦
| 1582年、ローマ教皇グレゴリウス13世の時に制定された、現在の世界でもっとも普及している太陽暦。ローマ時代のユリウス暦を改訂した太陽暦を基本としており、現在の暦法に継承されている。ユリウス暦は365日と4分の1とし、4年に一度閏年を設ける暦法であったが、わずかの差であった実際の太陽年(回帰年)との差が累積して、春分の日がカエサルの時から13日早まってしまい、春分の日を基準に復活祭の日を決める教会にとって困ったことになった。そこでローマ教皇グレゴリウス13世が、ユリウス暦を改定、400年間に3度、閏年を省略することで修正した。グレゴリウス13世は、宗教改革を受けてカトリック側の対抗宗教改革を進めた改革教皇の一人で、サンバルテルミの大虐殺のとき、新教徒の殺害を喜んで、ミサをあげたことでも知られている。
補足 「ユリウス暦法では4年のサイクルについて、一年の平均値は365.25日となるが、これは正しい値に比べて0.0078日大きすぎる。真の一年が過ぎ去っても、暦の一年がはじまるのが毎年平均して0.0078日おくれるということである。そこでシーザー時代には春分は3月23日ごろであったのに、16世紀には、この遅れがつもって、3月11日ごろになってしまった。春分はキリスト教国では最大の祝日の復活祭の日取りの基礎になるものであるから、その月日が移動しないようにしたいということと、3月20日ころにしたいということから、教皇グレゴリウス13世は、「1582年10月4日の翌日を10月15日と呼ぶこと、キリスト降誕(紀元)年数が、4の倍数の年を閏年とする。ただし紀元年数が百の倍数(当然4の倍数)である場合には、4百の倍数でない限り、平年とする。」と定めた。これがいわゆるグレゴリオ改暦で、西洋では当時これを新式暦と呼び、これに対して4年ごとに必ず閏年を置くユリウス暦を旧式暦と呼んだ。・・・」<吉野秀雄『年・月・日の天文学』1973 中央公論社・自然選書 p.147-148>
グレゴリウス暦の採用 グレゴリウス暦はヨーロッパのカトリック国では定着したが、他の地域ではすぐに用いられたわけではなかった。まず新教国であったイギリスとその殖民地アメリカはグレゴリウス暦をかたくなに拒んだ。彼らがこの変化を受け入れたのは1751年であった。また東方教会(ギリシア正教会)では、ローマ=カトリックの規則は無視し、イースターを決めるのに依然としてユリウス暦を用いた。またカトリック国のフランスでも、フランス革命が起きると反キリスト教の立場からグレゴリウス暦を廃止して、革命暦を採用した。しかしそれは定着せず、ナポレオンが権力を握るとグレゴリオ暦に戻し、カトリックとの関係も修復された。なお、中世以来、ユリウス暦を使用していたロシアでも、ロシア革命のときに太陽暦に基づく革命暦を制定したが、やはり定着せず、グレゴリウス暦に切り替えた。中国は辛亥革命で1912年に改訂、日本は明治5年の1872年からグレゴリウス暦に切り替えた。現在はイスラーム圏ではイスラーム暦を用いるのが建て前であるが不便な点が多いため、西暦、つまりグレゴリウス暦と併用となっている。<ダニエル・ブアスティン『どうして一週間は七日なのか』大発見1 集英社文庫 などによる> |
| f ローマ字
| |
| 3.文学・学問の分野 | |
| ラテン文学
| 古代ローマにおける、ラテン語による文学作品。ヴェルギリウス、ホラティウス、オヴィディウス、などが代表的な作者であり、アウグストゥス時代にその全盛期となった。ラテン文学は、ラテン語とともに教養に不可欠なものと考えられ、長くヨーロッパの古典として続く。 |
| a ヴェルギリウス
| アウグストゥス時代の詩人。英語名ヴァージル。アウグストゥスのローマ帝国創業をたたえ、叙事詩『アエネイス』を著す。前19年、アテナイにいる皇帝のもとに急ぐ旅路で日射病にかかり、草稿を焼き払うように遺言して死ぬ。しかしアウグストゥスは遺言の実行を禁じ、現在アエネイスは草稿として読むことが出来る。また田園詩人としても知られ、後のダンテなどにも影響を与えた。ダンテは、その『神曲』で地獄・煉獄・天上界の案内役として登場させている。 |
| 『アエネイス』
| 前1世紀の国民的詩人ヴェルギリウスが書いた叙事詩でローマの建国神話を伝える作品。アエネアスとも表記する。ミケーネとの戦いに敗れ、灰燼に帰したトロイアであったが、生き残った王族の血を引く部将アエネイスは、祖国再建の使命を帯で旅立つ。長い間地中海世界を放浪し、様々な苦労のすえ、イタリア半島にたどり着き、北上してラティウムというラテン人の土地にたどり着いた。そこでトロイア人とラテン人は激しい戦いの末に和平し、そこでアエネイスはラテン人の王の娘ラウィニアを娶り新しい都(ラウィニウム)を建設した。ここまでが『アエネイス』の伝えるもので、アエネイスの子孫の双子のロムルスとレムス兄弟のうちのロムルスがローマを建国するという神話につながる。 |
| ホラティウス
| アウグストゥス時代の詩人。ローマ人の普遍的な人間像を日常的な会話からひろってきて描いた『風刺詩集』、パトロンだったマエケネスにあてた『書簡体詩』などを残した。「征服されたギリシアが、野蛮な征服者(ローマ)をとりこにした」という有名なことばはホラティウスの詩の一節。ローマ文化が、ギリシア文化の模倣にすぎないことをローマ人として認めた言葉である。 |
| オヴィディウス
| アウグストゥス時代の詩人。ローマ社会の恋や風雅を歌い上げ『変身』を書く。彼自身も自由な恋愛に生き、アウグストゥスの孫娘ユリアとも関係があったらしく、黒海沿岸に流刑となった。 |
| b ガリア戦記
| → 第6章 1節 ゲルマン民族の大移動 ガリア戦記 参照 |
| c キケロ
| 前1世紀のローマ「内乱の1世紀」時代の政治家でかつ雄弁家、文章家、哲学者。地方の騎士の家柄に生まれ、ローマに遊学、修辞学、哲学、法律を学び、弁護士として頭角を現す。アテネ、小アジアに行き、ギリシア哲学を学びラテン語に訳す。前63年執政官となり、ローマで不平貴族や下層民を煽動した閥族派のカティリナの陰謀事件が起こった時、元老院で再三にわたりカティリナを告発し、ローマの危機を救ったとされる。カエサルとポンペイウスの抗争が始まるとポンペイウスを支持し、カエサルと対立して一時政界を引退。アントニウスが台頭すると共和政維持の立場からそれを批判し、かえってアントニウスの刺客によって殺されてしまう。政治的には波乱に富んだ一生であったが、その間残した著作『国家論』『義務論』などはラテン語の散文として高い評価を得ている。 |
| d リヴィウス
| ローマ建国からアウグストゥス時代まで142巻の大歴史書『歴史』を著した。そのうち現在は40巻ほどが現存する。彼は共和政的貴族政治を理想とし、カエサルの独裁以降に対しては批判的であったが、アウグストゥスは彼を援助し、全巻を完成させた。 |
| e タキトゥス
| ローマ帝政時代の歴史家、法律家、政治家。同時代のローマの歴史を批判的に述べた『歴史』や『年代記』、ゲルマン人の社会や政治のあり方を述べて、暗にローマの現状を批判した『ゲルマーニア』などが名文で知られる。 |
| ポリビオス
| ポリュビオスとも表記。ギリシア人。前168年、ピドナの戦い(ローマがマケドニアを滅ぼしたマケドニア戦争の最後の戦い)でマケドニア・ギリシア軍がローマに敗れた後、人質の一人としてローマに送られた。小スキピオの家庭教師となり、第3次ポエニ戦争に従軍。ローマが強大な国家になった理由を知ろうと、ローマ史を研究し、40巻の大著『歴史』をギリシア語で書いた。その書の中で政体循環史観・混合政体論を展開している。 |
| 政体循環史観
| 政治形態は、君主政→暴君政→貴族政→寡頭政→民主政→衆愚政→君主政、と循環するというローマ時代の歴史家ポリビオスの歴史観。ポリビオスは、前2世紀のギリシア人で、ローマに捕虜として連行され、小スキピオの知遇を得て第3次ポエニ戦争に従軍、ローマの隆盛を目の当たりにし、後に『ローマ史』を著し、政体循環史観の考えを述べるとともに、ローマの強さを君主政と貴族政と民主政が混合しているところにあるという混合政体論も展開した。 |
| f プルタルコス(プルターク)
| ローマ帝政五賢帝時代のギリシア人。カイロネイアの生まれで、アテネで学び、ローマに行ってトラヤヌス帝の知遇を得る。『英雄伝(対比列伝)』でギリシアとローマの歴史上の人物を比較して論じた。プルタルコスについての次の寸評が参考になろう。
「プルタルコス(紀元50年ごろ~120年ごろ)は「最後のギリシア人」と評されるが、その有名な『対比列伝』(英雄伝)、とくに人間味のあふれる『随想録(モラリア)』にみられる思想は、古代市民の考え方の集大成の感がある。プラトンに心酔し、他の哲学諸派にも通じ、自然科学もいちおう心得た知識人であったが、その彼がもっとも嘆いたのはデルフォイの託宣の衰退であった。彼はその復興をくわだて、託宣についていくつもの随筆を書いたほか、みずからデルフォイの最高神官になっている。彼にとり、アポロンの言葉はあくまで真理であった。」<村川堅太郎ほか『ギリシア・ローマの盛衰』1997 講談社学術文庫 p.185> |
| ストラボン | ローマ時代の紀元前後のギリシア人で、歴史家・地理学者。17巻の『地理書』は現存し、地中海世界とその周辺の厖大な情報を今に伝えている。 |
| セネカ | スペインのコルドバ生まれ。若くしてストア派の哲人の名声を得ていた。カリグラ帝、クラウディウス帝の時には罪を得て8年をコルシカ島で過ごした。アグリッピーナはセネカを息子ネロの家庭教師にした。ネロが皇帝になるとセネカはその政治の実権を握り、5年間はネロの善政をささえた。しかしネロ帝の暴政が始まるとそれを制御することが出来ず、辞任し隠棲する。狂気を増したネロは、セネカに陰謀の罪を着せ、セネカは自ら毒を仰いで死んだ。彼は多くの随筆を残しており、ローマ帝政期の代表的な文章家、哲学者として知られている。 |
| エピクテトス | ローマ帝政時代のストア派の哲学者。小アジアのフリギア出身の奴隷であったが解放され、文章家としてネロ帝などに仕える。外的なものに左右されず、自己を確立することによって自由を得ることを説いた。その思想は、五賢帝の一人、哲人皇帝といわれるマルクス=アウレリウス=アントニヌス帝にも影響を与えた。 |
| 新プラトン主義 | 古代ローマ末期のプロティノスにはじまる哲学。プロティノスは3世紀にエジプトのアレクサンドリアで学び、ギリシア哲学を研究した。そこでプラトンの言う「一者」や「イデア」という究極の真理は、人間が認識出来るものではなく、そこから流出するものを観照する(直感する)のみであると説く。感覚器官や言葉ではなく、沈黙のうちに絶対の真理と一体化しようと説く、神秘主義をとった。新プラトン派はキリスト教を否定したが、キリスト教徒の中ではアウグスティヌスらの教父が新プラトン主義を取り入れ、教父哲学を体系づけた。 出題 2004明大政経 |
| ミトラ教 | → 第1章 1節 ミトラ教 |
| マニ教 | → 第1章 1節 マニ教 |
| エウセビオス | 325年、最初のキリスト教史として『教会史』を著した司教。ニケーア宗教会議ではコンスタンティヌス帝に陪席し、その決議文を起草し、公認後のキリスト教の体系化の中心となった。彼はパレスチナのカイサリアで司教として活動し、迫害が終わりキリスト教が公認されたことを「神のみわざの証明」とし、信仰が正しかったことを確信して、イエスの出現から教会公認までのキリスト教の歴史を『教会史』としてまとめた。公認に踏み切ったコンスタンティヌス帝を讃え、『年代記』を著し、皇帝の位は「神の恩寵」であるとする「神寵帝理念」を示して国家教会主義への端緒を開いた。皇帝の専制政治を支える役割をはたしたといえる。 |
| g プリニウス
| ローマの博物学者、軍人、政治家でもあった。大プリニウスという。『博物誌』はその代表作。彼は79年8月24日のヴェスヴィオス火山の大噴火でポンペイが火山灰で埋没した際、艦隊司令官として救援に向かい、その犠牲となった。 |
| h プトレマイオス | 2世紀頃、アレキサンドリアで活躍した、天文学者・数学者・地理学者。ギリシア以来の天文学を集大成し、地球を中心とした太陽・月・惑星の運行を計算して体系づけ、その宇宙観は「天動説」としてその後ビザンツ世界、西ヨーロッパ世界、イスラーム世界の常識となり、1500年にわたって不動の定説となった。また地理学でははじめて地球上を経度緯度にわけて世界地図を作製した。その内容には誤りも多いが、科学的な最初の世界地図と言うことが出来る。プトレマイオスの天文学によって、ヘレニズム時代のアリスタルコスの地動説は否定され、忘れ去れてしまった。その天動説は、コペルニクス、ガリレイらが疑問を呈することによって誤りとされたが、プトレマイオス自身は神秘的な神中心の宇宙観を説いたのではなく、あくまで彼自身の観測と計算に基づく結論に従ったもので、前代のアリスタルコスの地動説よりも合理的な説明をすることに成功したために定説化したものであった。 |
| ガレノス | ローマ帝国時代の代表的医学者。ギリシアのペルガモン生まれで、アレクサンドリアで医学を学び、ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=アントニヌスの侍医となった。解剖学を創始したと言われ、ギリシア時代のヒポクラテスとともに、彼のギリシア語の医学書は後にアラビア語に翻訳され、アラビア医学に取り入れられる。そして中世ヨーロッパでは忘れ去られていたが、ルネサンス期にアラビア医学がヨーロッパに伝えられて、ヨーロッパでも知られるようになった。 |
 |