| 用語データベース 12_1 |
  |
| 第12章 欧米における近代国民国家の発展 |
| 1.ウィーン体制 |
| ア.ウィーン会議 |
| A ウィーン会議
| 1814年9月から1815年6月まで、オーストリアの首都ウィーンで開催された、ナポレオン戦争後のヨーロッパ諸国の秩序回復を図るための国際会議。19世紀の三大国際会議=ウィーン会議、パリ会議(1856年、クリミア戦争後の講和会議)、ベルリン会議(1878年、東方問題での国際会議)の一つ。
ウィーン会議の主な参加者:ロシア皇帝アレクサンドル1世、プロイセン王フリードリヒ=ヴィルヘルム3世、イギリス代表カスルレー、ウェリントン、オーストリア代表メッテルニヒ、プロイセン代表ハルデンベルク、フランスのタレーランらが出席。議長はメッテルニヒが務めた。
フランス革命とナポレオン戦争後のヨーロッパを、それ以前の状態に戻すこと(フランスのタレーランが唱えた正統主義)理念として会議が始まったが、実際には各国とも領土の拡張と有利な条件の獲得を狙って腹を探り合い、なかなか進捗せず、代表たちは舞踏会などでいたずらに時間を浪費したため『会議は踊る、されど進まず』と揶揄された。しかし、ナポレオンのエルバ島脱出の報を受けて、列国は合意の形成を急ぐこととなり、1915年にウィーン議定書の調印にこぎつけた。この会議によって、19世紀前半の保守反動体制であるウィーン体制が作られた。 |
| a 1814年〜15年 | ウィーン会議の開催期間。19世紀の初め、日本は天保の改革の時代。各地に飢饉が広がり、打ちこわしが起こった。滝沢馬琴・『南総里見八犬伝』第1巻刊行。伊能忠敬・『沿海実測全図』完成。杉田玄白ら『蘭学事始』完成。 |
| b ウィーン会議の目的 | ナポレオン戦争後のヨーロッパの戦後処理と、秩序再建。 |
| c メッテルニヒ
| オーストリアの外相、後の首相で、ウィーン体制時代を代表する政治家。ウィーン会議を主催し、保守反動体制の中心人物としてドイツのブルシェンシャフト運動などの自由主義、民族主義運動の弾圧を行い、さらにラテン=アメリカの独立運動ににも介入した。ウィーン体制下のヨーロッパ各国の外交を巧妙に乗り切ってきたが、1848年、ヨーロッパに革命の嵐が吹きまくると、その最大の標的とされ、三月革命の中をかろうじて女装して脱出し、イギリスに亡命した。 → メッテルニヒの失脚 |
| d 正統主義
| 敗戦国フランスの代表タレーランは、他の4国の闇取引を警戒、会議は公法の原則にしたがって開催すべきであるとし、各国の領土は正統な君主のものであると主張、フランス本土の解体を阻止しようとした。 |
| e タレーラン
| フランスの政治家。タレーランは息の長い政治家だった。軍人の家に生まれたが足が悪かったので僧侶となり、1789年の三部会では聖職者の代表のひとりとして参加した。立法議会の時期には外交官してイギリス・アメリカに渡り、1796年には総裁政府の外相となった。1799年、外相を辞任してナポレオンを支持し、ブリュメール18日のクーデタでその権力掌握を助け、その功績でナポレオン政権のもとで再び外相となった。1808年以降はナポレオンの侵略主義に反対して遠ざかる。ナポレオン没落後、ルイ18世の復古王政を実現して首相となり、ウィーン会議ではフランスの代表として正統主義の原則を提唱した。ナポレオンの百日天下の後、一時首相を務めた。ずっと後の1830年の七月革命ではルイ・フィリップの即位に貢献し、駐英大使を勤め、5年後80歳で隠退した。 |
| f 『会議は踊る、されど進まず』
| ウィーン会議の議事が進行しないことを皮肉ったことばで、オーストリアの将軍リーニュ公が言ったという。ザクセン帰属問題、ドイツの組織問題、ワルシャワ大公国処理問題でオーストリア・プロイセン・ロシアが対立、イギリスはロシアの進出を警戒し、各国代表は互いに牽制しあって話し合いは進展せず、舞踏会だけがきらびやかに続けられた。しかし、1815年3月、ナポレオンのエルバ島脱出の知らせをうけ、急きょ、結束することになった。 |
| ナポレオン(エルバ島脱出)
| → エルバ島 |
| B ウィーン体制
| ウィーン会議によって成立した、フランス革命とナポレオン戦争後のヨーロッパを、革命前の絶対王政体制に戻したもので、1815年から1848年の二月革命・三月革命までの期間を言う。その指導的立場にあったのがオーストリアのメッテルニヒであったので、メッテルニヒ体制とも言われる。またその理念とされたが、フランスのタレーランの提唱した正統主義であった。ウィーン体制を補完するものとして神聖同盟、四国同盟(後に五国同盟)が結成された。その本質は端的に言えば、保守反動体制であって、この間、ヨーロッパ諸国の自由主義と国民主義(ナショナリズム)は抑圧された。一方ではこの時期はイギリス資本主義が全盛期を迎えようとしており、イギリスはウィーン体制から身を引いて独自の植民地獲得(1840年アヘン戦争など)を展開しパックス=ブリタニカといわれる植民地帝国を形成する。アメリカもモンロー宣言(1823年)でヨーロッパ諸国とは別個な行き方をとって、アメリカ大陸で膨張していく。
ウィーン体制下ではヨーロッパの君主国間のバランスが、メッテルニヒの巧妙な外交によって維持されていたが、バルカン半島のオスマン帝国領内のギリシア独立運動をめぐって東方問題が起こるとその利害の対立が明らかになっていく。また1830年のフランスの七月革命はブルボン復古王政を倒し、各国の自由主義運動を燃え上がらせてウィーン体制にとっても大きな衝撃となった。ついで1848年にフランスで起こった二月革命がベルリンとウィーンの三月革命を呼び起こし、これによってウィーン体制は終焉を迎えた。 |
| a ウィーン議定書
| 1815年6月9日に調印された、ウィーン議定書の主な内容は次の通り。
(1)正統主義の原則に基づき、フランス・スペイン・ナポリ・ポルトガルなどの旧君主の復位>。それに伴いフランスは1790年当時の国境に戻す。
(2)ロシアはワルシャワ大公国の大部分を併合しポーランド立憲王国とし、ロシア皇帝がポーランド王をかねる。その他、フィンランド・ベッサラビアを獲得。
(3)プロイセンはザクセンの北半分とラインラント、ワルシャワ大公国の一部を獲得。
(4)オーストリアはネーデルラント、ポーランドなどの所領を放棄し、その代償としてヴェネツィア、ロンバルディアなどの北イタリアに領土を獲得。
(5)イギリスはケープ植民地、マルタ島、スリランカ(セイロン島)、イオニア諸島(ギリシア西岸)を獲得。
(6)スイスは永世中立国となる。
(7)ドイツは35邦4自由都市よりなるドイツ連邦を構成し、フランクフルトに連邦議会を置き、オーストリアが議長となる。
(8)スウェーデンはフィンランドをロシアに、ポンメルンをプロイセンに譲り、代わりにデンマークからノルウェーを獲得。
(9)オランダはベルギーを併合。 |
| b ポーランド立憲王国 | ポーランドの地にナポレオンによってつくられたワルシャワ大公国がその没落によって消滅し、その大部分の跡地に1815年のウィーン議定書でポーランド立憲王国が作られた。ウィーン会議の結果生まれた王国なので、会議王国といわれることもある。近隣三国によって分割されて消滅したポーランド国家の称号が復活したが、国王はロシア皇帝が兼ねているので、実質的にはロシア領であった。ロシアのアレクサンドル1世は、ポーランドの伝統の議会の復活を認めたので「立憲王国」とされ、当初は一定の自治を認めていたが、ロシア本国にはない議会の存在を忌まわしく思うようになり、次第に無視し専制政治を押しつけるようになった。反発したポーランド人はたびたび独立運動を起こし、いずれもロシア軍によって抑えつけられたが、ウィーン体制下の焦点の一つとなった。1世紀以上経って、第1次世界大戦の勃発とロシア革命により、1918年にポーランドは共和国として独立する。→ポーランドの反乱、ポーランド独立、ポーランド(第一次世界大戦後) |
| c スリランカ
(植民地化) | スリランカは植民地時代、およびその後もしばらくはセイロンと言われていた。1505年にこの島に到達したポルトガルは、1510年までに支配を固め、香料の産地および東南アジアの香料諸島への中継地として抑えた。ポルトガルの支配が長く続いたが、ついで17世紀中頃からはオランダが進出してきた。オランダと競いながら海上帝国として支配権を広げてきたイギリスは、ナポレオン戦争後の1815年のウィーン会議の結果であるウィーン議定書によってセイロン島を獲得した。それ以後、セイロン島はイギリス植民地として、主として本国向けの紅茶のプランテーション栽培が行われた。イギリス植民地支配がインドと同様に続いたが、ようやく第2次世界大戦後のインドの独立と連動して、1948年にイギリス連邦内の自治国として独立した。はじめセイロンという、イギリス統治時代の呼び名が使われたが、1972年に完全独立に際して国号をスリランカに改称した。現在、多数派民族のシンハリ人(仏教徒)とタミル人(ヒンドゥー教徒)の民族対立が続いている。 → スリランカ(現代) タミル人問題 |
| d ケープ植民地
| → 第10章 2節 ケープ植民地 |
| e ベルギー(の併合) | ウィーン会議では、フランスに隣接するベルギーをフランスの影響から分離させるため、ウィーン議定書でオランダに併合することに決定し、「オランダ連合王国」としてオランダのヴィレム1世を国王とした。しかし、オランダとベルギーは、前者がプロテスタント、後者がカトリックという宗教の違い、またオランダ語が公用語とされたこと、人口ではベルギーが多いのに、議会の議席は同数とされたことなどから、ベルギー独立運動が次第に活発になる。1830年、フランスの七月革命の影響で独立運動が高まり、ベルギーは独立を達成する。 |
| f 北イタリア
| |
| g スイス
| スイスは、中世には神聖ローマ帝国皇帝のハプスブルク家(オーストリア)の支配下にあった。13世紀末から独立運動が始まり、三十年戦争後の1648年のウェストファリア条約で独立が承認された。しかし各州の対立から統一が進まず、フランス革命時にナポレオンの征服を受けた。ウィーン会議では、スイスの安定はヨーロッパ各国の安全にとっても重要な意味があったので、その領土と国家形態について話し合いがもたれ、その合意として、1815年のウィーン議定書で、22州(カントンといわれる自治体)からなる連邦国家として独立することと永世中立国となることと同時に承認された。 → 現代のスイス
スイスが永世中立国となった理由:ウィーン会議において、スイス盟約者会議団(スイスは自らこう名乗っている)はスイスの独立と中立の承認をとりつけるため三人の代表が次のような主張を行った。「スイスの同盟体制を一瞥すれば、もし中立が不確かであったり、政治や戦争の変化にただ放っておかれれば、スイス国民ほどヨーロッパのなかで不幸な国民はいないことをただちに納得させられるであろう。しかし、この際スイスの安寧だけが考えられているわけではない。この中立はドイツ、イタリア、それにフランスの平安にも決定的に大事なのである。これらの国々にとっては、ヨーロッパ内の最近隣国が最も強力な防衛位置であると同時に、最も危険な攻撃地点でもある。」<森田安一『物語スイスの歴史』2000
中公新書 p.167>
つまり、スイスが永世中立となることは、ドイツ、フランス、イタリアおよびオーストリアという周りの4国にとってもその安全保障上、好ましいことであったのである。またスイスの各州(カントン)にとってもスイスとしての統一を維持するためには周辺の強国のいずれとも同盟関係を結ばず、永世中立であることが必要だったわけである。 |
| 永世中立
| 永世中立とは国際法上の概念で、通常の外交上の中立政策とは意味が違う。永世中立とは、他国との条約によって、他国に対して武力を行使せず、また他国間の戦争にも参加せず、武力行使を義務とする同盟などは締結しないこと(局外中立)を誓約することである。永世中立国は、やむを得ない自衛の場合を除いて武力を行使しないことを誓約し、条約締結国はその独立と中立を承認し、保障する。このような永世中立国の最も典型的な例が、ウィーン議定書でのスイスである。それ以外にも、1839年のベルギー、1955年のオーストリア(オーストリア国家条約)などがある。 |
| h ドイツ連邦
| |
| i 1848年 | → 1848年 |
| C イギリス | 19世紀前半のイギリス |
| a パックス=ブリタニカ | |
| D ロシア | |
| a 神聖同盟 | 1815年9月、ロシア皇帝アレクサンドル1世の提唱で成立した、ウィーン体制を補完するヨーロッパの君主国の同盟。ロシア皇帝アレクサンドル1世が皇后エリザベータの信じていた予言者クリュデネル夫人から、皇帝は神から選ばれた人間であり、ナポレオンは悪魔であった、と暗示されて、原文を作成。皇后が「神聖同盟」と名付けた。メッテルニヒもわずかしか手を加えず、オーストリア皇帝フランツ、プロイセン王フリードリヒ=ウィルヘルムが署名。初めはこのロシア、オーストリア、プロイセンの三国だけであったが、ヨーロッパの君主国が次々と加盟し、ウィーン体制の反動性の象徴となった。イギリス国王、ローマ教皇、オスマン帝国のスルタンは加盟しなかった。 |
| b アレクサンドル1世 | ロシア・ロマノフ朝の皇帝、在位1801〜25年。治世の初めにはスペランスキーなどの改革派を登用して、三権分立の導入などの改革を図ろうとしたが、ナポレオン戦争が勃発して改革は停止された。1805年のアウステルリッツ三帝会戦では敗北を喫し、ロシアの防衛体制を固め、ナポレオン軍の侵略に備え軍備を増強した。1810年からナポレオンのロシア遠征が始まり、ボロディノの会戦では敗れたが、クトゥゾフ将軍の戦略によってモスクワを放棄したが粘り強く戦い、ついにナポレオンを撃退した。ついで攻勢に転じ、ライプツィヒの戦いでナポレオン軍を破り、ナポレオンを追ってパリに入城し、ナポレオン支配を終わらせた。このとき、ロシア軍の青年将校の一部はフランスの自由な社会に触れ、ロシア社会の改革の必要を感じることとなり、後の蜂起につながったことは皮肉であった。
戦後のウィーン会議では大きな発言力を持ち、ポーランドを事実上支配下に置くなどの利益を得た。また神聖同盟を提唱し、保守反動体制の中心勢力となった。戦後のアレクサンドル1世は専制権力を強めたので、フランス遠征などで自由主義の洗礼を受けた青年将校の反発を受け、急逝した1825年には青年将校らによる自由主義を目指すデカブリストの乱が起こった。急遽即位した弟のニコライ1世のもとで反乱は鎮圧されたが、ロシアの後進性が次第に明らかになっていく。 |
| c 四国同盟 | 1815年、イギリス・ロシア・オーストリア・プロイセンの四国が締結したウィーン体制を補完する同盟。イギリスの外相カスルレーが提案し、四国の協力でウィーン体制下のヨーロッパの秩序と平和を維持することを大原則とし、ボナパルト家の復活とフランスの侵略戦を防止し、定期的に会議を開いて、フランスのパリ条約の実施を監視することを約した。カスルレーのねらいは、フランスの武装を解除し、ロシアのアレクサンドル1世がイギリスと対抗するためにフランスの軍事力を復興させようとした狙いを粉砕する事であった。この条約に始まる定期的な会議がこの後の国際政治に新しい行きかたをもたらした。1818年にはフランスの加盟を認め、五国同盟となる。 |
| d 五国同盟 | 1818年、先の英・露・墺・普の四国同盟にフランスを加えた同盟。四国同盟はフランスの再起を押さえる目的を持っていたが、フランスは復古王政のルイ18世のもとで、1817年には制限選挙制を定め、保守的な支配体制が完全に復活し、また18年には戦勝国に対する賠償金の支払いを内外の銀行からの調達によって済ませたため、いわば国際社会に復帰が認められた。その結果、1818年にフランスが加盟して五国同盟が成立、ウィーン体制下のヨーロッパ秩序維持が図られることとなった。しかし、1820年にナポリやスペインで自由主義者が立憲革命を起こすと、それへの介入を巡ってオーストリア、イギリス、フランスの利害の対立が明確になり、同盟は次第に有名無実となる。 |
 |
| イ.ウィーン体制の動揺
|
| A ウィーン体制の動揺 | ウィーン体制は、フランス革命とナポレオンによって生み出された自由と平等、国民の統一という革命理念を否定し、革命以前の絶対王政の支配権を復活させるための、反動体制であった。それにたいして、各国で自由と国民の統一を求める運動、自由主義と国民主義の運動が展開され、ウィーン体制を脅かした。それらの運動は各国の保守勢力や、「ヨーロッパの憲兵」の役割を担ったロシアの介入でいずれも抑えつけられたが、体制の動揺は続き、ついに1848年に崩壊することとなる。また各国の利害も必ずしも同じではなく、メッテルニヒは巧妙な外交政策で乗り切ろうとしたが、特にギリシアの独立問題から始まった東方問題では各国の思惑の違いが明確になって、体制の崩壊を早めた。 |
| a 自由主義
| 自由主義は18世紀の啓蒙思想に始まり、経済の発展を背景にして高まった、人間(個人)を封建的な束縛から解放し、自由を実現させることを求める運動。経済的には経済活動の自由と特権の廃止などを要求し、政治的には憲法の制定、議会の開設、普通選挙の実現を通じて一般市民の参政権を実現することを求めた。フランス革命とナポレオンの登場によって火のついた後、ウィーン体制の時期には各国の反動体制のもとで抑圧されながら、運動が展開された。また自由主義の運動は、封建的な分断国家にとどまっていたドイツやイタリアでは一つの国民国家を作り上げようという国民主義と結びついていた。 |
| b ナショナリズム(国民主義) | nationalism の訳語は、「民族主義」、「国家主義」、「国粋主義」などの語が当てられており、その理解には注意を要する。世界史の上で限定して使用される場合は、主としてフランス革命に始まり、ナポレオン戦争を通じて成立し、19世紀前半のウィーン体制時代にヨーロッパで高まって19世紀後半に世界に拡大された、「国民が一つの主権のもとで統合された国家を形成すべきである」という、主権国家の考え方を意味することが一般的であり、その場合は「国民主義」という訳語が最もふさわしい。そのような意味でのナショナリズムの運動とは、具体的には次のようなものが挙げられる。
ナショナリズムの諸概念
・他民族によって抑圧されていた民族が、独立して国家を形成しようとした例:オーストリア帝国支配下のハンガリー、チェコ、ポーランドなどのナショナリズム。イギリス支配下のアイルランドの独立運動。(英語圏では nationalism といえばアイルランド独立運動のことを指す)
・一つの民族がいくつもの権力のもとで分裂していたものを統合して一つの国家を形成しようとした例:ドイツとイタリアの統一運動。
これらの運動は、市民革命後形成されたイギリス、フランス、アメリカ合衆国という先行する近代的主権国家に刺激され、内部の封建的な社会の仕組みの克服と、産業の発展を果たしながら進められた。
・なお、広い意味のナショナリズムとして用いられる「民族主義」は、主として植民地、あるいは他国に従属している民族が独立を目指して、民族意識を高めようとした用いられた、「宗教、言語、文化などの共有意識」を強調する思想をいう。インドのガンジー、中国の孫文、ベトナムのホー=チ=ミンらの思想がその典型であろう。
・なお、民族主義は「人種主義」(人種間の優劣を主張する考えで、人種差別を生む racism)と区別しなければならない。
・また、「国家主義」とは、国家をあらゆる価値の上位に置いて個人の人権や自由を制限、抑圧し、また国家目的なるものを構想して他国領土を侵略することで国家を拡大する思想であり、典型的にはナチスドイツやファシズム・イタリア、軍部支配の日本に見られた。またスターリン時代のソ連もそれにあたる。「国家主義」が「民族主義」と結びつくと、極端な排他思想である「国粋主義」に転化する恐れがある。そのような「狂信的愛国主義」にあたる言葉はショーヴィニズム chauvinism であり、健全な国家の独立や国民の統合を願う「愛国主義」または「愛国心」(パトリオティズム patriotism という)と区別されるべきものである。
・一方でマルクスは国家を階級関係における抑圧機関と考えたから、国家の死滅を予測し、そのための運動として国際組織 international をつくった。さらに国家に何らの価値も見出さず、無用なものと見てその破壊をめざす思想がアナーキズム anarchism である。 |
| 国民国家
| 主権国家において、国民主権が確立し、憲法と議会政治が実現した国家。ほぼ近代国家は国民国家に該当する。英語では、nation state という。16〜17世紀の西ヨーロッパに成立した「主権国家」は、主権が国王に集中し、絶対王政という政治体制をとっており、「国民」の実態とまとまりはまだなかった。ところが、18世紀の主権国家間の抗争(七年戦争など)を経て絶対王政が動揺し、アメリカ独立革命とフランス革命という「市民革命」が起こって国家主権が国民が持つという意識が生まれた。そして一定の国境の中に居住する人々を国民としてとらえ、「主権、国民、国境」という「国家の三要素」を持つ国家が次第に形成されていった。ウィーン体制の時期は一時絶対王政が復活したが、1848年革命の前後にフランス・イギリスは、憲法と議会を持ち、国民が主権者である国家を形成させた(フランスは第2帝政となるがそれも国民が選出する皇帝であった)。またドイツ、イタリアはともに19世紀後半に統一を成し遂げ、国民国家を形成させる。
西ヨーロッパでは19世紀までに国民国家が形成されたが、東ヨーロッパにおいては20世紀前半の第1次世界大戦後がその時期に当たり、アジアでは日本などは19世紀に曲がりなりにも国民国家を形成させたが、多くは植民地か半植民地状態にあったため、20世紀後半の第2次世界大戦後に国民国家となっていく。
なお、最近の議論で、「国家」や「国民」とは、人工的に作られた「想像の共同体」にすぎない、という見解が注目を集めている(ベネディクト=アンダーソン『想像の共同体』1983)。「国民国家」概念も含め、まだ論議の途上にあるといえる。 |
| a 学生組合運動(ブルシェンシャフト)
| ブルシェンシャフトは1815年6月、ドイツ主義の体操家ヤーンを精神的指導者として、戦場帰りの学生を中心にイエナ大学に生まれた新しい学生組合。まだ「決闘の美風」を残し、ユダヤ教徒を排斥したが、祖国としてはただ一つドイツがあるのみとして、「名誉・自由・祖国」をスローガンとし、黒・赤・金(解放戦争の一義勇軍団の軍服の配色に由来する)を旗印にした。この運動は、中部ドイツのイエナから南北ドイツの諸大学に広まった。1817年10月、宗教改革300年祭とライプツィヒの戦勝記念祭を兼ねた祝祭を11大学500人の学生を集め、ルターゆかりの古城ワルトブルクで開催した。その夜、一部の急進派の学生が反動的書物や法規を焚書したことが各国政府を驚愕させた。1819年3月過激派の一学生が、当時ロシアのスパイと目されて学生の憎悪の的となっていた劇作家コッツェブーを暗殺する事件が起き、メッテルニヒは本格的な弾圧を決意する。 |
| カールスバート決議 | |
| b カルボナリ
| ウィーン体制下のイタリアで、自由と国民の統合を求めて組織された秘密結社。カルボナリとは炭焼き人の意味。その起源は不明だが、1809年頃南イタリア・カラブリア山中でフランス支配に反対して形成されたといわれ、もとはフリーメーソンの一分派であったとも見られている、神秘的・宗教的性格の強い結社であった。集会所を山林中の炭焼き小屋に偽装し、賤業とされた炭焼き人と称することで現在秩序への反発を主張した。ナポリを本拠として1816年頃には約6万の党員を有した。スペインの1820年軍人革命に刺激されてナポリで蜂起、立憲革命を起こし、ついで21年3月北イタリアのピエモンテではオーストリア支配からの解放を掲げて蜂起した。ブルジョア革命としては早熟で、オーストリアの介入によってくずされてしまった。しかし、19世紀前半を通じて展開され、1860年に一応の達成を見るイタリアの統一をめざす運動(いわゆるリソルジメント)の第一歩となる運動であり、青年イタリアを組織したマッツィーニもカルボナリの隊員から出発した。 |
| c 立憲革命
| スペインでは、復活したブルボン王朝のフェルナンド七世の絶対主義王政に対し、自由主義派は秘密結社を作り、抵抗。1820年、たまたま新大陸に出航しようとしてアンダルシーアで待機中の部隊を反乱に立ち上がらせることに成功した。中央部の軍隊も反乱側に組し、国王は1812年の憲法(ナポレオン戦争下カディスで開催された議会で改革派が中心になって成立させた憲法。主権在民・出版の自由などが規定された。)を承認した。事態に唖然となったヨーロッパを尻目に、スペインは自由主義革命の行く手を照らす国となり、ポルトガル・イタリアでも同じ様な運動が起こった。しかし、ナバーラとカタルーニャの農村部では王党派の反乱が起こり、カタルーニャには臨時政府が出来た。自分達の領主権が侵される危険を感じた地主と貴族、労働者の騒乱に自分達の立場が危うくなることを恐れた資本家たちは立憲政治への共鳴を失った。1823年、「聖王ルイの十万の王子達」と呼ばれたフランス軍が侵入してくると、ろくに戦わずしてスペインにおける二度目の立憲政治の試みはあえなく崩壊してしまった。<J.ビセンス・ビーベス『スペイン』P.165-7> |
| B ラテンアメリカ
| 地域:ラテンアメリカは一般に「中南米」地域を言う。中南米は「中米」はメキシコ・中央アメリカ諸国・カリブ海域を含み、「南米」は南アメリカ大陸を意味する。この地域をラテンアメリカというのは、1860年代にフランスのナポレオン3世がメキシコを支配したときに、スペイン植民地(イスパノアメリカ)一帯を、スペイン・ポルトガル・フランスに共通するラテン性を強調してフランス語でラメリーク=ラティーヌと称し、その英語表記ラテンアメリカが日本で定着した。つまりラテンアメリカとはラテン系の文化を継承している地域という意味になる。厳密にはこの地域には、カリブ海のジャマイカなどはイギリス、スリナムはオランダという非ラテン諸国独立した国々もあるが、地域名称としてはすべてラテンアメリカに含めている。
歴史:ラテンアメリカの歴史は、「先コロンブス時代、植民地時代、独立国家の時代」に大別される。1492年のコロンブスの到達以後が「植民地時代」であり、1810年に始まる独立戦争を経て一斉に独立する1820年代以降が「独立国家の時代」といえる。ただし、カリブ海諸国の独立は1960年代(キューバとパナマは20世紀初頭)までずれこむ。「先コロンブス時代」にはアステカ文明、インカ文明に代表されるインディオの文化が存在していたが、1521年のアステカ王国滅亡以後は、1821年の一斉独立までの300年間のスペインによる植民地支配が続いた。ポルトガルは、ブラジルを植民地化し、砂糖プランテーションを設けて支配した。いずれの地域でも労働力不足を補うものとしてアフリカから多数の黒人が奴隷としてもたらされた。その結果、植民地時代に本国生まれの白人、現地生まれの白人(クリオーリョ)、白人と現地人との混血(メスティーソ)、現地人(インディオ)、現地人と黒人の混血(ムラート)、黒人、という人種的な身分制が形成された。 →ラテンアメリカの独立
現在:ほぼすべてが独立し、現在は33ヵ国を数える。南米ではフランス領ギアナ、カリブ海ではアメリカ領プエルトリコ、フランス領マルティニーク島などが独立していない。33の独立国のうち、スペインを旧宗主国とするのは18ヵ国で、中南米のほとんどを占め、これらではスペイン語が公用語とされている。カリブ海域を中心としたイギリスを旧宗主国とする国が12ヵ国で、これらでは英語が公用語とされている。他にハイチがフランス語、ブラジルがポルトガル語、スリナムがオランダ語という、それぞれ旧宗主国の言語を公用語としている。ただしカリブ海域で使われている英語・フランス語は本来のものからかなり変形し、クレオール語と言われている。<国本伊代『概説ラテンアメリカ史』2001 新評論> |
| ラテンアメリカの独立 | フランス革命によって自由主義の影響が及んだこと、ナポレオンのスペイン征服(1808年)によって、スペインの植民地であったラテンアメリカに独立の気運が高まった。ヨーロッパ本国の動きは約2ヶ月遅れでラテンアメリカの植民地にもたらされていた。また、イギリス外相カニングは、自国製品の市場としてこの地域がスペインから独立することを期待して、支援した。1804年のハイチの独立を皮切りに、1810年代から20年代にかけて中南米諸国が一斉に独立を達成していった。そのような中で、シモン=ボリバルの「大コロンビア共和国」構想のようなラテンアメリカの統合の動きがあったことは注目されるが、結果的に地域対立を克服することができず、群小国家の分立という形になった。また独立後も複雑な人種的身分制社会を抱え、産業の未発達もあって貧富の差が大きく、独裁権力が出現したりクーデターが相次ぐなどが政治的不安定が続いた。キューバなどハイチ以外のカリブ海諸国の独立は遅れ、20世紀にずれこむ。 |
| a ハイチ
| 1804年、ラテンアメリカで最初の独立国、しかも黒人が建国した国家である。西インド諸島の中で二番目に大きいエスパニョーラ島の西側約3分の1占める。エスパニョーラ島はコロンブスが第1回航海から根拠地を設けたところで、以後、スペイン人の入植が活発で、島民(アラワク人)は現地労働力として酷使されるうちに絶滅してしまった。それに変わる労働力として、アフリカ大陸から黒人奴隷がもたらされ、人口の大半を占めるようになった。島の西部は17世紀からフランス人の進出が始まり、サンドマングと言われるようになり、1697年にはスペインから正式にフランスに割譲された。サンドマングは砂糖のプランテーションが開かれ、本国に大きな富をもたらしたが、白人支配者と、黒人およびムラート(白人と黒人の混血児)からなる被支配層の対立が激しくなった。フランス革命が起こるとハイチでも自由を求める声が強まり、1791年にサンドマングの黒人奴隷暴動が起こった。94年には本国の国民公会が奴隷制の廃止を宣言した。その指導者として登場した黒人のトゥーサン=ルヴェルチュールは、98年には干渉してきたイギリス軍を破り、さらに本国で権力を握ったナポレオンが送った軍隊を破り、その結果1804年にハイチ共和国として独立した。フランスも25年に承認した。ハイチは後に黒人の大統領が皇帝となり、黒人帝国となる。なお、イスパニョーラ島東部はスペイン領であったが、1819年に独立を宣言しドミニカ共和国となる。ところが1822年にハイチが武力侵攻し、首都サント=ドミンゴを占領。その占領は1844年まで続いた。その後も安定を欠き、一時スペイン領に戻ったこともあった。その後もハイチとの対立は尾を引いている。 |
| b トゥサン=ルベルチュール
| 最初の黒人共和国ハイチの独立運動を指導した黒人。1791年、エスパニョーラ島西部のフランス植民地サンドマングで黒人暴動が起きるとそれを指導し、独立運動に転化させた。94年のイギリス軍、ナポレオン軍とも戦って活躍したが、1803年に捕らえられてフランスに送られる途中、獄死した。その意志を継いだ黒人指導者が1804年にハイチ共和国の独立を実現させた。
Epi. 黒いジャコバン トゥーサン=ルヴェルチュールは1743年に奴隷として生まれた黒人。そのフランス人奴隷主は寛大であったので、トゥサンは私財を蓄えることができた。フランス革命が起きると、黒人暴動を組織、山岳地帯を根拠にフランスへの抵抗をはじめた。干渉してきたイギリス軍などを撃退してその勢力を強め、エスパニョーラ島東部にも進出し、1081年には独立を宣言し、憲法を制定した。その憲法にはすべての奴隷の解放が宣言された。ナポレオンはこの独立を認めず、2万3千の軍隊を派遣した。フランス兵は黄熱病に悩まされ、苦しんだ結果、ようやくトゥーサンを捕らえた。トゥーサンはフランスに送られ、1803年に獄中で死亡した。その戦いぶりはフランスの人々を驚かせ、「黒いジャコバン」(ジャコバンはフランス革命での過激なグループの名前)と呼んだ。 |
| 黒人共和国
| 最初に1804年にフランスから独立したハイチのこと。 |
| c シモン=ボリバル
| 19世紀初め、ラテンアメリカ諸国の独立を指導した人物。「南アメリカ解放の父」と言われる。ベネズエラのカラカスの富裕なクリオーリョに生まれた。彼が独立運動に関わった国は、スペインの植民地ヌエバ=グラナダ副王領から独立したコロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ボリビアからペルーに及ぶ。まず1810年、ベネズエラのカラカスで独立運動が起こると、イギリスの協力を得ようとしてロンドンにわたっが失敗し、カラカスに戻って1811年7月、独立宣言を行った。ところが12年3月26日、カラカスで大地震が発生、約2万人犠牲が出たのに乗じてスペイン軍が反撃し、ボリバルは敗れ、以後いくつかの地を経てジャマイカに逃れる。1816年、兵力を整えたボリバルは南米大陸に上陸、各地を転戦し、1819年にボゴダ付近のボヤカの戦いでスペイン軍に勝利し、12月に大コロンビア(グラン・コロンビア)共和国の独立を宣言し大統領となった。1922年にはエクアドルに進撃し、キトを解放した。しかし、ボリバルの構想した大コロンビアは、現在のベネズエラ・コロンビア・エクアドルを含む広大な地域であって、それぞれの地域の対立があり、1830年に分解してしまった。また1826年にはラテンアメリカの新たな独立国に働きかけ、ヨーロッパ諸国の干渉に対する共同防衛のための集団的安全保障体制をめざしてパナマ会議を招集したが、批准までは至らなかった。ボリバルは失意のうちに1830年の12月にチフスにかかり死去した。ボリバルの働きかけは後のパン=アメリカ主義につながる。 |
| 大コロンビア
| 南米大陸の北端のスペイン領としてヌエバ=グラナダ副王が治めていた地域は18世紀にはカカオやコーヒーの生産、金の産出などで経済力を強め、現地のクリオーリョの独立志向が強まった。1810年、カラカスで独立運動が始まり、シモン=ボリバルはスペイン軍と戦い、ボヤカの戦いで勝利して1819年に独立を宣言し大統領となった。ボリバルの構想は、ヌエバ=グラナダ植民地全域を統合して、北米大陸のアメリカ合衆国と同じような大国をつくることであったが、まもなく地域的な対立が生じ、1830年には大コロンビア共和国はコロンビア、ベネズエラ、エクアドルの三国に分裂してしまった。 |
| エクアドル
| 南米大陸のアンデス山脈北端にあたる、赤道直下のラテンアメリカ諸国の一つ。かつてはインカ帝国に支配されていた。スペインはこの地を武力で制圧し、1534年にキト市を建設。その後、シモン=ボリバルの指導で独立した大コロンビアに属したが、1830年に分離して独立した。国名のエクアドル Ecuador は「赤道」Equator を意味するスペイン語に由来する。 |
| ボリビア
| 南アメリカ中央部のアンデス山中で、かつてインカ帝国の一部であった。スペイン植民地時代はアルト・ペルー(高地ベルー)と言われ、1545年にポトシ銀山が発見されて、重要な植民地とされた。南米では遅くまでスペイン副王領の拠点として残り、1825年にようやくシモン=ボリバルによって解放され、独立を達成し国号をボリバルにちなんでボリビアとした。
Epi. もう一つの「太平洋戦争」 ボリビアは現在は海岸に面していない内陸国だが、建国当時は現在のチリ北部もボリビア領で、太平洋に面していた。その地方はアタカマ砂漠が広がるが硝石(ガラスや肥料の原料)の産地だった。その資源をめぐってボリビアとチリの間で1879年から83年にかけて展開された戦争を太平洋戦争と言っている。ボリビアは軍事同盟を結んでいたペルーとともに戦ったが、敗れ、アタカマ地方をチリに割譲し、内陸国となってしまった。 |
| パナマ会議 | 1826年、シモン=ボリバルが呼びかけて、パナマで開催された、ラテンアメリカの独立諸国の会議。ボリバルはこの会議で、ヨーロッパからの干渉に対してラテンアメリカ諸国の連帯と結束を呼びかけた。この時は具体的な成果はなかったが、彼の理念はパン=アメリカ主義として継承され、後の1889年、ワシントンで開催されたパン=アメリカ会議の源流となった。 |
| ベネズエラ
| 南米の最北端でカリブ海に面する地域。カカオの産地。スペインのヌエバ=グラナダ副王領の一部であったが、1810年大陸では最も早く独立運動を開始、シモン=ボリバルの指導のもと、1819年まず大コロンビア共和国として、西の現在のコロンビアやエクアドルと一体で独立した。しかし、地域対立が起き、1830年に分離してベネズエラ共和国となった。20世紀にはマラカイボ地方で石油が発見され、産油国の一つとして経済を発展させている。 |
| コロンビア
| スペインのヌエバ=グラナダ副王領から、シモン=ボリバルの指導により、1819年大コロンビアとして独立した。地域対立により、ボリバルの死後の1830年にベネズエラとエクアドルが分離した後、コロンビア共和国となった。コロンビアという国名はコロンブスに由来する。 |
| d サン=マルティン
| シモン=ボリバルが南米大陸北部の独立の英雄であるとすれば、南部の英雄がサン=マルティンである。サン=マルティンはアルゼンチン生まれのスペイン軍人で、アルゼンチンの独立運動に共鳴し、スペイン本国の拠点となっていたペルー副王の本拠を攻撃するため、1817年独立軍5000を率いてアンデスを越え、チリの独立を支援し、さらに北上して1821年にペルーを解放した。最後に残ったアルト・ペルー(後のボリビア)の攻略を目指したが、1822年にエクアドルのグアヤキルでボリバルと会見、最後の独立戦争の指揮権をボリバルに譲り、ラプラタに戻った。そこでは内紛が続いていたので嫌気がさしたのか、ヨーロッパに渡り、アルゼンチンに戻ることはなかった。彼の遺骸が南アメリカの解放者と認められてブエノスアイレスに戻るのは1880年のことだった。 |
| アルゼンチン
| 現在のアルゼンチンは、スペイン植民地時代はラプラタ副王領とされていた。副王都市ブエノスアイレスは、貿易港として18世紀から急速に発達し、現時生まれの白人であるクリオーリョの商人が独立を求めるようになった。1806〜07年、ブエノスアイレスに侵攻したイギリス軍を民兵が撃退して自信を深め、1810年にはスペイン本国の混乱を機に副王を追放した。1816年にはラプラタ地域の諸地方を統合して「ラプラタ諸州連合」として独立を宣言した。1862年に連邦共和制となった。このとき、スペイン語の国号ラ=プラタを嫌い、同じ銀を意味するラテン語のアルヘントゥムに基づきアルゼンチン(現地の発音ではアルヘンティーナ)に改めた。 |
| チリ
| アンデス南部の太平洋側に南北に連なるチリも、1810年にサンチャゴで臨時政府が樹立され、スペイン人官吏を追放しペルー副王の派遣した軍に対してオイギンスを司令官とする独立解放の戦争を続けた。独立軍は、ラプラタ地域の独立運動指導者サン=マルティンの支援を受けて1817年のチャカブコの戦いでスペイン軍を破り、1818年に独立を達成した。1879年〜83年の太平洋戦争で、ボリビア・ペルー連合軍に勝利して、アタカマ地方を獲得し、その地の硝石資源を獲得、チリの重要な輸出品となる。 |
| ペルー
| ペルーはアンデス山脈中心部のかつてのインカ帝国が繁栄した地域で、スペイン植民地時代はペルー副王がの統治を受けていた。1780年、最初で最大のインディオ反乱と言われる「トゥパク=アマルの反乱」が起こった。インカ皇帝の直系子孫を名乗るコンドルカンキがスペインのの搾取に対して立ち上がったもので、一時はクスコを包囲しインディオの国の樹立を目指したが、副王軍に敗れ100人ほどが処刑されて鎮圧された。ペルー副王はその後、本国スペインがナポレオンによって征服されたことによって南米各地に独立運動が起きるとその弾圧の拠点となった。1821年、ラプラタ(アルゼンチン)のサン=マルティン率いる独立支援軍の攻撃を受け、ついに降伏し、7月サン=マルティンが独立を宣言した。 |
| e メキシコ
| メキシコはスペインによってアステカ王国などが滅ぼされ、1535年以来、ヌエバ=イスパニャ植民地とされ副王が統治していた。特にメキシコ産の銀から鋳造した「スペイン銀」はアカプルコとフィリピンのマニラを結ぶガレオン貿易の重要な輸出品となり、本国の繁栄をもたらした。スペインはメキシコに対し、初めはエンコミエンダ制、ついでアシエンダ制をしいて植民地支配を進めたが、支配権を握っていたのは本国生まれのスペイン人であったので、現地生まれのスペイン人であるクリオーリョやインディオとの混血であるメスティーソの不満が強まっていた。1808年、本国のスペインがナポレオンによって征服されたのを機に、独立運動が始まった。1810年、最初の放棄を指導したイダルゴが捕らえられて処刑されると、メスティーソの神父のモレーロスがあとを継いで運動を継続した。彼も捕らえられて運動は一時抑えられたが、1820年にスペイン立憲革命が起こると、イトゥルビデの率いる富裕なクリオーリョ層が本国との分離を策し、1821年に独立を宣言した。独立したメキシコは、スペイン人とクリオーリョの差別は撤廃されたものの、カトリック教会の財産と特権は保障され、翌年はイトゥルビデを皇帝とする君主国となった。1824年には共和政に移行するが、内部対立が続き、1846年にはアメリカ合衆国との戦争で領土の半分以上を失い、1864〜67年にはフランスのナポレオン3世のメキシコ出兵があり、マクシミリアンの帝政が行われる。 |
| イダルゴ
| 「メキシコ独立の父」と言われる、メキシコの独立運動指導者。ミゲル=イダルゴは貧しいクリオーリョの生まれで、ドロレス州の小さな村の神父となった。ルソーの思想に共鳴し、1810年9月16日の日曜日の朝、信者たちに武器を配り、「悪政を倒せ、スペイン人を殺せ!」と叫んで行進を始めた。途中、インディオやメスティーソも加わり、大きな勢力となったが、武器は少数の小銃があるだけで、あとは弓矢や槍、斧などだった。12月にバリャドリドで議会の設立を宣言、奴隷を解放し、インディオに土地を与えた。しかし翌年1月、副王軍に敗れ、アメリカに逃れようとしたところをチワワで捕らえられ、7月26日に処刑された。イダルゴの生きている間にメキシコの独立が達成されたのではないが、彼が立ち上がった9月16日は、現在でもメキシコの独立記念日とされている。<中屋健一『ラテン・アメリカ史』1964 中公新書> |
| f ブラジル
独立 | ポルトガル領であったブラジルの独立の経緯は他のラテンアメリカ諸国と異なっている。1807年7月、ナポレオンはイギリスと結んでいたポルトガルに対して、そのすべての港をイギリスに使用させないよう要求、ポルトガルがそれを拒否すると、11月にフランス軍を侵攻させ、リスボンを占領した。このときポルトガル王室はイギリス海軍の保護のもとに植民地ブラジルに避難した。その結果、リオ=デ=ジャネイロは1808年から14年間はブラジルの首都となった。ナポレオンが倒れた後の1821年に、ポルトガルのジョアン6世は本国に戻り、息子のドン=ペドロを摂政としてブラジルに残した。すでに本国の支配を離れて自立していたブラジルのポルトガル人(クリオーリョ)大土地所有者や資本家は、ドン=ペドロを押し立てて、翌1822年に「ブラジル帝国」として独立宣言した。
独立後のブラジルは、1888年奴隷制を廃止、89年に共和制に移行。はじめはゴム(自動車の普及に伴いタイヤ用のゴムの需要が急増した)、第1次世界大戦後はコーヒーの大農園による生産が増大、特にコーヒーは先行のジャワや西インドを抑えて、世界最大の産出国となった。またヨーロッパから多数の移民を受け入れ、1908年からは日本からの移民も始まった。しかし、コーヒーという単一の商品作物に依存する経済は、その価格変動に常に左右されて安定せず、また第2次大戦後の急速な工業化も社会のひずみを招き、軍事独裁政権が出現するなど政治も混乱した。 |
| g クリオーリョ
| スペイン語で本来は外地で生まれたヨーロッパ人を意味した。英語ではクレオール creole 。後にラテンアメリカ地域で現地生まれのスペイン人を意味するようになった。なお、本国生まれのスペイン人はペニンスラール(半島人、イベリア半島生まれということ)、蔑称がガチュピンと言われた。ラテンアメリカのスペイン植民地ではクリオーリョは法的には本国人と同じで、土地を持ち、商業を営むことはできたが、官吏になる路はなく、政治的には無権利であった。そのため1810年代以降のラテンアメリカ諸国の独立は彼らクリオーリョが中心となって起こされることが多かった。独立後は彼らが社会的な支配層となり、メスティーソやインディオ、黒人、ムラートとの対立が生じてくる。
なお英語の creole は、アメリカ南部のルイジアナ州に多いフランス系の人々をいう。 |
| h メスティーソ
| ラテンアメリカの人種的身分集団の一つで、白人と現地人インディオとの混血を意味する。多くは白人男性とインディオ女性の間に生まれた人で、クリオーリョからは差別され、商人組合や職人組合には入れなかった。そのため、アシエンダ(大農園)の管理人や牧童などになることが多かった。スペイン人社会とインディオ社会のいずれにも属さないことから、たびたび社会不安の原因となった。 |
| i インディオ
| インディオはラテンアメリカの先住民族。スペイン人、ポルトガル人などヨーロッパ人の侵入によってその文明を破壊され、酷使されて人口が激減した。植民地支配の時代も、独立後も、白人からは差別される存在であった。彼らは白人社会とは隔離され、馬に乗ることや武器を持つことを禁止されたほかに、ぶどう酒を飲むことやスペイン人の衣装を身につけることもできなかった。16世紀のラス=カサスなどの運動で、インディオに対する待遇は改善され、法的には人格が認められ、奴隷扱いされることはなくなったが、その生活は解放された黒人よりも貧しいものがあった。彼らは植民地時代のペルーのトゥパク=アマルの反乱のような抵抗を行ったが、独立後もインディオに対する社会的不平等はラテンアメリカの不安定要素の一因となった。 |
| j ムラート
| ラテンアメリカのカリブ海地域や、ブラジルなどの砂糖プランテーションではアフリカ黒人奴隷が大量に労働力としてもたらされた。その経過の中で生まれた白人男性と黒人女性の間の混血をムラートという。一つの人種的身分集団を構成し、社会の下層に置かれた。なお、先住民インディオと黒人の混血はサンボと言われた。 |
| C モンロー教書
| 1823年12月、アメリカ合衆国大統領(第5代)モンローが大統領教書として発表した、ウィーン体制下のヨーロッパ諸国のアメリカ大陸への干渉を排除し、合衆国の孤立主義の外交原則を表明したもの。「モンロー宣言」(Monroe Doctrine)ともいう。なお、教書(Presidental
Message)とは、大統領が連邦議会に対して発する意見書のことで、三権分立のもとでの議会が有する立法権に大統領が関与する制度である。モンロー大統領は、ラテンアメリカでのスペインの商業的独占の復活を恐れたイギリス外相カニングの共同での声明発表の申し出を受けたが、単独での声明とした。議会への教書として示された内容は次の4点である。
- 合衆国は、新世界でヨーロッパ強国が所有している植民地に干渉しない。
- ヨーロッパ強国がその君主制の制度を西半球のいかなる地域にせよ広げようとすることは我国の平和と安全にとって危険なものと見なす。
- すでに独立を達成した国を圧迫するヨーロッパの強国は合衆国に対する非友好的な意向を示すものと見なす。
- アメリカ両大陸は今後、ヨーロッパ強国によって将来の植民の対象と考えてはならない。また、合衆国としては、ヨーロッパの事態に干渉する意図はない。
モンロー教書の背景:1823年にモンロー教書が出された背景にはポイントが二つあって、一つはウィーン体制のもと、ヨーロッパの旧君主国(神聖同盟諸国)が復活し、メッテルニヒなどによる南北アメリカ大陸への干渉が強まってきた事への反発であった。もう一つの動きはロシアがアラスカに進出し、北緯51度まで太平洋岸を南下する動きを示したことに対する反発であった。このモンロー教書は、その後のアメリカ合衆国の外交の基本姿勢となる孤立主義(モンロー主義)の原型となる。 → アメリカの外交政策 |
| a 1823
| |
| b モンロー
| → モンロー大統領 |
| c 相互不干渉
| |
| d カニング
| George Canning (1770-1827) 19世紀初頭のイギリスの政治家。トーリ党に属していたが、自由主義的な思想を持ち、自由貿易や議会制度の改革を推進した。特に外相として活躍し、1822年にメッテルニヒらに指導されたヨーロッパ列強がラテンアメリカの独立運動に介入しようとしたことに反対し、ラテンアメリカへの不介入宣言をアメリカに呼びかけたことで知られる。この呼びかけに対してアメリカ合衆国のモンロー大統領は単独でモンロー教書を発表した。 カニング外相は、ただちにモンロー宣言の支持を明らかにした。その意図は、スペインのラテンアメリカ支配の復活を阻止し、産業革命を進展させたイギリスにとって、ラテンアメリカを大きな市場とすることであった。
Epi. カニングという名前 このカニング Canning はキャニングとも表記されるが、日本ではカンニングに通じ、響きがよくない。しかし不正行為意味するカンニングは、cunning
なので念のため。なお、英語ではテストの不正行為はカンニングとは言わず、cheating というそうです。ところでカニングはなかなか面白い人で、小ピットの薫陶を受け、トーリ党でも最も才気のある人物だったという。それだけに敵も多く、1807年に初めて外相となったときは、陸軍大臣だったカスルレー(ウィーン会議のイギリス代表)と衝突して辞職し、決闘騒ぎとなり、負傷した。その後、インド監督局総裁を経て22年に外相に再任され、さらに1827年に首相となったが、在任4ヶ月で病死してしまった。 |
| 孤立主義
(アメリカ) | アメリカ合衆国の伝統的な外交政策の原則とされた、ヨーロッパ諸国への不介入のと、その干渉を認めないという外交姿勢を言う。1823年のモンロー大統領が掲げた「モンロー教書」によって明確にされたのでモンロー主義とも言われ、ヨーロッパとの相互不干渉と同時に、ラテンアメリカなど西半球へのアメリカ合衆国の優先権を主張した。すでにワシントンもジェファーソンも、新国家建設のためにはヨーロッパ諸国の対立に巻き込まれるべきでないと考え、国際的には中立の立場をとり、外交より内政を重視すべき出るとしていた。その一方で、初代財務長官ハミルトンに見られるように、積極的なヨーロッパとの通商を行い、海洋国家として外交を展開すべきであるという論調もあった。建国期以後もウィルソン大統領のように民主主義の理念を世界に押し広げるのが課題であると考える潮流、さらにジャクソン大統領のように国家の安全と繁栄を最優先に、軍事力の行使も辞さないという国威高揚をはかる路線もある。
孤立主義外交の展開:19世紀中ごろ、南北戦争を機に工業国家としての統一をなしとげ、ナショナリズムが成立するとともに、フロンティアが消滅すると海外膨張の傾向が出てきて、帝国主義段階になると、1898年の米西戦争でラテンアメリカおよび太平洋方面への進出を図るようになり、さらにT=ローズヴェルト大統領は「モンロー主義の系論」を掲げて棍棒外交といわれる力による外交を展開した。これはモンロー教書を拡大解釈したものであった。第1次世界大戦でもウィルソン大統領は当初中立を守ったが、途中から孤立主義を転換し参戦、14カ条の原則では国際協調を世界に提起した。しかし国内の孤立主義の伝統を守る保守派の抵抗で彼の提案した国際連盟にはアメリカは参加できなかった。戦間期の孤立主義の傾向は、1924年の移民の受け入れを制限する移民法の制定などにも現れている。には経済繁栄を背景としてヨーロッパ情勢にも関わりを持たざるを得なかったが、ファシズムの台頭に対しても当初は1935年に中立法を制定して介入を避けていた。
孤立主義からの転換:しかし、ナチスドイツの侵略行為が強まり、アジアにおける日本の台頭がアメリカの権益を脅かすようになるとF=ローズヴェルトは武器貸与法の制定や大西洋憲章などで孤立主義を放棄して、アメリカが世界の民主主義と自由をまもる戦いの中心となるという使命感から第2次世界大戦に参戦し、戦後においても国際連合の一員であるとともにドルが世界の基軸通貨となるなど、経済面でも世界の大国としての義務と責任を果たすという姿勢を強めた。しかし、東欧などでのソ連・共産勢力の拡大を大きな脅威と受け取ったアメリカは、トルーマンドクトリンで東側世界の封じ込めに転じ、冷戦期に入った。冷戦期にはソ連と社会主義陣営と対決する自由主義陣営の盟主として、朝鮮戦争への派兵や、その他の国や地域に対する干渉的な軍事行動を展開するようになった。ここでは、孤立主義は姿を消し、アメリカの国際協調主義と大国意識が結びついた、覇権的な行動が目立った。その典型がベトナム戦争であったが、その長期化は国際収支の悪化や反戦運動の高まりなど、アメリカを根底から揺るがすこととなり、70年代初頭のドルショックや、中国との国交回復という大きな転換をもたらした。こうして70年代以降は西側世界のアメリカ一極構造は終わりを告げ、経済統合を進めた西欧諸国、経済を復興させた日本などとの多極化の時代に入った。そのころから、アメリカには保護貿易主義が台頭するなど孤立主義的な傾向が復活し、冷戦が終結してアメリカが唯一の軍事大国となった現在は孤立主義が単独行動主義(ユニラテラリズム)という形に変形して現れているのではないか、との見方がある。 → アメリカの外交政策
|
| E ギリシア独立戦争 | ビザンツ帝国滅亡(1453年)後、ギリシアはオスマン帝国の支配を受けていた。オスマン帝国の支配下では、ギリシア人はギリシア正教の信仰は認められた(ミッレト制のもとで宗教共同体を構成していた)が、経済的・政治的な自由は認められていなかった。19世紀初めになって、フランス革命・ナポレオンの登場に刺激され、独立をめざすようになった。またイギリスなど西欧諸国内に、ギリシア文明を西欧文明の原点として敬愛する運動である「ギリシア愛護主義」が起こり、独立運動の支援が活発になった。1814年には、ウィーンに滞在しフランス革命の理念などの影響受けたギリシア人青年たちが友愛協会(フィリキ・エテリア)を組織、1821年3月、イプシランディスに率いられてオスマン帝国(マフムト2世)からの独立戦争を開始した。22年には独立宣言(最初の憲法制定)。ヨーロッパ各地からもイギリスの詩人バイロンのように義勇軍が参加した。しかし、ウィーン体制のもとで、オーストリアのメッテルニヒは自由主義・民族主義の高揚に危機を感じ、独立に反対、神聖同盟も独立に反対を表明した。オスマン帝国はエジプトのムハンマド=アリーの支援をうけて独立運動を抑えにかかり、アテネを占領し、独立軍は苦戦となった。ロシアのニコライ1世の南下政策によるギリシア援助を始める、イギリス・フランスも東洋進出を狙って支援を強化、27年のナヴァリノの海戦で英仏露連合艦隊がトルコ・エジプト海軍を破って独立を認めさせた。29年、オスマン帝国とロシアはアドリアノープル条約を締結、オスマン帝国は黒海北岸をロシアに割譲した。ギリシアの独立は、1830年にロンドン会議で国際的に承認された。この結果、オスマン帝国の権威は低下し、神聖同盟の結束がバルカン方面の利害を巡って対立し、ウィーン体制の動揺につながった。
→ 東方問題 → ギリシア王国 |
| a オスマン帝国
| |
| b ギリシア愛護主義 | ヨーロッパで自由主義運動がたかまった19世紀前半、古代のギリシア文化をヨーロッパの起源と考え、理想化するギリシア愛護主義(フィルヘレニズム)がヨーロッパ各国に興った。代表的な人物がイギリスの詩人バイロンである。他にフランスのシャトーブリアン(作家)、ドラクロワ(画家)、ドイツのミュラー(詩人)、ロシアのプーシキン(作家)などがいる。彼らはギリシアの独立運動を資金面でも援助した。ドラクロワの絵画『キオス島の虐殺』(「シオの虐殺」ともいう)は1824年に発表され、オスマン帝国軍の虐殺事件を描き、人々を憤激させた。最も行動的であったのはバイロンで、1821年にギリシア独立戦争が始まると、彼自身が義勇兵を組織してギリシアまで出かけた。彼は病に倒れるが、ヨーロッパ中の声援の中で1830年にギリシア独立は達成される。 |
| c ナヴァリノの海戦 | 1827年、ギリシア独立戦争での最後の決戦となったギリシアの東海岸沖合での海戦。ギリシアを支援したイギリス、フランス、ロシアの連合艦隊が、オスマン帝国(マフムト2世)・エジプト(ムハンマド=アリー朝)の連合海軍を破った。ナヴァリノはペロポネソス半島の南西に位置する。英・仏・露連合艦隊は、イギリスの提督コドリントンが指揮、双方の砲撃の後、激戦となり、オスマン帝国・エジプト艦隊が全滅した。この敗北でオスマン帝国はギリシアの独立を認めた。ナヴァリノの海戦は「帆船時代の最後の大海戦」と言われる。 |
| d ロンドン会議 (1927〜31) | 1927年から31年まで断続的に続いた、イギリス・フランス・ロシアなどによる国際会議。1930年にはギリシア独立を正式に承認し、またベルギー独立問題についても協議し、31年にはその独立を承認した。 |
| ギリシア王国
| ギリシアは長い歴史を持つが、近代ギリシアの歴史はオスマン帝国からのギリシア独立戦争を経て1830年に国際的に独立が認められたところから始まる。当初共和国として発足したが、初代大統領(カポディストリアス)は31年に暗殺された。イギリス、フランス、ロシアの列強は王制とすることを独立の条件として、ヨーロッパの王家の中からドイツのバイエルンの王子オットーを迎えることとなった。それがギリシア王国初代のオトン王(オットーのギリシア名)。このようにギリシア人は外国人の国王をあてがわれて独立を認められた。オトン王はギリシアの伝統を無視してドイツ風の統治を行おうとしてうまくいかず、また後継者もいなかったので退位し、1864年には列強はデンマークの王族グリュックスブルク家のクリステイアン・ウィリアム・フェルディナンド・アドルフス・ゲオルク王子を選び、ギリシア風にゲオルギオス1世と名乗った。この王家が中断をはさみながらも1974年までギリシャを統治した。古代に繁栄したアテネがギリシア王国の都として復活した。
このギリシア王国は、ほぼペロポネソス半島とエーゲ海のいくつかの島々だけで現在のギリシアから見ればごく限られた地域を占めるだけであった。マケドニアやクレタ島、小アジア西岸に多くのギリシア人がいたが、彼らは依然としてオスマン帝国の支配を受けることとなった。そのため、ギリシア人の中かから、小アジアも含めてのギリシア人居住地域すべてをギリシアとして統合すべきであるという大ギリシア主義(メガリ・イデア)が起こってくる。一方でギリシア王国はその初めから外国の力を借りて独立したという弱みが続き、その後もイギリス、フランス、ロシア、そしてオーストリアとドイツという列強のバルカン半島に翻弄され、王政は安定せず政治的混乱が続く。第2次大戦後の混乱期にはトルコの衰退に乗じて大ギリシア主義を実現しようとし、小アジアのスミルナ(イズミル)に侵攻し、ギリシア=トルコ戦争を起こしたが、ムスタファ=ケマル(アタチェルク)のトルコに反撃されて敗北し、1923年には王政もいったん倒れる。 → ギリシア語論争 ギリシア(第1次大戦後) |
| ギリシア語論争
| ギリシアの公用語を何にするか、という論争であるが、対立したのは、民衆に広く用いられていた民衆語(ディモティキ)か、古典ギリシア語を復活させた古典語(カサレヴサ)のいずれにするか、ということであった。インド=ヨーロッパ語系のギリシア人はいくつかの方言に分かれていたがヘレニズム時代にアテネを中心としたアッティカ語が各地の方言と混合してコイネーが生まれ、それが「ギリシア語」として公用語とされ、ビザンツ帝国時代まで使われた。オスマン帝国時代には公用語ではなくなり、ギリシア正教会の中の特殊な言葉として残っていた。民衆の中では長い時間と異文化の影響の中で大きく変化し、民衆語「ディモティキ」が形成されてきた。両者は文字は同じだが、文法や発音ではかなりの違いがある。19世紀に西欧諸国でギリシアを西欧文明の起源の地として尊崇する動きであるギリシア愛護主義が盛んになると、その影響を受けて古典語(カサレヴサ)を復活させ、公用語としようと動きが強まり、ギリシア王国では学校教育の中で強要されるようになった。民衆にとってはそれは学校の中で教えられるだけの、いわば文語だった(日本で言えば古典や漢文)ので、苦痛になるだけだった。最近までこのいずれを公用語とすべきか論争(ギリシア語論争)が続いたが、1976年にようやくディモティキを公用語とすることが決まった。 → ギリシアの民主化 |
| F デカブリストの反乱 | ロシアでは、貴族出身の青年将校たちの間に、皇帝の専制政治に対する不満が強まっていた。皇帝アレクサンドル1世が急逝し、新皇帝ニコライ1世が即位した1825年12月14日に、青年将校たちは反乱を起こした。しかし、反乱は軍隊の一部に止まり、民衆的な広がりはなく、政府軍の反撃によって鎮圧され、首謀者(ペステリ、ルイレーエフ、アポストルなど)はいずれも絞首刑となった。さらに事件に関係があるとされて500人以上が逮捕された。事件の起こった12月をロシア語でデカーブリというので、この事件に参加した人々はデカブリスト(十二月党員)と呼ばれることになった。 |
| ナポレオン戦争 | |
 |
| ウ.フランス七月革命とイギリスの諸改革
|
| A 復古王政
| ナポレオン1世の第1帝政が1814年にその退位で終わった後(1815年に一時ナポレオン1世の帝政が百日天下として復活するが)、フランスで復活したルイ18世以降のブルボン王朝の支配時代を「復古王政」という。1814年から、七月革命の起こる1830年まで。革命前のアンシャン=レジームの復活を策したが、市民意識は定着していたので、所有権の不可侵や法の下の平等などの革命の成果は保障された。ルイ18世に次いで弟のシャルル10世が即位すると、より反動的な政治が行われて、復古王政に対する反発が強まり、1830年の七月革命で倒される。
Epi. スタンダールの『赤と黒』 復古王政時代のフランスを舞台とした文学がスタンダールの『赤と黒』(Le Rouge et le Noire)である。復古王政の終わった七月革命の年、1830年に発表されている。田舎ものの製材屋の息子ジュリアン=ソレルが、野心に燃えて貴族の家庭教師、さらに秘書から身を起こそうとしながら、二人の女性との恋の激しい葛藤を続け、ついには破滅する物語であるが、題名の『赤と黒』とは、一般に赤が軍服を、黒が僧服を意味し、いずれも復古王政時代に幅をきかせていた軍人と僧侶の象徴であるとされている。ジュリアンは密かにナポレオンを敬愛しながらそれを隠し、驚異的な記憶力を発揮して聖書を丸暗記して聖職者への道を歩もうとする。また、その才能を買われて秘書となった貴族の家で、その娘と恋仲になり、遠ざけられて軍人になる。物語は、フランス革命とナポレオンによって自由と平等にあこがれるジュリアンと、それを許そうとしない貴族や地方の有力者側にいる人妻と令嬢との道ならぬ恋・・・と読むことができる。<スタンダール『赤と黒』上・下 岩波文庫 桑原武夫・生島遼一訳> |
| a シャルル10世
| フランス・ブルボン復古王政の二代目の国王。1830年の七月革命で退位し、ブルボン家最後の国王となった。彼はルイ16世とルイ18世(プロヴァンス伯)の弟。王位継承前はアルトワ伯と称し、革命の早い時期に亡命し、ドイツのコブレンツなどを拠点に亡命貴族(エミグレ)の中心にあった。その後、ナポレオン没落後、兄のルイ18世の王政復古後は、最も反動的な王党派貴族に担がれ、その象徴となった。1824年、兄ルイ18世の死に伴いシャルル10世として王位を継承したが、兄王が立憲君主政をとったのに対して、絶対王政の完全な復活を策し、亡命貴族の財産を保障するなど、より反動的な政策をとったため、国民の反発を強く受けるようになった。このシャルル10世の復古王政の時期には、カトリック教会の聖職者が特にそれを支える保守勢力として力を振るった。1830年、彼は国民の反発をそらすため、アルジェリア出兵を行い、王政批判の言論を厳しく取り締まったが、ついに七月革命が勃発し、退位してイギリスに亡命、フランスのブルボン王朝は終わりを告げた。 |
| b アルジェリア出兵
| 1830年、復古王政のシャルル10世は、国内の人気を得るために、地中海の対岸のアルジェリア(16世紀以来、オスマン帝国の宗主権の下にあった)に出兵し、占領した。同時に七月革命が勃発し、シャルル10世は退位しイギリスに亡命した。フランスは七月王制下においてもアルジェリアから撤退せず、それに対してアラブ人首長アブド=アルカーディルによる反フランス闘争が1832年から始まる。1847年、アブド=アルカーディルは捕らえられ、晩年はフランスに協力するようになり、抵抗運動は衰えた。その後130年にわたりフランス植民地支配が続き、第2次世界大戦後、アルジェリア民族解放戦線(FLN)による独立運動が始まり、激しい闘争の末、1962年に独立を達成する。 →アルジェリア独立 アルジェリア戦争 |
| B 七月革命
| 1830年、フランス復古王政のシャルル10世の言論弾圧などに対して、ブルジョワ共和派を支持するパリ市民が蜂起して、絶対主義体制を倒し、七月王政を出現させた変革。ヨーロッパの各地の反動勢力にも大きな打撃となり、ウィーン体制を大きく動揺させた。
1830年7月27日早朝、発行された『ナショナル』『グローブ』などの新聞が直ちに警察によって没収される。印刷所では抵抗が始まり、パリ市街に暴動が起こる。一旦鎮圧されたが、軍が引き揚げた後、バリケードが築かれ、学生と労働者、カルボナリの残党がパリ12区の蜂起のための委員会を作った。翌日、パリ市庁、ノートルダムで激しい争奪戦。銀行家ラフィトはポリニャック首相に勅令撤回・内閣交替の要求を国王に伝えるように要請したが、面会拒否される。その夜、ラフィト邸が抵抗運動本部となる。夜通しの戦闘で市庁舎は奪回され、翌朝、ラ=ファイエットを国民軍司令官とし、ラフィトらをパリ市委員会に任命、市庁舎に乗り込む。政府軍の一部が共和派に寝返り、戦局は一転、ルーブルでもスイス人守備隊の抵抗を排除背手して市民が突入し、時計台に三色旗を掲げ、玉座にひとりの戦死者を座らせた。ヴェルサイユから9キロのサン−クルーにいたシャルル10世もようやく内閣会議を開き、勅令撤回と内閣の交替を決定した。これが『栄光の3日間』といわれる。この戦いには『幻想交響曲』作曲中の27歳のベルリオーズも参加し、33歳の画家ドラクロワは大作『民衆を率いる自由の女神』を描いた。この結果、シャルル10世は退位し、復古王政は終わりを告げ、ルイ=フィリップが国王となり七月王政となる。 → 七月革命の影響
|
| オルレアン家
| |
| a ルイ=フィリップ
| 七月革命が起こると、銀行家ラフィトらはブルボン家のオルレアン公ルイ=フィリップを国王に推挙、共和派はラ=ファイエットを大統領とする共和政を主張したが、ラ=ファイエットはフランス革命の時のように共和政のもとでジャコバン化することを恐れて、君主制がいちばん良いのだ、といって逃げた。ルイ=フィリップは「ブルボンを倒せ!」という市民の声に対して、市庁の広間で三色旗につつまれ、ラ=ファイエットとだきあってみせ、8月1日には人民主権・上院廃止・行政粛正等とともに、「共和的な制度につつまれた民衆的玉座」を約束。2日、シャルル10世は退位を宣言してイギリスに渡り、9日ルイ=フィリップはブルボン宮で「フランス人の王」となった。14日には憲法を制定、七月王政が始まった。国王ルイ=フィリップとしての統治はもっぱら銀行家などの上層ブルジョアジーの利益の保護にあたり、「株屋の王」と揶揄された。48年、二月革命が勃発し、退位してイギリスに亡命。 |
| b 七月王政
| 1830年の七月革命によって成立した国王ルイ=フィリップのもとでの立憲君主政。1848年の二月革命まで続く。政治体制は1830年の憲法に基づく、立憲君主政。議会は制限選挙制によって有産者が多数を占め、上層ブルジョアジーが支配権力を握った。そこで、ルイ=フィリップを市民王、七月王政をブルジョア王政などという。この七月王政の18年間はフランスが産業革命時代となり、機械化が進み鉄道の建設が始まった。また1830年に始まるアルジェリアの植民地化をさらに進め、またエジプト=トルコ戦争でのムハンマド=アリーへの支援など、東方問題への介入を強めた。一方、産業革命の進行に伴い、都市の中産階級と労働者階級も形成され、彼らは普通選挙などの改革を要求して上層ブルジョアジー政権である国王ルイ=フィリップとギゾー内閣への批判を強め、1848年の二月革命がもたらされる。 |
| c 立憲王政
| |
| d 産業革命
| → 第11章 1節 フランスの産業革命 |
| C 七月革命の影響
| 1830年にフランスで起こった七月革命は、ウィーン体制下の反動的権力に抑えられていたヨーロッパ各地の自由主義運動、民族独立運動に影響を与えた。まず、隣接するオランダからのベルギー独立運動がおこり、12月に独立を達成した。ロシアの支配を受けていたポーランドの独立運動もおこったが、こちらはロシア軍の介入で弾圧された。また、同年にはドイツ各地で自由主義者が蜂起したが鎮圧された。翌年の31年にはイタリアの反乱が起こったがオーストリア軍によって鎮圧された。そのころイギリスの自由主義的改革が進められており、第1回の選挙法改正が行われ、七月革命の民衆の勝利の影響を受けて選挙権の拡大を要求するチャーティスト運動が盛んになった。 |
| a ベルギーの独立 | 1830年、フランスの七月革命の影響を受けたベルギーが、オランダから独立した。
オランダ領となるまで:ベルギーはネーデルラントの南部諸州のことで、北部と共にスペイン=ハプスブルク家の領地であったが、北部がオランダとして独立(1648年)した後も、カトリックの勢力が強かったため初め独立しなかった。後にオーストリア=ハプスブルク家領となって続いていた。18世紀末にフランス革命の影響を受けて独立運動が起こったが、達成する前にオーストリアがナポレオンによって倒され、その後1815年にウィーン議定書の結果、オランダによってベルギー併合がおこなわれた。
ベルギー独立:ベルギーはオランダの支配(保護貿易の強制、教育の統制、公用語オランダ語の強制など)に不満を強め、フランスで七月革命が起こると、ベルギー独立運動に飛び火し、オランダ国王ウィレムに対する自治要求となってあらわれた。国王はそれに対し、ブリュッセルに軍隊を派遣、1830年9月、3日間の戦闘となった。市街戦のさなか25日臨時政府を樹立、29日議会は分離を決定した。10月4日独立宣言。翌1831年、ロンドン会議でベルギーの独立が認めら、レオポルド1世が即位し、立憲君主国として国際的に承認された。1839年にはオランダもベルギーを永世中立国として承認した。なお、これによってフランドル地方は北部がベルギー領(フランデレン)となり、南部がフランス領とされることとなった。
ベルギーの産業革命:中世以来の毛織物産業や、商業資本の蓄積を生かし、独立を達成した1830年代にイギリスに続いて産業革命を展開し、工業化を進め、小国ながらヨーロッパ有数の工業国となっている。逆にベルギーを失ったオランダは財政的に苦しくなり、植民地のオランダ領東インドで強制栽培制度という収奪を強めることとなる。 → ベルギーの産業革命 → 現在のベルギー王国
Epi. ベルギーの1830年「音楽革命」 フランスの七月革命が起こると、8月25日、ブリュッセルのラ=モネ劇場でスペインからのナポリの独立をテーマにしたオベール作曲のオペラが上演され、その最後の場面で「さよなら祖国愛よ、復讐をとげん、自由よ、わが宝、まもりてたたかわん‥‥」と唱われると、観衆が立ち上がってこれに唱和し、街頭に出た群集が暴動を起こした。独立運動はたちまち全土に広がり、ついに独立を勝ち取った。 |
| b ポーランドの独立運動
| ウィーン会議でロシア皇帝の支配を受けることとなったポーランド立憲王国で、フランスの七月革命の影響で起こった独立運動。1830年11月25日、ワルシャワの士官学校でロシア人教官が二人の若い生徒をむちで打とうとしたのをきっかけに、反乱が始まった。コンスタンチン大公(ポーランド総督。ロシア皇帝ニコライの兄)の宮殿を襲い、30名の生徒が侵入した。大公は頭に負傷したが危うく逃れ、反乱軍はワルシャワで秘密警察の隊長を縛り首にした。フランスから義勇兵がかけつけ、不揃いの武器が国境をこえて密輸された。プロイセン、オーストリアは革命の飛び火を恐れてツァーリを助けようとした。ポーランド革命勢力の中にも急進派と妥協的な保守派が対立していた。31年1月、急進派のジャコバン人民派が政権を握って国会を開き、独立を決定。それに対して2月にロシア軍が進撃を開始。ポーランドは4月30日に独立を宣言したが、9月8日にロシア軍がワルシャワを制圧し、ポーランド独立運動は押さえられてしまった。その後、1846年にはポーランド南部のクラクフで独立運動が起こったが、オーストリア・プロイセン・ロシア三国の軍隊によって鎮圧された。1848年にフランスの二月革命、ウィーンとベルリンでの三月革命が勃発してウィーン体制が崩れ、ヨーロッパに「諸国民の春」といわれる民族独立運動の大きなうねりが起きると、ポーランドでもポスナニとガリツィアで独立運動が起こったが、それぞれプロイセン軍とオーストリア軍によって鎮圧されてしまった。さらに1863年の1月にはポーランドの反乱が起きるが、それもロシアに抑圧され、ポーランドの独立が達成されるのは、第1次世界大戦とロシア革命を待たなければならない。 |
| c ワルシャワ (陥落) | ウィーン体制下のポーランド独立運動が激化するなか、1831年9月、ロシア軍はワルシャワに総攻撃をかけ、8日ついに占領、1万5千にのぼる亡命者がフランスに逃れた。ニコライ1世はポーランドを事実上属州にし、ロシア化政策をとった。
Epi. ショパンの『革命』 ショパンは前年30年の冬、20歳でウィーンに演奏をしていた。独立戦争の勃発に熱狂して帰国しようとしたが、父親に音楽に生命をかけるよう手紙で説得される。31年7月パリに向かい、途中シュツットガルトでワルシャワ陥落のニュースを聞く。その衝撃が作品10第12のハ短調練習曲『革命』である。 |
| ドイツの反乱(1830)
| |
| イタリアの反乱(1831)
| フランスの七月革命の影響を受けてイタリアで起こったオーストリアからの独立と自由を求める民衆蜂起。パリに亡命していた自由主義者ブォナローティらが指導し、中部イタリアのモデナ、パルマ、ボローニャで1831年2月に勃発し、ボローニャには一時臨時政府が成立した。反乱側はフランスの七月王政政権の支援を期待したがその介入もなく、また各都市間の連携もなかったので、3月末にはオーストリア軍の出動によって鎮圧された。カルボナリの蜂起に続いてイタリアの統一と独立を目指す運動が挫折したことを反省したマッツィーニらは、同年末に亡命先のマルセイユで、より明確な方針を掲げた組織として「青年イタリア」を結成する。 |
| イギリスの諸改革
| |
| A 自由主義的改革の進行
| 18世紀前半の20年代から40年代にかけて、ウィーン体制の時期のイギリスは、ナポレオン戦争の痛手から回復し、産業革命がさらに進展して産業資本家が進出、並行して労働者階級も成長してさまざまな権利を要求するようになった。特に1830年のフランスの七月革命による接待王制の打倒されたことに影響されて諸改革が進んだ。政治面ではホイッグ党(自由党)が有力となり、自由主義的な改革を主張するようになった。この間ホイッグ党(この頃から自由党と称するようになる)のグレー内閣のもとでいくつかの改革が実現し、その後のトーリー党(このころから保守党と称するようになる)内閣もその路線を継承したので、この時期にイギリスの経済と政治両面での改革が進んだ。これによってイギリスは資本主義の自由な市場経済原則と、議会制民主主義という近代社会の二本の柱を確立させ、次の18世紀後半のヴィクトリア朝時代の繁栄をもたらすこととなる。この時期の自由主義的改革には次夜のようなものが挙げられる。
カトリック教徒の平等の実現:オコンネルら、カトリック教徒の運動が成果を上げ、1828、年審査法の廃止。1829年のカトリック教徒解放法。これによって非国教徒であるカトリック教徒も公職就任ができるようになった。しかしアイルランドの独立問題は解決されなかった。
選挙制度の改正:1832年、第1次選挙法改正。産業資本家の政治参加が実現した。しかし、労働者階級への選挙権付与は無かったので、30年代後半からチャーティスト運動が始まった。
自由貿易政策:コブデン・ブライトら、反穀物法同盟の運動が盛んとなり、1846年に穀物法が廃止され、さらに1849年には航海法が廃止された。それより前、1833年に奴隷制度廃止法が成立(奴隷貿易禁止法はすでに1807年に制定。)また、1834年には東インド会社の中国貿易独占権も廃止された。これら一連の政策によって、絶対王政時代以来の重商主義(保護貿易主義)は終わり、自由貿易政策が採られることになった。
社会政策の改良:1824年に団結禁止法が廃止され、労働組合が多数結成されるようになった(法的公認は1871年の労働組合法制定)。1833年には一般工場法が制定され、労働者保護の立法措置が行われた(その後も改良が続く)。 |
| a 審査法の廃止 | → 第10章 1節 ウ.イギリス議会政治の確立 審査法 |
| b カトリック教徒解放法
| 1829年成立したイギリスの法律で、カトリック教徒が公職に就くことを認めたもの。イギリスではエリザベス1世による国教会の確立以来、カトリック教徒はきびしく差別されていた。特に1673年の審査律で公職から排除されていた。つまり、国会議員にもなれない、ということであった。カトリック教徒の多いアイルランドで、カトリック教徒への差別に反対する運動が起こり、1828年その指導者オコンネルは、自ら下院議員選挙に立候補して当選したが、審査律に阻まれて議席につくことが出来なかった。これを機に運動が盛り上がり、翌年、「カトリック教徒解放法」が制定され、カトリック教徒に国教会教徒と同等の権利が認められた。しかし、アイルランドにおけるカトリック教徒への差別的な感情はなくならず、その後も「アイルランド問題」として現代まで続いていく。 |
| c オコンネル
| |
| d 奴隷制度廃止
(イギリス) | イギリスの奴隷制度廃止:1833年のグレー内閣(ホイッグ党)の時に実現した、自由主義的改革の一つ。イギリスの奴隷貿易は、重商主義政策の柱の一つで、イギリスとアフリカ西岸、北米大陸・カリブ海域を結ぶ三角貿易の中で大きな利益をもたらしていた。またアメリカ植民地だけでなく、イギリス国内でも黒人奴隷制度が認められていた。しかし、18世紀中ごろに始まる産業革命を経て自由貿易主義が台頭すると批判的な声が強くなり、特にキリスト教の人道的な立場からウィルバーフォースらが奴隷制反対を主張するようになった。まず、1807年には奴隷貿易禁止法が実現し、さらにそれを実質的なものにするためには奴隷制度そのものの廃止が必要と考えられるようになり、1823年には奴隷制度反対協会が結成され、32年の第1回選挙法改正の翌年、1833年に奴隷制度廃止法が成立した。これはイギリス帝国内における奴隷制度を廃止するもので、奴隷所有者に賠償金200万ポンドを払う有償方式で実施され、38年までに完了した。これによってイギリス帝国内の西インド諸島、アフリカ西海岸の比重は小さいものとなった。なお、奴隷制度廃止が決定された1833年は、一般工場法も制定されており、いずれも自由主義改革の重要な内容である。<山川世界各国史『イギリス史』旧版 p.220,514>
イギリス以外の奴隷制度廃止:フランスでは革命で一時停止が決まったが、ナポレオンが復活させた。その後、1820年に奴隷貿易を禁止し、48年には奴隷制度を廃止した。アメリカ合衆国では、独立宣言の草稿には奴隷制度廃止が入っていたが実現せず、1833年にギャリソンらがアメリカ反奴隷制協会を設立し、奴隷解放運動が始まり、南北戦争の最中の1863年にリンカン大統領が奴隷解放宣言を発表、奴隷制廃止は南北戦争終結後のアメリカ合衆国憲法修正13条で正式に廃止された。 |
ウィルバーフォース
| 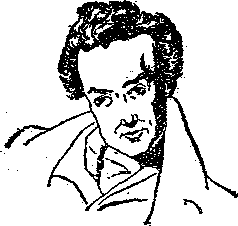 イギリスの奴隷貿易禁止および奴隷制度廃止に大きな役割を果たした政治家。貴族の出身で、キリスト教福音主義(教会によらず、個人の宗教的会心を重視する新教徒)の影響を受け、人道的な立場から奴隷貿易の禁止を主張するようになった。有力政治家の小ピットに働きかけ、1807年に奴隷貿易禁止法を、さらに1833年にはイギリス帝国全域の奴隷制度廃止法の制定を実現させた。 イギリスの奴隷貿易禁止および奴隷制度廃止に大きな役割を果たした政治家。貴族の出身で、キリスト教福音主義(教会によらず、個人の宗教的会心を重視する新教徒)の影響を受け、人道的な立場から奴隷貿易の禁止を主張するようになった。有力政治家の小ピットに働きかけ、1807年に奴隷貿易禁止法を、さらに1833年にはイギリス帝国全域の奴隷制度廃止法の制定を実現させた。
左図 William Wilberforth 1759-1833 (BRITAIN'S STORY Told in Picture p.60) |
| B 選挙法改正運動
| → 第12章 2節 イギリス 選挙法の改正 |
| a 腐敗選挙区
| 当時の選挙区は16世紀の区割りのままであったので、産業革命に伴う人口移動の結果、農村部の人口の激減した地域の選挙区が存在し、一方、マンチェスターやバーミンガムなどの工業都市では一人の議員選出もできなかった。 |
| b 第1回選挙法改正 | 1832年、ホイッグ党のグレイ内閣のもとで行われたイギリス最初の選挙制度の改正。新たに選挙権を与えられたのは、都市では10ポンド以上の家屋の所有者または借家人、地方では10ポンド以上の土地保有者と長期借地人など。また、都市に多く議席が配分されるよう選挙区の区割りを変更し腐敗選挙区を無くした。その結果、有権者は16万から96万に増加したが、その多くは都市の中産階級であり、有権者の全人口に占める割合も、わずかに4.5%にすぎなかった。議員の被選挙権も改正されなかった。労働者階級の普通選挙を求める声はさらに強くなり、チャーティスト運動となる。 |
| グレイ
| イギリスのホイッグ党(自由党)の政治家で、1830年〜34年の間首相を務め、第1次選挙法改正や一般工場法、奴隷制度廃止法の制定などの自由主義的改革を進めた。第1次選挙法改正案にたいしてはトーリー党は貴族院を拠点に徹底して抵抗したためすぐには成立しなかった。議院の外では、グレイ内閣を支持する中産階級の市民が盛んに運動し、また労働者層はグレイ案よりも普通選挙を要求して運動を起こし、各地で民衆と軍隊が衝突した。グレイはいったん総辞職して下院の総選挙に打って出て勝利を占め、下院で法案を通した。貴族院側はなおも抵抗したが、グレイは新貴族を任命する手続きをほのめかして貴族に妥協を迫った結果、32年6月にようやく成立した。 |
| C チャーティスト運動
| 第1次選挙法改正で選挙権が認められなかった都市の労働者階級による、普通選挙を議会に要求する請願運動。1838年に「人民憲章」(People's Charter)に普通選挙などの要求を盛り込んで誓願したので、彼らはチャーティストと言われた。1839年と42年は特に盛り上がり、議会で審議されたが、共に否決された。労働者は請願行動にとどまらず、小規模ながら武装蜂起したり、ランカシャーなどでのストライキなどが闘われた。1842年以降は、イギリスの景気が鉄道建設ブームで好転し、運動は停滞するようになった。1848年にフランスの二月革命に刺激されて最後の高揚期を迎え、第三次請願運動が行われたが、その後は急進派と穏健派の対立などもあって運動は衰退した。
Epi. インチキ署名簿・・・請願運動の限界 1848年の第三回請願は200万近い署名簿を指導者のオコンナーを先頭に議会に届けようとした。しかし請願のデモ行進は15万人の大警備陣によって阻止されてしまった。やむなく馬車で議会に届けられることになった署名簿を点検したところ、そのなかには、獅子っ鼻、団子っ鼻、ヴィクトリア女王、ウェリントンといったインチキ署名が多数発見されため、オコンナーたち指導者の面目は丸つぶれとなり請願ション提出は断念された。<村岡健次『世界の歴史』22 中央公論新社 p.405> |
| a 「人民憲章」
| People's Charter 1838年、ロンドン労働者協会のラヴェットらが議会への請願書としてまとめたもの。1830年代末から40年代にかけて盛り上がった、都市労働者の普通選挙を要求するチャーティスト運動の請願書。次の6ヵ条から成る。1)成年男子の普通選挙権、2)秘密投票、3)毎年の選挙と1年任期の議会、4)被選挙資格の財産による制限の廃止、5)議員への歳費支給、6)10年ごとの国勢調査により調整された平等選挙区。 |
| D 自由貿易主義の実現
| 絶対主義時代の重商主義政策が依然として継承され、さらに穀物法などの地主階級保護のための貿易政策がとられていたが、産業革命の進行に従って、資本家階級からも自由な貿易を求める声が強くなってきた。自由貿易主義の理論は、産業革命の進行中に発表された1776年のアダム=スミスの『国富論』(諸国民の富)である。彼は「神の見えざる手」によって導かれる社会正義の中での経済活動の「自由放任主義」(レッセフェール)を主張した。1830年代〜40年代の一連の改革、つまり1833年の奴隷制度廃止、1846年の穀物法廃止、1849年の航海法の廃止などによって自由貿易主義の思想が実現した。その結果、1830年代から70年代のイギリスは「世界の工場」として繁栄したが、イギリス資本主義のための世界市場の拡張という基本を掲げ、自由貿易を推進したのがパーマーストン外交である。1840年のイギリスの中国とのアヘン戦争、50〜60年代の日本に対する開国要求などは清朝や江戸幕府の管理貿易を打破し、自由貿易を強要するものであった。一方、インドに対しては50年代にインド大反乱を鎮圧して、東インド会社による統治から政府による直接統治に改めたのである。 |
| a 東インド会社
(19世紀) | 東インド会社は、1600年創設以来、インドと中国の貿易の独占権を与えられていたが、18世紀末以来、インド−中国−イギリス本国をむすぶ三角貿易が進展する中で、自由貿易を求める声が強まった。また産業革命の進展は自由貿易主義の要求を強め、1813年には東インド会社のインド貿易の独占権は廃止され、さらに1833年には、インドでの商業活動は全面的に停止され(東インド会社はインド統治機構のみとなる)、翌34年には中国貿易での独占権も廃止された。1857年のインド大反乱(セポイの反乱)の翌58年、東インド会社そのものが解散する。 |
| b アヘン戦争
| → 第13章 3節 アヘン戦争 |
| c コブデン
| イギリスのマンチェスターで綿工業を営み成功した産業資本家。1838年、ブライトらとともに、穀物法の廃止を求める反穀物法同盟を結成し、時の保守党政権の保護貿易主義に反対し、自由貿易主義への転換を進める運動の指導者となった。41年からは自由党の下院議員となり、1846年に穀物法廃止を実現させた。 |
| d ブライト
| イギリスのマンチェスターで綿工業を営みながら、1838年にコブデンらとともに穀物法の廃止を求める反穀物法同盟を結成した。43年から自由党員として下院議員に当選、46年には穀物法の廃止を実現させた。その後も自由貿易政策の推進に努め、何度か大臣も務める。1886年、アイルランド自治法案でグラッドストンに反対して自由党を離党した。 |
| e 反穀物法同盟
| 1838年、イギリス綿工業の中心地であったマンチェスターの綿織物業者は、保護貿易の廃止と自由貿易政策への転換を要求し、特に穀物法(1815年制定)の廃止にしぼって圧力団体を結成した。これが反穀物法同盟で、自由党員であるリチャード=コブデンとジョン=ブライトが運動を指導した。このグループはマンチェスター派ともいわれた。運動は労働者層の支持も受けて盛り上がり、1846年に穀物法の廃止を実現させ、自由貿易政策に転換させた。 |
| 穀物法
| Corn Law 穀物法は1815年、地主や農業資本家が多数を占める議会で成立した。ナポレオン戦争後、ヨーロッパからの穀物輸入が増え、穀物価格が下落し、農業不況の様相となったので、時のトーリー党(保守党)政府は「小麦価格が1クォーター80シリング以下の時は小麦の輸入を禁止する」という穀物法を制定した。これは地主や農業資本家の利益を守るねらいから定められた保護貿易政策であり、そのため穀物価格は高くなって消費者である都市住民、労働者が反発し、またそのため貿易も停滞して工業製品(綿織物など)の輸出が阻害されたので、産業資本家も強く反発するようになった。 |
| リカード
| → リカード |
| f 穀物法廃止
| 1846年のイギリスでの穀物法廃止は、「伝統的な支配階級で農業に経済的基盤を持つ地主階級と、工業化を主導する新興ブルジョワ階級の利害がついに正面衝突し、工業の利害が凱歌をあげた自由貿易運動のクライマックス」であった。
穀物法は1815年に地主の利益を守るために、外国からの小麦輸入を制限する法律。産業革命が進行し、産業資本家が成長すると、彼らは工業製品の自由な輸出を阻害する穀物法に反対するようになった。また産業革命に伴う都市への人口移動によって生まれた都市の市民、労働者など広範な消費層も、こぞって穀物法に反対するようになった。その中心になったのが、1838年にマンチェスターで結成された、コブデンとブライトなどが指導する反穀物法同盟である。自由貿易主義者はこの穀物法廃止を最も強い要求としてかかげ、盛んに世論を喚起した。その結果、1846年に保守党ピール内閣は穀物法廃止に踏み切った。これは、奴隷貿易廃止(1833)、航海法の廃止(1849)と並んで、自由貿易主義の勝利を意味する出来事であり、資本主義の完成した段階に入る前提となったといえる。 → 農業革命
穀物法廃止の背景:地主階級を基盤とする保守党は穀物法堅持を党方針としていたが、首相のロバート=ピール自身は大綿業家の息子で、自由貿易派だった。穀物法反対が盛り上がると廃止に踏み切るタイミングを計っていたかもしれない。1845年にアイルランドでジャガイモ飢饉が起きると情勢は大きく転換した。ピールはついにマンチェスター派に同調し、廃止に踏み切った。こうして党首に裏切られた保守党は分裂し、翌年穀物法廃止法案は議会を通過した。 |
| g 航海法廃止 | 1849年、自由貿易主義政策の一環として航海法が廃止された。航海法(航海条令)はピューリタン革命の時、クロムウェルが1651年に制定したもので、イギリスに運ばれるヨーロッパ以外の産物、商品はすべてイギリスの船で運ばれること、またヨーロッパの産物、商品はイギリス船かその産出国の船で運ばれることを定めた。ねらいは、当時海上貿易権で争っていたオランダが中継貿易(自国産品でない商品を中継する)で利益を上げていたことに打撃を与えることであった。航海法制定の翌年から英蘭戦争が勃発した。その後もイギリスの保護貿易政策の一環として、継承されていた。産業革命後、成長した産業資本家たちはイギリス産品を自由に輸出するためには航海法は障害になるとして廃止を主張した。 |
| h パーマーストン外交 | パーマーストンは1831年〜65年の間、約10年を除き、外相あるいは首相として、イギリスの外交を推進した政治家(はじめトーリ党、後にホイッグに移る)。この間のヴィクトリア朝前半のイギリス外交を「パーマーストン外交」という。その基本は、自由貿易主義の理論に立ち、イギリス資本主義の世界市場の拡張にあたり、ヨーロッパ列強とは勢力均衡を図りながら、東欧やアジアの専制国家に対しては開国と自由貿易を要求するものであった。この段階のイギリスは、自由市場の拡大が主要な目的であり、次の19世紀後半からのディズレーリ以降の帝国主義的外交と区別されるが、その手段はアヘン戦争やインド支配に見られるように抵抗があれば武力を行使する点で同じ性格のものであった。イギリス国内の選挙法改正や労働者保護法の制定など、自由主義社会の枠組みが形成られる一方で、武力に訴える植民地政策をとっていたことを忘れてはいけない。また日本の開国の時期がイギリスではパーマーストン外交の時期に当たっていることも注目する。以下、この時期のイギリス外交の主要な内容。
・東方問題への介入 1831年〜 エジプト=トルコ戦争で両勢力を調停 1840年 ロンドン会議
・トルコ=イギリス通商条約 1838年 アジア諸国への不平等条約押しつけの最初
・中国侵出 1840〜42年 アヘン戦争 → 南京条約、 1856〜60年 アロー戦争 → 北京条約
・白人植民地の自治付与 1840年 カナダを最初の自治植民地とする
・クリミア戦争 1853〜57年 ロシアの南下政策に対し、フランスなどと協力してオスマン帝国を支援
・インド支配 1857〜59年 インド大反乱を鎮圧、 1858年 東インド会社解散
・イタリア統一戦争 1859年〜 ガリバルディらのイタリアの統一を支援 |
 |
| エ.社会主義思想の成立
|
| 初期社会主義 | 以下のロバート=オーウェン、サン=シモン、フーリェなど、19世紀初頭の産業革命期に現れた、資本主義社会の改革をめざし、労働者の状態の向上をめざす思想。いずれもブルジョアジーの立場からの改良に止まり、社会改革の理念と手段とを持たなかったところから、19世紀中葉のマルクス、エンゲルスからは「空想的社会主義」と批判された。 |
| ロバート=オーウェン | ロバート=オーウェン(英)は紡績会社の経営に成功したが、労働者の貧困という現実を見て、その救済を目指した。はじめは資本家の努力による社会改良が可能と考え、自らもニューラナークに人道主義的な紡績工場を造った。法律と教育によって労働者の環境を改善できるという考えていたが、1813年頃から社会主義的改革を主張するようになり、労働運動や協同組合運動を指導するようになった。1825年にはアメリカに渡ってニューハーモニー村という共産制社会の実験を行ったが失敗した。 |
| サン=シモン | サン=シモン(仏)は貴族の出であるがアメリカ独立戦争にも参加した自由主義者として出発し、ナポレオン戦争時代には独自のヨーロッパ連合の構想や産業社会の到来を予測した。労働者の解放は階級闘争に依ってではなく、ブルジョアジーの助力によって実現できると考えた。 |
| フーリエ | フーリエ(仏)は商人の家に生まれ、フランス革命で財産を失い、革命後のブルジョア社会を投機と利益追求に走るものとして批判、また産業革命によって生み出された労働者の労働も無味乾燥なものとなって人間性が失われていると指摘した。自ら2000人程度の「協同体」をつくり成員が農業中心に生産と消費を行うという社会を作ろうとした。 |
| 空想的社会主義 | |
| 一般工場法 | 1833年にイギリスで制定された工場での労働条件に関する法律で、1802年の工場法から始まる労働者保護のための立法を本格化したもの。イギリスの、つまり世界最初の労働者保護法は1802年の「工場法(徒弟法)」でったが、その内容は不十分なものだった。1819年にオーウェンの努力で「紡績工場法」ができ、9歳以下の労働の禁止と16歳以下の少年工の労働時間を12時間に制限された。しかし、監督官制度が無かったために実行力はなかった。1833年の「一般工場法」では、12時間労働、9歳未満の労働禁止、18歳未満の夜業禁止、工場監督官の政府任命などが定められた。同じ1833年には奴隷制度廃止法も成立している。 |
| ルイ=ブラン | |
| プルードン | 19世紀フランスの無政府主義思想の創始者の一人。ピエール=プルードン(1808〜65)はカール=マルクスと同時代の人であり、マルクスの論敵であり、ルイ=ナポレオンに追放された人物。プルードンは学校を中退した後、地元ブザンソンの印刷所に就職、仕事を通じて同郷の社会主義者フーリエを知り、影響を受けた。印刷所を経営したが失敗した後、奨学金を得てパリに出て勉学に専念し、1840年『所有とは何か』を発表し、”所有とは盗みである”という衝撃的な文言で評判となった。1846年には『貧困の哲学』を発表し、経済的な矛盾の中で生きるためには社会の成員が相互に共同する事が必要であるという「相互主義」を打ち出した。この著作はマルクスから強烈な批判を受けたことで有名になった。プルードンは著作にとどまらず、相互主義を実戦して「人民銀行」を設立して、貨幣にかわる「交換券」を発行し、資本主義の事情自由主義の競争社会を克服しようとした。この思想は、市場原理主義が行き詰まっている21世紀の現在、バングラデシュで試みられているグラミン銀行など「貧者の銀行」の源流となる思想として注目されている。<本山美彦『金融権力−グローバル経済とリスク・ビジネス』2008
岩波新書 p.189-198>
→ アナーキズム(無政府主義) |
| B 科学的社会主義
| 資本主義社会の矛盾を科学的に追求し、社会の変革をめざす思想。フランスの初期社会主義・ヘーゲルやフォエルバッハなどドイツ哲学・イギリスの古典派経済学を批判的に摂取し、単なる思想に止まらず、資本主義社会の克服、現実の労働者の解放、をめざす革命運動を指導した。19世紀中葉の資本主義勃興期にドイツのマルクスとエンゲルスによって体系づけられ、社会主義革命運動は大きな潮流となり、帝国主義の矛盾が激化する中で最初の社会主義革命であるロシア革命(1917年)を実現した。 → 帝国主義下の社会主義運動 |
| a カール=マルクス
| カール=マルクス(1818〜1883)は、ドイツのトリアーに生まれ、はじめ急進的な共和主義者として活動したが、次第に社会主義に移り、1848年、エンゲルスと共に『共産党宣言』を発表。ドイツの革命運動を指導。その思想はヘーゲル哲学から出発し、フォイエルバッハの唯物論、フランスの初期社会主義、イギリス古典派経済学を批判的に摂取して、独自の史的唯物論・弁証法的な階級史観などを体系づけた。とくにイギリス亡命中に書かれた『資本論』(第1部は1867に発表)は、徹底的に資本主義の矛盾を明らかにする「マルクス経済学」の理論を作りだした。マルクスはまた思想家であるに止まらず、第1インターナショナルの結成などの革命運動の先頭に立った。 |
| b フリードリッヒ=エンゲルス
| フリードリッヒ=エンゲルス(1820〜95)はドイツのライン州に生まれ、イギリス滞在中に資本主義の実態を見て共産主義に共鳴し、パリでマルクスと会い、その協力者となった。マルクスと共に『共産党宣言』を執筆、共産主義者同盟の指導に当たった。ドイツの革命運動運動が退潮してからはマルクスと同じくイギリスに渡り、マンチェスターで会社勤めをしながら、マルクスを援助。その死後は、草稿を整理して『資本論』第2部(85)、第3部(94)として刊行した。 |
| c 『共産党宣言』
| 1848年2月末、ロンドンで刊行された、マルクスとエンゲルスの共著。前年の6月、ロンドン発足した『共産主義者同盟』の宣言を出すことになり、その起草がブリュッセルとパリに亡命していたマルクスとエンゲルスに依頼された。出来上がった原稿は二月革命の数週間前にあたる1月末に印刷のためロンドンに送られ、48年2月末、ロンドンで本となった。3月20日ごろパリに千部ほど送られたらしい。<岩波文庫版解説P.105-6>
『共産党宣言』の有名な冒頭の一節。『ヨーロッパに幽霊が出る−共産主義という幽霊である。ふるいヨーロッパのすべての強国は、この幽霊を退治しようとして神聖な同盟を結んでいる、法皇とツァー、メッテルニヒとギゾー、フランス急進派とドイツ官憲。‥‥共産主義はすでに、すべてのヨーロッパ強国から一つの力と認められている‥‥』<岩波文庫『共産党宣言』P.37> |
| マルクス主義 | 史的唯物論に立ち、資本主義権力を革命によって倒し、労働者の解放を目ざす。 |
| 社会主義 | 私有財産を否定し産業の国有化など計画経済によって平等な社会の実現を目ざす。 |
| 共産主義 | 社会主義をによって労働者の解放と平等社会を実現させ、理想社会を目ざす思想。 |
 |
| オ.1848年の変革
|
| 1848年革命 | 1848年はヨーロッパ各地で保守反動の君主制国家に対する、自由主義・ナショナリズムの反乱が連鎖反応的に起こり、一挙にウィーン体制が崩壊した。フランスの七月王政を倒した二月革命、ウィーンとベルリンにおける三月革命、さらにメッテルニヒの失脚というオーストリア帝国の動揺に乗じた、その支配を受けていた諸民族の独立運動である、イタリアのマッツィーニによるローマ共和国の建国、ミラノとヴェネティアなどイタリアでの革命、またハンガリーの独立運動など、この年に起きた一連の革命を「1848年の革命」と総称する。この年の2月にマルクスとエンゲルスの『共産党宣言』が刊行されている。 → 1848年 |
| A 七月王政 | → 七月王政 |
| a 選挙法改正運動(フランス)
| 1830〜40年代の七月王政期にフランス産業革命が進行、都市の労働者人口が増えてきたが、彼らは経済的な困窮にさらされ、また不況期には失業者が生まれていた。当時の選挙権は納税額200万フラン、被選挙権は同じく500万フランという財産による制限が加えられていたため、労働者は政治的にも無権利の状態に置かれていた。ルイ=ブランなどの社会主義思想も生まれ、彼らは普通選挙を実現して労働者の参政権を獲得することによってその地位を高めようと考え、一部のブルジョワの支持も受け、41年から毎年のように選挙法改正案が議会に提出された。しかし上層ブルジョワを基盤とするギゾー内閣は普通選挙の実施をかたくなに拒否したため、運動は激しさを増し、官憲の取り締まりをさけるため、改革宴会という形をとって運動が繰り広げられた。その高まりの中から、1848年の苦く革命が勃発し、七月王政とギゾー内閣が倒れ、普通選挙制が実現されることとなる。 |
| b 改革宴会
| フランスの七月王政末期に、市民と労働者が普通選挙制の実現を要求して開催した政治的集会。時のギゾー内閣は政治集会を禁止していたので、取り締まりを逃れるために、「宴会」と称してレストランなどで開催されたので改革宴会という。1848年2月、政府が改革宴会禁止を打ち出したことを機に二月革命が勃発した。
「改革派の野党議員は47年7月9日、モンマルトルに近い街角のシャトー・ルージュとよぶダンスホールで大宴会を開いた。参加者はパリの有権者1200名、会費は10フランだった。宴会戦術は取締法の裏をかくプロパガンダで、7月から12月末まで70回ほど行われ、2万近い会衆を動員した。」<井上幸治『世界の歴史12』中公版p.334
P.339-341> |
| B 二月革命(フランス) | 1848年2月、パリの市民、労働者が蜂起して、七月王政を倒した革命。フランスに共和政を復活させた二月革命はただちにベルリンとウィーンに飛び火して三月革命を勃発させ、ウィーン体制を崩壊させた。
1848年「2月13日改革派は政府の禁をおかして22日にパリ十二区で改革宴会を開催することを決定。……当日朝パリの労働者・学生が続々集結し、マルセイエーズとA=デュマのはやらせたという「ジロンド党員の歌」を唱いながらデモ行進、コンコルド広場からブルボン宮殿に向かい議会に示威運動を行い、バリケードを築いた。 翌23日、国民軍の大半が民衆に共鳴。ルイ=フィリップ、ギゾーを罷免してモレに組閣を命じる。赤旗(労働者の旗として用いられた最初か)を掲げたデモ隊が外務省に向かうと、キャプシーヌ街で守備していた政府軍が一斉射撃し、50名ほどが死亡。 24日モレ首相組閣できず。国王、ティエールに組閣を命じ、ビュジョー元帥に鎮圧に当たらせようとしたが、ティエールはリヨン暴動の、ビュジョーはトランスノナンの虐殺の張本人であったのでかえって民衆は激昂、民衆は武装してチュイルリー宮を襲撃、国王一家はからくも脱出したが、宮殿は民衆の手で荒らされた。急進共和派(ルイ=ブランら)は『レフォルム』、ブルジョア共和派(ラマルティーヌら)は『ナショナル』の各新聞を本拠とし、革命後の政権を構想した。議会ではユゴーなどは君主制維持を主張したが多数で否決され、臨時政府設立が決定される。……その夜遅く、共和政を宣言。」<井上幸治『世界の歴史12』中公版P.343-354> → 第二共和政
※文学上の二月革命:フローベールの『感情教育』(1869)<生島遼一訳 上下 岩波文庫>は、この二月革命からルイ=ナポレオンのクーデター事件までのパリを舞台とした小説で、これらの事件が生々しく再現されている。 |
| a 1848年
| 19世紀のほぼ中頃にあたるこの年は、世界史上の重要なことが集中して起こっている。その同時性に注目しておこう。まず1848年革命といわれる一連の二月革命、三月革命でウィーン体制が崩壊した。それをうけてオーストリアに抑圧されていた民族の独立運動が一斉に起こった。この自由主義・民族主義の高揚は「諸国民の春」と言われてた。フランスに第二共和政が成立、イギリスでは議会政治の発展の中で労働者の選挙権要求であるチャーティスト運動の最後の高揚を見せ、一方では前年の46年に穀物法廃止、翌49年の航海法廃止で自由貿易主義が勝利を占めている。ドイツでも統一と民主化をめざす運動が激化し、イタリアではマッツィーニらの青年イタリアが一時権力を握り、ローマ共和国を建国。アメリカではカリフォルニアでの金鉱の発見によってゴールド=ラッシュが起こり、その勢力が太平洋岸まで及ぶ。時代はこの年を転換点として、ウィーン反動期から資本主義の全盛期としての19世紀後半へと移っていく。ヨーロッパ社会の新たな対立軸は、従来の絶対君主対市民ではなく、資本家階級と労働者階級という階級対立に移ったことを示すのが同年に発表されたマルクスとエンゲルスの『共産党宣言』であった。同時に世界全体ではヨーロッパ資本主義諸国によるアジア、ラテンアメリカ諸地域への植民地支配の本格化とそれへの抵抗の始まりというテーマに移行していく。アジアではイランでバーブ教徒の反乱が起こっている。その前後に1840年のアヘン戦争、50年代の太平天国の乱、アロー戦争、1857年のインド大反乱が起こったことを想起しよう。→1848年(アメリカ) |
| b ギゾー内閣
| 七月王政の国王ルイ=フィリップのもとでギゾーが組織した内閣。パリなどの都市で強まってきた市民や労働者の普通選挙制度要求を厳しくはねつけた。ギゾーは選挙権がほしければ「金持ちになりたまえ!」と言ってのけて反発を受けたことで有名。ギゾーは歴史家としても著名で、『ヨーロッパ文明史』などの著作がある。七月王政で文部大臣となり学制の改革に当たり、1840年からは首相として国政に当たった。保守主義の立場から自由主義には厳しく反対し、改革派の批判の的となった。二月革命で失脚しイギリスに亡命、その後は文筆に専念した。 |
| c ルイ=フィリップ
| → ルイ=フィリップ |
| C 第二共和政 | 1848年の二月革命によって成立したフランスの共和政。フランス革命時の第一共和政(1792年9月〜1804年5月)に次ぐ共和政。当初は社会主義者も含む臨時政府のもとで改革が進められたが、経済不安が続き、国立作業場の廃止に伴い労働者の暴動が起こり(六月暴動)、王党派の勢力が増大するなど、動揺が続いた。第二共和政憲法は人民主権、三権分立、大統領制を採用したが、48年末の大統領選挙で当選したルイ=ナポレオンは、51年にクーデターを起こし、憲法を修正して、52年1月ナポレオン3世として即位して第二共和政は終わった。 |
| a 臨時政府 | 2月24日、その夜遅く、共和政が宣言され、第二共和政が発足。臨時政府の11閣僚の内、七名はブルジョア共和派(ナショナル派。ラマルティーヌら)、四名は急進共和派(レフォルム派。フロコン、ルドリュ=ロランは小市民、アルベール、ルイ=ブランは労働者)。武装をまだ解かない労働者・秘密結社員は、赤旗を革命の旗とするよう政府に要求したが、ラマルティーヌは「秩序」と「財産」を代表して雄弁をもってその要求を拒否、三色旗を国旗として採用した。2月25日、普通選挙制を宣言、4月に憲法制定議会選挙を約束、3月、植民地の黒人奴隷制を廃止、奴隷主には1人60フランを賠償、など改革を推進した。 |
| b ルイ=ブラン | → ルイ=ブラン |
| c 国立作業場 | 1848年の二月革命で七月王政を倒し、臨時政府に加わった社会主義者ルイ=ブランが中心となって設置した、失業者救済のための施設。臨時政府はまずすべての市民の労働権と生活権を保障する布告を出し、ついで2月28日、ルイ=ブランを総裁とする労働者対策委員会を設置、国立作業場(アトリエ=ナショナル)をつくることとした。この委員会は3月にはパリで6時間、地方で12時間の労働時間制を決定した。政府内部のブルジョワ共和派は、二月革命で金融貴族から権力を奪った上は早急に経済恐慌を克服し、生産を軌道に乗せる必要があると考え、ルイ=ブランらの社会改革に反発、「赤い妖怪」の排除を策した。そのため国立作業場は反ルイ=ブランの商務大臣マリの管轄に置かれ、単なる失業対策にすりかえらた。マリは国立作業場を失敗に終わらせるために、作業場には不急無要の土木工事しか与えないにもかかわらず、作業員には一日二フラン、仕事のない日でも1.5フランを支給し、支出を膨大なものにした。4月普通選挙の結果、社会主義派が後退したため、ブルジョワ共和派は国立作業場の閉鎖を決め、それに反対した労働者を弾圧する六月暴動が起きた。 |
| D 六月暴動 | 1848年6月に、4月普通選挙で社会主義派が後退したことをうけてブルジョワ共和派の政府が国立作業場を兵際したことに対して労働者が暴動を起こし、政府軍が出動して鎮圧した事件。
6月21日夜、政府の国立作業場閉鎖に抗議し労働者デモが始まる。22日、4000人の労働者と政府(執行委員会)の交渉物別れとなり、翌日パリ東部に労働者のバリケード構築。議会、カヴェニャック将軍に反乱鎮圧の全権を委任し、パリに戒厳令をしく。カヴェニャックは徹底的な鎮圧作戦をとる。26日までの市街戦で、即時銃殺された者1500人。捕虜2万5千人は死刑になるか、アルジェリア・カイエンヌに流刑となった。ルイ=ブランは辛くも逃れてイギリスに亡命した。この暴動はブルジョアとプロレタリアの最初の大規模な階級闘争であった。 |
| a 4月普通選挙
| 1848年の二月革命で七月王政が倒され、3月5日に21歳以上の男子全員による普通選挙制が布告された。それまでの選挙権は納税額200万フラン、被選挙権は同じく500万フランという制限が無くなったため、有権者は一挙に900万に増えた。男子普通選挙の実現という選挙制度の歴史上、画期的なものであった。
臨時政府のもとで憲法制定議会が招集され、4月23日に第一帝政いらい途絶えていた普通選挙が実施された。選挙結果は、900の議席中ブルジョワ共和派(ナショナル派)が約500を占め、王党派も約300を獲得した。ルイ=ブランが期待した社会主義派(ブランキなど)は惨敗し、第二共和政はブルジョワ共和派が権力を握ることとなった。ブルジョワ共和派、王党派が進出した背景には、農民が保守化し、社会主義の進出を警戒したためと考えられる。二月革命を推進したルイ=ブランらの社会主義政策は後退せざるを得なくなった。それを受けた臨時政府のブルジョワ勢力が国立作業場を閉鎖したため、労働者の六月暴動が起きる。 |
| 第二共和政憲法
| 1848年11月、憲法制定会議で制定されたフランス第二共和政の憲法。フランス革命以来の「自由・平等・博愛」を掲げ、家族・労働・財産・公共の秩序を基礎とする、ブルジョワ共和政憲法である。しかし、第二共和政がブルジョワ勢力と労働者の対立下にあったことを反映し、労働の権利は「慈善の義務」にすり替えられ、言論・出版・集会の自由には公共の安全に反しない限り、という制限がつけられた。また三権分立の原理に従い、立法権は普通選挙によって選出さえる立法議会がもち、行政権は国民投票によって選出される大統領(任期4年、再任不可)にあたえられた。大統領には軍事・外交上の大権、閣僚・官吏の任免権など大きな権限が与えられ、大統領に選出されたルイ=ナポレオンが権力を強める根拠となった。 |
| E ルイ=ナポレオン | ルイ=ナポレオン(1808〜)父はナポレオン1世の弟オランダ王ルイ。その3男。母はナポレオンの前妃ジョゼフィーヌと前夫(革命で処刑された)との間に生まれたオルタンス=ド=ボアルネ。1815年
ナポレオン一族とともに追放されイタリアに亡命。兄のルイとともに次第に愛国的貴族と近づきカルボナリに参加し、イタリアの革命運動にかかわる。その後イギリスに渡る。1840年8月
ナポレオンの遺骸がパリに帰還したのに乗じ、突如ブーローニュに上陸、蜂起を企てるがとらえられ、パリ北東のアムの牢獄に送られる。1846年5月 脱獄。ロンドンにわたり、父の遺産で享楽生活を送る。1848年の二月革命で復古王政が倒れ、第2共和政となると、9月の 共和政補欠選挙に立候補し当選し、パリに戻る。ナポレオンの子供は夭逝していたため彼がその後継者となったので、次第に国民的な人気を獲得する。同年の12月の大統領選挙では、ブルジョワ共和派のカヴェニャック、ラマルティーヌ、社会主義共和派のラスパイユ、正統主義者のシャンガルニエらの対立候補を破り、547万(投票総数の4分の3)で当選し、フランスの大統領となる。社会主義におびえ、経済不況にもてあそばれた農民、債権のに苦しむ小商店主、小工場主などが彼を支持した。また、銀行家・産業家もルイ=ナポレオンが財産・宗教・家族の尊重など社会秩序を約束したので彼を支持した。ついで1851年のクーデターで権力を握り、翌52年に人民投票で圧倒的な得票で皇帝位につき、ナポレオン3世となった。この第二帝政の時代、彼は社会政策の実行と対外戦争の勝利によって国民的な人気を維持しようとしたが、1870年の普仏戦争の敗北によってその権威は崩れ、イギリスに亡命して権力の座からしりぞいた。 |
| a 1851年のクーデタ (フランス) | 12月2日(アウステルリッツの戦勝とナポレオン1世の戴冠式の記念日)ルイ=ナポレオンはクーデタを決行。ティエールら秩序党首領を逮捕、議会を軍隊が包囲し、戒厳令を布告。議会解散と普通選挙の復活を告げる布告を出す。逮捕をまぬがれたヴィクトル=ユーゴー、ジュール=フェーブルら共和派はその夜、抵抗委員会を組織、サン=タントワーヌ街を中心にバリケードを築く。3日夜から4日にかけての市街戦で政府軍の砲火を浴び、粉砕され山岳派議員ボーダンら死亡。ユーゴーはからくもベルギーに逃げる。立法議会が解散させられたことによって1848年憲法は失効し、第二共和制は事実上ここで終わった。12月21日に行われた人民投票では、投票率83%、賛成92%の圧倒的多数がクーデターを支持するという結果となった。
クーデタの背景 六月暴動以来の弾圧で指導者を失った労働者は、議会共和派の反動化で絶望、「貧困の絶滅」をうたう「皇帝社会主義」に期待する者も出てきた。ブルジョアジーは独裁よりも「赤い妖怪」の方を恐れ、小土地所有者は第一帝政時代の夢を追い、クーデタを支持した。12月21日国民投票、約740万対60万でクーデタ承認され、翌年1月大統領任期を10年とし権限を強化した新憲法が発布される。 |
| b ナポレオン3世 | → 第12章 2節 ナポレオン3世 |
| F 三月革命 | フランスの二月革命の報知はたちまち全ドイツに広がり、都市では出版の自由、自由主義内閣、陪審裁判制等の「三月要求」を掲げる市民集会やデモが開かれ、農村では封建的賦課の廃棄を迫って領主の城館を襲った。その結果各国に自由主義者の指導する「三月内閣」が生まれた。ウィーンでは3月13日、市民・学生が蜂起(ウィーン暴動)、憲法制定国会の召集とメッテルニヒ解任の要求を実現させた。同時にロンバルディア、ヴェネツィアではイタリア人の、ハンガリーではコッシュートが指導するマジャール人が蜂起(ハンガリー民族運動)し、ベーメンのチェッコ人も自治権を要求して立ち上がった。 |
| a ウィーン三月革命
| |
| b メッテルニヒ
(の失脚) | オーストリアの外相としてウィーン会議を主催、1821年からはオーストリアの首相としてウィーン体制を動かした。つぎつぎと起こる自由主義・民族主義の運動を弾圧、ギリシアの独立運動や中南米諸国の独立運動にも介入した。ウィーンに三月革命が起こると、イギリスに亡命した。官邸から逃げ延びる時、女装して脱出したという。 |
| c ベルリン三月革命 | 他国の事態をみて譲歩を決意した国王は、3月18日出版の自由を認めるとともに、憲法を約束、ドイツを国民議会をもつ連邦国家に改編することを提案する旨の勅書を発した。しかし、王宮前の民衆と軍隊の間で二発の銃声が響くと同時に市街戦となり(ベルリン暴動)、翌19日、国王は完全に屈服し、ブルジョア自由主義者(カンプハウゼン)を首相とする「三月内閣」発足させた。 |
| d フランクフルト国民議会 | 1848年のウィーンおよびベルリンの三月革命の後、ドイツの統一の気運が高まり、5月にフランクフルトに召集された「憲法制定ドイツ国民議会」のこと。ドイツ統一と憲法制定を目ざしたが、君主政と共和政の対立、大ドイツ主義と小ドイツ主義の対立によって紛糾し、統一を実現できず、翌49年6月に解散させられた。
国民議会の開催:1848年5月、フランクフルト=アム=マインの聖パウロ教会に召集されてたドイツ最初の議会。ドイツ連邦の全域から普通選挙で選ばれた議員の職業構成は裁判官・検事157名、行政官吏118名、弁護士66名、教師57名、大学教授49名など。他に農業経営者60名、商人46名、手工業者4名。6月にはオーストリアのヨーハン大公が「ドイツ国摂政」に任命され、そのもとにドイツ中央政府も組織され、従来のドイツ連邦議会は活動を停止した。議会ではドイツ統一の方式、憲法の制定などを話し合ったが、次のような対立から紛糾した。
ドイツ統一問題 :大ドイツ主義とは、オーストリアのドイツ人居住地域を含むドイツ連邦全域の統一したドイツ国民国家を主張するものであり、小ドイツ主義は多民族国家であるオーストリアを含まず、プロイセン主導で統一を図ろうとするものである。はじめは大ドイツ主義が優勢であったが、オーストリア帝国は大ドイツ主義をとれば、北イタリアやハンガリー・チェコの非ドイツ地域が排除されることになるので強く反発した。おりから、ハンガリー、チェコ、北イタリアで民族独立運動が起きるとオーストリアはそれらを厳しく弾圧し、49年3月、オーストリア帝国の単一・不可分を宣言した欽定憲法を発布し、大ドイツ主義は最終的に否定された。こうして小ドイツ主義でやむなしとなって、同月「小ドイツ的」なドイツ帝国憲法が成立した。
国民議会の解散:フランクフルト国民議会は1949年3月、ドイツ帝国憲法を採択し、世襲皇帝としてプロイセン国王フリードリヒ=ヴィルヘルム4世を選出したが、彼は「議会の恩恵による」帝位につくことを拒否し、憲法は宙に浮く。結局、プロイセンとオーストリアなど主要国が憲法を否認したため憲法は流産した。議会は解散されることとなり、一部の急進的な共和派が蜂起して議会の継続と統一憲法の制定をめざした(帝国憲法闘争)が、プロイセンの軍隊によって鎮圧され、ドイツ統一を目ざす革命は失敗に終わった。<この項、坂井栄八郎『ドイツ史10講』2003 岩波新書 p.129-133 などによる> |
| ドイツ統一問題 | 神聖ローマ帝国時代の領邦の連合体にすぎなかったドイツが、イギリスにおける議会政の発展やフランスにおける市民革命の進展などに刺激され、ドイツ国民国家としての統一と憲法の制定を目ざす動きがウィーン体制のもとで進んだ。その動きは1848年の三月革命で一気に燃え上がり、フランクフルト国民議会が開催され、ドイツ統一と憲法の制定が審議されることとなった。ドイツ統一は、当初はドイツ人の居住地域である旧神聖ローマ帝国のドイツ連邦の全域が含まれるものと考えられたが、この大ドイツ主義をとることになると、オーストリア帝国内のドイツ地域は含まれるが、その支配下にあるハンガリー、チェコ、北イタリア(ヴェネツィアなど)は含まれないことになる。このように多民族国家であるオーストリアの扱いをめぐって生じたのがドイツ統一問題である。当然オーストリア側は大ドイツ主義による統一に難色を示すこととなったので、オーストリアを含まない範囲でドイツ統一を実現しようという小ドイツ主義が台頭した。フランクフルト国民議会は最終的に小ドイツ主義におちつき、オーストリアを除いたドイツ諸邦の中で最も有力であったプロイセンを中心に統合されるこになった。(しかし、プロイセン国王がドイツ皇帝即位を拒否したので、この時はドイツ統一は実現せず、普仏戦争の際の1871年1月のドイツ帝国の成立を待たなければならない。)
後にヒトラーは、第三帝国と称して神聖ローマ帝国領の復活を実現し、オーストリアを併合した。しかし、ヒトラードイツの敗北により、第2次世界大戦後はオーストリア国家条約でドイツと分離され、統合は禁止された。とはいってもオーストリアはドイツ人の国家であり、ドイツ語が使われ、ドイツ文化圏にあるので、現在も「大ドイツ主義」は復活しかねない問題である。 |
| G 諸国民の春
| |
| a ベーメン
| |
| b ハンガリー
| |
| c コシュート
| |
| d ロシア
| |
| e ヨーロッパの憲兵
| 18世紀の後半、デカブリストの反乱を鎮圧、ポーランドの独立運動を抑圧した、ニコライ1世からアレクサンドル二世のツァーリズムの時代のロシアは、保守反動の中心となり「ヨーロッパの憲兵」と言われた。対外政策では南下政策を積極化する一方、国内では農奴解放令(1861年)など改革を行ったが、封建的な社会体制の矛盾は進行し、革命運動が起こってくる。 |
| f イタリア
| → マッツィーニ ローマ共和国 |
| g チャーティスト運動
| → チャーティスト運動 |
| H ウィーン体制の崩壊
| |
| a 資本家階級と労働者階級の対立
| |
| b 自由主義
| → 自由主義 |
| c 民主主義
| |
| d ナショナリズム
| → ナショナリズム |
| e 第2次アヘン戦争
| |
| f インド大反乱
| |
 |
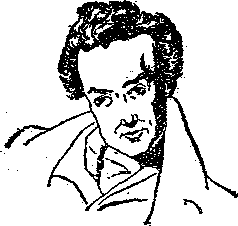 イギリスの奴隷貿易禁止および奴隷制度廃止に大きな役割を果たした政治家。貴族の出身で、キリスト教福音主義(教会によらず、個人の宗教的会心を重視する新教徒)の影響を受け、人道的な立場から奴隷貿易の禁止を主張するようになった。有力政治家の小ピットに働きかけ、1807年に奴隷貿易禁止法を、さらに1833年にはイギリス帝国全域の奴隷制度廃止法の制定を実現させた。
イギリスの奴隷貿易禁止および奴隷制度廃止に大きな役割を果たした政治家。貴族の出身で、キリスト教福音主義(教会によらず、個人の宗教的会心を重視する新教徒)の影響を受け、人道的な立場から奴隷貿易の禁止を主張するようになった。有力政治家の小ピットに働きかけ、1807年に奴隷貿易禁止法を、さらに1833年にはイギリス帝国全域の奴隷制度廃止法の制定を実現させた。