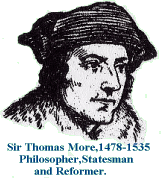| 用語データベース 09_2 |
  |
| 2.ルネサンス |
| ア.ルネサンス |
| A ルネサンス
| 14世紀のイタリアに始まり、15世紀に最も盛んとなって、16世紀まで続いた、ヨーロッパの文化、芸術上の動き。ルネサンスとはラテン語で「再生」を意味することば。日本では「文芸復興」と訳すことも多かったが、それはこの文化運動がギリシア文化・ローマ文化のいわゆる「古典古代」の文化を「復興」させるという面があったからである。ルネサンスの意義はさまざまな論議があるが、従来の一般的な見方は、ゲルマン民族という蛮族の侵入と、それによってもたらされた封建社会、そして神を絶対視し人間を罪深いものとするローマ教皇の思想が支配している中世を「暗黒の時代」と見て、その暗黒から人間を解放しようと言う運動がルネサンスである、というものであろう。1860年に発表されたドイツの文化史学者ブルクハルトの『イタリア・ルネサンスの文化』<上下 中公文庫>はそのような見解の古典的な作品であり、またそこではルネサンスの意義として、「個人の解放」、「ヒューマニズム」という理念が協調された。現在では、中世=暗黒時代、ルネサンス=明るい近代への序曲、といった単純な見方は影を潜め、中世の段階での文化の豊かさ(カロリング=ルネサンスや12世紀ルネサンス)が強調されるようになり、一方ではルネサンス以降の社会でも例えば魔女裁判が続いたことなどのように暗黒面が残っていたことが言われている。見方はだいぶ変わってきているが、ルネサンスが絵画、建築などの美術や文学の面で新しい内容とスタイルを生み出したものであり、思想の面でもより人間性に光が当てられるようになったことは確かであり、その際の手本となったのがイスラーム文化を通じて伝えられた、キリスト教以前のギリシア・ローマの古典古代の文化がであったことも事実であり、その価値は変わることはない。しかし、ルネサンスは文化、芸術、思想上の運動であり、キリスト教支配そのものや封建社会そのもへの批判や価格を目指すものではなかった。ヨーロッパの変革は、宗教面では16世紀の宗教改革、政治面では17世紀のイギリス革命、社会面では18世紀の産業革命とフランス革命が必要となる。 |
| a 14世紀
| 14世紀はじめ、イタリアではフィレンツェなどの都市共和国の繁栄を背景に、ダンテ、ペトラルカ、ボッカチオらが現れ、まず文芸でルネサンスが始まった。絵画ではジョットが先駆となった。一方で前代からの教皇党(ゲルフ)と皇帝党(ギベリン)の抗争が続き、教皇のバビロン捕囚や教会大分裂など、カトリック教会の権威が揺らぎ始めた。1339年には英仏の百年戦争が始まり、その間にイギリスのワット=タイラーの乱やフランスのジャックリーの乱などの農民叛乱が起こった。これらは黒死病の流行とともに、封建社会の矛盾を進行させた。ドイツでは1356年に金印勅書が出され、神聖ローマ帝国の皇帝選出ルールが定まったが、 |
| b 15世紀
| 百年戦争が終結したが、イギリスでは引き続いてばら戦争に突入、長期にわたる戦争で英仏とも封建領主の没落が進み、反面、王権の強化が始まった。レコンキスタを完了させたポルトガル、スペインはいち早く王権を強化し、ヨーロッパの東方でオスマン帝国が進出したという情勢に併せて、新航路の開拓に向かい、大航海時代を出現させた。世紀の終わりごろにはイギリスのチューダー朝、フランスのヴァロア朝の国家機構の整備が進み、スペインはハプスブルク家のもと、神聖ローマ帝国の領土と併せ、さらにポルトガルを併合したので海外領土を含め絶頂期を迎えた。このような15世紀、つまり1400年代(クワトロチェント)は、イタリアのフィレンツェ、ついでローマを舞台に、ルネサンスが最も華やかに展開された時期であった。 |
| c 16世紀
| 15世紀から16世紀にかけて、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなど、ルネサンスを代表する画家が活躍し、エラスムス、トマス=モア、マキャベリなどの近代思想の先駆となる思想家が排出した。イタリア=ルネサンスの中心はフィレンツェからローマに移り、またルネサンス芸術はアルプス以北のフランス、オランダ、ドイツ、イギリスなどにひろがった。1517年、宗教改革が始まり、ヨーロッパは深刻な宗教対立の時代に突入する。また主権国家の形成も進み、イタリア戦争に見られるフランス王室とハプスブルク家の対立が軸となった国際関係がなおも続く。宗教改革とからんでオランダのスペインからの独立戦争が始まり、オランダを支援したイギリスが1588年にスペインの無敵艦隊を破ったことに見られるように、スペインの急速な没落が始まった。それらの背景にあるのが、大航海時代によって成立した新しい世界の経済システム(近代世界システム)の形成であった。 |
| d イタリア
(14〜16世紀) | 14世紀から16世紀の北イタリアは、神聖ローマ皇帝の支配が終わり、十字軍時代後の商工業、東方貿易などの遠隔地貿易が再興され、ヴェネツィア、ジェノヴァ、フィレンツェ、ミラノなどの都市共和国が成長し、互いに競い合っていた。またローマ教皇もアビニヨン捕囚、大分裂によって権威は衰えたものの、中部イタリアに教皇領を所有し、宗教的にはまだ絶対的な力を握り、政治的にも都市共和国を牽制しながら、キャスティングボードを握っていた。このようなイタリアの分裂状態に対し、フランスとスペイン(神聖ローマ帝国)が介入し、複雑な国際情勢が展開され、両国軍がたびたびイタリアに侵入してイタリア戦争を繰り返していた。このような政治的には混乱した時代が、イタリア=ルネサンスが展開した時代なのであった。 |
| e ネーデルラント | ネーデルラントとは、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクのベネルクス三国に北フランスを加えた広い範囲を指す地名である。早くから毛織物業が発達し、ヨーロッパの産業の一つの中心地であり、北海貿易とも交易が活発であった。16世紀に相続によってハプスブルク領となり、カール5世の統治する神聖ローマ帝国の一部となった。商工業が早くから発達していたことで、イタリアと並ぶルネサンスの勃興した地域となった。 |
| f ルネサンスの意義
| 人間性の自由・解放を求め、個性を尊重しようとする文化運動 |
| g ルネサンスの意味
| ギリシャ、ローマの古典文化を手本とし、それを再生しようとすること |
| h 再生
| |
| i ヒューマニズム(人文主義、人間主義)
| |
| j 封建社会
| |
| B イタリア・ルネサンス
| |
| b ビザンツ・イスラーム文化との接触 | イタリアは北イタリアのヴェネツィアやジェノヴァなどの商人による東方貿易(レヴァント貿易)によってビザンツ、イスラーム世界と接触していたが、十字軍運動によってもたらされた新しい情報も集まってきていた。また南イタリアはシチリア島などで直接イスラーム教徒と接触することがあり、キリスト教文明の価値観を超えた刺激を受けやすい一にあったといえる。特にイタリア=ルネサンスに大きな刺激となったのが1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落、つまりビザンツ帝国の滅亡でった。その際、ギリシアの学者たちはイスラーム教の支配を逃れて、まずヴェネツィアに亡命したが、ヴェネティアでは彼らを受けいれる気風はなく、そこからさらにフィレンツェに移ってきた。彼らによってギリシア思想がフィレンツェに移植されたことも、ルネサンスの発展を考える際に重要である。彼らはギリシア・ローマの古典をもたらしただけでなく、イスラーム文化の影響もヨーロッパ世界に伝えることになった。 |
| C ルネサンス期のイタリア | → イタリア(14〜16世紀) |
| a フィレンツェ(ルネサンス期) | 北イタリアの代表的なコムーネ(都市共和国)であるフィレンツェは毛織物業、金融業などで繁栄し、政治的にはゲルフ(教皇党)の中心勢力であった。13世紀の中頃、ギベリンは衰退したが、フィレンツェのゲルフはより革新的な白派(ビアンキ)と保守的な黒派(ネリ)に分裂して再び激しい抗争を展開、両派の政権交代が行われた。
14世紀以来、フィレンツェ共和国では民主政が維持されてきた。その概略は、市民から選ばれる「正義の旗手(ゴンファロニエーレ)」が執行機関の最高責任者であり、8名の「総務(プリオーレ)」が一種の内閣を形成し、「人民(ポーポロ)評議会」が市民を代表して代議制が行われていた。フィレンツェの住民すべてが「人民」とされたわけではなく、アルテという各種の同業者組合の構成員に限られていた。アルテには大アルテと小アルテがあり、毛織物・絹織物・梳毛業・商人・銀行・医師薬剤師・法律家公証人の7団体が大アルテで、豊かで発言力が強く「ポポロ・グラッソ」といわれ、小アルテは石工、肉屋、酒屋、大工、左官など普通の職業で14団体で「ポポロ・ミヌート」といわれて区別されていた。かつては貴族の専制に対してともに戦ったが、この時代には、大アルテが権力を握った一種の同業組合国家という性格が強かった。参政権を持つ同業者組合構成員も全住民9万のうち、わずか300人ほどであったと言われている。次第に共和政は形骸化し、有力者による寡頭政治(シニョーリア制)の状況となっていく。
15世紀からはメディチ家が権力を独占するようになり、コシモ=ディ=メディチと孫のロレンツォ=ディ=メディチがあらわれルネサンス黄金時代をもたらした。彼の死後、サヴォナローラという僧侶が狂信的な神政政治を行い、メディチ家は一時追放されるが、16世紀初頭に復活すると共和政は否定され、メディチ家の独裁となり、周辺地域とあわせてトスカーナ公国というメディチ家世襲下の君主国となる。この混乱の時代に、君主制のあり方を思索したのがフィレンツェのマキャヴェリである。 |
| b メディチ 家 | フィレンツェの大富豪でルネサンスの保護者として知られた一族。13世紀ごろからフィレンツェで薬屋を営み(その紋章の赤い6つの玉は、丸薬を示す看板だったという)、財をなしたらしい。15世紀までには銀行業を営み、全ヨーロッパにも知られ、主要な町に支店を置くようになっていた。特にローマ教皇の管財人となりその財産の管理にあたり名声を高め、またフランス王やドイツの諸侯などにも融資している。後にその紋章の6つの赤い玉の上に、フランス王家の紋章である百合の花をつけることを許されている。メディチ家はフィレンツェの共和政の中で大きな発言力を揮うようになり、15世紀のコシモ(”イル=ヴェッキオ”古老の意味)とその孫のロレンツォ(”イル=マニフィコ”偉大な、という意味)の二人の時が最も有力であり、まさにフィレンツェがルネサンス文化の中心地として栄えた時代であった。その時代のメディチ家からはレオ10世とクレメンス7世という二人のローマ教皇も出ている。メディチ家はその後、16世紀にはカール5世からフィレンツェ公の地位をあたえられるが、同時にフィレンツェは共和国の時代が終わり、1569年以降は周辺を併せたトスカナ公国となり、メディチ家がトスカナ大公の地位を世襲し、18世紀まで継続する。フランスのユグノー戦争の時の王妃カトリーヌ=ド=メディシスもメディチ家の出身である。 |
| c コシモ=ディ=メディチ
| コシモの父、ジョバンニ=ディ=メディチは、フィレンツェにおけるメディチ家の政治的基盤を作った人であった。ジョバンニは「正義の旗手」に選ばれると、資本家から7%の資本税をとることを決め、下層市民から大きな支持を受けた。1428年、その子コシモが後を継いだが、彼は重要な役職には就かなかくとも絶大な民衆の支持を背景に隠然たる力を発揮し、「イル=ヴェッキオ」(古老の意味)と呼ばれ、大きな富を文芸、芸術の保護にあてて、ルネサンスの代表的な保護者(パトロネージ)となった。生活は質素で、私生活もきちんとしていた。
彼の保護を受けた芸術科は、建築家のブルネレスキ、彫刻家のドナテルロ、ギベルティ、画家のボッティチェリ、フラ=アンジェリコ、哲学者のピコ=デラ=ミランドラ、フィチーノなど枚挙にいとまがない。またギリシア語の文献を収集し、そのラテン語訳をフィチーノに命じ、プラトン思想の研究のため「プラトン=アカデミー」を創設した。これらは次のロレンツォにも引き継がれ、ルネサンスの思想のまさに中心となっていく。1464年没。死後も「祖国の父」と称えられた。 |
| d プラトン=アカデミー
| 1459年、フィレンツェのコシモ=ディ=メディチは、別荘の建物を改装して、「プラトン=アカデミー」とし、若い哲学者フィチーノに命じてギリシアのプラトンの著作のラテン語訳に従事させた。古代ギリシアのアテネにプラトンが作ったアカデメイアの再興をめざし、フィレンツェの学者が集まり、プラトンの著作などのギリシア哲学について盛んに議論し、研究が進められた。コシモの孫のロレンツォもその議論に加わっており、メディチ家の当主となってからも続けた。プラトン=アカデミーにはピコ=デラ=ミランドラら、当代のすぐれた学者、思想家が集まり、ルネサンスのユマニスムス(ヒューマニズム)の拠点となった。
フィレンツェにギリシア思想が知られたのは、1439年、コシモが招聘してフィレンツェで東西教会合同のための宗教会議が開催されたとき、ビザンツ帝国から皇帝自身と、ベッサリオンやゲミストゥスなどのギリシア人の学者がフィレンツェにやってきて、プラトンやアリストテレスを引用しながら盛んに議論をしたときからである。フィレンツェの知識人はこの時初めてプラトンのイデア論とアリストテレスの形相の概念を知り、キリスト教信仰にとってどちらが真理か、という哲学論争を経験した。フィレンツェ人はプラントンの思想をより支持したため、プラトン学者であったゲミストゥスは感激し、コシモにプラトン=アカデミーの設立を働きかけたという。この宗教会議は、迫りくるオスマン帝国に対抗するためのものであったが、目的の東西教会の合同は結局できず、1453年にビザンツ帝国は滅亡した。 |
| ロレンツォ=ディ=メディチ
| ロレンツォはコシモの孫、ピエロ(「痛風病み」イル=ゴットーゾ)の子。1469年、父のピエロが死に、20歳で推されてフィレンツェの「国家の長」の地位につく。民主政なので世襲はできないが、この時期までにメディチ派は市政の要職を独占していたのでその後見で権力を握ることができた。しかし、反メディチ派の襲撃を受け、危機一髪で難を逃れ(この時弟のジュリアーノは殺された。1478年のパッツィ事件)、またフィレンツェの強大化を恐れ反メディチ派と結んでいたローマ教皇とナポリ王国もすぐれた外交手腕で屈服させ、かえって権力を強めることに成功した。彼自身は父の作ったプラトン=アカデミーで思索し、詩を作る文人でもあった。「イル=マニフィコ」(偉大な人)と言われた彼の時代、フィレンツェのルネサンスは爛熟の極にあったといえる。
Epi. ロレンツォの臨終。サヴォナローラその罪を追求する しかし、そのような芸術の開花を苦々しく思う、聖職者がいた。ロレンツォがわざわざ説教師として招いたジロラモ=サヴォナローラであった。彼は次第に激しくロレンツォの専制と華美な文化を攻撃するようになる。1492年、臨終の床でロレンツォはサヴォナローラを招いて懺悔を頼んだが、サヴォナローラはそれを許さず、不当に取り上げた富を返すこと、人民に自由を回復することを条件に迫ったという。その死後、サヴォナローラはフィレンツェの市政と宗教の改革に乗り出す。<モンタネッリ/ジェルヴァーゾ『ルネサンスの歴史』黄金世紀のイタリア 上 中公文庫 p.205〜224 「ロレンツォとジロラモ」> |
| e ビザンツ帝国
| →第6章 2節 ビザンツ帝国も滅亡 |
| f ミラノ
| →第6章 3節 ミラノ公国 |
| g ローマ教皇
(ルネサンス期) | ルネサンス期のローマ教皇は、イタリア中部を支配する政治勢力であるとともに、依然として神聖ローマ教皇に対抗し、イギリス国王やフランス国王とも対等、あるいはそれ以上の力で渡り合っていた。また、ルネサンスの保護者としても大きな存在であった。しかし16世紀にルターがローマ教会の批判を開始し、宗教改革の嵐にさらされることとなる。
ルネサンス期の教皇としては、アレクサンデル6世(在位1492〜1503年)、ユリウス2世(在位1503〜1513年)、レオ10世(在位1513年〜1521年)が重要。 |
| ユリウス2世
| ルネサンス期を代表するローマ教皇。在位1503〜1513年。教皇に選出されると、前教皇の庶子で教皇領で大きな勢力となっていたチェーザレ=ボルジアを捕らえて失脚させた。その後、教皇に敵対的であったヴェネツィア共和国を討つため1508年にフランス王ルイ12世、スペイン王フェルナンド5世、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世とカンブレー同盟をむすぶなど、政略家ぶりを発揮した。イタリア戦争の一環で、フランス王ルイ12世が北イタリアで勢力を強めると、一転してスペイン、ヴェネティア、スイスと「神聖同盟」を結成、フランス軍と戦い(1512年ラヴェンナの戦い)、その勢力を排除することに成功した。このように、政略的・好戦的な教皇として知られるが、一方ルネサンスの保護にも務め、1506年からサン=ピエトロ聖堂の改修を開始し、ブラマンテに設計を担当させた。またミケランジェロにシスティナ礼拝堂(ヴァチカン宮殿内の礼拝所)の天井画と壁画「最後の審判」を発注した。 |
| h サン=ピエトロ大聖堂
| ローマのヴァチカンに隣接する、カトリックの総本山。使徒ペテロの墓所とされており、コンスタンティヌス帝がそこに教会堂を建てたというが、中世の長い時期に放置され荒廃していたので、1506年、教皇ユリウス2世の時、大改築が開始した。ブラマンテが最初の設計にあたり、ついでラファエロ、ミケランジェロなど、ルネサンス時代の芸術家がその設計や建設、壁画の制作などに加わった。ルネサンス様式の代表的な建造物とされる。このサン=ピエトロ大聖堂の修築費用を捻出するためにローマ教皇レオ10世はドイツでの贖宥状の発売に踏み切り、それに対する反対運動としてルターの宗教改革が始まった。 |
| レオ10世
| フィレンツェのメディチ家出身のローマ教皇。在位1513〜1521年。サン=ピエトロ聖堂の改修費用を得るために、ドイツで贖宥状(免罪符)を発売し、それを批判したルターが宗教改革を開始した。レオ10世はルネサンスの保護者として知られ、特にラファエロを後援したことで有名。彼の時代にはサン=ピエトロ聖堂の改修はほとんど進まず、彼はもっぱら教皇の住む宮殿の増築に費用を充てたという。 |
| D ルネサンスの限界 | |
| E イタリア・ルネサンスの衰退
| |
| a イタリア戦争
(の勃発) | ロレンツォ=ディ=メディチの死んだ1492年(くしくもコロンブスの新大陸到達の年)から2年後の1494年、フランス軍のイタリア侵入が始まり、イタリア戦争が勃発した。このイタリア戦争は15世紀の終わりから、16世紀の前半まで、ちょうどイタリア=ルネサンスの時代のイタリアで展開された、主としてフランス(ヴァロア朝)とハプスブルク家神聖ローマ帝国(スペイン、ドイツなどを支配)との戦争である。その間北イタリアは戦場となり、そのためにイタリア=ルネサンスは衰退していく、と言われている。 → イタリア戦争
その始まりである第1期の、1494年のフランス王シャルル8世のイタリア侵入の事情は次のようなことであった。ナポリ王国は1435年にフランス系アンジュー家の王位が断絶し、スペインのアラゴン家が王位を継承していた。そのフェルティナンド1世が亡くなると、フランス王シャルル8世は、王位を継承権を主張し、ローマ教皇アレクサンデル6世に承認を求めた。ローマ教皇はそれを拒否すると、シャルル8世はスイス人傭兵からなる部隊を率いてイタリアに侵入、ローマを経て、95年2月にはナポリを占領した。ミラノの実力者ルドヴィコ=イル=モロはフランスを支持した。教皇アレクサンデル6世は、スペイン国王(兼シチリア王)フェルディナンド5世、神聖ローマ教皇マクシミリアン1世、ヴェネティア、フィレンツェに呼びかけ、フランス王に対抗し、3月に神聖同盟を成立させた。退路を断たれることを恐れたシャルルは、急遽ナポリからフランスに戻ろうとし、7月フォルノヴォの戦いで敗れ、ようやくパリに帰還した。このようにシャルル8世のイタリア遠征は失敗に終わったが、そのスイス傭兵を中心とした軍隊の侵入は、分裂していたイタリア諸勢力に大きな脅威となり、フィレンツェではメディチ家の独裁がいったん終わってサヴォナローラの神権政治がはじまるなどの影響があった。当時のフランスは、1453年に百年戦争を終え、シャルル7世、ルイ11世の2代の国王の間に中央集権体制を固めつつあったが、産業の発達は遅れていたので、北イタリアの進んだ経済力を支配下におくことをねらっていたものと思われる。 |
| b 大航海時代
| → 第9章 1節 ヨーロッパ世界の拡大 大航海時代 |
| a サヴォナローラ
| サヴォナローラは、ドミニコ派の聖職者で、ピコ=デラ=ミランドラの紹介で、ロレンツォ=ディ=メディチがフィレンツェに招き、サン=マルコ修道院で活動していたが、次第にメディチ家の独裁政治やローマ教皇の腐敗、ルネサンスの華美で軽薄な風潮に反発し民衆を煽るようになった。フランス王シャルル8世のフィレンツェ入城してメディチ家が追放された後、1494年から98年まで政権にぎり、厳しい神政政治を行った。最後は民衆の支持を失い、教皇アレクサンデル6世によって破門され、焚刑に処せられた。サヴォナローラはルネサンスの全盛期に現れた特異な宗教改革者であったが、民衆の支持を受けることが出来ず、自滅したといえる。
Epi. サヴォナローラの「虚飾の焚刑」 フェラーラで生まれ、ボローニャで訓練をうけたサヴォナローラは、1482年にフィレンツェに招かれ、サン・マルコ修道院で説教を始め、その情熱的な説教が人気を呼んだ。彼はフィレンツェの教会で説教するうち、おりからのロレンツォ=ディ=メディチの独裁政治のもとて、フィレンツェの人々が腐敗した享楽生活を送っていることを鋭く批判するようになった。1492年、サヴォナローラはロレンツォの臨終に際してその罪を責めたといわれる(ロレンツォ=ディ=メディチの項参照)。サヴォナローラの鳴らした警鐘の通り、フィレンツェは災難に見舞われた。1494年にイタリア戦争が勃発、フランスのシャルル8世軍がせまってきたのである。ロレンツォの息子ピエロは抵抗することが出来ず逃げ出してしまい、あっけなくメディチ家の統治は途絶えた。かわって市民の代表に選ばれたのが、この事態を予言したサヴォナローラだった。かれは1498年までの4年間、フィレンツェの政治を行い、市民の贅沢を戒め、堕落の元凶として裸婦を描いた絵や楽器を没収し、あつめて焼き捨てるという「虚飾の焚刑」を実施した。しかし彼の厳しい神政政治は次第に市民の反発を受け、またローマ教皇庁、ドミニコ派と対立していたフランチェスコ派の宣教師たちの反発も強まり、1498年、教皇アレクサンデル6世はサヴォナローラを異端であるとして破門した。フィレンツェ市民はサン・マルコ修道院に押し寄せ、サヴォナローラを捕らえて引き立て、裁判かけて有罪にし、最後は焚刑にしてしまった。<高階秀爾『フィレンツェ』1966 中公新書などによる> |
| チェーザレ=ボルジア
| スペインのボルジア家出身のローマ教皇アレクサンデル6世の庶子。教皇となった父の保護のもと、聖職者となり、18歳で枢機卿となる。フランス王ルイ12世のもとに教皇特使として派遣され、その信任を得る。聖職者から還俗し、ナヴァラ王の妹と結婚、ヴァレンティノワ公となり、ローマ教皇領の拡大に努め、傭兵部隊を駆使してロマーニャ地方を攻略、すぐれた政治的手腕を発揮した。しかし、父のアレクサンデル6世が死ぬと後ろ盾を失い、新教皇ユリウス2世と対立し、捕らえられてスペインに送られ、1506年戦死した。その権謀術数を駆使した政治的駆け引きは、同時代のマキャヴェリが、『君主論』で君主のあるべき姿として賞賛している。
<アレクサンデル6世、チェーザレ=ボルジア、ルクレツィア=ボルジアなど、ボルジア家はルネサンス時代のイタリアに登場し、陰謀や毒殺など悪徳の限りを尽くした一族であった。くわしくはマリオン・ジョンソン『ボルジア家』中公文庫、などを参考。> |
| b マキアヴェリ | ニコロ=マキアヴェリ(1469〜1527)。マキアヴェッリとも表記。マキアヴェッリは1469年、フィレンツェのメディチ家のロレンツォ=ディ=メディチが20歳で「国家の長」に就任したときに生まれた。サヴォナローラ処刑後のフィレンツェでフィレンツェ政庁の書記に任命された。おりから1499年、フランスのルイ12世がミラノに侵攻し、ロドヴィコ=スフォルツァ(イル=モロ)を追い出すことがあり、それにからんでマキアヴェリはフランス王との折衝を命じられ、パリに派遣された。ここで外交交渉の現場にたった。また1502年にはフィレンツェに圧力をかけてきたローマ教皇の子チェーザレ=ボルジアとも交渉した。その後も、ローマ教皇マクシミリアン1世、フランス王への使節としてフィレンツェの外交を担っていった。独裁者メディチ家を追放したフィレンツェでは民主派が権力を握り、指導者ソデリーニが統治し、マキアヴェッリもそれに協力した。ソデリーニはフランスと結び、ローマ教皇と対抗しようとした。フランスは1512年、再びイタリアに侵入した、4月11日のラヴェンナの戦いで、教皇及びヴェネツィア軍と衝突した。これは近代最初の大会戦といわれているが、教皇側にスペイン、神聖ローマ皇帝、イギリスも加わり、スイス傭兵も教皇側についたので、フランスは敗れ、フィレンツェは孤立し、ソデリーニは逃亡、フィレンツェにはメディチ家の支配が復活した。その結果1512年11月にマキアヴェッリは解任され、一時は投獄されるなどの不遇の時期を迎えた。この時期に執筆したのが『君主論』であり、フィレンツェの新しい権力者ロレンツォ=ディ=メディチ(大ロレンツォの孫。小ロレンツォ)に献呈された。しかし小ロレンツォは彼を復帰させることなく、マキアヴェッリはその後文筆活動を続け、『リヴィウス論』、『フィレンツェ史』、『ローマ史』などの歴史書や、小説、戯曲などを発表した。1525年フランス王フランソワ1世がアルプスを越えてイタリアに侵入、フィレンツェが再び脅かされる状況でメディチ家政権はマキアヴェッリを復帰させたが、1527年、イタリア戦争がピークに達し、神聖ローマ帝国皇帝カール5世がローマに進軍、「ローマの劫掠」が行われるに及び、フィレンツェでもメディチ家が再び追放され、マキアヴェッリも失脚し、同年6月に死去した。<佐々木毅『マキアヴェッリと『君主論』』1978 講談社学術文庫による要約> |
| c 『君主論』
| マキアヴェリが、1513年頃著し、フィレンツェの君主ロレンツォ=ディ=メディチ(大ロレンツォではない。その孫。)に献呈した、国家統治者たる君主はいかにあるべきか、を論じたもの。有名な、君主は「ライオンのような勇猛さと狐のような狡猾さ」が必要である、という主張は次のような文脈で出てくる。
「ところで戦いに勝つには、二種の方策があることを心得なくてはならない。その一つは法律により、他は力による。前者は、人間ほんらいのものであり、後者は獣のものである。だが多くのばあい、前者だけでは不十分であって、後者の力を借りなければならない。したがって君主は、野獣と人間をたくみに使い分けることが肝心である。・・・どちらか一方がかけていても君位を長くは保ちえない、そう教えているわけだ。そこで君主は、野獣の気性を適切に学ぶ必要があるのだが、このばあい、野獣の中でも、狐とライオンに学ぶようにしなければならない。理由は、ライオンは策略の罠から身を守れないからである。罠を見抜くという意味では、狐でなければならないし、狼どものどぎもを抜くという面では、ライオンでなければならない。」そこで、
「名君は、信義を守るのが自分にとって不利をまねくとき、あるいは約束したときの動機が、すでになくなったときは、信義を守れるものではないし、守るべきでもない。・・・人間は邪悪なもので、あなたへの約束を忠実に守るものではないから、あなたのもうも他人に信義を守る必要はない。・・・・」となる。
次のような言葉はまさに現代の政治家の本質を突いている。「国を維持するためには、信義に反したり、慈悲にそむいたり、人間味を失ったり、宗教にそむく行為をも、たびたびやらねばならないことを、あなたは知っていおいてほしい。・・・そして前述のとおり、なるべくならばよいことから離れずに、必要にせまられれば、悪に踏みこんでいくことも心得ておかなければいけない。・・・・」<訳文は池田廉訳『君主論』 中公クラシックス p.133など>
マキアヴェリが、君主のあるべき姿として取り上げたのは、同時代のローマ教皇領を統治した、チェーザレ=ボルジアであった。また、マキアヴェリは、従来の傭兵制や外国軍に依存するのでは、国家の統一と自立は不可能であり、国民軍の創設が必要であることを強調している。フィレンツェ、ミラノ、ベネツィア、ローマ教皇領、ナポリ王国などに分裂し、フランス王やスペイン王、神聖ローマ皇帝などに蹂躙されていた16世紀のイタリアの状況に対する、痛烈な反省をこめた提言であった。その言葉は反道徳的なものと受け取られ、長い間危険な書物として禁書扱いされてきたが、政治目的の実現のためには権謀術数も必要であるという現実的な政治論は、マキアヴェリズムとして近代政治論に大きな影響を与えていく。
※『君主論』は、翻訳がたくさん出ており、文庫本でも読める。最も読みやすいのは中公クラシックス版の池田廉訳か。ただ訳語にはいろいろ異説があって、河島英昭訳の岩波文庫版では細部でかなり違う。また解説が充実しているのが佐々木毅訳の講談社学術文庫版。 |

|
| イ.文芸と美術
|
| 1.文芸(文学)と思想
|
| A ルネサンス文芸
| |
| a ダンテ
| 1265年、フィレンツェに生まれた。本名は、ドゥランテ=アルギエリ。そのころイタリアではまだゲルフ(教皇党)とギベリン(皇帝党)の抗争が続いており、フィレンツェでも両派の争いが続いていた。ダンテの家は代々ゲルフであった。少年時代に出会ったベアトリーチェという少女に恋をしたが破れ、その気持ちを唱ったのが第1作の『新生』である。その後詩人として歩み、若い詩人グループ「清新体派」をつくった。1289年、フィレンツェはゲルフの主力として、ギベリンの本拠アレッツォを攻撃、勝利を収めたこのカンパルディーノの戦いに参加した。その後、フィレンツェのゲルフは、ヴィエーリ・チェルキの率いる白派(ビアンキ、新興勢力でフィレンツェの民主化を図ったグループ)とコルソ・ドナーティの率いる黒派(ネリ、古い家門の保守的グループ)に分かれて党派闘争が始まった。ダンテは白派に属し、黒派が追放されたあとの1300年には選挙で最高の役職の総務(プリオリ)に選出された。ところが、フィレンツェの服属都市ピストイアで黒派が皆殺しにされる事件が起き、ローマ教皇ボニファティウス8世がフィレンツェを破門、フランス王(ヴァロア朝フィリップ4世)も軍隊を派遣してくると、1302年、白派政権は崩壊、ダンテは死刑の判決を受けたが直前に脱出した。こうしてフィレンツェを離れたダンテは、各地を転々としながら、強力な皇帝によるイタリア統一を期待するようになった。その願いは実現することなく、晩年はラヴェンナで執筆活動に専念し、代表作『神曲』を書き続け、1321年に死んだ。
Epi. ダンテと永遠の恋人 「少年期については、わずかにエピソードがひとつ知られているだけだが、これがダンテの生涯と作品に決定的な刻印を残すこととなる。すなわち、ベアトリーチェとの出会いである。この永遠の恋人が実在したかどうか、古くから議論が絶えなかったが、今では架空説は影をひそめ、当時フィレソツェで人望厚かった銀行家フォルコ・ポルティナーリの娘であると、一般に認められている。ダンテと同い年で、のちにシモーネ・デ・バルデイに嫁ぎ、一二九〇年、たぶん産祷熱で亡くなった女性である。ダンテによれば、ベアトリーチェとの出会いは一二七四年、二人が九歳の年、子供の祝祭の日としているが、事実よりも数の迷信を尊重する癖のあったダンテのことだから、簡単には信じかねる。三という数が完全数とされていたから、三およびその自乗数九にダンテは弱かったのだ。『神曲』は三行韻を踏んで書かれ、地獄・煉獄・天国の三部に分れ、地獄の旅は計九日かかり、煉獄は九層より成る等々、枚挙にいとまがない。ベアトリーチェに初めて会ったのが九歳、再会したのが十八歳と言っているが、多分に眉唾ものだ。」<モンタネッリ/ジェルヴァーゾ『ルネサンスの歴史』黄金世紀のイタリア上 中公文庫 p.52「ダンテ」> |
| b 『神曲』
| ダンテの代表作。正確な完成年度は不明だが、14世紀の初頭である。内容は、古代ローマの詩人、ヴェルギリウスが、死後の世界の地獄、煉獄、天国を経巡る物語で、それぞれ33歌、序の1歌をあわせて、全部で100歌となる。各歌は三行韻の連鎖でつづられ、1行11音節、第1行と第3行が韻を踏み、第2行は次の三行韻の第1行目と韻を合わせるという形式になっている。描かれている内容は、中世的な世界観、名神の域を出ていないが、重要なことはこの作品がトスカナ地方の口語で書かれたことであった。ダンテは、『俗語論』という論文も残しており、そこでもラテン語はすでに死後になったことを確認し、口語すなわち話し言葉が方言のまま洗練されずにいることを懸念し、美しい「国語」に高める必要がある、そのためには国民的統一が必要であると主張している。この思想がイタリア語の形成の第一歩となった。 |
| c 口語(トスカナ語)
| |
| d ペトラルカ
| 1302年のフィレンツェでの黒派が権力を握ったとき白派の多くは国外に亡命した。そのとき、ダンテと一緒にアレッツォに亡命したペトラッコという人の子で、1304年に生まれたフランチェスコがペトラルカである。一家は当時、「教皇のアヴィニヨン捕囚」によって教皇庁がおかれていた南仏アヴィニヨンに移住、そこで少年時代を過ごした。ペトラルカはボローニャ大学で法律を学んだが、そこでヴェルギリウスやキケロ、セネカなどのローマの古典文学に触れ、ラテン語による詩『アフリカ』(ローマ時代の属州アフリカを題材としたもの)えお発表した。またラウラという理想的な女性に触発され、ダンテの『神曲』の影響も受けて、抒情詩『カンツォニエーレ』(『叙情詩集』)をトスカナ語で連作した。ラウラは1348年の黒死病(ペスト)の大流行で死んだが、『カンツォニエーレ』にはその死を悼む作品がある。ルネサンス最初の人文主義者(ヒューマニスト)と言うことができる。 |
| e ボッカチオ
| 1313年パリに生まれたが父はフィレンツェ出身の商人。名前はジョバンニ。ボッカッチョとも表記。15歳で父から業務見習いにナポリに行かされる。仕事の傍らラテン語を学び古典に親しむ。1331年にフィアンメッタという女性に恋をし、詩作をはじめ、彼女に捧げる詩作をたくさん作った。父の出身地フィレンツェに戻り、ペトラルカなどと交わり、1348年の黒死病(ペスト)の大流行を体験する。1353年、『デカメロン』を発表、その冒頭には黒死病の様子が語られている。またボッカチオは、中世ヨーロッパでは忘れられていたホメロスの『イーリアス』のギリシア語原典を発見し、それを翻訳して紹介したこともルネサンスの中での彼の大きな業績である。 |
| f 『デカメロン』
| 1353年、ボッカチオが発表した小説。この作品は、散文形式の小説で、黒死病の難を逃れて郊外に非難した10人の男女が、寂しさを紛らわすために1晩に一人が1話ずつ話をするという形をとり、つまり100話からなる短編集である。話は卑猥なものが多いが、そこに描かれた人物像は、生き生きとして個性あふれており、この小説は近代小説の最初の傑作とされている。 |
| g チョーサー
| 14世紀後半のイギリスで活動。しばしばイタリアに赴き、ダンテやボッカチオの作品の影響を受ける。『カンタベリ物語』はイギリスの国民文学の誕生と言われる。 |
| h 『カンタベリ物語』
| 14世紀末のイギリスのチョーサーが著した文学作品。イギリスの農民がカンタベリ大聖堂への巡礼の道中で語り合う形式をとり、『デカメロン』のイギリス版と言われる。 |
| B ヒューマニストの活動
| ヒューマニストとは、人間主義者、人文主義者とも訳す。ヒューマニズム(ラテン語ではフマニスムス)、つまり人間中心の思想をもつ人びとという意味であり、16世紀のルネサンス時代に登場した、カトリック教会の神中心の世界観に対して人間そのものの美しさや価値を見いだした思想家たちである。代表的なヒューマニストとしては、ドイツのロイヒリン、オランダのエラスムス、イギリスのトマス=モア、フランスのラブレーやモンテーニュらである。彼らの思想は、カトリック教会の権威主義を否定することとなり、たびたび弾圧されたが、宗教改革の出現を促し、近代的な合理思想の源流となった。 |
| ロイヒリン
| ドイツの人文学者(ヒューマニスト)で、古典研究を進め、聖書の研究のためにヘブライ語の理解が必要であるとして、1506年、『ヘブライ語入門』を著す。これに対して保守的なカトリック神学者たちは、従来のラテン語による聖書解釈を脅かし、ユダヤ人を擁護するものと警戒し、ヘブライ語研究の自由を禁圧しようとし、1512年、ロイヒリンを異端として宗教裁判所に告発した。ロイヒリンも各地の人文学者の支持を背景に、対抗して争った。ルターの宗教改革に先駆ける動きであった。 |
| a エラスムス
| オランダ(ネーデルラント)のロッテルダム生まれの代表的なヒューマニストで、文献学者。文献に基づく確かな知識を大切にすることを主張した。その主著『愚神礼賛』(1509年)は聖職者たちの偽善を暴き、当時の全ヨーロッパに衝撃を与えた。イギリスに渡り、トマス=モアとも親交を持った。1516年に『校訂新約聖書』をバーゼルで刊行し、ギリシア語原典に立ち戻って新約聖書を校訂した。彼は聖書の正確な本文を確立し、老若、男女、貧富、地位、母語の相違を越えて誰でもが聖書を読み、聖書にもとづく生活をできるようにするべきだと主張した。この主張はルターの改革理念である「万人祭司主義」を先取りしているといえる。「エラスムスが産んだ卵をルターがかえした」と言われるほど、ルターやツヴィングリの宗教改革の先駆となったが、彼自身はルターの宗教改革にも批判的で、新旧両派から距離を置いた。 |
| b 『愚神礼賛』 | 1509年に発表された、オランダのエラスムスの著作。エラスムスがロンドンを訪問した際、トマス=モアと知り合い、その家で1週間で書き上げたという。刊行に際してもトマス=モアに献呈されている。『痴愚神礼賛』とも表記。痴愚の女神が語るという形式で、当時の教会の形式化や、聖職者の偽善をするどく風刺した書物。翻訳は岩波文庫『痴愚神礼讃』渡辺一夫訳がある。 |
c トマス=モア
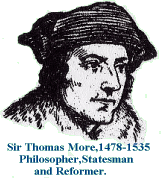 | ルネサンス、宗教改革時代のイギリスの代表的人文主義者(ニューマニスト)。『ユートピア』の作者。離婚問題などでヘンリ8世を批判したため大逆罪とされ、1535年に処刑された。
オックスフォードでギリシア語を学び、ヒューマニズムを知る。次いで法律を学び、法律家となる。若い頃、ロンドンにきたエラスムスと知り合い、生涯の友情を結んだ。エラスムスの『愚神礼賛』はロンドンのモアの家で書かれ、モアに献呈されている。1515年、外交交渉の一員としてオランダに渡り、アントワープに滞在中に『ユートピア』を書き始め、翌年ロンドンで発表した。外交交渉での手腕を買われ、帰国後ヘンリー8世の宮廷に出仕し、裁判官として務め、1529年には法律家としては最高位の大法官に任命された。しかし、そのころ、ルターの宗教改革の嵐がイギリスまで及んできて、宗教界は大きく揺らぎ始めた。トマス=モアは、ローマ教皇から信仰擁護者とされたヘンリー8世を支持し、ルターの改革には反対し、カトリックが唯一の正当なキリスト教である立場を守った。ところが、ヘンリー8世は、男子世継ぎを得るため王妃の離婚問題が起こると、モアはローマ教会の認めない離婚は不可であるとし、さらにヘンリー8世がローマ教会からの分離を図った首長法(国王至上法)の制定に対しても、俗人が教会の首長となることは不可能であるとして賛成せず、大法官を辞任した。ヘンリー8世は、反逆罪に当たるとしてモアをロンドン塔に幽閉、裁判の結果死刑が確定し、1535年7月6日に断頭台で処刑された。
Epi. この髯だけは大逆罪を犯していない――モアの処刑 「1535年7月6日、15ヶ月近く幽閉されていたため見るかげもなくやつれていたモアはついに処刑のために塔から引っ張る出された。その朝、ヘンリの使いが来て、刑場で群衆に向かって余り物をいわないようにとの命令を伝えた。途中で長女のマーガレットはモアの姿を群衆にまじってじっと見ていた。その際やせ衰えたモアに一人の婦人がすすみよって葡萄酒をすすめたが彼はそれを辞退した(マーガレットその人であったかもしれない。)モアはゆっくり断頭台にのぼり、ひざまずいて・・・・「詩編」五十一編を誦した。いよいよ最後になった時、モアはその場にいた人々に向かって「どうか私のために祈って下さい、そして私が聖なるカトリック教会の信仰を持ち、またその信仰のために、ここに死刑に処せられると言うことの事実の証人となって下さい。」といった。また伝説的な物語として、一度首きり台に首を横たえてから、また急に首斬人に向って「一寸まってくれ、髯をのけるから。この髯だけは大逆罪を犯していないからね。」といったという話がある。かくして、「法の名の下に行われたイギリス史上最も暗黒なる犯罪」が行われた。」<『ユートピア』 岩波文庫 平井正穂解説 p.209>
Epi. 映画『わが命つきるとも』 1966年製作、フレッド・ジンネマン監督作品。トマス=モアを名優ポール・スコフィールドが演じていた。モアがヘンリー8世の離婚問題に反対して処刑されるまでを、娘(スザンナ・ヨーク)の結婚などをからめて描いた映画で、淡々とした態度で自説を国王に説くモアの姿や、16世紀イギリスの宮廷生活が誇張無く淡々と描かれていて、この時代を知るよい勉強になる。 |
| d 『ユートピア』
| 1516年に発表されたトマス=モアの主著。ヒスロディという名の人物(アメリゴ=ヴェスプッチの航海に同行したという設定になっている)が対話するという形式をとり、理想社会としてユートピア(モアがギリシア語から造語したもので、「どこにもない国」の意味)という国を仮想し、イギリスの制度や社会を批判した。彼の描いたユートピアでは、人は6時間しか働かず、余暇を教養を高めることに充てることができ、僧とか貴族は存在せず、誰もが満ち足りた生活のできるものであった。一方で奴隷の存在はそのまま認めるなど、当時の限界を示している。また、当時進行した、新興地主による農地の囲い込み(エンクロージャー)を、「羊が人間を食べている」として批判したことも重要。『ユートピア』発表の翌年、ドイツでルターの宗教改革が始まる。
Epi. 『ユートピア』ところどころ トマス=モアが描く理想郷ユートピアはどんなところでしょうか。いくつか興味深い話をとりあげてみます。訳はいずれも岩波文庫の平井正穂訳による。
自由に出入りできる家:「どの家にも入口は二つある。一つは表通りへ、も一つは裏の庭へという風に。どちらの入口も両開きになっていて錠もかかっていなければ閂もおろされていない。指先で一寸押しただけでもすぐ開くし、閉まるのもひとりでに閉まる。したがって家の中に入ろうと思えば誰でも自由に入ることができる。それというのも、家の内には私有のもの、つまり誰々個人のものといったものがないからである。家そのものは十年ごとに抽籤によって取換えることになっている。」<p.77>
6時間労働制:「ユートピア人は昼夜を24時間に等分し、その中僅か六時間を労働にあてるにすぎない。すなわち、午前中三時間の労働、正午には直ちに昼食、食後は二時間の休息、その後で再び三時間の労働、次に夕食、――とこういう風になっている。・・・・・生活必需品にしろ文化品にしろ、あらゆる必要な物資を潤沢豊富にそろえるには、六時間という労働は決して足らないどころか、むしろ多すぎるくらいなのである。・・・・まず第一に、ほとんどすべての女子が、この仲間(労働者)にはいる。これが全人口の半数を占めているのである。・・・・」<p.82-84>
大きな病院:「なんといっても彼らが一番大きな注意を払っているのは、病院に入院している病人である。市のまわりの、城壁から少し離れたところに四つの病院があるが、これらの病院は、その大きさ、広さ、そのどっしりとかまえている有様はまるで一小都市の観さえあるくらいである。なぜこんなに大きく設計されたかというと、その理由の一つは、病人がどんなに多くてもけっして込み合ったりごたごたしないように、つまり、のびのびと気持ちよく療養できるようにというためである。」<p.98>――これは現代日本ではまさにユートピアになってしまった。
金を便器に使う:「金や銀でだいたい彼らは何をつくるかといえば、実に便器である。汚い用途にあてる雑多な器具である。さらに奴隷を縛るのに用いる足枷・手枷の鎖である。そして最後に、罪を犯したために破廉恥漢として皆に蔑まれている人間が耳につける耳飾りであり、指にはめる指輪であり、首にまく鎖であり、はては頭にまく鉢巻である。かようにしておよそ考えられるあらゆる手段方法を通じて、金銀を汚いもの、恥ずべきものという観念を人々の心に植えつけようとするのである。・・・・金というものは元来それ自体としては何の役にもたたないものである。にもかかわらず今日全世界の人々の間において非常に尊重されている、それも、元来なら人間によって、そうだ、人間が用いるからこそ、尊重されていたのに、今では逆に人間自体よりももっと尊重されている。なぜそうなのか、ユートピア人にはどうしても合点がいかないのである。」<p.103,p.107>
奴隷制度:「一般に戦争中に捕らえられた俘虜は奴隷にしない。それから奴隷の子も奴隷にはしない。また、外国からつれだしてきた人間はどんな人間でも、たとえ外国で奴隷であったにしても、ユートピアでは奴隷にしない。奴隷にするのは彼ら自身の同胞で凶悪な犯罪を犯したため自由を剥奪された者か、他国の都市で重い罪科の為に死刑の宣告を受けた者かに限られている。・・・(彼らは)全く度しがたい人間というほかはなく、苛酷な刑に充分値するというのである。もう一つ別な奴隷がいるが、これはもともと外国で哀れな労働者として酷烈な仕事をやらされていた者で、自ら志願してユートピアの奴隷となった者たちである。これらの奴隷に対する取扱は全く良心的でその待遇も丁寧であり、・・・自由民とほとんど変わりないくらいである。・・・」<p.130>
外国と同盟を結ばない:「同盟というものは、他の所では国と国との間で結ばれては破られ、破られては結ばれるといった工合に、反復常なきものであるが、ユートピア人はどこの国とも同盟を結ぶということはしない。・・・・・けちな山や川のために国土が離れ離れになっているからといって、まさかその国民たちが人間性という絆で一つにならないわけでもあるまいし、ただこういう同盟などというものがあるために、かえって国民どうしが生まれながらお互いに仇であり敵であるような錯覚を持つにいたるのである。・・・・人間本来の友愛の精神こそもっとも強固な同盟にほかならない。そうだ、人間というものは同盟の条文よりも愛と寛裕によって、また単なる条文よりも溢れるばかりの誠意によってこそ、強く、固く一つに結ばれることができるのだ。これが彼らの信念なのである。」<p.140,142>
戦争について:「戦争や戦闘は野獣的な行為として、そのくせそれを好んで用いる点にかけては人間にかなう野獣は一匹もいないのだが、彼ら(ユートピア人)は大いに嫌い呪っている。そして他の国々の習慣とはちがって、戦争で得られた名誉ほど不名誉なものはないと考えている。・・・自分の国を守るためか、友邦に侵入してきた敵軍を撃退するためか、圧政に苦しめられている友邦国民を武力に訴えてでも、その虐政の桎梏から解放してやるためか、そのいずれかでないかぎり戦争をするということはない。・・・」<p.144>
真の共和政国家:「この国は、単に世界中で最善の国家であるばかりでなく、真に共和国(コモン・ウェルス)もしくは共栄国(パブリック・ウィール)の名に値する唯一の国家であろう。いかにも共和国(コモン・ウェルス=公共繁栄)という言葉を今でも使っている所は他にもいくつもある。けれども実際にすべての人が追求しているものは個人繁栄(プライヴェイト・ウェルス)にすぎないからだ。何ものも私有でないこの国では、公共の利益が熱心に追求されるのである。・・・・・今日いたる所で繁栄をほしいままにしているあらゆる国家のことを深く考える時、神に誓ってもよいが、私はそこに、共和国の名のもとにただ自分たちの利益だけを追求しようとしている金持の或る種の陰謀の他、何ものも認めることはできない。」<p.176、p.178>
現代に通じるトマス=モアの「喝」 以上、その内容はチューダー朝ヘンリー8世の統治するイギリス王国に対する辛辣な批判である。ただし、いずれもユートピアを見聞してきたヒスロディの言葉として述べられいる。トマス=モアは自らは聞き手としての立場にとどまり、末尾で「結局私としては、たとえユートピア共和国にあるものであっても、これをわれわれの国に移すとなると、ただ望むべくして期待できないものがたくさんあることを、ここにはっきりと告白しておかなければならない。」<p.182>と述べている。用心深く、自分の意見ではないと表明したわけであろう。しかし、次の文は、時代を超えて、現在の年金問題などにみられる日本国家のありかたに対する「喝」として聞こえるのである。
「紳士などと呼ばれている連中や金属商人や怠けることかお世辞をいうことしか知らない奴らをやつまらない娯楽の創案者などに多額の報酬を払っているくせに、国家がたちゆくためになくてはならない貧しい百姓や坑夫や人夫や馬車引きや大工などに対してはなんら厚遇する道を知らない国家、いや、さらに、若い元気な時にはさんざん労働者たちを酷使しておきながら、彼らが年をとって老衰と病気に悩まされ全く無一文になってしまうと、もう彼らの昔のあれほどの仕事ぶりも忘れ果て、あれほどの貢献にも知らん顔をして、あげくの果ては冷酷にも、悲惨なのたれ死をもって御恩返しをしようという国家――こういう国家こそまさに不正な、不人情な国家というべきではないだろうか。」<p.177-178> |
| e ラブレー
| 16世紀前半のフランスの人文主義者(ヒューマニスト)。1532年から『ガルガンチュワとパンタグリュエル物語』を著わし、カトリック教会の因循姑息だけでなく、当時始まった宗教改革の新教徒の狂信ぶりなども、おもしろおかしく風刺し、その作品は禁書とされた。
ラブレーはフランスのシノンに生まれたが、生年は従来1494年説がとられていたが、最近では1483年説が有力であるという<宮下史朗『ラブレー周遊記』1997
東大出版会>。父は弁護士で相当の財産はあったが末子だったラブレーは、フランチェスコ派修道院で修道士として修行に入ったらしい。1517年、ドイツに始まる宗教改革がフランスにも及んできたころ、彼はラテン語、ギリシア語などの古典や法学を学び、エラスムスなどの人文主義の影響を強く受けた。しかし修道院ではギリシア語原典の研究を禁止されてしまった。その後修道院を出て各地をめぐりながら医学をヒポクラテスやガレノスらのギリシア語原典から学んだらしい。1532年、伝説の巨人を主人公にした『パンタグリュエル物語』(後の「第二の書」)を著し発表した。その後フランソワ1世の重臣がローマに派遣されたときの侍医として何度かローマに赴き、医者として名声を上げながら、リヨンで34年秋、匿名で『ガルガンチュア物語』(「第一の書」)を発表、続けて『パンタグリュエル物語』の第三の書を発表した。これらの書物はパリ大学神学部によって、「ふとどきで猥褻」な書物でキリスト教を冒涜するものであるという理由で禁書に指定された。ラブレーはその追求を逃れて潜伏し、52年には「第4の書」を初めて本名で発表したが、翌53年に死んだ。死後にラブレーの名で「第5の書」が出版されたが、それについては偽作説もある。<以上、渡辺一夫『ラブレー第一之書ガルガンチュワ物語』1973 岩波文庫 解説および巻末ののラブレー年譜から要約> |
| f 『ガルガンチュワとパンタグリュエルの物語』 | 16世紀フランスのラブレーが書いた書物で、1532年から1564年にかけて刊行された。「第一の書」『ガルガンチュワ物語』と「第2の書」〜「第5の書」の『パンタグリュエル物語』の全5編からなる物語。ガルガンチュワとその子パンタグリュエルは、伝説上の巨人であるが、ラブレーはこの二人を主人公としながら、自由奔放に逸脱して物語を展開した。抱腹絶倒、場面によってはばかばかしい話であるが、内容は当時のカトリック教会や修道院に対する激しい風刺となっていたので、カトリック神学の殿堂であるパリ大学神学部からにらまれ、禁書に指定されることになった。しかしその文章にはラブレーのギリシアやローマの古典に対する豊富な知識によるさまざまな装飾が施されており、文学としても価値が高い。また単なる教会批判ではなく、一方でカルヴァン派などの新教徒の狂信ぶりや、高等法院(裁判所)の形式主義なども笑い飛ばしながら批判している。そのためカルヴァンもラブレーとその著書を非難罵倒している。この書の内容は大部であり、豊富である。日本語への翻訳は戦前の渡辺一夫氏のものが現在、岩波文庫5冊本で読むことができる。その洒脱な翻訳、詳細にわたる註など、訳業は敬服に値するが、正直言うと読み通すのはなかなか骨が折れた。 |
| g モンテーニュ
| 16世紀フランス、ルネサンス時代のフランスの人文学者(ヒューマニスト)。1533〜92年。西フランスのモンテーニュの城主ミシェル。1580年に『随想録』を発表。その後イタリアを旅行し詳細な旅日記を残す。帰国後、ボルドーの市長を務める。おりからフランスは激しい宗教内乱であるユグノー戦争の最中であったので、モンテーニュは新旧両派の仲裁に苦心した。 |
| h 『随想録』
| |
| C ルネサンス末期の文学
| |
| a セルバンテス
| スペイン・ルネサンス文学を代表する『ドン=キホーテ』の作者。24歳の時、レパントの海戦に参加し、捕虜になると言う経験を持つ。『ドン=キホーテ』は、時代錯誤の騎士ドン=キホーテと、従者サンチョ=パンサがスペイン各地をめぐりながら繰り広げる滑稽な話を通じ、時代を風刺したもの。 |
| 『ドン=キホーテ』
| |
b シェークスピア

発見されたシェークスピア像(朝日新聞より) | 16世紀末から17世紀初めの、イギリス・チューダー朝エリザベス女王時代に活躍した詩人、劇作家。悲劇、喜劇、史劇あわせて36編の作品がある。『ハムレット』『オセロー』『マクベス』『リア王』が4大悲劇、その他、『ロミオとジュリエット』『ヴェニスの商人』『リチャード3世』『真夏の夜の夢』などなど。
Epi. 発見された存命中の肖像画 朝日新聞2009年3月11日朝刊によると、「ロンドンで3月9日、新たに発見されたシェークスピアの肖像画が、シェークスピア生誕地協会のウェルズ会長によって披露された。同協会によると、この肖像画はシェークスピアが死去する6年前の1610年に描かれ、存命中の肖像画としては唯一現存するものと見られる。ゆかりの一族が代々保有してきたが、06年までこれがシェークスピアの肖像画とは気づかなかったという(ロイター)。」 |

|
| 2.絵画・建築
|
| A 近代美術のめばえ
| 絵画は中世までは教会堂に付属する装飾に過ぎなかったが、ルネサンスではじめて独立した美術の分野となった。絵画の成立をもたらしたものは、ひとつには油絵の技法と、もうひとつは遠近法であった。まず中世からルネサンス時代まで、建物の壁に描かれた壁画はフレスコ画であったが、15世紀にフランドルで油絵技法が開発され、それがイタリアにも伝えられて大きな技術改革となった。また遠近法も、ルネサンス絵画から取り入れられ、深みのある写実的な表現を可能にした。これらの技術革新のうえに、近代絵画の出発点としてのルネサンス絵画がある。 |
| フレスコ画
| フレスコ画とは、13世紀末にトスカナ地方で登場し、14〜16世紀がその黄金期であったもので、本来は下地の漆喰がまだ乾かない”新鮮な”(イタリア語でフレスコ)うちに、水で溶いた顔料で描くブオン・フレスコの技法のことをいう。漆喰壁は乾いてしまうと顔料が固定しないので、朝、その日描く範囲だけ上塗りし、そこに下絵(シノビア)を描き、乾かないうちに顔料を固定剤を加えずに水だけで溶いて彩色していく。顔料は漆喰が乾くと固形化して剥落しないので、長く堅牢な絵として残るのである。この技法は部分部分を完成させながら、跡で修正がきかないので、綿密な計画性と特別な熟練を必要とするものであった。<山手学院美術科の渡辺義明先生のご教示による> |
| 油絵技法
| 油絵技法(油彩画)は14世紀のイタリアの画家(チェンニーノ・チェンニーニ)にその技法に関する記述があるが、一般には、15世紀のフランドルで技術改良が行われ、ファン=アイク兄弟が高い芸術的水準を実現して以降、イタリア・西欧各地に伝わった。油彩はテンペラ画に使用された画材や画法の延長上に成立した。16世紀イタリアのヴェネツィア派(ジョルジョーネ、ティッツァーノら)により絵の具の厚塗りや筆触の効果など、近代的技法につながる表現方法が興った。そして17世紀スペインのベラスケスなどによって伝統的技法として確立させていく。<同上> |
| a ジョット
| 13世紀の終わりから14世紀初めにあらわれた、イタリア・ルネサンス美術の先駆者。フィレンツェのサンタ=マリア大聖堂に隣接する大鐘楼(ジョットの鐘楼)を建設し、絵画ではフレスコ画による宗教画を制作した。その画風はルネサンス様式の始まりとされる。代表作に『聖フランチェスコの生涯』など。 |
| b マサッチョ
| マザッチョとも表記。15世紀初めにフィレンツェにあらわれ、ジョットの画風を引き継ぎ、ドナテルロの彫刻と、ブルネレスキの建築に学びながら、ルネサンス絵画技法である遠近法を開拓した。『楽園追放』などが代表作。 |
| c 遠近法
| 遠近法(パースペクティヴ)は、フィレンツェのサンタ=マリア大聖堂の設計中に、ブルネレスキが気づいて、作図を始めたという。1436年のアルベルティの『絵画論』がその理論を展開した最初の書となり、たちまちのうちにさまざまな実験的な作品が作られた。マサッチョ、フラ=アンジェリコなどが初期の遠近法の作品を残している。そしてレオナルド=ダ=ヴィンチの『最後の晩餐』の背景が遠近法で描かれ、見る人に臨場感を深みを感じさせる作品となった。また、遠近法(透視画法)は、人間の視点から世界を見るという人間中心世界像の登場を意味する、との指摘もある。<高階秀爾『フィレンツェ』1966
中公新書 p.91> |
| ギベルティ
| 15世紀初め、フィレンツェで活躍した彫刻家。ゴチック様式の要素を残しながら、多くの作品を残した。1401年、フィレンツェのサンタ=マリア大聖堂のサン=ジョバンニ洗礼堂の扉の制作者を決めるコンクールで、23歳で当選し、25年かかって完成させた。 |
| ドナテルロ
| フィレンツェの彫刻家。ブルネレスキの近代的作風の彫刻を受け継ぐ。その時代はギベルティ風のゴチック様式を残した穏健、繊細な作風が主流を占めたので、ドナテルロの作品は評価が低かったが、次のミケランジェロにつながるものとして重要である。代表作はパドヴァの「ガッタメラータの騎馬像」など。フィレンツェではコジモ=ディ=メディチの保護を受けた。 |
| B ルネサンス様式 | ルネサンス様式の建築(あるいは美術全般)様式に先行したのは、ゴシック様式であった。ゴシック様式は教会堂建築に見られるもので、高い尖塔とそれを支える肋骨(リブ)が特徴であり、末期には装飾的となっていた。ルネサンス様式は15世紀にフィレンツェを中心のイタリアで隆盛したもので、ローマの古典文化を復活させ、優美と調和を理想とするものであった。また、イスラーム建築の影響も見られる。絵画では装飾的な要素は無くなり、写実性が強くなった。代表的なルネサンス様式の建築には、ブルネレスキが設計したフィレンツェのサンタ=マリア大聖堂や、ブラマンテ、ラファエロ、ミケランジェロが関わったローマのサン=ピエトロ大聖堂がある。 |
| a ブルネレスキ
| はじめは彫刻師(金属細工師)として、1401年、フィレンツェのサン・ジョバンニ洗礼堂の門扉の製作者を決めるコンクールで、ギベルティと最終選考をきそい、僅差で落選したという。両者同じテーマで競作したがギベルティの作品はゴシック的な要素を残した繊細なもので、ブルネレスキはドラマチックで新しい作風を示したという。ブルネレスキは落選したため、彫刻を断念し建築に向かうようになったという。このようにコンクールによって実力のあるものが評価されるというのが始まったのもルネサンス時代の特徴であった。建築に転じたブルネレスキは、1421年から36年までに、フィレンツェのサンタ=マリア大聖堂の大円蓋を完成させ、ルネサンス様式建築の代表作となった。<高階秀爾『フィレンツェ』1966
中公新書 p.66-71、100-107> |
| b サンタ=マリア大聖堂
| フィレンツェの町の中心部にある大聖堂。花の聖母マリア大聖堂(サンタ=マリア=デル=フィオーレ大聖堂)ともいう。13世紀の末から造営が始まっていたが、15世紀になってもまだ完成していなかった。最大の問題は中心の大円蓋をどのように建造するかであったが、当初の建築責任者であったギベルティに代わって建築を監督したブルネレスキが、1421〜36年の間に、八角形の胴部の上に二重殻構造を持った煉瓦作りの円蓋を載せることに成功した。このルネサンス様式を代表する建造物は、現在もフィレンツェの中心に当時のまま見ることができる。 |
| c ブラマンテ
| 中部イタリアのウルビーノの出身(1444〜1514)。ミラノの実力者ルドヴィゴ=スフォルツァ(イル=モーロ)にまねかれサンタ=マリア=デラ=グラッツィェ聖堂建築にあたった(その壁画はダ=ヴィンチが描いた『最後の晩餐』)。晩年はローマに招かれサン=ピエトロ大聖堂の建設にあたったが生前には完成せず、ラファエロ、さらにミケランジェロに引き継がれた。 |
| d サン−ピエトロ大聖堂 | → サン=ピエトロ大聖堂 |
| C ルネサンス美術の最盛期
| |
| a ボッティチェリ
| 15世紀、全盛期フィレンツェ出身の画家(1444〜1510)。フィリッポ=リッピとヴェロッキオの工房(アトリエ)で腕を磨き、ロレンツォ=ディ=メディチの愛顧を受け、プラトン=アカデミーにも招かれる。代表作『春』と『ヴィーナスの誕生』はともにキリスト教の題材、ギリシア神話を題材としたもので、当時のフィレンツェの思想動向である新プラトン主義と人文主義をよく示している。まさに人間賛歌ともいえるこの二つの傑作は、またルネサンスの華美と頽廃を象徴するものとして、サヴォナローラの批判を浴びた。メディチ家がいったんフィレンツェを追放された後、サヴォナローラが権力を握ると、ボッティチェリもその説に心酔し、画風を全く変えてしまう。そしてサヴォナローラ没落後は再び絵筆をとることなく、寂しい晩年を送ったという。
作品:『春』1478年。フィレンツェのメディチ家のロレンツォ(イル=マニフィコ)の従弟のために製作されたテンペラ画。オレンジの実暗い森の中でヴィーナスを中心にフローラや美の三女神を配し、春の喜びの到来を装飾的に描いている。また『ヴィーナスの誕生』と対になっていて、ヴィーナスが海の泡から誕生した神話を題材にしている。ヴィーナスはローマ神話の「美と愛」の女神(ヴェヌス)であり、ギリシア神話でのアフロディーテにあたる。ボッティチェリが、キリスト教の主題ではなく、神話に題材を求めているところに、ルネサンス美術の精神を見ることができる。 |
| b ラファエロ
| ウルビーノの出身で名はラファエロ=サンティ。同郷のブラマンテの推薦でローマに招かれ、サン=ピエトロ大聖堂の建築、壁画の制作にあたった。26歳でヴァチカン宮殿署名の間に『アテネの学堂』を描き、ルネサンス絵画の集大成と言われた。その後も『聖母子像』など大量の作品を描き続け、ブラマンテ死後はサン=ピエトロ大聖堂の建設の指揮を執った。37歳で早世し、その墓はローマのヴァチカン宮殿の中に作られている。
Epi. ルネサンス絵画の総合『アテネの学堂』 ヴァティカン宮殿署名の間の『アテネの学堂』には、プラトンとアリストテレスを中心に、たくさんのギリシアの学者を描き込んでいる。またそのモデルはラファエロと同時代の芸術家たちであった。例えば、プラトンはレオナルド=ダ=ヴィンチ、哲学者ヘラクレイトスはミケランジェロ、数学者ユークリッドはブラマンテをモデルにしたと言われている。<樺山紘一『ルネサンスと地中海』p.157> |
| c ミケランジェロ
| 1475年、フィレンツェ近郊の村で石工の子として生まれる。本名はミケランジェロ=ブオナロッティ。フィレンツェとローマで活躍し、ルネサンスを代表する彫刻、絵画、建築を残している。フィレンツェでは、『ダヴィデ像』(大理石の彫刻、1501〜4年に制作。もとはフィレンツェのシニョリア広場にすえられ、民衆のシンボルとなった。)が有名。ローマにはルネサンスの保護者となったユリウス2世に招かれて行き、教皇の墳墓設計にあたり、『モーセ像』(大理石彫刻)を制作した。ついで、ヴァティカン宮殿(ローマ教皇庁のある建物)の一部のシスティナ礼拝堂の壁画の制作にあたった。天井には『天地創造』を、正面の祭壇の背後の壁には『最後の審判』を、それぞれ、ほとんど独力で、フレスコ画の手法で描いた。ミケランジェロの作品に見られる人間表現は、古代のギリシアやローマの彫刻に範をとり、その肉体の美しさ、力強さを最大限に描いたものであった。ついでローマのサン=ピエトロ大聖堂の建築にも関わり、ブラマンテ、ラファエロなどに続き、ブラマンテの当初設計を拡大し現在の姿にした。 |
| d サン=ピエトロ大聖堂
| → サン=ピエトロ大聖堂 |
| e レオナルド=ダ=ヴィンチ
|
1452年、トスカナ地方の小さな村ヴィンチ村で生まれ(その生家と言われる家が今でも残っている)、1469年にロレンツォ=ディ=メディチの統治が始まったフィレンツェに出てヴェロッキョの工房で絵画、彫刻の修行をする。絵画としては『モナ=リザ』(油絵技法による神秘的な微笑で知られる、ルーブル美術館蔵)、『最後の晩餐』(従来のフレスコ画ではなく油絵技法による壁画でミラノの聖マリア=デッレ=グラツィエ聖堂にある。十字架にかかる前夜のキリストと12人の使徒を描いており、遠近法に構図と緊張感ある使徒の表情を注目。現在剥落が心配されている。)、彫刻ではミラノ公のための『騎馬像』などがある。彼は科学者、あるいは土木建築家としての一面もあり、潜水艦や飛行機、ヘリコプター、戦車などを構想し、人体の解剖も行った。また「リラ」という楽器の演奏にすぐれた音楽家でもあったとされており、ルネサンスの典型的な「万能人」であった。晩年はフランスのフランソワ1世に招かれて、アンボワーズに住み、国王の寵愛を受けながらフランスにルネサンスの風を吹き込み、1519年にそこで死去する。
Epi. レオナルド=ダ=ヴィンチの謎 レオナルドについては、その名声にもかかわらず、昔からさまざまな謎がつきまとっていた。その出生に関しては、私生児であることがわかっているが生涯独身を等したことも謎とされている。また左利きであったため、文字は裏返しに書く「鏡像文字」で書いていた。なお、フロイトは彼の手記を分析して同性愛者であったと推測している。<斉藤泰弘『レオナルド=ダ=ヴィンチの謎』−天才の素顔 1987 岩波書店> |
| f 万能人
| ルネサンス時代の人間観として、職業や趣味にとらわれることなく、あらゆる事に普遍的な関心を持ち、能力を発揮することが理想とされた。絵画や彫刻、建築などに通じ、また音楽や文学などにも親しみ、同時に科学的知識も豊かに持つというレオナルド=ダ=ヴィンチに典型的に見られるが、他のルネサンス期の人びともおよそそのような傾向を持っていた。近代以降の資本主義社会での分業システムが細分化され、職業が固定化されてしまったが、それ以前の中世からルネサンス期までの人間はむしろ、このような「普遍的な人間」が当たり前の存在であったといえよう。なお、「万能人」をルネサンス期の人間のあり方として論じたのも、19世紀のドイツの歴史家ブルクハルトで、その著作『イタリア・ルネサンスの文化』で展開したものであった。 |
| D アルプス以北のルネサンス美術
| |
a ファン=アイク兄弟

ヤン=ファン=アイク『アルノルフィニ夫妻の肖像』1434 | 14世紀末から15世紀初めのネーデルラントの一部、フランドル(フランデレン)の画家。ファン=エイクとも表記。兄(フーベルト)は1426年、弟(ヤン)は1441年没。フランドルのブリュッヘとヘント(いずれも現在のベルギー)で活動。兄弟合作のヘントの聖ヨハネ聖堂の祭壇画、弟ヤンの肖像画の作品が有名(代表作は『アルノルフィニ夫妻の肖像』1434年)。一般にファン=アイク兄弟は油絵技法の発明したと言われている。実際には兄弟の登場以前からフランドルでは油絵が描かれており、兄弟がその技法を完全なものにしたと考えられている。油絵の技法とは、顔料を亜麻仁油(リンシードオイル)で溶かし、何重にも塗り重ねができ、微妙な色のニュアンスをだせるもので、写実的な表現に適していた。この技法はフランドル地方ではじまり、イタリアに伝えられた。イタリアでは中世以来、フレスコ画やテンペラ画が作られていたが、15世紀以降は油絵が描かれるようになり、ルネサンス以後の絵画の主流となる。これはイタリア=ルネサンスがアルプス以北に影響を与えただけでなく、その逆もあったことの例である。<高階秀爾『フィレンツェ』1966
中公新書 p.83>
出題 05年 東大 「図版(左)は画家ヤン・ファン・アイクが1434年に製作した油彩画で、これはネーデルラントの都市ブリュージュ(ブルッヘ)に派遣されたメディチ家の代理人とその妻の結婚の誓いが描かれている。この時代のネーデルラントは、イタリア諸都市と並んで、この絵の中に描かれているあるモノの生産で栄えたが、やがてその生産の中心はイギリスへ移っていった。この製品の名称を答えなさい。」
→ 解答 毛織物 夫妻が着ている着物が毛織物。毛織物の産地はイタリアとネーデルラントからイギリスに移った。 |
| b フランドル派
| ルネサンス期の14世紀末にフランドル地方(ネーデルラントの一部。現在のベルギー)で起こった絵画の一派。フランドル地方は毛織物業が発達し、ヘント(ガン)やブリュージュなど商業都市が繁栄していたことが、職業的な美術家が輩出した背景にあると考えられる。まずファン=アイク兄弟が油絵技法を発明し、独自の写実的な画風を確立し、イタリア絵画にも大きな影響を与えた。16世紀には農民生活に題材を求めたことで知られるブリューゲルが現れた。フランドル派絵画はバロック美術にも受け継がれ、ルーベンスとファン=ダイクが活躍した。 |
| c ブリューゲル | 16世紀のフランドルの画家(1528〜69)。農民生活を題材に、生き生きとした作品を多数残している。 |
| d デューラー | ドイツのニュルンベルク生まれの画家(1471〜1528)。生涯に二度、イタリアを訪ね、ヴェネティアでルネサンス絵画を学んだ。ドイツでは伝統的に版画が盛んで、デューラーも多くの版画を残しているが、このイタリア訪問でヴェネツィア派の多彩な自然描写と人体表現を学んだ。ドイツに帰国して折からの宗教改革に遭遇し、その影響を受けた宗教画を生み出す。1526年の『四使徒像』が代表作。デューラーはこの作品を、注文によってではなく、自己の表現欲から制作しており、ルネサンスの中で、画家が注文によって詩作する「職人」から、自分の意志で創作する「作家」に変質したことを示している。 |
| e ホルバイン | 16世紀前半のドイツの画家。イタリアで学んだ後、イギリスに渡り、ヘンリー8世の宮廷で画家として仕え、多くの肖像画を残した。ヘンリー8世、トマス=モア、エラスムスなどの肖像がある。 |

|
| ウ.科学と技術
|
| a 地動説
| |
| b コペルニクス
| ポーランドの天文学者(1473〜1543年)。生涯を地動説の研究に充て、その死の年に『天球の回転について』を出版。 |
| c ジョルダーノ=ブルーノ
| 16世紀に登場したイタリアの自然哲学者で、15世紀にギリシアからもたらされたヘルメス文書という古代の科学に関する文献を解読し、物質をごく微細な原子(アトム)の集合体と見なし、人体から天体まですべての存在をアトムの離合集散で生成し分解すると宇宙観に達した。ブルーノの説は自然観察をもとにしたものではなかったが、近代以降の宇宙観を直感によって先取りするものであった。しかし彼の説は、魔術に属するものとされ、教会は異端の宣告をした。そのため著作は発禁とされ、1600年に有罪判決を受け、ローマで火刑に処せられた。一般に、16世紀最末年ののジョルダーノ=ブルーノの処刑を以て、ルネサンス時代の終わりとされる。 |
| d 羅針盤
| → 第3章 3節 羅針盤 |
| e 遠洋航海
| → 第9章 1節 遠洋航海術 |
| f 火薬
| → 第3章 3節 火薬 |
| g 火砲(鉄砲)
| 中国では11世紀頃までに硝石、硫黄、木炭を主成分とした黒色火薬が知られていた。それが13世紀ごろヨーロッパに伝わり、次第に発火装置が改良されて、14世紀末から15世紀の百年戦争の時代に、火砲が作られるようになったがそれは大砲という形であり、手で持ち運べる銃はまだ発明されていない。大砲は初めは鋳物として作られ、臼砲とカノン砲の二種類があった。臼砲は大きな弾丸を高く発射して着弾させるもので方針は太くて短く、カノン砲は小型の弾丸をまっすぐ飛ばして目標に当てるもので方針は細くて長い。砲弾は初めは石だったが鉛から鉄になり、15世紀中頃には破裂弾も作られた。また独立した砲兵隊が車に乗せた大砲を運搬するようになった。その大砲を小型化して持ち運べるようにしたのが小銃で、15世紀に現れた火縄銃が最初である。ヨーロッパではルネサンスの末期にあたる15世紀末から16世紀前半に起こったイタリア戦争で、火砲の使用が急速に重要度を増し、戦争の形態を一変させる軍事革命が起こった。さらに17世紀には火打ち石装置の銃に改良され、18世紀以降は大砲・小銃とも急速に発達して、戦争の時代を出現させた。 |
| h 活版印刷術
| 活版印刷とは、活字とインク、それに紙、そして活字に付いたインクをうまく紙に刷る印刷機、の4つの条件が必要であるが、それらの条件のそろった活版印刷は15世紀にヨーロッパで始まった。木版印刷はすでに唐の時代からあったし、ローマでも金属に文字を刻んで布にすることが行われていたがそれらは活版印刷とは言えない。13世紀の高麗で、金属活字が作られたが、それは大蔵経という経典を作るためのもので一般的な書物の発行のための活版印刷としては進歩しなかった。一般に活版印刷を始めたのはドイツのグーテンベルクといわれているが、はっきりしたことは解らない。グーテンベルクは最初の発明でなかったかも知れないが、彼が改良した印刷機は大量な印刷を可能に、彼自身も印刷所を最初に経営しているので、活版印刷の創始者の栄誉を担っていると言っていいだろう。 |
| i グーテンベルク
| 15世紀のドイツ、マインツの出身。シュトラスブルクで活版印刷術を研究し、1440年ごろに完成させたという。後にマインツに戻って印刷業を開業。1455年頃、『グーテンベルク聖書』と言われる聖書を出版した。この活版印刷による聖書の普及が、宗教改革の広がりに大きく貢献した。また、グーテンベルクの考案した活版印刷は、その後急速に発達し、近代の印刷術の基礎を作った。 |
| j 宗教改革
| → 第9章 3章 宗教改革 |
 |