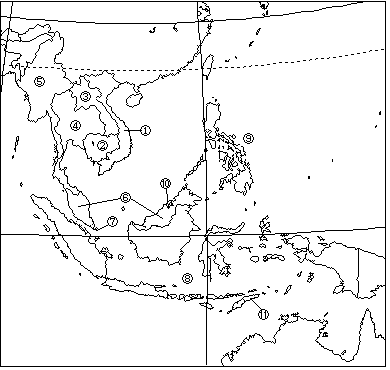
1.東南アジアの諸地域 全体の特性をつかみ、かつAとBの地域の違いをつかむこと。
A.大陸部 インドシナ半島。主要河川 紅河、メコン川、チャオプラヤ(メナム)川、イラワディ川
B.諸島部 マレー半島と島々。主要な島 スマトラ島、ボルネオ島、ジャワ島、スラウェシ島、モルッカ諸島など
作業 1.白地図に上記の河川と河川名、および半島名、島嶼名を記入する。
2.大陸部と諸島部の現在の国家を下の白地図で確認する。
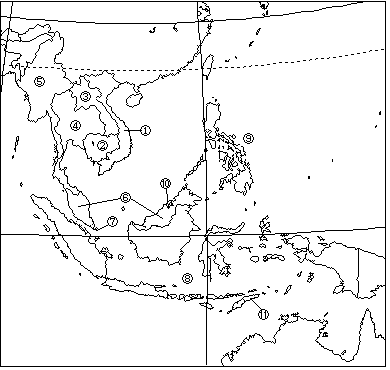
2.東南アジア史の重要ポイント 流れをつかむ
・前5世紀~紀元前後 a 大陸部は中国文明の影響を受け、ベトナム北部は秦・漢の支配を受ける。
・1世紀~ b 季節貿易が盛んになり、ベトナム南部の扶南など港市国家が発達。
・3世紀~ c 大陸部で「インド化」始まり、チャム人、クメール人の文化が形成される。
・7、8世紀~ d 諸島部のシュリヴィジャヤ王国、シャイレンドラ王国など港市国家の発展。
・12~13世紀 e 半島部のクメール王国の全盛期。アンコール=ワットの建造。
・13世紀~ f 元軍の来襲。パガン朝は滅亡。陳朝は撃退。タイ人の南下。ジャワ島でマジャパヒト王国が最盛期に。
・15世紀~ g 諸島部のイスラーム化が進み、マラッカ王国が繁栄。明の鄭和艦隊が来航。
・16世紀~ h ヨーロッパ勢力(ポルトガル)の進出始まり、香辛料貿易を展開。
・19世紀~20世紀 i スペイン、オランダ、イギリス、アメリカによる植民地支配が進む。
→ 日本軍国主義の進出 → 第2次世界大戦後の独立、ASEAN諸国の発展。(以下別項)
| 1.北部ベトナムの動き a ベトナム人 はオーストラロアジア語族(南アジア語)に属する。 | |
| 前5世紀ごろ |
北部ベトナムの紅河流域にb ドンソン文化 おこる。中国の影響を受けた文化。 青銅製の祭祀用具(c 銅鼓 )が特徴 → 東南アジア各地に広がる。 |
| 前3世紀 | 秦の始皇帝の支配を受ける。秦末の混乱で、d 南越 が中国南部を含み独立。 |
| 前2世紀末 |
e 漢の武帝 がd 南越 を滅ぼし、北部ベトナムにf 交趾 、九真、日南郡の三郡を 設ける。 → 後漢も北部ベトナム支配を継続、交州と改称。 |
| 1世紀中頃 |
g 徴姉妹の反乱 チュンチャクとチュンニの姉妹が後漢の支配に抵抗。 → 直接支配に切り替え、その後も中国諸王朝の支配続く。 |
| 7世紀 |
h 唐 が交州にi 安南都護府 をおく。 → 鎮南都護府となる(日本人の阿倍仲麻呂が都護となる) |
| 10世紀 | 唐の衰退、ベトナムの自立すすむ。呉朝、丁朝、黎朝など短期王朝が続く。 |
| 1009年 |
j 大越国 が成立。李公蘊がk 李朝 を建てる。ベトナム最初の統一王朝。 都昇龍(ハノイ)。中国文化を取り入れ、仏教や儒教を保護。 → 宋軍を撃退。中国南部の大理や中部ベトナムのチャンパーに遠征。 |
| 1225年 | l 陳朝 が起こる。 → 科挙を整備。戸籍を作る。 |
| 13世紀 |
三度にわたるm 元の侵入 を撃退。 漢字をもとに独自の文字であるn 字喃(チュノム) をつくる。 |
| 1400年 1407年 |
o 胡朝 成立。n 字喃(チュノム) を奨励。 明のp 永楽帝 に征服され併合される。 |
| 1418年 |
黎利が明から独立しq 黎朝 を建てる。その後は朝貢を続ける。 → 都はハノイ(東京)。明朝の制度を学び、朱子学が盛んになる。 |
| 15世紀後半 |
ベトナム中部のr チャンパー (占城)を征服。 → ベトナムの統一。 → 南北に分裂。 北部を |
| 1773年 1778年 |
s 西山党の乱 。西山党の阮氏がベトナムを統一。 t 西山朝 となる。 → 南部ベトナム(メコンデルタ)に支配を及ぼす。 |
| 1802年 |
u 阮福暎 が、v 阮朝 を建てる。フランス人宣教師ピニョーが支援。 都はフエ。w 清 を宗主国とし、越南国王と称す。 |
| 2.中部ベトナムの動き a チャム人=オーストラロアジア語系 | |
| 紀元前5世紀頃 129年ごろ 2世紀末 |
ドンソン文化と同時期、中南部ベトナム海岸には漁撈民のb サーフィン文化 が成立。 後漢から自立 → 東西貿易の中継地となりc 港市国家 として発展。 d 林邑 を建国(中国史料での表記)。後には環王とも表記される。 |
| 3世紀頃 7世紀以降 9世紀~ |
e インド化 が始まる。 f チャンパー と称するようになる。 中国でg 占城 と言われるようになる。 →h 占城稲 、宋に伝えられる。 |
| 11~12世紀 13世紀 15世紀後半 17世紀まで |
北部ベトナムのi 大越 と抗争、 西のj アンコール朝 とも抗争し一時制圧。 k 元の侵入 を受けるがしりぞける。 北部ベトナムのl 黎朝 によって、ほぼ滅ぼされる。 → ベトナムの統一すすむ。 残存勢力も完全に滅亡。中部ベトナムは阮氏政権に支配される。 |
→19世紀後半 ベトナム全土にm フランス が進出。カンボジア・ラオスと共に植民地化。
| 1.カンボジア a クメール人 オーストラロアジア語系(マレー=ポリネシア系説もある)。 | |
| 1世紀末 |
メコン下流にb 扶南 を建国。南部ベトナムを含む。=東南アジア最古の王朝。 インドから来航したバラモンと現地の女性が結婚して建国したという神話を持つ。 → その港のc オケオ からは中国、インド、ローマの遺品が出土している。 → 南シナ海交易圏のd 港市国家 として海上貿易で繁栄。→7世紀まで存続。 |
| 3世紀 | e インド化 が進み、ヒンドゥー教が浸透。 |
| 6世紀 |
f カンボジア(真臘) メコン川中下流域に建国。都アンコール。 → 扶南をあわせメコン中下流を支配。g ヒンドゥー教 を国教とする。 |
| 8世紀 | 南北に分裂(北部を陸真臘、南部を水真臘という) |
| 9世紀以降 | 統一を回復、h アンコール朝 という。唐に朝貢。 補足 クメール文字をつくる。 |
| 12世紀 |
i スールヤヴァルマン2世 がj アンコール=ワット を建設。 = はじめk ヒンドゥー教 寺院として造営される。→ |
| 1177年 | 中部ベトナムのl チャンパー に侵攻される。 |
| 12~13世紀 |
m ジャヤヴァルマン7世 、チャンパーを撃退し、全盛期となる。 n 大乗仏教 を信仰。o アンコール=ワット はn 仏教 寺院となる。 王宮のp アンコール=トム を建設。インドシナ全域を支配する。 道路網、病院、石造寺院を多数建築。その死後、アンコール朝衰える。 |
| 補足 | 1296年 元の使節に従い、周達観が来る。『真臘風土記』を残す。 |
| 15世紀 | 西隣のタイのq アユタヤ朝 の勢力に圧迫される。 |
| 18世紀後半 19世紀 |
メコン川下流、デルタ地帯をベトナムに奪われる。 都をプノンペンに移す。 |
→ベトナムとカンボジアはラオスと共にr フランス の植民地となり第2次世界大戦後独立。
| 1.タイ はじめa モン人 =オーストロアジア語系、後にb タイ人 =チベット語族が建国。 | |
| 7世紀 ~8世紀 |
チャオプラヤ川下流にモン人が c ドヴァーラヴァティ王国 を建国。 →d 上座部仏教 ひろがり、仏像などが作られる。唐に朝貢。 チャオプラヤ川を利用し、内陸部と南シナ海交易圏を結ぶ、e 港市国家 であった。 |
| 12世紀 | カンボジアのクメール人f アンコール朝 の支配を受ける。 |
| 13世紀 | モンゴルが中国南部の雲南地方に侵入、その地のb タイ人(シャム人) が南下。 |
| 1257年 | タイ人がg スコータイ朝 家国。チャオプラヤ川上流でアンコール朝から自立。 |
| 13~14世紀 |
ラーマカムヘーン王の時、全盛期となる。上座部仏教を保護する。 クメール文字をもとにh タイ文字 が作られる。 |
| 14世紀中頃 |
タイ人のi アユタヤ朝 、チャオプラヤ川下流に起こり、アンコール朝を破る。 スコータイ朝を併合。米などの輸出で繁栄した、典型的なe 港市国家 。 |
| 17世紀初め | 都のアユタヤは国際都市として発展、j 日本人町 なども作られる。。 |
| 17世紀 | 全盛期となり、領土最大となる。→ ビルマ、マレー半島にも進出。 |
| 1680年代 1767年 1782年 |
親フランス政策をとり、ルイ14世に使節を派遣。 → ビルマのk コンバウン朝 に滅ぼされる。一時、トンブリ朝となる。 タイ人のl チャクリ(ラーマ1世) 、ビルマ人を退けて独立。 =m ラタナコーシン朝(チャクリ朝) →n バンコク朝とも言う。 |
| 19~20世紀 |
o ラーマ5世 、近代化政策に成功。 現在も立憲君主国として存続。 |
| 2.ラオス a ラオス人(ラオ人) はタイ人と同じシナ=チベット語系。 | |
| 14世紀なかば |
メコン中流にb ランサン王国 が繁栄。ランサンとは「百万頭の象」の意味。 はじめルアンプラバンを都とする。 |
| 16世紀 17世紀 19世紀 |
都をビエンチャンに移す。ビルマの侵攻を撃退。 スリニャウォンサー王のとき、全盛期。その死後、分裂し衰退。 c フランス の植民地支配を受ける。 |
| 1.ビルマ イラワディ川流域に、シナ=チベット語系の民族が興亡した。 | |
| 8~9世紀 | イラワディ川中流にa ピュー人 (シナ=チベット語系)の国が栄える。 →b 上座部仏教 を受け入れれる。 → 北方の南詔の攻撃を受け、衰退。 |
| 9世紀 | イラワディ川河口海岸部 ペグーにc モン人 (オーストラロアジア系)が繁栄。 → ベンガル湾でインドとの交易を行ったd 港市国家 。 |
| 10世紀 | チベットからe ビルマ人 (シナ=チベット語系)が南下、先住民と同化。 |
| 1044年 | イラワディ川中流に ビルマ人のf パガン朝 が成立。ビルマを初めて統一。 海岸部のモン人からg 上座部仏教 を受け入れる。スリランカと交流。 → h ビルマ文字 を作る。 → 首都パガンに多くのi 仏塔・寺院 が建立される。j 建寺王朝 という。→ |
| 1287年 | k 元の侵入 を受けて滅亡する。 いくつかの地方政権に分裂。 → 海岸部にはモン人のl ペグー朝 が存在。 |
| 16世紀 | ビルマ人、m トゥングー朝 が成立。1539年、ペグー朝を併合。 仏教国。 米、獣皮などの輸出で繁栄。 → 海岸部のモン人の離反で滅びる。 |
| 1752年 1767年 |
ビルマ人のn アラウンパヤー がモン人を制圧しo コンバウン朝 を建国。 タイのp アユタヤ朝 を滅ぼし、一時有力となる。 |
| 19世紀 |
インドからq イギリス が進出。三度にわたるr イギリス=ビルマ戦争 で敗れる。 |
→ビルマはイギリスの植民地となり第2次世界大戦後独立。現在、国名はs ミャンマー となる。
| 1.マレー半島とスマトラ、ジャワ島など現インドネシア a マレー人 =マレーポリネシア語系の地域 | |
| 1世紀頃 | インド洋のb 季節風貿易 始まり、マラッカ海峡から南シナ海に交易圏広がる。 |
| 7世紀 |
スマトラ島東南部のc シュリーヴィジャヤ王国 マラッカ海峡をおさえ繁栄。 → 唐に朝貢、中国で室利仏逝・三仏斉と表記される。中心都市パレンバン。 → 唐のd 義浄 が訪れ、大乗仏教の繁栄の状況を中国に伝える。 |
| 8世紀 |
ジャワ島 e シャイレンドラ朝 ジャワ島を中心に海上貿易を支配。 f ボロブドゥール にg 大乗仏教 の寺院などの建造物を残す。 ジャワ島に古マタラム王国が存在。プランバナン寺院(ヒンドゥー寺院)を残す。 |
| 10世紀 |
ジャワ島東部に、h クディリ朝 が起こる。 =ヒンドゥー教国。 → インドから『マハーバーラータ』『ラーマーヤナ』が伝わり、 i ワヤン=クリ (影絵芝居)が始まる。 |
| 11世紀 1222年 1292 |
南インドのチョーラ朝の侵入のため、シュリーヴィジャヤ王国は衰退。 ジャワ島東部にj シンガサリ王国 が起こり、クディリ朝を滅ぼす。 → フビライの使節を追い返したが、内紛によって滅亡。 |
| 2.諸島部のa イスラーム化 の始まり | |
| 13世紀末 |
ムスリム商人の活動、b スーフィズム の活動により、c イスラーム教 が広がる。 スマトラ島北部の港市サンドラ=パサイの王がイスラーム信仰を始めたという。 |
| 1293年 14世紀 |
ジャワ島東部に、元軍を撃退したd マジャパヒト王国 が興隆。 →はじめ仏教を保護。 → 全盛期となり、インドシナ半島にも進出。 → 次第に、e ヒンドゥー教 化する。 |
| 1400年頃 |
マレー半島にf マラッカ王国 成立 → g マラッカ海峡 を抑え香辛料貿易で繁栄。 → 国王がc イスラーム教 に改宗(東南アジア最初のイスラーム教国)。 |
| 15世紀 |
→ マレー半島の南西部を拠点に、h 港市国家 として繁栄。 →諸島部のa イスラーム化 進む。フィリピン南部ミンダナオ島まで広がる。 |
| 1405年 |
明の永楽帝の派遣したi 鄭和 が来航。 → アフリカ・インド・東南アジア・中国をつなく、交易の中心となる。 |
| 16世紀初め | ジャワ島のd マジャパヒト王国 、イスラーム勢力に押され、滅亡。 |
| 3.ヨーロッパ勢力の侵出 | |
| 1511年 |
a ポルトガル のインド総督アルブケルケ、b マラッカ王国 を占領し、征服。 → さらにc モルッカ諸島 (香料諸島)を支配。 |
| 16世紀末 |
諸島部のイスラーム教国、香料貿易で栄える。 ジャワ島西部にはd バンテン王国 、ジャワ島東部にe マタラム王国 スマトラ島北部にf アチェ王国 |
| 1602年 1619年 |
g オランダ が h 東インド会社 を設立。香料貿易に割り込む。 ジャワ島西部に拠点i バタヴィア を建設。 → ポルトガル勢力を駆逐。 |
| 1623年 |
j アンボイナ事件 :モルッカ諸島でのオランダとイギリスの衝突。 →k オランダ の勝利、l オランダ領東インド 形成。イギリスはインド経営に向かう。 |
| 1786年 | m イギリス がマレー半島進出、n ペナン を領有。→中継港建設。 |
| 19世紀 ~20世紀 |
オランダ植民地支配、ジャワ島でo 強制栽培制度 による収奪。 → オランダに対する抵抗 p ジャワ戦争 、q アチェ戦争 が続く。 |
| 1826年 |
イギリス、r マラッカ 、n ペナン 、s シンガポール をt 海峡植民地 とする。 |
| 1.フィリピン フィリピン人は、マライ=ポリネシア語族。 | |
| 14世紀後半 1521年 1543年 |
南部のミンダナオ島などには、イスラーム教が伝えられる。その子孫をモロ人という。 a スペイン のb マゼラン が来航。セブ島に上陸。首長ラプラプとの戦いで戦死。 → 部下が船団を率い、リスボンに帰着し、世界一周を達成。 皇太子フェリペの名により、フィリピンと命名。 |
| 1565年 |
スペインのc フェリペ2世 、レガスピを派遣。メキシコのd アカプルコ とを結ぶ e ガレオン船 によるf ガレオン貿易 を開始。(1815年まで続く。) |
| 1571年 |
g マニラ を建設。h エンコミエンダ制 を初める。(スペインのフィリピン支配) → スペインによるi カトリック への強制改宗。 → 砂糖、マニラ麻、タバコ等の商品作物のj プランテーション 経営がすすむ。 |
| 17~19世紀 1834年 |
スペイン、ミンダナオのk イスラーム教 を弾圧。(モロ戦争) 他の欧米諸国の参入を拒否していたが自由貿易の要求強まり、マニラを自由港にする。 → 19世紀のフィリピン |