彼らはコロンブスが到来した当時には南北アメリカ大陸におよそ9000万人いたと推定されており、北はカナダ、アフリカから南はフエゴ島までに広がっており、それぞれ自然環境に応じた多様な文化を形成していた。アラスカやカナダでは魚やアザラシなどの漁が行われ、北米大陸の大平原にはバイソン狩猟を中心とした狩猟文化が発展し、メキシコやペルーには農耕牧畜に支えられた高度な文明を持った国家が形成された。アマゾン川流域では漁業とキャッサバの焼き畑農業を中心とした生活を送っていた。
この南北アメリカ大陸の先住民は、新人(ホモ=サピエンス)のモンゴロイドに近い特徴を持っており、最も古い確実な文化は1万3500年前のクローヴィス型尖頭器を特徴とする旧石器文化である。恐らくそれ以前の21000年前から14000年前の最終氷期のピーク時に海岸線が100m近く後退し、ベーリング海峡(現在でも幅50km、深さは50mほどしかない)が消滅して陸橋になった時期にユーラシア大陸から移動してきたものであると考えられている。人類学上はアジア系の人種との近親関係が認められる新大陸先住民であるが、彼らのことばは旧大陸の言語のどれとも親族関係が認められない。 → ホモ=サピエンスの新大陸への拡散
Epi. 南アメリカ先住民はなぜO型が多いか 南北アメリカ大陸の先住民(インディオ)がモンゴロイドであることは、シャベル形切歯(中切歯の裏側がシャベル状にへこんでいる)などでも確かであるが、顔つきなど現代のアジア人とは異なる特徴もある。また南アメリカの先住民は圧倒的にO型血液型が多く、AやB型はごく少ない。これは、彼らが移住していく過程で、大きな自然災害などで急激に人口が減ったときにおこる「ボトルネック効果」で説明されている。一時的に集散サイズが小さくたったときたまたまO型の遺伝子を持った個体が多かったため、後の子孫もほとんどO型になったと説明されている。<海部陽介『人類がたどってきた道』2005 NHKブックス p.268>
先古典期:前1200年頃からのオルメカ文明で都市文明の段階に達し、石造建築や絵文字などが生まれた。これは前400年頃まで続き、メソアメリカ文明の先古典期(形成期)とされる。
古典期:次いで紀元前後頃から、メキシコ高原にはテオティワカン文明、ユカタン半島にはマヤ文明というそれぞれ特徴のある都市文明が成立した。この段階をメソアメリカ文明の古典期(または開花期)とする。7世紀頃からメキシコ高原のにトルテカ文明が生まれ、その勢力がユカタン半島のマヤ文明にもおよんでいく。そのため古典期のマヤ文明は衰退した。
後古典期:11世紀頃からかわってチチメカ人の活動が活発となり、メキシコ北部からユカタン半島まで大移動を行った。14世紀にはチチメカ人の一部からアステカ人が有力となり、テノチティトランを都としてアステカ王国を建設し、15世紀にはアステカ文明の繁栄期を迎えた。一方のマヤ文明圏ではキチューやカクチクルなどの小国が分立した。チチェン=イツァーにはアステカ文明の影響で巨大なピラミッドが建設された。しかしこれらのメソアメリカ文明は、16世紀初めからスペインの侵略を受けて征服され、伝統的文明は破壊され、植民地支配のもとでカトリック信仰、スペイン語などのヨーロッパ文明を受け入れていく。
アンデス文明とジャガイモ:アンデス文明の都市文明を産みだし、支えていたのはトウモロコシであったというのが従来の定説であった。増大した都市人口を支えるだけの食糧備蓄ができるのは、穀物かトウモロコシであるというのが一般的な理解となっている(教科書にもそのような説明がされており、南北のアメリカ文明を支えたものの第一にトウモロコシがあげられている)。しかし、最近ではアンデス高地の文明を支えたのはジャガイモであるとの説も出されている。この説ではアンデスの高冷地での栽培に適したものはジャガイモであり、さらにアンデスではジャガイモを乾燥させた「チューニョ」として保存されるていることも知られ、食糧備蓄が可能であることから、ジャガイモによって文明化をもたらすことができたとしている。また、インカ帝国においても、主食はジャガイモであり、トウモロコシは儀礼用の酒の原料とされていたと考えられている。
戦争と飢饉でヨーロッパに普及したジャガイモ:南米大陸のインカ帝国を征服(1532年)したスペイン人によってジャガイモがまずスペインにもたらされた(その正確な時期はわからない)。16世紀末まではフランス、ドイツに広がった。ドイツでは、悲惨な戦争と飢饉が続いた三十年戦争(1618〜1648年)の時期にジャガイモ栽培がひろがった。ヨーロッパ北部の主作物は小麦やライ麦であったが、これらの穀物は収量が少なく飢饉が頻発していた。そのためヨーロッパ各国は戦争をくり返し、敵の麦畑を踏み荒らしたり、貯蔵庫の麦を略奪した。ジャガイモは畑を踏み荒らされても収穫できたし、畑を貯蔵庫がわりにして必要なときに収穫できたので、戦争の被害が比較的少なかった。そのためヨーロッパでは戦争がくり返されるたびにジャガイモ栽培が普及していく。戦争によるジャガイモの普及の発端となったのが1680年代のルイ14世によるベルギー占領の時であった。ドイツではスペイン継承戦争(1701〜14年)の時にジャガイモが重要な作物になった。さらに、七年戦争(1756〜63)のときにジャガイモが東方に伝わりプロイセンやポーランドにひろがり、ナポレオン戦争(1795〜1814年)でロシアまで拡大した。
Epi. フリードリヒ大王とジャガイモ:18世紀のプロイセンのフリードリヒ大王はジャガイモ栽培を農民に強制し、飢饉から人々を救ったとされている。家畜の餌とされていたジャガイモを人間が食べるようになった。生涯を戦争に明け暮れたフリードリヒ大王の最後の戦争が、1778年のバイエルン継承戦争(バイエルン王位をめぐる、オーストリアのヨーゼフ2世との戦争)では、オーストリア軍との間で、互いに敵国のジャガイモ畑を荒らしあったので「ジャガイモ戦争」と言われている(戦闘がヒマで兵士がジャガイモ栽培に精を出したためだとも言われている)。
Epi. フランスのパルマンティエとジャガイモ:七年戦争でドイツの捕虜となったフランスの農学者パルマンティエは、ジャガイモを食事に与えられたことをヒントに、フランスに帰国した後、ルイ16世の庇護のもとジャガイモ栽培の普及に努めた。彼はジャガイモが貴重な作物だと言うことを農民にわからせるため、ジャガイモ畑に見張りをつけて、夜になると見張りを立ち退かせてわざとジャガイモを盗ませるようにしたという。ただしこの話の真相は明らかではない。しかし彼によってジャガイモに対する偏見が打破され、フランスでジャガイモが普及するきっかけとなったことは確かで、彼の功績をたたえて、パリの地下鉄にはパルマンティエ駅があり、そこには彼が農民にジャガイモを手渡している像がある。<山本紀夫『ジャガイモのきた道』2008 岩波新書 p.67-68> 出題 2006年センターテスト 第4問B
アイルランドのジャガイモ飢饉:イギリスでは始めは有毒で危険な作物であるとか、聖書に書かれていないから「悪魔の植物」だ、などといわれて普及しなかった。広がったのは遅れて19世紀中ごろであった。それでもフィッシュ・アンド・チップスが庶民の食べ物として定着した。隣のアイルランドでは風土に適していたからか、17世紀からジャガイモが取り入れられ、18世紀には主食とされるようになった。ところが、1845年から始まったジャガイモ疫病の大流行によってジャガイモ飢饉といわれる大飢饉に陥った。飢饉は1851年まで続き、食糧不足と体力不足からチフス、赤痢、コレラなどが流行し、約100万人が犠牲となった。犠牲が大きくなった原因はアイルランドの食料がジャガイモだけに依存していたこと、緊急食料輸入が穀物法で制限されてできなかったことなどがあげられる。大飢饉に直面したアイルランドの人々はアメリカ大陸などに移民として逃れていくこととなる。<以上、山本紀夫『ジャガイモのきた道』2008 岩波新書 による>
Epi. いけにえの泉−マヤの人身御供:マヤ文明には他の文明から見て奇妙なことが多い。さかんに人身供犠が行われたことも一つだ。神に捧げるいけにえの方法には、弓矢で殺すもの、胸を裂いて心臓をつかみ出すもの、「いけにえの泉」に投げ込むものが伝えられている。そのうちの第三の方法は次のようなものだ。チチェン=イツァーにある「いけにえの泉」は石灰質のユカタンの地表が陥没して、そこに地下水がたまったもので、経約66m、高さ20mの垂直の断崖に囲まれている。水は周囲の緑を映して青く深い。マヤ人は干ばつの年に、人間を生きながらこの泉に投げ込んで神に捧げ、そのいけにえはけして死なないと信じていた。あるいは金や銀の財宝を泉に投げ込み降雨を祈ったという。1885年、ひとりのアメリカ人青年がこの湖の調査を行った。インディオが不安そうに見守る中、巨大なクレーンで浚渫を試みたが思った成果が出ない。そこで青年は自ら潜水することを試みた。それらの調査の結果、多数の金属と人骨が泥の中から見つかった。しかし金属類は主に銅製や合金で、高価な金はごく少なかった。人骨の21個は18ヶ月から12歳に至る小児、13個は男子、8個は女子のものであった。<石田英一郎『マヤ文明』1967 中公新書 p.74-80>

マヤの絵文字は果たして表音文字か? 左は同書より、マヤのアルファベットの一部を抜粋したもの。最下段はその使用例。ただしこれらの文字の読み方は16世紀の宣教師ディエゴ=デ=ランダが採取し、その著『ユカタン事物記』に残したもの。実はランダ自身は、マヤ文字の資料を異教の有害な文書であるとしてその多くを焼却してしまった張本人。そのため残されたマヤ絵文字の一次資料は、世界にドレスデン、マドリード、パリの3ヶ所に残された三点しかない。それでも19世紀以来、言語学者、文字学者が解読に取り組み、一時は表音文字であるとの説が有力になった。しかし同じ絵が同一の発音で読まれるという証明はできず、20世紀には表音文字説は否定され、表意文字であるとされた。最近ではコンピュータによる分析、解読の試みも行われているが、その結果、表意と表音が混在して用いられているとの説が有力となった。しかし完全な読み方はまだ明らかになっていない。<石田英一郎『マヤ文明』1967 中公新書 p.99-120>
巨大な宗教都市テオティワカン:テオティワカンは海抜2200mのメキシコ市の北東50kmのところにあり、現在では遺跡として残されているだけであるが、紀元後350年〜650年の間はおそらく20万人の人口を要する大都市であった。当時でいえばきわめて大きかったコンスタンティノープルを除けば、2万人以上の都市はなかったと考えられるから、その繁栄ぶりが理解できる。都市は太陽と月のピラミッドと南北に走る「死者の大通り」を基準として計画され、その建築は煉瓦(アドベ)で築いた傾斜した壁(タロー)と垂直の壁(タブレーロ)を交互に重ねる新しい様式で建造され、その表面を漆喰で覆って壁画が描かれた。太陽のピラミッドは高さ65 m、底辺222 m×225 m、月のピラミッドは高さ47 m、底辺140 m×150 m、死者の大通りは長さ4 km、幅45 mに及ぶ。
Epi. 太陽の伝説 テオティワカンは西暦650〜700年の間に、何ものかによって破壊された。「それとともに歴史は神話に転化した。伝説的な過去においてこの大都市をつくりだしたのは、もはや人間ではなく、巨人たちと神々自身であるとされたのである。こうしてこの巨大な廃墟の名称が生まれた。テオティワカンとは、神々の場所、つまり神々がつくりだされる場所という意味である。・・・伝説によるとテオティワカンを照らしていたのは「四番目の太陽」であった(それより前の三つの太陽はすでに消滅していた)。この太陽が死に、それとともに人類が絶滅すると、神々は自分たちをうやまってくれる者がいないことを嘆き、テオティワカンへ集まった。そして一柱の神が太陽に変わり、さらに一柱の神が月となった。いまでもわれわれを照らしているのは、この二柱の神であり、それらとともに歴史時代がはじまったのである。」後のアステカ王国の王も毎年この地に巡礼した。<メキシコ大学院大学『メキシコの歴史』1978 新潮選書 p.49>

メキシコ国旗に描かれた「サボテンに止まって蛇を捕まえた鷲」
メキシコの始まり:アステカ人はまたはメシカ人ともいい、都の置かれた場所をメシコ・テノチティトランと呼んだ。メキシコの国名はこのメシコということばに由来する。その語源は太陽と戦いの神ウィツィロポチトリの別名メシトリであるため、メキシコは「太陽の国」と呼ばれることがある。アステカとは、この民族の発祥地アストラン(白鷺の生息する地)からとられている。ウィツィロポチトリ神がアステカの人びとに「サボテンに鷲が止まった場所」を都に定めよと予言が下り、1325年にこの地を都とした。この予言を図案にしたのが現在のメキシコ国旗である。 → 現代のメキシコ
アステカの文字と暦法:アステカ人も農耕と宗教が結びついた暦を使っていた。トナルポワリという20の絵文字と13の数字を組み合わせた260日の祭式暦と、シウポワリという365日(20日からなる18ヶ月と5日の余り)の太陽暦を用いていた。この二つの暦の第一日が再び一致するのが最小公倍数の18980日、つまり52年目となる。アステカ人はこの52年を1周期とし、その周期ごとに創造と破壊が行われるという、東洋の還暦と同じような年代観を持っていた。<以上、大垣貴志郎『物語メキシコの歴史』2008 中公新書 p.30-32>
アステカ王国の成立:伝承に拠れば、彼らは1325年にメキシコ中央高原のテスココ湖の中の小島に移り住み、テノチティトランの町を築いた。初めは有力なテパネカ族に服属していたが、15世紀の前半のイツコアトル王のとき独立し、1469年まで統治したモクテスマ1世の時に周辺のベラクルス地方やアオハカ地方を征服し、帝国をつくった。16世紀の初め、スペイン人が現れた頃のアステカ王国は、現在のメキシコ高原一帯に、イタリアと同じぐらいの広さの領土を支配していた。
アステカ王国の政治と戦争:皇帝と頂点とし、祭祀と軍事を担当する貴族がその政治を支えた。皇帝はウイツィロポチトリの最高の祭司であり、軍隊の長であるが、世襲制ではなく選挙で選ばれた。しかし初代以来常に同一の家系から選ばれていた。皇帝は太陽神の司祭であるが、太陽神は夜の間姿を消し、翌日のために精力をつけなければならない。太陽の好んだ唯一の栄養分は人間の生き血であるとされていあので、アステカの皇帝は常に人身犠供のための捕虜をえるために戦争を続けなければならなかった。それだけアステカ王国には敵も多かったと言える。<以上、メキシコ大学院大学『メキシコの歴史』1978 新潮選書 p.60-69>
アステカ王国の滅亡:アステカ王国は1521年、スペイン人の征服者コルテスによって滅ぼされた。コルテスは、インディオの反アステカ勢力を味方に付け、火器と騎兵で武装してテノチティトランを攻撃した。反アステカのインディオを含め超すテスの軍勢は総勢10万に上ったという。また、スペイン人によって疫病がもたらされ、特に天然痘が免疫がなかったアステカの戦士に感染し、戦力が低下したのもアステカ王国の敗北の一因である。。3ヶ月におよぶ湖上の都テノチティトランの包囲戦でも降服しなかったため、都に入城したスペイン軍はアステカ人を3万人も大虐殺したといわれている。<大垣貴志郎『物語メキシコの歴史』2008 中公新書 p.34> → アステカ王国の滅亡
農耕の開始=チャビン文化:約1万年前に南米大陸に移動し長い狩猟採集生活を営んでいたモンゴロイドが、前1200年頃に土器をつくりトウモロコシとジャガイモを栽培する農耕段階に入った。それから500年ほど経って、アマゾン上流に突然、巨大な神殿、雄渾な土器、石の彫刻、黄金細工を伴う文化が現れた。それがチャビン文化である。この文化はまたたくまにアンデス地帯一帯にひろがったが、それは政治的な統合や軍事的な征服によるものではなく、宗教的な人間行動が文化を広めた結果と考えられている。
開花期:チャビン文化は前500年頃、急にアンデス地帯から姿を消す。その原因は明らかではないが、おそらく住民の信仰の内容が変わり、強い地方意識が各地におこってきたように思われる。その背景にあるのはおそらく集約的灌漑農耕の発達である。チャビン文化後「前開花期」が約2世紀続き、次に各地に現れたものが、北部のモチカ文化、南海岸のナスカ文化が、「開花期」といわれる地域文化で、それが6世紀以上続く。
大都市形成期(ティアワナコ・ワリ文化期):開花期に並行してチチカカ湖周辺の山岳地帯のペルー・チリ国境付近からボリビアにかけてティアワナコ文化が起こった。その影響のもとで、500年頃からワリ文化が急速に広がり、開花期の地域文化は消滅して再び広範囲な普遍的文化の時期となる。アンデスの文化が均質化された後、いくつかの大都市が現れ、国家が形成されていく。
地域国家の形成からインカ帝国の統一へ:1000年頃からティアワナコ・ワリ文化は頽廃し、各地に大都市が出現、その中からかわってアンデス北部にモチカ文化を継承したと思われるチムー帝国という有力な国家が形成される。他にもいくつかの国家が各地に興亡する中で、12世紀頃にクスコ周辺に起こったケチュア族が有力となり、15世紀にチムーなど周辺諸勢力を圧倒して大帝国を建設する。このインカ帝国は16世紀に入って内紛が発生して動揺したが、そのような時期にスペインのピサロによる征服が始まり、1533年に滅亡する。<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.228、/大貫良夫他編『ラテンアメリカを知る事典』1987 p.57 などを参照>
Epi. アンデス文明の脳外科手術 アンデス文明の遺跡から頭蓋骨に穴を開けたミイラが多数見つかっている。紀元前500年頃のパラカス・カベルナスの墳墓の55体のミイラのすべてに頭蓋変形(幼少時に板をあてがって頭の形を細長く変形する)がほどこされ、しかも大部分が脳外科手術(頭蓋骨に孔を開けて、脳圧を下げる治療方法、古代社会または未開社会において広く行われている)をうけている。インカ帝国でもその伝統を受け継いで、戦争による負傷者の微妙な脳手術を行っていた。その際にはコカ(麻薬のコカインの原料)やベヤドーナ(緩弛緩剤)などの薬草が使われた。インディオの使用した薬草には、現在も使われているキニーネ(解毒剤)などがあり、タバコも鼻を治す薬として用いられていたという。<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.52,178-180>
Epi. 地上絵以外にもあるナスカ文化の謎 ナスカの地上絵は岩石砂漠の明るい色の台地に、黒い小石を並べて描かれている。多くの銭は平行だが一部のものはいろいろ角度を変えて交差し、放射線状や、動物の像が描かれている。マリヤ・レーチェという長い間その謎に取り組んできた学者の説は、23本の放射線状の2本は夏至の線であり、1本は秋春分の線であるという。大部分の線の長さは182mまたはその半分、ならびに4分の1である。別の単位は26mで、これらはナスカの人びとが用いた距離の単位であろう。ナスカの地上絵は有名だが、他にも「柱の場所」または木のストーンヘンジといわれる謎がある。これはナスカ川の谷の中心部にあり、砂交じりの平らな土地に木の幹が一ヶ所に固まって立てられている。大部分が2mおきに12列に並んでいる。そこからは墳墓は見つかっておらず、何の遺跡か謎である。<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.68-75>
Epi. 海抜4000mの文明 アンデス高原の海抜3800m、つまり富士山より高いところにチチカカ湖がある。氷河が溶けてできた氷蝕湖で水は切れるように冷たい。その南岸のティアワナコという小さな村に、長さ1000m、幅450mに及ぶ大遺跡群が横たわっている。その中に巨石を積み上げたピラミッドとともに、「太陽の門」がある。門の上部には幅3m、長さ3.75m、重さ10トン以上の一枚岩が乗せられ、表面に大きな神像が浮き彫りにされている。付近は住居跡などほとんど見つかっておらず、この古典ティアワナコ遺跡は巡礼の集まる神殿であったと思われる。<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.76-80>
・太陽信仰を中心とした、アニミズム的な宗教による国家統制。首都クスコには太陽の神殿が建設された。
・トウモロコシ、ジャガイモを中心とする高度な潅漑農業が行われていた。リャマ、アルパカなどの牧畜も行われていた。
・高度な石造建築技術。太陽の神殿や灌漑施設、道路、公共浴場など、大規模かつ精巧な石造建築が発達した。
・石造建築技術を駆使した大都市がアンデス山中に建造された。首都のクスコや世界遺産マチュピチュがその例。
・独特の意匠を持つ土器類がつくられ、綿織物、毛織物の技術とともに金銀、銅、青銅の金属加工技術が高度に発達した。
・独自のキープ(結縄)による記録方法を持っていたが、文字は用いられなかった。
・アンデス文明の伝統を継承して、コカ、タバコなどの薬草の利用や脳外科手術など独自の医療技術が存在した。
・旧大陸との関係が無かったため、独自の文化を発展させたが、鉄器、車の利用など欠けるものもあった。
→ 新大陸の文明にないもの
インカの国名:「インカとは元来はクスコに住んでいた小さな部族の名称で、その部族が中心となって後に大帝国が建国された。当時皇帝の命令によって、インカと同じ言語を使用していたものを、すべて「インカ」とよぶことになった。ところがスペイン人が侵入してきて、この意味をさらに拡大し、帝国そのもの、またはスペイン的でないものすべてを「インカ」とよんだ。さらにまた、帝国の皇帝をも「インカ」とよぶようになった。これは部族の名称で、その族長の地位をあらわす、ヨーロッパの古い習慣(例えばスコットランドのキャンベル氏族の族長の地位をキャンベルとよんだ)を援用した結果であった。」<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.182>
正式な帝国の名称はタワンチン・スウユである。タワンチン・スウユとは、「四つの地方からなる国土」の意味で、帝国を東西南北の4地域に分割してそれぞれ地方長官を任命していたことによる国名であった。
インカ帝国の成立:アンデス世界では文字の記録がないので、その起源は定かではないが、神話から推察するとアンデス世界の大都市形成期のなかば、1200年頃に、ケチュア族の中のインカ部族が中央アンデスのクスコに地方的小国家をつくったと思われる。スペイン人の年代記作者の記録も矛盾することが多いが、それらを総合すると、初代のマンコ=カパックから13人の皇帝が即位した。初代を除く12人の皇帝は実在の人物のようであり、ここから逆算するとインカ帝国の成立は1200年ごろと推定される。
アンデス世界の統一:2代から8代にわたる200余年のあいだは、帝国というよりも部族と呼んだ方がふさわしく、クスコを中心として数10キロ以内の諸部族と戦闘を交えていたにすぎない。ところが15世紀の中ごろ、長年にわたる仇敵であった北方のチャンカ族と戦って勝利を収めると、インカ部族は急速に征服を開始、第9代のパチャクチ皇帝は在位33年間に帝国の版図を約一千倍に拡張した。第11代のワイナ=カパックはさらに領土を拡張してアンデス世界の1000000平方km、南北の距離は4000kmに及ぶ大帝国となった。
インカ帝国の滅亡:ワイナ=カパックの死後、皇位継承をめぐって争いが起こった。皇妃との間に生まれた正統な皇子ワスカルと、側妻の子アタウワルパが帝位をめぐって争い、帝国は二分されて内戦となった。1532年、結局アタウワルパが勝利を収めて帝位を嗣いだが、時を同じくしてスペインの征服者ピサロが北端のツンベスに上陸する。ピサロはわずかな部下を率いて進撃し、アタウワルパを欺して捕らえ、殺害する。これによって1533年にインカ帝国は滅亡した。 → インカ帝国の滅亡
インカ帝国の政治と社会:インカ帝国は宗教と政治が一体化しており、太陽信仰が国家の基本であり、皇帝は「太陽の子」または太陽の化身として統治するという「太陽の帝国」であった。皇帝を支える貴族層と太陽の神殿の儀礼を司る聖職者が存在した。大部分の国民は農民としてトウモロコシやジャガイモの栽培にあたり、重い賦役や兵役を負担した。国土は4つの地方にわかれ、それぞれ長官が置かれた。農民はアイユウという母系的な氏族集団であると同時に生活領域である集団に所属し、内婚制で維持される2〜3の胞族(フラトリー)を構成していた。経済は厳しい統制経済であり、人口や産業、税額や取引額はキープ(結縄)によって記録され、毛織物の原料であるヤーマの牧畜は公営で行われた。道路網の建設、灌漑施設、鉱山などの事業も公営で行われ、このようなインカの社会を「太陽の社会主義」と評した人もいる。
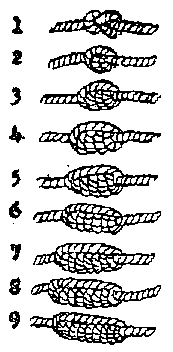
インディオは、トウモロコシ・サツマイモ・落花生・南瓜(カボチャ)・数種の豆・トマト・チリ唐辛子・タバコ・ジャガイモなど、旧大陸には無い植物を栽培した。「しかし農具は、堀棒・踏み鋤・鍬の程度で、牛馬のような大型家畜を使用する犂類は知らなかった。一方灌漑の工事は精巧をきわめたが、家畜類は貧弱で、ヤーマ、アルパカ、ワナコのような駱駝科の動物と、七面鳥、鵞鳥、アジア系統の犬を飼育したに過ぎない。・・・・紡織、染色の技術は旧大陸のそれと変わらないが、土器をつくる場合、ろくろやうわぐすりを使用しなかった。金属器は、銅・青銅器をつくったが、鉄を知らなかった。そのほか、ガラス、車、弦楽器、アーチ、円天井などはついに発明されなかった。」<泉靖一『インカ帝国』1959 岩波新書 p.8>