● 特別公開 ●
Special exhibit
紋銭つくし之図 三双目貫
MONSEN TSUKUSHI no ZU SANSOU-MENUKI
| 指表目貫: ●天聖元寶(長崎貿易銭:万治2年(1659) 幕府の許可を得て、貿易決済用貨幣として鋳造された。) ○永楽通寶 ●聖宋元寶(建中靖国元年(1101年)に銭文を年号ではなく聖宋元寶と称名:篆書) 指裏目貫: ●背十二(淳祐元寶:南宋・淳祐年間(1241〜1252))背の穿上下に「十二」の文字があります。 ○永楽通寶 ●大宋元寶(寶慶年間(理宗、1225〜1228年)に鋳工された貨幣)「大宋」は年号ではなく銭名。 |
 |
| 永楽通寶の家紋について: 足利時代にお隣の中国の明の時代(永楽年間1403〜23年)に鋳造で作られた 「永楽通寶」を輸入し、貨幣として国内で使用し始めたのが始まりで、 この貨幣を紋章として使うようになった。 古くは、文献(羽継原合戦記)に、 「永楽の銭は、三河国 水野の紋…」と記述が残されている。 戦国の武将 織田信長が「永楽」の文字を旗紋に用いている。 家来の将士(仙石氏、荒尾氏、黒田氏)へも分け与えている。 その他にも下記の諸氏が使用していた。 松平氏、奥村氏、本郷氏。永見氏。中山氏 |
辻 京二郎氏 所蔵 鮫皮
TSUJI KYOUJIROU SHI SYOZOU-SAME-KAWA
柄巻師 捲山(けんざん)辻京二郎氏が使うためにお持ちになっていました鮫です。
当時の価格で五万円したと伺っております。
名古屋帯の生地で飾ってみました。

| 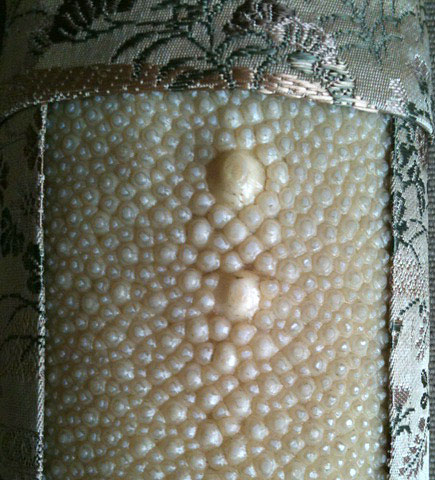 |
生ぶの尾張柄前
OWARI TSUKAMAE
幕末から明治の尾張柄前です。14菱半・五分常組み糸巻き。うぶのままで、とても良い状態です。
 |
||
 |
生ぶの肥後柄前
HIGO TSUKAMAE
頭:櫻山道 目貫:鹿
kashira:sakura michi menuki:shika(doe)
クスベ革ではありませんが。時代の感じがとても良い状態です。
 |
生ぶの薩摩柄前
SATSUMA TSUKAMAE
 |
 |
● 特別公開の拵 ●
Special exhibit of KOSHIRAE
生ぶの薩摩拵
SATSUMA KOSHIRAE
 |
薩摩拵
SATSUMA KOSHIRAE
 |
 |
柄板
TSUKAITA
 |
 |
● 特別公開の刀装具 ●
Special exhibit of TOSOUGU
 |
 |
鐔 茶室之図
TSUBA TYASHITU no zu
花押 時代不明
KAOU It un-identifies about a JIDAI
 |
 |
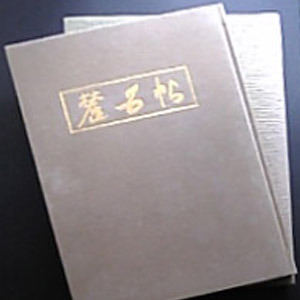 |
 |
鐔 太刀金具師 草花之図
TSUBA TACHIKANAGUSHI SOUKA no zu
無銘 書載 時代不明
MUMEI SYOSAI It un-identifies about a JIDAI
 |
 |
 |
 |
越前大掾長常(花押)と千鳥の図(無銘)
ECHIZENDAIJYONAGATSUNE(KAO) AND CHIDORI NO ZU(MUMEI)
親愛なる友からの贈り物
This goods are presents from the dear friend.
 |
 |
長常(花押)くりがた
AGATSUNE(KAO) KURIGATA
鶴之図
TSURU NO ZU
● 肥後の縁頭 ●
HIGO
 |
肥後 縁頭
HIGO FUCHIKASHIRA
頭:魚子山道 縁:シボ革包み 桶形
KASHIRA:NANAKO YAMAMITI FUCHI:SHIBO-KAWATUTUMI OKEGATA
● 献上鮫 ●
KENJYO-SAME
| 大変に貴重な完全な形の「献上鮫」です。 |
 |
● 花梅花皮(かいらぎ)鮫 ●
KAIRAGI-SAME
|
研ぎ出しの鞘に着せられて使われております。 この刺が非常に鋭いので、手荷物だけでも痛いです。 |
 |
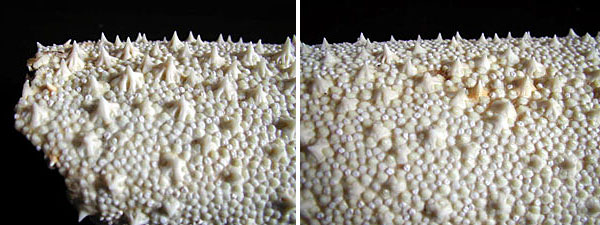 |
● コロ鮫 ●
KORO-SAME
|
細川三斎公の愛刀兼定にかけられた拵え、「歌仙拵」に使われている「コロ鮫」です。 拵の細部は、 鐔:正阿弥作 鉄磨地丸形鐔丸耳 左右影蝶大透 頭:四分一(山銅)平山道深彫 縁:素銅地皺革包青漆石地塗 鐺:鉄地舟底形 目貫:金無垢鉈豆容彫 柄:黒塗鮫着 燻革諸撮巻漆懸 菱数十三半 鞘:黒研出鮫 腰元印籠刻 無櫃 下緒:茶色糸重打組紐 |
 |
|
 |
 |
● 藍鮫(アイザメ) ●
AI-SAME
 |
● カメ鮫 ●
KAME-SAME
|
天正拵の柄前に黒の漆を塗られて使われております。 本鮫とは、親粒の大きさや配列が違っています。 |
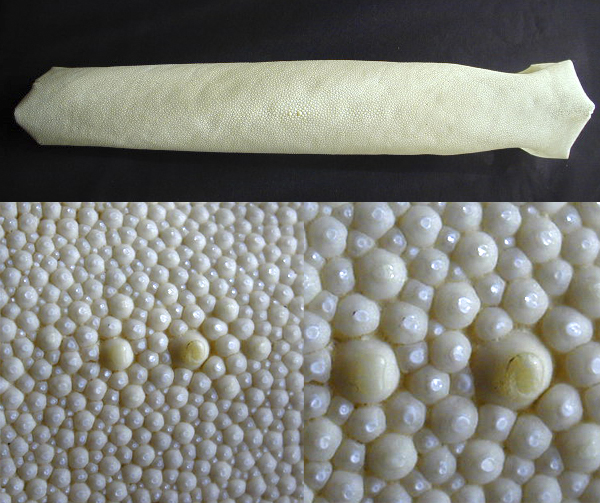 |
● 本鮫 ●
HON-SAME
|
約50年前に採られた「本鮫」です。 まだ漉いていないので、かなり硬い状態の皮です |
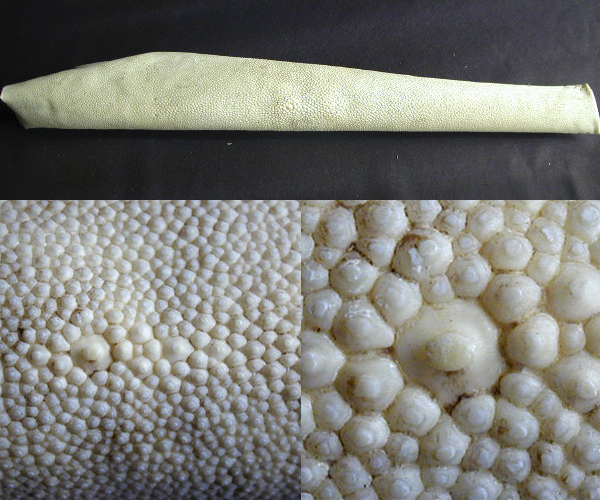 |
● 柳鮫 ●
YANAGI-SAME
|
かなり貴重な「柳鮫の皮」です。柳のような、模様が見えております。 小さめの鮫皮です。短刀ぐらいでしたら、研ぎ出し鮫で使えそうです。 |
 |
| 珍しい鮫が手に入りましたら、随時ご紹介いたします。 |