Gregorianish-Hiroko
|
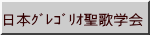
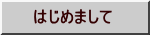 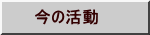 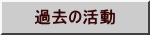 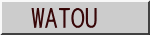 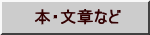 
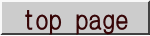 |
第18回日本グレゴリオ聖歌学会東京大会開催
2014年 9月27,28日
聖心女子大学同窓会館、聖堂に於いて
2014年9月27日 (同窓会館)
11時より、総会(学会員のみ)
13:40 大会(一般に公開)
基調講演 橋本周子学会員
「日本におけるグレゴリオ聖歌の将来的展望」
研究発表Ⅰ 西脇純学会員(真言会司祭)
「カロリング朝におけるグレゴリオ聖歌の霊性の理解について」
研究発表Ⅱ 久野将健学会員 (京都ノートルダム女子大学)
「グレゴリオ聖歌の旋法とオルガン伴奏」
報告 高橋正道副会長
「AISCGre理事会報告と第10回ルガーノ国際大会について」
16:00 終了予定
2014年9月28日 (聖堂)
14:00 第2回Gregorian Festival
出演団体 Cantate Domino カペラ・グレゴリアーナ
コール・マリエ コ―ロ・ファンタジア
スコラ グレゴリア-ナ ナガノ Filles du Sacre Coeur
16:00 閉会ミサ Pro Pace
主司式 西脇純神父 共同司式 国本静三神父
Festival出演グループ+由比ヶ浜グレゴリアンを歌う会+全参会者
17:30 終了予定
2014・9・14、
日本グレゴリオ聖歌学会 の歴史
| 1975 |
|
国際グレゴリオ聖歌学会 AISCGre クレモナで発会
長年、教皇庁立宗教音楽大学の教授として、セミオロジー(音楽古文書学)を駆使 して、画期的なグレゴリオ聖歌の研究を進めたカルディーノ師(ソレムのベネディクト会士)を中心にその弟子たちが発足させた。 活発な研究が続けられ、源泉に戻るべく数多の論文が書かれ、4年に1度の世界大会で研究発表、また新たな研究に沿った歌唱が展開されている。 |
| 1977 |
|
第1回AISCGre クレモナ大会 |
1979
|
|
第2回AISCGre クレモナ大会
|
| 1980 |
7/25 |
日本グレゴリ オ聖歌研究協会創立
AISCGre の日本支部として広島で設立大会を持って発会
名誉会員:P.アヌイ、川上きよ、T.ゲッペルト、G.ゴールドマン 、 J. テホン、高田三郎、岳野慶作、野村良雄
初代役員:会長・水島良雄、理事・石川和子、帘功、
高橋正道、橋本周子 事務局長・高橋正道
総会員数など不明
|
| 1981 |
5/30
|
ボレッティーノ 第1号 発刊 |
| |
9 |
第2回全国大会 東久留米 |
| 1982 |
|
|
| 1983 |
3/15 |
ボレッティーノ 第2,3号 発刊 |
| |
9/23
|
ボレッティーノ 第4号 発刊
|
| |
9 |
第3回全国大会 大阪 |
| |
6 |
第3回 AISCGre ルクセンブルグ大会 |
| 1984 |
9/28 |
ボレッティーノ 第5号 発刊 |
| |
10 |
第4回全国大会 広島 |
| |
|
日本グレゴリオ聖歌学会 と改称 |
| 1985 |
|
|
| 1986 |
6/25
|
ボレッティーノ 第5号 発刊 6号に訂正 |
| 1987 |
? |
AISCGre 大会 エッセン? |
| 1987 |
7/31
|
ボレッティーノ 第6号 発刊 7号に訂正 |
| |
9/15
|
ボレッティーノ 第7号 発刊 8号に訂正 |
| |
9 |
第5回全国大会 東久留米 |
1988
|
|
|
| 1989 |
|
|
1990
|
9/15 |
ボレッティーノ 第8号 発刊 9号に訂正 |
| 1991 |
5
|
第4回 AISCGre ヴェローナ大会 |
| |
8/15 |
ボレッティーノ 第9号 発刊 10号に訂正 |
| |
9/15 |
ボレッティーノ 第10号 発刊 11号に訂正 |
1992
|
|
|
1993
|
9/15 |
ボレッティーノ 第11号 発刊 12号に訂正 |
| |
? |
?大会?名古屋? |
1994
|
2/1
|
ボレッティーノ 第12号 発刊 13号に訂正 |
1995
|
? |
第5回 AISCGre ウィーン大会
|
| |
8/31
|
ボレッティーノ 第13号 発刊 14号に訂正 |
1996
|
8/31
|
ボレッティーノ 第14号 発刊 15号に訂正 |
| 1997 |
9/23
|
ボレッティーノ 第16,17 発刊 |
| |
9 |
第10回大会 広島 |
| 1998 |
|
|
| 1999 |
3/31 |
ボレッティーノ 第18号 発刊 |
| |
? |
第6回 AISCGre ヴェローナ大会
|
| |
? |
第11回大会 東久留米(聖グレゴリオの家) |
2000
|
7/31 |
ボレッティーノ 第19号 発刊 |
2001
|
9/9 |
第12回大会 長野(清泉女子短大) |
2002
|
5/10 |
ボレッティーノ 第20、21号発刊 |
| 2003 |
? |
第7回 AISCGre ヒルデスハイム大会 |
2004
|
9/3
|
ボレッティーノ 第22,23号 発刊 |
| |
|
聖グレゴリオ1世1400年記念ミサ(東京カテドラル) |
| |
9/4 |
第13回大会 八王子(東京純心) |
2005
|
|
|
2006
|
7/10
|
ボレッティーノ 第24、25号 発刊 |
| |
9/3 |
第14回大会 神戸勤労会館 |
| |
|
聖グレゴリオ1世教会博士記念ミサ(神戸中央教会) |
| 2007 |
5
|
第8回 AISCGre フィレンツェ大会 |
| 2008 |
9/13
|
第15回大会 八王子 役員改選 |
| |
13,14 |
セミオロジー・セミナー |
| |
10/20
|
ボレッティーノ 第26,27号 発刊 |
| 2009 |
5/4,5 |
セミオロジー・セミナー (広島) |
| |
9/19,20 |
セミオロジー・セミナー (八王子) |
| 2010 |
9/19,20 |
第16回大会 広島 役員改選 |
| |
12/8 |
ボレッティーノ 第28,29号 発刊 |
| 2011 |
4/1 |
事務局 八王子→広島 |
| |
5
|
第9回 AISCGre ポツナム大会
|
| 2012 |
8/25 |
第17回大会 広島 |
| |
|
聖母被昇天のミサ (広島カテドラル) |
| |
26
|
第1回 グレゴリアン・フェスティヴァル(広島カテドラル) |
| 2013 |
2 |
事務局 広島→鎌倉
2011年4月-2015年3月の役員
会長・水嶋良雄 副会長・高橋正道 理事・蒔田尚昊、
渡辺宏子(事務局長兼任)
|
| 2014 |
9/20 |
ボレッティーノ 第30号 発刊 |
| |
9/27 |
第18回大会 東京(聖心女子大学)
2015年4月―20193月の役員
会長・高橋正道 理事・渡辺宏子、橋本周子(事務局長兼任)
石川和子、水嶋良雄
|
| |
9/28 |
第2回 グレゴリアン・フェスティヴァル、 閉会ミサ「平和を祈る」 |
| 2015 |
9 |
第10回 AISCGre ルガーノ大会
|
| |
|
|
| |
|
|
グレゴリオ聖歌研究(ボレッティーノ)発刊記録
日本グレゴリオ聖歌学会は、学会として諸論文を掲載した小冊子の発刊を発会時から続けている。その記録をまとめて掲載する。第4号は記録用保存版しかないが、それ以外はバックナンバーがあるので、大会の折にでも求められることは可能である。
すべての論文は題名に英欧語訳があるが、ここでは省略する。
第1号 -1980-
日本グレゴリオ聖歌研究協会設立の趣旨
日本グレゴリオ聖歌研究協会設立へのメッセージ Dom Eugene Cardine
グレゴリオ聖歌の美学 野村良雄
セミオロジーと解釈 Eugene Cardine 水嶋良雄訳
グレゴリオ聖歌解釈における進歩の現状 Luigi Agusoni 水嶋良雄訳
日本グレゴリオ聖歌研究協会設立大会
第2・3号 -1981.1982 合併号-
グレゴリオ聖歌解釈における進捗の現況 Luigi Agustoni 水嶋良雄訳
第1節 グレゴリオ聖歌の多様性
時代的要素・地域的要素・楽式的要素・構造的要素・旋法的要素
第2節 解釈の歴史的変遷と批判的方法論にもとずいたグレゴリオ聖歌セミオロ
ジー
ネウマ記号の形態と表現性・明白な脈絡・付加文字・パレオグラフィック な同族記譜法間およびパレオグラフィックな異属記譜法間の比較・昔の
弁別符号をもったパレオグラフィックな記号の類縁性
第3節 セミオロジックな解釈の発展にともなう諸問題
計量主義・グレゴリオ聖歌の音価・同度音の反唱・ネウマの表現的分離 ・ ネウマ末尾音のアーティキュレーション・付記他
第4号 -1983-
グレゴリオ聖歌の研究と聖歌集 水嶋良雄
Graduel Neume ・ Graduale Triplex ・ Psalteium Monasticum
ラン 239 写本に見られるティロ記号の研究 岡田智子
第1節~第4節
ロレーヌ系写本に見られる指示文字
Graduale Triplex ひ転写する際に生じている誤謬
第5号 -1984-
アヌイ霊父とグレゴリアン 野村良雄
これからの教会におけるグレゴリオ聖歌の役割と課題 帘 功
カトリック大学の音楽教育におけるグレゴリオ聖歌の位置づけ 角地正純
グレゴリオ聖歌のリズム構造ーE.カルディーノの考え方ー 高橋正道
第6号 -1985-
国際グレゴリオ聖歌学会第3回世界大会にみられるグレゴリオ聖歌の研究事情
水嶋良雄
音楽教育とグレゴリオ聖歌 Sr.石川和子
第7号 -1986-
グレゴリオ聖歌におけるセミオロジーの限界 Dom.E.カルディーノ
訳 水嶋良雄
グレゴリオ聖歌の記譜法について 水嶋良雄
第8号 -1987-
(日本の教会)とグレゴリオ聖歌ー生活の中から生まれる賛美と感謝ー 帘 功
ラン 239 写本のネウマにみられるリズム・プラン上の特徴 古賀磨由美
悲しみの聖母のミサ曲 水嶋良雄
第9号 -1988-
<神の仕事>のまえには ゲレオン・ゴールドマン
ザンクト・ガレン 359 写本の指示文字
スルスム、レヴァーテ、アルツィウスの研究 下山容子
第10号 -1990-
ドン・ウージューヌ・カルディーヌ ルイ・ソルトネ
訳 水嶋良雄
第11号 -1991-
ヴェローナ学会に見られるグレゴリオ聖歌の研究事情 その1 水嶋良雄
ヴェローナ学会に見られるグレゴリオ聖歌の研究事情 その2 十枝正子
第12号 -1992-
グレゴリオ聖歌の受容の現状 国本静三
グレゴリオ聖歌集 GRADUALE SIMPLEX について 高橋正道
第13号 -1993-
キリシタン時代の音楽とグレゴリオ聖歌 水嶋良雄
ヨーロッパ音楽の起源と本質
ゴーデンハルト・ヨッピヒ氏の講演より 橋本周子
第14号 -1995-
ザンクトガレン359 写本における始部稀薄トルクルス 吉岡聖司
ラン 239 写本における指示文字の研究
テネーテ、アウジェーテ 若本麻里
第15号 -1995-
G.ヨッピヒ氏の東京講演(1994)より G.ヨッピヒ
ヨーロッパ音楽の始まり 訳・構成 橋本周子
第5回国際グレゴリオ聖歌学会(ウィーン)報告 十枝正子
第16・ 17 -1996/1997合併号-
グレゴリオ聖歌古写本における同度音分離 沖野祐子
知られざるーラテン語の手稿グレゴリオ聖歌教則書ー
翻訳と注解 十枝正子
我が国で近年公表されたグレゴリオ聖歌関係書籍等の現状と課題 水嶋良雄
グレゴリアン音楽祭ワトゥー’97 水嶋良雄
第18号 -1998-
グレゴリアン音楽学会の設立過程と終戦までの活動状況 安足磨由美
グレゴリオ聖歌古写本にみられるヴィルガ、クリヴィスの研究 沖野祐子
第19号 -1999-
第6回国際グレゴリオ聖歌学会ヴェローナ大会報告1 水嶋良雄
ミサ固有唱の成立を中心に
第6回国際グレゴリオ聖歌学会ヴェローナ大会報告2 十枝正子
聖歌旋律修復を中心に
「正統的」グレゴリオ聖歌の復元とヴァティカン版聖歌旋律の修復」
第20・21号 -2000/2001合併号-
未来への遺産ーー日本グレゴリオ聖歌学会の歩みと今後の役割ーー 水嶋良雄
歌となった祈りーー最先端の演奏技法を学ぶーー 水嶋良雄
私の古ネウマ観 石川和子
復活の主日の昇階唱《Haec Dies》の演奏解釈 十枝正子
聖歌写本ファクシミリの近刊からーフランスの場合ー 西間木 真
第22・23号 -2002・2003合併号-
第7回国際グレゴリオ聖歌学会(ヒルデスハイム2003)報告 水嶋良雄
K.レヴィー教授によるラテン・ネウマの考古学
第7回国際グレゴリオ聖歌学会(ヒルデスハイム2003)報告2 十枝正子
一般報告
J.B.ゲシュル: E.カルディーヌの著作「グレゴリオ聖歌の指揮についての
若干の考察
A.トゥルコ: ネウマ記譜法と楽曲
私の古ネウマ観 石川和子
第
第24・25号 -2004.2005 合併号-
天使のミサをうたって 石川和子
グレゴリオ聖歌の反唱に関する新解釈とそれに基づく独自の演奏法についての考察
村上由紀子
第26・27号 -2006・2007合併号-
オリジナル旋律を巡って 石川和子
第8回国際グレゴリオ聖歌学会(フィレンツェ2007)報告1 十枝正子
一般報告
J.B.ゲシュル : グラドゥアーレ・ロマーヌム100年
G.バロッフィオ : メディチ版とヴァティカン版
第8回国際グレゴリオ聖歌学会(フィレンツェ2007)報告2 渡辺宏子
N.アルバローザ : セミオロジーによる演奏解釈の発展
D.ソルニエ : カルディーヌとその演奏解釈のルーツ
第28.29号 -2008・2009合併号-
グレゴリオ聖歌の<音価>に関する述語 水嶋良雄
Salicusの働き 石川和子
グレゴリオ聖歌歌唱に関する所感 鈴木 仁
2009 第10回 WATOU Gregorian Festival 参加報告 渡辺宏子
パリに行ったREQUIEM 宮脇百合江
* * *
2011年から 日本グレゴリオ聖歌学会の理事という仕事をすることになりました。1999年に入会した弱輩ものですのでので、学会のこともよくわかっていません。事務局を引き受けて過去のボレティーノを通読して、以上の経緯をしらべました。まだ不明の部分がたくさんありますので、事情をご存知の方お教えいただきたいと思います。
以下は2011年年5月30日からの、国際グレゴリオ聖歌学会、AISCGre のポツナム大会にでかけましたので、その報告を載せておきます。 |
国際グレゴリオ聖歌学会・AISCGre
Poznan (Poland) 5・30~6・4 2011
国際グレゴリオ聖歌学会の国際大会は、私は前回のフィレンツェの経験しかない。しかもこの学会はイタリー語とドイツ語が公用語であり、出掛けたところで、研究発表はちんぷんかんぷんなのは、承知だったのだが、日本支部の理事をお引き受けしたこともあり、また、インターネットによるプログラムでは、毎日ミサがたてられ、コンサートもいくつかあったので、新しい研究の結果を音としては聴くことはできると思いでかけることにした。
5月30日
フランクフルトトランジットで、ポツナン着 17:40.双発のプロペラ機、45人乗りの小さな飛行機だった。鎌倉駅より小さそうな飛行場。タクシーで20分でホテルへ。大急ぎで荷物を部屋に放り込んで、またタクシーで開会のミサとオープニングレセプションのある旧市街の FARA
of POZNAN(大きな教区教会・もとはイエズス会のものだったそうである)へ。ピンク色の外壁の美しい教会で、すばらしい大理石の柱が並び(後で聞くと模造だそうだが)大きなパイプオルガンが後陣の高みにある。 ミサは聖霊の votiva
のミサであり、主司式はポツナンアークビショップ。クワイヤーは今回の事務局長Mauriusz Bialkowski 率いる Canticum cordium,Poznan
。女声のみ。若い女性中心。きちんと訓練され、新しい研究の成果が取りいれられている感じ。通常文はⅢ。閉祭はVeni Creator. ポーランドは国民の95%がカトリックだそうで、一般の人も良く歌う感じ。主司式のアービショップのラテン語がうつくしい。
前回のフィレンツェであった人、またWATOUであった方など顔なじみも多いが、どうも、日本人は私ひとりらしい。Mr.Mizushimaはどうしたとみんなに聞かれる。Watouのベルナール夫妻もいてうれしかった。レセプションに40分ぐらいでて、ホテルに帰る。20分くらいで歩いて帰れると踏んで、歩き出す。緯度がたかいので、まだ明るい、9時前、明るいうちにホテルに着く。とったホテルは旧市街と新市街の中間にあり、とても具合がいい。長い第一日目終了。
 
5月31日
8:00 聖ミカエル教会(新市街、コングレスセンターの近く)「ご訪問のミサ」主司式、ポーランドのマリウス神父、クワイヤーはプラッスル教授のGrazのグループ。素晴らしいソリストが居る、女声のグループ10人足らず、キリアーレはⅩ offertorium
が Ave mariaの交唱に詩編をつけてなかなか。マリウス神父の叙唱はすばらしかった。 ソルニエ師共同司式。久しぶりにお目にかかる。ミサ終了後コングレスセンターに移動
9:00 Gosschl 教授のレクチャ- Principles of interpretation of Gregorian Chant:Situation
analysis and explanation of principles. 英語の紙あり。
10:00 幾つかのCDをかけて聴き比べ、いろいろ意見百出、イタリー語かドイツ語での発言であり、ポーランド語の訳がさしはさまれるが、英語は無視。
Passer invenit sivi コーヒーブレイク
11:45 4つのグループに分かれて最終日のミサのための練習、私のグループは今日は、Contiさんの指導。どうも、気になるところが私とは若干異なるような、、 昼食と休憩
15:00 Albarosa教授のレクチャー Mensuralism and Gregorian rhythm.
英語の紙あり
15:45 若手の指揮者による公開練習、それに対する助言に様なものはなかった。
17:15 D.Saulnier教授のレクチャー Paleographic foundation of the melodic edition
of the vespeeale Romanum 2009。 紙なし、イタリー語??
18:00 Fara of Poznan で Vespers (市電で移動、コングレスの名札で公共機関はフリーキップ) 夕食
20:00 諸聖人教会で、コンサート オランダのMaastricht。 WATOUで聞いたことがある。男性15人、一糸乱れずきちんとしているのだが、少々うるさい、力技みたいなところあり。後半いねむり、、、
教会は白くロココ調でうつくしい、パイプオルガンまで白。 Fara までもどって
タクシーで帰る。
 
 
6月1日
9:00 Rumphorst 教授のレクチャー、The relation the notation of St,Gall and Metz.
英語の紙あり。 レクチャーにさきだって、最近上梓した
Graduale Novumを 教皇ベネディクト16世に献呈した時の話があった。この本入手。45ユーロだった。すべてのミサの固有文がでているわけではなく、主日と、祭日が中心。
10:00 CDでの比較試聴 Cristus factus est . 5種類聞く、さまざま
11:30 グループ練習 Kurris さん? 印象ない。
15:00 Bernagiewicz 教授のレクチャー Musica Enchiriadis and the sung praxis of
Gregorian Chant., ポーランドの人でポーランド語。題からすると興味深く内容を知りたいのだがまったくわからない。 英語の紙なし。
15::45 Exercitium publicum
17:15 ミサの練習
18:00 パドバのアントニー教会でミサ あまり大きくない教会だが美しくかざられ、またそれが生き生きとしていて生きている教会の感受ける。 ST.
Iustini のミサ、主司式Cichyビショップ、ラテン語美しいし、声もよく響いてうつくしい。朗読がポーランド語でなされたが、ラテン語の場合と同じような朗誦で、まったく違和感なく、うまい。ヨーロッパ言語は、それができるが、日本語だとそうはうまくいかないことを痛感。
20:00から、各支部ごとに別れて、ミーティングが行われたが、私はホテルに帰って休む。
 
6月2日
8:00 聖ミカエル教会でミサ・復活節第6週木曜日、主司式 ポーランドのArchaniola師、この教会でするときは若い助祭が第一朗読をするのだが、みなきれいなラテン語で、とても上手である。スコラはGrazのプラッスル教授の手勢。指揮も、団員が代わりあってする。キリアーレはⅩⅢ、奉納唱は短いアンティホンに詩編をつけるというパターン。
9:00 コングレス会場に移り、Prassl 教授のレクチャー
The manuscripts of St. Gall tradition as manifestation of the sung praxis
英語の紙はない。
10:00 Exrcitinm publikam Abelardo と Schweizer さすが。
11:45 練習。今日のりーダーは ランプフォルストさん。マリアの続唱・Victime pascali によく似た、というか、それより派生したものであろう・を練習する。指導はふつう、特別な印象はない。
昼食、休憩のあと、みなで町の東側にあるカテドラルに市電で移動。ここから
イタリー語ドイツ語英語のガイドがついて、旧市街の中心まで、Walking
若い美人の御嬢さんで、英語はとてもうまい。カテドラルの解説の後、町まで歩き、由緒ある建物,教会など説明。町の中心の広場がブリュッセルやブルージュをおもいださせる。とても規模は小さいが、かわいい建物に囲まれてなかなかである。広場の真ん中に、無粋な建物がのさばっている。共産時代の遺物だそうだ。ガイドとわかれて、ベルナール夫妻、スペインの好青年カルロス(数年前ザビエル生誕400年?で、来日、大分、東京麹町教会で演奏会)と広場のカフェでおしゃべり、来年のWATOU のことうちあわせる。カルロスも子供たちを連れて参加予定だそうである。
コングレスセンターにもどって夕食
20:00 新市街をさらに南に3停留所くらいいったところのMadonna Addolorata教会でコンサート。 今日はアルバローザひきいる熟年女声の
Nedia Aetatis Sodalicium。アルバローザは今回、ずいぶん年をとられたような弱弱しい印象だったのだが、1時間半精力的に指揮。歌い手は、素晴らしい声の持ち主ぞろいで、よくそろい美しいのだが、〈国民性?〉、あまりきらきらして、これが固有文?というかんじで、オペラのアリアを聴いている気分。美しいのだがどれも同じ印象で途中いねむり。アルバローザは今夜は活力に満ちていたが、終了後、感謝状のようなもの渡されれていたので、そろそろ引退?来年のWATOUの出演予定にはいっているが?大丈夫?という感じを今回は受けた。
6月3日
8:00 聖ミカエル教会でミサ。「ルワンダの殉教者聖カルロとその仲間」
予定と変わってアメリカ人のベネディクト会の司祭だったと思う。ラテン語もう一つ。スコラは今日もGrazのPrassl教授のグループ。とても安定している。入祭はGTの曲ではなく、たぶんA.M.のAntまたはSimplexであろう。短いのでスコラの後、全員でくりかえしてから詩編Ps.97.キリアーレは Ⅰだったのだが、Kyrie
はトロープスつきでおもしろかった。トロープス付の本を入手したので、そのうち試みてみたい。Off.も Com.も同様の曲種であった。
9.00 Turco 教授のレクチャー、イタリー語で相変わらず英語の紙はない。
Neume and Mode
10:00 CDの比較試聴。Off の Ave Maria 。やはりいろいろ、音は修正してあるのがほとんど。 私の気にしている2度繰り返しの最低音、やや長いのが一般的のようである。
11:45 グループ練習、今日はシュヴァイツァー、てきぱきしていてよい。
どれかの発音の時、ひどく悲しげな顔になるのが気になった。
昼食。休憩。
15:00 General assembly
シュヴァイツァーがイタリー語とドイツ語を駆使して司会。マリウスがポーランド語で訳を挟むという進行。ちんぷんかんぷんである。
会計報告がされたらしいが、中身は不明。 日本は分担金を145ユーロもとめられたらしいが、私にはその根拠も、例年がどうだったかもしらないので、日本代表みたいに思われてもとても困るとおもった。誰かもっと責任の持てる人を、派遣すべきである。
トップの4人は
Goschl, Sr.Dolores, Schweitzer, Bardazzi
(やはりアルバローザは引退なのであろう)
あと投票があって理事かなんかをえらんだ
Achermans, Conti, Rumphorst, Prassl が選ばれた
だいたいすんでから、シュワイツァーに 1%しかわからなかったといったら、「ごめんごめん」という感じで記録を日本に送るといってくれたが、1月半たったが、まだなんとも。それとも日本事務局にはきているのか?
WATOUで私たちが演奏した後、HIROKOはどこで勉強したのか?と不思議がられたが、この学会に出る人はドイツかイタリーの学校で一時期すごすのが一般的なのであろう。ほとんどの人がイタリー語かドイツ語は過不足なく操れる人たちのようである。
夕食の後、St.Martin 教会で、コンサート もっとも古い教会だそうで、茶色いレンガのいかにも中世的な外観の教会、私のホテルから数分。
今日の演奏者は Goschel率いる、Schola Gregoriana Monacensis
びっくりするほど大きな身振りで全身で指揮するGoschel さん、若い人が多い男性グループはとても良い演奏だった。若いソリストが何人かいたがみなとてもよかった。 聖週間から復活ににかけての聖歌であった。今回のコンサートでは一番。
 
6月4日
荷物をまとめて、タクシーでカテドラルへ
9:00 最終ミサのリハーサル「聖母の Votiva」 入祭唱は、トラピスト用に私が選んだのと同じ Salve sancta . キリアーレはCum
jubilo 面白い続唱を歌う。ミサがはじまるまえに、役員の人たちにあいさつ、水島先生によろしくといわれる。また何人かにヴェロニカ橋本によろしくといわれる。
主司式はマリウスだった。ミサが始まると、仲良しになったレーゲンスブルグのルドルフが導入のオルガンをそれはそれは美しく、巧に弾く。教会音楽家,教会オルガニストというのはこういうものかと痛感。日本に来たらオルガニストの友人たちにぜひ引き合わせたいと思った。
閉祭と同時にカテドラルを出てタクシー相乗りで空港へ。せっかく替えたズロチという現地通貨をあまり使う機会もなく、空港でチョコレートを買って始末。
こんどはミュンヘン乗継で成田へ。トランジットの時間が短かったのだが、どうやらうまくいって無事帰国。
 
ポツナンの空港からミュンヘンまでシュワイツアーやベルナール夫妻といっしょ。 用意された冊子はとても使いよかったし、英語の通訳、ペーパーの問題以外運営はうまくいったのじゃない?ときいたら、Schweitzerによると、今回はかなりの出費over
だったらしい。会場,教会なども国が貧しいゆえか、かなりの請求があったらしい。
次回はどこかと聞いたらまだ未定とのことであった。これまでドイツとイタリーが交互に開催していて、今回は初めてのケースだそうである。
言語の問題で私にはもったいない旅だったのかもしれない。でも、やはり多くの音楽を聴き、うつくしい典礼にあずかり、多くの友人を得た。出掛けた意味はあったとおもう。
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|