
か 行
【解珍・解宝】5〜7巻
1)梁山泊に所属する、双子のエキスパート。それぞれ、『両頭蛇の解珍』『双尾蠍の解宝』のコードネームを持つ(ちなみに、輪郭の丸い方が解宝)。
最近エキスパートに入ったばかりの新人で、直属の上司は李忠である(7巻では、代理で周通?)。正義感あふれる性格であり、元は兄弟で虎などを狩っていた猟師だった。
普段は梁山泊は双尾蠍救助隊の一員として、エキスパートや市井の人々の救出を第一任務としている。
2)足の速さが特徴のエキスパートだそうだが、刺す又で首根っこを捕らえたり、投網を張って血風連を召し取ったりする描写からすると、捕縛術も得意のようである。
3)元ネタは水滸伝。二人がかりで賞金首の虎を退治したはいいが、村の有力者にそれを奪われ、挙げ句の果てに
【怪ロボ】
1)主にBF団が使用するロボット達の俗称。BF団は大規模な破壊工作に用いるため、このような怪ロボットを多数保有している。
本編やOPで登場した怪ロボのほかに、小説版でドクトル・トランボを旅客機ごと連れ去った怪ロボ(怪ロボ1号?)や、GRと並ぶほどの怪力を持つ、最強十傑集の操る最強ロボット集団(六神体?)が存在するらしい。
2)なお、OVAを見ていると認識にインフレが起こりがちだが、本来、怪ロボはBF団にとっても貴重な戦力らしく、よほど重要な作戦でなければ、怪ロボを二機も三機も投入することはないそうである。
《登場ロボリスト》
名称 |
解説 |
| 《BF団》 | |
| ガルーダ ネプチューン ご神体 GR2 GR3 大怪球フォーグラー 維新竜・暁&白瀧 ウラエヌス ギャロップ(5巻) ウェラヌス(ダルマ) 怪ロボ1号(B) 怪ロボ2号(C) 怪ロボ3号(A) OPロボ(船持ち上げ) OPロボ(トゲトゲ) OPロボ(二本角) OPロボ(頭でっかち) OPロボ(真っ黒) OPロボ(ハゲ) OPロボ(大量生産) モグラメカ |
三つの護衛団の一体。空戦/移動用。 三つの護衛団の一体。超巨大海戦用ロボ。 通称、光弾ロボ。BF団最強ロボ軍団『六神体』の一体。 海戦用のGRシリーズ。ミサイルパンチと衝角が武器。 空戦用のGRシリーズ。指先からミサイルを放つ。 重力レンズ砲を持つ、バシュタール動力炉のレプリカ。 列車型の秘密工作用怪ロボ。 自身の質量を変化させられる。地中潜行能力もあり。 本来は海竜型ロボ。パーツ毎に分離・合体する。 通称、“冷凍ロボ”。(漫画版では念動力ロボ) 十常寺操る怪ロボの一体。飛行する“爆撃ロボ” 〃。二本角。素早く走り回る、通称“高速ロボ”。 〃。背中に巨大シズマ管を背負う。通称、“発電ロボ”。 怪力を誇る、“ものすごく強い探査(偵察)用ロボ”。 “竜巻ロボ”。 怪ロボ2号のOP版。昔の資料では“蒸発熱光線ロボ”。 特に設定の記述なし(^^;)。原作ではロボットを大量生産する。 〃。原作通りなら妨害電波を出す。 〃。目からレーザー光線。 〃。 7巻。ペンタゴン地下900mにいる。 |
| 《国際警察機構》 | |
| GR1 日本支部の28号 自由の女神砲 |
解説無用。最強の陸上戦闘能力を持つ。 名称のみ判明。金田一正太郎が操縦すると思われる。 小説版のマンハッタン支部が保有。レーザー兵器。 |
【花栄】
1)梁山泊で、九大天王に継ぐ“指南”の地位につく弓の名手。別名、鎮三山・花栄。
戴宋に匹敵するほどの実力を持ち、実際、花栄と黄信の師である九大天王、“霹靂火の秦明”が亡くなった時、彼ら2人と戴宋の名が新たな九大天王の候補に挙げられた程である。
2)だが、候補には挙げられたものの、(指揮官であり、またその実力のために別行動を取ることも多い?)九大天王の地位に対して、自ら部下と共に死地に赴くことを信条にしている彼らは頑なにそれを固辞。見るに見兼ねた戴宋が止むを得ずその地位に付いたというエピソードがある。
3)そのような信条のため、射手としてはありがちな後方からのスナイパー的な弓術ではなく、前線に出て、マシンガンのように次々と弓を射たり、一体、何の必然性があるんだか分からないが、足を開脚しながら矢の雨を降らして道を作る(しかも敵には一本も当たらない)『追魂奪命剣』など、やたらとアクティブな弓術を披露してくれた。
4)なお、聖アー・バー・エーでは赤兎馬(『三国志』随一の名馬)らしき馬に乗っていた。
5)性格は、行動を好み、俗っぽいところも持ち合わせている“動”の性格だそうな。
6)原作の『水滸伝』では、弓の花栄とも呼ばれる、弓を取っては天下一の腕の持ち主で、梁山泊の中でもとりわけ目立つ活躍をしていた。
【影丸】
1)九大天王の一人。忍術の達人であり、マスク・ザ・レッドにライバル視されている。一時期、“影”の名称で設定されていたこともあった。
2)元ネタは、『伊賀の影丸』の主人公、影丸。徳川家に仕える伊賀の隠密であり、隠密取締まり役である服部半蔵を上忍とする。
ほとんど少年と言っていいぐらいの若さだが、“木の葉隠れ”やそれ以上に優れた基本的な忍術により、さまざまな奸計(忍者だし(^^;))を巡らせて数多の忍者に打ち勝った。
得意技の“木の葉隠れ”は、風に木の葉を乗せて自分の姿を隠す技だが、隠れるためだけに使うわけではなく、火を引火させて攻撃する“木の葉火輪”や、木の葉に睡眠薬を染み込ませて睡眠効果を狙ったり、風下の相手にしか効果がないという弱点を逆手にとって、技のことを知っている敵を風上におびき寄せたりと、技の特性を利用して幾多もの戦法を取ることを得意とした。
ちなみに影丸のライバル的なキャラとして、不死身の甲賀忍者“天野邪鬼”(幻夜そっくり(^^;))がいる。

《影丸(伊賀の影丸より)》
【金田正太郎(金田一正太郎?)】
1)ショタコン(正太郎コンプレックス。つまり、ロリコンの少年版)の語源でもある、鉄人28号の操縦者。Gロボ世界にも『(国際警察機構)日本支部の28号』が存在したり『少年探偵 金田一正太郎登場編』などがあることから、彼も立派にGロボ世界に存在するものと思われる。
2)ところで大作の服装って、正太郎の服装をそのまま持ってきたものなんだけど……(特に半ズボン)出るとしたら、正太郎の服装ってどうなるんだろ?
《金田 正太郎(鉄人28号・扉より)》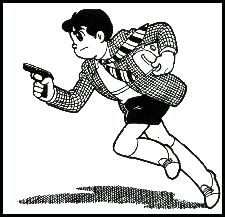
【ガルーダ】6巻
1)風圧でカワラザキらの乗る凧を吹き飛ばした、ビッグ・ファイア様の三つの護衛団の一匹(?)。プテラノドン型の怪ロボで、動力はシズマドライブ以外のものを使用しているものと思われる。
2)元ネタは、もちろんバビル2世のロプロス。一見、生物なのだが、原作でもれっきとしたロボットであり、バビル2世の主な移動手段であった。
【カワラザキ】 → 【激動たるカワラザキ】
【韓信元帥】3、5、7巻
1)随所で名前が登場する、国際警察機構が誇る最強の元帥にして梁山泊の最高司令官。中条長官ですら、重要な作戦の時には彼に許可を得なければならない。ちなみに、九大天王の一人でもある。
(梁山泊に?)軍師の地位に就くキャラは三人いるはずだが、韓信元帥の名ばかりが登場していることからして、彼が一番の責任者のようである(って、他の軍師の名前はイベントでの今川監督のトーク以外には出てないんだけど(^^;)
)。
2)元ネタは『項羽と劉邦』から。
【北の梁山泊】 →【梁山泊】
【ギャロップ】4巻OP、5巻
1)5巻で幻夜が鉄牛を撃退するために呼び出した、頭だけの怪ロボット。目だけを分離して独立操作することができる為に死角を補うことができ、また、口に吸引機を備えている。
2)ちなみに、本来は飛行能力を持った小型パーツによって形成される神出鬼没の海竜形ロボット(4巻OP参照)。原作の鉄人28号では、ギャロンという名前で鉄人を苦しめていた。
【九大天王】
1)国際警察機構が誇る、9人の最強メンバーの名称。国際警察機構における十傑集とも言うべき存在であり、十傑集に対抗できるのは国際警察機構の中でも彼らのみである。
2)長らく、今川監督の頭の中で試行錯誤が続いていたらしいが、7巻で最終的に
・神行太保・戴宗
・大あばれ天童
・無明・幻妖斉
・影丸
・静かなる中条
・大塚署長(^^;)
・ディック牧
・豹子頭・林冲
・韓信元帥
のメンバーに決定された。(あと、戴宗の前任ですでに亡くなっている『霹靂火の泰明』という設定もある)
3)コミック版で九大天王だった『天鬼』はいなくなったらしい。また、同じく『張飛』や『ブレランド』なども、一時期九大天王の名に挙がっていたが、没になったようである。(大塚所長に負けたのか……この3人は(--;))
4)ちなみに『霹靂火の泰明』が倒れた時、戴宗、花栄、黄信の三人が新たな九大天王の候補に挙げられたが、自ら部下と共に死地に赴くことを信条にしている花栄と黄信の二人は頑なに固辞したため、見るに見兼ねた戴宗が止むなく九大天王の席に着いたそうな。
5)ってことは、戴宗が一番の新入りのはずだから……九大天王板の名前って、天王入りの順番なのかな?(古参と思われる、韓信元帥や林冲が最後だし)
6)九大天王のネーミングは、香港の著名な映画スターが連名で名を連ねて歌う時のユニット名/CD名が元ネタかと思われる。
7)ちなみに九大天王の名板には、
『梁山箔九大天王
江湖 至今影“示見”圏許多武術人才
那少年哈哈大笑
《九大天王の名前》
江碧鳥逾白 山育花欲然 托塔
今春看又過 何日是帰年 晁蓋』
と書かれているようである(保証はしません(^^;))。
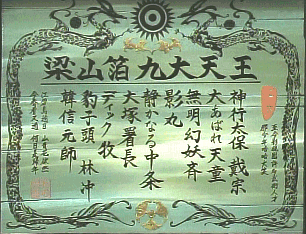
【Qボス】 → 【オズマ】
【銀鈴】
1)国際警察機構のエキスパートにして、フォーグラー博士の実の娘。名前は『銀の鈴』と言うコードネームの略であり(イヤリング由来?)、本名はファルメール・フォン・フォーグラー。
2)その能力は、移動した距離や質量に応じて消耗を伴うテレポート能力であり、バシュタールの惨劇から呉学人と共に脱出できたのも、アンチ・シズマ・ドライブの反応に、呼応して反応してしまったこの能力によるものである。
作中での描写を見る限りでは、一定フィールド内の物質を一旦エネルギー(光子?)化し、目的の場所まで跳んでから再実体化する能力であり、村雨が大怪球の中に飛ばされていたことからして、ある程度は飛ばされる人間の意志が関与できるようである(ヒィッツが、自らの意志で踏みとどまろうとしたからああなったのか、銀鈴の意志でああなったのかは不明)。
3)バシュタールの惨劇のその場に居合わせ、その真実を全て知っていたものの、父親が死んだと考えており、また、シズマ博士たちのみが、父の意志を実現できるものと考えていたため、博士等を告発せずに真実を自分の胸の中にだけ秘め、フォーグラーの名を捨てることのできる唯一の場所、国際警察機構に入った。
当年とって18才であり、惨劇の当時は8才でしかなかった。
4)ちなみに、恋人は村雨健二であり、過去がそうさせたのかどうかは分からないが、死ねない男の辛さを理解したのは、彼女だけだった。
5)ところで7巻、大作の決意や幻夜がああなった事は概ね満足として……銀鈴自身は何も決着がついてないのが大いに不満。6巻のラストで『お父様を信じて……』と決意して、7巻では命を削ってまで大怪球の中にテレポートし、村雨にも彼女自身の選んだ道を行けと言われたのに、いざ幻夜に会うととたんに躊躇して、これまでの決意を否定しちゃってるし……。これじゃ、何のためにこれまでストーリーを作ってきたんだか分からない。
せめて、“銀鈴が父親の遺志を貫こうとし、それを止めようとした幻夜が彼女を射殺。しかし銀鈴の行動は成功し、彼女の死の後で、フォーグラー博士が、本当は銀鈴の信じた通りの善人であり、幻夜の思い込みは間違いだったことが分かる”というストーリーラインだったら納得いったのに……。
6)元ネタは『狼の星座』で主人公に惚れられながら、主人公を裏切って殺そうとした“銀玲”なんだそうな(『その名はワンゼロワン』でバビル2世を匿って殺された、女スパイの“王 銀鈴”も入ってると思うけど)。
7)なお、ファルメールの名前は、フランスのシンガー、ミレーヌ・ファルメールが元ネタだそうな。
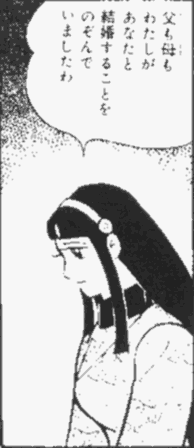
 《左・銀玲“狼の星座”より》 《右・王 銀鈴“その名はワンゼロワン”より》
《左・銀玲“狼の星座”より》 《右・王 銀鈴“その名はワンゼロワン”より》
【Gen・Reiシリーズ】
1)Gロボ作製費を捻出するために作られたという噂(?)のある、銀鈴を主役としたパラレルワールドの別シリーズ。
2)しかし、ロボの購入者と、銀鈴シリーズの購入者って、かなりずれてるような……。
3)まぁ、『青い瞳の〜』は比較的シリアス路線で悪くはなかったかも(TVアニメでやるジャイアント・ロボの、可もなく不可もない回のようなエピソードだったし)。
【クエラー・ドライブ】
1)設定段階のシズマドライブの呼称(仮称?)。初期段階の設定資料などで目にすることが出来る。
2)元ネタは、アメリカのSF・TVドラマ『スペース1999』、13話『宇宙の破壊者・核爆弾船(英題:VOYAGER’S RETURN)』に登場する同名の動力装置から。
クエラー・ドライブとは、エルンシスト・クエラー博士が人類の発展を願って恒星間ロケットの為に開発した原子力エンジンであり、銀河系の知的生命の探査を目的に打ち上げられた『ボエジャー1号』に搭載されて未知への探索へと旅立ったのだが、危険な高速中性子を噴射して進むシステムだったために接近した二つの惑星の全生命を滅ぼしてしまい(どんな生命探査だ(--;))、復讐に駆り立てられた彼らから地球を守るため、自ら招いた惨状をなんとかしようと、クエラー博士自身がボエジャーに乗り込み、助手に研究を託して彼らを防いだエピソードに登場する。
ちなみにこのクエラー博士、ドライブ開発の過程で助手夫婦を死なせてしまい、失意の末に名を変えて別の人間として暮らしていたり、この助手夫婦の子供が、ボエジャーに乗り込む際に研究を託した助手であったりなど、かなりロボの元ネタっぽい雰囲気があるんですが……本編を見たわけではないので断定できません(泣)。
【草間大作】
1)言わずと知れた(?)、Gロボの主人公。父親の手によって、世界最強のロボット兵器、ジャイアント・ロボに声紋を登録させられてしまったため、わずか12歳にしてBF団と戦わねばならなくなってしまった運命を持つ。
作中ではさんざごねながら、随所随所で暫定的な答えを出したりもしたが、7巻でついに、“父の遺言の是非は分からないが、とにかくその答えを見いだすまで、試してみる”という結論に達し、これまでの迷いを振り切った。
2)1巻の封入紙によれば、父の草間博士ばかりでなく、彼の母親も大作を逃がすために殺されたんだそうな(消えている設定の可能性が強いけど、これじゃGガンと同じ……(^^;)
)。
なお、小説版では、ひょっとしたらバシュタールの惨劇で亡くなったのかも……という記述があることから、かなり前に亡くなっているようである。
ちなみに一番最新の記述では、大作の母親は『幸せは犠牲なしには得られないのか』の言葉を遺言に草間博士に託して亡くなったことになっている(いつ亡くなったかは不明)。
3)影が薄い、影が薄いと言われているが、実はGロボは大作が主人公の話ではなく、大作がいかに主人公になるか、という話であり、銀鈴と幻夜は大作と同じく、父親から巨大な遺産と責任を受け継いだ人間の合わせ鏡のような未来の姿を表しているんだとか。
(ってことは、幻夜に問いかけられた『こんな恐ろしい遺産を父親に勝手に手渡され、どうする!?』って台詞が『バベルの籠城編』で生きてきそうだけど……)
4)なお、大作の声には、今川監督から、子供と大人の確執を、“子供というのは大人たちほど事の重要さを捕らえていないんじゃないか”という一面を色濃く出したいために、わざと棒読みで、しかも可能な限り一番幼い声にしてくれ、と注文があったんだそうな。
(現に、一番最初の『砕け!ジャイアント・ロボ』と、7巻最期の同じ台詞では、全然演技が違うし)
5)原作でも、ジャイアント・ロボの主人公である。

《草間大作(ジャイアントロボ・サンデー版より)》
【草間博士】
1)大作の父にして、GRシリーズの開発者。
元・国際警察機構の兵器開発部長官だったが、『幸せは犠牲なしに得ることはできないのか?時代は不幸なしに越えることはできないのか?』という妻の遺言に答えるためと、BF団の甘言に乗せられてとで、一度は警察機構を裏切り、BF団の『GR計画』に加担した。
2)しかし、GR計画の真の目的を知り、自分の犯した過ちの大きさに気付いた結果、ロボをBF団に使わせてはならないとロボ奪取の計画。
企みはその時GR計画の任についていたセルバンテス(GR計画が大変重要かつ巨大プロジェクトだったため、十傑集が交代で任に就いていた)に発覚。自身は彼の手によって重傷を負わされ力果てたものの、大作にGR1(と妻の遺言)を託すことで、結果的にBF団の手からGR1を奪取することに成功した。
3)ちなみに元ネタは、バビル2世でバベルの塔を襲撃してきたヨミ配下の特殊訓練兵、ダックと思われる。
 《ダック(バビル2世より)》
《ダック(バビル2世より)》
【グレタガルボ】
1)国際警察機構が所有する、全長200mの超大型飛行船。北京支部の移動司令本部でもある。
重量1万t前後に及ぶロボを飛行機で空輸するのはあまりに非現実的であったため、ロボの輸送に使用されることになった。
2)武器としては旋回機銃を数門装備している位で戦闘能力は皆無に等しいが、ディーゼル機関によるサブ動力システムを備えているためにアンチ・シズマフィールド下でも行動することが可能。
非常時にはブリッジ部分を切り離して飛行(滑空?)することができ、また、混交竜、僕天周鳥、玉麒麟という3機の小形戦闘ヘリを搭載している。
3)なお、漫画版では姉妹機として『デートリッヒ』(昔の映画女優の名前)や『ジャンヌ・ダルク』などが確認されている。また、初期の資料でグレタの艦載ヘリは『ガリレオ』、『コペルニクス』、『シュリーマン』という名称だった。
4)名前の元ネタは、36歳で引退し、私生活は全くの謎に包まれていたアメリカの映画女優、グレタ・ガルボから。代表作は『アンナ・クリスティ』『肉体と悪魔』など(注:かなり古い)。
【暮れなずむ幽鬼】6、7巻
1)鳥や虫、獣や植物に至るまで、あらゆる生物を自在に操る能力を持つ十傑集。とりわけ、体内に飼う(?)『群雲虫』は敵を包み込んで数秒で食らい尽くす、恐るべき直属部隊である。
2)ちなみに、これらの能力は生まれ持った強力なテレパシー能力のなせる技であり、幼い頃は無意識に人の心を読んでしまうため、人の心の裏までも知らされることとなり極度の人間不信になっていたが、カワラザキとの出会いによって閉ざされた自我を開放。BF団に入団したらしい。
3)とは言え、現在でも決して他人を信用することはない孤高の戦士であり、(設定が生きているかどうかは知らないが)国際警察機構の天鬼を宿敵としているそうな。
4)元ネタは『伊賀の影丸 七つの影法師』に出てくる同名の忍者。巧みな隠形術で伊賀側を苦しめ、影丸にさえ瀕死の重傷を負わせたが、最期は天鬼の『布とりで』に術を破られ、相討ちになった。
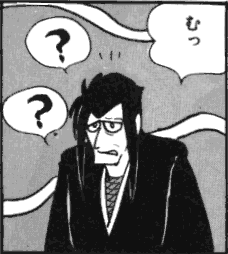
《幽鬼(伊賀の影丸―七つの影法師―より)》
【黒いアタッシュケース】
1)1巻の副題にもなっている、アンチ・シズマドライブが収納された黒いアタッシュケース。全部で三つ存在する。最初は全てBF団の手にあったが、1つは奪回の目的で自らBF団に捕らえられたシズマ博士の手によって、国際警察機構の手にもたらされた。
2)シズマ博士がそんなことをしなかったら、全てが丸く収まっていたはずだが
【軍師・張良】
1)梁山泊が誇る三軍師の一人。未公開エピソードの1つ、『史上最大の決戦 韓信 対 孔明』で活躍するらしい。
2)元ネタは『項羽と劉邦』から。
【激動たるカワラザキ】6、7巻
1)強力な念動力を用いる十傑集の最年長。BF団創世期より在席しており、十傑集の初代リーダーとして組織を統括していたが、新たに現れた孔明の存在に疑問を持ち、牽制策としてリーダーの座を樊瑞に譲り、十傑集の結束を強めたという過去を持つ。現在は樊瑞たちの良き参謀役として活躍し、激動のじいさまと呼ばれて親しまれている。
2)その能力は強力な念動力であり、年季を経て練られた能力は、パワーはもちろん微妙な繊細さをも有し、多数存在するBF団の念動力者の中でも、未だ他に追随を許さない最強の地位を誇っている。
3)また、念動力以外にも二つの能力を持ち、片方の能力は6巻において披露される……はずだったが、収録時間の関係で仕方なく削られたんだそうな。なおもう一つの能力はこれまでに一度も使われたことがなく、彼の切札であるらしい。
4)元ネタは『マーズ』に出てくる地球監視者の一人。凍気を発し吸引機能を持つ巨大なダーツを発射するダルマ型怪ロボ、ウラヌス(1、2巻OPや、コミック版に登場)を操り、マーズを追い詰めたが、ガイアーに攻撃され、ウラヌスごと蒸発した。
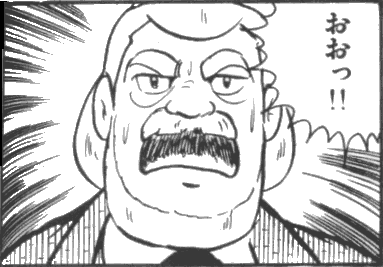
【血風連】6巻
1)直系の怒鬼に仕える、編み笠の私兵達。七節棍を使う。十傑集直下だけあって、一人一人が、かつて九大天王の候補にも上げられた花栄&黄信と真っ向から斬り合えるほどの実力を持つ。
持つはずなんだが……7巻では普通のエキスパートにもやられてたし……弱い連中しか飛ばされなかったのか、それとも怒鬼がいないから弱いのか……。
2)私兵が禁じられているBF団にあって、何故怒鬼だけが私兵を許されているかは謎であり、一説には怒鬼がBF様の弟であるからだという噂がある(でも、それだと怒鬼自身には権威が無くなるので、個人的には嫌(^^;))。
また、怒鬼の直属であるはずの彼らが何故、孔明からの指令に従っているかも謎である。
3)ちなみに、7巻でそれぞれ固有の人格や外見をしていることが判明し、“血風連は怒鬼の実体分身説”は否定された。
4)元ネタは『闇の怒鬼』に出てくる幕府の元暗殺組織“血風党”で、土鬼は、脱党した父から習い覚えた彼ら自身の武術を武器に、彼らと血戦を繰り広げた(って書くと、仮面ライダーみたい(^^;))。
《血風党(闇の土鬼より)》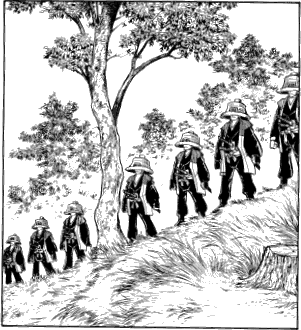
【阮三兄弟】5、7巻
1)警察機構のエキスパート、阮小二、阮小五、阮小七ら三兄弟の通称。石ヶ村(石碣村?)の漁師でもある。
2)必殺技はデンデン太鼓を使った共鳴技。エネルギーを利用してバリアーを張ったり、共鳴による衝撃波で敵をなぎ倒したり出来る。
3)5巻で中条長官と共に聖アー・バー・エーに向かったが、7巻で梁山泊が落ちてくるまで目立った活躍はせず、以後は暴走するシズマのエネルギーを使ってバリアーを張ったり、迎え来る血風連をなぎ倒したりしていた。
4)原作の水滸伝では、水中での運動能力において他に追随を許さないものがあった。
【原子力】
1)ともすれば放射能漏れを起こし、そうでなかったとしても廃棄物の処理に大いに悩まされるエネルギー発生方法の一つ。エネルギー変換効率が優れているため、様々な弊害がありながらも、一部に好んで用いられる傾向がある。
2)より優れたエネルギー機関であるシズマドライブが誕生したため、シズマ機関完成時にBF団でさえ全てを廃棄したとされていたが、ロボの動力として残されていた(破損が前提の戦闘用ロボットに使うような動力じゃないと思うけど)。
3)ちなみにシズマ以外の動力で動いているロボットは、ガルーダ、ネプチューン、GR1〜3であり、少なくとも、GRシリーズの中で原子力を用いているのはGR1だけである。
4)GRシリーズに、何の動力が用いられているかがジャイアント・ロボのシナリオの根幹に関わるそうなんで、とりあえず、現在の技術で実用可能なエネルギー源を挙げてみると下の表みたいになるんだけど……(地熱はロボには無理か)あんまし信用できないかも。
Gロボの世界では、新たに発見された科学技術はシズマ・ドライブくらいで、それ以外の科学的発展はなされていないいないみたいだから、基本的に既存(現代で)の技術を使っていると思われるけど……SF設定協力:川又千秋って辺りが、少々恐いかも(もっとも、タキオンとか、モノポールとかの一部のマニアにしか分からない科学考証は、レトロなGロボ世界には出てこないと思うけど)。
5)小説版の“周囲の空気と反応して、高純度の可燃性物質を生み出す”ってあるのと、アンチシズマフィールド下で、シズマ中心核が急速に増大した時に周囲が無酸素状態になったことからして、個人的には、シズマ中心核は周りの溶液と酸素を使って、エネルギーと不純物を排出する、効率のいい空気電池みたいなものかなって気もするんだけど……。(ただ、シズマ中心核の分裂の仕方が、あまりに生物的だったのが気になるけど……)。
6)ちなみに、空気電池ってのは、空気中の酸素と反応して電気を生み出す、長寿が売りの電池のことである。
【動力特性比較】《実在のもの含む》
| 原料からエネルギーへの変換方法 | 名称 |
直接取り出せるエネルギー | 原料 |
不明 |
シズマ・ドライブ | チャンバーにより変化(可燃物質/電気/熱) | 不明←リサイクル処理をして何度も流用可 |
不明 |
アンチ・S・ドライブ(旧) | 負のエネルギーフィールド | 不明 |
| アンチ・S・ドライブ(新) | アンチ・シズマフィールド | 不明 | |
| 例) | |||
(シズマ・ドライブ) |
中条長官のライター | 可燃性物質 | 周囲の大気 |
(シズマ・ドライブ) |
シズマ発電所 | 電気 | 不明 |
| 《既存のエネルギー機関》 | |||
| 蒸気機関(タービン) | 火力発電 | 熱 | 石油、石炭 |
〃 |
原子力 | 光・熱 | ウラン |
〃 |
地熱 | 熱 | 地熱 |
| 水車(水力タービン) | 水力発電 揚水発電 |
運動 | 高い所にある水の位置エネルギー |
| 風車(風力タービン) | 風力発電 | 運動 | 風の運動エネルギー |
| 爆発機関(ピストン) | ガソリンエンジン | 運動 | ガソリン |
〃 |
ディーゼルエンジン | 〃 | 重油/軽油 |
| フロート | 潮汐発電 | 運動 | 潮の干満 |
| 化学反応 | 太陽電池 | 電気 | 太陽熱←Gロボ世界では効率が悪い |
〃 |
化学電池 | 電気 | 各種金属、他 |
| 火 | 火 | 光・熱 | 可燃性ガス |
| 《未来の?エネルギー機関》 | |||
| 対消滅 | 対消滅機関 | 光・熱 | 反物質&通常物質 |
P.S.(厳密な意味での)蒸気機関と言うのは、熱エネルギーによって水を蒸気に変化させ、その膨張率によってタービンを回し、運動エネルギーに変える変換機の総称。
また爆発機関というのは、名前こそ怪しいが単なるガソリン・エンジンであり、ピストン内で原料を爆発させて、その力でピストンを上下させ、運動エネルギーに変える機関の総称である。
【幻夜】
1)『地球静止作戦』の立案で急昇進した、BF団のA級エージェント。その正体はフォーグラー博士の実子、エマニュエル。28才。
バシュタールの惨劇の時にテレポートで一緒に生き延びた父親が、完成したシズマドライブを見たとたんに狂おしい様子で研究室にこもり、“シズマを止めろ”との言葉と共に、3本のアンチ・シズマ・ドライブ残された。
フォーグラー博士の真の意志は欠陥品であるシズマドライブを直そうとしたものであり、二本揃った状態で起こるシズマドライブの暴走は、その副産物でしかなかったのだが、幻夜はシズマしか止めないその効果を見て、これはシズマドライブへの復讐のために作られた物だと判断して、孔明に誘われるままBF団に入団。
『地球静止作戦』を(シズマドライブが完全に世界中の動力と入れ替わる時まで待って=聖アー・バー・エーの完成を待って?)立案し、実行に移した。
2)だが、3本揃えて父の真意を知った時には、既に3本目のドライブを手に入れるために唯一の肉親である妹、ファルメールを自らの手で殺してしまっており、挙げ句の果てにその狂乱のさなかで自爆装置まで作動させてしまっていたため、幻夜は三本のサンプルと銀鈴の鈴を大作の手に残して(テレポート対象から外して?)大怪球ごと宇宙にテレポート。爆発して、この世から去った。
3)こうしてあらためて書いてみると……やっぱり、フォーグラー博士、“世界の破壊者”呼ばわりされてもバチは当たらんような気が……(特に幻夜から)。
4)本来はクラシックとワインを愛する物静かな性格であったが、父への思いを抱く時、その素顔は復讐鬼としての面しか表さなくなってしまった。
なお、コードネームは、父親の台詞『我々は手に入れた!美しい夜を!それは幻ではない』から由来。シズマがもたらした『美しい夜』を『幻』とするための決意の現れであると思われる。
5)銀鈴と同じく猛烈な消費を伴うテレポートの他に、影縫い、幻覚による変装、髪による攻撃など、多彩な能力を誇る。
6)ちなみに、数々の同人誌で話題の種となった黒パンツの元ネタは、知る人ぞ知るカルトミュージカル(映画もあり)『ロッキー・ホラー・ショー』に登場する城主のパロディーだそうな。
7)元ネタは“伊賀の影丸”七つの影法師に出てくる伊賀側の凄腕の忍者、幻也斎。
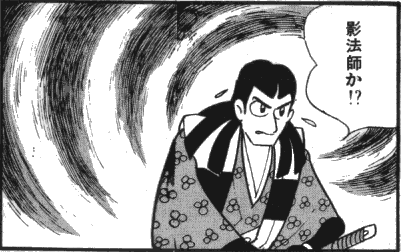
《幻也斎(伊賀の影丸―七つの影法師―より)》
【眩惑のセルバンテス】5巻
1)巧みな話術と強烈なカリスマによって、いつの間にか相手を取り込んでしまう、精神に直接作用する心理攻撃“眩惑”の能力を得意とする十傑集の一人。十傑集の中で唯一、表の顔(オイル・ダラー)を持ち、時にはその立場を利用して作戦に挑むこともあった。
2)個性の強い十傑集の中で、彼とアルベルトのみが、唯一、お互いを尊重しあい、連携も可能な間柄であったのだが、『ドミノ作戦』の時に戴宗によって倒されてしまい、そのことがつぶされた自身の右目の恨みとも相まって、アルベルトのトラウマとなっていた。
3)ちなみに、誕生編の草間博士逃亡事件については、『GR計画』があまりに重要で、かつ巨大なプロジェクトであったため、十傑集が交代で任務についていたのを、たまたま彼が責任者になっていた時に起こった出来事であり、GR2に命令しているからといって、特に彼がGR2の操縦者だった訳でも、ロボット操縦能力に長けていた訳でもないらしい。
4)ちなみに、草間親子とは結構親密な付き合いがあったらしく、大作からは『セルバンテスさん』と呼ばれていた。
5)元ネタは(目の下の線こそ無いものの)コンビネーション攻撃でバビル2世を苦しめたヨミ配下の特殊訓練部隊の一人、ムチ使いの陳かと思われる。
《陳(バビル2世より)》
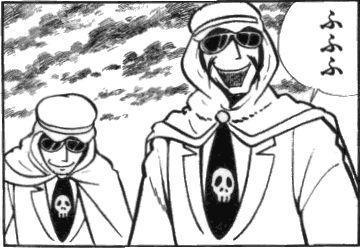
【コ・エンシャク】1〜7巻
1)神出鬼没の謎のエージェント。一言も口を開くことはなく、常に十傑集を含む全てのBF団団員を監視しているため、一部では、ビッグ・ファイアが放った監視者ではないかと噂されている(実は、孔明直属の部下)。
主に作戦リーダーの護衛(兼監視)役を努めている。
2)特技の二条鞭の他、常に影に潜み、影から出没する能力や、マントを回転させての防御に、(設定上では)怪しい幻術も使えるなどの多用な技を見せているが、特筆すべきは、何度倒されても、次の瞬間には蘇っているその不死性であり、封入紙の記述によれば彼は“G・Rの世界でも秘密の存在であり、生死については問題外のキャラクター”となっているそうな。
3)なお、コ・エンシャクが影に隠れたり、影から出現したりしているように見えるのは、“影”の能力ではなくて、影に見せかけた不定形からエンシャクの形状に実体化したり、エンシャクの姿から影を模した形状に不定形化しているのであり、5巻で鉄牛に仮面をやられてあんなに苦しんだのは、実は目が弱点だからなんだそうな。
4)しかし、不定形化の能力って事は……やっぱり、コ・エンシャクの正体って、アレなんだろうか?
5)元ネタは『水滸伝』の官軍将軍、呼延灼。元は梁山泊の連中を退治するために攻めてきたが、のちに説得されて梁山泊に入った。
【黄信】
1)梁山泊の指南の地位につく剣術使い。別名、小李広の黄信。OVAを見る限りでは、常に花栄と共に行動しているようである。
2)戴宋に匹敵するほどの実力を持つ。
花栄と共に、九大天王“霹靂火の秦明”に師事していたが、師が戦死した時、彼ら二人と戴宋の三人が新たな九大天王の候補に挙げられたものの、自ら部下と共に死地に赴くことを信条にしている彼らは頑なにそれを固辞し、見るに見兼ねた戴宋が止むを得ずその地位に付いたという逸話がある。
3)花栄が“動”の性格なのとは対照的に、黄信の方は冷静沈着で知略を好む“計”の性格であるが、大作を子供扱いせず、攻めるべき所はためらわずに攻め、感謝すべき所は素直に感謝するという、一本気な情熱家でもある。
4)本編を見る限りでは、剣で大地を切り裂き、巻き起こす衝撃で敵を攻撃する戦法を好むようである。
5)原作の『水滸伝』でも花栄とは親友同士であり、なかば花栄に巻き込まれる形で梁山泊入りキャラだが、花栄ほど目立つ活躍はなかったようである(得物の違いにもよるけど)。
【黄帝・ライセ】
1)上映会の今川監督のトークではミヨとも言及された、国際警察機構の首領。BF団に対抗するため、国際警察機構を結成したようだが、その真意は定かではない(と書くと、読みすぎか
(^^;))。2)元ネタは、世界征服を目指して、その障害となるバビル2世と戦いを繰り広げた、バビル2世と同じ血を引く悪の首魁、ヨミである。
3)善悪が全く立場を変え、バビル2世が世界征服を目指し、ヨミが世界を守っている辺り、なかなか味のある配役である。
4)ちなみに原作では、部下全員の命を人質に捕られて、罠とは分かっていてもわざわざ助けに戻るなど、通り一辺の悪役では無いところも見せていた。
【呉学人】
1)国際警察機構のエキスパート。鉄扇子を使って戦闘を行なうことも可能だが、その能力の真髄は卓越した頭脳にあり、そのため“智多星”の二つ名を頂いている(失敗ばかりしてるけど)。
2)元フォーグラー博士の助手であり、バシュタールの惨劇のその場にも居合わせていたのだが、銀鈴と同じ理由で、口を包んでいた。
3)実は、役柄的に、彼には横溝正史の著作における金田一耕助の役割を与えており、真相に気付きはするものの、それはいつも全てが終わってからというパターンや、『私は重大なことを見逃していました。この事件は実は十年前に発端があるんです』といった類の台詞は、すべて金田一耕助の台詞や役柄から来てるんだとか(^^;)。
彼の作戦が失敗だらけなのも、根底はここに由来しているものと思われる。
4)なお、キャスティングは『ロッキー・ホラー・ショー』から。この作品でオカマの暴君を演じる江原正士さんが、オカマのなよなよした博士を演じてみたらどうなるか、という発想で決められたんだそうな。
5)元ネタは、梁山泊の軍師、呉学人から。
→ 【横溝正史】
【国際警察機構】
1)BF団の存在に気付いた複数の国家首脳達が、彼らの画策した陰謀により互いに疑心暗鬼になりつつも、それまで締結されていた安全協力条約を元にして作り上げた組織。
警察機構の名が示すように彼らは軍隊ではなく、BF団の陰謀を事前に察知してうち砕くのが彼らの目的であるが、国境を越えて暗躍するBF団に対抗するため、彼らには国家主権をも凌ぐ捜査権が与えられている。
なお、初期の設定では黄帝ライセを陰の指導者として頂いており(設定、消えてるかも)、北と南の二つの梁山泊を総本山とする。
2)警察機構が守る側であり、どうしても後手を踏まざるを得ないと言う理由もあるが、それ以上にBF団の計画が恐ろしく緻密であり、またBF団エージェントらの能力がエキスパート達のそれを大きく凌いでいるため、警察機構は地球静止作戦時点でBF団に大きく押されてしまっており、警察機構側は多数のエキスパートやいくつかの支部を失って、圧倒的に不利な立場にいるんだそうな。
3)原作のジャイアント・ロボではユニコーン機関/国連特別捜査機構(版によって違う)の名称であった。
4)なお、現時点で階級名/所属支部が分かっている警察機構のメンバーは以下の通り。
《所属支部》
| 階級 | キャラ名 |
| 故人 | 晁蓋、霹靂火の秦明 |
| 本部・梁山泊 | 韓信元帥、花栄、黄信、李忠、周通、解珍、解宝、(阮三兄弟?) |
| 北京支部 | 中条長官、呉学人、戴宗、楊志、鉄牛、一清道人、銀鈴、大作 ・GR1、弾丸列車、グレタ・ガルボ |
| パリ支部 | 村雨 |
| 日本支部 | 人間コンピュータの敷島、金田一正太郎 ・28号 |
| マンハッタン支部 | 俊敏なるシャープ ・自由の女神砲 |
《国際警察機構・支部》
| 国際警察機構 | 登場シーン |
| 南の梁山泊 北の梁山泊 北京支部 パリ支部 日本支部 ロンドン支部 マンハッタン支部 インディアン支部 インド支部 スイス支部 南極支部 ロシア支部 アフリカ支部 パプアニューギニア支部 |
エキスパートの総本山。OVA終了現在、クレーター化。 エキスパート達の修行場。 ロボや戴宗、中条長官らが所属。警察機構、有数の実力派。 村雨が所属。北京支部と並ぶ腕利き揃い。 28号や、人間コンピュータの敷島らが所属。 小説版に登場。 小説版に登場。自由の女神砲を所有。ニューヨーク 設定画に登場。支部員はインディアンの姿をしている。 〃。支部員は僧の姿。 〃。 〃。 〃。 〃。 〃。支部員は、怪しい原住民姿。 |
【国際警察機構 日本支部】
2)小説版に
“人間コンピューターの敷島”が草間博士には『さんざんお世話になった』と言っていることからして、草間博士もかつてはこの支部にいたものと思われる。【国際警察機構 北京支部】
1)支部の中でも、トップクラスの実力を保有している支部。近くに梁山泊が存在し、またジャイアント・ロボがいたことから、BF団と存分に戦えるだけの力を残している数少ない支部の一つとして名を連ねていた。
2)カモフラージュを兼ねてか、かつての原子力発電所跡を利用した施設であり、北京基地が襲撃された際には炉心跡にロボを設置してあった。
【国際警察機構 パプアニューギニア支部】
1)設定画にしか存在しない、国際警察機構の一支部なんだが……制服がとんでもなかったりする。
2)おそらくは、警察機構の中で派遣されたくない支部ナンバー1。
いや、そりゃまあ、一応秘密の組織なら周囲にとけ込む必要があるから必然性は分かるんだけど……だからってなぁ(^^;)。
《各国支部の制服》
【国際警察機構 パリ支部】
1)村雨の所属する、国際警察機構の一支部。北京支部と並ぶ腕利き揃いの筈だったが、BF団がノートルダム寺院地下に秘密基地を作る関係でか、(小説版では)静止作戦前の一週間で支部員の半数が殉職してしまっていた。
2)なお、BF団の勢力は特にヨーロッパ地方で強く、警察機構の監視が行き届かなくなり始めていたため、大怪球を建造させてしまうと言う大失態を引き起こしてしまったんだそうな。
【国際警察機構 マンハッタン支部】
1)“俊敏なる”シャープが支部長を務めている、国際警察機構のアメリカ大陸における支部の1つ。エンパイア・ステート・ビル地下深くに存在し、隠し玉として超長距離レンジのレーザー兵器、『自由の女神砲』を所有している。
2)なんでも、BF団の活動が盛んなヨーロッパと違い、(小説版では)アメリカ大陸は唯一、BF団の怪ロボの上陸を拒み続けてきたんだそうな(でも、OVA版ではペンタゴン地下にBF団のモグラメカが存在してたりしてるんだけど……(^^;))。
3)ちなみにマンハッタンとは、自由の女神像が存在する、ニューヨークの5自治区のうちの1つである。
【ご神体】1〜6巻OP
1)全話のOPの最後に出てくる、全身から光子弾をまばゆい位に放つ、金色に輝くロボットであり、“国際警察にGRあれば、BF団に神体あり”というように、GR1に対する最強の敵として設定されている。
2)元ネタは、『マーズ』に出てくる最強ロボ、ガイアー。原作では光子弾を効率よく使うため、引力装置で対象を引き付け、近付いた所で至近距離で光子弾を命中させるという、かなり極悪な能力を持っていた。
3)原作ではマーズが操っていたが……どうせならビッグ・ファイア様が直接あやつるって形になんないかな?(某アニメのカヲル君みたいに、何も動作はせずに、腕を組んだまま《マントをなびかせたまま》操るとか)
4)未確認情報では、“大地の歌”という名称だった記事もあるとか。
5)BF団の最強ロボット集団『六神体』の一体(という設定が7巻販売後に公表された(^^;))。ちなみに、マーズで六神体の一つだったウラエヌスやウェラヌスは六神体には含まれていない様子である。
【5人の博士】
1)シズマドライブを作り上げた、五人の博士。つまり、ドクター・ダンカン、シムレ教授、ドクトル・トランボ、シズマ博士、フランケン・フォン・フォーグラー博士のこと。彼らは、シズマドライブのエネルギー理論の発見によりノーベル賞を受けた。
2)どうやら、シズマ博士の派閥(フォーグラー博士以外の4博士)とフォーグラー博士の派閥(博士自身+助手に呉学人&エマニュエル)があり、それぞれ別の方式のドライブを模索していたようである。
3)ところで、ノーベル賞って受賞者は1部門3人までって限定されてるんだけど……(^^;)(グループで研究していても、上の制限によりリーダー格の3人までしか賞をもらえないし)。
4)ちなみに、シムレ&ダンカンはバビル2世に登場する、ヨミ配下の超能力者。ドクトル・トランボはマーズに登場するタダの医者が元キャラだが、原作のシムレ&ダンカンとGR世界のシムレ&ダンカンは逆になっている。

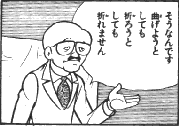
《シムレ&ダンカン(バビル2世より)》 《ただの医者(マーズより)》
【混世魔王 樊瑞】
1)仙力と呼ばれる力を使う十傑集の現リーダー。仙力とは道教の神、北斗真君(北斗七星の化身で、人間の死や寿命を司る)を源とする一種の霊的エネルギーであり、その詳細な力は未だ未知数であるが、7巻を見る限りでは銅銭を使った技を得意としているようである。
2)かつて二仙山で仙術を教える羅真人の一番弟子としてその将来を嘱望されていたのだが、何があったのか、俗世と接触する禁を破って二仙山を下山。BF団に引き抜かれてしまったため現在は破門されており、弟弟子にあたる一清道人が彼の追っ手として下山・派遣されている。
なお、二仙山を脱出する際に樊瑞は、国際警察機構に入ってはいたものの、世界を放浪してたまたま二仙山の近くにいた中条長官(長髪のヒッピースタイル(^^;))と対決したことがあり、その際にこれまでの戦いの中で唯一の傷を負わされたんだそうで、7巻の九大天王の名板が出る場面で、この時を回想するシーンが、絵コンテまで切っていたものの尺の都合で泣く泣く切らざるを得なかったんだそうな。
3)ちなみに、同門とは言え樊瑞の方は仙術の技が先達なのに加え、様々な技能をプラスしているため、一清とは段違いの実力を有している。
4)圧倒的な力を持ちながらも、それを誇る事は無い温厚かつ冷静な性格をしており、それゆえか、アルベルトから彼の娘を託され、後見人まで努めて面倒を見ている。
5)なお、マントのデザインはヤマトのデスラー総統がモチーフだそうな。
6)元ネタは、水滸伝8巻に出てくる同名の仙術使いで、一山の山賊のボス。人数が多くなってきたために梁山泊を襲おうと計画していたところ、それを察知した梁山泊軍に先手を打たれ、彼自身の仙術も一清道人に破られたために斬り死にしようとしていたところ、呉学人らに説得されて、梁山泊に入った。
《混世魔王 樊瑞(水滸伝より)》
