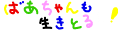平成三年
| 小山忠次 | 昭和十八年七月三十日命日 | |
| 五十回 昭和六十七年(平成七年) | 行年七十九才 | |
| 小山繁之 | 昭和三十一年三月二十一日命日 | |
| 行年五十五才 |
昭和六十三年 正月調
| 昭和十八年七月三十日命日 行年七十九才 | 至誠院釋亮玄 小山忠次 | |
| 明治四十二年十一月二十一日命日 行年三十二才 | 釋尼妙味信女 小山マナ | |
| 昭和三十一年三月二十一日命日 行年五十五才 | 恭敬院釋成滿 小山繁之(二男) | |
| 昭和九年五月二十八日命日 行年三十一才 | 釋定靜信士 小山定次(四男) | |
| 明治三十六年三月七日命日 行年五才 | 釋電光童子 忠次長男 平之 | |
| 明治四十年八月二十八日命日 行年四才 | 釋徳乘童子 忠次三男 徳次 | |
| 明治四十二年十一月二十五日命日 行年一才 | 釋尼妙観女 忠次長女 スヤ |
悦 明治四十年一月一日生
昭和六十三年
一月二日
今日は墓にうまってねむってゐる、小山家の家族親子全部を書き出した。これをお寺に送る。
一月一日
正月のお重つめ合せのごうかなもので三段重ねで立派なものである。五人でおいしいおいしいとつまんでおなか一ぱい大した御馳走だった
おなかふくれてねてしまった。ぐっすりね込んで目をさましてみたら、ゆき、まり、お菓子造りを始めてゐる。女の子だ、あんなものをつくり度いとは。内の子は一寸風変りかと思ってゐたら女気はあるみたい
今はともかくいつかいい人でも見つけてくれてひ孫でもつくってくれるかとほっとする。
昭和六十二年 一月一日 晴
正月の重の物も立派に二人で念入りに造ってくれた
珍らしくかす合へまで出来てゐる
たのしい水入らずの正月も今年で相すみになるのかとも思うとたのしいやら淋しいやらと思う
昭和六十一年
十二月三十一日
正月料理もゆき、まり、二人で何もかもしてくれた。酢ごぼう等一寸ずつ教へたのでよく出来た。考へてみると、もういい女ざかりばかりだもの今年数へで三十才にもなるのかと思うとぎょっとする。
正月の道具出すのさえ忘れてゐた。
よほどぼっとしてゐる。今年は重箱のいいのを出すと云うのでうれしい 奥に入れてあるのを出してやった。昔の物で一つもきずがない。いい物で父繁之の遺物である
しずが入学の時の運動会のべんとう箱もある 見せておきたい。父忠次はりちぎな人で一揃の家の道具をそろへてあった。会席の膳一揃の?膳わん十人前は揃へてあった。東京へひき上げるとき、下町と寺岡に分けてやった。
十二月三十日
もう私もいらなくなった
酢ごぼうをした。おいしく出来た
十二月二十九日
生えびを頂きお正月の分に煮て取っておいた
きれいな十箱の御馳走が出来るであらう
黒豆を煮る
煩悩が多く自信がないのでよく出来なかった
十二月二十八日
明日は黒豆をたかねばと思い水につけた
正月の御馳走もまり・ゆきが造るであらう
おにしめ丈は私がしようと思う
昭和五十八年
一月三日
今朝は雑煮をする。いつもに帰った正月みたい
やっぱり正月は内で年取りをしたいと思う
おとそを祝って、ぞう煮をたべて仕直しの元旦
やっと落ちついた気持
明日のパパの友達のマージャンの用意もする
ゆきあすまで居るそうだ
一月二日
ゆったりと朝湯に入り、正月気分にてテレビ眺めつつしずかに雑煮どもしてたべ、かずの子つけて、酢ごぼうをして皆の帰りを待つ。
一月一日 晴
生れて初めてよそで迎へる元旦
新宿のセンチュリーホテルにてパパ、ゆき、まり、私四人にて旧三十一日午後より宿泊する。しず外国旅行故にパパの気を使ったサービスに感謝して
明けて元旦五時に目をさましバス(洋式)に湯を入れゆっくりゆっくり湯につかりいい気分で部屋の窓より静かな町を眺めいる。しばらくして又床にもぐり九時過ぎ起き出でて、おせち料理に出かける。
関西料理にておいしい味付に舌うちならし満腹する。
幾夜泊まってもせんないことと思い、私一人家に帰る。