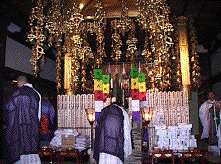|
|
 |
|
 |
|
 |
12月31日 歳末報恩会 1月1日〜3日 新年祝祷会 |
随時受付 |
水子供養 |
当山では年中行事の初めとして正月の三ヶ日間、朝5時の水行に心身を清め、6時より「新年祝祷会」にて法華経を讀誦し、本年の檀信徒の皆様方の家内安全・身体健全をご祈念致しております。
さて、お正月は氏神様や鎮守様にお参りすると共にご自分のご先祖様にもお詣りすべきが本来です。「一年間無事に過ごす事ができ、新年を迎えることができました。」という感謝の気持ちでお墓参りすることをお奨め致します。
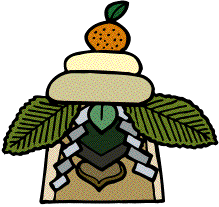

2月の行事といえば「節分」です。節分と言うとすぐ「鬼は外、福は内」の豆まきを連想しますが、本来、節分と豆まきは別の行事でした。
節分は、陰暦で立春(りっしゅん)の前日、大寒(だいかん)の末日のことです。一年を春夏秋冬の四季に分けるのはご存知の通りですが、陰暦の暦法ではこの四季の一つをさらに六つの節気(せっき)に分けて一年に二十四の節気(せっき)をたてます。これを二十四節気(にじゅうしせっき)と呼びます。たとえば、立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至・大寒などがよく耳にする二十四節気(にじゅうしせっき)のうちの一つです。立春からはじまる一年二十四節気の最後の日で、翌日の立春からまた新しい節気がはじまるという節気の切り替わりの日なので「節分」というのです。
この節分にお寺や神社で「追儺(ついな)」や「鬼遣(おにやらい)」といって豆まきをするのですが、「追儺(ついな)」の「儺」の字は「難」と同じ意味を持つ字で、「難を追い払う」ということから駆疫の意味をあらわすようになりました。
この時節の変わり目に疫を駆逐する厄除けの行事は、紀元前3世紀頃から中国で行われていましたが、それは桃の木の杖で疫鬼を追ったり、桃の木の弓と葦の矢で鬼を射る行事で、豆とは関係ありませんでした。
この時節の変わり目の厄除けの行事が古く日本にも伝えられ、7世紀頃の宮中では大晦日の夜、年越しの行事として「追儺(ついな)」が行われていました。
豆まきについては、「豆打ち」といって宇多天皇(888年)の時代に、鞍馬山(くらまやま)の鬼が都に降りて来たので、三石三斗(さんせきさんと)の豆を投げつけてこれを追い払ったという言い伝えから始まったなど、諸説ありますが定かではありません。
いずれにしても、立春を正月とする古代中国の影響により、節気の変わり目の「節分」と、年越しの厄除けの行事である「追儺(ついな)」と、豆で鬼を払って疫や災いを除く「豆打ち」の行事が重なり合って、現在のような「節分の豆まき」になったようです。
一般に豆まきは、炒った大豆を升に入れ、「鬼は外 福は内」と唱えながら撒きますが、当山では鬼子母神様をお祀りしている為、古来より「鬼は外」は言わず、「福は内」だけを唱え、その後にお題目「南無妙法蓮華経」を唱えています。

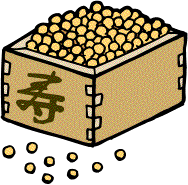
日本の仏教行事の代表的なものとして、「お盆」とならんであげられるのが、春と秋の「彼岸会(ひがんえ)」です。
彼岸会(ひがんえ)は春分の日と秋分の日それぞれを「中日(ちゅうにち)」とし、その前後三日間の都合一週間を春・秋の彼岸(ひがん)として、各寺院では法要(ほうよう)などが営まれています。また、多くの方もご家族そろってお墓参りにお出かけのことでしょう。
彼岸(ひがん)は、古代インドのサンスクリット語「パーラミター[波羅蜜多](はらみった)」の訳語「到彼岸(とうひがん)」を略した言葉です。
到彼岸(とうひがん)とは、「此岸(しがん)」すなわち、人間の苦しみ、恨み、悲しみ、喜びなどが混在している迷いの多いこの世界から、「彼岸(ひがん)」すなわち、仏様の世界、迷いのない理想的な世界へと自分を高めて、永遠の「安らぎ」の世界へ到達しようと努力することを意味します。
彼岸会(ひがんえ)の「中日(ちゅうにち)」である春分・秋分の日は、昼と夜の長さが同じで太陽は真東から昇り真西に沈んでいきます。
この昼と夜が同じでどちらにも偏らないということを、仏教の基本理念である「中道(ちゅうどう)」にあてはめます。「中道(ちゅうどう)」とは「足して二で割る」ような安易なことではありません。とらわれを離れた不偏中正(ふへんちゅうせい)の正しい決断、行動をなすことで、仏様の悟りの内容を実践することです。
大乗仏教ではこの仏様の世界へ至る実践徳目として、六つの実行を説いています。これを「六波羅蜜(ろくはらみつ)」といい、布施波羅蜜(ふせはらみつ)「=他のために励むこと」、持戒波羅蜜(じかいはらみつ)「=決まりを守り、それを持つこと」、忍辱波羅蜜(にんにくはらみつ)「=我慢強く耐え忍ぶこと」、精進波羅蜜(しょうじんはらみつ)「=常に努力すること」、禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ)「=常に心を落ち着かせること」、智慧(般若)波羅蜜(ちえ(はんにゃ)はらみつ)「=ものごとを正しく判断すること。前の五波羅蜜(ごはらみつ)を成就(じょうじゅ)することで得られる心の作用」を実践することです。これら六波羅蜜(ろくはらみつ)を中日(ちゅうにち)の前後三日間に配して、「到彼岸会(とうひがんえ)」としているのです。
したがって、お彼岸の一週間はお墓参りや先祖供養(せんぞくよう)をするだけの行事ではなく、本来であれば日々を心して過ごさなければならないのですが、ともすると怠惰(たいだ)に流れがちな私達の心をひきしめ、自覚と反省を促すために設けられた、私達自身の修養(しゅうよう)のための行事なのです。
尚、このお彼岸の行事はインドや中国にはなく、日本特有の仏教行事であることから日本人の仏教観(ぶっきょうかん)を最もよく表した行事であると言えましょう。

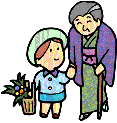
花まつりとは、毎年4月8日にお釈迦様の御誕生をお祝いする行事で、正式には『釈尊降誕会』・『灌仏会』などと言います。
お釈迦様が、ルンビニーという花園でお生まれになったとき、七歩あるいて、右手で天を左手で地を指さし、「天上天下 唯我独尊」(すべての世界において、私ただ一人が尊い)と叫ばれました。この言葉は「人間は生まれや育った環境によって差別されるものではなく、みな平等に尊い存在である。」ということを意味します。そしてその時、天から龍が降りてきてお釈迦様に甘露(甘い味のする雨)の産湯をそそいだ、という伝説から、美しい花で飾った「花御堂」を作り、御誕生の姿を型どった「誕生仏」を安置して、甘茶をかける風習が生まれました。
この甘茶は、漢方薬の一種の甘草の根を煎じたもので、これを飲むと健康になるというので、昔は参詣のおり甘茶を持って帰り、一家の無病息災を祈って家族みんなで飲んだものでした。
当山では「甘茶」の試飲コーナーを設けておりますので、是非ご賞味下さい。
仏教では「四有(しう)」と言う考え方があり、「死の瞬間=死有(しう)・初七日から七七日忌までの49日間=中有(ちゅうう)または中陰(ちゅういん)・受胎した瞬間=生有(しょうう)・生きている間=本有(ほんぬ)」と言うように生命の誕生は受胎の瞬間にあると捉えます。ですから水子であっても母胎から生まれてこなかっただけで、この世に生を受けた一人の人間ですので、その供養と成仏を願うことは当然のことでもあります。また、仏教で数え年を使用するのも上記の理由からです。
さて、我々日蓮宗の教えに「水子供養」のための特別な方法はありませんが、命の尊厳性を説く法華経の教えに基づき、久遠本仏のお釈迦様や日蓮大聖人の大慈大悲(だいじだいひ)の救済力によって水子の霊の成仏を祈るのであります。
やむを得ない事情で妊娠中絶を選択した方は、特に懺悔滅罪(さんげめつざい)[自ら犯した過失を仏様の前に告白し、忍んで許しを乞い、罪を消滅させる行法]の念をもってお題目(南無妙法蓮華経)を唱え、手篤く追善供養(ついぜんくよう)を営むことが大切です。
このような人達のためにも当山では、現住職が発願し檀信徒の方々の浄財により「水子地蔵尊」をお祀りし、水子の霊と大慈大悲の久遠本仏のお釈迦様や日蓮大聖人とを仏縁で結んでいただき、不幸にしてこの世にうまれなかった子供さんに供養を捧げています。
また、この仏縁を大切にしていただき、ご両親の罪障消滅とすべての水子の霊の供養を兼ねて、毎年5月24日に「水子地蔵尊精霊会」を行っています。
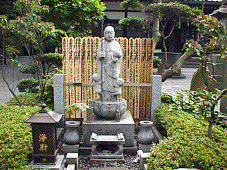
鬼子母神は、古代インドの神話に出てくる夜叉(鬼女)で、その名を「ハーリティ」といい、訶利帝母(かりていも)などとよばれます。
ハーリティは自分の子供だけを溺愛し、他人の子はさらっていって殺していましたが、お釈迦様の教えを受け、自らの過ちに気づきその罪を償う意味で、「永遠に子供を護ります」とお釈迦様に約束しました。この誓いになぞられ、子供を抱き天女の形をした鬼子母神は、安産・子育ての神様として信仰されるようになりました。
また鬼子母神は、十人の羅刹女と共に法華経の行者や信者を守護するという誓いが、法華経の中に説かれていることから、日蓮宗では他と異なり鬼形の鬼子母神をお祀りし、日蓮宗の祈祷本尊(鬼形鬼子母大善神)として、広く信仰されてています。
また日蓮宗では、毎年11月1日から翌年の2月10日までの100日間、「日蓮宗加行所」(にちれんしゅうけぎょうしょ)が開設され、100名以上の僧侶が秘法を授かろうと発願し、1日に7回の水をかぶり、白粥をすすり、読経三昧、約2時間の睡眠という大荒行を行っています。
当山では、古くから伝わる鬼子母神様を本堂に安置し、毎年2月28日に鬼子母神大祭を行っています。午後2時の水行の後、当日参集の皆様に加持祈祷を授け、檀信徒の家内安全・息災延命と世界平和をご祈念申し上げております。


日蓮大聖人が建長5年(1253)4月28日、千葉県小湊清澄山の旭ヶ森という所で、太平洋から昇る太陽に向かい、初めて「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えられた日です。つまり、日蓮宗の誕生の日です。
この日から、日蓮大聖人の身命を惜しまない弘通のご生涯が始まったのです。私たちも、この日蓮大聖人の信仰にしたがい、法華経を弘めてゆこうとお誓いする日です。

日蓮大聖人は、弘安5年(1282)10月13日の午前8時頃、池上宗仲公の邸(現在の東京都大田区池上)で、61才のご生涯を閉じられました。このご命日の法要が「お会式」(おえしき)で、「御影講」(みえいこう)とも呼ばれています。
池上本門寺では、10月11日〜13日にかけ盛大な法要が営まれ、特にお逮夜の12日の夜には各地より「万灯」(まんどう)が繰り出し、広い境内が参詣者でうめつくされます。そして、13日の午前8時の法要では「臨滅度時の鐘」(りんめつどじのかね)が、代々貫首様の手によって打ち鳴らされています。
当山でも毎年10月24日の午後3時より「お会式」の法要を営み、午後7時より万灯練り供養が行われ、境内には10基あまりの万灯が立ち並び、太鼓や笛の音が鳴り響き、まといが乱舞し、夜店も出て大変にぎわっています。
この万灯練り供養は、一時期途絶えていたものを、現住職の提案により昭和52年に復活させたものです。その時に発足した会が、了源寺檀信徒青年会(了信会)で、現在約40名の会員で「お会式」を盛り上げています。


施餓鬼(せがき)とは、餓鬼に色々な飲食物を施すことをいい、今の自分に与えられた生命を尊び感謝し、生かしていただく意味をもっています。この施餓鬼の由来については、「救抜焔口陀羅尼経」(くばつえんくだらにきょう)というお経に次のように説かれています。
[お釈迦様の十大弟子の一人に、説法を一番よく聞いた、阿難尊者(あなんそんじゃ)という方がおりました。ある時、阿難尊者が一人で静かに坐禅をしていますと、突然目の前に痩せ衰え手足が針金のように細く、髪は逆立ち口からは焔(ほのお)をだした、焔口(えんく)という餓鬼があらわれて、「三日のうちにお前は死ぬ。そして、私のような醜い餓鬼に生まれ変わるだろう。そうなりたくなければ、餓鬼たちにたくさんの飲食物を施し、三宝(仏・法・僧)に供養すれば、その功徳によってお前も救われるであろう。」と告げたのです。
阿難尊者は驚き、すぐお釈迦様のもとへ行き、どうしたらよいでしょうかと尋ねますと、「施餓鬼棚に新鮮な山海の食物をお供えし、修行僧に施餓鬼会の法要を営んでもらいなさい。修行僧のお経の力によって少量のお供物は無量のお供物となり、すべての餓鬼に施される。そして多くの餓鬼は救われ、お前も長寿を得られ、さらに尊いお経の功徳によって悟りを開くことができるであろう。」とお答えしました。
さっそく阿難尊者が、お釈迦様のいわれた通りにすると、命は助かり、さらにお釈迦様の弟子のなかでも、一番長生きされたそうです。]
なお、この施餓鬼会はお盆に行われることから、とかく両者が混同されがちですが、本来は特定の日を決めずに営まれる行事です。しかし、阿難尊者の物語と、目連尊者(もくれんそんじゃ)の母にちなんだお盆の物語が似ていることから、一般にはお盆の行事として考えられるようになりました。
当山では、毎年8月16日に「盂蘭盆施餓鬼会」を営み、併せて新盆にあたる霊位の供養を行っています。また、法話によってお釈迦様や日蓮大聖人の教えをわかりやすくお伝えしています。