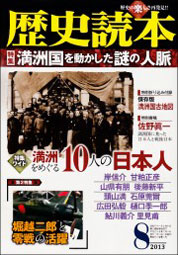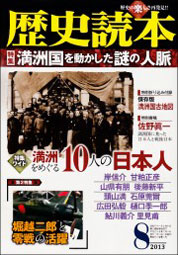※以下の文章は、2013年6月24日発売の「月刊歴史読本 8月号」(中経出版)に掲載されたものです。同誌は第2特集として「堀越二郎と零戦の活躍」を採り上げ、その中で映画『風立ちぬ』と宮崎駿監督について寄稿を依頼されました。ただし、堀越二郎の生涯や業績については、他の方の原稿で詳述されるため、触れないで欲しいという条件付でした。このため、どちらかと言うと堀辰雄の生涯と小説『風立ちぬ』に力点を置いた構成となっています。また、映画完成前の5月末に脱稿されている為、制作に至った経緯を中心に記されています。
2015.2.15.
●堀越二郎とその時代を描く
宮崎駿監督の映画「風立ちぬ」は、実在する堀越二郎の半成を描いた作品と謳われている。
堀越は、戦前・戦後を通じて三菱重工で航空機の設計主任を務めた人物であり、具体的には零戦(零式艦上戦闘機)の設計者として航空史にその名を刻んでいる。堀越は設計の試行錯誤を記録した著書も多数執筆しているが、本作は堀越の著作の映画化ではない。設計にまつわる事実関係はほぼ堀越の記録を踏襲しているが、プライベートの描写は創作と言って良い。いわば、堀越の業績に刺激を受けた宮崎が虚実を混合させて創造したオリジナルである。
零戦にまつわる映画やドラマは数多く作られてきたが、ほとんどが航空隊やパイロットに焦点を当てた作品であり、設計技師を追いかけた作品は前例がない。たとえば、柳田邦男のノンフィクション『零戦燃ゆ』の冒頭部は堀越二郎を中心に記されていたが、同名の映画(八四年/舛田利雄監督)では、テスト機墜落を詫びるシーンでほんの数カット、堀越(北大路欣也)が登場するだけであった。エンタテインメント作品で専門的な技術や用語解説を要する試行錯誤のダイナミズムを描き出すのは困難であり、生死を分かつ前線のドラマに傾くことは必然であったろう。
本作は、『崖の上のポニョ』(〇八年)制作中の宮崎が、過度のストレスから何故か堀越二郎のことで頭が一杯になったことに端を発しているという。それには長い前史があった。
宮崎の自宅がある埼玉県所沢市には「所沢航空発祥記念館」がある。今年は特別展「日本の航空技術100年展」が開催中であり、飛行可能な零戦実機まで展示されている。同館の白砂徹事業課長は、二月七日付「埼玉新聞」の記事で「宮崎監督と話す機会があり、父親が零戦を製作していた中島飛行機に部品を納入していた宮崎航空興学という会社を経営していたそうです」「三億円で零戦を買おうとしたが、奥さんに叱られてやめたそうです」と答えている。
堀越二郎とその時代を描くことは、宮崎にとって父を知ること、自らの幼少期の憧れを描くことであり、念願であったのではなかろうか。
●模型誌の漫画連載
宮崎が、堀越二郎を描く為に最初に選んだ表現は漫画であった。これにも長い前史がある。
一九四一年生まれの宮崎は、少年時代から戦闘機・戦車・戦艦などの兵器に深い興味を抱いており、それらの模写やイラストを大量に描き続けた過去を持つ。アニメーターとなってからも、その趣味は健在で、仕事の合間に独自調査で蓄積した雑学を披露し、機会を見つけては落書きを描いていた。たとえば、『赤毛のアン』(七九年)の舞台設計の鳥瞰図には、関係のない単葉機が描き込まれていた。
模型誌に数多くの連載を持つ先輩アニメーター・大塚康生は、七一年から老舗模型誌「月刊ホビージャパン」に宮崎の兵器関連のイラスト提供を求め、宮崎もこれに応えた。八一年には東京ムービー新社ファンクラブの会報で兵器や飛行機にまつわるイラストとエッセイを綴った「ぼくのスクラップ」の連載が描かれた。
八四年、「月刊モデルグラフィックス」(大日本絵画)創刊の際、大塚から「『ぼくのスクラップ』の続きを」と勧められた宮崎は、『雑想ノート』と題した連載を開始。この連載は、映画制作と漫画『風の谷のナウシカ』の連載(八二〜九四年)という、いわば「本業」のストレス解消と気晴らしを意図した趣味的「副業」として、長期に亘って断続的に続けられた。当初はエッセイ風の表現形態であったが、途中から本格的な漫画に発展して行った。
九〇年、『雑想ノート』の挿話として、漫画『飛行艇時代』が描かれた。一九二〇年代末のアドリア海を舞台とした、紅い飛行艇を駆る豚の中年パイロットの物語。これを元に映画『紅の豚』(九二年)が制作された。
その後も、『雑想ノート』は描き続けられ、九五年にはニッポン放送でラジオドラマ化され、CDも発売された。九八年には『妄想ノート』と改題され、漫画『泥まみれの豚』が描かれている。
かくして〇九年、勝手知ったる 「モデルグラフッィクス」誌上で、新構想の漫画連載が復活。タイトルは『妄想カムバック 風立ちぬ』であった。零戦以前の九試単座戦闘機の試作機を「美しい」と讃え、物語のクライマックスに設定。企業人としてクライアントの無理な条件に挑み続けた堀越の姿勢を、自らのスタジオ運営や映画制作に重ね見たシーンも描き添えられていた。
しかし、この時点では、宮崎はあくまで漫画で描き切る構想であった筈であり、映画の原作を意図していたわけではない。ちなみに、堀越二郎は『雑想ノート』の慣例に倣い、豚鼻の顔に描かれていたが、映画ではきちんとした人間に描き直されている。
●堀辰雄から得たもの
メインタイトルの『風立ちぬ』は、堀辰雄の同名小説に由来する。
映画『風立ちぬ』の企画書に、宮崎は次のように記している。
「実在した堀越二郎と同時代に生きた文学者堀辰雄をごちゃまぜにして、ひとりの主人公“二郎"に仕立てている」
「完全なフィクションとして1930年代の青春を描く」
宮崎は、前述の堀越二郎をエンタテイメントとして描くための視点として、堀辰雄の生涯と作品を採り入れるという、およそ常人には及びもつかぬ構想を思いつく。堀越は一九〇三年六月二十二日生まれ、堀は一九〇四年十二月二十八日生まれで、同年代。堀越と堀は、痩躯で面長の顔に眼鏡をかけていたという容姿、謙虚で物静かであったという周囲の評価などに共通項もある。
堀辰雄の小説『風立ちぬ』は次のような筋立てである。
主人公の「私」は、長野県軽井沢で絵を描いていた少女「節子」と出会い、やがて婚約するが、二人は共に結核を患っていた。重度の節子の療養の為、二人で高原のサナトリウムに入所するが、節子は回復せずに亡くなる。「私」は、節子との生活を小説にしたため、節子の愛情に支えられた自らの生を思う。
これは、後述のように堀の実体験に根ざした作品であった。生い立ちや仕事外の苦悩から恋愛まで、堀の文学的な生々しさは、従来の「実直な天才」という堀越のイメージを食い破る斬新なものだ。
自ら 「いま自分の心を充たしているものが、実は死の一歩手前の存在としての生の不安である」(『菜穂子』)と記した堀辰雄は、自ら死の影を背負いながら、母、師、恋人、友人を先に喪い、その慟哭と苦悩の中から、静かに「生と死」のモチーフを追求した小説家であった。
辰雄は堀浜之助と西村志気の間に私生児として生まれ、認知はされたが、二歳の時に母子は堀家を出た。母は上条松吉と結婚したが、辰雄は両親と別姓のままとされた。
二三年、文学を志しはじめた十九歳の八月、室生犀星を介して芥川龍之介と知り合い、軽井沢に招かれる。同年九月一日に関東大震災が発生。辰雄と松吉は一命をとりとめたものの、母は水死。隅田川に浮かぶ累々たる遺体の中から、三日三晩母を捜して見つけ出し、大八車で運んだ。母の死の衝撃と疲労が元で、肋膜炎を起こす。以降生涯に亘って肺を患い、療養と回復を繰り返す。
室生と芥川に師事し、都内と軽井沢を行き来して活動するが、二七年に芥川が突然自殺。またも衝撃を受ける。三〇年、芥川の死の呪縛から抜け出せない自身と周辺をモデルとした『聖家族』で文壇デビューを果たす。
三三年、軽井沢で「一輪の向日葵が咲きでもしたかのように」快活な、「絵具箱をぶらさげ」た少女(『美しい村』三四年)矢野綾子と知り合う。三四年、矢野と婚約するが二人とも結核であった為、八ヶ岳山麓の療養所に入院。辰雄の看病虚しく、綾子は冬に死去する。
三六年から三八年にかけ、綾子との生活と死別を題材に『風立ちぬ』を書き上げる。
三七年、辰雄は加藤多恵と結婚。三九年、弟のように可愛がっていた建築技師で詩人の立原道造が二十四歳の若さで結核により死去。四一年、既婚女性の結核療養と自立を描いた長編『菜穂子』を発表。菜穂子の幼馴染みとして、立原がモデルと思しき男・都築明を登場させた。
第二次大戦末期から辰雄の病状が悪化し、晩年は信濃追分で長い闘病の末に五三年に死亡。享年四十八歳と六ヶ月であった。
(参考/堀多惠子著『堀辰雄の周辺』九六年)
なお、映画のヒロイン・堀越の婚約者は「菜穂子」となっており、これも堀辰雄の同名小説に由来する。『風立ちぬ』の婚約者「節子」とは異なり、「菜穂子」は人妻であり、雪の中を療養所を抜け出して列車に駆け込み、東京に出て来るなど苛烈なところも描かれている。また、宮崎は映画の二郎像に、立原道造のイメージも重ねていたとも聞く。おそらく、これらも「ごちゃまぜ」なのであろう。
余談だが、辰雄と綾子と入院した富士見高原療養所(現・富士見高原病院)は、宮崎が休暇に利用する山小屋の近くだと思われ、付近を訪れた可能性もある。余談だが、同じ長野県富士見町には、映画『もののけ姫』の猪神の語源となった「乙事」という地名も存在する。
●複数のイメージからキャラクターと物語を紡ぐ
実は、宮崎駿が二人の人物(架空か実在かを問わず)を「ごちゃまぜにして」一人のオリジナル・キャラクターを創造したのは、本作が初めてではない。
長編映画初監督作『ルパン三世 カリオストロの城』(七九年)のヒロイン、クラリス・ド・カリオストロは、モーリス・ルブランのアルセーヌ・リュパンシリーズ『カリオストロ伯爵夫人』に登場する若き日のリュパンの婚約者クラリスと、『緑の目の令嬢』のヒロイン・オーレリーを掛け合わせたキャラクターと思われる。
『風の谷のナウシカ』(八四年)のナウシカは、『ギリシャ神話小辞典』掲載のパイアキアの王女ナウシカの挿話と、『堤中納言物語』の「虫愛づる姫君」のイメージを融合させて創造したと言う。
また、 宮崎は専ら架空のキャラクターを描き続けており、実在した主人公は本作が初と思われがちだが、過去の企画構想や漫画などでは実在の人物を何度も扱っている。
たとえば、戦中の奄美・加計呂麻島を舞台に、特攻隊長・島尾敏雄(戦後は小説家)と島娘ミホ(後に島尾の妻で小説家)が、イギリス空軍パイロットのロアルド・ダール(戦後はミステリー・児童文学作家)が出会う映画を構想したことがあると語ったことがある。(堀田善衛・司馬遼太郎との鼎談集『時代の風音』九二年)もちろん、島尾夫妻とダールが出会った事実はなく、完全なフィクションである。ちなみに、ダールは一九一六年生、島尾は一九一七年生。こちらも堀越・堀と同じく一つ違いであり、イメージを重ねていた可能性もある。奔放なダールと生真面目な島尾の仲の進展で行き詰まり、断念したという。
ほか、前述の『雑想ノート 第八話Q・ship』(八六年)にもドイツ海軍Uボート艦長フォン・アーノルド・ラ・ペリエールが豚顔で登場。この挿話を起点とした「多砲塔潜水カン映画」のスポンサー募集まで呼びかけている。『妄想ノート 泥まみれの虎』(九八〜九九年)ではドイツ陸軍戦車隊の英雄オットー・カリウスを、やはり豚顔で登場させ、史実のエストニア・レンビツ地区の攻防を詳細に描き出している。宮崎が敬愛するロバート・ウェストール著『ブラッカムの爆撃機』(岩波書店版、〇六年)には「ウェストール幻想 タインマスへの旅」と題した漫画を寄稿。その中で犬顔のウェストールと豚顔の宮崎自身の対話が描かれている。
そして、漫画『妄想カムバック 風立ちぬ』には、一九二〇〜三〇年代に活躍したイタリアの航空機製造者ジャンニ・カプローニが度々登場し、堀越二郎を「美しい航空機設計」の世界へと誘う。カプローニ社は、「ジブリ」の語源となった偵察機を製造した会社だが、堀越がカプローニと交流があった事実は確認されておらず、これも宮崎の妄想である。髭の紳士「カプローニおじさん」は、映画でも重要な役割を担う筈である。
このように、宮崎の中では常に虚実入り乱れて様々な人物のイメージが飛び交い、各々の不足部を補い結合を果たすことで、全く新たなキャラクターとその物語を再構築しているものと思われる。
●時代とのシンクロニシティ
プロデューサーの鈴木敏夫が漫画『風立ちぬ』の映画化構想を持ちかけた際、宮崎は「映画は子供たちに向けて作るべき」と断固として拒否したという。しかし、鈴木の粘り強い説得に「今作るべき作品」と思い直した宮崎は準備作業に入った。その矢先、東日本大震災が発生した。
当時、宮崎は映画の絵コンテを執筆中であった。描いていたのは、何と、映画冒頭に予定されていた関東大震災のシーンであったという。宮崎は、その絵コンテを廃案とすることもなく、逆に「全然変更する必要ない、このままやるべきだ」と覚悟を決めたという(「CUT/二〇一一年九月号」)。
ふり返れば、『崖の上のポニョ』は東日本大震災の三年前に大津波と洪水による世界の水没を描いていたし、『On Your Mark』(九五年)は原子力災害後の近未来世界で、(オウム真理教事件以前に)宗教団体と警察の銃撃戦を描いていた。時代が宮崎に「創らせている」とでも解したくなる、恐るべきシンクロニシティである。
堀辰雄の文学には、直接ではないが関東大震災と世界恐慌の影響、忍び寄る第二次世界大戦の予兆が通奏低音のように漂っていたように思われる。一言で言うと、「生きにくい」時代の閉塞感である。本作のコピーは「堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて。 生きねば」。おそらく老境に至った宮崎駿が、現代日本の閉塞感と格闘した結果を示したものとなるのではないだろうか。