HOMEへ戻る
「高畑勲論」トップへ戻る
「アルプスの少女ハイジ」で
高畑演出が目指したもの
文責/叶 精二
※以下の文章は「BSアニメ夜話Vol.7 アルプスの少女ハイジ」(2008年3月26日/キネマ旬報社発行)に掲載されたものです。
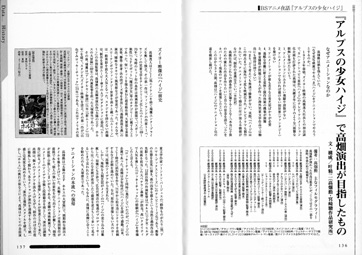

※以下の文章は「BSアニメ夜話Vol.7 アルプスの少女ハイジ」(2008年3月26日/キネマ旬報社発行)に掲載されたものです。
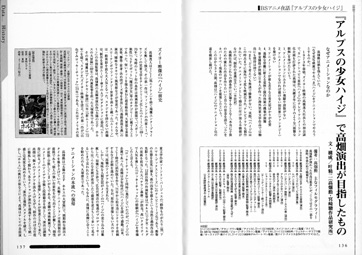

●なぜアニメーションなのか
高畑勲は頭を抱えていた。
「なぜ実写映画でやるべき『ハイジ』をアニメーションでやろうとするのか。」
1973年春頃、ズイヨー映像の高橋茂人社長との初会談で、ヨハンナ・シュピリ原作「ハイジ」のテレビ・アニメーション化企画を打診された高畑は、矢継ぎ早に以下のような「困難な根拠」を挙げたという。
1. アニメーションにふさわしい飛躍や誇張がない
2. アニメーションでなければ描けない別世界(ファンタジー)を築けない
3. アニメーションが最も苦手な日常芝居ばかりが必要
4. 過酷な労働に耐える覚悟と制作体制の構築が困難
5. 資金獲得が問題(日本人が作った海外児童文学作品では輸出にも期待は持てない)
つまり、どう考えても無謀で勝算がない。実際、「ハイジ」はこの時点までに海外で4度も映画化され、テレビドラマも制作されていた。アニメーションとして独自に付け加える価値がなければ、制作の意義は乏しい。(※註記)
高橋社長はこれらの諸条件に反論することなく、「本当に子供のための優れた作品を作りたい」と自らの信念を語り、「5」をカバーすべく現地のロケハンを提案したという。
この日から3ヶ月間、高畑は「ハイジ」のアニメーション化の道を模索し続けた。
※註記
「ハイジ」(1937年/アラン・ドワン監督/アメリカ)、
「ハイジ」(1952年/ルイジ・コメンチーニ監督/スイス)、
「A Gift for Heidi」(1958年/ジョージ・テンプルトン監督/アメリカ)、
「ハイジ」(1965年/ウェルナー・ヤコブス監督/オーストリア・西ドイツ)、
「ハイジ」(1968年デルバート・マン監督/西ドイツ・アメリカ合作のTVドラマ)など。
●ズイヨー映像の「ハイジ」前史
高橋茂人は、TCJ(現エイケン)を経て瑞鷹エンタープライズを興して独立。その第一作は、フィンランドの作家トーペ・ヤンソンの児童文学をテレビシリーズ化した「ムーミン」(69〜70年)。当時のヒット作の条件は、漫画原作が前提で、「スポーツ根性」「SFロボット」「魔法少女」等のカテゴリーに属することであった。短いカットを積み重ねた超省略作画、大袈裟な喜怒哀楽、爆発・変身・決め技ポーズ等を多用した「過剰表現主義」の演出、曖昧なカキワリ風美術などが常套であった。そんな中、スローテンポでファンタジー世界を淡々と綴った「ムーミン」は一際異彩を放ち、大人気となった。スタジオを持たない高橋は、制作を東京ムービー傘下のAプロダクションに委託。「ムーミン」の作画監督は、高畑勲の長編初演出作「太陽の王子 ホルスの大冒険」(69年)の作画監督を担った大塚康生であった。
その後、瑞鷹は「アンデルセン物語」(71年)「新ムーミン」(72年)を経て、スタジオ「ズイヨー映像」を設立。その第一作が「山ねずみロッキーチャック」(73年)である。これは、アメリカの児童文学作家ソーントン・バージェスの「動物ものがたり(現「アニマル・ブックスシリーズ」)」のテレビシリーズ化。動物の生態を忠実に描き、森の四季を綴るという自然主義的作品の先駆となった。12話以降の作画監督は「ホルス」で少女・ヒルダの原画を担当した大ベテラン・森康二が担当。高いクオリティで人気を博した「ロッキーチャック」の経験が「ハイジ」を準備したと言える。ちなみに、高橋に森を紹介したのは大塚康生であった。
「ロッキーチャック」と同時に進行していたのが、「ハイジ」の企画であった。高橋は、少年時代に「ハイジ」を読んで感動。以来、TCJ時代に試作版を作り、71年から松木功にシナリオを依頼するなど、企画を温めていた。なお、原作に登場しない犬のヨーゼフは、高橋のアイデアから生まれた。
しかし、地味な人間芝居がメインの「ハイジ」の売り込みは難航した。局側にも不評で、広告代理店の電通のプロデューサーからは「こんな企画が成功したら銀座を逆立ちして歩いて見せる」とまで言われたという。
ちなみに、高畑に高橋に会うことを勧めたのも、大塚康生であった。
●アニメーションの本流への復帰
高畑勲は、「太陽の王子 ホルスの大冒険」で、画期的な演出スタイルを築き上げていた。長編アニメーションは集団制作が前提であり、個人の強い作家性を打ち出すことが難しく、個性が拡散・分散してしまいがちである。老舗の東映動画でも、アニメーターのアイデア合戦と技術競合を核として、演出は調整役に回る“アニメーター主導型”スタイルが常道とされて来た。高畑は、個々のアイデアを汲み上げながら、制作のほぼ全行程に徹底して関わり、各セクションが演出を通過することで統一感と完成度を高めるという、“演出主導型”スタイルを確立。しかし、「ホルス」の興行不振などにより、高畑はテレビの各話演出への降格処分となってしまった。前述のような劇画調テレビ企画に辟易としていた高畑に、活躍の場がないことは明らかであった。
71年、高畑は「ホルス」で苦楽を共にしたアニメーター・小田部羊一と宮崎駿を伴ってAプロに移籍。用意された仕事は、スウェーデンの作家アストリッド・リンドグレーン原作「長くつ下のピッピ」であった。移籍の契機の一つは、「ムーミン」の大塚の仕事に感心したからだった。高畑は、この企画に全力で取り組んだ。その時に記された「スタッフへの覚え書き」の一部を以下に抜粋する。
「非日常的な緊張に満ちた特異な世界に子供を誘い込む劇画物から百八十度転換して、子供の日常生活、等身大の実生活にその基盤をすえます。したがって、これまで投げ捨てられて来た平凡な子供らしい欲望(食欲など)の復権、いわゆる「幼稚さ」の復権を試みます。(中略)
事件主義ストーリー主義ないしドラマ主義(葛藤と解決)でもなければ、主人公の「意図」と「結果」のくいちがいや「役割」の面白さでもなく、主人公の行動描写から直接生まれる楽しさや面白さ、行動の過程の中にひそむ面白さが基本的なテーマなのです。(中略)
これはいわばアニメーションの本流への復帰を意味します。(中略)子供たちの想像力をふくらませ、遊びの解放感と発見の喜びを味わわせる方向へとその表現をたかめることを要求されているのです。」
「ホルス」で架空世界のリアリズムを突き詰めた高畑は、更に現実的な世界の構築と日常描写を志向していた。高畑にとって「アニメーションの本流」とは、絢爛豪華なミュージカルでも、カートゥーンのドタバタしたおっかけでもなかった。確かな実在感のある世界を構築し、そこにふさわしいキャラクターを設計し、卓越した観察力と技術力で演技を克明に描き起こすこと、つまり、人間の心理的外面的メタモルフォーゼをコマ(1/24秒)単位で追求することであったのだ。児童文学のアニメーション化は、その挑戦にふさわしい企画であった。
年代や空想の度合いは異なるが、「ピッピ」も「ハイジ」もヨーロッパの女性作家による児童文学であり、日常描写の中に機微を詰め込んだ点では共通項がある。高橋社長の企画意図と高畑の方向性は「良心的作品を」という一点でも一致していた。
なお、「ピッピ」制作に当たり、宮崎はスウェーデンに単身ロケハンを行い、多くの素材を収集している。詳細は省くが、「ピッピ」は原作者の版権不許可で制作中止となり、その際のアイデア・技術・思想は、たまたま舞い込んできた中編映画「パンダコパンダ」「バンダコパンダ 雨降りサーカスの巻」の2本に結実した。メインスタッフは、演出/高畑、作画監督/大塚・小田部、案・脚本・画面設/宮崎。食事・掃除・洗濯といった日常描写の積み重ねの上に、ハプニングの顛末を盛り込むというスタイルは、結果的に「ハイジ」へのステップボードとなった。
●前代未聞のハードワーク
話を冒頭時点に戻す。高畑は高橋社長との会談後、「ハイジ」の原作(野上彌生子訳)を読み返し、森康二とパイロットフィルムの絵コンテを描き、キャラクターのデザインを練っている。森は「ロッキーチャック」の作画監督としてズイヨーに移籍したばかり。まさに奮迅の活躍中で、翌年の企画準備との平行作業はとても無理であっただろう。
結局、高畑はこの仕事を引き受けた。確かな現実感に裏打ちされた世界を構築し、そこに住む子供たちの行動過程を丁寧に描き起こし、その場に視聴者を一年間も立ち会わせるという、前代未聞の挑戦である。ファンタジーの曖昧な世界観を封印し、日常芝居の過程を印象づけるアニメーション。それは、誰も手をつけなかったアニメーションの新たな可能性の開拓であった。
それが「出来る」と判断したのは、何よりも小田部・宮崎とトリオを組むという前提があったからだ。時間的空間的連続性を重視する高畑は、場面設計(レイアウト)を宮崎に、キャラクターのデザインと作画の統一を小田部に割り振った。日本のテレビアニメーションでクレジットに「キャラクターデザイン」「場面設計」の役職が用いられたのは初めてである。
7月16日から25日まで、高畑、小田部、宮崎、プロデューサーの中島順三の四名はロケハンへ出発。スイスのチューリッヒやマイエンフェルト、ドイツのフランクフルトなどを訪れ、風景・地形・生活・習慣・建築・道具・音楽など様々な収穫を得て帰路に着いた。日本のテレビ・アニメーション企画でロケハンが行われたのも初めてである。
帰国後、小田部は現地でのスケッチなどを元にキャラクター設計を開始。宮崎は地形や各舞台・建物・小道具の設定に取りかかった。東京・阿佐ヶ谷のズイヨースタジオは、古いプレハブであったが、まもなく聖蹟桜ヶ丘の新社屋(後の日本アニメーション)に移転した。
常駐スタッフは、高畑、宮崎、小田部、美術の井岡雅宏、動画チェックの篠原征子、仕上検査の小山明子、制作進行・編集など、各セクションのチーフが一名のみ。絵コンテ・原画・動画・背景・彩色・撮影など中間行程は全て外注。スタジオに寄せ集められた素材をメインスタッフがギリギリまでチェック・修正し、クオリティを高めて行くスタイルであった。
高畑は、脚本・絵コンテの打ち合わせと発注、そのリテイク・再発注と自らの訂正、レイアウト・原画・背景のチェック、アフレコや編集の立会いなど、数話分の全行程を同時並行でこなし続けた。
高畑は、多数の斬新な技法を導入。カメラはFix(固定カメラ)を基本とし、動かす時は超スロースピードに徹した。特に山登りのシーンなどで、1コマに0.25ミリ(1秒で6ミリ)ずつ遠景と近景を上下左右に動かす新技法を開発し、立体的な臨場感を演出。また、脚本段階でハイジの感情の変化を階段状に想定し、長い1カット内で微妙な心理的変化の描写を試みた。(1話のハイジが服を脱ぎながら除々に笑顔になるカットなどはその典型)一方、雪ぞり競争(39話)ではゴールの瞬間を無音にするなど、ドラマチックな効果も欠かさなかった。
宮崎は毎週300カット分のレイアウト(外注コンテの大幅な修正、実質的な第一原画を兼ねる)を描き、カメラワークから空間・建物・小道具配置に至るまで、作品世界や演技設計を緻密に構築した。小田部は、ひたすら膨大な原画の修正と統一をこなした。
井岡は、自ら筆を執ることはもちろん、外注背景にも加筆を怠らず、羨望の地・アルプスを豊かな色彩と会画風の筆致で描き出した。特に演出上の要点となる部位に集中的に筆を入れる、陰を黒で絞らずに緑など多数の混じり合いで表現するなど、特異の工夫があったという。
篠原・小山は、各々一週間に8000枚(一日1000枚以上)の原動画とセルの全てに眼を配り、不出来なカットは自ら描き直す・塗り直すなど、ひたすら手を入れ続けた。日本初の動画チェッカーである篠原は(アシスタントとして5話〜28話に水田めぐみ、29話〜52話は前田英美との二人体制)で、三十六時間不眠不休のチェックもザラであったという。小山の平均睡眠時間は二時間。二人とも数週間帰宅もせず、長椅子で仮眠をとるだけの生活に愚痴一つこぼさずに耐えたと言う。労働の総量は、おそらく通常のテレビシリーズの2〜3倍であったと思われるが、制作の予算枠は決められていた筈で、労働時間に見合った残業手当などはなかったとも言われている。
こうした、常軌を逸したハードワークは、全て「より良い作品に到達しよう」とする高い志と、「全てのカットを自分でチェックしなければ」という職人的な意地に支えられていた。一人でも病欠が出れば機能不全になってしまうという緊張感の中、「せめて一週間が10日になれば…」「天変地異でスタジオが壊れて欲しい」と真剣に夢想していたという。
●原作を膨らませる
高畑の勝算はもう一つあった。原作の弱点の補強である。前述の「覚え書き」には以下のように記されている。
「原作にない話やシークエンスを作る時、リンドグレーン女史になりかわってピッピらしいセリフがかけるかどうか、これも非常に重要な問題となるでしょう。」
「ハイジ」では、「シュピリになりかわって」大量のオリジナルエピソードが創作された。前半部のアルムの山小屋での生活描写は原作の数倍で、四季が丁寧に綴られている。秋の山葡萄狩り(8話)は井岡雅宏の提案から生まれた。
小鳥のピッチーの飼育と別れ(4話〜8話)、嵐の木に集まる動物たち(9話)、雪ぞり競争(39話)などの話には、詩人のゼリーナ・ヘンツの物語にアロア(アロイス)・カリジェが挿絵を担当したスイスの絵本「フルリーナと山の鳥」「大雪」の影響が感じられる。
特筆すべきは、創作エピソードの追加によってキャラクターの性格が大きく改変されている点である。
物語の後半、クララは、ハイジを慕ってアルムを訪れるが、原作ではこれに同行するのは優しいおばあさま。最初からおじいさんと意気投合してクララは問題なく山小屋に預けられる。高畑演出では、クララに同行するのは家庭教師のロッテンマイヤー女史であり、都会生活とのギャップに何かと問題が発生する(42話〜47話)。
原作では、ロッテンマイヤーは硬直した都会人の象徴的扱われ方で、アルム滞在も拒否。以降は登場すらしない。高畑演出では、クララを思う一途な一面と、憎めないユーモラスな奮闘ぶりが描かれる。この変更により、ロッテンマイヤーは分別ある保護者としての膨らみを得て、単なる憎まれ役から脱することが出来た。
また、ペーターはクララにハイジを独占されることに腹を立て、車椅子を崖から突き落とし壊してしまう。以降彼は、ずっと罪の意識にさいなまれるが、物語の最後に宗教的な免罪が語られる。
高畑演出ではこれを丸ごと変更。ペーターはクララを気遣って牧場まで背負って登る優しい少年(45話)である。この改変により、ペーターをめぐる「罪と罰」の訓話的要素が取り除かれた。底抜けに明るい子供たちの遊びが浮上した。
車椅子は、クララ自身が「頼りたくない」と決意して一端しまい込んだものの、弱気になってこっそり納屋から出そうとして壊してしまう(51話)。この時、クララは辛いリハビリから逃げ出そうとした自らを恥じ、本格的な歩行訓練を決意することになる。他人に依存しながら没主体的に訓練するクララではなく、己の意志で車椅子を捨てて「共に歩きたい」「走りたい」と心身共に葛藤する姿が鮮明になった。自分自身との闘いに勝って初めて歩けたのである。原作では、歩行訓練に至る過程にクララの強い能動的意志が感じられず、おじいさんの戦地での介護経験まで説明的に語られるなど、クララの介護法の正しさも添えられている。
また、原作ではアルムおんじの出自や改心による村人との和解まで記されており、子供のいないクララの主治医が冬の家を買い取り、ハイジの後見人を申し出るなど、大人の宗教的救済まで語られている。出来すぎた展開だが、牧師の娘と医師を両親に持つ敬虔なクリスチャンのシュピリにとって、「信仰による魂の救済」は主要なテーマであったろう。しかし、生活の要が教会でない主な日本の観客には馴染めない。
高畑は、原作の枠組みは守りながら、子供たちの目線で「解放感と発見の喜び」を与える方向を選んだ。確かな世界の構築が、原作の人物像を越える実在感を生み出し、物語もそれにふさわしい成長を遂げたのだ。
●「ハイジ」の余波
このように、大きな成果を獲得した「ハイジ」であったが、高畑の総括は大変厳しいものであった。物語は、ハイジの天真爛漫な性格が周囲の人々を癒し結び付けて行くという基本構造を持っていたが、余りにも大人の理想とする「よい子」に描きすぎていたのではないかという疑問である。もっとありのままの子供像を描くべきではないかという反省は、高畑は新たなテーマとなった。それは、終生のテーマとなった。
高畑のテーマは「母をたずねて三千里」(76年)の大人に媚びない自立型の少年マルコから、横穴で大人達と隔絶した生活を営んで死んでいく「火垂るの墓」(88年)の清太へ、過不足ない日常をそれなりに楽しく過ごす「ホーホケキョ となりの山田くん」(99年)の山田一家へと引き継がれて行く。
一方「ハイジ」の理想化された子供像を生き生きと描く路線を引き継いだのは、宮崎駿であった。「となりのトトロ」(88年)の冒頭、引っ越しで階段を探して大騒ぎする姉妹、大樹を見上げてくしゃみをするメイ、これらは全て「ハイジ」のワンシーン(38話・28話)の変奏である。
現在は志向の異なる高畑・宮崎の両監督が一体となって作り上げた「ハイジ」は、その後の両氏、ひいては日本のアニメーション全体にとって特別な位置を占める作品だ。まさに、「天の時、地の利、人の和」が生み出した奇跡的な作品である。
(了)
禁無断転載