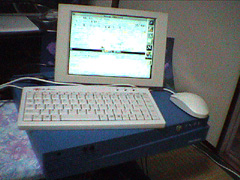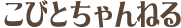 
|
| Note of Handmade PC/AT compatible put in case of SiliconGraphics INDY |
|
このページはAT互換機のパーツをsgiの名機INDYの筐体に詰めて、きちんと動作する一台のAT互換機を組み立てるという伊達と酔狂の顛末を描いた手記です。実用性はほとんど皆無の文章ですが、気が向かれましたら読んでみて頂ければ幸いです。 (注:この雑記の内容は事実を元に書かれたものですが、その内容が正確であるという保証は一切ありません。また、ハードの改造は危険な行為かつ全て自らの責任で行うものであるということをあらかじめご了承ください。この雑記の内容を参考にしてハードの改造を行ったことで何かが起こっても筆者は一切関知しません) |
| 材料一覧 | |||
|
| 筐体の加工(M/B側) |
| INDYの筐体はM/Bなどが入っている部分と電源ユニット(以下『電源』)が入っている部分の二つのブロックに分かれています。どちらから加工しても大丈夫ですが、ここではまずM/B側(←このページでは筐体の『M/Bなどが入っている部分』のことを指します。M/Bそのもののことではありません)を加工することにします。 |
| 初めにINDYの上蓋を、筐体背面のツメを外しながら前方に引っ張って外してからINDYの筐体に着いているM/BやCPUのサブボードを全部外します。筐体背面のインターフェイス部分のネジも外す必要があるので注意しましょう。なお、筐体前面側のシャドウベイの金具は最終的には流用できますが、これを着けたままだとHDの交換ができないのでこれもとりあえず外しておきます。 |
| 次に筐体から生えているスペーサーを移設します。スペーサーはペンチで力を入れて少しずつ前後左右にしばらく揺らしていると抜けますので、抜けたらM/Bのネジ穴と合う場所に移設します。以上でM/B側の筐体の加工はおしまいです。 |
| (なお、私がスペーサーを移設した際は接着剤で固定したため強度的に不安を感じたので、図1.の赤○の位置にあるスペーサーは移設せずそのままM/Bのネジ留めに利用し、残りのスペーサーをM/Bのネジ穴と合う場所に移設するようにしました) |
| 筐体の加工(電源側) |
| M/B側の加工が終わったら今度は電源側を加工します。なお、INDY本来の電源からも先がATX電源のそれと同じ形をしたケーブルが出ていますが、ピンアサインがATX電源とは違うのかAT互換機のM/Bにそのケーブルを挿して通電しても動作しませんでしたので、少なくともそのままでの流用はできないようです。ということで、ここではINDY本来の電源を外し、代わりにAT互換機用の電源を収めるための加工をすることにします。 |
| まず筐体の電源側の蓋を開けて、電源と排気用ファンを取り出します。ちなみに電源は筐体前面に着いている基板とつながっているケーブルを抜かないと取り出せません。その後、筐体の電源側にも生えているスペーサーを移設します。以上で電源側の筐体の加工はおしまいです。 |
| (ちなみにここでも私は筐体の加工の際と同じく図1.の青○の位置にあるスペーサーは移設せず、他のスペーサーは移設するという方法を採りました) |
| AT互換機のM/BとHDの装着 |
| 筐体の加工が終わったら、いよいよ筐体のM/B側にAT互換機のM/Bを装着します。M/BにはあらかじめCPUやメモリを装着しておいたほうが良いでしょう。次に筐体から外しておいたシャドウベイの下側にHDを装着し、シャドウベイを筐体前面側に装着しなおします。 |
| (なお、私は図1.の赤○の位置にあるスペーサーを移設せずそのままM/Bのネジ留めに利用することにしたのと、筐体背面のインターフェイス部分をAT互換機のM/Bに合わせて加工することは避けたかったのとで、M/Bは前後逆に装着しました) |
| その後、あらかじめ用意しておいたディスプレイケーブル+オスメス変換コネクタ・LANケーブル+延長コネクタ・PS/2延長ケーブル×2・IDEスマートケーブルをAT互換機のM/Bのそれぞれのインターフェイスに接続し、IDE以外のケーブルは筐体背面の図2.の位置にコネクタを引き回します。以上でM/B側のパーツの装着はおしまいです。 |
| 電源の装着とスピーカなどの配線 |
| 最後に、筐体の電源側にAT互換機用の電源を装着します。大きさから言って普通のATX電源はどうやっても入らないのでSFX(MicroATX)電源を、さらにケースをバラして入れることになりますが筐体の電源側には元々INDY本来の電源がむき出しで入っていたので、そこにむき出しにしたAT互換機用の電源を入れることになってもノイズについてはおそらく心配する必要は無いものと思われます。ただし、むき出しの電源を装着する際には最悪、火災やショートによるM/Bなどの破壊が起こることも考えられますので各種ケーブルが電源のヒートシンクなど、通電時に高温となる部分に接触し続ける状態にならないよう注意してください。 |
| 電源が装着できたら、排気用ファンを元々備えつけてあった位置に装着し、排気用ファンの電源ケーブルと筐体背面に備えつけられているAC電源コネクタからのケーブルを電源に接続します。どちらのケーブルもおそらく電源のそれぞれの専用コネクタにつなげるだけで済むと思います。 |
| (ちなみに元々備えつけてあった排気用ファンは一見流用できそうにも見えるのですが、私が今回使った電源につなげたところ動作しなかったため結局SFX(MicroATX)電源のケースに着いていたファンを装着しました。元々のものと比べてちょっと小さめですが実用上の問題は無いようです) |
| 次に、あらかじめ用意しておいたオーディオケーブルの一端を切断し、左(L)のほうだけケーブルの中の線をむき出しにして筐体に備えつけられているスピーカーのそれぞれの端子に一本ずつハンダづけします。その後、オーディオケーブルを電源から出ているM/B用やストレージ用の電源ケーブルと一緒に筐体のM/B側に送ります。その際には元々INDY本来の電源ケーブルが通っていた穴が利用できます。各種ケーブルを筐体のM/B側に送ったらそれぞれHDとM/Bの電源端子やオーディオ入力端子に接続し、筐体の電源側には元どおり蓋をしてこの項はおしまいです。 |
| 各種インターフェイスケーブルの接続と起動試験 |
| 筐体背面の図2.の位置に引き回しておいたコネクタにそれぞれのインターフェイスケーブルを接続します。ケーブルの接続が終わったらいよいよ起動試験です。まずはAC電源ケーブルをAC電源コネクタに挿して、電源をオンにしてみてください。 |
| (なお今回、私が使ったM/Bにはキーボードの操作で電源をオンにできる機能が備わっていたため電源スイッチの配線は行いませんでしたが、当該機能が無いM/Bを使用する場合にはこの時点までに電源をオンにするための何らかの手段を講じておく必要があります) |
|
電源オンの後、異音や異臭はしませんか? もし異音や異臭がした場合はパーツの装着や配線に問題があると思われます。即、AC電源ケーブルを引き抜いて、パーツの装着や配線をチェックしてみてください。 |
|
さて、異音も異臭もしない場合、ディスプレイにはきちんとBIOS画面などの表示がされ、キーボードでの操作も可能でしたか? そしてもし既にHDの中にマウスやEthernetやサウンドを扱えるOSが入っていた場合、マウスやEthernet、INDYの筐体に内蔵されているスピーカはきちんと使えましたか? 特に問題無いようであれば、ついに新生INDYの完成です。姿形はINDYのままですが中身はAT互換機そのものですから、あとはx86プラットフォームの豊富なソフトの中から自分の好きなOSやアプリを選んで入れて活用してあげましょう。 |
 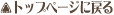
|