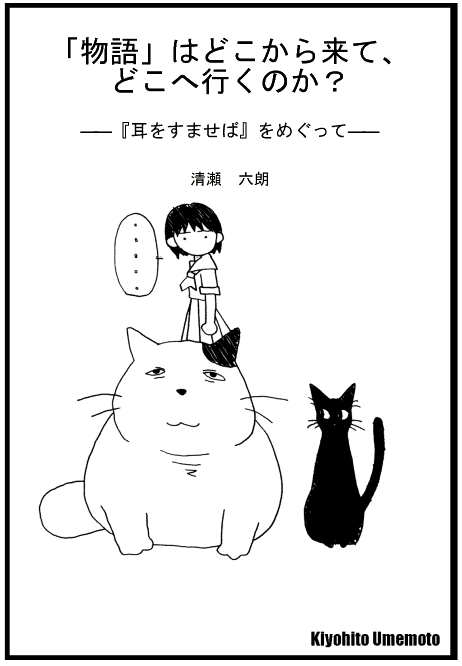
「物語」はどこから来て、どこへ行くのか?
――『耳をすませば』をめぐって――
清瀬 六朗
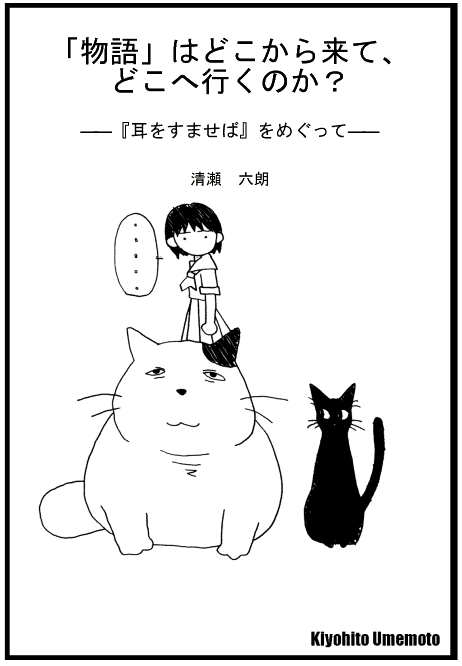
1.
近藤喜文監督(柊あおい原作、宮崎駿脚本・絵コンテ)の『耳をすませば』が夜の町を高いところから見下ろした場面から始まる。
大きな川沿いの京王線沿線の町だ。視点はだんだんと町のまんなかまで降りてきて、何ごとにも無関心を装って帰宅時間の人たちが通り過ぎる。
その何ごとも無関心を装っている人びとのなかから、コンビニエンスストアの自動扉を通って、この映画の主人公は現れる。さすがに一目見れば主人公だとわかるけれど、そこではただの「何ごとにも無関心」な一人の女の子にすぎない。
映画に出てくる雫の場所は狭い。二段ベッドの下の段と机のまわりとだけだ。
しかも、ベッドの上の段からはお姉ちゃんに口出しされるし、玄関を入ってすぐ――つまり家族みんなが家に入ってきたらすぐに見る場所――からもまっすぐに見通せる場所だ。完全な自分の場所などどこにもない。
雫はもう中学校の三年生だ。進路も決めなければいけないし、内申の成績も気にしなければいけない。つまり生活のすべてを「受験のため」を基準に決めなければいけない。したがって、日々の暮らしのなかでも、自分の自由になる余地は狭い。
映画の雫はとても窮屈な場所にいるのだ。
その狭い場所のなかで、自由にいられる場所が物語のなかだった。
けれども、その物語のなかの世界も無限に広いというわけにはいかないことに雫は気づきはじめている。
すべての物語は、仕組まれている。幸せに、うまく行くように、仕組まれている。
物語のなかの自由は自分を幸せに導いてくれると雫は思っていた。だが、その幸せが仕組まれたものだと気づいたとき、自由そのものが仕組まれたものだとわかってしまった。そうして物語の世界の窮屈さにも気がついてしまったのだ。
成長する――ということは、世界が小さく、狭くなっていくということなのだ。
雫はそんな妄想にとらわれていた。
自分は物語が用意した罠にはめられていることに気づきながら、雫はそれでも物語のなかの自由を追い求める。
というより、自分を罠にかけない物語がどこかにあるのではないかと探し求める。
妖精の住む森を切り開き、魔法使いが世を避けてひっそり住む谷を埋めて、人間はコンクリートで「狭い空間」をひたすらに拡げてきた。
物語なんかそんな世界のどこにももうあるわけがない。
けれども、広い空間は、どこかにはある。
飛行船は低い空を飛んでいる。空を飛ぶ飛行船がどんなに低い空を飛んだところで、手を伸ばして届くはずもないし、走って追いかけて追いつくわけもない。ゆったり飛んでいるように見えても飛行船は速いのだ。
でも、低い空を飛ぶ飛行船は、空が無限に遠くにあるのではないという錯覚を起こさせてしまう。
その広い空には、物語が、あるかも知れないし、それは手が届く世界かも知れない。
雫は、電車で会った猫を、べつの映画の幼い女の子のように追いかける。
でも、暇にまかせて、偶然に底の抜けたバケツのそこから見えた「もの」を、それが何なのかも知らないで無心に追いかけていく小さい女の子とはやっぱりちがう。雫はもっと必死だ。猫のほうはもしかするとほんとうは猫ではなくて、都会化に適応したトトロだったのかも知れないけれど。
猫が新しい物語を開いてくれることを雫は知っている。
というか、確信している。
というか、期待している。
というか、もしかして新しい物語を開いてくれるといいな、と思っている。
そしてたぶん、それが一時の幻想に終わるかも知れないことを知っている。
というか、恐れている。
というか、確信している。
でも、そういう期待はずれには、雫はもう慣れているはずだ。
あれは一時の楽しい物語だった、物語はそれだけでも幸せな時間をくれたのだ――だからいいんだと自分を納得させてあきらめることを雫はもう何度も経験している。
降りた駅も、自分が住んでいるのと同じようなコンクリートに固められた町だった。
自分は物語の端緒にからかわれているのだと気づいたとき、物語は扉を開いてくれた。
物語をめぐる物語の広い空間へと雫は足を踏み入れた。
雫はもうコンクリートの道の上で何ごとにも無関心を装っていた少女ではない。
というより、何ごとにも無関心を装っていた少女には戻れない。
世界は最初から広かった――と気づいてしまったから。
物語が自由という罠をかけてハッピーエンドに導いていたのだとすれば、「受験生」という罠は、中学三年生にとって広すぎる物語の広がりをわざと狭く見せるための罠だった。
「進路」とは「どこの高校に行くかということ」だと「受験生」は思わなければならない。けれどもほんとうはちがう。姉は大学に行ってもまだ進路を見つけていないというし、母親も大学院で修士論文なんか書いているところを見ると、やっぱりまだ進路を探しているつもりなのだろう。
もうもとの狭い世界には引き返すことはできない。
そのことを雫はあらかじめ知ってはいたはずだ。
2.
ペルセウス座流星群明けの夏の晴れた空の下から、少女は帰ってきたのだろうか。
雨の降りつづく夏の日、自分の部屋で、少女は物語を読み終えたところだ。
家はもちろん一戸建てで、部屋も自分一人の部屋だ。
(しかし今度はお母さんも顔つきで描かれてますね、柊先生)。
少女の机の前には窓が開けている。見ようと思えば窓から外の世界を見渡せる。広い空だって、何かにすがって探さなくても、最初から少女の窓の外に広がっている。もちろん窓の外を見ないで机の上に身を投げ出していたってだれが見とがめるわけでもない。
だから、少女は、そこで雨の歌のなかで雫がしたたる音をじっと聴いていることもできる。
夏休みに学校に行くにも、コンクリートの道なんかじゃなくて、自然のなかを歩いていく。妖精や魔法使いはそんななかにいるかも知れない。だから話のとっかかりをつくるためには、コンクリートの道をではなく、妖精を否定しないといけない。そんな世界だ。
電車は単線だし、駅ごとに表情がちがう。
少女はまだ中学生になったばかりで、自分の前には広い世界が開けているということを単純に信じている。
いや、単純に信じる必要もなければ、世界が広いと感じる必要もない。
見上げればいつでも広い空はあるのだ。
その広い空を映したような空間のなかで心が動く。
でも、それがいったいどこにあるのか、その広い空の飛行船のようにつかまえることができない。すぐ近くに見つけたつもりでも、気がついたら、自分の心はどこか遠くに行っている。
自分で自分の心をつかまえることができない不安――けれどもそれは「速く見つけなきゃ」というあせりをともなった期限つきの不安ではない。いつまでも楽しみとともにある不安だった。
だが、少女にとって残念なことには、ほんとうは世界は狭かったのだ。
すこし町に出れば「何ごとにも無関心な少女」を装えるような町ではない。日々、ベッドの上から姉に見張られているような息苦しさはないけれど、かわりに町を走っているところをいつ姉に見とがめられるかわからない。たまたま会った人が姉の恋人かも知れないし、両想いになりそうな男子と女子の両方と親友かも知れない。そんなのだから「悪い予感」も当たってしまったりする。
空の広さに気づき、その空の広さに自分があこがれていたことに気づいたとき、少女は、何年か前に自分より年上のだれかが踏み出さなければいけなかった一歩を踏み出さなければいけなかった。
自分の世界の狭さ、窮屈さ、自分を一生束縛するかも知れない関係に気づいたのだ。
笑いたくもないのに笑顔をつくり、うそをついて友だちの関係を維持していく――そんなことにも慣れなければいけなかった。
自分で選んだ一歩ではなかった。でも、広い空間のなかでいつまでも自分の心を見失っているわけにはいかなかった。
自然に聞こえていた音が聞こえなくなったときに、こんどは耳をすましてその音をたどり直さなければいけない。
自分で選んだ一歩ではなかった。
だが、自分は昨日とまったくちがう世界にいきなり投げ出されたのだ――耳をすませば聴こえる、いや、耳をすまさないと聞こえないその音だけを手がかりに残して。
3.
一人の少女は狭いと思っていた世界からいきなり広い世界へと、自分からわかっていて――すくなくとも自分ではそのつもりで足を踏み入れた。
もう帰れないことも自分で知っていた。
物語が自分を導いてくれた時代は終わったのだ。あとは自分で物語を追い求めていかなければならない。しかも、自分で物語を追い求めていかなければならないことも、物語を追い求めるためには遠くのものが大きく見えて近くのものが小さく見える特別な瞬間を見つけなければならないことも――つまり物語の追い求めかたの最初の一歩から自分で見つけ出さなければならない。
主人公は自分を導いてくれたように見えた。けれどもちがうのだ。主人公は自分を物語の世界に導いておいて、物語の世界のなかに雫を置き去りにしてしまう。
そこから先は自分の力で物語をまとめていかなければいけない。書きたいことがありすぎてまとまらない場所で、物語がまとまる場所まで自分で引き返さなければならない。
つまり、物語のなかににせの自由を仕組み、自分で仕組んだ幸せまで戻ってくる道を見つけなければいけない。その仕組まれた自由と仕組まれた幸せにだまされたときの気もちは自分のなかに生きている。こんどはその自由を仕組む罪を自分で背負わなければならない。
それも、期限つきで。
そうしてもう一人の少女は広い世界にあこがれたとたんに自分の世界が狭いと気づいてしまった。
べつに望んだわけでもなかった。
だから、世界が広いことにも気づかず、世界の広さにあこがれることも知らない時に帰っていくしか、少女にはやることがなかった。
成長するというのは、断ち切られた時代に来てしまうまえにいた場所へと帰っていくことだった。
帰らない生きかたもあることを少女は知っていた。つまり、それがなくなってしまった瞬間のことを思い出し、なくなってしまった時代を追憶しながら生きる生きかたもできた。
つまり帰るか帰らないかのどちらか一つなのだ。
自分の心を広い空間で見失っていたようなあの不安は、その帰りの旅立ちの予兆だった。どちらかひとつを選ぶように求められることの予告だったのだ。
少女は帰る旅に出ることを決意する。
少女にとっては、その旅を導いてくれるものが物語だ。
だから、物語は自分でつくるものではない。物語は、見たり、聞いたりしたものをことばにして書き留め、残しておくものなのだ。
帰って行くために。
広い世界を取り戻すために。
晴れた遠い空を自分のものにして、空の広さなんか気にも留めなかった自分の世界をもういちど取り戻すために。
物語はきっと自分をその世界へと自分を進めてくれる。自分の役割はその物語の声を聞きながら書き留めていくことなのだ。
そうすれば、きっと――。
4.
こうやって、原作の雫と映画の雫は、まったく正反対に物語をたどりはじめる。
映画の雫は帰らないことを自分で決意して、「世界は狭い」という罠を破り、広漠とした世界を拓いていくために、自分から物語を追い求める。物語は勝手に雫を物語のなかまで連れていってくれる。しかし、いろいろな物語が錯雑と積み上がるなかで生き埋めにならないためには、そこから帰ってくる道は自分で探さなければならない。
原作の雫は、いきなり帰れない場所へと投げ出され、世界の広さを意識することもなかった広い世界に帰ることを求めて、自分の周囲の物語に気づいていこうとする。物語は自分の周囲に流れている。でも、その物語は自分で耳をすまして見つけださなければいけない。
でも、それは、同じことではないのだろうか?
自分だけが物語を追い求めていたと思っていたのに、じつは自分の物語が追い求められたと気づくとき、自分だけが流れていく物語を見つけだそうとしていたとき、だれかが自分を見つけだそうとしていることに気づいたとき、その特別の時間には、どちらの少女の前にもあの広い空が広がるのだから。
もちろん、その特別の時間は、時計が進めば消えてしまう。
少女はそのまままた先へと進みつづけるのだろう。
行くか、帰るか、目的地はちがったとしても。
いや、それはもしかするとちがわないのかも知れない。それはだれにもわからない。
ただ、二人の少女は、これからも物語を追い求め、見つけだしながら行くのだろう。
物語にはつねにもう一つの語られざる物語が寄り添っている。「物語を書く」という物語が。
そして、その「もう一つの物語」にだって、いろんな物語があっていいではないか――と私は思う。
結び
「あの子、机にかじりついて何やってるのかしらね?」
はい、ごめんなさいっ!
同人誌の原稿書いてましたっ!
(終)
蛇足その一
お母さん、卒業して働くつもりだという話だが――修士論文落ちたらどないすんねん?
蛇足その二
飯塚雅弓ちゃん、出てたんですね。
『ミントと口笛』いいですよ〜。
(1998/12)