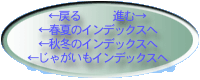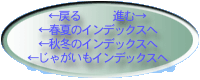|
風の盆で夜を明かした。富山の八尾に通うようになって、今年で10年近くになる。
最終日の夕方から嵐になった。八尾の知人の家で飲んでいたら、一時過ぎに雨は上がり、月も出た。明け方まで八尾の町を歩き回った。ここ数年は、どんな時間になっても、観光客の多さに閉口させられる。かく言う自分も観光客の一人だが、悪の権化は、勉強要らずのバスツアーだ。旅行社の用意したままにバスに乗せられ、時間まで放り出され、そのあとは、バスの中だか、タコ部屋のような旅館だかに放り込まれて、ああ、人が多くて疲れただけ、なんて言うんだろう。
最終日の三日が月曜日だからと言って、人が少ないということもなくなったが、今年はさすがにこの嵐で、人が減った。久しぶりに、町を流す踊りに音色に、見惚れ聞き惚れた。
この日は、寝ぼけたまま日本海を北上して、新潟の出雲崎に良寛を訪ねるつもりだったが、直江津の手前でまきば園の看護婦長から連絡が入った。その先はトンネルが多くて、なかなか携帯電話が使えない。トンネルの切れ目を狙って、「まきば園に電話して。トンネルが多い」と妹にメールしたが、仕事中とあって、なかなか通じない。事情がよく分からないだろうと長いメールを書いても、トンネルが切れない。長岡で降りて、まきば園に電話する。同じ頃、妹からもメールが入る。
危篤だというわけではない。ハワイアンまつりのときと変わりはない。ただ、その時に備えて、具体的なことを確認しておきたい、との話だった。
だから、出雲崎で一泊してから、その帰りに立ち寄ることで構わない、と婦長も妹も、その話を聞いた父も言う。
電話を終えて、出雲崎にいる自分を想像してみた。風の盆では飲み過ごして祭りを楽しむことができなかった父、明日長岡まで出るのにも時間がかかる、すぐに行ったほうがいいよ、と勧める友人、旅の空の下にいたら、上の空になりそうだ。
二人分の宿をキャンセルしてひとり出雲崎に向かう友人と別れて、寝不足と移動に継ぐ移動で疲れた様子の父を引きずって長岡から上越新幹線。思わず、大移動日になった。
旅を遮って、婦長さんが恐縮するよ、と妹が言う。それどころか、明日行くとなると、休暇を取るつもりだったから、そちらの都合に合わせて出てくると言う婦長に恐縮した、と私。恐縮しあって、と妹。
本筋を見落としてはいけない。ばあちゃんやわたしたち家族がよりよく生きられるよう、まきば園の人たちがサポートしてくれている、ということ。
五時頃、まきば園に着いた。婦長と30分ほど話して、事務室でコーヒーを馳走になる前に、ばあちゃんのところに行くと、ぐっすり眠っていた。
六時から夕飯なので、どの部屋もほとんど空っぽ。ばあちゃんの部屋の人々は、みな、眠っている。眠っているあいだは、食事だと起こしたりしないのだろうか、と父。歩ける人たちの多い一階にいれば、刺激になるだろう、と二階のムギの部屋からヨーデルに移ったのは、二年前。メシ抜きなんてことはない。ぎりぎりまで寝かせておいてくれるだけだ。
まきば園に着いてすぐに、臨終前後のことを具体的に確かめるようにして、婦長と話した。そして、この七年を振り返った。婦長の目に涙。鼻の奥がつんとする。最後の最後のことを家族としてどう考えているか、いざと言うときに入院させるか否か、亡くなったあとどうするか。
炎症を起こしたときに応急処置としてする点滴と、延命のための食事がわりの点滴とは違い、後者は、病院でなくてはできない。最後は入院させた、そこまでやった、という、家族としての責任の取り方もある。自宅で亡くなると返って手続きが複雑になるという話を聞いたこともあるが、延命措置はしないということについては、ばあちゃんと一緒に暮らしていたときから考えていた。まきば園であっても、時間によっては、医者の確認が遅れることもあるそうだ。手続きや体面などで不具合というのが出てくることもあるのだろう。
でも、ばあちゃんの嫁入り先をまきば園に決めたときから、ここのオンナノコたちに看取ってもらいたい、時間的にそれが無理だったとしても、彼女たちに見送ってもらいたい、と思っていた気持ちに変わりはない。
園のどこに安置するのか、どこで荼毘に付すのか、園の近くでお別れの会ができれば、焼香にスタッフのみんなが来られる。父が思い出す。真宗のばあちゃんが、以前、本願寺で戒名を頂戴していたのを。お骨になってから、菩提寺に話すことになるだろう。
こんな話をしてると知ったら、ばあちゃん何くそぉと思うかもしれないね、と三人で笑った。そうなったらいいな、と。
婦長との話を終えて、園長たちとコーヒー。父が日常の不便をあれこれ訴え始めたのを機に、もう食堂にいるはずのばあちゃんに会いに行くと、定位置だと思っていたところにばあちゃんがいない。食卓についたばかりの車椅子の人に食事の用意をしていた男性スタッフが、笑顔で迎えてくれたので、ばあちゃんどこ?って聞いたら、その車椅子の人がばあちゃんだった。
やっぱりまぶしい。ばあちゃんじいちゃんが一斉に集う食堂は。人の顔がよく見えない、んじゃなくて、よく見ていないのだ。
ばあちゃんの右隣にイスが用意されていた。隣にも、ばあちゃんみたいに車椅子に座ったまま、身じろぎもせずに食卓を見つめている人がいる。スタッフが、口にスプーンを運びながら、名前を呼んだ。顔をよく見ると、ムギの部屋にいたとき同室で、元気に歩き回っていたころの仲良し三人組のひとりだった。離ればなれになるころには、互いに精神的におぼろになってはいたが、喧嘩までするほどだった。三人組のうちひとりは去年亡くなった。
亡くなった人が一番威勢がよくて、車を呼んであるから帰ろうと旗を振り、それぞれに荷物をまとめては、下まで降りていき、スタッフに見つかって、部屋に戻される。そんな「大脱走」を繰り返していた。その二人がいまこんな風にして両側にいる。若いスタッフに話すと、ほんとですかぁ、とびっくりしていた。
若いスタッフ、顔なじみのスタッフ、父、園長、と入れ替わり立ち替わりやってくる。父にイスが用意された。父にもこの光景はまぶしそうだった。ばあちゃんに話しかけたり、他の人たちの様子を見たりしてしばらくすると、向こうで待ってると立ち去った。
その間、ばあちゃんは、スプーンで何さじ分食べたろうか。ご飯や肉らしきものがミキシングしてあるが、喉にひっかかるらしく食べられない。フルーツのミキサー食とヨーグルトも、いつまでも口の中に残っていて、なかなか飲み込めない。
人々を凝視する、そのまなざしの強さ、ということを、婦長が話していた。ハワイアンまつりのときも、暗がりや動いている人をじっと見やる姿が印象的だった。
婦長がテーブルの向こうから声をかけると、はあい、と口を動かした。こちらの問いに答えるかのように頷いた。問いの内容が分かっているのかどうかは分からない。もう食べないの?と聞こうが、まだ食べるよね?と聞こうが、同じように頷く。
スプーンを口元に近づけると口を開ける。舌の上に前に口に含んだものを乗せたまま。空のスプーンで舌の奥のほうを刺激すると、しかめっつらしながらゴクンと飲み込む。
飲み込むというのがこんなに大変な作業とは。母の臨終のときを綴った母の友人の詩を思い出した。息をするということはこれほど大事業だったのね。
両手の指が全部内側に曲がってしまっている。右手を首の右下にあてがい、指を服の襟首にひっかけて、首筋を掻いている。痒そうだ。いかにも痒そうな膚の具合だ。スタッフが言う。「かゆかぁ」ともこのごろ言わなくなったと。左手は腹のあたりに置かれたまま。曲がった指の爪はハサミ式の爪切りで切るそうだ。持参する耳クリンで耳垢を取らなくなったのは、いつからだったか。
口を固く結んで、何かをじっと見ている表情。母に似ている。こんなに似ているとは、と今になって思う。母の生前、顔の似た親子とは思わなかった。
視線の力が弱まり、上まぶたが下がるようになってきた。眠たげだ。
もう少し生きていてよ。
|